- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.03.29
『震災と向き合う子どもたち』徳水博志著(新日本出版社)を読みました。「心のケアと地域づくりの記録」というサブタイトルがついています。著者は、1953年生まれ。元宮城県石巻市立雄勝小学校教員(定年退職)。文芸教育研究協議会会員、新しい絵の会全国委員、日本子どもの版画研究会会員。日本生活教育連盟全国委員、みやぎ教育文化研究センター会員。現在、東北工業大学非常勤講師。著書に『森・川・海と人をつなぐ環境教育』(明治図書出版)、共著に『生存の東北史』(大月書店)、『東日本大震災 教職員が語る子ども・命・未来』(明石書店)などがあります。
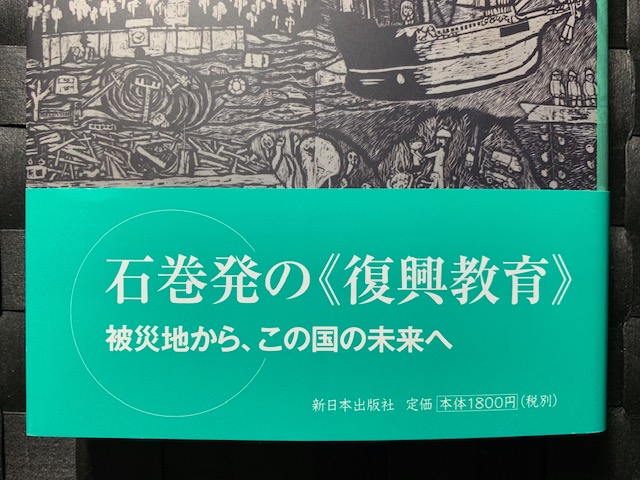 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「石巻発の《復興教育》」「被災地から、この国の未来へ」と書かれています。アマゾンの「内容紹介」は、以下の通りです。
「津波で地域が壊滅、家族はじめ多くの大切なものを失い、心に傷を負った子どもたち。その再生をめざす歩みは、教師と学校にとっても手探り、苦難の道でした。故郷の未来を見つめながら学ぶことが子どもにどんな力を与えるか、その心のケアには何が必要か。この国の現在と未来へ、深く問いかけ考えさせる感動的で貴重な記録!」
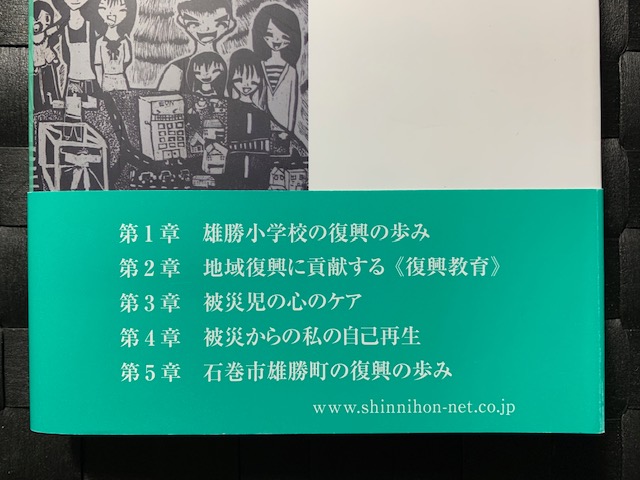 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」
第1章 雄勝小学校の復興の歩み
第2章 地域復興に貢献する《復興教育》
第3章 被災児の心のケア
第4章 被災からの私の自己再生
第5章 石巻市雄勝町の復興の歩み
「あとがき」
「解説――人間復興への四つの風景」梅原利夫
本書の存在は、「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生から教えていただきました。ムーンサルトレターの第166信で、鎌田先生が本書を紹介され、著者について以下のように書かれたのです。
「徳水博志さんは、わたしより2歳若い1953年生まれです。石巻市立雄勝小学校教員を10年務め、2014年3月に60歳で定年退職しました。雄勝小学校はわたしも何度も訪問したことがありますが、2011年3月11日の東日本大震災の津波で全壊し、108人いた児童が転校などで41人にまで減りました。徳水さん自身も津波で家や親族を喪いましたが、子どもたちと共に俳句や作文、震災前の雄勝町のジオラマづくり、版画制作、町づくり活動への参加など、創作活動や地域とのつながりを通して徐々に元気を取り戻し、だんだんと立ち直っていきました」
「まえがき」の冒頭には「七海」さんという雄勝小学校5年生の女子の詩が紹介されていますが、これを読んだだけで泣けてきました。以下のような詩です。
「わたしはわすれない」
わたしはわすれない
地鳴りがして
おびえ からだがふるえて
しゃがみこんだことを
わたしはわすれない
ガソリンスタンドのおじさんが
走ってきて
助けてくれたことを
わたしはわすれない
豆腐屋のおじちゃんが
みんなを避難させて
自分だけは津波に流されたことを
わたしはわすれない
豆腐屋のおじちゃんが
ふいていたラッパの音を
わたしはわすれない
誕生日にお母さんにもらった
大切なネックレスを
流されたことを
わたしはわすれない
家族 友達 わたしが
写っていた思い出の写真を
流されたことを
わたしはわすれない
自衛隊の車に乗って
こわれた北上川の横を走り
雄勝から出てきたことを
わたしはわすれない
避難所でいただいた
スープのあったかさと
おにぎりの味を
わたしはわすれない
飯野川中の避難所で遊んでくれた
お姉さんたちの
笑顔とあたたかさを
わたしはわすれない
こわされた家を
流された命を
助けられた恩を
人のあたたかさを
わたしはわすれない
大震災の記憶の
すべてを
この詩を紹介した後で、著者はこう述べています。
「震災直後はテレビからコマーシャルが消え、日本全体が喪に服しました。震災を機に日本が生まれ変わるのではないか、と多くの人が期待しました。ところが時間の経過とともにその期待は裏切られ、震災以前にもまして経済至上主義の社会に逆戻りしていきました。その波は学校にも押し寄せてきました。被災校でも『学力向上』が強調され始め、子どもたちは旧秩序の学力競争の世界に連れ戻されていきました」
しかし、学校秩序だけが元に戻っても、被災児はもう元の世界には戻れないと指摘する著者は、「泣いても叫んでも、亡くなった親は帰ってはきません。最終的には震災を人生の一部として引き受けて、現実を受け入れるしかありません。そのためには、震災とは何だったのかと問い、納得する意味づけを見つけねばなりません。そのために学校の教師にできることは何なのか」と述べるのでした。
第1章「雄勝小学校の復興の歩み」では、「”早く山さ逃がして! お願いだから!”」として、大震災発生当時の様子が以下のように書かれています。
「午後2時46分。巨大地震の後、校庭に子どもを第一次避難させ、大津波警報10メートルが発令される中、保護者に子どもの引き渡しを行うため校庭に待機させていました。ところがわが子を引き取りに来た佐藤麻紀さんから、『ここにいたら津波にさらわれるから! 頼むから! 早く山さ逃がして! お願いだから!』という強い呼び掛けをもらって、ようやく山に避難したのです」
学校の避難マニュアルでは神社から裏山へ避難というルートが決まっていましたが、なぜか学校側は避難場所を誤り、体育館へ避難という指示を出していたそうです。裏山に避難し、しばらく経ってから(5分から8分後)、17メートルの巨大津波に襲われ、体育館や校舎もろとも流されて町は水没してしまったそうです。著者は述べます。
「雄勝小学校の避難行動から学ぶべき教訓は、避難マニュアルを教師、児童、保護者(地域)の三者で共有する大切さです。三者で共有していたために、学校側の判断ミスを保護者が修正してくれたのです。さらに裏山から清掃工場までの山越えのルートは、教職員の中で誰ひとり知りません。地域の地理に詳しい消防団員の誘導で避難所にたどり着いたのでした。このように学校と地域の連携の大切さを教訓として学ぶことができます」
さらに、著者は以下のようにも述べています。
「私たち雄勝小学校の負の経験から教訓を述べるとすれば、次のようになります。大災害の下では次々と想定外が起こります。教育行政の指示は途絶え、マニュアルも使えません。自主的判断力で学校を運営せざるをえません。その場合、何を原則に運営するかが問われます。『子どもにとって最善の利益とは何か』という原則で判断すれば、まず間違いはないといえます」
第2章「地域復興に貢献する《復興教育》」では、1「《震災復興教育を中心にした学校運営(経営)》の提案」の「子どもの実態の理解」として、著者は「私の被災体験からいえることは、「被災者が持っている《喪失感情》の本質とは、人と人とのつながり(関係性)の喪失である」ととらえていると指摘し、さらには以下のように述べます。
「雄勝の被災者は、自宅と地域を丸ごと流されてしまいました。それは、震災前に自分がつながっていた多くの人や物事との《つながり》が切れたことを意味します。特に家族を失うと、大きな《喪失感情》を抱くことになります。地域コミュニティーを失っても同じように、《喪失感情》を抱きます。これも《つながり》、つまり《関係性》が切れたことから生じる《喪失感情》です。その上、失業すれば生活不安がのしかかってきます。この状態の被災者の意識を一言でいえば、『希望を持てない』状態といえます」
子どもたちの心のケアのために、著者は具体的な方策を考えます。具体的な「方針」とは、「震災で切れた《つながり》を再びつながり直すこと」でした。一言でいえば、《人とつながり希望を紡ぐ》ことです。「方策とは《つながり》直すこと」として、著者は以下のように述べます。
「子どもがつながっていた物事とは、地域、家族(親・兄弟・祖父母)、地域コミュニティー、学級集団、友達などです。この切れた《つながり》を再構築することで、喪失感情が癒され、希望が生まれてくると考えました」
では、学校の「教育活動」として、子どもたちを《つなぐ》ことで、一番教育効果が期待される活動は何かと考えた結果、著者は「地域の人たちと《つながり》、地域の復興活動に参加することではないか」と考えたそうです。
2「地域とつながる復興活動――南中ソーラン」では、以下のような具体的事例が紹介されています。
「総合学習に先立って、すでに取り組んでいた復興活動がありました。地域主催の雄勝復興市へ、『南中ソーラン』で出演した実践です。『南中ソーラン』とは、民謡歌手の伊藤多喜雄がソーラン節をアップテンポにアレンジした曲に、北海道の稚内市立稚内南中学校の教員と生徒が振り付けを考案した踊りです。雄勝小学校では、震災7年前に私が持ち込んで、子どもたちに指導しました。それ以来、子どもたちが学習発表会で踊ったり町の『海鮮市』で踊ったりして、住民の皆さんに馴染みの演舞でした」
被災者たち、特に高齢者たちが子どもたちの「南中ソーラン」を喜んだとして、著者は以下のように述べています。
「被災者にとって、子どもはその存在自体が希望です。子どもの笑顔や天真爛漫に遊ぶ姿それ自体が、無条件に被災者に生きる力を与えてくれます。瓦礫の中で南中ソーランを踊る子どもの姿はなおさらです。被災した住民の前で一生懸命に南中ソーランを演じる姿を見ると、なぜか涙が流れてくるのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「観客の住民の方々も、みんな涙を流しています。自分を支えていたすべてを奪われて、丸裸にされた被災者は、自分たちのために健気に踊る子どもの姿に涙し、真心から感謝します。『なぜか涙が出るちゃねえ』と話す住民の皆さんの頬は涙に濡れながらも、その表情は晴れやかでした。心を込めて踊る子どもの健気さは被災者の心を癒し、『よし! 前を向こう』という力をくれるのです。子どもはまさしく《地域の宝》でした。そして、子どもの命の輝きは、復興への希望となりました」
そして、「南中ソーラン」について、著者は以下のように総括するのでした。
「住民に評価されることで、期せずして子どもは自信を持つことができました。その結果『自己有用感』を高めて、運動会や学習発表会でもやりたい、という前を向く力や目標を生み出しています。この事実から、私は受け身で支援を受けるよりも、能動的な行動が自分自身を癒す力があることに気づいたのです。
つまり、子どもたちが、一方的に支援を受ける立場から転換して、地域住民とつながり、《関係性》を回復して、地域復興に参加したときに自らを癒し、希望を生み出すことができたということ、その事実に気づいたのでした。そして、この『南中ソーラン』の実践から、私が直感的に抱いていたことに確信を持つようになりました。それは、《人とつながり希望を紡ぐ》という人間復興思想は、教育実践にも応用できるという確信です」
第3章「被災児の心のケア」の1「震災二年目から起きた”新たな荒れ”」では、「被災児の心のケアの方針」として、著者は以下のように述べています。
「まず被災児の心のケア的教育の方針を立てました。被災児は、自宅、地域、親兄弟を失って、人生が180度激変しました。どんなに泣き叫んでも家族は帰ってきません。どんなにあがいても、元の世界には戻れないのです。これが峻厳な現実でありました。まだ10歳にも満たない年端のいかぬ子どもに、このような過酷な現実が突きつけられたのです。厳しくても子どもは、震災とどこかで折り合いをつけねばなりません」
また、著者はこのようにも述べています。
「私自身の自己省察から、私はこう考えました。子どもが震災から受けた悲しみ・つらさ・喪失感情などを語り、言語や絵画表現などで《対象化》し、《意味づける力》を獲得すること、そして、人生の新たな『物語』を描き直して、失ったものとのつながりを《再構築》することが必要である、と考えたのでした」
2「震災と向き合い、意味づける学び――震災体験を記録する」では、「震災体験の対象化(国語科)」として、被災児童に書かせた作文が紹介し、以下のように述べています。
「自宅に忘れた犬を助けに帰り、津波に追いかけられて九死に一生を得た子、高台から故郷の街並みが流される様子を見て恐怖を感じた子、巨大地震の揺れから難を逃れた後に聞こえてきた大津波警報のサイレンに”次は死ぬんだ”と死を恐れた子、親と離れ離れになり親の死を覚悟した子など、その震災体験は想像以上に過酷でつらい内容でした。
一方で、家族が一番大切と再認識したこと、避難所でふれた人々の優しさ、みんなのために避難所で働くリーダー役の人への尊敬の念など、人間を信頼して肯定する内容も書かれていました」
第4章「被災からの私の自己再生」の1「喪失感情とそこからの回復」では、「《人とつながり希望を紡ぐ》人間復興思想」として、著者は以下のように述べています。
「こうして絶望のどん底にいた私が、地域住民とつながることで希望を生み出したのです。この私の自己再生のプロセスを、《人とつながり希望を紡ぐ》人間復興思想と名づけることにしました。このように、《人とつながり希望を紡ぐ》人間復興思想とは、義母と故郷の町を失って失意のどん底にいた私が、地域住民とつながり、地域復興に参画する中で身体に刻みつけられた、私自身の再生プロセスで到達した復興思想です」
続けて、著者は「希望」について述べています。
「希望とは、受け身で待っていては生まれてきません。連帯と共同の行動が必要です。希望とは、連帯を横糸に、共同行動を縦糸にして、自ら紡ぎ出すものです。つまり被災者が一方的に支援される側から転換して、人とつながり、主体的に復興活動を起こせば、自らを癒すことができ、希望を生み出すことができるということです。これが、《人とつながり希望を紡ぐ》という人間復興思想の意味であります」
3「喪失感情の本質とは《関係性の喪失》である」では、関係性について以下のように述べられています。
「私という人間は、さまざまなつながり(関係性)で支えられてきました。(1)雄勝地域の自然とつながり、(2)地域コミュニティとつながり、(3)教師という職業で社会とつながり、(4)夫として妻とつながり、(5)父親として子どもとつながり、(6)義母とつながっており、そのさまざまなつながりに支えられて生きてきました。つまり、私という人間は(1)~(6)のつながり(関係性)の中で生きてきたわけで、つながりの全部が私という人間です。つまり《関係性》の総体が私という人間といえます」
さらに、著者は以下のように述べています。
「人間は一人で生きてはいません。さまざまなつながりに支えられて生きている『社会的存在』であり、多様なつながりをもった総体です。難しい言葉でいいますと、私という人間の本質は多様なつながりで支えられた『社会的諸関係の総体』であります。そのつながり(関係性)の1つでも失えば、喪失感情や悲嘆感情が生じるということに気づいたのでした。つまり喪失感情の本質とは、《関係性の喪失》であるという認識に到達したのです」
4「最後に残った《不条理の感情》」では、宮沢賢治の「雨ニモマケズ」が取り上げられ、教育者であり賢治研究者でもあった故・三上満氏がこの詩の思想を「イッテの思想」と述べたことが紹介されます。「震災で私の人生は狂ったと考える子にはなってほしくない」という一心で、著者も子どもの傍らにイッテ、寄り添いました。そして、この「イッテの行為」で子どもの心のケアに取り組んだときに、逆に著者は癒されたとして、こう述べます。
「この意味づけに支えられながら、毎日与えられる命を生きています。そして、人間に襲いかかる苦難や死という厳粛な宿命は、いったい何のためにあるのか。それを自分が納得するまで探求することが、今後の私の知的な作業となりました」
著者は、「例えば『ペスト』を書いたフランスの作家カミュのように、人間の地平にとどまりながら苦難と向き合って、自己意識の分裂に耐えながら人間的誠実さを追求し、生き抜くことは可能です」と述べ、あるいは「超越性の世界に飛躍して、例えば神に出会って悟りを開き、そこから現実に往還して生きることも可能です。後者の場合、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』はそのテーマを扱っていると私は考えています」と述べています。
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「『銀河鉄道の夜』を書いた宮澤賢治は、最愛の妹トシを亡くし、その悲嘆感情を乗り越えるために、この物語を書いたと一説にはいわれています。宮澤賢治が妹トシの死とどのように折り合いをつけたのか。人間の死をどのように解釈し、意味づけたのか。そして人間にとって本当の幸せとは何なのか。多くの謎がある作品ですが、愛する人の死を受け入れ、意味づけて、愛する人との《関係性の再構築》のために参考になります」
 「サンデー新聞」2011年4月30日号
「サンデー新聞」2011年4月30日号
『銀河鉄道の夜』といえば、わたしは東日本大震災の直後に新聞に書評を書きました。そこで、『銀河鉄道の夜』とは臨死体験の物語であると述べました。この作品は、死が霊的な宇宙旅行であり、死者の魂は宇宙へ帰ってゆくという真実をうまく表現しています。さらに何よりも重要なことは、ジョバンニが死後の世界からの帰還後、「ほんとうの幸福」に気づいて、その追求を決意する点です。それは、賢治が影響を受けたというメーテルリンクの『青い鳥』のチルチルとミチルの気づきと同じでした。
拙著『涙は世界で一番小さな海』(三五館)にも書いたことですが、「死」について説明するとき、「宗教」や「哲学」や「科学」という方法があります。でも、その他に「物語」という方法があることを本書は教えてくれます。読者は、この物語によって「死とは何か」を知るでしょう。新聞に書いた『銀河鉄道の夜』の書評の最後に、わたしは「東日本大震災で亡くなった方々が銀河鉄道に乗って、『ほんとうの幸福』が待つ場所へと無事に行けますように」と書いたのでした。改元まで、あと33日です。
