- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1753 論語・儒教 『なぜ論語は「善」なのに、儒教は「悪」なのか』 石平著(PHP新書)
2019.07.31
『なぜ論語は「善」なのに、儒教は「悪」なのか』石平著(PHP新書)を読みました。「日本と中韓『道徳格差』の核心」というサブタイトルがついています。著者は1962年、中国四川省成都生まれ。北京大学哲学部卒業。四川大学哲学部講師を経て、1988年に来日。1995年、神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了。民間研究機関に勤務ののち、評論活動へ。2007年、日本に帰化する。著書に『なぜ中国から離れると日本はうまくいくのか』(PHP新書、第23回山本七平賞受賞)など。
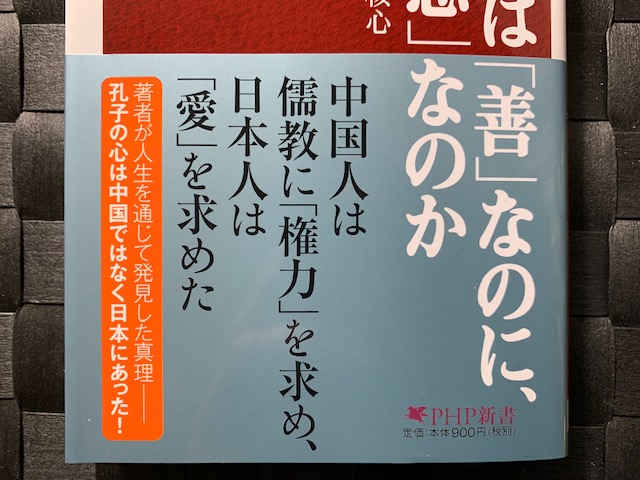 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「中国人は儒教に『権力』を求め、日本人は『愛』を求めた」「著者が人生を通じて発見した真理――孔子の心は中国ではなく日本にあった!」と書かれています。また、カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「論語はすなわち儒教のことである――日本人の多くにとっての『常識』であろう。ところが、実はそうではない。子供のころ、祖父の摩訶不思議な『教え』から『論語』に接した著者は、のちに儒教の持つ残酷な側面を知り、強い葛藤を抱く。実際の孔子は「聖人」であったのか? なぜ『論語』は絶対に読むべきなのか? 御用教学・儒教の成立と悪用される孔子、朱子学の誕生と儒教原理主義の悲劇など、中国思想史の分析を重ねた果てに著者がたどり着いた答えは、なんと『論語は儒教ではない』というものだった。曇りのない目で孔子の言葉に触れ、『論語』を人生に生かすための画期的な書」
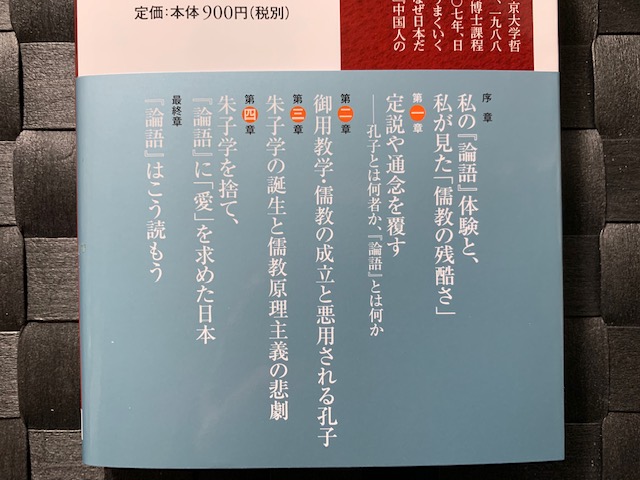 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 私の『論語』体験と、私が見た「儒教の残酷さ」
第一章 定説や通念を覆す──孔子とは何者か、『論語』とは何か
第二章 御用教学・儒教の成立と悪用される孔子
第三章 朱子学の誕生と儒教原理主義の悲劇
第四章 朱子学を捨て、『論語』に「愛」を求めた日本
最終章 『論語』はこう読もう
「あとがき」
序章「私の『論語』体験と、私が見た『儒教の残酷さ』」では、「まさに偽善と欺瞞以外の何物でもない『残酷さ』」として、夫を亡くした未亡人は自ら命を絶たなければならないというかつての「礼教殺人」の実例を示し、それがいかに非人間的なものであったかを糾弾して、以下のように述べます。
「明清時代に流行った礼教とは、要するに中国伝統の儒教の発展型であって、新儒教と呼ばれるものである。南宋時代に確立した朱子学が『天理』と『人欲』との対立軸を打ち出し、それを受けて、いわゆる『存天理、滅人欲(天理を存し、人欲を滅ぼす)』という過激なスローガンの下で誕生したのが、すなわち新儒教としての礼教であった。つまり礼教というのは、まさに『存天理、滅人欲』というスローガンの下、『礼』という強制力のある社会規範をもって、人間性と人間的欲望を抑制し圧殺することを基本理念とするものだったのである」
また、著者は「『論語』と礼教とのギャップに抱えた葛藤」として、こう述べます。
「『論語』は確かにさまざまな場面で『礼』を語り、『礼』を大事にしている。『貧而楽道、富而好礼』(貧しくして道を楽しみ、富みて礼を好む)や、『礼與其奢也寧倹、喪與其易也寧戚』(礼は贅沢であるよりは質素であったほうが良い、お葬式は形を整えるよりも心底から悲しむのが良い)などである。
しかし『論語』の語る『礼』は、どう考えても、礼教が人間性や人間的欲望の抑制に使うような厳しい社会規範としての『礼』とは全然違う。『論語』の語る『礼』は要するに、相手のことを心から大事にする意味での『礼』であって、人間関係を穏やかにするための『礼』である。そこには、人間的暖かみはあれ、礼教の唱える人間抑圧の匂いはいっさいない。とにかく後世の礼教の残酷さと冷たさとはまったく違い、『論語』から感じられるのはむしろ優しさと暖かさである。『論語』と礼教との間にはどう考えても、何の共通点もないはずである」
著者は、「デュルケームと『礼の用は和を貴しと為す』」として、こう述べています。
「私の大学院の修士課程での専攻は社会学である。私の指導教官は、フランスの近代社会学者である、エミール・デュルケームの思想を研究のテーマの1つにしていた。ある日のゼミで、デュルケームの『社会儀礼論』がテーマとなった。その学説を簡単に説明すると、デュルケームは社会統合における儀礼の役割をとりわけ重視し、人々が儀礼を通じて関係を結び、共に儀礼を行うことによって集団的所属意識を確認し、集団としての団結を固めていくものである、との説である」
また、著者は以下のようにも述べています。
「確かに『礼之用和為貴』という『論語』の言葉は、あのデュルケームの『社会儀礼論』が言わんとする真髄の部分を、一言で鋭く言い尽くしている気がする。日本の中国思想史研究家の金谷治氏は、この言葉を『礼のはたらきとしては調和が貴いのである』(金谷治訳注『論語』岩波文庫)と現代日本語に訳しているが、デュルケームの『社会儀礼論』の本質はまさに、この簡潔な一言に凝縮されているのではないか」
さらに、著者は以下のようにも述べるのでした。
「『礼の用』、すなわち礼の働きはまさに『和為貴』、つまり『和』を大事にして人間関係や社会を調和させることだ。そしてここでの『和』とはすなわち和むことであり、和やかな心であり、親和であり和睦であり、心の暖かさと温もりがその背後にあるはずである。このような『礼の用』の作り出す『和』は、まさに私が自分の保証人の奥様の振る舞いから感じたあの暖かい『和』と同質のものだ」
わたしはこれを読んで、新元号は「令和」ではなく「礼和」なら良かったのにと改めて思いました。
著者は「『論語』と儒教はまったく別々のものである」として、こう述べています。
「孔子の『論語』と、儒教とを同一視する今までの学術上の定説と歴史上の通念は、まったく間違っている。『論語』と儒教は、その本質においてまったく異なっており、そもそも別々のものでしかない。『論語』はとにかく儒教とは違うのだ。『論語』の精神は『論語』にあって、儒教にあったのではない。『論語』は『論語』であって、儒教は儒教なのである、と。そして、『論語』の精神と考えには、われわれにとって普遍的な価値のあるものが多く含まれているから、『論語』は大いに読まれるべきである。しかし、儒教とは単なる過去からの負の遺産であり、廃棄物として捨てておくべきものである、と」
 『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)
『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)
第一章「定説や通念を覆す──孔子とは何者か、『論語』とは何か」では、「実際の孔子は『聖人』であったか?」として、著者はこう述べます。
「孔子に対する共通の称号は『聖人』である。儒教の本場・中国では、孔子は宋の時代に『至聖文宣王』との称号を皇帝から与えられている。明王朝ではそれが『至聖先師』と改称され、清王朝の時代に『大成至聖先師』として定着した。そのいずれも『至聖』という肩書きがメインであって、要するに孔子は単なる聖人ではなく、聖人の道を極めた聖人の中の聖人、という意味合いである。
もちろん、歴代王朝からこのような称号や肩書きを贈られただけでなく、中国を中心とした儒教の世界においては今でも、孔子は普通、『聖人』と見做されている。『孔子=聖人』は常識の中の常識であり、疑うことのできない通念でもある。そして、この『聖人』としての孔子は、儒教における崇拝の対象ともなっているのである」
ちなみに、わたしは『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)で、聖人としての孔子について詳しく書きました。
著者は、「作られた『聖人像』を打破すべき」として、以下のように述べています。
「結局、孔子という人間は時々、意地悪くて人の気持ちをわざと弄ぶこともあれば、カンシャクを起こして弟子の自尊心を平気で傷つけることもあった。あるいは、われわれ普通の人間と同じように、怨念や妬みなどのマイナスの感情を持つこともあった。
もちろんそれは孔子の全てではないし、これだけをもって『孔子は駄目な人間だ』と、この歴史上の偉人を貶めるつもりも筆者にはない。ここで言いたいことはただ1つ、要するに孔子は決して『完璧にして理想的な人間』ではないということだ。彼にもさまざまな人間的弱みがあって人格的な欠陥もあり、良くない感情も悪い癖も持っているのだ。もちろん彼は優れた人物であるが、同時に、ときにはわれわれ普通の人間とそんなに変わらない側面を見せることもある。つまり彼は決して、後世の人々が理想化したような『聖人』ではないのである」
また、著者は「『論語』は聖典でもなければ経典でもなく、常識論の書だ」として、『論語』について以下のように述べています。
「まず確実にいえることの1つは、『論語』は哲学の書ではないということだ。ドイツの大哲学者であるヘーゲルは、『論語』の独訳を読んで『こんな書物のどこが哲学なのか』と失望して、『孔子の名誉のためにも、『論語』は翻訳されないほうがよかった』との名言を残しているが、実はドイツ人あるいは西洋人の基準からでなくても、中国人自身の思想史の基準からしても、たとえば後述の孟子や朱子の哲学を基準にして見ても、『論語』はどう考えても『哲学の書』ではない。何しろ、本章において見てきたように、孔子はそもそも哲学者ではないからである。もちろん孔子は聖人でもないから、『論語』という書物は決して、恭しく拝読すべき『聖典』ではない。そして孔子は宗教家ではないから、『論語』はキリスト教の聖書やイスラム教のコーランのような教典でもない」
著者いわく、『論語』は孔子という「常識人」が語る「常識論の書」であるといいます。
第二章「御用教学・儒教の成立と悪用される孔子」では、「『王道』と『礼治』――儒学を打ち立てた孟子と荀子」として、著者は以下のように述べています。
「要するに中国思想史上、儒学がその始祖とすべきは戦国時代の孟子であり、決して春秋時代の孔子ではない、ということである。孟子よりも半世紀後の戦国時代末期に生まれた荀子もまた、儒学の学問的体系化に貢献した一人である。荀子は趙国の出身であるが、生涯において政治権力に疎まれた孟子とは違って、荀子は各国を遊説する中で、斉の国の襄王や楚の国の春申君などの権力奢に仕えることができ、政治に携わりながら学究の生活を送った」
前漢の第7代皇帝であった武帝の時代に、董仲舒という儒学者が登場し、「天人相関説」や「性三品説」というものを唱えました。中でも「性三品説」は、孟子と荀子の儒学思想をつまみ食い的に借用しているとして、著者は以下のように述べます。
「『上品の性が生まれつきの善』という説は当然、孟子の『性善説』の借用であるが、『下品の性が生まれつきの悪』というのは当然、荀子の性悪説を受け継いでいる。そして、『王は民を教化して善へと導く』という説はやはり、孟子の『王道思想』と荀子の『礼治主義』から大きな影響を受けているのであろう」
続けて、著者は以下のように述べます。
「そういう意味では、董仲舒の『性三品説』は孟子と荀子の儒学思想の焼き直しにすぎない。彼の独創性あるいはオリジナル性は、孟子と荀子の儒学思想のいくつかの要素を借りてきて、皇帝に奉仕するような権力正当化の御用理論、すなわち政治的イデオロギーを再構築した点にある。つまり董仲舒の手によって、学問としての儒学は政治権力を正当化するためのイデオロギーとなり、まさに後世にいう『儒教』になったわけである」
「『論語』とは無関係の儒教の成立、そして孔子の神格化」として、著者は述べます。
「董仲舒が中核となる前漢の儒学者たちは『天人相関説』や『性三品説』を打ち立てて王朝の政治権力と皇帝の権威の正当化に躍起になる一方、『五経』というものを生み出して新しい数学体系の根幹にした。そこで成立したのがすなわち後世にいう『儒教』というものである。そして、この時点から南宋時代における朱子学の登場までの約1300年間、この『五経』が儒教の基本経典として儒教思想の中核的な地位を占めていたのである」
著者いわく、前漢以後の儒教には、本物の「孔子」はもはやいません。前漢以後の儒教には『論語』も生きていません。前漢以後の儒教はただの儒教であって、孔子の『論語』とは何の関係もないというのです。
第三章「朱子学の誕生と儒教原理主義の悲劇」では、「心の救済への渇望と仏教の勢力拡大」として、著者は魏晋南北朝時代に外来宗教の仏教が中国に入ってきて、急速に勢力を拡大したことを指摘し、以下のように述べます。
「仏教が中国に伝来したのは、およそ後漢時代であるが、それが本格的に広がり始めたのは五胡十六国時代と南北朝時代である。紀元4世紀頃、西域僧の鳩摩羅什などの尽力により仏典が大量に漢訳されたことは、仏教の中国普及を可能にした要因の1つであるが、仏教勢力の拡大を促す、いくつかの歴史的、社会的要因があった。その1つは、後漢末期から長く続いた殺戮と破壊の大乱世の中で、あまりにも多くの苦難を体験した人々が、心の救済を強く求めていたことである。中国伝統の儒教は、権力への奉仕こそを本領とする数字であって、大衆の救済には何の興味もないし、その役割を果たすことができない。そこで、苦しみからの解脱や死後の極楽の世界を説く仏教が現れると、それが人々の心を摑んで離さなかったのは、むしろ当然の成り行きであった」
また、「『論語』の憂鬱――『四書』の選定と祭り上げ」として、著者は述べます。
「前漢の儒教は『五経』を制作するときに孔子の名を悪用しながら、孔子と孟子の両方を儒教の最高経典から排除して、いわば『孔孟冷遇』の儒教を打ち立てた。それに対し、前漢以来の儒教を頭から否定したは、逆に孔子と孟子を引っ張り出してきて、その空白を埋めようとしたのである。朱熹の立てた道統においては、周の文王・武王・周公から北宋の周敦頤に直結するのはいくらなんでも無理があり、その思想的・歴史的繋ぎ役が必要となってくるのである。朱熹がそのための繋ぎ役として選んだのがすなわち、孔子と孟子である。前漢の儒学者たちが孔子を散々悪用したのと同様、朱熹はまた、孔子と孟子を利用しただけである」
著者は、「結局、孔子と『論語』は誕生してから1500年以上、必要とされるときだけ都合よく利用されてきたわけである。前漢から朱熹までの儒教の歴史は、孔子と『論語』にとっては、散々利用され、悪用された不本意にして憂鬱な歳月だったのであろう」とも述べています。
さらに、「漢民族の明王朝において支配的地位を確立」として、著者は述べます。
「朱熹の名声が高まったのはその没後である。彼の学問は徐々に読書人の間で広がっていって、朱熹は『朱子』と呼ばれるようになった。そして1241年、朱熹の死後41年目にして、彼は文宣王廟(孔子廟)に従祀され、朱子学が国家の正統教学であることが示された。しかし、その38年後の1279年には、南宋が元の侵攻によって滅び、中国大陸が蒙古族の建てた元朝によって支配されることとなる。だが、この異民族王朝の下で科挙試験制度が復活されたとき、科挙試験の準拠する儒教経典の解釈に朱子学が採用されることとなった。朱子学はこれで初めて国家的教学としての地位を得たのである。朱子学がさらに支配的地位を固めて一世を風靡したのは、1368年に創建された漢民族中心の明王朝においてである」
そして、「『殉節』と『守節』に追い込まれる中国女性の悲哀」として、著者は以下のように述べるのでした。
「要するに朱子学と礼教の世界では、夫の性欲を満足させその後継を生み、そして子供を育てることが『道具』としての女性の役割であるが、夫が亡くなって子供もいないなら、この女性にはもはや生きる価値はない、死ぬ以外にないのである。そして、このような考えに従って『殉節』を遂げた女性は、官府と社会から、場合によっては朝廷から『烈婦(烈女)』だと認められて大いに表彰されるのである。
このように、朱子学と礼教が盛んであった明清時代の中国社会では、夫に先立たれた女性ほど不幸なものはなかった。『守節』して夫の残した子供と家族に奉仕していくか、『殉節』して自らの命を絶つか、この2つの道しか許されない。人間としての権利、女性としての幸せなどはもってのほかであった」
第四章「朱子学を捨て、『論語』に『愛』を求めた日本」では、「朱子学を取り入れつつ、完全離脱した日本」として、著者は以下のように述べています。
「戦国時代の乱世に終止符を打って天下統一を果たした徳川家康は、安定した政治的仕組みを作っていくために、儒教を幕府の政治理念として取り入れた。そのとき朱子学が中国・朝鮮を含めた東アジアの世界では支配的地位を占めていたから、幕府の導入した儒教はもはや飛鳥時代に日本に伝来したような伝統的儒学ではなく、時代のトレンドとなった新儒学、すなわち朱子学であった。かくして、朱子学は一時、日本の思想界を支配することになったが、幸いなことに、日本人は朱子学を受け入れながらも、それとペアになっている「礼教」にはまったくの興味を示さなかった」
また、「『論語』との矛盾に気がついた伊藤仁斎」として、著者は江戸前期の思想家で朱子学に対して最も根本的な批判を展開した伊藤仁斎を取り上げ、こう述べています。
「朱子学による儒学古典の曲解や歪曲を一度洗い落として、儒教思想の本来の姿を取り戻すべきだと、仁斎は考えた。そのために彼が開発した独自の学問の方法とは、朱子学による古典の注釈や解釈を無視して、『論語』や『孟子』に書かれている古の言葉をその本来の意味において理解し会得することだった。それがすなわち仁斎の『古義学』というものである」
「仁斎が取り戻そうとした『愛』の原理」として、著者は「仁斎が取り戻そうとした儒学の原点とは何であったか。それは仁斎自身が『最上至極宇宙第一の書』と絶賛する『論語』と、仁斎自身が『論語』から読み取った『愛』の原理である」と述べます。
「『朱子学の理は残忍酷薄』という痛烈な一撃」として、著者はこう述べます。
「考えてみれば、日本の良き伝統が綿々と受け継がれる京都の町人社会の、その自由闊達な気風と文化的豊かさの中で育った仁斎が、中国流の峻烈な原理主義の朱子学から離反したのは、むしろ自然の成り行きであっただろう。『仁斎の造反』によって日本人は、江戸思想史における『脱朱子学』の決定的な一歩を踏み出したのである。その中でも、朱子学の『理』に対する仁斎の批判はまさに正論であって痛快でさえある。朱子学の原理主義に対して仁斎が投げつけた『残忍刻薄の心』の一言によって、中国の朱子学と礼教の本質が端的に表現されたのである。仁斎が同時代の中国で流行している『殉節』や『守節』の実態を知っていたかどうかは定かではない。だが、彼のこの一言はある意味では、礼教によって殺されていった何千何万の中国人女性の心を代弁していると思う。伊藤仁斎は偉大である」
「あとがき」では、著者はこう述べています。
「『論語』が語るのは「愛」であり、思いやりの『恕』であり、温もりのある『礼節』であった。だが、後世の儒教や礼教はもっぱら、『大義名分』たるイデオロギーによって、人間の真情としての『愛』や『恕』を殺そうとし、実際にそれらを見事に殺した。前漢から南宋期までの千数百年は董仲舒流の儒教が中国社会を支配し、元朝から清末までの六百数十年間は朱子学と礼教が支配したわけだが、その間の中国は、まさに『悪の教学』の毒によって冒されているかのごとき異様な社会となっていた。また、本場の中国よりも『朱子学中毒』となった朝鮮半島の李朝500年もやはり、窒息しそうな病的時代であったといってよいだろう」
非人間的な儒教が発展した中韓とまったく違ったのが日本であるとして、著者は以下のように述べています。
「日本人は古代から『論語』を読んできたが、江戸時代になって朱子学を『官学』として受け入れて以降も、『論語』は重んじつつ、しかし礼教には最初からほぼ一顧だにしなかった。そして、江戸時代の代表的な儒学者たちは、最初は朱子学から出発しておきながらも、やがて朱子学を打ち捨て『真の儒学』を求めていったのである。とりわけ、京都の『町の儒学者』である伊藤仁斎がたどり着いたものこそ、『論語』であった。彼は『論語』のなかに人間の『愛』を再発見し、『論語』を『宇宙第一の書』として推奨したのである」
そして最後に、著者は「おそらく仁斎の推奨の功もあったのだろう。江戸時代から現在に至るまで、儒教のいわゆる『四書五経』のうち、日本で一番広く読まれて、日本人に一番親しまれてきたのは『論語』であった」と述べるのでした。この『論語』に最も親しんだのが日本人であるのは同感ですが、日本が儒教の神髄を理解しているかというと疑問です。というのも、儒教は何よりも葬礼を重んじますが、日本では「葬式は、要らない」などという妄言が流布し、家族葬や直葬など、葬儀の簡略化が進む一方だからです。この点、中国や韓国のほうがまだ葬礼を重んじていると言えるでしょう。本書の内容は、一条真也の読書館『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』で紹介したケント・ギルバート氏のベストセラー著書の内容に通じていますが、同書の書評でも同じことを書きました。
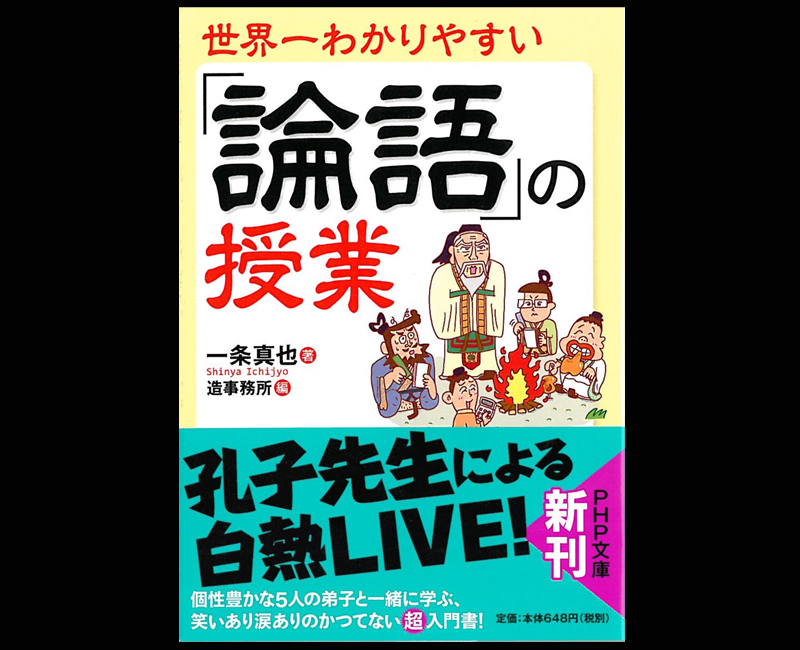 『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)
『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)
わたしは大学の客員教授として「孔子研究」の授業を担当してきました。これまで多くの日本人学生をはじめ、中国人留学生や韓国人留学生たちにも『論語』を教えるという得難い機会を与えられましたが、その授業内容をまとめた本が『世界一わかりやすい「論語」の授業』(PHP文庫)です。また、現代日本の子どもたちのために江戸時代の寺小屋の『論語』教本のアップデートを目指して作ったのが『はじめての論語』(三冬社)です。ともに多くの方々から読まれています。
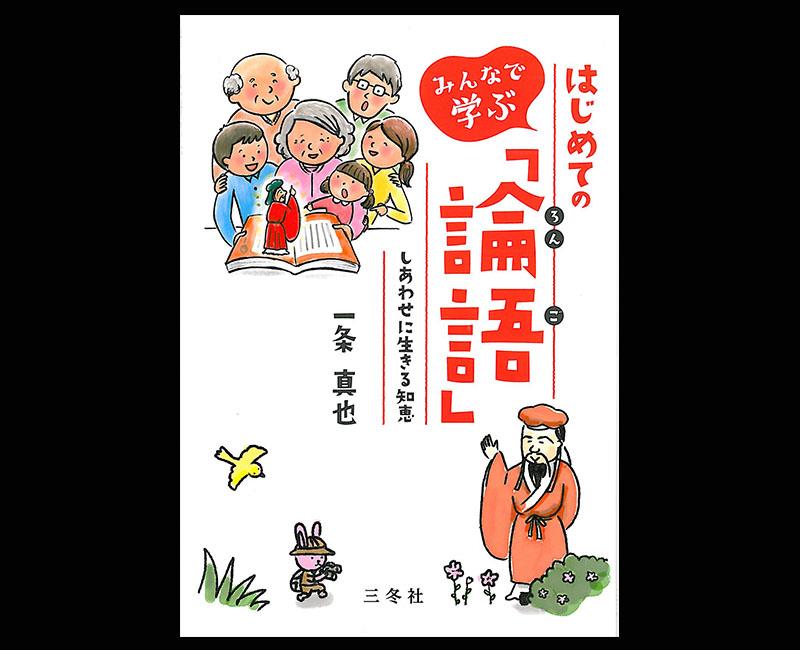 『はじめての論語』(三冬社)
『はじめての論語』(三冬社)
最後に、本書のテーマとも通じるのですが、わたしには『徹底比較!日中韓 しきたりとマナー〜冠婚葬祭からビジネスまで』(祥伝社黄金文庫)という監修書があります。この本には、東アジアの平和への強い願いが込められています。もともと、日本も中国も韓国も儒教文化圏です。孔子の説いた「礼」の精神は中国で生まれ、朝鮮半島を経て、日本へと伝わってきたのです。しかしながら、ケント・ギルバート氏や石平氏も言うように、現在の中国および韓国には「礼」の精神が感じられません。
 『徹底比較!日中韓 しきたりとマナー』(祥伝社黄金文庫)
『徹底比較!日中韓 しきたりとマナー』(祥伝社黄金文庫)
中国や韓国は、日本にとっての隣国です。隣国というのは、好き嫌いに関わらず、無関係ではいられません。まさに人間も同じで、いくら嫌いな隣人でも会えば挨拶をするものです。それは、人間としての基本でもあります。この人間としての基本が広い意味での「礼」です。「礼」からは、さまざまな「しきたり」が派生しました。それぞれの国の「しきたり」を知ることは、その国の文化を知ることです。そして、互いの文化の違いと共通点を知ることは、その国の国民の「こころ」を知ることにほかなりません。わたしは、冠婚葬祭や年中行事に代表される「しきたり」を知ることによって、日中韓の相互理解、国際親善、そして世界平和につながることを心から願っています。なにしろ、孔子が説いた「礼」とは究極の平和思想なのですから……。