- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.08.11
死者を想う季節の中で、『死と生』佐伯啓思著(新潮新書)を読みました。日本を代表する社会経済学者で思想家でもある著者は、1949年奈良県生まれ。京都大学名誉教授。東京大学経済学部卒。東京大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。2007年正論大賞。ブログ『反・幸福論』で紹介した本をはじめ、『隠された思考』(サントリー学芸賞)、『日本の宿命』、『正義の偽装』、『西田幾多郎』、『さらば、資本主義』、『反・民主主義論』、『経済成長主義への訣別』などの多くの著書があります。
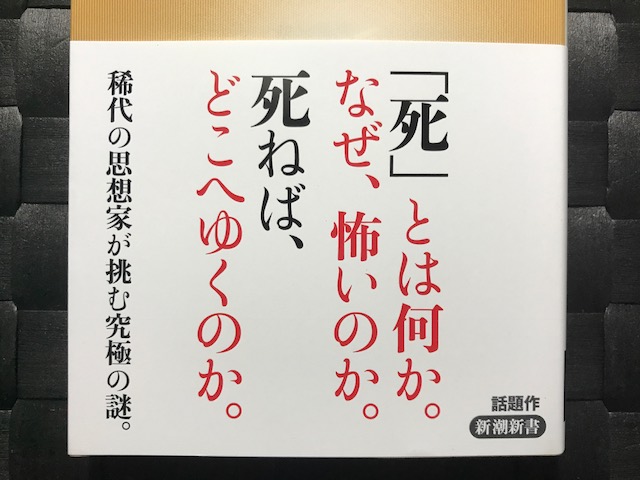 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「『死』とは何か。なぜ、怖いのか。死ねば、どこへゆくのか。」「稀代の思想家が挑む究極の謎」と書かれています。
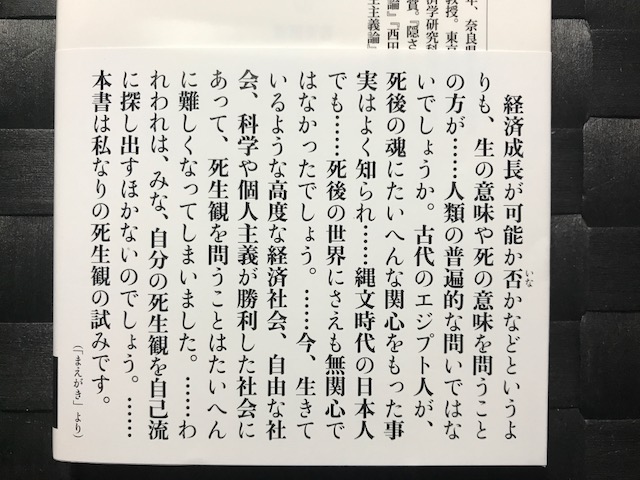 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「『死』。それは古今東西、あらゆる思想家、宗教家が向きあってきた大問題である。『死ぬ』とはどういうことなのか。『あの世』はあるのか。『自分』が死んだら、『世界』はどうなるのか――。先人たちは『死』をどう考えてきたのか、宗教は『死』をどう捉えているのかを踏まえながら、人間にとって最大の謎を、稀代の思想家が柔らかな筆致で徹底的に追究する。超高齢化社会で静かに死ぬための心構えを示す、唯一無二の論考」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「まえがき」
第一章 超高齢化社会で静かに死ぬために
第二章 「一人では死ねない」という現実を知る
第三章 われわれは何ひとつわからない
第四章 死後の世界と生命について
第五章 トルストイが到達した「死生観」
第六章 仏教の輪廻に見る地獄
第七章 「あの世」を信じるということ
第八章 人間は死ねばどこへゆくのか
――浄土と此土
第九章 「死の哲学」と「無の思想」
――西部邁の自死について
第十章 「死」と日本人
――生死を超えた「無」の世界
「あとがき」
「まえがき」で、著者は以下のように述べています。
「政府も識者も財界人も、イノベーションとグローバリズムで日本は成長できる、経済はよくなる、われわれの生活は大きく変化する、というのですが、同時に、今日の日本の大問題は、人口減少社会化、高齢社会化ではなかったのか、と思ってしまうからです。いや、『思ってしまう』などという主観的かつ印象的ないいかげんな話ではなく、まぎれもない客観的かつ統計的な現実なのです。すると、このふたつの傾向を掛け合わすとどうなるのかというと、年寄りばかりが国土を覆ってゆくこの日本社会で、AIやロボットやドローンや生命科学といったイノベーションをどんどん推進し、グローバルに活躍できる人材を育てれば大きく成長できる、といっているわけです」
また、著者は以下のようにも述べています。
「高齢化社会とはまた、本来は、もはやモノを増やして、生活の物質的な向上を求めるような経済段階ではありません。食べ物や着るものや遊ぶものをいくら増やしても、それほどありがたみのある社会ではありません。それは本来は成熟社会のはずなのです。成熟社会とは、長い人生の生の意味づけや、やがてすべての人に訪れる死への準備へと人々の関心が向けられる社会です」
続けて、著者は以下のように述べています。
「人生の最後をどう迎えるか、というのはただ高齢者だけの関心ではなく、本当は、若者もマスメディアも含めて、ひとつの国民のもつ死生観の問題なのです。ただ日本のような『超』高齢化へと突入する社会は、この普遍的な問題を、実際上、高齢者の切実な社会問題へと押し上げてしまうのです。ただそれは、私には、介護施設やターミナルケアといった目に見える社会問題であるだけではなく、それ以上に、まずはひとつの国民の精神的な文化や内面的な価値の問題だと思われるのです。にもかかわらず、現実には、高齢化社会のもつ精神的価値や文化への関心などどこかへ吹っ飛んでしまい、もっぱら、『一億総活躍社会』をつくれば日本はますます元気になる、といった調子になっている」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「経済成長が可能か否かなどというよりも、生の意味や死の意味を問うことの方がはるかに人間的な問いでもあり、若干、大げさにいえば、人類の普遍的な問いではないでしょうか。古代のエジプト人が、死後の魂にたいへんな関心をもった事実はよく知られていますが、おそらくは縄文時代の日本人でも、ただただ生きるために食物を探しまわっていただけではなく、生を可能ならしめるために儀式めいたことをやり、死後の世界にさえも無関心ではなかったでしょう。歴史をもう少し手前まで手繰り寄せれば、人々は、確実に、生を可能とするものや死をもたらすものに強い関心を持っていました。つまり宗教的意識であり、死生観です」
第一章「超高齢化社会で静かに死ぬために」では、「年寄が『生きた粗大ゴミ』になる」として、著者は述べます。
「今日65歳以上の高齢者人口はすでに3000万人を超えていますが、2025年には約3700万人になると予想されています。そして、そのうちの10%近くの約350万人が認知症になるとみられている。また、高齢者の1人暮らしの世帯は2025年で680万世帯(約37%)と推計されているのです(国立社会保障・人口問題研究所の推計)。へたをすれば相当な数の認知症老人がそのあたりを徘徊しかねない。私もその1人ですが『生きた粗大ゴミ』が巷に大量放出されることになるのです。これが『2025年問題』といわれるもので、戦後日本の経済成長を牽引してきたいわゆる団塊の世代(ベビーブーム世代)が、75歳以上の後期高齢者になるからです」
また、「孤独に老いてゆくこと」として、著者は述べます。
「60歳過ぎになって定年で仕事をやめ、いわば社会から放り出されて1人でいる、ということ。そして、そのままどのようにして死を迎えるか、ということ。1人で老い、死へ向かうこと。その最後の生をどう過ごすか、ということ。ある意味では、この人間の普遍的な問題にわれわれは、日々、この高齢化が進む社会で、誰もが改めて直面し、もはや目を背けることができなくなった、ということなのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「かつては家族があった。地域もあった。それが、かろうじて老いや死の露出を回避していたのです。しかし、今日、家族も地域もほとんど崩壊状態になってしまうと、われわれは、むきだしの老いや死に直面せざるをえなくなる。いや、この人間の生の普遍的で根本的な問題がむきだしのままで露呈してきたのです。しかし今日、老いや死に面して、それをいかに受け入れるか、あるいは処遇するかというと、われわれには何の手掛かりもありません」
第二章「『一人では死ねない』という現実を知る」では、「本当に恐ろしいのは『死に方』である」として、著者は以下のように述べています。
「多くの人がいいます。『死など考えても仕方ない』『死などこわがっても仕方ない、どうせみんな死ぬんだから』と。それはそうです。私もそのことには大賛成です。しかし、こういうことをいうたいていの人が見落としているのは、死とは、生が徐々に衰退し、変形し、われわれの存在の在り方を歪めてゆくプロセスであり、その極限に現れるものだ、という事実です。こういう厳然たる事実を見落としているか、もしくは、見ないふりをしているかでしょう」
続けて、著者は以下のように述べています。
「われわれが気にしているのは、死そのものではなく、死のほんの少し手前、つまり、死にゆく、その最後の生の在り方です。『死』ではなく『死に方』なのです。『死』は経験できませんが、『死に方』は経験できるのです。いやそれどころではありません。いやおうなく『経験』させられてしまうのです。この経験から逃れることはできません。それが恐ろしいのではないでしょうか。『死』が恐ろしいとか恐ろしくない、とかいっても意味がありません。経験できないものについて、恐ろしいも恐ろしくないもないからです。しかし、『死に方』は、いやでも経験させられ、それから逃れることはできないのです」
また、「人は一人では死ねない」として、著者は述べます。
「『死』ほど個人的なことはほかにありません。日常的な『生』のなかで起きる多くの事柄は他者によって代行可能です。少なくとも、想像上の可能性の次元においては代替できるでしょう。しかし、『死』だけは絶対的に代行不可能です。他者の介在する余地はまったくありません。心中などといっても、死にたいもの同士が時間と場所を共有しているだけのことです。あくまで『死』は『個』にやってきます」
さらに、「死によって励まされる」として、著者は以下のように述べています。
「はっきりとしていることは、とてもではないが、人は1人では死ねない、ということなのです。急激にバタッと倒れても自分では何もできない。排泄の始末も自分ではできません。痛み止めの加減も自分では指示できないでしょう。延命治療の判断も自分では指示できません。肝心なことは何ひとつできないのです。最後の点滴をはずすという行動も本人にはできないのです。誰かにケアしてもらうほかないのです。ケアするとは、『うまく死なせる』ということです」
そして、「『自死という生き方』について」として、著者はこう述べるのでした。
「人間の死に方としては大雑把に3つあるでしょう。第一に事故や災害死や戦死、つまり、外部からの力による不可避的で突然の死。第二に老衰や病死、つまり、生物学的な自然死。そして第三に『自死』です。まだ世の中が貧しく、また人々が若くして病死した時代、あるいは戦時中は、人々はともかくも生の確保に必死でした。生きることに精いっぱいだった。しかし、元気に活動ができる健康寿命を越えて、はるかに寿命の延びた現代では、3番目の『老人の自死』という問題こそが、最大の焦点になってくるのかもしれません。実際、老老介護で疲れて自死する老人は結構いるのです」
第三章「われわれは何ひとつわからない」では、「『答え』の出ないやっかいな『問い』」として、著者は以下のように非常に興味深いことを述べています。
「おそらく人間にとっての根本的な逆説は、人間にとってもっとも重要でかつもっとも関心のある事項について、われわれは何ひとつわからない、ということでしょう。『死』がそれです。おそらくは、このもっとも根本的な事実、誰もがとても深く関心をもっているこの不可避な事実について、ほとんど何ひとつ確実なことを論じることも、また書くことさえできない、ということなのです」
これを読んで気づいたのですが、わからないことに対する人間の答えこそが「儀式」ではないでしょうか。「死」とともに「結婚」も謎に満ちています。誕生や成長や老いも謎だらけです。その「わからないこと」に対して、人間は誕生祝い、七五三、長寿祝いなどの「かたち」を与えて、「こころ」の不安をコントロールしてきたのではないでしょうか。詳しくは、拙著『儀式論』(弘文堂)をお読みいただきたいと思います。
「人間を超えた圧倒的な『力』」として、著者は述べます。
「『死』は『絶対的なもの』というよりほかありません。『絶対的なもの』を人は経験もできなければ、言葉で言い表すこともできません。それは名状しがたい、しかし、厳然とある何ものかなのです。それは、もはやわれわれの経験を超えた事実であり、それについて論じることさえいっさい受け付けない確たる事実なのです。われわれの経験には不確かなものはいくらでもありますが、『死』という事実ほど確たるものはありません。実際、『生』の中身は人によって様々でしょう。幸福も様々ですし、生き方も様々な可能性をもつ。人の知恵や努力によって変えることもできます。それらはすべて相対的なのです。偶発的でもある。しかし、『死』という事実だけは、きわめて普遍的で、絶対的で、必然的です。『死に方』はいろいろあっても、『死』という事実(状態)は、男女、貴賤、人種、美醜、善悪をまったく問わず、まったく同じであって、人智でも努力でも祈願でもどうにもなりません。まさしく『絶対的』なのです」
また、「『絶対的な無意味』の不気味さ」として、著者は以下のように述べています。
「われわれは、普通、『生』から『死』へと一挙に相転移するわけではありません。『生』と『死』の間に、『生』でも『死』でもないような、『老』や『病』があるのです。『生』は徐々に力を失い、意味を薄めてゆき、世界は色あせてゆき、そのあげくに『死』へといたる。そのプロセスが苦しく、つらく、想像を絶するようなものであり、屈辱的でさえあるのです。『死』へいたるためには、もはや『生』ともいえない『生』を送らざるをえない」
それに比べれば、「死」は救済とさえいえると指摘し、著者は以下のように述べています。
「『生』の究極の時間からの解放であり、苦をもたらす物理的身体からの解放だからです。『絶対的な無意味』である『死』に対しては、怖いも恐ろしいもありません。怖さや恐ろしさは、何かある意味をもった存在や事態についていえることだからです。『死』へと向かって『生』が徐々に蝕まれ、衰弱し、意味を喪失してゆくことが恐ろしいのです。多くの人が、病気で苦しんで死んだ自分の近親者の死に顔を見て、『ようやく安らかな顔になった』といって、ほっとしたりします。『死』は恐怖どころか『救済』でもあるのです」
「誰も論じられない」として、著者はこう述べます。
「不気味さから逃れるにはどうすればよいか。さしあたり答えは簡単です。意味を求めないことです。意味のないものに意味を求めるから不気味になるのであって、意味のない、もしくはわかりようもないものについて意味を求めるのをやめることです。それは、この『絶対的な無意味』について論じることには意味はない、と高をくくることです。『絶対的な無意味』にそもそも意味を求めようとするから困る。つまり『死』について論じたり、思念したりすることには意味がない、と割り切ればよい。そんなことを論じても考えても仕方ないのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「実際、考えてみれば、西洋も日本も併せて、われわれの前には膨大な数の哲学書も文学書も積まれていますが、正面から『死』について論じたものはほとんどない、といってよいほどでしょう。現代の哲学者や文学者でも、この主題でまとまったものを書いた人はほとんどいないでしょう。驚くべきことといえば驚くべきことで、『死』というこの人生の最大級の問題に関心がないはずはない。しかし、実際には、論じることはできないのです。それは、先に述べたように、それについて論じることは『死』ではなく『生』の側の行為だからであり、言い換えれば、『死』を論じることは、『死』ではなく『死の概念』に意味をもたせることだからです。そして『絶対的な無意味』に意味をもたせることはできないからです」
正面から「死」について論じた本といえば、最近では、話題になった一条真也の読書館『「死」とは何か』で紹介したシェリー・ケーガンの哲学書が思い浮かびますが、同書もまた、「死」ではなく「死の概念」に意味をもたせたといえます。
「『不気味さ』の正体とは」として、著者は述べます。
「たとえば親しい人が急に死んだとき、多くの人は、悲しいとかつらい、というより前に、まず、何とも言えない奇妙な不気味な感じをもつのではないでしょうか。私の場合は、だいたいそうでした。まだ子供だった頃、近所のよく知っているおばあさんが死に、葬式にいってお棺に納まった死体を見たときの印象は、何か名状しがたい不気味なものでした。怖いというのでもなく、悲しいというのでもなく、ただ不気味だったのです。そして、その感じは、大人になって、親しい人の遺体を見た時にも同じでした。死者とは生物体なのか単なる物質なのかよくわかりません。物質化した生物体というか、生命を失った生物体というのか、ともかく、その『意味』を確定するのが難しいのです。私の場合、お棺に入った遺体を見た時、たいてい、何とも表現のしようのない居心地の悪さを感じてしまいます。怖いでもなく寂しいでもなく、しいていうと不気味さということになるのですが、それは、必ずしも動かない死体のはなつ不気味さではない。むしろ昨日までは話をし、活動をしていた『生』というものを無意味化するという『死』そのもののもつ不気味さといったものでした」
そして、著者は「なぜ『死』を恐ろしく感じるか」として、こう述べるのでした。
「『観念としての死』は、われわれに『死とは何なのか』という問いを差し向けるのですが、それは決して出口へとわれわれを導くものではなく、答えのない、しかも窓もない暗室のような部屋へとわれわれを誘導してゆく。この密閉された部屋で、われわれは、苦しい呼吸のなかで、出口を探して、ひたすらもがくだけでしょう。そしてそれはまさしく恐怖にほかなりません。『死』という必然によって『生』が囲い込まれ、脅かされるという感覚は、確かに『死』こそは恐ろしい、という恐怖を与え続けるでしょう。こうしてわれわれは、それを『死の恐怖』などというのです。『死は恐ろしい』と考えてしまうのです。しかしそうではありません。『死が恐ろしい』のではなく、『死について考えること』が、われわれを恐怖に陥れるのです。より正確にいえば、『死について考えるにもかかわらず、まったく何の解答も得られないこと』が恐怖を与えるのです」
第四章「死後の世界と生命について」では、「死んだ後に何が起きるか」として、著者は以下のように述べています。
「私は、いくら『死ねば何もなくなる』といっても、ここで述べられている数多くの霊的現象をすべて錯覚だというほどの勇気はありません。少なくとも、地震や津波で身内を突然失った多くの人々が、何か説明のつかない不思議な体験をしたと信じていることは事実であり、しかも、多くの場合、その霊的体験によって残された家族が多分に安らかな気持ちになれた、という事例を読めば、そのことに疑いをさしはさむ必要もありません。それを読んでいるこちらもつい静かな感動に誘われてゆきます。いくら『死ねば何もない』といっても、こうした感動まで否定することはできません。とするなら、やはり『わからないことはわからない』というほかないのです」
また、著者は「ソクラテスはこう教えている。『人間は肉体から抜け出て霊的(精神的)存在になればなるほど真理に近づく。だから死を恐れる理由は何もない』と。ショーペンハウエルはいう。『そもそも人間の意思と認識がなければ、この世界は存在しないのである。だから、世界の本質は空無である』と。そして仏陀はいう。『苦痛と病気と死の避けがたさを意識しながら生きゆくことはできない。だからわが身を生より脱却させ、死後に生命が二度とよみがえることのないように解脱すべきである』と。このどれもが、生の苦痛や無意味さを述べているのです」とも述べています。
さらに、著者は以下のように述べています。
「宇宙の素粒子から出発しようと、この世界の背後にある『空無』であろうと、あるいは、ソクラテスのいうような霊性の世界(エルの物語に述べられる冥府)にせよ、いわば『無限』(永遠)の世界である。これに対して、われわれの生きているこの人間世界はあくまで『有限』である。『有限』な人間世界の出来事の意味を『無限』から眺め、その結果、無意味だという結論を導いたそのやり方が間違っていた、というのです。人間の有限の世界の意味はあくまでその有限の現実社会のなかに手掛かりを求めるべきであった。それを絶対的で永遠の『無限』と混同していた、というのです。宇宙的な『無』であろうと、物質を構成する最小の素粒子であろうと、はたまた、永遠の霊魂であろうと、そもそも、この『無限なるもの』は理性で把握できるものではなく、理性を超えたもうひとつの知恵によってとらえるほかない。それは信仰の世界だというのです」
著者はロシアの文豪トルストイの『人生論』に言及し、「私とは何なのだろうか」として、こう述べます。
「トルストイはきわめて優秀だった兄の死に大きな衝撃を受けました。では兄が死ねば、それで兄との関係はすべて終わったのか。そうではありません。兄の思い出が残る。それは、兄の顔形や声というより、むしろ『精神の形の思い出』だというのです。肉体的つまり物質的なものではなく、兄のもっていたある種の精神の力が、自分の精神にこれまでよりも強く働きかける。思い出とはそういうものです。思い出とは、声や顔や動きというおぼろげな物的な形象をとるとしても、本質的には精神に働きかけるものであり、精神に働きかけるものは精神でしかありません」
こういう作用を何といえばよいのか。トルストイはそれを「生命」と呼ぶと指摘し、「キリストとトルストイ」として、著者はこう述べます。
「イエス・キリストの死は、彼を実際に見ていない、何の交流も関係もない数えきれない人々の生を変え、人生に影響を及ぼしてきたではないか。兄の死は、身近で起きたことだ。しかし、記憶や伝承や想像力がある限り、人は、ずっと昔に死せる者からも影響を受けることはできる。兄の死が、1000年前であっても、私は影響を受ける。それこそが『生命力』である。こうして、私の生の根本は、すべて、私以前に生き、とうの昔に死んだ人々の生命からなっている、ということになる」
続けて、著者は以下のように述べています。
「したがって、人はまた誰でも、自分の死後も他人のうちに生き続けることができるのでしょう。その意味で、死んだ人々の生命はこの世限りのものではないのです。もしも、このように考えれば、これまた死は恐れるものではなくなります。私が死んでも『生命』の消滅するはずのないことを信じられるからです。いや、そう信じることができれば死は恐怖でも何でもなくなるでしょう」
そして、著者はトルストイの死生観について、「トルストイの死生観はなかなか興味深いものです。一方には生も死も『無』であるという意識があり、他方には、生も死も超えた永遠の『生命』がある、というふたつの極をもっているのです。これは実は、仏教や日本的な自然観に親しんだわれわれにも馴染み深く感じられることではないでしょうか」と述べるのでした。
第五章「トルストイが到達した『死生観』」では、著者はトルストイが「生と死」を扱った小説である『イワン・イリイチの死』を取り上げ、「『すべて偽物で無意味』という虚無」として、以下のように述べています。
「『死』という途方もない『絶対』を前にすれば、この世という、それこそ相対世界におけるささやかな成功や失敗や名声や利益などは、塵、芥ほどの価値もない、ということになるでしょう。どんぐりの背比べで、勝ったの負けたの、得をしたの損をしたの、といってもたかが知れた話です。しかし、その勝ち負けや、得や損で一喜一憂し、家族にも苦労を与え、他人も傷つけて、自分も得意になったり落ち込んだりしていた。それは確かに偽りの人生だったということになる。とすれば、それ自体がたいへんに罪深いというほかありません」
また、「死ねばすべては『無』になる」として、著者は以下のように述べています。
「たとえば、ハイデガーは、常に死を想起し、死を前提として覚悟的に見据えることから生の実存的意味を見出す、という方向をとったわけです。あるいは、『葉隠』のような日本の武士道にも似たところがあり、これも常に死を意識し覚悟することで武士としての生の意義を確かなものとするわけです。ところが、では実際の「死」は、というと、とてもではありませんが、『葉隠』が想定しているような見事な、意思的な決断による生の遮断どころではありません。実は『葉隠』も同じ問題を抱えてはいたのですが。それは、もはや武士のように戦場で名を残して戦士として死んだり、主君に殉じて切腹するという時代ではなかったということです」
第六章「仏教の輪廻に見る地獄」では、「『地獄』とは何か」として、著者は「死は生にとって二重の意味をもってきます」と指摘し、「第一に、生が、大きな苦しみだとすれば、死は、生という苦痛からの解放であり唯一の希望ですらある。そして第二に、それにもかかわらず、死後の世界がまったく不明であり、想像を絶するものであるとすれば、死は恐怖である。つまり、死は、救済と恐怖のふたつの面をもってくるでしょう」と述べています。
第七章「『あの世』を信じるということ」では、「『あの世』を信じられない高齢者」として、著者は述べます。
「死が身近にリアリティをもってくると、むしろ曖昧なものや未知なものに死を委ねようという気がしなくなるのではないでしょうか。しかし平安末期や鎌倉となればだいぶ違います。信仰ということの切迫性が違うのです。同じ『あの世を信じる』や『輪廻転生を信じる』といっても、彼らの方が、信仰のもつ切迫感ははるかに強かったでしょう。死を意味づけるものが他に何もないのです。救済を求める心理ははるかに強かったでしょう。だから、具体的な浄土や極楽というもののイメージを必要としたのでしょう。そこでこそ、仏教学者の鈴木大拙のいうような『日本的霊性』がくっきりと立ち上がった、ということもできるのです」
また、「『植物的死生観』と『生死連続観』」として、著者はいkのように述べています。
「農耕を基盤とした生死連続的観念は、古神道的な儀式のなかにいくらでも見て取ることができるでしょう。たとえば、神社や鎮守の森で、田の神に豊作祈願をして歌や踊りを奉納する儀式は、一種の鎮魂儀式といってよい。そこにまた、豊穣をもたらす力をもった『迦微(カミ)』の観念が生み出され、これらの農耕儀式はまた、カミの供応という意味ももってくるでしょう。それが天皇を軸にした国家共同体的な儀式にまでなったのが『大嘗祭』です。大嘗祭のような本格的なものではなく、こぢんまりとした農耕儀礼は今日でも地方の祭りのなかにいくらでも残っているでしょう」
著者は、哲学者の磯部忠正氏が著書『「無常」の構造――幽の世界』や『日本人の信仰心』(ともに講談社現代新書)において、日本における「自然の根源的な生命のリズム」を繰り返し強調していることを紹介し、「鎮魂呪術と日本人」として、こう述べます。
「磯部氏によると、豊作祈願の踊りとは、衰弱しつつある生命に活力を取り戻し、また死んだ生命を蘇生する儀式なのであり、それは別の言い方をすれば「霊(たま)ふり=魂(たま)ふり」の儀式ということになる。『霊ふり』とは、霊魂の宿った身体を揺さぶり、振ることによって霊魂に再び活力を与える。それはまさに鎮魂呪術にほかなりません。鎮魂とは、身体から遊離したり、遊離しそうな魂を招き寄せて、再び身体に定着させることなのです。しかも、昔は、農耕だけではなく、人が死んだときの葬送においても、『霊ふり』の儀式が行われた。『鎮魂』とは、もともとは、死んで活力を失い、肉体から遊離しかかっている魂を肉体に呼び戻し、再び生命力を与えるための歌舞儀式だったのです」
また著者は、磯部氏の言説を引用しながら、以下のようにも述べています。
「『日本の祭りは、本質的に鎮魂呪術であり、その中心になったのが歌舞や音楽をともなった魂振りだった』(『日本人の信仰心』)ということにもなるのです。それは農耕儀礼から葬礼の儀式にいたるまで基本的には同じなのです。なぜなら、それは農耕における植物も人も包摂した生命の再生と刷新であり、そのための死霊の招迎と鎮送だったからです。民俗学者の折口信夫が述べたように、こうした儀式をもともと『遊び』といったのであり、その役割をつかさどる職業的儀礼者を『遊部(あそびべ)』と言ったのです。すると、植物と同様に、人間もその身体は滅んで消えてなくなっても、生命は引き継がれている。死んでもまた再生する。この生命とはいいかえれば『霊魂』といってよい。とすれば、『霊ふり』の儀式や鎮魂の儀礼が、やがて『祖霊の招致』になっても不思議はありません」
このあたりは拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の内容にも通じます。同書では、「遊部」についても詳しく述べました。
さらに著者は、「生命力の再生とは霊魂の清め」として、以下のように述べています。
「死から再生へと向けるには、まずは、この穢れを取り払う、つまり、浄化するという清めの儀式が必要になった。肉体から魂を切り離し、魂の浄化、霊魂の浄化、ということです。先の『霊ふり』も、魂の浄化と見てよい。生命力の再生とは、霊魂の清めにほかなりません。かくて、日本の、とりわけ神道系の宗教では、清浄を中心的な価値におき、『清め』ということが儀礼の中心に置かれる。穢れを取り払うことこそがその重要な役割となるのです」
そして、第十章「『死』と日本人――生死を超えた『無』の世界」では、「日本人にとっての『死』」として、著者は以下のように述べるのでした。
「生も死も自然のなかにある。そこにおのずと生命が循環する、ということです。この自然の働きに任せるのです。とすれば、われわれは特に霊魂はあるのかないのか、あるいは来世はあるのかどうか、などということに悩まされる必要はない。確かに、生も死もどちらでもよい、などと達観することはできません。しかし、この達観に接近しようとしたのが日本的な死生観のひとつの大きな特徴だったのであり、それは現代のわれわれにも決して無縁ではないでしょう」
オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。死の事実を露骨に突き付けることによってオウムは多くの信者を獲得したが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、言挙げする必要などありません。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということです。問われるべきは「死」でなく「葬」なのだと思います。そんなわたしですが、本書は非常に興味深く読みました。「死」だけではなく「葬」の意味まで考えさせてくれ、さらには「人間とは何か」という問題を考えさせてくれる名著だと思いました。
