- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1760 グリーフケア 『グリーフケアの時代』 島薗進、鎌田東二、佐久間庸和(弘文堂)
2019.08.24
東京に来ています。23日、わたしが監査役を務める互助会保証株式会社の株主総会、取締役会、監査役会、役員意見交換会に出席。この日の朝、『グリーフケアの時代』(弘文堂)の見本を受け取りました。「『喪失の悲しみ』に寄り添う」というサブタイトルがついています。上智大学グリーフケア研究所の所長の島薗進氏、同研究所の副所長で特任教授の鎌田東二氏、そして同研究所の客員教授である佐久間庸和の3人の共著です。
『グリーフケアの時代』(弘文堂)
佐久間庸和とは、わたしの本名です。島薗氏は東京大学名誉教授、鎌田氏は京都大学名誉教授でもあり、ともに日本の宗教学の世界のツートップです。このお二方と小生の名前が並ぶなんて、信じられない思いです。本書は98冊目の「一条本」であり、本名では4冊目の著書となります。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「癒やしを求める人のために いまできる、すべてのこと」と大書され、続けて「大切な人を失った人たちと、その悲しみを癒やしたいと願う人たちに捧げる、日本で最初のグリーフケア研究所による鎮魂のためのテキストブック」と書かれています。
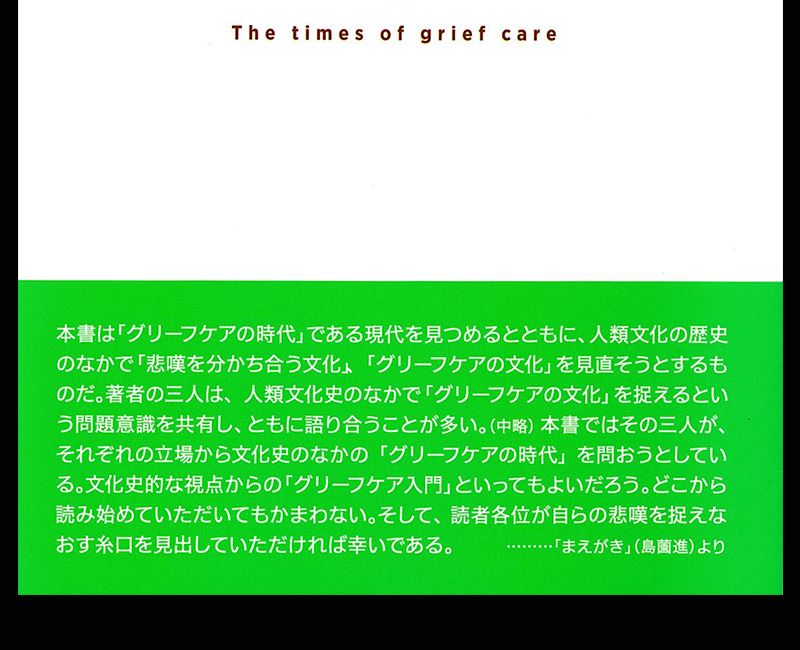 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンには、以下のように書かれています。
「上智大学グリーフケア研究所は、グリーフ(死別による悲嘆)を抱える方のケアについての研究と、グリーフケア、スピリチュアルケアに携わる人材の養成を目的として設立されました。『臨床傾聴士』『スピリチュアルケア師』等の資格取得のための専門課程の他、一般向けの公開講座にも力を入れています。本書は学問としてのグリーフケアの要点をまとめた入門書として、大切な人を亡くしたご本人はもちろん、宗教家や支援職の方々にも資する内容となっています」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」島薗進
第1章 日本人の死生観とグリーフケアの時代(島薗進)
一 ふるさとが蘇る?
「グリーフケア」の語が身近になる過程
絆の回復と故郷
いのちの源としての「故郷」
古くなった「故郷」
復活した(?)「故郷」
妣が国へ 常世へ
二 「喪の仕事」と宗教文化
フロイトのグリーフ論
喪の仕事
「対象喪失」と愛のゆくえ
喪の文化がまだ健在だった頃
悲しみを分かち合う儀礼の後退
三 ともに唱歌・童謡を歌う国民だった頃
赤とんぼと童謡
野口雨情と悲しい歌
故郷から遠くへ去った子供
「大衆のナショナリズム」の底上げ
悲しみを共有・分有することの困難
四 悲嘆を分かち合うことが困難になる
悲しみをともにするという感覚
死者のためにともに泣く生者たち
戦死した若い軍人・兵士の追悼の困難
悲嘆を分かち合うことの困難をどう超えていくか
五 寄り集い悲嘆を分かち合う
「ちいさな風の会」から「Withゆう」へ
「生と死を考える会」の中のグリーフケア
事故や事件の被害者とグリーフケア
日航機墜落事故と8・12連絡会
一人ひとりの悲しみがつながっていく
六 グリーフケアと日本人の死生観の更新
御巣鷹山に登り、死者と会う
悲しみをわかち合う新しい社会の在り方
水俣病と「本願の会」
本願の会と罪・魂・祈り
せめて魂の救われるよう共に祈り続けたい
悲嘆の分かち合いの新たな広がり
伝統的な宗教性や死生観の蘇生
第2章 人は何によって生きるのか(鎌田東二)
はじめに
一 予期せぬ痛みと「ヨブ記」の問い
モーセの言葉
三つの問いと六つの命題
何を支えに生きるのか
不条理な苦しみや痛み
さらなる三つの命題
二 心の不可思議~仏教の心観
神を放棄
嘘というケア
「心」の処方
「怨み」の捨て方
最澄と空海
三 心の清明――神道の心観
異世界接続法と現実直視法
『古事記』というテキスト
『古事記』の光と闇
変貌するスサノヲ
四 二種類の死生観
~本居宣長と平田篤胤の安心論
国学者たちの希望
「死」も曖昧さでとらえる
徹底的に探究した平田
身の丈に合った死生観
五 現代人の死生観探究
マインドフルネス瞑想とは
「臨床宗教師」とは何か
「G.R.A.C.E.」とは何か
死の受容
おわりに
第3章 グリーフケア・サポートの実践(佐久間庸和)
はじめに――グリーフケアとの出合い
悲嘆の原因とプロセス
●ケース1 ケアとしての葬儀の取り組み
葬儀をあげる意
●ケース2 ケアとして遺族会の役割
「うさぎの会」という自助グループ
グリーフケア・サポートの目指すもの
●ケース3 ケアとしての「笑い」
●ケース4 ケアとしての「読書」
物語から学ぶ死の真実
涙は人間がつくるいちばん小さな海
ハートフル・ファンタジー
五つの物語からのメッセージ
●ケース5 ケアとしての「映画」
臨死体験としての映画鑑賞
幽霊映画とグリーフケア
「あとがき」鎌田東二
「まえがき」の冒頭を、島薗氏はこう書きだしています。
「大切な人の死によって、からだの一部をもぎとられたような衝撃を受けたり、心に大きな空白ができてしまったように感じ途方に暮れたといった経験をした人は多い。死別による悲嘆ということであれば、ある年齢以上の人なら見に覚えのあるのがふつうかもしれない。親やきょうだい(さらには、祖父母、おじおば、いとこ)との死別はごくふつうのことだが、逆に子どもの死に立ち会うのは辛い。親やきょうだいが死んだ子どもの辛さは代弁するのも困難だろう」
続いて、島薗氏は以下のように述べています。
「こうした喪失による重い悲しみを、グリーフとか悲嘆とよぶ。すぐに思い浮かぶのは、近しい他者との死別だが、生き別れ、大切な仕事や生活の場の喪失、誇りや生きがいの喪失など、悲嘆をもたらす喪失の原因はいろいろある。そして、悲嘆を抱えながらも、新たな生活の形へと向かっていける人もあるが、なかなかそれができない人もいる。また、悲嘆を人と分かち合うことができないために、胸がふさがれて苦しんでいる人もいる」
「まえがき」の最後では、島薗氏はこう述べています。
「本書は『グリーフケアの時代』である現代を見つめるとともに、人類文化の歴史のなかで『悲嘆を分かち合う文化』、『グリーフケアの文化』を見直そうとするものだ。著者の三人は、人類文化史のなかで『グリーフケアの文化』を捉えるという問題意識を共有し、ともに語り合うことが多い。映画はとくに盛り上がる話題だが、また、世界の宗教文化や儀礼文化の歴史について論じ合い、日本の宗教文化、儀礼文化の未来についても語り合う仲である。本書ではその三人が、それぞれの立場から文化史のなかの『グリーフケアの時代』を問おうとしている。文化史的な視点からの『グリーフケア入門』といってもよいだろう。どこから読み始めていただいてもかまわない。そして、読者各位が自らの悲嘆を捉えなおす糸口を見出していただければ幸いである」
第3章「グリーフケア・サポートの実践」の「はじめに――グリーフケアとの出合い」を、わたしは次のように書きだしています。
「筆者は冠婚葬祭互助会を生業にしている。長年にわたって多くの葬儀をお手伝いしてきたが、愛する人を亡くしたばかりの方々に接する仕事は、けっしてビジネスライクな感情だけで済まされるものではなく、いつも魂を揺さぶられる思いを味わう。なぜなら、死による別れは誰にとっても一生に一度のつらい経験だからである。その直後のご遺族をサポートさせていただく中で、筆者は数多くの悲嘆を目撃してきた。食事も喉を通らず、まどろむことさえできず、日夜ひたすら亡くなった方のことばかり考え、葬儀が終わるまでご遺体のそばから離れようとしないご遺族、涙が枯れ、喉が嗄れてもなお、体の奥からわき上がる嗚咽を止められないご遺族――目の前にそのような方たちがいれば、なんとか支えたい、励ましてさしあげたいと願うのは、人間にとってとても自然な感情であることを筆者はつねづね実感している」
続いて、わたしは以下のように述べています
「悲嘆の中にいるご遺族に、何かしら心のケアをできないだろうかーーそう考えていたところ、20世紀が終わる頃に『グリーフケア』という言葉に出合った。愛する人を亡くした悲しみ(グリーフ)をケアする、これこそが自分たちにできる最高のサービスかもしれない、と直感したのである。しかしながら、冠婚葬祭互助会や葬儀社に代表される葬祭業によるグリーフケアの活動に対しては、営利目的の営業活動としてとらえられるおそれがあるのも事実である。そこで本章では、葬祭業としてグリーフケアのサポート活動に取り組むことの難しさと、わたしたちが現在実践している試みについて取り上げてみたい」
「悲嘆の原因とプロセス」のケース1「ケアとしての葬儀の取り組み」では、「葬儀をあげる意味」について書きました。葬儀という文化装置がいかにグリーフケアという側面で構築されてきたかを知ることができるかを強調しました。当然のことながら古今東西、人間は死に続けてきました。しかし、そこに儀式というしっかりした「かたち」のあるものが押し当てられると、不安が癒されていくのです。
親しい人間が死去する。その人が消えていくことにより、愛する人を失った遺族の心は不安定に揺れ動きます。残された人は、大きな不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。この不安や執着は、残された人の精神を壊しかねない、非常に危険な力を持っています。つねに不安定に「ころころ」と動くことから「こころ」という語が生まれたという説も「こころ」が動揺していて矛盾を抱えているとき、この「こころ」に儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心にはいつまでたっても不安や執着が残るのです。
もう1つ、葬儀には、いったん儀式の力で時間と空間を断ち切ってリセットし、そこから新たに時間と空間を創造して生きていくという意味づけもできます。もし、愛する人を亡くした人が葬儀をしなかったらどうなるか。そのまま何食わぬ顔で次の日から生活しようとしても、喪失で歪んでしまった時間と空間を再創造することができず、「こころ」が悲鳴を上げてしまうのではないでしょうか。
さらに、回忌などの一連の法要も同様の文化装置です。故人を偲び、冥福を祈るとともに、故人に対して、「あなたは亡くなったのですよ」と現状を伝達することで現実を受け入れ、定期的に主宰することで遺族の心にぽっかりと空いた穴を埋める役割もあります。近年はこうした儀式を形式的だと軽んじる傾向もありますが、動揺や不安を抱え込んでいる「こころ」には「かたち」を与えることが大事なのです。儀式とは、定型であり、伝統であるからこそ、人を再生する力があるのです。
さらに細かくみていくと、葬儀には、主に五つの役割があるとされています。それは、①社会への対応、②遺体への対応、③霊魂への対応、④悲しみへの対応、⑤さまざまな感情への対応です。①については、ヒトは社会の中で生きており、会社や友人などいろいろな関係性や縁をもっている。葬儀には、社会に対してきちんとその死を示し、社会はその死について対応するという役割があります。②については、人が亡くなると、物理的にその遺体への対応を行わなければなりません。故人の尊厳を守り、遺体を火葬や埋葬するための過程の行動としての役割があります。
③については、ヒトは死によってその存在がなくなるのではなく、実在した「この世」から霊魂となって「あの世」に行くという、遺された人との間に新たな関係性を作り出す宗教的儀式としての役割があります。④については、最愛の人の死は深い悲しみをもたらし、人によっては受け入れるのに長い時間を要する場合もあります。ほとんどの宗教において、葬儀は人の心に沿って段階的(枕経から葬儀、初七日から四十九日に至る法要など)に行われ、人が受け入れやすいように長い年月をかけ形作られています。また葬儀には、悲しみを避けることなく悲しみに正面から向かい、しっかり悲しむ時間を創出する役割もあります。
⑤については、人には人それぞれにさまざまな感情があります。例えば、歴史的に人の死は祟りなどに対する恐怖心や、故人に対しての過去からの憎悪や嫌悪感など、葬儀にはこのようなさまざまな人の感情をきちんと弔うことで和らげる役割もあります。さまざまな感情には「怒り」や「恐れ」などがあります。具体的には、「どうして自分を残して死んでしまったのだ」という怒り、あるいは葬儀をきちんと行わないと「死者から祟られるのではないか」という恐れなどです。
しかし、残された人々のほとんどが抱く感情とは「怒り」でも「恐れ」でもなく、やはり「悲しみ」でしょう。「悲しみへの対応」とは、遺族に代表される生者のためのものだといえます。遺された人々の深い悲しみや愛惜の念を、どのように癒していくかという対応方法のことです。通夜、葬儀、告別式、その後の法要などの一連の行事が、遺族に「あきらめ」と「決別」をもたらしてくれます。葬儀とは物語の力によって、遺された人々の悲しみを癒す文化装置です。たとえば、日本の葬儀の9割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのである。
筆者は、「葬儀というものを人類が発明しなかったら、おそらく人類は発狂して、とうの昔に絶滅していただろう」と、ことあるごとに言っています。ある人の愛する人が亡くなるということは、その人の住む世界の一部が欠けるということにつながります。欠けたままの不完全な世界に住み続けることは、必ず精神の崩壊を招きます。不完全な世界に身を置くことは、人間の心身にものすごいストレスを与えるわけです。まさに、葬儀とは儀式によって悲しみの時間を一時的に分断し、物語の癒しによって、不完全な世界を完全な状態に戻す営みにほかなりません。葬儀によって「こころ」に「けじめ」をつけるとは、壊れた世界を修繕するということである。だから、筆者は、幣社の葬祭スタッフにいつも、「あなたたちは、こころの大工さんですよ」と言っています。
また、葬儀は接着剤の役目も果たします。愛する人を亡くした直後、遺された人々の悲しみに満ちた「こころ」は、バラバラになりかけます。それを1つにつなぎとめ、結び合わせる力が葬儀にはあります。多くの人は、愛する人を亡くした悲しみのあまり、自分の「こころ」のうちに引きこもろうとします。誰にも会いたくない。何もしたくないし、一言もしゃべりたくない。ただ、ひたすら泣いていたいのです。しかし、そのまま数日が経過すれば、いったいどうなるでしょうか。遺された人は、本当に人前に出られなくなってしまいます。誰とも会えなくなってしまうのではないでしょうか。葬儀は、いかに悲しみのどん底にあろうとも、その人を人前に連れ出す。引きこもろうとする強い力を、さらに強い力で引っ張り出すのです。葬儀の席では、参列者に挨拶をしたり、お礼の言葉を述べなければなりません。それが遺された人を「この世」に引き戻す大きな力となっているのです。
ケース2「ケアとして遺族会の役割」では、わたしが経営する冠婚葬祭互助会であるサンレーがサポートする「月あかりの会」や「うさぎの会」などの自助グループの内容と活動について詳しく紹介し、グリーフケア・サポートの目指すものについて述べました。また、ケース3「ケアとしての『笑い』」では、サンレーのグリーフケア・サポートおよび隣人交流サポートでは、毎月、漫談家を招いて「笑いの会」を開き、半年に一度は落語家を招いて大規模なイベントを開催していることを紹介しました。笑いこそは、自死や孤独死を防ぐ最大の力を持つと考えているからです。「笑う門には福来たる」という言葉があるように、「笑い」は「幸福」に通じます。笑いとは一種の気の転換技術であり、笑うことによって陰気を陽気に、弱気を強気に、そして絶望を希望に変えることができるのです。
ケース4「ケアとしての『読書』」では、読書について述べました。グリーフケアの目的として、一般的には「死別の悲嘆の回復」が挙げられますが、それに加えて、「自らの死の不安を軽減する」こともあるとされています。そこで、重要となるのが読書です。長い人類の歴史の中で、死ななかった人間はいませんし、愛する人を亡くした人間も無数にいます。その歴然とした事実を教えてくれる本、「死」があるから「生」があるという真理に気づかせてくれるのが本です。なぜ、自分の愛する者が突如としてこの世界から消えるのか、そしてこの自分さえ消えなければならないのか。これほど不条理で受け容れがたい話はありません。本書では、その不条理を受け容れて、心のバランスを保つための本を具体的に紹介しています。
ケース5「ケアとしての『映画鑑賞』」では、映画の本質について述べました。わたしは、映画をはじめとした動画撮影技術が生まれた根源には、人間の「不死への憧れ」があると思っています。わたしは、すべての人間の文化の根底には「死者との交流」という目的があるとの仮説を持っていますが、映画そのものこそは「死者との再会」という人類普遍の願いを実現するメディアでもあると考えています。そして、映画館という人工洞窟の内部において、わたしたちは臨死体験をするように思えます。なぜなら、映画館の中で闇を見るのではなく、わたしたち自身が闇の中からスクリーンに映し出される光を見るからであす。闇とは「死」の世界であり、光とは「生」の世界です。つまり、闇から光を見るというのは、死者が生者の世界を覗き見るという行為にほかなりません。つまり、映画館に入るたびに、観客は死の世界に足を踏み入れ、臨死体験するわけです。本書では、「死」があるから「生」があるという真理に気づかせてくれる映画、死者の視点で発想するヒントを与えてくれる映画などを具体的に紹介しました。
「あとがき」では、鎌田東二氏が長い教師生活の中で、さまざまな悲嘆現場に遭遇し、生徒や学生や保護者や教員の悲嘆の現場を垣間見てきたことを告白し、さらに「そうした過程で、40年以上島薗進氏とは深い交わりを持ち、佐久間庸和氏とは30年近く兄弟のような付き合いをしてきたが、私にとって兄弟とも同志とも同朋とも言える同僚と共著で『グリーフケアの時代』という書名の本を出すことができることを、何とも言えない不思議な僥倖のような、宿命のような、ただならぬ因縁というものを感じている」と書いています。
そして、鎌田氏は「グリーフケア(Grief Care)とは、さまざまな種類の喪失などによる悲嘆(グリーフ,Grief)に向き合い寄り添うケアのことで、広義のスピリチュアルケア(Spiritual Care)の一つである」と指摘した上で、次のように述べるのでした。
「私はスピリチュアルケアを「嘘をつけない自分や他者と向き合い、対話的な関係を結び開いていく試みとその過程」と捉え、『スピリチュアリティ(Spirituality)』を、嘘のつけない、ごまかしのきかない、心の深みや魂の領域とはたらきだと考えてきたが、この領域は実に具体的でデリケートで簡単に割り切ることができないが、リアルかつ切実に迫ってくる。その、まことに難しく、しかし重要なケアの領域にしっかと連携しつつ三人三様のアプローチで問題提起したのが本書である。本書がこの時代の『グリーフ』の理解とケアに少しでも役立つところがあれば幸いである。関係各位に心から感謝の意を表したい」
 島薗進、鎌田東二の両氏と
島薗進、鎌田東二の両氏と
わたしは、島薗進氏と鎌田東二の両氏は、日本のグリーフケア研究の世界において、心理学におけるフロイトとユングであり、日本民俗学における柳田國男と折口信夫のような二大巨頭であると思っています。そんな2人の偉大な師を前にして、わたしはアドラーや渋澤敬三を目指す気概で本書の3分の1を書きました。葬祭業界や互助会業界の方々にも参考になるように意識して書きました。本書が日本のグリーフケアの夜明けにあることを願っています。『グリーフケアの時代』は8月27日発売です。どうぞ、ご一読下さい。そして、一緒に、グリーフケアの時代を拓きましょう!