- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.10.18
『教養としての世界史の読み方』を読みました。著者は、早稲田大学国際教養学部特任教授、東京大学名誉教授。博士(文学)。1947年、熊本県に生まれる。1973年、一橋大学社会学部卒業。1980年、東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。東京大学教養学部教授、同大学院総合文化研究科教授を経て、現職。専門は古代ローマ史。『薄闇のローマ世界』でサントリー学芸賞、『馬の世界史』でJRA賞馬事文化賞、一連の業績にて地中海学会賞を受賞。
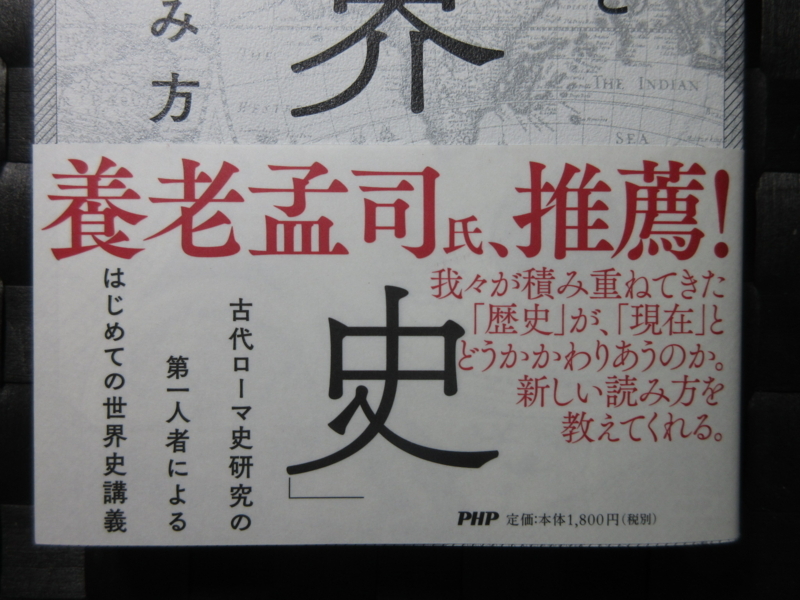 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「養老孟司氏、推薦!」と大書され、「我々が積み重ねてきた『歴史』が、『現在』とどうかかわりあうのか。新しい読み方を教えてくれる」「古代ローマ史研究の第一人者による、はじめての世界史講義」と書かれています。
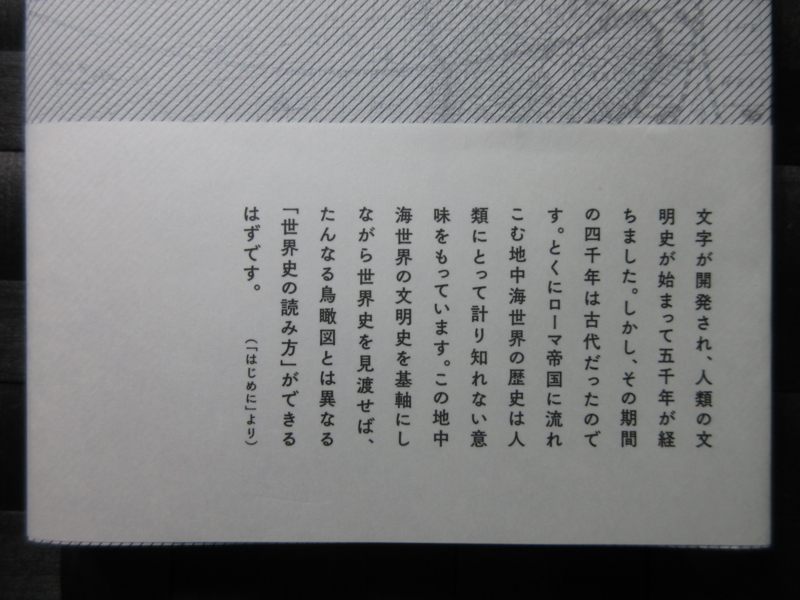 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「文字が開発され、人類の文明史が始まって5000年が経ちました。しかし、その期間の4000年は古代だったのです。とくにローマ帝国に流れこむ地中海世界の歴史は人類にとって計り知れない意味をもっています。この地中海世界の文明史を基軸にしながら世界史を見渡せば、たんなる鳥瞰図とは異なる『世界史の読み方』ができるはずです。(「はじめに」より)」
カバー前そでには、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と大書され、「経験というのは、個人の体験でしかないので、自ずとその範囲も規模も限定されてしまうが、歴史は、少なくとも過去五千年にわたる文明史の、あらゆる人々の経験の集大成なので、故人の経験より遥かに多くのことを学ぶことができる」という「序章」の言葉が引用されています。
アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。
「『混迷の現代』を読み解くカギは『歴史』の中にある。古代ローマ史研究の第一人者によるはじめての世界史講義。教養としての『世界史』の読み方とは、『歴史に学ぶ』ということ、『過去と現在との関わり合いを知る』ということ。東京大学教養学部で28年間、教鞭をとった著者が教養として世界史をどう読むかを教える1冊。文明の発祥、古代ローマとの比較史、同時代史、民族移動、宗教、共和思想……、世界史を読み解く上で大切な視点を新説や持論を織り交ぜて、わかりやすく、面白く講義する」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 「歴史に学ぶ」とは何か?
――愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
第1章 文明はなぜ大河の畔から発祥したのか
――文明の発達から都市国家と民主政の誕生まで
第2章 ローマとの比較で見えてくる世界
――ローマはなぜ興隆し、そして滅びたのか
第3章 世界では同じことが「同時」に起こる
――漢帝国とローマ帝国、孔子と釈迦
第4章 なぜ人は大移動するのか
――ゲルマン民族、モンゴル帝国、大航海時代から難民問題まで
第5章 宗教を抜きに歴史は語れない
――一神教はなぜ生まれたのか
第6章 共和制から日本と世界の違いがわかる
――なぜローマは「共和制」を目指したのか
第7章 すべての歴史は「現代史」である
――「今」を知るために歴史を学ぶ
「おわりに」序章
序章「『歴史に学ぶ』とは何か?」では、「グローバルスタンダードの『教養』とは何か」として、著者は以下のように述べています。
「国際人として、いえ、それ以前に社会人として、教養は語学力以上に大切です。国際社会でも通用する教養を身につけたい。そう思ったときに問題になるのが、国際社会における『教養』とは何か、つまりグローバルスタンダードの『教養』とは何か、ということです。これについては、異なる意見をお持ちの方もいるかもしれませんが、私はグローバルスタンダードの『教養』は、『古典』と『世界史』だと思っています。長い年月にわたって、多くの人に読み継がれてきた文芸や思想の作品である『古典』には、時代が大きく変化してもなお変わることのない、人間社会の普遍的な真理が詰まっています」
また、「なぜ人は『歴史に学ぶ』ことができないのか」として、著者は述べます。
「なぜ人は歴史に学ぶことが難しいのか、ということについても深く考えました。そして気づいたのが、『人間は見たいものを見るのであって、現実そのものを直視する人は少ない』ということでした。いくら知識を詰め込んでも『歴史に学ぶ』ことができないのは、現実から『意味』を見いだすことができていないからです。歴史から『意味』を汲み出すことができれば、それがいい意味であれ、悪い意味であれ、人は学びを得ることができるのだと思います」
さらに、著者は以下のように述べます。
「歴史の中に潜む意味や教訓は、わかりやすいところにばかりあるわけではありません。よくよく考えたときに初めて見えてくるものがとても重要なこともあるのです。そして、そうした隠れた意味や教訓は、事実そのものを直視して、真摯に歴史と向き合わないと見えてこないものなのです。これが、人々が歴史に学ぶことがなかなかできない理由なのだと私は思います」
歴史を学ぶことについて、著者は「トルストイが『戦争と平和』を書き上げたのは、彼を批判した歴史家に対するアンチテーゼとしてであり、この作品を通して、歴史家に『どうだ、読んでもらえる歴史というのは、こうやって書くものなんだ!』と言いたかったのでしょう」と指摘し、さらには「トルストイの痛烈な歴史家批判」として、「トルストイの『戦争と平和』は、確かに読んで面白いものです。しかし、大まかな歴史の流れは押さえているものの、やはりあれは小説、面白く作られたフィクションです。フィクションと比べれば、歴史家が書くものは面白くないかもしれません。それでも歴史家が書いたものには、彼らが真摯に向き合った人類の経験が、最も史実に近い形で詰まっているのです。その価値は、フィクションとはまったく違ったところにあるものだと思います」と述べています。
「『教養』を身につけるための7つの視点」として、著者は、歴史哲学を味わう7つのポイントを提示します。「この7つの視点は日本人が苦手とする内容です。なぜなら学校であまり教えてくれないものだからです。しかし、グローバルスタンダードの『教養』を身につけるには必須のことだと思います」と述べます。「7つの視点」は以下の通り。
(1)文明はなぜ大河の畔から発祥したのか
(2)ローマとの比較で見えてくる世界
(3)世界では同じことが「同時」に起こる
(4)なぜ人は大移動するのか
(5)宗教を抜きに歴史は語れない
(6)共和政から日本と西洋の違いがわかる
(7)すべての歴史は「現代史」である
第1章「文明はなぜ大河の畔から発祥したのか」では、アフリカ大陸を流れるナイル川流域に栄えた「古代エジプト文明」、西アジアのティグリス・ユーフラテス川流域で発展した「「メソポタミア文明」、インドのインダス川流域で興った「インダス文明」、東アジアの黄河流域の「黄河文明」の4つ、いわゆる「四大文明」を取り上げます。「『四大文明』が通用するのは日本人だけ」として、著者は以下のように述べます。「最近、『四大文明』という言い方はあまりされなくなっています。なぜなら、四大文明のほぼ同時期や、もっと古い時代に、ほかにいくつもの文明があったことが明らかになり、最近ではそれが常識的な知識として広く認知されるようになっているからです。それに、この『四大文明』という歴史用語を使うのは、実は日本だけなのです。日本が近代化し、世界史という学問が成立していったとき、世界の文明発祥時期に大きな文明が4つあることがわかっていたことから、当時の学者がそれらを『四大文明』という形で総称するようになったのです。そのため、『四大文明』という言い方は世界ではほとんど通用しません」
では、そもそも文明とは何か。「文明発祥に必須な条件は?」として、著者は以下のように述べています。
「文明発祥に必要な条件とは? 何をもって文明というのか、いわゆる文明の定義には、いろいろな意見があると思いますが、よく言われるものの1つに『文字の発明と使用』があります。先ほどの四大文明でも、メソポタミアでは楔形文字、古代エジプトではヒエログリフ、インダス文明ではインダス文字、そして黄河文明では漢字のもととなった甲骨文字が、それぞれ発明・使用されています。でも日本は、大陸から漢字が伝来するまで文字を持たなかったためか、太古の歴史区分に土器の名称が用いられているためか、日本人は文明の発祥と聞くと土器の使用を思い出します。もし文明と土器がそれほど密接に結びついているのなら、世界最古の土器が出土したところが世界最古の文明が生まれた場所だということになります。では、その世界最古の土器が出土した場所とはどこなのか。実は日本がその1つなのです」
また、文明の発祥について、著者はこうも述べています。
「乾燥化と、それに伴う人々の水辺への集中が、なぜ文明発祥に繋がるのかというと、少ない水資源をどのようにして活用するか、ということに知恵を絞るからです。つまり、環境的に恵まれなくなったから文明が生まれた、と言っても過言ではないのです。
まず、人の生存に欠かすことのできない『水』が非常に大きなファクターとなり、人口が一カ所に集中することで、それまで小さな村ぐらいでしかなかった集落が都市的な規模になる。その結果、水争いを防ぐための水活用システムが生まれ、そうしたことを記録する必要から文字が生まれたのです。実際、古代の記録は、取引記録など実務的なものが多く見られます。文字は必要だから生まれてきたのですから、なぜ必要になったのか、ということを追究するには、何が記録されているのかを見るのが一番です」
さらに、「恵まれた環境に文明は生じない」として、著者は述べます。
「乾燥化が文明発祥の大本にあったということがわかれば、なぜいち早く土器を生み出した日本が、なかなか『文明』と言える段階に至らなかったのかが見えてきます。それは、日本では乾燥化が起きなかったからです。大きな文明が生まれたところというのは、大河があるものの、その周りは乾燥化が進んでいます。しかし、日本は島国であるにもかかわらず、水がとても豊かです。自然環境に恵まれ、乾燥化が起こらなかった日本では、人口の集中も起きず、少人数の集落で安定した社会が長く営まれていたと考えられます。実際、縄文時代は1万年もの長きにわたっています。日本がなかなか『文明』という段階に至らなかったのは、水が豊かすぎて水活用すステムを作る必要がなかったから、そして、人口の集中が起きなかったからだと考えられます」
第2章「ローマとの比較で見えてくる世界」では、その冒頭を、著者は「『ローマの歴史の中には、人類の経験のすべてが詰まっている』そう語ったのは、政治思想史学者の丸山眞男氏でした。これはローマの歴史が、興隆、発展、安定、衰退という、いわゆる文明の起承転結の過程が非常にはっきりしているからだと思います。しかもその起承転結は、人の一生になぞらえられるほどドラマチックなのです。長大な『ローマ人の物語』で名高い作家の塩野七生さんは『ローマ史は世界史のブランド品』と語っています」
「ローマは、なぜ帝国になりえたのか――ギリシアとローマの違い」として、ポリュビオスの『歴史』を取り上げます。この本にはローマ貴族の葬礼について述べた文章があるのですが、そこで彼は以下のように、とても面白い考察をしています。
「偉業を成し名を上げた人々の肖像が一堂に並び、まるで生命を吹き込まれたかのような姿を見せているそのありさまを見て、恍惚としない者がいるだろうか。これに勝る光景がいったいどこにあり得よう(『歴史』より)」
これは、葬礼の場で、親族が死者そっくりの仮面をつけて現れたのを見たときの驚きを述べたものですが、ポリュビオスがこれほどまでに驚き、「これに勝る光景はない」とまで言った理由について、著者(本村氏)はこう述べます。
「この光景を目にしたときポリュビオスは、ギリシア人は公よりも個を大切にするが、ローマ人は個よりも公共の安泰を重んじる。なぜ、ローマ人はこれほどまでに公共を重んじることができるのか、という謎の答えに気づいたからなのです。ポリュビオスは、ローマ人が公共を重んじるのは、若者の頃からこうした感動的な葬儀を経験することで、『たとえ死んだとしても、その英雄的功績はこうして永遠に語り継がれるのだ』という思想的刷り込みが行われているからだ、と考察しています」
ローマにおける「感動的な葬儀」には心を動かされました。これからも、可能な限り、調べてみたいと思います。
第3章「世界では同じことが『同時』に起こる」では、「『ザマの戦い』と『垓下の戦い』は、同じ前202年に起きた」として、著者は以下のように述べています。
「始皇帝(前239~前210)の建てた秦帝国は彼一代で崩壊しています。アレクサンドロス大王の帝国も、彼の死と共に分裂してしまいました。ですから永続的な世界帝国という意味では、やはり世界史の中では、ローマ帝国と漢帝国が冠たるものなのです。そして、その世界史初の世界帝国の誕生が、期せずして前202年に、西と東で同時に起きているのです」
しかし著者は、ローマが帝国としての条件を整えたのは、第二次ポエニ戦争の勝敗を決定づけたザマの戦い(前202)において、ローマがカルタゴに勝利したときだと考えているそうです。その理由について、「なぜならザマの戦いこそが、ローマのその後の運命を決めた、まさにターニングポイントだからです。そういう意味で、私はローマ帝国が誕生したのは、ザマの戦いに勝利した前202年だと考えています」と述べています。
さらに著者は、「西でローマが、その覇権を確定したのとちょうど同じ前202年、ユーラシアの東、現在の中国で、似たような事件が起こっています。垓下の戦いです。これは四面楚歌のエピソードで知られる項羽(前232~前202)と劉邦(前256~前195)の決戦です」と述べるのでした。これが垓下の戦いですが、項羽の死という決定的な勝利が、漢帝国の誕生を決定づけたのです。つまり前202年は、漢帝国とローマ帝国という、東西ユーラシアにおける世界帝国が、ほとんど同時に出現するという、非常に珍しいことが起こった年なのです。この共時性は、とても興味深いですね。
「ローマ帝国と漢帝国を襲った『三世紀の危機』」として、著者はローマ帝国で皇帝が乱立すると、民衆のあいだには、もう誰がなっても変わらない、という投げやりな空気が漂ったと指摘し、こう述べます。
「人々が政治に期待しなくなった中、社会的不安を抱えた民衆が心の拠り所としたのがキリスト教でした。イエスが磔になったのが紀元30年頃、それから五賢帝の時代まではローマのキリスト教徒はほとんど増えていません。いなかったわけではありませんが、その数は人口の僅か1%以下。それが230年頃から、急激に増えているのです。つまり、ローマにキリスト教が普及したのは、軍人皇帝の時代における社会的不安の増大が大きく関係していたのです」
著者は、時代の共時性について、もう1つの例を挙げます。
「ソクラテス、ゾロアスター、ウパニシャッド、釈迦、孔子の枢軸時代」として、以下のように述べています。
「前1000年紀にも、非常に興味深い同時代性が見られます。それは、思想の誕生です。当時の文明先進地域であるギリシア、オリエント、インド、中国で、ほぼ同時に思想や哲学が生まれているのです。ギリシアではホメロスからイオニア自然哲学を経て、ソクラテスやプラトンに代表されるギリシア哲学が生まれ、オリエントでは、エレミヤなど旧約聖書に登場する多くの預言者が輩出され、現在のイラン辺りでは拝火教の始祖ゾロアスターが生まれています。インドではウパニシャッド哲学が出現し、少し遅れて仏教の開祖・釈迦(ゴータマ・シッダールタ)が誕生しています。そして中国では、孔子、老子を筆頭に諸子百家と称されるほど多くの思想家が輩出されています」
また、著者は以下のようにも述べています。
「20世紀のドイツの哲学者カール・ヤスパース(1883~1969)は、この時代に着目し、それを『Achsenzeit/枢軸時代』と呼びました。彼が『軸』と称したのは、この時代に花開いた思想が、どれもその後の人類の思想の基本となるものだからです。私は、このことは前2000年紀に起きた文字と一神教と貨幣の誕生と切り離して考えられるものではないと思っています」
ヤスパースの唱えた「枢軸時代」については、拙著『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)でも詳しく紹介しました。
さらに、著者は以下のように興味深い発言をしています。
「現在の歴史学では、アルファベットと一神教の登場と貨幣の誕生というのは、それぞれ別々に取り上げられているので気がつかないのですが、私には、これらはどれも、当時の人間の考え方の同じところに根ざしているものと思えてなりません。そして、この前2千年紀後半からのシンプリフィケーションの動きがあったからこその、枢軸時代の到来なのではないかと思うのです」
わたしも、著者の考えとまったく同じであることを告白します。
第4章「なぜ人は大移動するのか」では、「民族移動がもたらす価値観の対立が国家を揺るがす」として、著者は以下のように述べます。
「ローマ人というと、キリスト教を弾圧したというイメージがありますが、実はローマは信仰に対して非常に寛容で、征服地でも『おまえたちがおまえたちの神を信じるのは自由だ』と常に認めてきました。これはキリスト教に対しても同じだったのです。私はこのことについては、これまでもいろいろな著書で述べているのですが、寛容なローマがキリスト教を弾圧するようになった最大の理由は、キリスト教徒たちが『キリスト教以外の神々はニセモノだ。そんなものを信じてはいけない』と主張したからなのです」
第5章「宗教を抜きに歴史は語れない」では、一条真也の読書館『神々の沈黙』で紹介した名著を取り上げ、「かつて人は神々の声に従って行動していた」として、著者はこう述べます。
「プリンストン大学の心理学教授ジュリアン・ジェインズは、著書『神々の沈黙――意識の誕生と文明の興亡』(『The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind』/紀伊國屋書店)で、3千年前の人類は、実際に神々の声を聞き、その通りに行動していたということを、ホメロスの『イーリアス』と『オデュッセイア』の記述をひもときながら検証しました。そしてジェインズは、こうした神々の声が聞こえていた時代を『二分心/Bicameral Mind』の時代と称しました」
「神」について、著者は以下のように述べます。
「人間は「文明」と呼べるものができる以前から、宗教的習慣を持っていたことが考古学的研究によって明らかになっています。でも、人間以外の動物には神も宗教もありません。そう考えると、神は人間が脳を発達させた結果、手にしたものの1つだと考えることができるわけです。
では、人間にとって神とは何なのでしょう。
私は、人間にとって神とは一種の『理想』だと思っています。人間というのは、理想に近づこうとする宿命のようなものを背負っています。行動するときに、実際その通りにできるかどうかは別として、理想的な行動をしようとするのもそのためです。つまり宗教とは、人間が神という理想に近づくための方法を示すものだといえるのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「宗教は迷信として片づけられるものではなく、脳を発達させた人類の宿命のようなものなのではないか、そう考えていた私には、ジェインズの二分心はまさに古典の文献に即してしっくりくるものだったのです。神々を心の中で身近に感じていたので、古代人の作品には神々が生き生きと描かれているのです。彼らにとって神々は神話や空想ではなく、もっと肌身に迫ってくるものだったのです」
さらに、著者は「人はなぜ唯一神を必要としたのか」として、こう述べています。
「私は、この『神々の声が聞こえなくなった』ことが、同時期に起きた一神教の登場と深く関わっているのではないかと考えています。つまり、神々の声が聞こえなくなってきたことで、人間は自ら考えて、指針を持たなければならない状況に陥ったのです。そこで人間が生きる指針としてつくり出したのが全知全能の唯一神なのではないか、ということです。そう考えると、同時代性のところでも触れましたが、ヤスパースが枢軸時代と名づけたこの時期に、優れた思想家が世界各地で登場した謎も解けるのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「神々の声が聞こえていたとき、人間は『生きる指針』など必要ありませんでした。聞こえてくる神々の声に従えばよかったからです。神々の声が聞こえなくなったからこそ、人は絶対的な神を必要とし、物事を判断するために思想を必要としたのではないでしょうか。つまり、神託や占いと同じように、唯一神も、思想も、聞こえなくなってしまった『神々の声』の代用品だった、ということです」
神や宗教というと、すぐ「対立」や「戦争」を連想する人がいますが、著者は「イスラム教対キリスト教という構図の嘘」として、以下のように述べます。
「イスラム原理主義者のせいで、イスラム教は怖いというイメージが蔓延してしまいましたが、イスラム教の聖典である『コーラン』を読むと、その教えが決して恐ろしいものではないことが分かります。イスラム教は弱者救済的な面が強く、有名な一夫多妻にしても、その背景にはお金持ちが孤児や父無し子を救済するためのものという一面もあると言われています。弱者救済は、『旧約聖書』にも『新約聖書』にも、『コーラン』にもある、3つの一神教すべてに共通する倫理的な教えです。3つの一神教は、そういう親近性と言えるものを持っているのですから、本来なら相互に対決すべきものではないはずなのです」
このあたりは、拙著『ユダヤ教vsキリスト教vsイスラム教』(だいわ文庫)で詳しく述べています。よろしければ、お読みください。
キリスト教のトップは、カトリックの総本山と言われるバチカンのローマ教皇です。「ローマは欧米人の自負心の源である」として、著者は以下のように述べています。
「ローマ教皇がなぜ広く尊敬を集めているのか、不思議に感じる日本人もいるようですが、実は欧米人にとって、『ローマ』は今も特別な存在なのです。ローマは、あれほど広大な地域を、あれほど長いあいだ平和に治めた大国であるだけでなく、欧米人にとってはルーツなのです。そのためローマは、欧米人の自負心の源であると同時に理想でもあるのです。欧米ではこうした意識を『ローム・イディ(Rom idee)』と言います」
「ローム・イディ」と言う言葉は、日本ではほとんど知られていません。敢えて訳すとすれば、「ローマ的理念」あるいは「ローマ的理想」と言えるとして、著者は、「要するに、キリスト教世界の精神的な拠り所になっている、その根底にローマがあるのです。ローマ帝国が滅んでから今に至るまで、欧米、特にヨーロッパ人の心にはこうした思いが根強く生きているのです。極端な言い方をすれば、ヨーロッパ人の心の奥底には、今もローマの再現、つまり『ローマによる世界統合を目指す』という意識があるのかもしれません」と述べています。
第7章「すべての歴史は『現代史』である」では、「すでに第三次世界大戦は始まっている」として、著者は以下のように述べています。
「今、世界で何が起きているのか?
これは非常にショッキングな表現ですが、私はすでに第三次世界大戦は始まっていると見ています。これまで『第三次世界大戦』というと、核兵器を保有する国同士が周囲の国々を巻き込みながら敵対し、互いに原爆や水爆を打ち合うような戦争がイメージされていました。これは、1962年に起きたキューバ危機が影響しています。しかし、キューバ危機から半世紀以上経った今、そんなことをしてしまったら人類が滅亡しかねないことを多くの人が知っています。そのため、人々が自覚しないうちに世界における『戦争の形』が変わってきているのではないかと思うのです。世界各地で多くの犠牲者を出しているゲリラ戦やテロ、これこそが、第三次世界戦争の形のような気がします」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「興味深いのは、モラルが低下していくとともに、人々が優しくなっていく傾向が見られることです。これは見方を変えれば厳しさの欠如であったり、優柔不断とも言えるのですが、退廃にむかう社会では人は自分にも他人にも優しくなっていくのです。今の日本も、必要以上に優しい社会になってきているような気がします。でも、これは本当の意味での優しさではありません。本当の優しさは、自分というものをきちんと持った人が、周りに対して示す寛容さです。人間社会は繁栄すると必ず退廃していく。歴史はそのことを物語っていますが、われわれ人類は、まだどうすればこの問題を解決できるのかという学びは得られていません」
世界史研究の第一人者が書いた本でかって、本書は説得力に富んでおり、「世界史」と言葉がいかに「教養」や「リベラルアーツ」に近いがよく理解できました。歴史の奥深さ、面白さを教えてくれる一冊です。
