- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.11.11
『この地上において私たちを満足させるもの』乙川優三郎著(新潮社)を読みました。一条真也の読書館『二十五年後の読書』で紹介した著者の前作に登場した小説で、同書の刊行後にすぐ本書も刊行されました。著者は1953年東京生まれ。ホテル勤務などを経て、1996年小説家デビュー。2001年『五年の梅』で山本周五郎賞。2002年『生きる』で直木三十五賞。2013年初の現代小説『脊梁山脈』で大佛次郎賞。2016年『太陽は気を失う』で芸術選奨文部科学大臣賞。2017年『ロゴスの市』で島清恋愛文学賞を受賞しています。
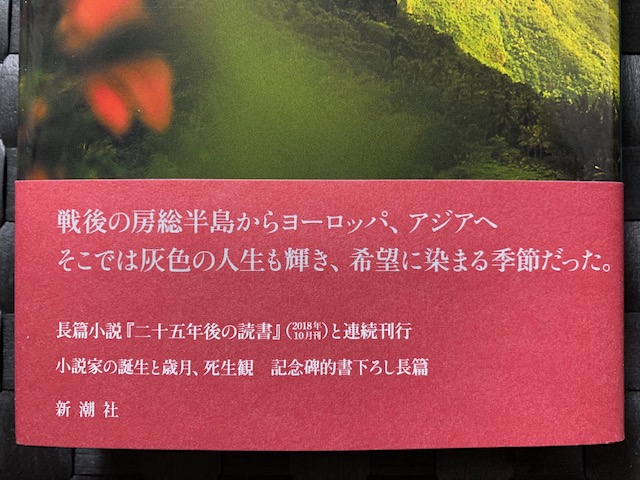 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「戦後の暴走半島からヨーロッパ、アジアへ」「そこでは灰色の人生も輝き、希望に染まる季節だった。」「長篇小説『二十五年後の読書』(2018年10月刊)と連続刊行」「小説家の誕生と歳月、死生観 記念碑的書下ろし長篇」と書かれています。
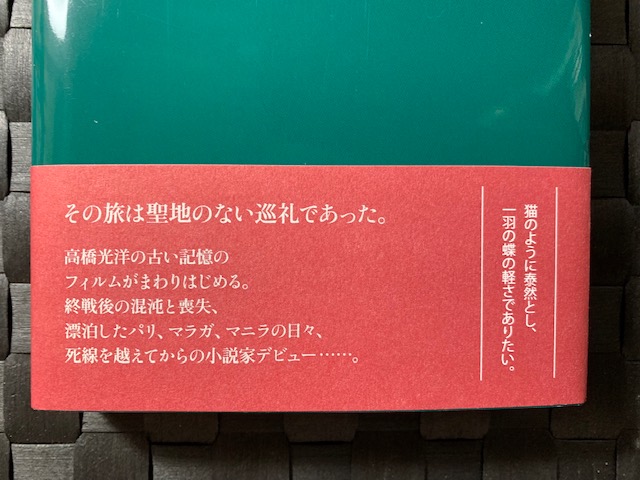 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、「その旅は聖地のない巡礼であった。」として、「高橋光洋の古い記憶のフィルムがまわりはじめる。終戦後の混沌と喪失、漂泊したパリ、マラガ、マニラの日々、死線を越えてからの小説家デビュー……」と書かれ、さらには「猫のように泰然とし、一羽の蝶の軽さでありたい」という言葉が添えられています。
アマゾンの「内容紹介」には、次のように書かれています。
「戦後の房総半島からヨーロッパ、アジア、そして日本で。そこでは灰色の人生も輝き、沸々と命が燃えていた。あのとき、自分を生きる日々がはじまった――。縁あって若い者と語らううち、作家高橋光洋の古い記憶のフィルムがまわり始める。戦後、父と母を失い、家庭は崩壊、就職先で垣間見た社会の表裏、未だ見ぬものに憧れて漂泊したパリ、コスタ・デル・ソル、フィリピンの日々と異国で生きる人々、40歳の死線を越えてからのデビュー、生みの苦しみ。著者の原点と歳月を刻む書下ろし長篇」
前作『二十五年後の読書』において、作家の三枝昴星は年齢を重ねていくうちに筆の衰えを自覚します。彼は残りの人生も少なくなる中で、書き手としての煌めきを今一度放ちたいという願いを込めて『この地上において私たちを満足させるもの』という小説を書き上げます。『二十五年後の読書』の中では、主人公で書評家の中川響子が手にして読む場面は登場しますが、その内容はわかりませんでした。ただ、「美しい小説」「完璧な小説」をめざして書かれたものということだけはわかりました。そう、「完璧に美しい小説」と呼ばれるジョン・ウィリアムスの小説『ストーナ-』のような……。その幻の小説である『この地上において私たちを満足させるもの』をついに読むことができるわけです。わたしの胸は期待で高鳴りました。そして、本書は「老い」を含む「人生」というものを見事に描いた傑作でした。
本書の主人公である作家の高橋光洋は明らかに著者・乙川優三郎の分身と思われます。乙川と同じく、高橋もその青春時代に世界を放浪します。「丘の上の下町」という章の冒頭は、以下のように書きだされています。
安泊まりのホテルでアスピリンと軽い朝食をとったきり、なにも腹に入れていなかったが、フランクフルトからザールブリュッケンを経てパリに着くまで光洋は空腹を忘れていた。始発駅からお喋りと寝息をたっぷり詰めて列車はすすんでいたが、漂泊の旅を隠せない東洋人のとなりに座る人はなく、チョコレートをすすめてくれる人もいなかった。もっとも腹には前夜過ごした酒が残り、方にはドイツ文化を堪能したあとの重たい充足と疲れが溜まっていたから、気晴らしに食堂車を除く気にもなれなかった。かわりに彼は本を読んでいたが、それも傍目には貧しい旅行者の気取りに見えていたかもしれない。くたびれた表紙の本は原書で、モームの「雨」であった。(『この地上において私たちを満足させるもの』P.60)
メスヴィルから乗り込んできたらしい青年が光洋の膝の上の本を見て、「単なる人生の素人」と英語で話しかけてきました。彼は光洋に「古い本が好きらしいな」とも言いましたが、そこにはいくらかの嘲りが込められていました。「傑作は古くなりませんから」「それを傑作と思うのが古いね、部分的には素晴らしいところもあるが、結末が見えてしまうのはよくないし、主人公の人間性もお粗末で共感できない」「読書の意義は共感することよりも自分とは違う人間を見つめることにあると思う、芸術家には尻で発想する人もいますから、頭で向き合うと不遜なことになります」「おもしろいことを言うじゃないか」と、二人は読書論議を交わすのですが、非常に興味深かったです。著者は「そういう彼も文学をこよなく愛する創作科の学生で、気がつくと二人は旧友のように語り合っていた。フランスの田舎を走る列車の中でドイツ人と日本人が語らうさまは、モネなら一幅の絵になる」と書いています。
光洋には遅い結婚で一緒になった早苗という編集者の妻がいましたが、彼女は末期の膵臓癌に侵されておりおり、もはや緩和処置を受けるしかありませんでした。気力を費消した反動からか一度観念すると食欲がぶっつり絶えて、モルヒネで痛みをやわらげるだけの自宅療養を続けました。死期が迫ってきても、編集者である妻は作家である夫の仕事を案じます。
病床の1日は付き添う光洋にも長く、一月(ひとつき)は短かった。十年にも満たない歳月がふたりの歴史であったが、繰り返した日々の底に濃縮された喜びが溜まった。光洋はそれが自分たちの結晶だろうと思い、早苗は未練の泥だと言った。
「あなたとやりたいことが一杯あったのよ」
あるとき彼女は言った。
「編集者として高橋光洋を海外へ売り込みたかったし、なにもかも捨てて1年だけ気儘な旅もしてみたかったわねえ」
「どこへ行きたい」
「まず世界の果て」
「それなら簡単だ。東京から見れば世界一周の果ては富山あたりだろう」
光洋が言うと、作家がそんな夢のないことを言ってはだめよ、と窘めた。彼女の理想の旅は光洋とふたりでタイタニックのような客船に乗り、地中海をスペインへゆくことであった。そこで飲んで、笑って、思い切り踊りたいという。コスタ・デル・ソルの眩しさを知っている光洋は彼女にぴったりの目的地だと思った。しかし外山への旅すら叶いそうになかった。(『この地上において私たちを満足させるもの』P.178)
彼女を虚ろにさせる貞井の心残りは人間としてなにかを成したという実感の希薄なことであった。ただ精一杯生きたというだけでは充たされない、美しくも欲張りな心の持主である。目の前の1日を愉しむことに才能を発揮しながら、千日の努力の向こうを見ているような編集者でもある。生きることの目標になにかしら美の要素があることが重要であったが、それも行きながら探すことになるので実現はむずかしい。彼女のような人には人生が短く感じられる原因でもあろう。光洋はそのあたりまで早苗を理解していたから、日々の生活に追われて突きつめずにきてしまったことが悔やまれた。しかし今になりそういうことを話すのは手遅れであるばかりか、非常な仕打ちになりかねない気がした。
目を閉じている時間が長くなっても、なにも考えていないわけではないので、できるだけそばにいて聞けるときに聞いてやるのが彼の務めになった。彼も彼女も唯物論者ではないが、あの世や神や魂を信じているとも言えない。ただなにかあるという気がするのは2つの心がときおり通信するからであった。(『この地上において私たちを満足させるもの』P.179)
早苗の死後、抜け殻のようになった光洋はタヒチを訪れます。そこに彼の担当編集者であり、早苗の後輩の女性編集者である佐川がやって来ます。彼女は、光洋に新作を書く決意を固めさせようとして、はるばる南の島まで飛んで来たのでした。二人はラグーンの浅瀬に白い丸テーブルと二脚の椅子を置いた海のレストランでランチを取ります。ビーチパラソルの日陰はささやかですが、テーブルクロスの上には一流レストランと同じテーブルウェアが並べられ、脇には大きなワインクーラーが突き立てられて、シャンパンやヒナノビールが冷えていました。食材を載せたボートが近くに停泊していて、その場でシーフードをグリルしてくれるのでした。このようなリゾートビジネスをはじめとしたハートビジネスもまた、「この地上において私たちを満足させるもの」の1つであることを、著者は見事に表現していました。料理はみちろん、パンもスープもきれいに平らげた後、佐川は「最高ですねぇ」としみじみと言い、光洋は「タヒチアン顔負けの健啖家に乾杯」と言った後で、次のように語るのでした。
「早苗の骨をここに散骨しようと思う、この明るさ、このラグーンそのものが彼女の墓所だと思えば私の気も休まる」
「ティアレの木立が見守るでしょう、奥さまにふさわしいお墓だと思います」
「タヒチアンは今もゴーギャンの墓にティアレの花を供えるそうだ、小さな墓は海を望む丘の斜面にあって、あまり人もゆかないらしいが、誰か優しい人がいるのだろう、このラグーンならそんな心配もいらない」
そう言ってオテマヌ山を仰ぐ男のさっぱりした顔を見て、
「これ以上の鎮魂はありませんね」
と佐川も言った。
「それからもうひとつ、正直に言おう、きのうから君を見ていて仕事をしたくなってきたよ、どんなものが書けるかは分からないが、気持ちがそっちへ動いている」
「ありがとうございます。ここ、やっぱり最高ですねぇ」
「早苗もここなら満足だろう、今はあの山の上から私たちを見ているかもしれないな」(『この地上において私たちを満足させるもの』P.201~202)
その後、光洋は房総半島の太平洋側の漁師町に手ごろな別荘地を求め、野良猫付きの中古住宅を購入して移り住みます。空の広いこと、陽射しの強いこと、月のやたら大きいことになぐさめられて、彼は久しぶりの自然を満喫するのでした。このあたりは、本書が房総半島の御宿を終の棲家としたボヘミアン乙川優三郎の自伝的長編であることが明示されています。
小鳥の棲む林があって野良猫がいるのも自然のうちであろうし、小さな命を愛おしむようになっていた彼は空き家のときから棲んでいる猫をそのまま飼うことにした。母親とその子供らしい二匹の猫で、食事を与えるとじきに馴れて家にも上がるようになった。この口をきけない仲間の存在がことのほか張り合いになって、新生活は淋しいこともなく流れていった。
晩年を意識して好きなように暮らしてみると、小説を書くことにもより気高い目標が生まれた。老いても精魂を傾けることがあるのは幸せだと思う。念願の傑作はまだ書けていないが、生きることの目的は残る命の幅に絞られ、日々の充足は言葉との闘いのうちにもたらされた。思うように書けないことが煩悶ではなく踏み継ぎとなって、明日の張り合いに変わるという昇華も経験した。(『この地上において私たちを満足させるも』P.207)
病後の体は頼りないものの、酒を飲めるうちは大丈夫だという気もする。手術で半分になった胃袋が少食しか受け付けなくなったように、男ひとりの世間も小さくなって、すべてに恬淡としてきた。よいのか悪いのか、創作に向かう情熱だけが埋み火のように燃えつづけて、雑多な1日を切り盛りする男の心棒になっている。たとえ10行でも佳い文章が書ければ作家の両親を維持できるし、美味い酒が飲めれば休らう。それで差し支えもないのが、また自由であった。もっとも電話をくれる編集者は少なく、猫のほかに話し相手のいない日常であったから、不意に人恋しくなって街のバーへ出かけたりもした。
「お手伝いさんを世話しましょうか」
そう言ってくれた人がいたが、田舎の中古住宅をやっと手に入れた男にそんな経済力はなかった。作家といってもピンからキリまであって、収入で言うなら光洋はキリであった。働いてどうにか食べてゆける人間に過ぎない。だから気儘に見えるサーファーが羨ましくもあった。(『この地上において私たちを満足させるもの』P.208)
しかしながら、光洋は素晴らしいお手伝いの女性を迎えます。彼女はソニアといって、フィリピンから来た学生でした。かつて、光洋が若い頃にフィリピンの貧しい母娘に大金を与えたことがあったのですが、その後、サラジェーンという名の娘はそのお金を学費にして女医になっていました。そのサラジェーンが「人生の恩人」である光洋への恩返しとして、ソニアを日本に送ってくれたのでした。ソニアに日本語や日本文化を教えながら、光洋は心満たされる日々を過ごします。
断っておきますが、大金を与えた母娘とも、ソニアとも、光洋は一切、男女の関係を持っていません。「清い関係」などという陳腐な表現を使うよりも、お互いに人間として認め合って、高め合っている関係と言えるでしょう。わたしたちが思っているほど、この世界は悪くないし、人はずっと優しい……この小説を読んで、わたしはハートフルな気分になりました。この上なく美しい日本語で書かれていますし、生きる気力が湧いてきます。人生を卒業する勇気も持てます。一条真也の新ハートフル・ブログ「人間失格 太宰治と3人の女たち」で紹介した映画のように、荒んだ人生を送った太宰治のような人が本書を読んだら、どのような感想を抱いたでしょうか。ふと、そんなことを考えました。
