- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.11.21
『舞踏会へ向かう三人の農夫』上下巻、リチャード・パワーズ著、柴田元幸訳(河出文庫)を読みました。一条真也の読書館『ブッチャーズ・クロッシング』で紹介した本をアマゾンで参照したとき、「よく一緒に購入されている商品」として本書がが並んでおり、その存在を知りました。著者は1957年アメリカ合衆国イリノイ州生まれ。イリノイ大学で物理学を学ぶが文転し、同大で修士号を取得。 1985年に発表した本書でデビュー後、着実なペースで読みごたえのある作品を発表しています。
上下巻共に、本書のカバー表紙にはこの小説のテーマになったモノクロ写真が使われ、上巻のカバー裏表紙には「それは1914年のうららかな春、プロイセンで撮られた一枚の写真から時空を超えてはじまった――物語の愉しみ、思索の緻密さの絡み合い。20世紀全体を、アメリカ、戦争と死、陰謀と謎を描ききった、現代アメリカ文学における最重要作家、パワーズの驚異のデビュー作」
また下巻のカバー裏表紙には「文系的知識と理系的知識の融合、知と情の両立。百科全書的な知識で『人間とは何か』を描く。『パワーズはたったひとりで、そして彼にしかできないやり方で、文学と、そして世界と戦った』(解説より)◎解説―小川哲」と書かれています。
この壮大な小説は、著者がボストン美術館で1枚の白黒写真を目にしたことから始まっています。プロイセンで撮影されたそれは、3人の男がぬかるんだ畦道に立って、こっちを振り向いている写真です。わたしの感想では3人ともけっこうなハンサムですが、彼らはみんなよそ行きの帽子にスーツ、ステッキと盛装していますが、スーツやズボンには皺が寄っていますし、ステッキも長すぎるようです。おそらく3人とも普段はこういう服装に縁がないような人々が借り物の服を着ている印象です。著者はこの写真に付されたキャプションに「舞踏会へ向かう三人の農夫、1914年」と書かれていることについて、第一章「セント・アイヴズへの旅支度」の最後にこう書いています。
「年を見るだけで、三人が舞踏会に予定どおり向かってはいないことは明らかだった。私もまた、舞踏会に予定どおりに向かってはいなかった。我々はみな、目隠しをされ、この歪みきった世紀のどこかにある戦場に連れていかれて、うんざりするまで踊らされるのだ。ぶっ倒れるまで踊らされるのだ」
著者は、さまざまなヒントからこの写真が撮影された日付を1914年5月1日と特定します。農民が舞踏会に行く可能性のある年に1度の春祭りが開かれたのが5月1日だからですが、その日は労働者の日である「メーデー」でもありました。「訳者あとがき」で、柴田元幸氏は以下のように述べています。
「1914年5月1日。とすれば、歴史がこれからどこへ行こうとしているかは明らかだ。同じ年の6月末にサラエボで起きた暗殺事件が引き金となって、8月に入り宣戦布告の連鎖はヨーロッパのみならず日本までも巻き込み、世界大戦という名の、その後4年にわたって大きな悲惨と荒廃をもたらすことになる死の舞踏がはじめる。それとともに、真の意味での20世紀がはじまったと言ってよい。三人の農夫の写真から出発するパワーズの小説も、最終的なテーマは20世紀そのものだ。かくして三人の農夫の物語のなかに、ヘンリ―・フォード、サラ・ベルナール、ニジンスキー等々、時代の貌となった人々の言動が織り込まれるのはむろん、写真論あり伝記論・小説論あり歴史論あり、さらには、現代にあってザンダーの写真に憑かれた『私』の思索的な物語と、同じく現代にあってパレードで見かけた謎の女性を追い求めるピーター・メイズのコミカルな物語とが並行して語られ、20世紀全体を――少なくとも西洋から見た20世紀全体を――視野に入れた作品世界が展開されている」
著者にとっての20世紀とは何だったのか。
わたしにはNHKで放映された「映像の世紀」という言葉がフィットしますが、柴田氏は以下のように述べています。
「パワーズが描く20世紀は、何よりもまず『距離の消滅』という事態が起きた世紀と言ってよいと思う。自動車の発明による、物理的な距離の消滅(むろん文字通りに消滅したわけではないが、A点からB点に到着することのみが意義を持つようになり、『道中』は問題にされなくなった)。写真などの発達による、製作者と鑑賞者の距離の消滅。占領地に見られるような、個が全体に対しそれぞれ直接責任を負わされる状況。科学における、観察行為と観察対象との不可分。こうした事態にあって、過去というものもまた、現在にとって単なるノスタルジアの対象ではない。両者はみずからを少しまた作り直している。過去を考えることは――というより、何について考えることであれ――自伝を書く行為なのだ。とすれば、我々がこの『舞踏会へ向かう三人の農夫』を読むことも、我々自身の自伝を書く行為であるだろう」
「舞踏会へ向かう三人の農夫、1914年」という写真を撮影したのは、ドイツ人アウグスト・ザンダーでした。彼は『20世紀の人間たち』と題すべき壮大な写真集のアイデアを思いついた人物です。『20世紀の人間たち』について、著者は「写真という普遍言語で書かれた、膨大かつ包括的な、人間たちのカタログ。それは人々の容姿、性格、社会的地位を仔細に吟味し、さまざまな代表的タイプをそれぞれ、いくつものカテゴリー、サブカテゴリ―から成る全体的構図のなかに位置づけ、相互参照する作品」と表現し、さらには「今日の我々には信じがたく思えるが、勤勉に努力さえすればそうした記録を完成できるものと、ザンダーは信じていた。20世紀特有の防御メカニズムたるアイロニーには彼は無縁だった。19世紀の人間であったからこそ、『20世紀の人間たち』が着想できたのである」
しかし、ザンダーは『20世紀の人間たち』を完成して世に送り出すことはできませんでした。第四章「時代の顔」で、著者は以下のように書いています。
「プラネタリウムの機械が夜空の星をすべてカバーできはしないように、ザンダーのカメラが20世紀の人間たちを網羅的に記録することなど、もとより無理な相談である。にもかかわらず、彼の仕事は、その挫折においてみずからを完成する。崩れ去った、あまりに野心的な未完の作品は、伝達不可能なテーマを伝えるのに何よりふさわしく思える。現存する、あるいは悪意とともに破壊された、あるいは決して撮られることのなかった、何万枚にも及ぶ機械的に複製されたプリントの集合から、1人の被写体が浮かび上がってくる。あるときは協力的、あるときは自己破壊的な、またあるときは寡黙、あるいは慎み深いその人物は、足し算不可能なその全体分の和を通しても、命名と分類と果てしない編集作業とを通しても、決して完全に捉えることはできない。不完全な資料集こそもっとも正確なのだ」
そのザンダーが撮影した1枚の写真からインスピレーションを与えられて書かれた本書もまた「20世紀」というものを丸ごと描こうとする野心に支えられた書物のように思えます。もっとも、本書に書かれているのは20世紀の前半だけとも言えますが、中でも著者は「1913年」に注目し、第七章「アラビアゴム手法で描いた肖像」で以下のように書いています。
「1913年、当時40歳の詩人、ジャーナリスト、社会主義者、ローマカトリック教徒という異様な組み合わせであった人物シャルル・ペギーは、有名な、その後何度も引用されてきた発言を行なった。すなわち、世界はこの30年間で、イエスの死からそれまでよりも大きく変わった、と。何百万という同時代人を代表して、幾何級数的に加速していく文化への恐怖と興奮とを、ペギーは言い表わしてみせたのである」
その「1913年」について、著者はこう書いています。
「1913年は、ルネッサンス以来もっとも豊かに〈偉大なる個人〉が輩出した時期であった。ウィーンとパリ、といえばおそらくもっとも相容れない2つの党派の代表だろうが(一方は外向性で君主制的、一方は内向性で無秩序的)、この二都において輩出した〈偉大なる個人〉を挙げるなら、フロイト、ピカソ、ヴィトゲンシュタイン、プルースト、アポリネール、シェーンベルク、ヴェ―ベルン、ベルク、ジッド、ジャリ、ドビュッシー、クリムト、ストラヴィンスキー、ベルナール、マーラー、総合病院の医師や科学者たち、スタイン、メリエス、クラウス、ヴェルフェル、ルソー、とまさに枚挙にいとまがない」
続けて、著者は以下のように書いています。
「この時代はしばしば、これら個人の人生の補足説明として語られがちだが、こうした習慣もあながち責めるわけにはいかない。当時の時代みずからも、自分をそういうふうに捉えていた観があるからだ。まるで、古い形の進歩――個人の天才によって作られる連続的な飛躍――の最後のあえぎが、これを限りと、爆発的な多産ぶりによってみずからを吹き飛ばし、新しい、同時性の時代に座を明け渡した、そんな感じなのである」
第十三章「第一次大戦の偉人たち」では、こう書かれています。
「ツェッペリン伯爵は飛行船の爆発を防ぐのに忙しかった。ディーゼル[ディーゼル機関の発明者、1858-1913]は行方不明となりドイツ・イギリス双方の諜報局がたがいに罪をなすりつけあった(実は株で巨額の金を失って自殺した)。血友病の息子とともに毎勉夜更けまで過ごしていた皇后アレクサンドラは、息子の出血を止められる男にめぐり遭ってまもないころだった。ド・ブロイ、プランク、ハイゼンベルク、アインシュタインはそれぞれの『奇跡の年』における発見に解釈を加えつつあった。マーラーは何もかもがばらばらに壊れる第九交響曲をどうかまとめ上げようとしていた。孫文は5億の人々を開放するために奔走していた。婦人参政権論者エミリー・デーヴィソンはイギリスのダービーで国王の馬の足下に身を投げ、見事な写真に記録されたこの「1票」によって、劇場へ行く権利を永遠に放棄した」
続けて、さらなる偉人のオンパレードが繰り広げられます。
「ライト兄弟は鍛冶屋仕事に励み、スターリンは新聞記事を書き、カフカは公式文書に判を押していた。ハーストは記者たちの尻をたたいてラグタイム音楽糾弾の記事を書かせた。シュヴァイツァーはバッハの研究書を書き、アフリカにキャンプを張った。今世紀における最重要物質の発見者アレグザンダー・フレミングは1000のシャーレを忙しく並べ、ビール工場から迷い込んできた胞子が鼻汁と混じりあってペニシリンの抗菌作用を明かすのを待っていた。そしてさらには、もしも運に恵まれていたなら、以上に挙げたどの業績よりもさらに上を行く偉業をなしとげたかもしれぬ無数の人々がいた」
そのように〈偉大なる個人〉が輩出した時代にあっても、ひときわ異彩を放っていたのが初代ヘンリ―・フォードでした。「自動車王」あるいは「大量生産の生みの親」などと呼ばれた彼は本書の中でも最重要な役割を果たすのですが、「第十章 安物の船」で、著者はこう書いています。
「世紀初頭の、歴史は偉人によって作られるという説がまだ有効だったころ、もろもろのアメリカ人権力者のなかにあって、フォードは誰よりも矛盾した存在であった。昔風の大富豪モーガンは1913年に死んでひとつの時代を終わらせた。ウィルソンは煮えきらぬアイビーリーグ・エリートであった。野心的な功利論者エジソンは床に噛み煙草の汁を吐く悪癖の持ち主だった。ノリスとドライサーは心あるジャーナリストにすぎなかった。ライト兄弟、ダッジ兄弟、ファイアストーン父子、みな今日の素人発明家とさして変わらぬ単純な連中でしかない。フォード1人が謎のままなのである。実際家と理想化との、革新者と反動家との、平和論者と戦争商人との、およそありそうもない出会い」
第十六章「私は可能性に住む」で、フォードについて、著者はこう書いています。
「人生はすべて、雑多な集合体である。農夫フォード、文盲フォード、機械の天才フォード、進歩主義者、反動主義者、反ユダヤ主義者、博愛主義者。現代という時代は、定義上すでに、その数十億倍も雑多な集合体である。この一方の集合体をもう一方の集合体になぎ合わせるのは、相当量の編集作業が必要となり、それゆえ相当の個人的気質が紛れ込むことになる。伝記作者が〈これこそがこの人物を偉大な、代表的な人間にしている〉と言うとき――すなわち、その人物を追いかけることに自分が何年も時間を浪費してきた理由を説明しはじめるとき――伝記作者は自分を巻き込みはじめている。自分の個人的気質を、そして逆説的なことに自分の時代の物の見方を、巻き込みはじめているのである」
ヘンリー・フォードは、言わずと知れたアメリカ合衆国の企業家です。フォード・モーターの社主として、世界有数の富豪となり、有名人となった彼は、第一次世界大戦の頃には平和主義を主張し、戦争を止めるためにアメリカからヨーロッパまで「平和船」を出しました。その彼の志は欧州の人々から嘲笑される結果となります。また、彼はリンカーンの肖像を自分の肖像に変えたコインを製造したり、とにかくエピソードにはことかきません。反ユダヤ主義者としても知られ、『国際ユダヤ人(英語版)』という書籍を出版しました。
一条真也の読書館『ヒトラーの秘密図書館』で紹介したように、アドルフ・ヒトラーはフォードのことを人種的に純粋な「絶対的北方型人間」として、非常に尊敬していました。人類史上最大の愚行ともされるユダヤ人のホロコーストにつながったヒトラーの反ユダヤ主義はフォードの影響が大きかったのです。わたしは、本書を読んで、フォードの人生と思想に強い興味が湧いてきました。「超」がつくほどの怪人であったフォードについての本格的な伝記は日本では未だ出版されていませんが、アメリカでは多数出ています。ぜひ、それらの翻訳出版を望む次第です。
さて、本書『舞踏会へ向かう三人の農夫』は、すぐれた写真論でもあります。もともと1枚の写真からはじまった物語なわけですが、第十九章「安価で手軽な写真」で、著者はこのように書いています。
「写真が持つ不思議な説得力は、選択的な正確さが選択的な歪曲と結託することから生まれる。複製は、見た人の頭のなかに連想の鎖を生じさせる程度には十分オリジナルに似ていなければならないが、見る人が自分の思いによってそれを肉付けし枠組を創り出す余地を残す程度にはオリジナルと違っていないといけない。写真というメディアは、こうした危うい混成にとりわけ向いているように思える。それはいわば感光塩で描かれたフィンガーペインティングだが、出来上がる絵は機械的に統制されている。その工程はもっとも自由であると同時に、もっとも限定されたものだと言える。シャッターは閉じるか開くかしかない反面、結果として出てくる像は、決して完全には予測も修整も反復もできない」
また、19世にフォーマルな肖像写真が喜ばれた理由を著者は3つ挙げています。
「1.金持ちにしか手の届かなかった油絵の安価な代用になったこと。2.画家個人の癖なしに本人に似た像が得られたこと。3.金を出して写真を撮ってもらう人物にとっては、被写体となり、観客となり、さらには、注文し、ポーズをとり、最終的な作品を選ぶことによって作者にもなるという多重の楽しみがあったこと」
写真を買い、やがては写真を作りもした大衆にとって、スタジオ写真とは、おのれの生涯を記録しておこうという自伝的意志への願ってもない共犯者であったと指摘し、著者は以下のように書きます。
「寿命が今日より短く、死を強く意識せざるをえなかった19世紀の中流階級はまた、ダゲレオタイプや写真のなかに、髪の毛や先祖伝来のネックレスといった伝統的な品よりも確かな形見を見出した。当時の新聞に載った、ある写真館の広告に、『本物が色褪せる前に影を確保しておきましょう』という言葉が見られる」
ここに、肖像写真の本当のセールスポイントがはからずも浮かび上がっていると、著者は述べます。残された者たちにとって、影の方が本物よりははるかに融通がきくのであり、したがってより大きな意味を持つこともありうるのだとして、こう書いています。
「影の方が、見る者が対象を理解していきつつ間断なく編み上げていく伝記行為には適している。宗教的イコンたる楕円の肖像写真が、祭壇たるタンスの上に祀られ、記憶のよすがとして、解釈の積み重ねたる伝記に肉付けを与える。像にもともと備わっている性質は、その写真を撮った――あるいは撮った気になっている――人々の頭のなかに生じる連想の前では二義的なものでしかない。『この写真はスティーヴンの10歳の誕生日に撮ったんです。あの子が亡くなる2か月前のことですわ。写真屋さんは1ダース撮ってくれたんですけど、私がこの1枚を選んだんです。将来あの子がどんな人間になったはずか、この顔にはっきり表われていますわ。焼増しして親戚に配ったんですのよ』」
ちなみに「影」を意味する英語のshadowには「遺影」という意味もあります。さらに、写真の本質について、著者は書いています。
「現像された写真はみな、見る者が撮影者と一体化するよう誘う。消えた像をそうやって保存したという行為の背後にある価値観を、見る者が再構築することを写真は強いる。こうして、見ることはひとつの死の警告(メメント・モリ)となる。風景であれば肖像であれ、被写体の死を思い起こさせるものになるのだ。ずっと前に死にたえたそれら被写体は、我々がプリントを所有し、プリントにみずからかかわり合うことを通して再創造される。見る者にとって、写真に残る失われた光景を眺めることは、美学とも政治ともおよそ無関係な行為なのだ」
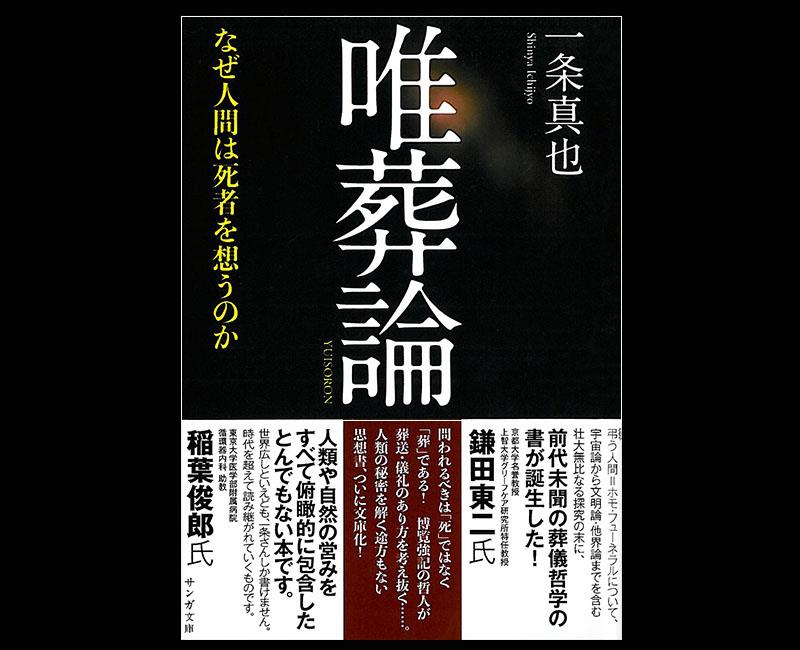 『唯葬論』(サンガ文庫)
『唯葬論』(サンガ文庫)
わたしは、これを読んで拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の内容を連想しました。アマゾンの哲学書ランキングでも1位となった同書ですが、宇宙論/人間論/文明論/文化論/神話論/哲学論/芸術論/宗教論/他界論/臨死論/怪談論/幽霊論/死者論/先祖論/供養論/交霊論/悲嘆論/葬儀論という18の論考から「死」と「葬」の本質を求めました。わたしは、葬儀とは人類の存在基盤であり、発展基盤だと思っています。約7万年前に死者を埋葬したとされるネアンデルタール人たちは「他界」の観念を知っていたとされます。「人類の歴史は墓場から始まった」という言葉がありますが、確かに埋葬という行為には人類の本質が隠されています。それは、古代のピラミッドや古墳を見てもよく理解できるでしょう。文明および文化の発展の根底には、「死者への想い」があるのだ。そして、写真こそは「死」のメディアです。なにしろ、すべての肖像写真は将来必ず遺影となるのですから。『唯葬論』では、心霊写真をはじめ、すべての写真とは死者と生者とのコミュニケーション・メディアであることを明らかにしました。
葬儀の祭壇の中央には遺影が飾られますが、もともと写真と葬儀は似ています。それは、ともに1人の人間が生きた証をこの世に残すからです。その営みを「メモリアル」というのです。1枚の写真から20世紀を概括する小説を書き上げた著者の筆力には感心しますが、結局のところ著者が言いたかったことは「あらゆる人間の生の営みは記録されるべきであり、記憶されるべきである」ということではないでしょうか。本書で詳しく書かれているヘンリ―・フォードやアウグスト・ザンダーやサラ・ベルナールといった偉人たちだけでなく、借り物の盛装をした3人の無名の農夫であっても、彼らがこの世に生きたことは確かなのであり、それは写真をはじめとした時代の断片として記録し、記憶されなければいけないということでしょう。
「解説」で、作家の小川哲氏が本書を総括しています。
「パワーズはたったひとりで、そして彼にしかできないやり方で、文学と、そして世界と戦った。ちょうど、ヘンリ―・フォードが世界を巻きこんだ戦争を個人の力で終わらせようとしたように、アウグスト・ザンダーが独力で人間のカタログを作ろうとしたように、あるいは、サラ・ベルナールが財産と片脚を失いながらも、ドイツ軍に立ち向かったように。20世紀とはつまり――作中で述べられているように――世界に対して個人で抵抗する意義が失われていった時代だ」『カービン銃に向かって突進したところで』『何もなしとげられはしない』のである。本書には、カービン銃に向かって突進した人ったいの話が繰り返し描かれている。そして彼らは、みなそれぞれの挑戦に失敗した」
 『ハートフル・ソサエティ』(三五館)
『ハートフル・ソサエティ』(三五館)
しかし、最後に小川氏はこうも述べています。
「パワーズは20世紀の文学に抵抗し、それによって世界に抵抗した。もしかしたら20世紀の世界はより強大化して、僕たち個人に襲いかかってくるかもしれない。そんなとき、本書の登場人物たちがどのように世界と向き合っていたのか、思い出してみるのもいいだろう、少なくともその一点において、パワーズの挑戦が古びることはない」
わたしは小川氏この文章を読んで、拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)のことを考えました。2005年に上梓した同書は、パワーズの小説と同じく、20世紀を俯瞰する試みであり、さらには21世紀を予見する試みでもありました。自分で言うのも何ですが、『舞踏会へ向かう三人の農夫』におけるパワーズの挑戦のように、わたしも『ハートフル・ソサエティ』で挑戦したように思います。そして今、わたしは15年ぶりに『ハートフル・ソサエティ2020』を書き上げ、2020年早々に弘文堂から上梓する予定です。小説としてはストーリーを追うのが難しくて非常に読みにくい『舞踏会へ向かう三人の農夫』ですが、そこに込められた志を読み取ったわたしは、パワーズを「同志」であると思いました。
