- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1835 ホラー・ファンタジー 『楽譜と旅する男』 芦辺拓著(光文社文庫)
2020.02.27
『楽譜と旅する男』芦辺拓著(光文社文庫)を読みました。
一条真也の読書館『奇譚を売る店』で紹介した本に続く、著者の幻想奇譚集第2弾です。著者は1958年大阪生まれ。同志社大学法学部卒。86年「異類五種」で第2回幻想文学新人賞佳作入選。90年『殺人喜劇の13人』で第1回鮎川哲也賞を受賞。この人は本格ミステリ作家として有名だそうですが、「幻想小説家としての資質も具えている」と評されており、ホラー小説のアンソロジーなども編んでいます。
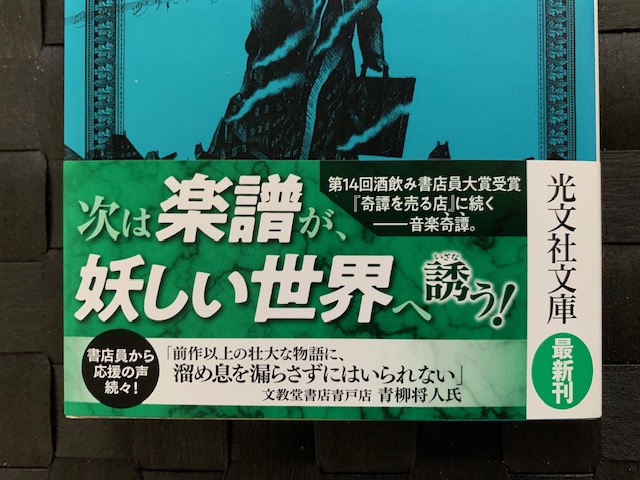 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、ひらいたかこ氏の幻想的(またも日野日出志の絵みたい)なイラストが使われています。帯には「次は楽譜が、妖しい世界へ誘う!」「第14回酒飲み書店員大賞受賞『奇譚を売る店』に続く――音楽奇譚」「書店員から応援の声続々!」「前作以上の壮大な物語に、溜め息を漏らさずにはいられない(文教堂書店青戸店 青柳将人氏)」と書かれています。
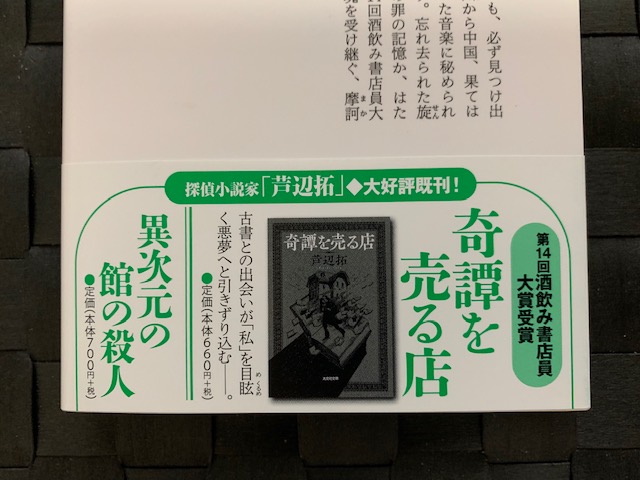 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「依頼があれば、どんな譜面でも、必ず見つけ出す――楽譜探索人。彼は欧州から中国、果ては日本まで……古今東西に散った音楽に秘められる人々の過去まで解き明かす。忘れ去られた旋律が響かせるのは、いつかの罪の記憶か、はたまた美しき愛の残像か。第14回酒飲み書店員大賞受賞『奇譚を売る店』の魂を受け継ぐ、摩訶不思議の連作幻想短編集」
『楽譜と旅する男』というタイトルは、明らかに江戸川乱歩の『押絵と旅する男』へのオマージュであることがわかります。本書の「解説」で、文芸評論家の東雅夫氏は「怪しき由来を秘めた押絵の額を抱えて、日本海に沿った鉄路の果て、『山間の小駅』の『闇の中へ溶け込む様に消えて行った』あの男……その幽暗な闇の彼方に芦辺氏は、押絵ならぬ楽譜とともに旅をする、もうひとりの放浪者(ワンダラー)の眩惑に満ちた物語を夢想したのに違いない」と述べています。
本書には「曾祖叔母オパールの物語」「ザルツブルグの自動風琴」「城塞の亡霊」「三重十字の旗のもとに」「西太后のためのオペラ」「悲喜劇ならばディオラマザ」という楽譜にまつわる6つの幻想短篇小説が収録されています。本書の帯には「前作以上の壮大な物語に、溜め息を漏らさずにはいられない」とありますが、わたしには前作のほうがずっと傑作に思えました。物語の舞台がロンドンザルツブルグ、デン、ブカレスト、上海、パリと、ワールドワイドになっていますが、どことなく板についていないというか、無理がある印象を持ちました。
また、「楽譜」というテーマも、前作の「古書」に比べて、著者の手に余るというか、こなれていない感じがしました。著者自身も、「『楽譜と旅する男』と旅して」と題する「あとがき」で、「『奇譚――』では、ミステリを書いているときにはあまり触れない私的な思い出や体験、友人たちまでがヒョイヒョイと登場して驚いたのですが、古本および古本屋というおなじみの領域に比べれば、今回はまるで知らない、知らなすぎる世界です」と告白しています。
それだけに、著者はかなり音楽の世界を勉強したようで、本書の各所に音楽史的な知識が散りばめられていました。たとえば、モーツァルトとベートーヴェンがたった14歳しか違わないということ。この事実を知った日本人で、音楽にそれほど詳しくない人は必ずといっていいほど驚くそうです。なぜ、彼らが明白な史実に驚くかというと、モーツァルトが「アマデウス」という劇でもおなじみのように、いかにもヨーゼフ2世の宮廷劇の登場人物として、あの奇妙なカツラやあでやかな刺繍入りの長衣に飾られているイメージなのに対し、ベートーヴェンは残された肖像画からしても、はるかに近代的な人間に見えるからです。
これは当時、18世紀から19世紀初めの社会や音楽家の在り方の激変によるものでした。宮廷作曲家として王侯貴族に仕え、常に臣下としての正装を要求されていた身の上から、新興の市民階級からの注文にも応じて生計を立て、したがって風体をかまう必要のない独立作曲家への変化です。父レオポルドの意向で宮廷に送りこまれたモーツァルトも中途からはフリーランスの作曲家をめざしましたし、ベートーヴェンは長らくエステルハージ侯のもとで楽長をつとめた師匠ハイドンのような道は、最初からめざしませんでした。
それ以上に、当時は音楽そのものが劇的に変化しつつありました。最もポピュラーな楽器であるピアノもまだ完成の途上にあり、現在は88と数の定まった鍵盤もまだはるかに少なかったのです。1700年頃にイタリアのバルトロメオ・クリストフォリが発明した‟アルビチェンバロ”は鍵盤数たった54、音域はC2からF6に過ぎませんでした。それがモーツァルトの頃にはヨハン・アンドレアス・シュタインが作った‟フォルテピアノ”で61鍵に増えました。
19世紀に入ると、いよいよベートーヴェンの時代になりますが、彼が最初の頃に用いたのはフランスのセバスチャン・エラールによる73鍵のもの、そしてコンラート・グラーフがウィーンの工房から鍵盤数78のピアノを送り出し、彼にとってはこれが最後の、そして最大の音域をもつ作曲道具になったのでした。わたしも音楽史にはそれほど詳しくありませんが、本書のところどころに出てくる音楽家や楽器、クラシックの名曲などに関するエピソードは物語そのものよりも興味深く、面白かったです。