- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1836 ホラー・ファンタジー 『おじさんのトランク 幻燈小劇場』 芦辺拓著(光文社)
2020.02.28
『おじさんのトランク 幻燈小劇場』芦辺拓著(光文社)を読みました。一条真也の読書館『奇譚を売る店』、『楽譜と旅する男』で紹介した同著者の本のほうが先に発表されており、その流れの中に本書もあるのですが、実際は本書を一番初めに読みました。わたしはファンタジー小説やホラー小説の類に目がないのですが、何か新作はないかとアマゾンで探したところ、本書を見つけたのです。著者は1958年、大阪府生まれ。同志社大学法学部卒。1986年、「異類五種」で第2回幻想文学新人賞佳作入選。1990年、『殺人喜劇の13人』で第1回鮎川哲也賞を受賞。2018年、『奇譚を売る店』で第14回酒飲み書店員大賞を受賞しています。
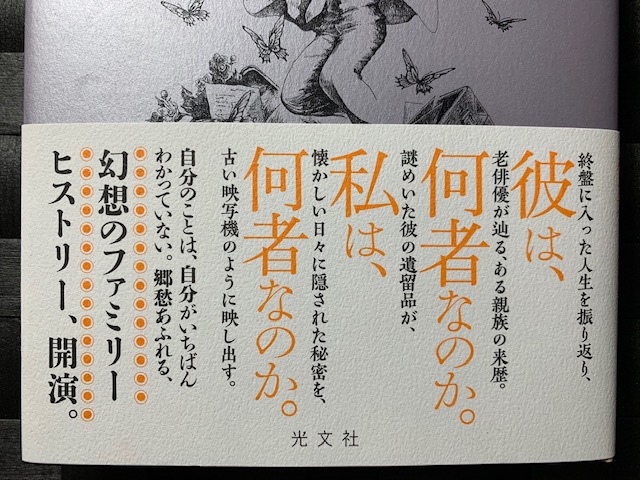 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「彼は、何者なのか。私は、何者なのか。」「終盤に入った人生を振り返り、老俳優が辿る、ある親族の来歴。謎めいた彼の遺留品が、懐かしい日々に隠された秘密を、古い映写機のように映し出す。」「自分のことは、自分がいちばんわかっていない。郷愁あふれる、幻想のファミリーヒストリー、開演。」と書かれています。
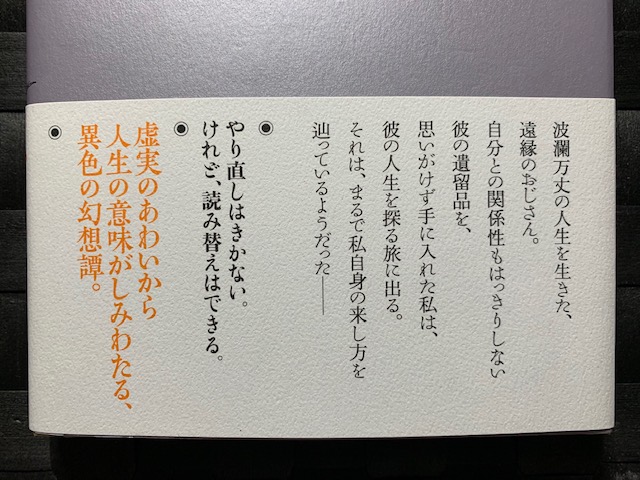 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、「波瀾万丈の人生を生きた、遠縁のおじさん。自分との関係性もはっきりしない彼の遺留品を、思いがけず手に入れた私は、彼の人生を探る旅に出る。それは、まるで私自身の来し方を辿っているようだった――」「やり直しはきかない。けれど、読み替えはできる。」「虚実のあわいから人生の意味がしみわたる、異色の幻想譚。」と書かれています。
物語は、1人の老俳優が幼い頃に憧れた「おじさん」の遺品であるトランクを思いがけず手に入れます。トランクの中身から、さまざまな戦前戦中の破天荒なエピソードが明らかになります。ホテルでの殺人事件の容疑者にされたり、欧亜連絡国際列車に乗り込んだり、欧州での反ナチス運動に加担したり、幻の蝶を探しにジャングルを探検したり、「おじさん」の人生はロマンに満ちていましたが、最後は意外な真実が明らかになります。
物語自体は薄味というか、あまりワクワク感がなかったのですが、最初は謎だらけだった「おじさん」の正体が次第に明らかになっていくところは興味深かったです。本書では、主人公である老俳優が探偵になって「おじさん」の正体を探っていくのですが、わたしは哲学者の内田樹氏が著書(バジリコ)において、探偵の仕事について鋭く分析したことを思い出しました。
内田氏は、きわめて興味深いことを指摘しています。
「探偵は一見して簡単に見える事件が、被害者と容疑者を長い宿命的な絆で結びつけていた複雑な事件であったことを明らかにする。読者たちはその鮮やかな推理からある種のカタルシスを感じる。それは探偵がそこで死んだ人が、どのようにしてこの場に至ったのかについて、長い物語を辛抱づよく語ってくれるからである。その人がこれまでどんな人生を送ってきたのか、どのような経歴を重ねてきたのか、どのような事情から、他ならぬこの場で、他ならぬこの人物と遭遇することになったのか。それを解き明かしていく作業が推理小説のクライマックスになるわけだが、これはほとんど葬送儀礼と変わらない」
なんと、探偵の仕事が葬送儀礼と同じであったとは!! これには、つねに葬儀の意味について考え続けているわたしも仰天しました。内田氏は、さらに次のように書きます。
「死者について、その死者がなぜこの死にいたったのかということを細大漏らさず物語として再構築する。それが喪の儀礼において服喪者に求められる仕事である。私たちが古典的なタイプの殺人事件と名探偵による推理を繰り返し読んで倦まないのは、そのようにして事件が解決されるプロセスそのものが同時に死者に対する喪の儀礼として機能していることを直感しているからなのである」
この内田氏の言葉を読んで、わたしは、行旅死亡人と呼ばれる人々のことを思い浮かべました。氏名も職業も住所もわからない行き倒れの死者たちです。いわゆる「無縁死」で亡くなる人々です。そんな死者が、なんと日本に年間3万以上もいるといいます。明日、自宅の近くの路上にそんな死者が倒れている可能性がないとは言えません。その人が何者で、どのような人生を歩んできたのか。それを、みんなで推理しなければならないのが無縁社会です。わたしたちは、「一億総シャーロック・ホームズ」の時代を生きているのかもしれません。『おじさんのトランク』を読んで、そんなことを考えました。