- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1883 エッセイ・コラム 『猫を棄てる』 村上春樹著(文藝春秋)
2020.05.23
会社の会議が開かれ、久々に会長である父と一緒になりました。今年で85歳になりますが、非常に元気で、わが社の稟議書システムの改善を強く訴えていました。小倉織のマスクをプレゼントしたところ、喜んでくれました。
さて、「父親について語るとき」というサブタイトルを持つ『猫を棄てる』村上春樹著(文藝春秋)を読みました。月刊誌「文藝春秋」2019年6月号に掲載されたエッセイを書籍化したものですが、全体で104ページしかなく、そのうえイラストが多く添えられているので、すぐ読めます。わたしもランチタイムの間に20分ぐらいで読み終えました。
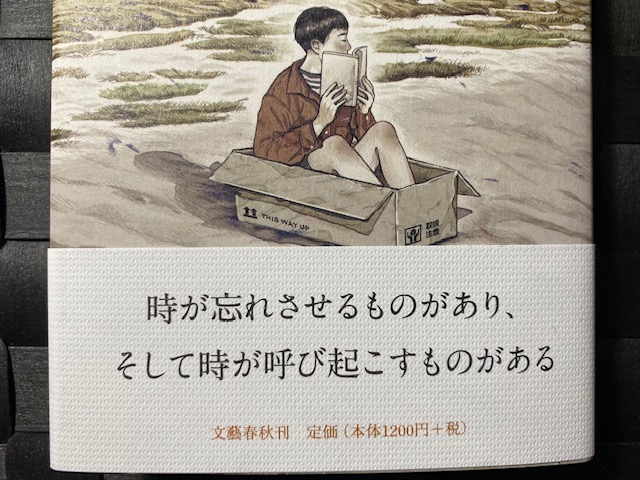 本書の帯
本書の帯
カバー表紙には、海岸の砂浜のような広い場所で段ボる箱に入った少年が本を開きながら近くの鳩の群れを眺めているイラストが使われています。台湾出身の若い女性イラストレーターである高研氏のイラストですが、これが非常に素晴らしい。本書の中にはたくさん彼女の絵が使われていますが、著者自身が「彼女の絵にはどこかしら、不思議な懐かしさのようなものが感じられる」と「あとがき」に書いていますが、同感です。また帯には、「時が忘れさせるものがあり、そして時が呼び起こすものがある」と書かれています。帯の裏には、「ある夏の日、僕は父親と一緒に猫を海岸に棄てに行った。歴史には過去のものではない。このことはいつか書かなくてはと、長いあいだ思っていた。――村上文学のあるルーツ」と書かれています。
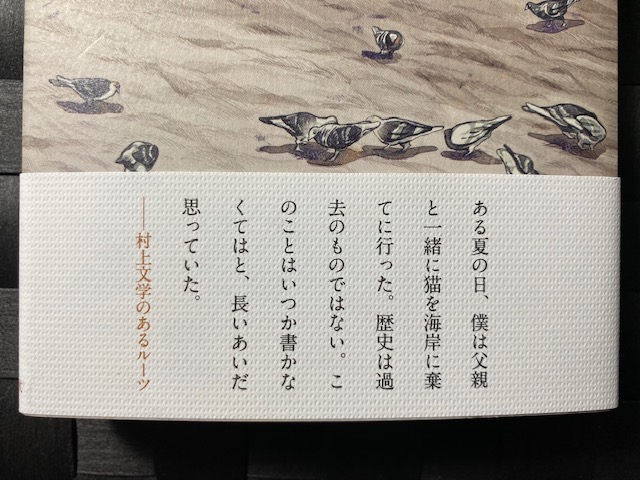 本書の帯の裏
本書の帯の裏
この本は薄いのですが、ハードカバーです。カバーを取ると、エバーグリーンの本体が出てきますが、ちょうどそのとき、わたしがエバーグリーン色の布マスクをしていたので、その偶然に驚きました。そのカバーを外した本体は新書版で小さいのにガッチリと作られていて、昔、岩波書店から出ていた『漱石全集』の新書版を連想しました。そう、一条真也の読書館『ビブリア古書堂の事件手帖』で紹介したベストセラー小説にも登場する『漱石全集』新書版です。すると、漱石の処女作である『吾輩は猫である』と本書『猫を棄てる』のタイトルが「猫」でつながり、夏目漱石と村上春樹という新旧2人の国民作家のイメージが重なってきました。
 ヤフー・ニュースより
ヤフー・ニュースより
その猫の話から本書は始まります。著者と父が海辺に飼い猫を棄てくるのです。「当時は、猫を棄てたりすることは、今に比べればわりに当たり前の出来事であり、とくに世間からうしろ指を差されるような行為ではなかった」と書かれている文章を読んで、ふと目の前のパソコンがメールを受信したので、そちらに目を移し、ついでにヤフー・ニュースをチェックしたところ、わたしの目は点になりました。なぜなら、そこには「秋田の警察官、猫を遺棄か」の見出しで、近所の飼い猫など数匹を捕まえて自宅から離れた郊外に捨てたとして、秋田市の警察署に勤務する男性警察官が書類送検していたことが書かれていたのです。猫を棄てたニュースなんて初めて見ましたが、それがヤフーのTOPニュースになっていたのです。最近、秋山眞人氏の新著『シンクロニシティ』という本を読んだばかりでしたが、こういった不思議な偶然の一致が起こるときは、わたしの感受性が研ぎ澄まされていることの証なのだそうです。実際、そうかもしれません。
それはともかく、父親と著者が棄てたはずの猫は、なぜか2人よりも早く帰宅していました。著者は、「そのときの父の呆然とした顔をまだよく覚えている。でもその呆然としたは、やがて感心した表情に変わり、そして最後にはいくらかほっとしたような顔になった。そして結局それからその猫を飼い続けることになった。そこまでしてうちに帰ってきたんだから、まあ飼わざるを得ないだろう、という諦めの心境で」と書いています。著者の父は、京都の浄土宗の住職の息子として生まれ僧侶の資格も持っていながら、3度も戦地に送られるという経験の持ち主でした。父は戦争では死なずに帰還し、戦後は国語教師となります。父が戦争から無事に帰ってきた「隠された理由」を読み解くことが本書の大きなテーマになっているのですが、棄てたはずの猫の帰宅に、父は自らの運命と共通するものを感じたようです。
2009年、村上春樹氏はエルサレム賞を受賞しました。イスラエルのガザ地区攻撃で多くのアラブ人が死亡したこともあり、イスラエルには国際的な批判が高まっていました。当然、そんな国の文学賞を受賞した村上氏もいろいろと言われました。多くの人々は「辞退すべきだ」と主張しましたが、彼はあえて受けました。そして、エルサレムに出かけ、英語で受賞スピーチを行いました。「高く堅牢な壁と、そこにぶつかれば壊れてしまう卵があるなら、私は常に卵の側に立とう」という彼の言葉は、一人の作家の勇気ある平和のメッセージとして有名になりました。言うまでもなく、「壁」とは体制であり、「卵」とは一般民衆をさしています。
もちろん、この言葉も多くの人々に深い感動を与えた素晴らしいメッセージですが、わたしにはスピーチの中の次のくだりが非常に印象に残りました。英語で語られた言葉を意訳すると、「わたしの父は、去年90歳で亡くなりました。父はもと教師でしたが、たまに僧侶の仕事もしていました。京都の大学院にいたときに徴兵された彼は、中国戦線に送られました。わたしは戦後に生まれましたが、父の毎朝の習慣を目にすることがよくありました。彼は、朝食の前に自宅にある小さな仏壇に向かい、長いあいだ深く真剣な祈りを捧げるのです。なぜ、そんなことをするのか。一度、彼に尋ねたことがありますが、そのとき、『すべての人々のために祈っている』と答えました。そして、『味方も敵も関係ない。戦争で亡くなった人全員の冥福を祈っている』と言いました。仏壇の前に座った父の背中をながめながら、父の周囲には死の影が漂っているような気がしました」
この村上春樹氏の言葉を聞いたとき、わたしには1つの謎が解けたような気がしました。その謎とは、「なぜ、村上春樹の文学には、つねに死の影が漂っているのか」ということです。実際、彼の作品にはおびただしい「死」が、そして多くの「死者」が出てくる。 一条真也の読書館『もういちど村上春樹にご用心』で紹介した本で、哲学者の内田樹氏は「およそ文学の世界で歴史的名声を博したものの過半は『死者から受ける影響』を扱っている。文学史はあまり語りたがらないが、これはほんとうのことである」と述べています。そして、近いところでは村上春樹のほぼ全作品が「幽霊」話であるというのです。もっとも村上作品には「幽霊が出る」場合と「人間が消える」場合と二種類ありますが、これは機能的には同じことであるというのです。
このような「幽霊」文学を作り続けてゆく村上氏の心には、きっと、すべての死者に対して祈りを捧げていた父上の影響があるのかもしれません。それは、「死者との共生」という意識につながります。日本にはもともと祖霊崇拝のような「死者との共生」という強い文化伝統がありますが、どんな民族の歴史意識や民族意識の中にも「死者との共生」や「死者との共闘」という意識が根底にあると思います。SFの巨匠アーサー・C・クラークは、名作『2001年宇宙の旅』の「まえがき」に、「今この世にいる人間ひとりひとりの背後には、30人の幽霊が立っている。それが生者に対する死者の割合である。時のあけぼの以来、およそ一千億の人間が、地球上に足跡を印した(伊藤典夫訳)」と書きました。クラークがこの作品を刊行したのは、わたしが5歳のときの1968年ですが、わたしにはこの数字が正しいかどうか知らないし、また知りたいとも思いません。それよりも問題なのは、わたしたちの傍には数多くの死者たちが存在し、わたしたちは死者に支えられて生きているという事実です。
多くの人々が孤独な死を迎えています。亡くなっても長いあいだ誰にも発見されない「孤独死」、葬儀に誰1人として参列者のいない「孤独葬」も増加しています。最近では、新型コロナウイルスで亡くなられた場合、家族は最期のときにも会えず、通夜も告別式も行うことはできません。一度も顔が見れないまま、故人は遺体焼却されてしまうのです。このような今日、わたしたちに必要なのは死者たちを含めた大きな「魂のエコロジー」とでも呼ぶべき死生観であると思います。病死、餓死、戦死、孤独死、大往生……これまで、数え切れない多くの人々が死に続けてきました。わたしたちは常に死者と共生しているのです。絶対に、彼らのことを忘れてはなりません。死者を忘れて生者の幸福などありえないと、わたしは心の底から思います。村上氏のエルサレム賞受賞のスピーチから感じた以上のようなことを、わたしは拙著『ご先祖さまとのつきあい方』の最後の「生命の輪は廻る~あとがきに代えて」に書きました。
そして、このスピーチで村上氏が自身の父親について話した内容が本書『猫を棄てる』には詳しく書かれているのです。僧侶であり兵士であった父の戦場での苦悩、惨殺された中国人捕虜の悟りきったような最期の姿、戦死した戦友たちの遺骨のうちには、今でも野ざらしになっているものも少ならからずあること……それらすべてを抱えたまま戦後の平和な日本を生きた著者の父の生き様が描かれています。その父と著者の関係は疎遠になり、著者がプロの作家になってからは関係がより屈折したものとなり、最後には絶縁に近い状態になったそうです。じつに20年以上も顔を合わせませんでしたが、最後にようやく顔を合わせて話をしたのは父が90歳になって亡くなる前でした。著者も60歳近くになっていましたが、最後にぎこちない会話を交わし、和解のようなことを行ったそうです。
本書には、著者の子ども時代の、猫にまつわる思い出がもう1つ書かれています。それは当時飼っていた白い小さな子猫が自宅の庭の高い松の木にするすると上っていき、ずっと上の枝の中に姿を消したものの下に降りれなくてなって情けない声で鳴き始めたそうです。目で見えないほどの高い枝の中で鳴いている子猫に対して、著者も父もどうすることもできませんでした。翌日の朝起きたときたとき、もう鳴き声は聞こえず、それから子猫は再び姿を現さなかったそうです。その後、著者は、その枝に小さな爪を立て、必死にしがみついたまま、死んでひからびてしまった小さな子猫のことをよく想像したそうです。それは、まだ幼かった著者に「降りることは、上がることよりもずっとむずかしい」という生々しい教訓を残してくれました。「より一般化するなら、こういうことになる――結果は起因をあっさりと呑み込み、無力化していく。それはある場合には猫を殺し、ある場合には人をも殺す」と、著者は書いています。
そして、最後に著者は「我々は、広大な大地に向けて降る膨大な数の雨粒の、名もなき一滴に過ぎない。固有ではあるけれど、交換可能な一滴だ。しかしその一滴の雨水には、一滴の雨水なりの思いがある。一滴の雨水の歴史があり、それを受け継いでいくという一滴の雨水の責務がある。我々はそれを忘れてはならないだろう。たとえそれがどこかにあっさりと吸い込まれ、個体としての輪郭を失い、集合的な何かに置き換えられて消えていくのだとしても。いや、むしろこういうべきなのだろう。それが集合的な何かに置き換えられていくからこそ、と」と述べるのでした。このくどいまでに「一滴」という単語が出てくるこの一文は、明らかに著者の大学の先輩でもある国民作家・五木寛之氏の『大河の一滴』の影響があると思います。思えば、『大河の一滴』も、教師でありながら敗戦とともに無気力になった父親への五木氏の供養の書であったような気がします。そして、そこでも仏教の思想が背景にありました。2人の大学の後輩であるわたしの中で、五木寛之と村上春樹という2人の国民作家が初めてつながりました。
「あとがき」で、著者は「歴史は過去のものではない。それは意識の内側で、あるいはまた無意識の内側で、温もりを持つ生きた血となって流れ、次の世代へと否応なく持ち運ばれていくものなのだ。そういう意味合いにおいて、ここに書かれているのは個人的な物語であると同時に、僕らの暮らす世界全体を作り上げている大きな物語の一部でもある。ごく微小な一部だが、それでもひとつのかけらであるという事実に間違いはない」と書いています。これは、わたしが『ご先祖さまとのつきあい方』の「生命の輪は廻る~あとがきに代えて」で述べたこととほぼ同じだと思いました。