- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.10.15
14日に発表された東京都の新型コロナウイルス感染者数は、177人でした。危機は、なかなか消え去りませんね。『危機の正体』佐藤優著(朝日新書)を読みました。「コロナ時代を生き抜く技法」というサブタイトルがついています。
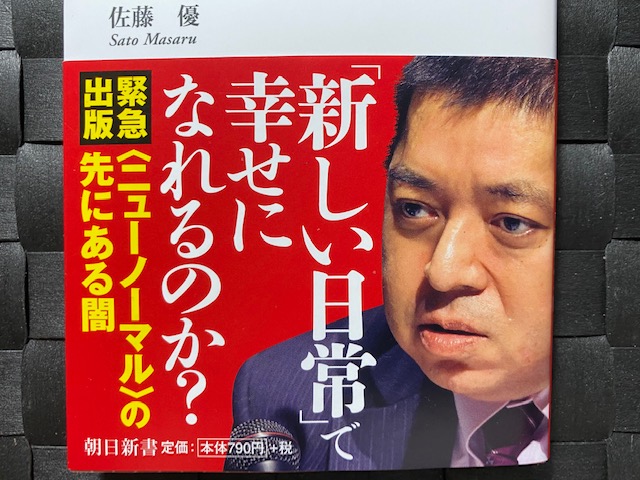 本書の帯
本書の帯
帯には、いつものように著者の顔のどアップの写真が使われ、「『新しい日常』で幸せになれるのか?」「緊急出版〈ニューノーマル〉の先にある闇」と書かれています。また帯の裏には、「国家機能強化に飲み込まれないためのサバイバル術」と書かれています。
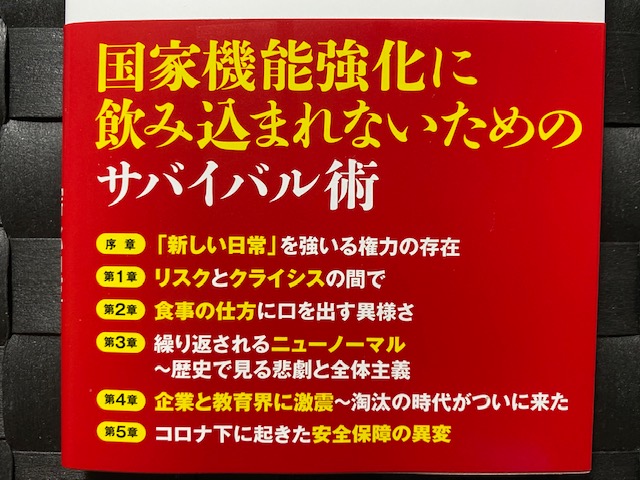 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには「密集と接触を極力減らす〈反人間的〉な振る舞いが要求されるニューノーマル(新しい日常)の時代、変容する価値観の中を私たちはどう生き抜けばよいのか?」として、「人とのつながりを断絶させた新型ウイルス。国家機能は強化され、格差はますます加速し、富の多寡が感染リスクを左右する。疫病がもたらす不条理を生き抜く知恵を近過去の歴史と思想から探る」と書かれています。
さらにアマゾンでは、【出版社から】として、 「『料理に集中、 おしゃべりは控えめに』『横並びで座ろう』――事細かな”生活様式”を無条件で受け入れていくうちに、私たちの生活はもちろん、思考回路や価値観までもが変質していってしまうのではないでしょうか。『ニューノーマル(新しい日常)が何をもたらすかは歴史が教える』と著者の佐藤優氏は力説します。1968年『プラハの春』以後に起きたチェコスロバキアでの出来事(「正常化」の名のもとでの言論弾圧)をフェイト『スターリン以後の東欧』から説き、カミュ『ペスト』、オーウェル『動物農場』、冨山和彦『コロナショック・サバイバル』等を援用しつつ、〈反人間的〉時代を生き抜く思考法が明かされます」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 「新しい日常」を強いる権力の存在
第1章 リスクとクライシスの間で
第2章 食事の仕方に口を出す異様さ
第3章 繰り返されるニューノーマル
――歴史で見る悲劇と全体主義
第4章 企業と教育界に激震
――淘汰の時代がついに来た
第5章 コロナ下に起きた安全保障の異変
「あとがき」
序章「『新しい日常』を強いる権力の存在」の冒頭を、「けっこう幸せなのかも」として、著者は「限られた人への30万円給付から、全国民一律10万円給付へ。2020年3月から4月にかけて、新型コロナ禍における家計支援策をめぐり、安倍晋三首相は方針を大きく転換しました。安倍首相のブレは、新型コロナ感染が拡大する日本の「国家」と「社会」の動揺を反映したものでもあり、新型コロナ禍は、混沌としてその姿が見えづらかった国内外の問題を可視化するのではないか。私にはそう感じられました」と書きだしています。
また、「新型コロナで休業した職種」として、著者は「新型コロナ禍をきっかけに、働き方が変わるといわれています。リモートワークはその代表的なものでしょう。自宅から参加するウェブ会議に慣れなくて大変。子どもも休校で家にいて、在宅での仕事に集中できない。仕事と生活との区切りがつかず、かえって労働時間が増えた、などというリモートワークをしているビジネスパーソンの声をメディアは伝えていますが、ネット環境が整いリモートワークができるのは大企業の話です。給与も保証されています。アンダークラスの大変さとは根本的に質が異なります」と述べています。
不安定な雇用状況にある個々人が真剣に生き残りを考えるならば、サービス業から大規模な農業法人に移ったり、小規模ながら地産地消型で農業に取り組むグループに移ったり、産業間の移動も選択肢として出てくるだろうと推測する著者は、「新型コロナの影響は、正規雇用労働者にも及びます。企業では、コロナ禍で広がった在宅勤務を働き方の1つとして定着させようという動きが加速しています。在宅勤務とのセットで注視されているのが、企業が社員の職務内容を明確にし、成果で評価する『ジョブ型』の導入です。成果主義の導入は、日本経団連が2000年代初頭から提言していましたから、新型コロナ禍という”外圧”により、一気に在宅勤務が進んだことに伴って導入されるのではないでしょうか」と述べます。
さらに、「政治を『戦時の発想』に」として、新型コロナウイルスによる家計支援について、政権に対する国民の風当たりが厳しいにもかかわらず、立憲民主党や国民民主党などの野党が力を発揮できなかったことを指摘し、著者は「その理由は、どの党も『小さな政府』路線をとっているからです。野党で比較的、大きな政府路線を唱えているのは、増税による中負担、中福祉を主張する前原誠司氏(国民民主党)のグループくらいです。与党の自民党も小さな政府路線です」と述べます。小さな政府路線の何が問題になるのかというと、「簡単にいえば、小さな政府路線とは国民への再分配を絞って自由競争を促す。公共部門を民営化し、政府は借金を減らして身軽になり財務体質を改善するというものです」といいます。
10万円の一律給付について、公明党は一歩も譲りませんでした。これは、1964年(昭和39年)の発足時に、池田大作・創価学会第3代会長(当時)が提唱した「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」という指針が、公明党の価値判断の基準なのだと説明されます。創価学会はさまざまな社会階層の会員で構成されています。30万円給付が強行された場合、本来支援されるべき経済的弱者が「家」というセーフティネットに吸収されて、給付を受けられない可能性、また給付者に対する周囲の視線について、著者は「公明党は非常時に社会が分断されるような事態が起きることを危惧したのだと思います。しかも大衆に党の基盤を置く政党である以上、公明党は大きな政府路線を採ります。エリート中心の閉鎖空間にいる人たちの危機感とは質的に異なる民衆の皮膚感覚を体現する形で、公明党は与党にありながら、一旦決まった政策を動かしたのだと私は見ています」と述べています。
著者は、新型コロナが落ち着いて経済活動が再開されても、景気回復に時間がかかり、アンダークラスまでお金が回ってこなくなる可能性があることを指摘します。それでなくても一度アンダークラスに転落すると、上の階層に上がりにくくなるというのです。そして、「予想どおりアンダークラスが1000万人を超え、階層として一定の規模をもつと、独自の階層文化が生まれ、その文化の中にいる人々の間で再生産が始まるでしょう。そうなると、日本社会の分断が起きるかもしれません」と推測しています。
「ハラリモデルとトッドモデル」として、ニューノーマルの世界が新型コロナ禍前の世界と比べて、どのような世界になるのかについて、2人の学者の見解が紹介されます。両者ともに世界の論壇に影響力のある人物です。1人はイスラエルの歴史学者で、一条真也の読書館『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』で紹介した世界的ベストセラーの著者であるユヴァル・ノア・ハラリ氏です。〈新型コロナの嵐はやがて去り、人類は存続し、私たちの大部分もなお生きているだろう。だが、私たちこれまでとは違う世界に暮らすことになる〉(日本経済新聞電子版、2020年3月30日)というハラリ氏の発言を紹介し、著者は「ハラリ氏は、新型コロナ後の世界の状態を『抜本的な変化』と考えています。新型コロナ感染拡大防止を大義名分とした国家による市民監視を許すか否か。長時間の海外渡航禁止による国際社会の機能麻痺からどう脱却するかを、主な論点にしています」と説明します。
もう1人はフランスの人口学者で、『帝国以後』という世界的ベストセラーの著者であるエマニュエル・トッド氏です。〈新型コロナウイルスのパンデミックは歴史の流れを変えるのではない。すでに起きていたことを加速させ、その亀裂を露見させると考えるべきです〉(朝日新聞デジタル、2020年5月23日)というトッド氏の発言を紹介し、著者は「トッド氏は『すでに起きていた変化の加速』だといいます。グローバリズムの進展によって、すでに医療を含む公共性の高いインフラが『合理化』されていたこと、経済的な格差拡大が進んでいることなどを挙げ、新自由主義で生じた社会制度の脆弱性や矛盾を新型コロナウイルスに突かれたと捉えています」と説明します。
両者の言説は、どちらが正しいという性質のものではないとして、著者は「そもそも、新しいタイプの疫病の世界的拡大が人間社会にどんな影響を及ぼしたのかを巨視的に捉えることができるのは、事態が落ち着いた後から振り返って初めて見えてくるからです。2人の言説は、新型コロナ禍で起きた変化とニューノーマルという生活様式が私たちの仕事や暮らしに今後及ぼしうる影響と、こうした状況下でどのような思想を軸にして生きていくべきかを考える上で示唆に富んでいます。そのキーワードは、新自由主義、国家と市民、監視、格差、グローバルです」と述べるのでした。
第1章「リスクとクライシスの間で」では、イスラエルのネタニヤフ首相が、イスラエル公安庁に対して新型コロナの患者を追跡するために通常はテロリスト対策にしか使わない監視技術の利用を認めたことを取り上げ、著者は「イスラエルがそこまでして新型コロナウイルスの感染を防ごうとするのは、第2次世界大戦時のゲットーの記憶があるからだと思います。ユダヤ人の強制居住区域であるゲットーは、中世ヨーロッパに起源を持ち、20世紀に入って消滅していますが、ナチス・ドイツによって建設されたゲットーはその環境の劣悪さ、また、絶滅収容所移送までの一時的な居住地の役割も果たしていたという点において、かつてのゲットーの比ではありませんでした」と述べています。
たとえば、ポーランドに設けられた「ワルシャワ・ゲットー」という最大のゲットーでは栄養、衛生状態の悪さから発疹チフスが流行し、餓死者も含め約10万人のユダヤ人が命を落としたとされています。当時は満足な医療体制もなく、罹患者たちはバタバタと倒れていきました。著者は、「もし、新型コロナウイルスの感染が爆発的に広がると医療崩壊を招き、同じような事態が起きかねません。自国民に対する強権的な行動規制や個人情報の収集は、ゲットーでの悲劇を再び起こしてはならないという国家の強い意志の表れだと思います」と述べていますが、それに加えて、わたしはホロコーストで「人間の尊厳」が完全に失われた負の記憶が、新型コロナウイルスの感染対策を重視させているように思います。ホロコーストの犠牲者も、新型コロナ肺炎による死亡者も、人間らしい葬儀を行ってもらえないからです。葬儀は「人間の尊厳」に直結しているのです。
現時点では、新型コロナ禍が終息した後の世界は、すでに起きていることの加速、つまり変化に過ぎないのか、ハラリ氏が考える違った世界に暮らすことになるのかと問いかける著者は、「結論は出せません。私は今回の新型コロナ禍を、リスク以上、クライシス未満と考えていますから、いまのところ、トッド氏の見解に近い立場をとっています」と述べます。また、トッド氏のインタビューで興味深いと思った点が2つあるとして、「1つは、新型コロナ感染症対策が比較的うまくできた国と失敗した国とでは、国民の政府や政治エリートに対する信頼に差が生じると述べていることです。信頼が高まることが予想される国の例として韓国やドイツを挙げています。これらの国は歴史上、権威主義的な政治を経験した国だという共通点があることを指摘しています。日本も同じ権威主義の歴史がありますが、政治エリートに対する信頼が下がっていることを付け加えておきます」と述べます。
もう1点は、人口学者のトッド氏らしい視点だとして、著者は「興味深いというより、引っかかるものを感じたと言うほうが適切なのかもしれません。トッド氏は、新型コロナ禍が戦争だとは言えない理由を、自身の専門分野に立って展開しています」と述べ、トッド氏の〈私は人口学者ですから、まず数字で考えます。戦争やテロと今回の感染症を比較してみましょう。テロは、死者の数自体が問題ではありません。社会の根底的な価値を揺さぶることで衝撃を与えます。一方戦争は、死者数の多さ以上に、多くの若者が犠牲になることで社会の人口構成を変える。中長期的に大きな社会変動を引き起こします。今回のコロナはどちらでもありません〉という言葉を紹介します。
本来、高齢者よりも死ぬ確率が低い若者が多く亡くなったら、社会はどうなるか。著者は、「この世代は生産年齢人口として数えられます。つまり富を産み出す労働力の中心です。同時に、次世代を再生産する能力がある世代でもあります。若者が多く亡くなるということは、労働力と次世代の再生産力が失われるということです。こちらは明らかに『社会構造を決定づける人口動態に新しい変化』をもたらします。また、「今回のコロナの犠牲者は高齢者に集中しています。社会構造を決定づける人口動態に新しい変化をもたらすものではありません」というトッド氏の言葉の奥には、世代による命の価値の違いがあることが示唆されているとして、「スウェーデンでは新型コロナに対して、放置して集団免疫をつける方策をとりました。しかし、感染は拡大し続け、破綻しました。死者の90%は70歳以上の高齢者です」と述べています。
第3章「繰り返されるニューノーマル」では、「『自粛警察』という翼賛の手法」として、著者は「新型コロナウイルス対策の過程で、無意識のうちに翼賛という手法が強まっていると感じました。たとえば『自粛警察』がそれです。誰からも頼まれていないし、権限もないのに、自分の正義感から、新型コロナの感染を拡大させそうな人や店を攻撃する人々。公園で遊んでいる子どもたちを怒鳴る人々。咳をしただけで激昂する人々。県外ナンバー狩りをする人々。あるいは感染者ゼロの岩手県の達増拓也知事がコロナに感染した『第1号になっても県はその人を責めません』(朝日新聞デジタル、5月15日)と会見で言ったことの裏を返せば、岩手県で最初に感染した人は、プライバシーを晒され、激しく非難される危険性があり得ると考えたからでしょう。こうした自粛警察は、大政翼賛会の末端組織である隣組のようなものです。隣組は互助会組織であると同時に、お互いを牽制・監視する機能も果たしていました」と述べています。
また、「オーウェル『動物農場』の七戒」として、こうした自粛警察と肥大化する行政権の関係は、ジョージ・オーウェルの小説『動物農場』で説明できることを指摘し、著者は「イギリスの『荘園農場』の家畜たちは、自分たちをこき使い、搾り取れるだけ搾り取る農場主を追い出します。家畜たちは『動物農場』と名前を変え、七戒を掲げて民主的な農場を運営しはじめましたが、やがて、異論を許さない全体主義的な運営へと変わっていくという、示唆に富んだ小説です」と説明。さらに、自粛警察の「状況はよくわからないが、営業を続ける店は悪だ!」的な正義感、あるいは無自覚な「翼賛」は、権力に利用され、気づかないうちに自分たちもまた支配される者になるとして、「お前たちは支配され服従することで幸せになれる、という構造です。その構造はさらに強い同調圧力となり、翼賛体制は廃れることはなく、社会はさらに息苦しいものになっていくわけです。ニューノーマルの行き着く先が『動物農場』では困ります」と述べています。
第5章「コロナ下に起きた安全保障の異変」では、「人と距離を置くことが招く事態」として、東日本大震災の後、「絆」という言葉が叫ばれ、人と人とがつながることが呼びかけられたが、新型コロナ禍では、逆に人と距離を置くことが求められていることを指摘し、著者は「バラバラになった個人は必然的に内向きになり、関心が自分とその周辺に集まりがちです。一方で、私たちの暮らしを担保し続けてきた安全保障環境に変化が起きつつあることや、そのために噴き出した矛盾に関心が向かない――このような現状に私は強い危機感をおぼえています」と述べるのでした。わたしも、まったく同感です。
「あとがき」では、著者は、政治的にもっとも気をつけなくてはならない構造悪は民主主義(デモクラシー)の形骸化であると述べます。それについてドイツの社会哲学者ユルゲン・ハーバーマスの考察が優れているとして、以下の文章を引用しています。
〈デモクラシーはもはや、あらゆる個人の普遍化可能な利益を認めさせようとする生活形式の内容によって規定されてはいない。それは、もっぱらたんに指導者と指導部を選抜するための方法とみなされている。デモクラシーはもはや、あらゆる正統な利益が自己決定と参加への基本的な関心の実現という道を通って満たされうるための条件という意味では理解されていない。それはいまやシステム適合的な補償のための分配率、すなわち私的利益を充足するための調節器ということでしかない。このデモクラシーによって自由なき福祉が可能となる。デモクラシーはもはや政治権力の平等な分配、いいかえれば権力を行使する機会の平等な分配という意味での政治的平等と結びついていない〉(ユルゲン・ハーバーマス〔山田正行/金慧訳〕『後期資本主義における正統化の問題』岩波文庫、2018年)
新型コロナウイルス対策の過程で国家機能が強まっていることを、著者は本書で繰り返し指摘しました。国家機能の内部では、司法権と立法権に対して行政権が優位になっているとして、著者は「行政府の自粛要請に応じて、危機を克服するというアプローチが所与の条件下ではもっとも合理的であることは事実だ。しかし、この日本型の解決策は、ハーバーマスが指摘する『自由なき福祉』そのものだ」と述べるのでした。ハーバーマスの発言を最後に引用するところは、読書家の著者らしいなと思いました。新型コロナウイルスに関連して、著者は何冊かの著書を出していますが、ざっと読んだところ、本書が最も最新の情報が反映されていて、ニューノーマルに対する考えがまとまっている印象がありました。
