- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.01.11
『令和の「論語と算盤」』加地伸行著(産経新聞出版)を読みました。わが儒教の師である著者は1936年生まれ、京都大学文学部卒業。高野山大学・名古屋大学・大阪大学・同志社大学・立命館大学を歴任。現在、大阪大学名誉教授。文学博士。中国哲学史・中国古典学専攻。著書(編著などを除く)に「加地伸行(研究)著作集」三巻として『中国論理学史研究』『日本思想史研究』『孝研究』ならびに『中国学の散歩道』(研文出版)、『儒教とは何か』『現代中国学』『「論語」再説』『「史記」再説』『大人のための儒教塾』(中央公論新社)、『沈黙の宗教――儒教』『中国人の論理学』(筑摩書房)、『論語 全訳注』『孝経 全訳注』『論語のこころ』『漢文法基礎』(講談社)、『論語』『孔子』『中国古典の言葉』(角川書店)、『家族の思想』『〈教養〉は死んだか』(PHP研究所)などがあります。
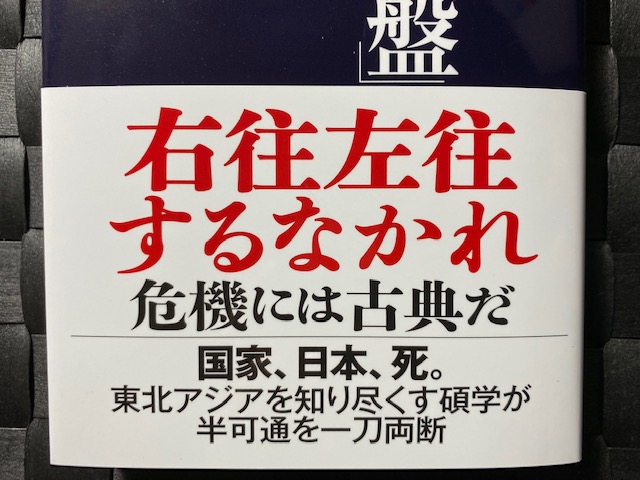 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「右往左往するなかれ」と大書され、「危機には古典だ」「国家、日本、死。」「東北アジアを知り尽くす碩学が半可通を一刀両断」と書かれています。また帯の裏には「”『論語』述而に曰く、……必ずや事(こと)に臨んで懼(おそ)れ[慎重に]、謀(はかりごと)を好んで而(しか)して成(な)す者たれ、と”」「日本人が知っておきたい根本」「不確定の時代を生き抜くための知恵と古典の教えが満載」と書かれています。
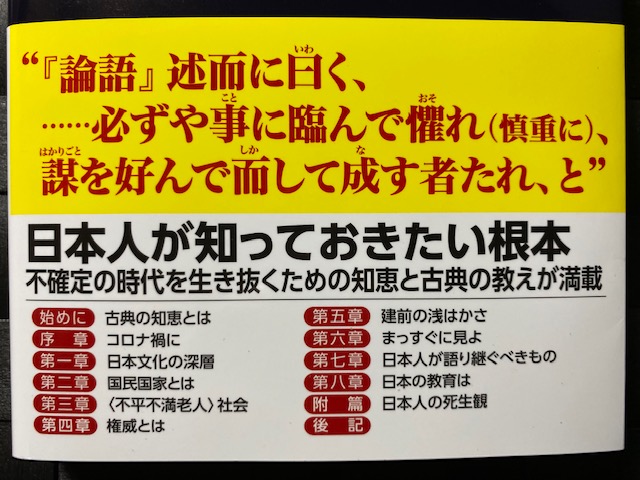 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
始めに──古典の知恵とは
序章 コロナ禍に
第一章 日本文化の深層
第二章 国民国家とは
第三章 〈不平不満老人〉社会
第四章 権威とは
第五章 建前の浅はかさ
第六章 まっすぐに見よ
第七章 日本人が語り継ぐべきもの
第八章 日本の教育は
附篇 日本人の死生観
後記
「始めに──古典の知恵とは」で、著者は以下のように述べています。
「『論語』述而にこうある。『述べて作らず、信じて古を好む』と。その意味は、私(孔子)は、〔古典・古制・古道について〕祖述しはするが、創作はしない。すなわち〈古代のすぐれた人たちのことば・考えを、信じ、彼らによって表されている〈古典・古制・古道が好きである〉と。つまり、自分がなにか或ることについて論じるとき、自分の考えをただ主張するのではなくて、古典を拠りどころにして、その主張の締めとして、その主張に該当する古典のことばを探し求め、その古典のことばを引用して記すという形を採ることとなる。そういう文章を読む人は、文中に引用された古典の文と出合うこととなり、ああ、これは『論語』だなとか、あ、これは『春秋左氏伝』だなとか、おう、これは『礼記』だな……と楽しんで読むことになるのである。こうした引用をする文章を読んで楽しむのが東北アジア文化圏の人々の〈教養〉であった。いわば、文章に埋め込まれた古典探しゲームのような遊びであった。この形は、もちろん日本や朝鮮半島等の教養人においても受け継がれていった。自分が書く文章に古典を埋め込んで引用するのが、すぐれた文章であったのである」
第一章「日本文化の深層」の「元号『令和』の出典」では、新元号である「令和」の出典が『万葉集』の或る〈序〉からと公表されたものの、その序は中国の『文選』中の帰田賦(きでんのふ)を踏んでいるので『文選』を出典とすべしという意見が妥当であるとした上で、令和は『万葉集』を出典とし、同箇所は『文選』を出典とし、それはさらに経書の『儀礼』『周礼』などを出典とするという話になってゆく。というような理屈を捏ねるのが、老生ら中国哲学・中国古典学者であるから、世人から嫌われるのも、宜なるかな」と述べています。
「全国戦没者追悼式は宗教行為」では、主催者の政府が〈祭〉の意味を知らずに書き誤っているとして、著者は「すなわち、いくら『全国戦没者之霊』と書いた柱を立ててる、式典会場の日本武道館にその神霊は存在していない。式典において、われわれが誠を尽くして諸霊をお招きし、それに感応された全国戦没者万霊が天上から地上に降り立たれる。その諸霊が憑りつかれる場所(依り代)として設営されたのが祭壇中央の柱なのである。霊魂の在す場所なのである。だから場所を表す『位』字が必要。正しくは『全国戦没者之霊位』と書くべきである。この依り代は、儒教における木主(神主)であり、日本仏教はそれを導入して位牌と称している」と述べています。まったく、その通りだと思います。
また、著者は、「人間の死後、その霊魂の存在を認め、生者遺族がその霊魂を招き降して出会い、慰霊鎮魂をする〈祭〉が、東北アジアの死生観の具体的行為であり、その本質はシャマニズムである」と述べています。著者いわく、この〈祭〉は歴とした宗教行為です。つまり、全国戦没者追悼式は政府主催の宗教行為そのものの〈国祭〉なのだとして、「霊魂の存在を認めること自体が宗教であることが分からぬのか。多くの日本人は、主として日本仏教を通じて、幼少のころから慰霊鎮魂の場に接し、誠を尽くすことを心得ている。仏壇の前での日々のお勤めがそれにつながっている。そういう国民的宗教心があってこそ全国戦没者追悼式が国民に支持されていることを、政府とりわけ保守政権は確と胸に刻むことだ。われわれ日本人は諸霊に対して粛然と襟を正し、慰霊する」と述べます。
「土葬の正統性を知らぬ社説」では、東日本大震災で、身元確認が困難な遺体を埋葬する必要がありましたが、そのことを「毎日新聞」が「火葬を望む遺族感情」として揶揄したことに対して、著者は「私は目を疑った」として、「結論だけを言おう。(1)儒教文化圏(日本・朝鮮半島・中国など)では、土葬が正統である。それは儒教的死生観に基づいている。(2)火葬はインド宗教(インド仏教も含む)の死生観に基づいて行われ、火で遺体を焼却した後、その遺骨を例えばガンジス川に捨てる。日本で最近唱えられている散骨とやらは、その猿まねである。(3)日本の法律で言う『火葬』は遺体処理の方法を意味するだけ。すなわち遺体を焼却せよという意味。その焼却後、日本では遺骨を集めて〈土葬〉する。つまり、日本では(a)遺体をそのまま埋める〈遺体土葬〉か、(b)遺体を焼却した後、遺骨を埋める〈遺骨土葬〉か、そのどちらかを行うのであり、ともに土葬である。(4)正統的には(a)、最近では(b)ということ。(b)は平安時代にすでに始まるが、一般的ではなく最近ここ50年来普及したまでのことである」と喝破していますが、これは痛快でした。まさに、その通りです。
「二十年ごとの新造と千年にわたる墨守と」では、平成25年(2013年)の伊勢神宮の式年遷宮について、著者は「式年遷宮に真剣に関わるのは、大工も参列者も生涯にただ一度という厳粛さに大きな意味があるからではなかろうか。一方、法隆寺。式年遷宮の始まりよりは少し前に建立されてから約1400年、火災は別として、ずっとそのままである。これまた凄い話。古き良きものを守り続けているのは、日本人の底力である。20年ごとの新造と1000年以上もの墨守との両者には、正反対のものを併せ持ってゆく日本人のしたたかさがある。新造―宋代の王安石曰く、変を尚ぶは天道なり(「河図洛書義」)、と。墨守―明代の王廷相曰く、千古を閲して(経て)変はらざる者は、気種(物の素)の定まる有ればなり(『慎言』)、と」と述べています。
「日本国憲法――抑止力なき個人主義」では、児童虐待で幼い命を落とした子どもたちについて、著者は「私ども老夫婦は、家の仏壇にこの子たちの紙牓(紙位牌)を立て、涙ながらに供養をし続けている。真言宗信者の作法に従い、般若心経一巻、光明真言をはじめとして諸真言を誦し奉る。わけても、地蔵菩薩の御真言『おんかかかびさんまえいそわか』――それは声にならなかった。幸薄く去ってゆくあの子たちに対して、この老夫婦ができることは、ひたすら菩提を弔い、供養を続けるほかない。私どもになにができようか」と述べています。わたしは、これを読んだとき非常に感動しました。そして、縁もゆかりもない気の毒な子どもたちにそこまでの情けをかけ、誠を捧げられる著者ご夫妻に心からの尊敬の念を抱きました。
日本に蔓延する個人主義について、著者は「欧米人が個人主義教育を可能にし実現してきたのは、ともすれば個人主義の自律からはずれようとする人間に対して、それを許さぬ抑止力として、唯一最高絶対神を置いていたからである。キリスト教がその典型。もちろん欧米人に無宗教者はいる。それらの人は当然に利己主義者となる。一方、われわれには個人主義という思想はなかったが、東北アジア流に自律してきた。それが可能であったのは、われわれ凡人への抑止力として、それぞれの祖先を置いたからである。『御先祖さまが許さぬ』という、われわれの抑止力は、かつては生きていたのである」と述べています。
さらに、著者は「自己の祖先を祭り〈生命の連続〉を実感しつつ生きてゆくこと、それは儒教的な死生観なのであるが、今日では、日本仏教の中に融合されている。戦後教育においては、祖先という抑止力を教えてこなかったため、抑止力なき個人主義教育からは、ただ利己主義者を生み出すのみとなった。そういう利己主義者が頼るのは金銭だけである。当然、祖先も、祖先以来の生命の連続の大切さ、厳粛さも分からない。ひたすら求めるのは日本国憲法の『婚姻は両性の合意のみに基づく』夫婦の幸せだけであり、子を虐待し〈殺人〉して恥じぬ人間の屑を生んできたのだ」とも述べます。
拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)で、わたしは以下のように書きました。
「わたしたちは、先祖、そして子孫という連続性の中で生きている存在です。遠い過去の先祖、遠い未来の子孫、その大きな河の流れの『あいだ』に漂うもの、それが現在のわたしたちにほかなりません。その流れを意識したとき、何かの行動に取り掛かる際、またその行動によって自分の良心がとがめるような場合、わたしたちは次のように考えるのです。『こんなことをすれば、ご先祖様に対して恥ずかしい』『これをやってしまったら、子孫が困るかもしれない』こういった先祖や子孫に対する『恥』や『責任』の意識が日本人の心の中にずっと生き続けてきました」
日本人は、欧米流の個人主義の外見だけを真似て、先祖という縦糸を視野に入れた価値観を忘れてしまいました。ぜひ、もう一度、大いなる「いのち」の連続性を思い出すべきであると思います。
第二章「国民国家とは」では、文部科学省が東日本大震災の被災地における私費留学生に対して、国費留学生なみに、3月の1ヵ月分(学部学生に12万5000円)を奨学金として支給することにしましたが、なんと台湾からの学部留学生は除外しました。このことについて、著者は「渡台後の生活において、公私ともになんの差別も受けなかった。のみならず、台湾の学者と私との間の合言葉は、『国家に国境あるも、学問に国境なし』であった。お蔭で、希望すれば、貴重な文献を自由に閲覧することができた。例えば、四庫全書という、清王朝における最大の国家的企画である巨大叢書(1781年完成)の原本(4セットの内の一つを台湾が所有・管理)を披見したとき、ぱーっと墨の香りが漂った。墨に依る写本だからである。その瞬間、まさに日中両国の〈筆硯の縁〉に感動した」と述べ、「学問に国境はない」ことを強く訴えています。
第三章「〈不平・不満老人〉社会」の「家族主義を教えない悲劇」では、山中伸弥・京大教授と老生との対談がBSフジにおいて放映された。(収録は28年1月18日)そのテーマとは、細胞の本質と儒教の根源とが、〈生命の連続〉を求めるという点で一致する不思議さについてが中心であった。併せて教育論も」として、その内容が以下のように紹介されています。
「細胞には、遺伝子を中心として、分化し展開してゆく設計図がすでに存在している。それは、生き続けるという生命の本質であり、細胞から成り立つ身体が老いてゆくと、次の新しい身体に乗りかえ乗りかえして連続して生きてゆく。その本質は〈生命の連続〉である。すなわち、細胞研究とは〈生命の連続〉の研究なのである」
一方、儒教について言えば、「〔己れの〕身は父母の遺体なり」(『礼記』祭義)という観念があるとして、著者は「『身』とは、『自分の身体』という意味。『遺体』とは、古くからある儒教のことばで、『遺した体』という意味。現代では、『遺体』は死体の丁寧な表現であるが、それは本来の意味すなわち『自分の身体は父母が遺した身体』という意味とずれて使われている。その元来の〈遺体〉観に基づき、儒教は、祖先から自己までの〈生命の連続〉を強烈に意識し、それを思想化してゆき、祖先崇拝という宗教化ともなっていったのである。これが儒教の本質なのである。そして地域的には、東北アジア(中国・朝鮮・日本・ベトナム北部等)に広がっていった」と述べています。
第五章「建前の浅はかさ」の「テレビコメンテーターはふわふわ分子」では、世論なるものは、ふわふわと浮き漂っているものであり、60年安保闘争で騒がしく、学生運動が盛んに時期にそれが顕著であったとして、著者はそれから60年を経たが、事情に変わりはない。世はふわふわ分子の海である。しかし、異なる点がある。今の人は集合するということをしなくなってきている。現代の大学では学生の集合など見かけない。集まっているとすれば、ライブショーだの講演会だのであって、集合の意味が違う。今の学生は、個か孤か知らんが、集まりはしない。けれど、大半は昔と同じくミーハーふわふわである」と述べています。
第六章「まっすぐに見よ」の「あふれる利己主義者」では、就職活動における学生の非礼を取り上げ、著者は「もし、会社から採用内定の通知が届いたならば、ただちに就職する会社を決め、そこへお礼と入社後はがんばりますという返事を出す。そして第二、第三の内定通知は、すぐさま辞退の返事をすべきである。にもかかわらず、内定通知が来たあと、順番に承諾の返事を出し、その3社の内、どれを選ぶか、じっくり考えると言う。と言うことは、3社の内、2社は採用計画が狂うのみならず、その2社に採用される可能性のあった学生の就職機会を奪ったことになる。そんな勝手極まる学生は、採用しても、ものの役に立たない。単なる利己主義者を雇うことになるだけではないか」と述べています。
また、自己の内定数を3とか5とかと誇るのは、人間としての資質に欠けるところがあるとして、著者は「つまりは、大学教育を受けたとしても、道徳性を高められなかったということだ。そうなると、教育の問題というよりも、その人間自身の持つ欠陥の問題であろう。そういう欠陥例の最たるものは、子の虐待死という行為である若者男女がくっついて同棲。やがて子が生まれると男はどこかへ逃げだす。女は再びつまらぬ男とくっつき、今度は己の実子を男とともに虐待して殺す。男は二人とも無職で、女の収入あるいは女の生活保護費にぶら下がる最低の連中。これは、己だけが幸せになればいいとする利己主義そのものである。のみならず、反省とか悔恨といった謙虚さなどまったくない。その実例が最近あった」と述べます。
第七章「日本人が語り継ぐべきもの」の「日本の皇室と中国の皇帝と」では、著者は「天皇には、少なくとも室町時代以降、権力がなかった。一方、中国皇帝には権力があったので、それを奪おうとする者が現れる。これが日中両国の歴史や人間の在りかたの大きな差となってくる。すなわち、日本では、権力の交替があっても、天皇の権威は奪われず常に権力の上に立ってきた。中国では、王朝の交替とは権威・権力の両方を奪うことであった。今日、世界の正常な国では、政権(権威・権力)は民主主義すなわち選挙方式によって承認される。だから、選挙結果によって権威・権力を失うことがある。そのとき、一種の不安定な政情となる。しかし、わが国はそうではない。わが国の政権には、権力はあるが権威はない。首相は権力者ではあるものの、権威は皇室に在る」と述べています。
また、現代日本人はどの首相に対しても敬意を払わないことを指摘し、著者は「首相に権威を認めていないからである。だから、首相がいくら交替しても、皇室の権威は不動であるので国家として不安定とならない。これがわが国の底力となっている。わが国はどのような危機に際しても、皇室の権威の不動によって政治が安定しており、必ず立ち直ることができたのである。それはこれからもそうであろうし、またそうでなくてはならない」と述べます。まったく同感です。
「皇室無謬派と皇室マイホーム派と」では、皇室無謬派こそ皇室を誤らせるとして、著者は「歴代の皇室では皇族の学問初めの教科書には『論語』と並んで、いやそれ以上に儒教の『孝経』を選ぶことが圧倒的に多かった。なぜか。『孝経』は、もちろん孝について、延いては忠について教えることが大目的であるが、もう一つ目的があった。それは臣下の諫言を受け入れることを述べる諫諍章(『孝経』第十五章)を教えることである。皇室は無謬ではない。諫言を受容してこそ安泰である。そのことを、皇室の方々は、幼少より学問の初めとして『孝経』に依って学ばれたのである。諫言――皇室はそれを理解されよ」と述べています。
また、折口信夫は、天皇の本質を美事に掴み出しているとして、著者は「すなわち、歴代の御製を拝読すると、中身がなにもないと言う。例えば『思ふこと今はなきかな撫子の花咲くばかり成りぬと思へば』(花山天皇)。このような和歌は庶民には絶対に作れない。庶民は個性を出そうとするが、天皇は個性を消し去る。それは〈無〉の世界なのである(折口説の出典名を失念、読者諸氏許されよ)」と述べています。しかしながら、この御製(出典:『後拾遺和歌集』)は、自らの息子たちの安泰を安堵した内容と解釈することが一般的であり、ある種、個性の塊ということが出来るのではないかとも思います。わが師の解釈に異を唱えるわけではありませんが、違った見方もできるように思われます。
それはともかく、折口の天才的文学感覚は御製の性格を通じて、〈無〉という天皇の本質を的確に示しているとして、著者は「〈有〉の世界にいるわれわれ庶民は、やれ個性の、やれゼニカネの、やれ自由の、やれ人権の、などと事・物の雁字搦めになっている。そして〈有〉のマイホーム生活を至福としている。皇室は〈無〉の世界に生きる。それを幼少からの教育によって培い、マイホーム生活と絶縁するのである。なお、皇室を神道の大本とするという論は一面的である。皇室は同時に日本仏教とも深く関わるからである。京都の泉涌寺に安置されている歴代天皇の位牌は仏教者であることを示す。皇族は、神道・日本仏教さらには儒教に深く関わり、東北アジア諸文化を体現する。日本の核にして〈無〉である以上、可能な限り、皇居奥深くに在され、やれ国際学会の、やれ国連なんとかの開会式などといった庶民のイベントにはお出ましにならないことである。これは、草莽の老骨の切なる諫言である」と述べるのでした。
「靖国神社――古代からの慰霊鎮魂」では、著者は「私はここに靖国神社に対して新しい1つの提案をいたしたい」と述べます。それは、日本人の心に沿ったありかたとしてであるといいます。その提案とは、靖国神社の現行の春秋二例大祭の他に、8月15日に夏季特別大祭を新しく設けるというもので、著者は「靖国神社拝殿に向かって左に、鎮霊社という小さな社がひっそりと建っている。昭和40年の創建で、靖国神社に合祀されていない日本人神霊(例えば西郷隆盛)や全世界の戦死者・戦禍犠牲者(例えば湾岸戦争関係者)の神霊がそこに祀られている。その諸霊を英霊とともに新設の夏季特別大祭において降神して祭神とし、慰霊鎮魂の誠を尽くしていただきたいのである」と述べています。わたしも、この提案に大賛成です。
われわれ日本人は、慰霊鎮魂を古代から行ってきました。敵への怨みも味方への親しみも越え、「怨親平等に回向する」のがわれわれ日本人であるとして、著者は「そうした心のままに、8月15日の靖国神社(全国の護国神社)夏季特別大祭に参拝しよう。この拙稿を記しつつある折しも、盂蘭盆の期間であり、人々は祖霊と有縁無縁一切精霊とに回向するときではないか。これは日本人の国民的心情である。それに基づけば、日本国を代表する首相であるならば、おのずと主体的に参拝することとなるであろう」と述べます。さらには、「主体的なのであるから、靖国神社問題を政策カードぐらいにしか思っていない外国勢力に右顧左眄することはない。いや、首相だけではない。両陛下もまた日本人の心情、『怨親平等』を深く確と理解しておられるはずである。『すべての戦死者のために、平和のために祈る』ことを靖国神社が具体的に積極的に示されんことを願ってやまない」と述べるのでした。
附篇「日本人の死生観」では、「一神教と多神教と」として、著者は「宗教では、人間の何万年という歴史の中で、いろいろなものが出ては消え、消えては現れて……といった長い歴史がある。その中で、今日にまで生き残っている世界的なものは、一神教とインドの諸宗教と、そして儒教の3宗教だけである」と述べています。これを断言することは大胆なようにも思えますが、なるほど、言われてみればその通りであることがわかります。宗教とは、とりもなおさず「死」を説明するものです。「儒教文化圏の〈死〉」として、著者は「遠い時代では、亡くなった方の頭蓋骨を家廟・祠堂(一族の慰霊安所)に納めておき、命日にそれを取り出してだいたいは孫がかぶった。その姿が(鬼)。明け方の暗い中で音楽を演奏して香を焚き、亡き人の魂を呼び、酒を撒いて魄を呼び、荘重な慰霊の文章を読み上げる。すると魂魄が帰ってくる」と述べています。
魂魄が帰ってくる場所とは、魂魄の依りつく形代(場所)です。やがて帰ってきた魂魄が形代に取りつき、亡き人の頭蓋骨をかぶった人(形代)が両手両足を動かして狂乱状態になるのですが、それが文字で残っています。すなわち異常の「異」であり、この状態になると故人が帰ってきたというわけです。著者は、「これが慰霊の根本的意味である。葬儀は家族が死者の思い出と共に皆と会う儀式である。インド仏教には祖先の霊を戻す儀式はない。お盆やお彼岸はインド仏教にはない。しかし、中国仏教・日本仏教は、インド仏教と異なり、お盆・お彼岸・先祖供養を取り入れていったので、儒教儀礼の色が非常に濃い」と述べています。
さらに、「儒教の本質は〈生命の連続〉」として、「頭蓋骨を使った儀式は気持ちが悪いこともあり、頭蓋骨に代わるものができた。それが木製の位牌である。位牌の上部は丸く削ってあるが、それは頭蓋骨の形の名残である。何万年も前から慰霊の儀式を行い、今も位牌を祀っている理由は、亡き人がこの世のその位牌に帰って依りつくことを信じているからである。真心を尽くして呼べば、亡き人(魂魄、霊魂)が帰ってくるとする慰霊の祭祀なのである。これらが〈死〉についての儒教の説明である」と述べます。なんという、わかりやすい説明でしょうか!
そして、著者は「昔は結婚式や葬儀に親戚一統が集まり、家族(一族)主義はついこの間までの日本にあった。お葬式のときは、遠くにいる親戚にも呼び掛けるべきなのである私の友人の話では、親戚が亡くなったので遠い郷里のお葬式に帰ったら、葬儀の日に、初七日も四十九日もするという。葬儀と同じ日においてである。次に会うのが大変だからと最近多いとのこと。そんなご都合主義を言ったらいけない。面倒でも一周忌にお呼びする、三回忌にお呼びする、そういう努力があってこそ親戚が仲良くなっていくのではないか。家族といった繋がりが消えてしまったら、これからの日本はどうなるのか。おそらく、単なる利己主義集団となってゆくことであろう。その利己主義を否定するために、個人主義あるいは宗族(一族)主義が生まれてきた歴史性を知らぬ愚かな〈現代化〉である」と述べるのでした。
わたしは冠婚葬祭業を営んでいますが、結婚式にしろ、葬儀にしろ、人の縁がなければ成り立たない商売です。わたしは常々、この仕事にもしインフラがあるとしたら、それは人の縁に他ならないと広言しています。「無縁社会」などと呼ばれている日本を、「有縁社会」へと変えなければなりません。特に、血縁を結び直す「法事」とは、先祖との交流の場です。わたしはそれを日常生活の中に持ち込みたいと思っています。それが「先祖とくらす」ということです。「先祖とくらす」文化の体系が「冠婚葬祭」です。
 加地伸行先生と
加地伸行先生と
わたしは、著者と現代社会のさまざまな問題について、よく1時間以上も電話で話すのですが、今年は直接お会いして、対談本を作ることになりました。まことに不遜ではありますが、日本最高の儒教研究の権威である加地先生と、ぜひ「冠婚葬祭」の意味や重要性について意見交換をさせていただきたいと願っています。
