- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.02.04
『操作される現実』サミュエル・ウーリー著、小林啓倫訳(白揚社)を読みました。「VR・合成音声・ディープフェイクが生む虚構のプロパガンダ」というサブタイトルがついています。著者はAIや政治、ソーシャルメディアを専門とする研究者兼著述家。テキサス大学オースティン校のジャーナリズム・スクール助教およびメディア・エンゲージメント・センターのプログラムディレクターを務めています。政治的操作のテクノロジーについて、ワイアード誌、ガーディアン紙、スレート誌などさまざまなメディアに寄稿。研究成果は、ニューヨークタイムズ紙、ワシントンポスト紙、ウォールストリートジャーナル紙などでも取り上げられているそうです。
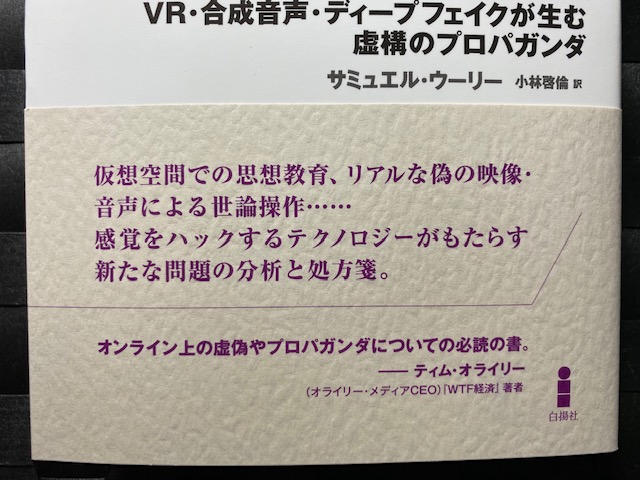 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「仮想空間での思想教育、リアルな偽の映像・音声による世論操作……感覚をハックするテクノロジーがもたらす新たな問題の分析と処方箋」「オンライン上の虚偽やプロパガンダについての必読の書。――ティム・オライリー(オライリー・メディアCEO、『WTF経済』著者)」と書かれています。
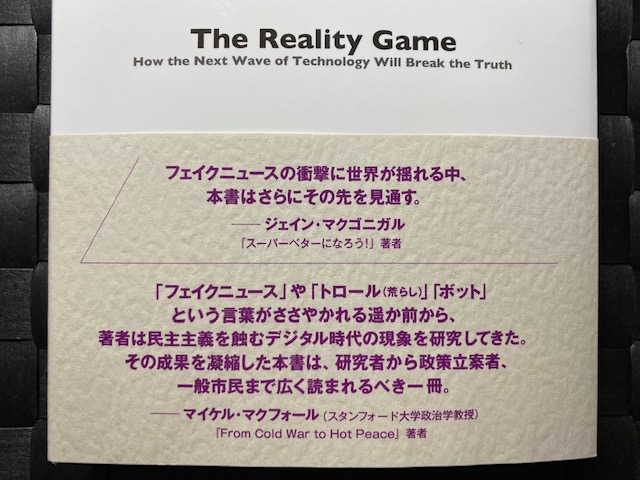 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「フェイクニュースの衝撃に世界が揺れる中、本書はさらにその先を見通す。――ジェイン・マクゴニガル(『スーパーベターになろう!』著者)」、「『フェイクニュース』や『トロール(荒らし)』『ボット』という言葉がささやかれる遥か前から、著者は民主主義を蝕むデジタル時代の現象を研究してきた。その成果を凝縮した本書は、研究者から政策立案者、一般市民まで広く読まれるべき一冊――マイケル・マクフォール(スタンフォード大学政治学教授、『From Cold War to Hot Peace』著者)」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「謝辞」
「はじめに」
1 曖昧な真実
2 真実の破壊――過去・現在・未来
3 批判的思考から陰謀論へ
4 人工知能――救いか破滅か
5 フェイクビデオ――まだディープではない
6 XRメディア
7 テクノロジーの人間らしさを保つ
8 結論――人権に基づいたテクノロジーの設計
「訳者あとがき」
「参考文献」
「索引」
「はじめに」の冒頭は、以下の通りです。
「『フェイクニュース』という概念が世界中に広まったのは、2016年の米大統領選挙期間中、明らかに間違ったニュースが大量に出回り、デジタル世界がゴミのようなコンテンツであふれた後のことである。リオ五輪の期間中には、ロシア選手団に対する中傷キャンペーンの噂が広がり、またジカ熱に関する誤報がブラジルやその他の地域に拡散して、『フェイクニュース』の影はさらに拡大した。『フェイクニュース』という言葉は、あろうことか時の権力者たちに取り込まれてしまった。すると、フェイクニュースと呼ばれるジャンクコンテンツを制作している人々自身が、この言葉を取り戻し、正統なジャーナリズムを弱体化させる手段、あるいは都合の悪い科学的発見を攻撃するとっかかり、あるいは自分たちの悪事に関する事実をひっくり返す手段として使うようになったのである。『フェイクニュース』という言葉自体が、フェイクニュースを広める道具となってしまったのだ」
1「曖昧な真実」では、「プロパガンダからコンピューター・プロパガンダへ」として、プロパガンダ自体は昔からあった話だと指摘し、著者は「人々が何を、どう考えるかを操作するという発想は、少なくとも古代ギリシャから存在している。ギリシャ神話や神々のイメージ(オリンポスの山頂に座って天候を支配し、不届きな人間に雷を落とすゼウスなど)が、壮大な政治的主張をしたり、王朝に正統性を与えたりするために利用された。最近の紛争や現代史における多くの選挙では、プロパガンダが人々の行動や信念の形成に重要な役割を果たしている。冷戦時代には、米国とロシアの間で記憶に残るプロパガンダの応酬が行われた。航空機とチラシを使ったプロパガンダ(敵国で政府を疑わずに生活している市民をターゲットに、彼らを説得するような情報を載せたチラシを作り、それを航空機からばら撒くというもの)は、第一次世界大戦にまで遡る心理的プロパガンダの一つであり、戦争で荒廃した地域において今日も採用されている(たとえばシリアなど)」と述べています。
ある意味で、わたしたちは今日、冷戦時代のプロパガンダ戦略が強力なテクノロジーによって増幅されたものを経験しているものの、コンピューター・プロパガンダが持つ、過去のプロパガンダとははっきり異なる側面を明確にしておくことが重要であるとして、著者は「それは、戦争の戦術として始まったものが、隣の家に住んでいてもおかしくないような一般人までが使う、政治的なコミュニケーションの手段になったこと。そして、何より明らかなのは、この情報操作の新しい手段は自動化でき、また完全に匿名で行える場合も多いということだ」と述べます。
2「真実の破壊――過去・現在・未来」では、「メディアの崩壊」として、フェイスブックやユーチューブといったサイトの急速な台頭は、そのシステムの設計上の欠陥によって、わたしたちの情報収集のやり方を劣化させていただけでなかったことを指摘し、著者は「これらのサイトは、自らのメディア機能を旧式の報道に替わるより良いものとして提示することで、伝統的なニュースメディアの役割を奪っていたのである。そうしたことを、ソーシャルメディア企業は大っぴらに、または人知れず行っているが、それは、新聞や雑誌、テレビ局が生み出した『トレンドな』素材を再投稿したり作成したりするだけで達成されている。その結果テクノロジー企業は、他の組織が制作した正式なニュースや報道コンテンツを使って、広告収入を得るようになっている」と述べています。
フェイスブックやツイッターは、ヤフーのような組織と異なり、独自のニュースは制作しませんが、自社サイト上のどこに他社の記事が表示されるのか、いつ表示されるのか、どのように表示されるのかをコントロールしているのは確かだとして、著者は「彼らはこの仕組みを示して、自分たちはメディア企業ではない(前述の通り「真実の裁定者」ではない)という従来の主張を強調し、自分たちはAT&Tのようなテクノロジー企業やサービスプロバイダーに過ぎないとほのめかしているが、この不誠実な主張は真実ではない。フェイスブックやツイッターはジャーナリストを雇ったり、独自のコンテンツを書いたりしてはいないのは事実である一方で、彼らのアルゴリズムと従業員は、毎日20億人以上が見たり吸収したりするニュースの種類を確実に制限し、コントロールしているのである。彼らは情報を制御し、それによって真実を裁定する。昔のニュースメディア同様、ソーシャルメディア企業は、私たちが『何を見るか』『どう見るか』を決定する。彼らは私たちが触れるニュースを、独自の方法で構築しているのだ」と述べます。
3「批判的思考から陰謀論へ」では、フェイスブックとユーチューブは2000年代からニュースの世界に手を出しているが、それには思慮が欠けていたとして、著者は「彼らは人々に大規模なデータへのアクセスを提供し、広大なソーシャルネットワークへの接続を可能にする刺激的な製品を作った。しかし彼らは、自分たちのシステムが情報にアクセスするための、つまりニュースにアクセスするためのデフォルトの手段になるとは考えていなかった。それから10年後、コンピューター・プロパガンダとジャンクニュースが世界に突如として登場したことで、彼らは自分たちがパンドラの箱を開けてしまったことに気づいた。彼らは自社の不透明なアルゴリズムが、天気予報からニュース速報に至るまであらゆる情報を収集し、整理・統合しているという単純な事実に取り組まなければならなくなった。彼らは他のオンライン情報も独占することで、広告をベースとしたビジネスモデルに革命を起こし(監視資本主義を基盤に、ユーザーの行動に関する膨大なデータによって駆動するモデルを確立し)、それを独占することとなった」と述べています。
また、「ソーシャルメディアはメッセージ」として、著者は以下のように述べています。
「政治、インターネット、テクノロジーの研究に集中している者として、私は答えをメディアに求めている。世界の大部分の地域において、メディアの利用方法は1973年と比べて大きく変化している。当時、人々はいくつかの主要なテレビネットワーク、ラジオ、地元の新聞、そしておそらくは全国紙を頼りにして、時事問題や世界に関する情報を得ていた。しかしインターネットによって状況は一変した。突如として、誰もがコンテンツを作成できるようになり、誰もがそのニュースについてブログを書けるようになった。しかし中国などの権威主義国家では、インターネットは最初から、厳しい統制下に置かれている。デジタル政治の専門家であるシャンティ・カラティルとテイラー・ボアズは、多くの政権がウェブへのアクセスを制限し、国内での利用を事細かに監視することで、それが持つ情報共有力を抑制しようとしてきたことをはっきりと証明している。彼らは『インターネットの[部分的]利用は権威主義的支配を強化し、多くの権威主義的政権では、国の考える利益に対抗するのではなく、それに奉仕するようなインターネットの開発が積極的に進められている』と指摘する」
インターネットは、想像を絶する厚さと複雑さで積み重なったプログラムの層によって覆い隠されているとして、著者は「ソフトとハードで構成されたこの難解なシステムを理解するには、多種多様なプログラミング言語に精通するだけでなく、入り組んだガバナンスの体系を理解する能力も求められる。そのため、このシステムを解読する能力と資源を持つ人々がネットをコントロールする力の大半を握っている。しかも多くの場合、オンライン上の生活やあらゆる種類のデジタル情報の追求は、匿名性によってあいまいにされ、自動化によって増幅される。もちろん、インターネットや他の技術に備わるこうした機能には、問題だけでなく利点もある。民主主義の活動家はソーシャルメディアの匿名性を利用して、強権的な政権から逃れることができ、報道関係者はボットを使って、速報記事を発信することができる。しかしそうした利点さえ、欠点によって次々と帳消しになっている。インターネットは民主主義を弱体化させ、批判的思考と陰謀論を区別できないようにするためにも使われてきたのだ」と述べています。
さらに、批判的思考と陰謀論的思考は混同されやすいと指摘し、著者は「どちらアイデアや議論、出来事を『深く掘り下げる』ことに注力しており、少なくとも表面的には、何が事実や真実なのかを調べようとするものだ。コンピューター・プロパガンダについて講演すると、私が事実とフィクションをどう見分けているのかという質問をよく受ける。つまり、本当のニュースとフェイクニュースをどう区別しているのか、本当のニュースとは、主観的であったり、センセーショナルであったりすることが多いのではないか、と聞かれるのだ。それに対し、社会科学の訓練を受けた者として私はいつもこう答えている。証拠とデータ、出来事をじかに体験した人々へのインタビュー、そして客観的であろうとする努力が必要だ、と。しかし鋭い人は、インタビューの対象者がバイアスの影響を受けている可能性はないかと聞いてくる。あらゆる研究は、研究者やジャーナリストの価値観によって歪められたものではないのか? ここまでくると話が複雑になり、人々は批判的思考の道から外れて、陰謀論的思考へと迷い込むことがある」と述べます。
陰謀論は人類の文明が誕生して以来、つまり権力と噂話が人々の会話に影響を与えるようになって以来、存在していたと言っても過言ではありません。しかし現在、従来のメディアによって広まってきた陰謀論よりも拡散しやすく、より強力で、より広範囲に及ぶ陰謀論を、ソーシャルメディアは生み出すようになっているとして、著者は「その影響はオフラインにも達する。世界中で、ソーシャルメディア発の陰謀論が拡散されると、それに暴力と死が続くという状況が生まれている。人々が自由に考えを議論できることは重要だが、その議論が暴力を扇動したり、憎悪を広めたり、中傷を長い間存続させたりするというのは良いことではないし、ほとんどの民主主義国では合法ではない。だからこそ、ソーシャルメディア企業はそうした情報の流れを止めなければならない。たとえば、特定の宗教や人種に対する暴力的な反応を引き起こすために、ありもしない『秘密』を持ち出すような陰謀論は、テレビと同じようにソーシャルメディア上で許されるものではない。なにより、こうした問題のあるロジックを、暴力を誘発する意図で使った人々は、ソーシャルメディアから追放されて当局に起訴されるべきだ」と述べるのでした。
5「ディープフェイク――まだディープではない」では、ここ数年、デジタル偽情報の台頭についての議論の中心になっているのがディープフェイクであると指摘します。これは「ディープラーニング」と「フェイク」を組み合わせた言葉で、AIで加工された動画を意味します。著者は、「ディープフェイクは、さまざまな感覚を通じて人々の現実認識を操作する、新たな手法である。多くの研究者や専門家が、政治家(あるいは映像內に映っている人々)が、映像に映し出されていることを本当に言ったり行ったりしたのかを、私たちが判別することはほとんど不可能になるだろうと指摘している」と述べています。
「普通の動画も強力なプロパガンダ・ツールに」として、著者は以下のように述べています。
「動画は、その複数の感覚に訴える性質によって、真実をさまざまな形に曲解させる強力なツールになる。研究によれば、動画は文章よりも記憶に残りやすいため、アイデアを広める際には効果的で、より有利なツールとなる。それは、私たちが目と耳で出来事を認識するからで、動画の方がより現実的に感じられるのである。3Mが発表している、効果的なプレゼンテーションを行うためのガイドラインによれば、脳は文章よりも6万倍速く映像を処理することができる。さらにオーストラリアの2人の学者が行った研究によれば、動きは注目を引き付け維持するのに非常に効果的な手段だ。これらを念頭に置けば、現在のテレビ番組や映画では、ひっきりなしに画面が切り替わるようになっているのは驚くことではない。またプロパガンダ行為者が、自分たちにとって望ましい現実を広めるためのツールとして、映像を利用しているのもうなずける」
6「XRメディア」では、「バーチャルの定義」として、「XR(Extended RealityまたはCross Reality)」を「仮想の現実と現実の世界を組み合わせるメディアツールの総称」、「VR(Virtual Reality〈仮想現実〉)」を「VRはXRのなかでもっともよく知られているメディアかもしれない。この分野ではいろいろな意味を含む言葉として雑多に使われているが、VRは実際には、コンピューターがリアルタイムで生成した多感覚の体験に、ユーザーを直接没頭させることに特化している。イヤホン付きのゴーグルやヘッドセットで、ユーザーを別の場所に送り込む、そういうものだと覚えておいてほしい」、「AR(Augmented Reality〈拡張現実〉)」を「ARは、デジタル画像を現実世界の上に表示する。具体的な例は、スマートフォンの画面とカメラを使って、現実世界の空間で捕獲するクリーチャーを見つけるゲーム『ポケモンGO』だ」、「MR(Mixed Reality〈混合現実〉)」を「MRも意味合いの広い言葉だ。この分野の広告では、MRが使われることが多い。正確に言えば、MRは複数種類のXRメディアを組み合わせたハイブリッドツールだ。それはVRとARの両方の要素を持つメディア体験を指す。現実世界と仮想世界の両方を融合させるメガネは、MRだと考えられる。言い換えれば、MRでは現実と仮想が同時に相互作用することが可能になる」と説明します。
没入型リアリティの利用は、既にゲームの領域を越えて広がっています。著者は、アーティスト、教育者、活動家などが、他のさまざまな目的のためにXRツールを活用しているとして、2017年、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督の映画Carne y Arena(肉と砂)」がカンヌ国際映画祭で初めてVRプロジェクトとして認められ、さらに20年ぶりにアカデミー特別業績賞が贈られたことを紹介します。著者は、「このVR映画は、監督が中米・メキシコ難民に対して行ったインタビューをもとに制作された。その視聴者は、米国に渡ろうとする人々の集団の中に身を置くことになる。同様に、いくつかの組織や技術者が、さまざまな違いや多様な経験を教育するためのXRメディア製品の開発に取り組んでいる。また人々が他の文化や、別の価値観について学ぶのに役立つツールを開発している組織や技術者もいる」と述べています。
しかしVRやARといったツールが良いことに使われるのであれば、他の目的にも使われる可能性があるとして、著者は「これらのツールが世論操作に使われたとき、真実や現実はどうなってしまうのだろうか? たとえば若者たちが、白人至上主義を掲げる『新たな歴史観』を植え付けるための多感覚体験に触れたとしたら、それは彼らの世界観にどのような影響を与えるだろうか? 人々は自分の価値観を他人にも植え付けようと、自らのXRメディアツールを作り始めるようになるのだろうか?それらのメディアの未来は、現在既にソーシャルメディア上で展開されている世論操作活動に見られるパターンと、そう違わないものになるかもしれない」と述べます。
「XRメディアと世論操作」として、ツイッターやフェイスブック、その他のソーシャルメディア・サイトの悪用に関する現在の論争には、ルールが整備されていない場合に何が起こるかを示す、背筋が寒くなるような事例が存在していることを指摘し、著者は「たとえば何千人ものVRユーザーが、本物そっくりの米大統領のアバターを用意して、それに不快なことをさせたり言わせたりしたらどうなるだろうか? 言論の自由に関する米国の強力な法律が機能していれば、おそらく何も起きないだろう。しかしドイツの白人至上主義者がヒトラーのアバターを作成し、それを使って反ユダヤ主義的なコンテンツや、誰かが攻撃してくるといったデマを広めたとしたらどうだろうか? あるいは指導者の名誉毀損を取り締まる厳しい法律を持つ権威主義国家の人々が、権力者をあざ笑うためにXRを使ったらどうなるだろうか?」と述べています。
「スローXR」として、著者は、小説『レディ・プレイヤー1』とその同名映画において描かれた「オアシス」のような社会空間を想像してほしいと呼びかけ、以下のように述べています。
「そこでは人々が、人生の大半をシミュレーションの中で過ごしている。このデジタル空間の中で人々と出会い、交流し、恋に落ちることさえできる。常に、望んでいた人生を創り出すことができ、なりたい自分になることができ、見たいものを見ることができる。しかし彼らはまた、今日のソーシャルメディアにはない新たな課題に直面している。人々が没入している、視覚・聴覚・触覚を通してリアルに感じられる環境によって、『なりすまし』、つまりアバターの背後に自分の身元を隠す行為がこれまで以上に容易になっている。また危険な状況から逃れる手助けをする代わりにお金を要求してきたり、誰かのVR資産を盗んで身代金を要求してきたり、その他の未知の犯罪行為や悪用を起こしたりするなど、これまでには想像もつかなかった詐欺行為がいくらでも可能になるかもしれない。VRやARはまだ試行錯誤の初期段階にあり、こうしたおそれが現実のものとなる前に、私たちにはバーチャル・プロパガンダやハラスメント、人種差別、ヘイトなどの問題に対処するための賢明なツールを揃えておくことができる。新しいテクノロジーが生み出す問題に対して、それが発覚してから数年後に対処するという同じ愚を繰り返してはならない」
「人間と人間に似たもの」では、著者は「仮想現実と拡張現実は、生きた体験をシミュレートするための素晴らしいツールだ。大好きな映画のキャラクターになれるだけでなく、行ったことのない場所に旅したり、まったくの空想の世界で友人に会ったりすることもできる。XRとAIは、テクノロジーと人間がますます絡み合うようになる中で、人間であるということの境界を広げている。ボットはより人間らしくなっており、人間はよりボットらしくなってきている。時がたつにつれ、人間であることと機械であることの間には、両者が混ざり合ったものがさらに現れるだろう」と述べています。このあたりは、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)のメッセージに通じます。インターネットによってグローバルに結びつけられた世界で、Society 5.0 の名のもとに、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)が高度に融合していく……その流れの中で、わたしたちの「心の社会」は、ハートフル・ソサエティにもハートレス・ソサエティにもなりえるのです。
7「テクノロジーの人間らしさを保つ」では、「マシンとの関係構築」として、テクノロジーの人間らしさが増し、反対に機械らしさが少なくなることで、人間とテクノロジーとのやり取りが変化していく可能性があることを指摘し、著者は「私たちの電話に搭載されたAI音声は、より丁寧に(あるいはよりくだけたものに)なったり、バリエーションが増してより楽しいものになったりするかもしれない。確かなことは言えないが、その結果次第では、私たちはマシンを操作できるようになるかもしれないし、マシンが人間を操作するようになるかもしれない。この関係性が進化し続ける中で、これまで以上に有益なテクノロジーを創造しようとして、同時に世論操作や服従をさらに容易にするツールを開発してしまわないようにするには、考慮しなければならない問題がいくつかある」と述べています。
また、「マシンが親切に振る舞うようにする」として、政治家やテクノロジー企業の幹部にすべきことがある一方で、一般の人々には単に、オンライン上でどんな写真や音声をシェアするかについて慎重になるという方法があることを指摘し、著者は「母親や上司に見られたくないものは、オンライン上で公開してはいけないということは、誰でも知っている。しかし自分の情報や画像を公開することで、政治的な目的を持つ荒らし行為や偽情報の拡散、あるいはさまざまな詐欺の被害者になる可能性があるため、注意する必要があることに気づいている人は少ない。あなたの顔や声が加工され、ディープフェイクに使われたり、政治ボットのプロフィールの元として使われたりする可能性さえある。一般の人々が自分のデータを守ることには、自分自身と、自分に関する真実の両方について守るという意味があるのである」と述べます。
結論「人権に基づいたテクノロジーの設計」では、「既存ソーシャルメディアの窮地」として、著者は以下のように述べています。
「デジタル虚偽の潮流の中で身を守るための既知の方法を用いて、わたしたちは社会に『情報レジリエンス(回復力)』、つまり一種の認知的な免疫を培う必要がある。そしてデータとテクノロジーの両方を検証するにあたっては、民主主義と人権に備わる価値を一番に考えなければならない。また、社会におけるさまざまな層の人々を保護し、彼らに力を与えるためにできることもある。複数の戦略を用いて、オンラインおよびオフラインにおける、デジタルのつながりやネットワークを促進すると共に、彼らに自らの独自性と、質の高い情報源を持つ権利を再認識させることで、ジャンクニュースや偽科学に対する『予防接種』を行うのである。さらに政府は、メディアリテラシー、ニュースリテラシー、情報リテラシー、デジタルリテラシーなど、呼び名は何であれそれらに本気で取り組むべき時に来ている」
また、「民主主義を再構築する」として、ソーシャルメディア・プラットフォームは民主主義の原則を蝕んだ最初のメディアツールではなく、またそれが最後になることもないだろうとして、著者は「私たちの世界には、他者を支配することで権力を構築し、維持しようとする人々が常に存在する。彼らはこの目標を達成するために、必要とあらば、新しいテクノロジーも含む利用可能なあらゆる手段を使う。ソーシャルメディア・プラットフォームは非常に人気があり、何十億人もの人々に利用されているため、情報を操作しようとする個人や組織はいま、このプラットフォームを利用して、自分たちの目標にできるだけ多くの人々を巻き込もうとしている。しかし彼らにとって最新のテクノロジーが有益なのは、大勢の人々へのアクセスを提供してくれるためだけではない。それが強力なのには、自動化され、匿名化され、ますます賢くなりつつあるためという理由もある。動画やVR、AR、音声合成システム、人間らしさを実現するテクノロジーといった新しい手段が登場すると、権力者たちは真実を自分たちに有利なように捻じ曲げるためにそれを利用しようとするだろう」と述べています。
そして、著者は「私たちは常に、すべての人々の権利と声を優先する民主主義を維持するために戦わなければならない。不公平は常に存在し、権力はしばしばごく少数の人々の手に集中するるのだが、私たちは自分たちを支配するために使われているのと同じテクノロジーを使って、その支配に対抗することができる。私たちは手を取り合って、テクノロジーを人権に配慮し設計するように要求できる。私たちは、社会は民主主義を中心に回るべきであると主張できるのだ」と訴えるのでした。
「訳者あとがき」では、小林啓倫氏が「ソーシャルメディアやVR(仮想現実)、AI(人工知能)といった先進テクノロジーのプロパガンダへの利用によって、私たちが真実を把握するのが難しくなっていること、それが民主主義を危機に陥れていることを描き、そうした現状にどう対処すべきかを考察している。新しいテクノロジーがプロパガンダに利用されるというのは、これまでの歴史においても幾度となく繰り返されてきた。15世紀にヨハネス・グーテンベルクによって完成された印刷技術は、カトリック教会の権威を批判する人々を後押しし、その後の宗教改革をもたらす一因になったと言われている。20世紀に何度も発生した戦争は、ラジオやテレビといった放送技術を駆使した宣伝合戦と無縁ではなかった。そうしたパターンが、21世紀における最先端テクノロジーの分野でも起きようとしているわけである」と述べます。
朝日新聞が2018年に報じたところによると、ドイツのエアランゲン・ニュルンベルク大学の研究チームが、14年に行われた日本の総選挙を対象に、投票日の前後に54万件のツイート(ツイッター上の投稿)を分析したそうです。するとツイートの8割がボット等によるもので、その多くが当時の安倍政権を支持するメッセージを拡散するものだったといいます。またプロパガンダの事例ではないが、本書でも取り上げられている「ディープフェイクによるアダルトコンテンツ制作」は日本でも発生しており、20年10月には初の逮捕者(合成動画を作成した大学生とシステムエンジニアの2名)が出ていることを紹介し、小林氏は「本書ではまだ可能性の段階として考察されている事例も、これから私たちの身の回りで現実のものとして発生してくるだろう」と述べています。本書には知らなかったことも多く、大変勉強になりました。わたしも、フェイクニュースには気をつけます!
