- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2008 歴史・文明・文化 『残酷な進化論』 更科功著(NHK出版新書)
2021.02.22
『残酷な進化論』更科功著(NHK出版新書)を読みました。「なぜ私たちは『不完全』なのか」というサブタイトルがついています。著者は1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業勤務を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。現在、東京大学総合研究博物館研究事業協力者、明治大学・立教大学兼任講師、東京学芸大学・早稲田大学・文教大学非常勤講師。著書に、一条真也の読書館『爆発的進化論』、『絶滅の人類史』、『宇宙からいかにヒトは生まれたか』で紹介した本などがあります。
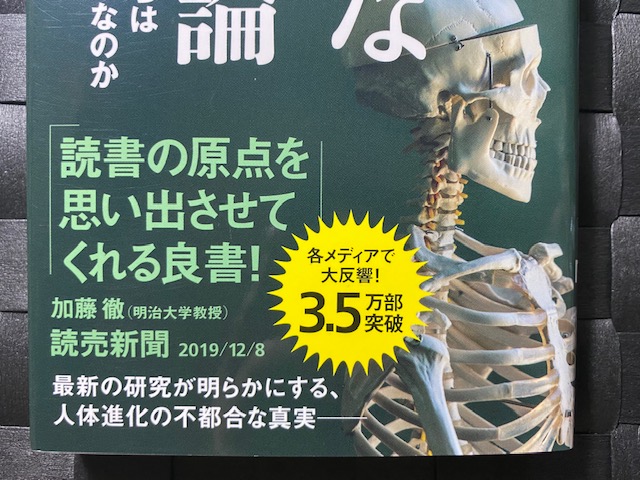 本書のカバー表紙の下部
本書のカバー表紙の下部
本書のカバー表紙には人体骨格標本の写真が使われ、「読書の原点を思い出させてくれる良書! 加藤徹(明治大学教授)読売新聞 2019/12/8」「最新の研究が明らかにする、人体進化の不都合な真実――」「各メディアで大反響! 3.5万部突破」とかかれています。
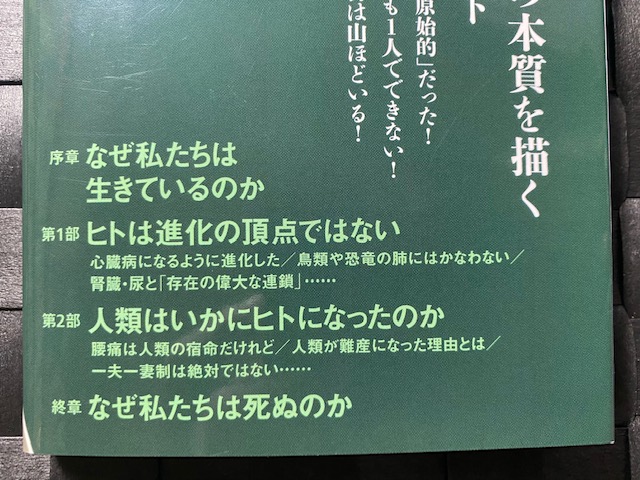 本書のカバー裏表紙の下部
本書のカバー裏表紙の下部
また、カバー裏表紙には、「『人体』をテーマに進化の本質を描く知的エンターテインメント」「●ヒトのほうがチンパンジーよりも、じつは『原始的』だった!」「●ヒトは腸内細菌の力を借りなければ、食事も1人でできない!」「●人類よりも優れた内臓や器官を持った生物は山ほどいる!」「●生物の寿命も進化によってつくられた!」と書かれています。
アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。
「ヒトは心臓病・腰痛・難産になるように進化した! 複雑な道具を使いこなし、文明を築いて大繁栄した私たちヒトは、じつは『ありふれた』生物だった──。人体は「進化の失敗作」? ヒトも大腸菌も生きる目的は一緒? 私たちをいまも苦しめる、肥大化した脳がもたらした副作用とは? ベストセラー『絶滅の人類史』の著者が『人体』をテーマに、誤解されがちな進化論の本質を明快に描き出した、知的エンターテインメント!」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 なぜ私たちは生きているのか
第1部 ヒトは進化の頂点ではない
第1章 心臓病になるように進化した
第2章 鳥類や恐竜の肺にはかなわない
第3章 腎臓・尿と「存在の偉大な連鎖」
第4章 ヒトと腸内細菌の微妙な関係
第5章 いまも胃腸は進化している
第6章 ヒトの眼はどれくらい「設計ミス」か
第2部 人類はいかにヒトになったか
第7章 腰痛は人類の宿命だけど
第8章 ヒトはチンパンジーより「原始的」か
第9章 自然淘汰と直立二足歩行
第10章 人類が難産になった理由とは
第11章 生存闘争か、絶滅か
第12章 一夫一妻制は絶対ではない
終章 なぜ私たちは死ぬのか
「おわりに」
序章「なぜ私たちは生きているのか」では、「生きるようにつくられたのが生物」として、著者は述べます。
「私たちはいろいろなことを考えながら生きている。もちろん、夢を追ったり、人のために努力したりするのは尊いことだ。可能なときは、そういう生産的な行動を積極的にするのもよいだろう。しかし調子が悪いときは、前向きに生きられないこともある。さまざまな事情で自由に生きられない人もいる。そういうときには、私たちは人間である前に、生物であることを思い出すのもよいかもしれない。生物は生きるために生きているのだから、私たちだって、ただ生きているだけで立派なものなのだ。何もできなくたって、恥じることはない。そんな生物は、たくさんいる」
第1部「ヒトは進化の頂点ではない」の第1章「心臓病になるように進化した」では、著者は「血管の内側にコレステロールなどが溜まって、血液が流れにくくなったり血管が硬くなったりすることを動脈硬化という。狭心症や心筋梗塞は、冠状動脈の動脈硬化によって起きる。その原因としては、高血圧、高脂血症(血液中の脂肪が増えること)、喫煙、肥満、糖尿病の5つがよく挙げられる。たしかに、これらの原因とされることを注意深く避ければ、狭心症や心筋梗塞になる可能性は減るだろう。しかし、それでも完全に避けることはできないようだ」と述べています。
また、「アイスマンが教えてくれること」として、1991年にイタリアとオーストリアの国境付近の氷河から、およそ5300年前のミイラが発見されたことを紹介し、著者は「このミイラはアイスマンと呼ばれ、この付近の山麓に住んでいた可能性が高い。アイスマンは喫煙もしなかっただろうし肥満でもなかっただろうが、遺体の分析から動脈硬化を起こしていた可能性が高いことがわかった。このような狭心症や心筋梗塞の徴候は、アイスマンにかぎらずエジプトやペルーなどのさまざまなミイラの分析からも報告されている」と述べます。
さらに、進化は心臓にも優しくないようだと指摘し、著者は「若くて子供がつくれるあいだは心臓にも元気に働いてほしいけれど、そのあとのことまでは考えてくれない。冠状動脈などの心臓の構造は、進化における設計ミスではなくて、進化にとっては理想的な構造かもしれない。ただそれが、私たちにとっては不都合な構造だったということだ。私たちと進化の利害関係は、しばしば一致しない。ときに進化は私たちの敵になる。もしそうなら、私たちも進化の言いなりになっている必要はないだろう。医学や健康な生活習慣は、進化と闘うための武器なのである」と述べるのでした。
第3章「腎臓・尿と『存在の偉大な連鎖』」では、「存在の偉大な連鎖」として、著者は「世界にはさまざまなものが存在する。生きているものも生きていないものも、たくさんある。このような世界の多様性を説明する仕組みとして、中世ヨーロッパのスコラ哲学者たちは『存在の偉大な連鎖』を考えていた。『存在の偉大な連鎖』とは、世界の多様性を石ころから生物、そして神へと上っていく階級制度に置き換えたものだ。ヒトは生物の中では一番上で、天使の下に位置しているとされた。しかし19世紀になると、『存在の偉大な連鎖』の地位が揺らいでいる。生物の多様性を説明する別の考え方が、広まってきたからだ」と述べています。
第2部「人類はいかにヒトになったか」の第7章「腰痛は人類の宿命だけれど」では、「脊椎の不自然な使われ方」として、著者は「もしかしたら、私たちの腰痛の大きな原因は、老化のせいかもしれない。野生の動物は、腰痛が始まる前に死んでしまうだけかもしれない。最近はイヌなどのペットが長生きするようになった。高齢化したペットには、たとえ体重が軽くて四足歩行をしていても、脊柱に問題が起きることが結構あるのである」と述べています。
第9章「自然淘汰と直立二足歩行」では、「なぜチンパンジーはいまも四足歩行か」として、著者は「直立二足歩行をする生物は、人類しかいない。しかし、直立しなくてもよければ、二足歩行をするサルや類人猿はたくさんいる。樹上を二足歩行するサルや類人猿もたくさんいる。約700万年前にその中の1種が直立二足歩行を始めた。もしかしたら、それは私たちでなくてもよかったのかもしれない。他のサルや類人猿でもよかったのかもしれない。進化では偶然も大きな役割を果たしているのである」と述べています。
第12章「一夫一妻制は絶対ではない」では、「人類が類人猿から分かれた理由」として、わたしたち人類が、チンパンジーに至る系統と分かれたのは、およそ700万年前と考えられていることが紹介されます。分かれた理由としては、人類の配偶システムが一夫一妻的なものになったからだという説があるそうです。「オスとメスがいる生物では、オスはたくさんの精子をつくるが、メスは限られた数の子しか産めない。したがって、オスはなるべく多くのメスと交尾して、たくさんの子をつくろうとする傾向がある」。ここまでは、一般論としては正しいだろうとしながらも、著者は「でも、そこから『一夫多妻が本来の姿なのだ』と結論するのは正しくない。それなら、オスとメスがいる生物は、自然淘汰の結果、すべて一夫多妻になるはずである。でも、実際にはそうなってはいない。生物の行動は、そこまで単純ではないのである」
また、著者は「なぜ牙がなくなったか」として、「チンパンジーは多夫多妻的な群れをつくる。群れの中には複数のオスと複数のメスがいて、乱婚の社会をつくる。そのため、メスをめぐってオス同士で争いが起きる。このとき使われるのが、牙だ。この牙で相手を殺してしまうことも珍しくないようだ。ところが人類には牙がない。だから、テレビのドラマを見ていると、犯人が人を殺すのにかなり苦労している。犯人は、拳銃とか刃物とか花瓶とか、わざわざ凶器を使わなくてはならない。チンパンジーなら、噛むだけで済むのに」と述べます。
では、どうして人類には牙がなくなったのでしょうか。この問いについて、著者は「大きな犬歯(牙)をつくるには、小さな犬歯をつくるよりも、多くのエネルギーが必要である。その分、たくさん食べなくてはならない。だから、もしも牙を使わないのなら、犬歯を小さくしたほうがエネルギーの節約になる。したがって、もし牙を使わなければ、自然淘汰によって、犬歯は小さくなっていくだろう。したがって人類は、あまり牙を使わなくなったと考えられる。おそらく、あまりメスをめぐって争うことがなかったのだろう。人類はチンパンジーより平和な生物なのだ」と答えています。
現生の類人猿では、オランウータンと多くのゴリラは一夫多妻、ゴリラの一部とチンパンジーとボノボは多夫多妻的な群れをつくるとして、「一夫多妻や多夫多妻の社会では、メスをめぐるオス同士の争いをなくすことは難しい。1頭のメスに、同時に複数のオスが集まるからだ。一方、一夫一妻的な社会では、メスをめぐるオス同士の争いは、一夫多妻や多夫多妻の社会よりも穏やかになる。そのため、約700万年前の人類は、一夫一妻的な社会をつくるようになったので、オス同士の争いが穏やかになり、犬歯が小さくなった可能性がある。だから、一夫一妻的な社会を仮定すれば、犬歯が小さくなったことを説明できる。ところがそれだけでなく、直立二足歩行を始めたことも説明できるのである」と述べます。
「難産と社会的出産」として、著者は人間の脳が進化によって大きくなってきたことを指摘し、「脳が大きくなることによって進化した特徴の1つは難産だ。難産については第10章で述べたが、簡単にまとめれば、人類は直立二足歩行をすることによって、少し難産になり、脳が大きくなることによって、さらに難産になった。ヒトはすべての哺乳類の中で、もっとも難産な種の1つである」と述べています。また、「難産になったため、出産には誰かがつき添うことが多い。現在では医療機関で出産することも多いが、かつては出産する女性の母親や姉妹や親族の女性などが、つき添うことが普通だった。このように、出産中に誰かがつき添う社会的出産は、単なる文化的なものではなく、何十万年も前から行われてきた生物学的なものである可能性がある」と述べます。
著者によれば、ヒトは脳が大きくなって、行動が複雑になったことは確かだといいます。そのため、行動の選択肢が増えて、いろいろな配偶システムでもやっていけるようになり、生まれた場所の文化にしたがって、そこの配偶システムに馴染んでいけるようになったのではないだろうかと推測しています。そして、「私たちは一夫一妻制に向いていないのか」として、著者は「私たちヒトは世界のさまざまな地域に住み、その地域によって、さまざまな配偶システムが存在する。一夫一妻も、一夫多妻も、多夫一妻も、多夫多妻も存在する。ヒトの行動には柔軟性があり、どの配偶システムでもそれなりにうまくやっていけるのだろう。それでも一番多いのは一夫一妻だ。子供の世話が大変なので、ゆるやかに一夫一妻に向かう進化傾向があるのかもしれない。しかし、そういう進化傾向があったとしても、文化的な影響のほうが大きいのだろう。そのため、さまざまな配偶システムが存在していると同時に、一夫一妻が多数を占めているのではないだろうか」と述べるのでした。
終章「なぜ私たちは死ぬのか」では、「細菌は40億歳」として、著者は「昔の生物は死ななかった。でも、私たちヒトは必ず死ぬ。どうしてだろうか。なぜ昔の生物は死ななかったかというと、細菌かそれに似た生物しかいなかったからだ。もちろん細菌も、環境が悪くなったり事故にあったりすれば、死ぬことはある。でも、好適な環境にいれば、細胞分裂を続けながら永遠に生き続けることができる」と述べています。また、「地球上に生物がいた最古の証拠は、約38億年前のものである。生物が生まれたのは、とうぜん最古の証拠よりも前のはずだから、ざっと40億年ぐらい前のことだろう。ということで、とりあえず細菌が生まれたのを約40億年前とすれば、現在生きている細菌は約40億年のあいだ生き続けてきたことになる。つまり、細菌に寿命はないのだ。無限に細胞分裂を繰り返すことができるのだ」とも述べています。
また、「寿命は進化によってつくられた」として、最高齢の記録には不確実なものが多く、どこまでを事実と考えてよいのか難しいけれど、少なくともフランス人のジャンヌ・カルマン氏(女性、1997年没)が122歳まで生きたのは確実とされていることが紹介されます。著者は、「おおよそこの辺りが、私たちの寿命の上限と考えてよいだろう。いくら好適な環境で生きていても、永遠には生きられないのだ」と述べます。現在では、世界一の長寿者は日本の田中カ子さんです。現在118歳の福岡県福岡市東区在住の長寿の女性ですが、日本並びにアジアの歴代最高齢者となっています。世界最高齢者であった都千代さんが2018年7月22日に死去して以来、長寿世界一並びに日本一となりました。
さらに、「『死』が生物を生み出した」として、著者は「自然淘汰が働くためには、死ぬ個体が必要だ。自然淘汰には、環境に合った個体を増やす力がある。しかし、なぜそういうことが起きるかというと、環境に合わない個体が死ぬからだ」「死ななくては、自然淘汰が働かない。そして、自然淘汰が働かなければ、生物は生まれない。つまり、死ななければ、生物は生まれなかったのだ。死ななければ、生物は、40億年間も生き続けることはできなかったのだ。『死』が生物を生み出した以上、生物は『死』と縁を切ることはできないのだろう。そういう意味では、進化とは残酷なものかもしれない」と述べるのでした。
「おわりに」では、死なないようにする行動、つまり生きようとする行動は、すべて生存闘争だとして、著者は「寒くて凍えそうだから、少しでも暖かくなろうと思って、手を擦り合わせる。それも生存闘争なのだ。気持ちよく晴れた春の午後。木々の梢を飛び回る小鳥たちが楽しそうにさえずっている。そんな小鳥たちは、いま何をしているのかというと……、もちろん生存闘争をしているのだ。そよ風が吹く草原で、ウシが草を食んでいる。森林性の動物たちとは棲み分けて、のんびりと暮らしている。そんなウシたちが、いま何をしているのかというと……、もちろん生存闘争をしているのだ」と述べています。
地球の大きさが有限である以上、生存闘争は必ず起きるとして、著者は「平和な風景で中の生物を見ていると、つい見逃してしまいがちだけれど、いつでもどこでも生存闘争は起きているのである。そして生存闘争というのは、自然淘汰が働くための必要条件である。小鳥たちには空を飛ぶのに適した翼がある。ウシたちには草原を走るのに適した蹄がある。これらは自然淘汰でつくられたものだ。したがって、そういう翼や蹄があることが、生存闘争が起きている証拠なのだ」と述べます。
さらに、「生存闘争」という言葉がよくないのかもしれないという著者は、「『自分の命を大切にすること』とでも言い換えればよいのかもしれない。『生存闘争』とはかなりイメージが異なるけれど、同じ意味だから。小鳥たちが飛び回る木々の梢や、そよ風が吹く緑の草原を生み出した進化をどう見るか。自分の命を大切にする平和な進化と見るか、生存闘争による残酷な進化と見るか。いや、そのどちらも正しい。それは単なる見方の問題であって、実際には1つのものを別の面から見ているだけにすぎない」と述べます。
そして、最後に著者は「ヒトは単なる生物の1種である。でも、おそらくは脳が大きいために、自分を特別視するくせがついてしまったのではないかと思う。でも、そういう視点は、ヒトという種を見るときにも、他の生物を見るときにも、目を曇らせてしまうだろう。とはいえ、あるがままに見るというのは、なかなか難しいことでもある。それは、ときに残酷なものを見なければならないから。『世界をあるがままに見たうえで、それを愛するには勇気がいる』。フランスの文学者、ロマン・ロランが言ったことは、ヒトの進化を考えるときにも当てはまるようである」と述べるのでした。前作『宇宙からいかにヒトは生まれたか』に続き、本書もロマン・ロランの素敵な言葉で締め括られました。著者の本は、科学を語っていながら、いつも文学の香りが漂っています。