- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2011 オカルト・陰謀 『もののけの日本史』 小山聡子著(中公新書)
2021.03.02
『もののけの日本史』小山聡子著(中公新書)を読了。「死霊、幽霊、妖怪の1000年」というサブタイトルがついていますが、素晴らしい通史でした。著者は1976年茨城県生まれ。98年筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業。2003年同大学大学院博士課程歴史・人類学研究科修了。博士(学術)。現在、二松学舎大学文学部教授。専門は日本宗教史。共編著に、一条真也の読書館『幽霊の歴史文化学』で紹介した本があります。
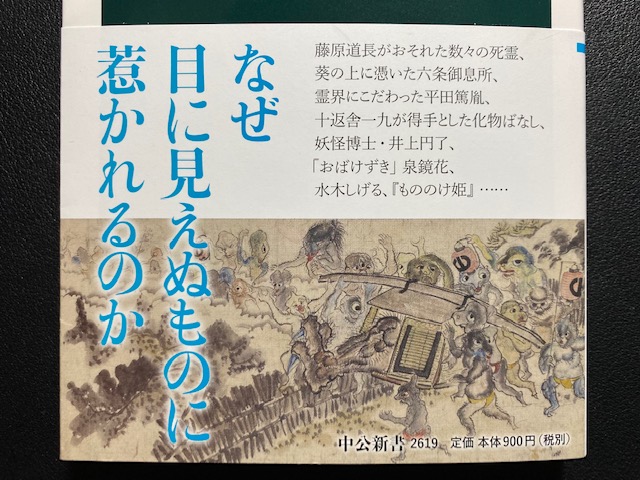 本書の帯
本書の帯
本書の帯には『稲生物怪録絵巻』(堀田家本)の一部が使われ、「なぜ目に見えぬものに惹かれるのか」と大書され、「藤原道長がおそれた数々の死霊、葵の上に憑いた六畳御息所、霊界にこだわった平田篤胤、十返舎一九が得手とした化け物ばなし、妖怪博士・井上円了、『お化け好き』泉鏡花、水木しげる、『もののけ姫』……」と書かれています。
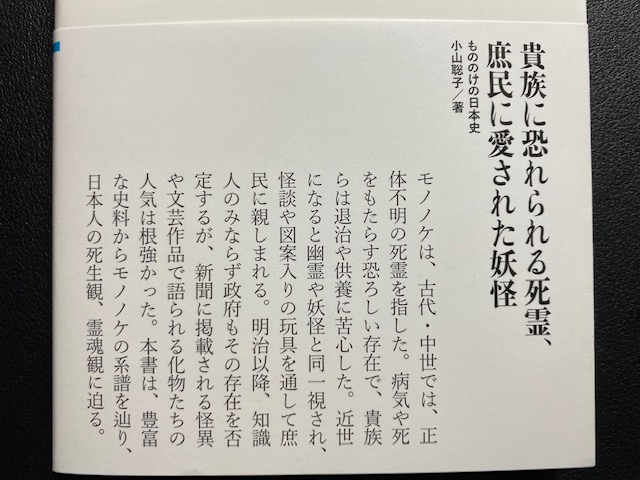 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「貴族に恐れられる死霊、庶民に愛された妖怪」として、「モノノケは、古代・中世において、正体不明の死霊を指した。病気や死をもたらす恐ろしい存在で、貴族たちを悩ませた。近世に入ると幽霊や妖怪と混同され、怪談や図案入りの玩具などで親しまれるようになる。近代以降、根拠がないものとして否定されつつも、怪異は根強い人気を博し人びとの興味をひきつけてやまない。本書は、モノノケの系譜をたどりながら、日本人の死生観、霊魂観に迫る」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
「まえがき」
序章 畏怖の始まり
第一章 震撼する貴族たち――古代
一、モノノケと戦う藤原道長
二、対処の選択――調伏か、供養か
三、モノノケの姿――鬼との近似
第二章 いかに退治するか――中世
一、高僧が説く方法
二、手順の確立――専門化と簡略化
三、囲碁・双六・将棋の利用
第三章 祟らない幽霊――中世
一、霊魂ではない幽霊
二、幽霊と呼ばれた法然
三、能での表現
第四章 娯楽の対象へ――近世
一、物気から物の怪へ
二、実在か非実在か――大流行する怪談
第五章 西洋との出会い――近代
一、迷信の否定と根強い人気を誇る怪談
二、古代・中世の遺物――曖昧なものへ
三、西洋文化受容の影響
終章 モノノケ像の転換――現代
「あとがき」
「主要参考文献」
「古文書・古記録の幽霊一覧」
「まえがき」で、著者は「古代におけるモノノケは、漢字では物気と表記し、多くの場合、正体が定かではない死霊の気配、もしくは死霊を指した。モノノケは、生前に怨念をいだいた人間に近寄り病気にさせ、時には死をもたらすと考えられていたのである」と述べています。現在、モノノケというと、映画、アニメ、漫画などの影響で、神の類や妖怪を思い浮かべることが多いですが、現代のいわゆる「もののけ」は、古代の貴族が恐れていたモノノケとは、全くの別物です。
そもそもモノノケは、どのような経過をたどって、現代に伝わったのでしょうか。著者は、「これまで、古代、中でも『源氏物語』のモノノケばかりが論じられてきており、その他の時代については見過ごされてきた。また、モノノケの歴史を扱っているかのように見える書籍も、言葉を厳密に区別せず、『物気』あるいは『物の怪』とは書かれていない霊、妖怪、幽霊、怨霊、化物の類まで含めてモノノケとして捉えて論じてきた傾向がある。しかし、それでは、モノノケの本質を明らかにすることなどできないだろう」と述べます。
本書では、史料に基づき、モノノケと幽霊、怨霊、妖怪を区別して述べています。著者は、「まず、古代の霊魂観がいかなるものであり、モノノケがどのように畏怖されはじめ、さらには中世を通じていかに対処されてきたのかを具体的に明らかにしていく。近世になって、モノノケは、幽霊などと混淆して捉えられるようになる。現在イメージするモノノケのはじまりと見ていいだろう。そこで、中世の幽霊についても説明し、近世におけるモノノケ観の展開について考察する。そして、近世を経てどのように近代、さらには現代に至っているのか、明らかにしていきたい」と本書の構成を説明します。
そして、著者は「生きとし生ける者には、必ずいつの日か死が訪れる。限られた命である以上、どれほどに科学が発達したとしても、死や死者に対する恐れは、決して消えはしない。そもそもモノノケへの畏怖は、死へのそれと不可分の関係にある。本書では、モノノケの系譜を明らかにすることを通して、とりわけモノノケを死霊と見なしていた古代・中世の日本人がどのように死や死者に対する恐怖を超克しようとしてきたのかという点や、いかにして死者と良好な関係を保とうとしたのかという点、各時代における日本人の心性についても迫りたい」と述べるのでした。
序章「畏怖の始まり」では、「死者の居場所」として、そもそも古代中国では、霊に関して魂と魄という二元的な把握がなされていたことが紹介されます。たとえば、中国の現存最古の字書『説文解字』では魂は「陽気」であり、魄は「陰神」であるとされました。儒教の経典『礼記』「郊特性」では、魂は天に帰り魂は地に帰るものだとされていました。さらに、孔子編纂とされる『春秋』の注釈書『春秋左氏伝』「昭公七年」では、人が生まれる時に「魄」ができ、「陽」の「魂」がその中に入るとされており、「魄」は体を指します。つまり、魂は精神を、魄は肉体をそれぞれつかさどる霊なのです。
古代中国の魂魄の思想は、日本の霊魂観にも影響を及ぼしています。たとえば、菅原道真による漢詩文集『管家文草』(昌泰3年〔900〕)三には、穀断ちをしている僧について、「今にも骨が肌を突き出るかと思われ、魂は魄から離れ昇天せんばかりである」とあります。さらに、『菅家文草』八では、官吏登用試験で道真が出題した「魂魄について論ぜよ」とする課題があり、魂は精神的なものであり天に帰する一方、魄は肉体に宿る性質を持ち地に帰するものだ、とされています。著者は、「ただし、官吏登用試験という国家最高試験で『魂魄について論ぜよ』とする問題が出されていたことから、この問いは実に難題だったと言えるだろう。けれども、すでに古代には、中国思想の影響のもと、魂と魄について二元的な理解があったことは間違いない」と述べます。
「霊魂と遺骨の関係」として、著者は「現代には墓参りをする習慣がある。墓前に手を合わせ、先祖に対し、最近の出来事の報告をしたり、なかなか墓参りできないことを詫びたり、時には自分に都合の良い願い事をしたりもする。それに対して古代には、霊魂は死とともに天上や山、海、黄泉国といった他所に行くのであり、遺体(もしくは遺骨)とは分けて捉えられる傾向にあった。それだからこそ、身分階層を問わず、骨への関心は稀薄であり、墓参りの習慣はなかったのである。庶民の遺体は、土葬も火葬されず、そのまま地上に置いて風葬とされるのが一般的であった。一方、上級貴族は、一族の墓所に葬られることもあった。そうではあるものの、基本的には墓の整備や墓参りの習慣はなく、死後ある程度の時間が経過すると埋葬の地も明確には把握されなくなる傾向にあった。古代は、現代と比較すると、驚くほどに、遺体や遺骨に無関心な時代だったのである」と述べています。
一条真也の読書館『死者のゆくえ』で紹介した宗教学者の佐藤弘夫氏の著書によれば、古代でも、骨と霊魂の密接な関係を示す史料はたしかにありますが、現代と比べると、遺体や骨への執着は少なく、霊魂と遺骨の関係は稀薄であったと言えます。「モノノケの『モノ』」として、霊への畏怖は、死に対する恐れと密接に結びついており、実に多くの史料に確認できると指摘し、著者は「とりわけ、非業の死を遂げたり、現世になんらかの怨念を残したりして死んでいった者たちの霊魂は、祟りをなすと恐れられ、鎮魂の対象とされた。現存する史料上における『怨霊』という語の初出は、『日本後紀』延暦24年(805)4月5日条の、藤原種継暗殺事件に連座して廃太子され絶食死した早良親王(?~785)の『怨霊』に謝するため、諸国に小倉の建築を命じたなど、とする記事である。社会的に大きな災いをもたらすと考えられた霊魂は、怨霊として畏怖され、鎮魂の対象とされたのである」と述べています。
「鬼と『モノ』」として、長谷川雅雄・辻本裕成・ペトロ・クネヒト「「鬼」のもたらす病――中国および日本の古医学における病因観とその意義(上)」の内容が紹介されます。それによれば、古来、中国では、人間は死ぬと冥界に行って鬼となって暮らすと考えられていました。鬼は死者や死者の魂を指し、神とも重ねられ「鬼神」とも表現されました。また、子孫によって祀られた鬼は子孫を守るとして尊重された一方、祀られない鬼や非業の死を遂げた者は祟りをなすと恐れられていたのです。著者は、「日本でも、『続日本紀』宝亀11年(780)12月4日条に、寺を造るために墳墓を壊して石を採ることは、『鬼神』を驚かせ子孫を傷つけることになるから今後においては禁断するという詔が記されている。ここでは、墳墓にいる霊魂を『鬼神』と呼んでおり、中国の思想の影響を見出せる」と述べます。
中国の鬼と日本のモノノケは、ともに死霊であり、人間に病をもたらす点で共通しています。日本のモノノケはしばしば鬼の姿でイメージされていたとして、著者は「中国の鬼と同様、日本の鬼には、人に病をもたらす性質があると考えられていた。たとえば、8世紀末成立の『続日本紀』天平宝字2年(758)8月18日の詔には『疾疫癘鬼』とある。さらに、『日本霊異記』中―24に登場する閻魔王の使いの鬼が、楢磐嶋という男に、『汝、我が気に病むが故に、依り近づかずあれ』(お前、我の気によって病気になるから、近づくな)と言った、とする話がある。すなわち、もし楢磐嶋が鬼に近寄れば、気に触れ、病気になるということになる」と述べています。わたしは、『「鬼滅の刃」に学ぶ』(現代書林)で、鬼とは疫病のメタファーであり、新型コロナウイルスの感染の不安に包まれた2020年の日本で「鬼滅の刃」が社会現象になったことの一因であると考えています。
「妖怪ではない妖怪」として、「妖怪」という語は、古くは『続日本紀』宝亀8年(777)3月19日条に、宮中にしきりに「妖怪」があるために大祓を行ったとする記事があることが紹介されます。大祓とは、罪や穢れを祓い清める行事です。同月21日には僧600人、沙弥100人を招請して宮中で大般若経を転読させています。ここでいう「妖怪」とは、化け物の類ではなく、怪異です。藤原実資(957~1046)の日記『小右記』長元元年(1028)7月25日条にも、「妖怪」が多くおこり夭死する者が多数出たとする記事があり、「妖怪」の語を怪異の意味で用いています。
拙著『唯葬論』(サンガ文庫)にも書きましたが、「妖怪」とは、そもそも中国で成立した漢語です。後漢の時代に編纂された歴史書『漢書』の「循史伝龔遂」にも「長い間、宮中にしばしば妖怪があった」とあり、「妖怪」を怪異の意味で用いています。日本古代の「妖怪」は、中国由来の語であることになります。また、「幽霊」も「妖怪」と同様に、中国で成立した語です。歴史書『後漢書』列伝「李陳龐陳橋列伝」41や、敦煌で発見された願文が収録されている『敦煌願文集』「追福発願文」などには、「幽霊」を死霊という意味で用いる事例があります。著者は、唐の僧であった善意のように中国から日本へ渡来してきた僧や、中国から帰国した日本人が、「幽霊」を日本に持ち込んだのだろうと推測しています。
第一章「震撼する貴族たち――古代」の一、「モノノケと戦う藤原道長」では、モノノケにのり移られた者たちは、それぞれ屏風で囲まれ、一人一人に験者が付けられ対処されていたことになることが紹介され、著者は「モノノケは、浮遊して移動し、さらに他者に移る特性を持つ、と考えられていた」と述べます。たとえば、『源氏物語』「夕霧」には、落葉の宮の母一条御息所が、モノノケによる病を患ったとき、宮にモノノケがのり移ることを恐れて中仕切を置き、宮が中に入ることを許しませんでした。「若菜下」では、光源氏はモノノケに憑依されたヨリマシを閉じこめ、病人である妻紫の上を別の部屋に移しています。著者は、「光源氏によるこの行為も、モノノケが再び紫の上に近づくことのないようにとの配慮によるものである」と述べています。
「道長の死とモノノケ」として、歴史物語である『栄華物語』において、モノノケの調伏に積極的な姿勢をとっていた道長に修法や加持が行われなかった理由は当の本人がそれを拒否したからだろうと推測し、著者は「万寿4年に道長が患う2年前には、娘の寛子と嬉子が、さらには万寿4年9月には妍子が、顕光らの霊によって殺されたと考えられていた。娘たちを死に追いやった原因を作ったのは、道長である。娘を次から次へと亡くした道長は、もはや自身を悩ます霊をあえて調伏しようとはしなかったのではないだろうか。調伏すれば病を快方に向かわせて生き長らえることができる可能性もあったものの、退治することができず死に至った場合には、極楽往生を遂げられなくなる危険もあった」と述べています。また、著書『往生際の日本史――人はいかに死を迎えてきたのか』において、著者は「道長は、モノノケを調伏して生き長らえるのではなく、極楽往生の方法が書かれている源信『往生要集』を参考にしつつ、念仏にすがり自身の極楽往生を目指したのであろう」と述べます。
二、「対処の選択――調伏か、供養か」では、「三条天皇の眼病」として、モノノケの正体によっては、調伏ではなく、供養された事例も多くあることを紹介。つまり、供養し成仏させることにより、悪さを防ごうとしたのです。病気治療の手段としては、悪さをなした霊の供養も有効だと考えられました。山田雄司『跋扈する怨霊――祟りと鎮魂の日本史』によれば、モノノケは、人間に病や死をもたらすとして非常に恐れられていたそうです。それと同時に、他者を傷つける横暴な言動を自重させる装置にもなり、社会の均衡を保つ役割も担わされていた。この点は、怨霊と同様です。著者は、「霊は、単に恐怖心を煽るのではなく、社会の中で必要とされていたからこそ意識されていたのだろう」と推測します。
三、「モノノケの姿――鬼との近似」では、モノノケは、本来「気」なので、姿かたちを持ちませんが、実際には、鬼の姿で表現されることが多かったことが紹介されます。著者は、「そもそも、中国では死者は鬼になると考えられていた。その思想が日本の鬼の観念に大きな影響を及ぼしたために、モノノケはしばしば鬼の姿だと考えられたのだろう」と推測し、「結局のところ、モノノケの姿は、鬼の図像をもとにして想像され、平安貴族が畏怖していたものも組み合わされた上で構築されていたと考えられる」と述べるのでした。
第二章「いかに退治するか――中世」の一、「高僧が説く方法」では、「阿尾奢法の経典」として、モノノケの調伏の方法は、経典にある阿尾奢法を根拠として編み出されたと考えられると書かれています。「阿尾奢」とはサンスクリット語「アーヴェーシャ」(āveśa)の音写であり、漢訳仏典では「遍入」と訳されることが多かったようです。著者は、「たとえば、空海(774~835)や円仁(794~864)らによって日本に招来された経典である不空訳『速疾立験魔醯首羅天説阿尾奢法』には、自ら魔醯首羅天になると観想した行者が真言を誦すると、所定の作法で加持した童男童女が震えだし『聖者』が遍入し、一切の善悪や吉凶などを問うと答える、とされている。阿尾奢法に関する経典としては、この他に『蘇婆呼童子請問経』や金剛智訳『金剛峯楼閣一切瑜伽祇経』などがある。阿尾奢法やそれに類するものは、漢訳仏典に多く見出すことができ、インド以来の密教にその淵源を遡ることができる」と述べています。
二、「手順の確立――専門化と簡略化」では、「神の調伏」として、神を調伏することは本来は禁忌であったことが紹介されます。谷口美樹「平安貴族の疾病認識と治療法―――万寿二年の赤斑瘡流行を手懸りに」によれば、病気の原因が疫病とモノノケの両方によると判断された場合、神気を畏れ、加持によるモノノケ調伏は避けられた傾向にあるそうです。著者は、「疫病は、疫神がもたらすものだからである。多くの場合、この双方を同時に患った場合には、陰陽師による禊や祓、祭によって対処された。神は人間に祟りをもたらすことにより、自身の要求を伝えると考えられていた。それによって、病気を治すために、神の要求を聞き入れることも行われていた」と述べます。
神事の日には、仏事は避けられるという神事優先の原則がありました。三橋正『平安時代の信仰と宗教儀礼』によれば、貴族社会では、仏事への依存が大きかったものの、神事を優先していたといいます。避けられた理由は、仏教が死のイメージと結び付けられ、穢れと同一の次元で捉えられていたからだと考えられるとして、著者は「それゆえ、たとえモノノケによる病を患っても、神事の日にはあえて加持をせず、神事終了後に行っていたのである。これほどまでに、神は畏怖されていた」と述べるのでした。
三、「囲碁・双六・将棋の利用」では、「中世の囲碁と双六」として、12世紀末頃の成立と考えられる河本家本『餓鬼草紙』二「伺嬰児便餓鬼」には、出産のための祈禱に携わった験者と巫女が描かれており、巫女の傍らには双六盤が置かれていることが紹介されます。著者は、「一体、何を示すために、わざわざ双六盤が描かれたのだろうか。実は、モノノケの調伏は、囲碁、双六、将棋と関わっていた。そこでその理由について探っていきたい。そもそも、囲碁や双六といった盤を用いるゲームは、占いに端を発していた。たとえば、古代エジプトの壁画にはゲームの盤を占具や祭具として用いる様が描かれているし、中国漢代のイコンには盤を使うゲームに興じる神々の姿が描かれている」と述べています。
安永一『中国の碁』によれば、中国古代の囲碁盤は祭祀の際の祭壇でした。後漢の斑固(32~92)の『弈旨』や北宋の張擬の『棊経十三篇』「棋局」によると、碁盤は大地を、碁石は天体を象徴し、盤の四隅は四季をあらわしており、白と黒の碁石は陰陽にのっとっているといいます。さらに、晋代の『抱朴子』や『捜神記』、唐代の『酉陽雑俎』、宋代の『太平寰宇記』などには、仙人が碁を打つ説話があります。大室幹雄『囲碁の民話学』によれば、仙人は、碁盤上にミニチュア化した世界の想像や破壊をして楽しむ、と考えられていたのです。
隋の歴史書で7世紀成立の『隋書』「東夷伝・倭国」によると、「倭人」は囲碁や双六、博打の戯れを好むとされており、日本で盛んに行われていたことが分かります。中国の思想は日本の囲碁観にも大きな影響を及ぼしていました。網野善彦「中世遍歴民と芸能」によれば、双六も、囲碁と同様に、占いのために行われていたそうです。少なくとも、12世紀前半には、国衙に双六別当という役職があり、神意を伝える役割を担っていたとか。また、増川宏一『日本遊戯思想史』によれば、双六博徒は、取り締まりの対象とされていたものの、芸能者でもありました。著者は、「囲碁や双六のみではなく、将棋も占いに関わっていた。源師時の日記『長秋記』大治4年(1129)5月20日条によると、鳥羽院は覆物の占いを行わせている。覆物の占いとは、射覆と言い、覆われた物の中身を当てることである。この時、占いには将棋の駒が使われた」と述べています。
「儀式に使われた囲碁盤」として、『長秋記』天永2年(1111)12月4日条では、髪の裾を切りそろえて成長を祝う儀式である髪曾木の儀で、幼少の鳥羽天皇(1103~56)が囲碁盤の上に立ったことが紹介されています。さらに、『同』長承3年(1134)12月5日条には、鳥羽天皇第二皇女統子内親王と第四皇子雅仁親王、第五皇子本仁親王の髪曽木の儀でも、三人とも囲碁盤に上っています。著者は、「中国では、囲碁盤は大地を、碁石は天体を象徴していた。親王や内親王が囲碁盤の上に立つことは、世の支配を象徴したのだろうか。あるいは、囲碁が仙人の遊ぶ遊戯であり、囲碁盤で占いもしており、神などの聖なるものと交流する具であったことからすると、健やかな成長を祈るためにその盤が用いられた可能性もあるだろう」と述べています。
幼少時に囲碁盤に上り髪を削ぐことは現代も継承されており、平成23年(2011)11月3日、悠仁親王が深曽木の儀(中世後期以降、深曽木という呼称が定着した)で囲碁盤に上り、毛先を切った後に飛び降りています。髪曽木の他には、釈迦が誕生したとされる4月8日の灌仏会で、布施を囲碁盤の上に置く作法がありました。また、「賽子の持つ力」として、産養(出産後、5、7、9日目の夜、赤子が丈夫に育つことを祈念し、邪霊祓いに粥を食べさせる真似などをする儀式)では、賽子や囲碁盤が使われていたことが紹介されます。さらに、「病気治療のための囲碁と双六」として、囲碁や双六、将棋は、占いや儀式の折ばかりではなく、なんと病気治療時にも必要とされていたことも紹介されます。
「庶民の治病」として、庶民の治療について描かれた14世紀の『春日権現験記絵』を取り上げ、著者は「疫病を患った男のもとには、民間陰陽師が描かれている。民間陰陽師とは、陰陽寮に所属していた官人陰陽師とは異なり、官職や位階を持たず民間で活動していた者たちである。彼らは、僧の姿をしていたことから法師陰陽師とも言われる。民間陰陽師も、庶民の病気治療に活躍していた。庶民は、大掛かりな修法や高僧による加持を受けることはできない。彼らの病気治療は、主に山伏や巫女、民間陰陽師らが担っていたのだろう。また、浄土真宗の開祖とされる親鸞の長男善鸞も、庶民の病気治療に携わっていたと考えられる」と述べています。
「薄れゆくモノノケへの意識」として、10世紀半ばから13世紀の史料に病気の原因として非常に多く記録されたモノノケは、依然として中世を通じて史料上に確認されるものの、次第にその数を減らしていくことが紹介されます。12世紀後期ごろより民間医が活躍しはじめ、13世紀末から14世紀には『医家千字文』や『頓医抄』、『万安方』、『産生類聚抄』など、数多くの医書が編纂されました。14世紀から15世紀には竹田昌慶や坂浄運、月湖、田代三喜らが明に渡り、先進的な医学を学んできました。著者は、「医学の発展とともに、病名や薬の種類も増えていき、医療の専門分化も進み、治病において医師の占める割合が拡大したこともあり、病気の原因をモノノケと見なすことが次第に減っていく」と述べています。
「モノノケを痛めつける赤童子」として、そもそもモノノケの調伏は、多くの場合、不動明王を本尊として行われていたことを指摘。治療をする僧は、護法を使役してモノノケを打ち責め、最終的には護法にモノノケを遠方へ追い払わせて病気を治す、と考えられたのでした。それに対して、中世後期の南都では、護法童子である赤童子を本尊とし、病気治療が願われたとして、著者は「僧の加持により赤童子を使役して治療するのではなく、赤童子像を病人の近くに懸けて祈り、赤童子に病気をもたらしたものを打たせ、平癒させることができると考えられていた。ここでは、物付も、囲碁盤も登場しない。複雑な祈繕は抜きにして、赤童子という名の護法童子に病気治療を依存するかたちとなっている」と述べます。
また、古代から中世にかけて、病気治療のあり方には変化が見られるとして、著者は「15世紀頃から盛んに信仰されるようになる赤童子には、実に簡略なかたちでの病気治療が期待されていた。モノノケ調伏のあり方が、複雑化しすぎた結果だろうか。中世後期、密教修法は、民間への浸透とともに、世俗化、平易化していく傾向にある。阿尾奢法をもとに、貴族社会を中心に行われはじめたモノノケ調伏も、その時代に有効だと考えられたものを取り入れながら変化していった。そして、中世後期になると、本来、モノノケ調伏の過程で僧に使役されていたはずの護法童子を本尊とする治療も普及するようになったのである」と述べるのでした。
第三章「祟らない幽霊――中世」の一、「霊魂ではない幽霊」では、「幽霊」という語が大いに誤解されてきたことが述べられます。古記録における「幽霊」の語の初出は、藤原道長の玄孫にあたる藤原宗忠の日記『中右記』寛治3年(1089)12月4日条です。宗忠は、道長の霊を「幽霊」と呼んでおり、「幽霊」の「成道」のために毎年12月4日には念誦しなくてはならないと述べています。なぜならば、12月4日は、道長の命日だからです。宗忠は、道長が成仏できるよう、その命日に供養をしていたのです。
三、「能での表現」では、これまで世阿弥が「幽霊」という新語を能に導入したとされてきたことが紹介されます。しかし、著者はこの説に異論を唱えます。「幽霊」という語は、すでに8世紀の史料に見え、その後の多くの史料に頻出する語であり、世阿弥が独創的に用いた新語ではないからです。著者は、「世阿弥の独創性は、『幽霊』という語を用いたことではなく、幽霊を能によって目に見えるかたちで表象したことにこそある」と述べていますが、まったく同感です。また、高橋悠介「能の亡霊と魂魄」によれば、能の曲中では、幽霊や亡霊は、墓やその者にとって重要な出来事があった場に登場し、「魄霊」と表現される傾向にあるそうです。
能における幽霊や魄霊の姿は、死後の時間の経過を示すため、老人や老女で表現されたほか、しばしば鬼の姿でも表現されました。たとえば、〈雲林院〉では藤原基経の「魄霊」は「悪鬼」の姿だとされており、〈昭君〉では「胡国」の大将韓邪将の「幽霊」は茨を頭にのせたように髪の毛の突っ立った「冥途の鬼」「鬼神」とされています。著者は、「魄霊や幽霊は、古代から中世にかけて恐れられたモノノケと似通った姿でイメージされていたと言えるだろう。能に幽霊が多く登場するようになった理由としては、14世紀からの霊魂観の転換を挙げることができる」と述べます。
佐藤弘夫『死者のゆくえ』によれば、14世紀後半からは、死後の世界のイメージが一変。この頃になると、浄土に対するリアリティが徐々に減退し、他界への往生をかつてほどには欣求しなくなっていきました。それによって、死後には墓地に安らかに眠り、子孫と交流することが願われるようになるのです。著者は、「このような状況の中、能の曲中で、墓などに出てくる幽霊が演じられるようになったのだろう」と推測するのでした。
第四章「娯楽の対象へ――近世」の一、「物気から物の怪へ」では、「怪談や霊への関心」として、近世になると、怪談が娯楽の一つとして大流行するようになることが指摘されます。著者は、「近世には、死者は墓に留まるという認識が社会的に浸透しており、生前に死者に悪事を働いたり、死後に死者の機嫌を損ねたりすれば、死者は報復行為に出ると考えられた。ただし、古代、中世の人間が死霊を心底恐れていたのに対し、近世の人間は死霊の実在に懐疑的となっていた。その上、近世は、比較的平和な時代であったこともあり、刺激が求められ怪談会が娯楽として盛んに行われたり、幽霊画が多く描かれ鑑賞されたりしたのである」と述べています。
このように死霊の実在が懐疑的に見られる中、怪談や霊について関心を抱いて言及する知識人もいました。本書には、「江戸幕府儒官林家の祖林羅山(1583~1657)は儒学者として『論語』述前篇の「子、怪力乱神を語らず」という立場にありながらも、やむを得ない場合に限って怪力乱神について語っても良く、その場合は必ず訓戒を含め人が惑うのを避けなくてはならないと言い訳めいたことを述べ、『本朝神社考』や『恠談』、『仙鬼狐談』などで怪異に関係することを書いている」「六代将軍徳川家宣のもとで幕臣となり補佐した朱子学者新井白石(1657~1725)は、朱子学の唯物論的な立場に立った上で『鬼神論』を著して鬼神(死霊、祖霊)や怪異について語り、それらを合理的に解釈しようと試みた」といった例が紹介されています。
その後、平田篤胤(1776~1843)は、白石の『鬼神論』にならって『新鬼神論』(文化2年〔1805〕。文政3年〔1820〕改稿。のちに『鬼神新論』として一部内容を改め公刊)を著し、鬼神の実在を証明しようとしました。また、大坂の町人学者山片蟠桃(1748~1821)は、文政3年(1820)に実学的合理主義の啓蒙書『夢の代』を著して新井白石の『鬼神論』を痛烈に批判し、死後における霊魂の存続や天狗、鬼、狐狸の類の実在を否定しました。
さらに、上田秋成(1734~1809)は、『万葉集』の注釈書『楢の杣』で、「鬼」の字は『万葉集』や「古書」では「もの」と読むとした上で、事例として「妖鬼」「鬼気」「鬼忌」を挙げています。また近世を代表する怪異短編集『雨月物語』(安永5年〔1776]刊行の初版本)では、「鬼化」のみではなく、「妖怪」や「妖災」にも「もののけ」とふりがなを振っています。上田秋成は怪談作家として知られていますが、国学者の本居宣長と天照大御神をめぐる論争である「日の神論争」を繰り広げたりしています。
「恐ろしくなくなる化物・妖怪」として、安永5年(1776)には、狩野派の流れを汲む鳥山石燕によって『画図百鬼夜行』が刊行され、次々と続編が刊行されるほど大変な好評を得たことが紹介されます。そもそも「百鬼」は、古代では、夜に大勢で現れ人間に災厄をもたらすものとして恐れられていました。それに対し、『画図百鬼夜行』では、「ぬうりひょん」や「ぬっぺっぽう」といった滑稽な容姿のものも含まれています。『画図百鬼夜行』のあとがきには、中国の『山海経』と狩野元信(1476~1559)の『百鬼夜行』を手本にして作ったと書かれています。
人々が眺めて楽しんだのは、手品や絵ばかりではありませんでした。近藤瑞木「化物振舞――松平南海候の化物道楽」によれば、出雲国松江の松平出羽守宗衍(1729~82)は、饗応の席で化物の姿をした者に客をもてなさせるなど、化物振舞を楽しんでおり、そのことは様々に語り継がれました。同時期には、奇形の女性の見世物も楽しまれるようになりました。香川雅信『江戸の妖怪革命』によれば、安永7年(1778)には、善光寺の阿弥陀如来の出開帳で、「鬼娘」の見世物が行われました。「鬼娘」は、頭に隆起があり、鬼のような風貌をした奇形の女性でした。近世にはこのような見世物が人気を博したのです。さらに、草双紙にも、妖怪、化物の類は非常に多く登場します。
また、和歌や俳句で死霊を成仏させるという考えが広まりました。著者は、「和歌には、霊的な力があると考えられていたのである。同様の性質は、俳句にも宿るとされた。とりわけ、多くの名句で知られる松尾芭蕉による俳句の詠吟の威力は、語るに足るものだったのだろう」と述べています。近藤瑞木「神職者たちの憑霊譚――『事実証談』の世界」によれば、近世には神職者によって書かれた怪談で、「物気」に対し神道的な方法である清祓や遷宮によって対処することが語られたそうです。モノノケ観の変容とともに、それへの対処も変遷しているのです。
二、「実在か非実在か――大流行する怪談」では、有名な『稲生物怪録』が取り上げられます。『稲生物怪録』のモノノケは、平太郎に成仏のための供養を求めることも、調伏されることもありません。さらに、帰り際に礼を言うなど、古代や中世前期のモノノケとは大きく異なります。その上、供の者を引き連れている点も異なるとして、著者は「古代や中世前期では、モノノケは個人的な怨念により病や死をもたらす死霊であることが多かったため、供の者を引き連れて現れるとは考えられていなかった。モノノケへの恐怖が現実的ではなくなった近世には、対処方法が真剣に模索されることはもはやなくなった。モノノケは、主に文芸作品で語られる対象となり、妖怪や化物とも明確には区別されなくなり、滑稽さが求められるようになったのである」と述べています。
ところが、『稲生物怪録』に異様なほどに関心を示し、「物怪」の実在の証拠にしようとした者もいました。それは、国学者本居宣長の死後の門人、平田篤胤です。「平田篤胤と『稲生物怪録』」として、霊界への関心から、篤胤が『稲生物怪録』にも大いに興味を示し、異本を三部入手して校合していることが紹介されます。篤胤の著述目録『大壑平先生著撰書目』によれば、篤胤は、「子孫の稚子等」に、世の中にはこのような物があることを知らしめ、「鬼神」の実在を立証しようとしたのです。篤胤死後、門人の手によって最終的な校合および三次での調査がなされ、文化3年(1806)に平田本『稲生物怪録』が完成しました。
吉田麻子「『稲生物怪録』の諸本と平田篤胤『稲生物怪録』の成立」によれば、篤胤が『稲生物怪録』に関心を抱いた理由は、『稲生物怪録』が実際に起きた事件を記録した著作とされていることによると推測されるそうです。というのも、『稲生物怪録』には、実在した人物や場所、建物が登場します。つまり、平田本『稲生物怪録』には、鬼神や幽冥界の実在を立証しようとする篤胤やその門下の強い意志が込められているのです。平田本の完成により、『稲生物怪録』は世に広く流布していくことになるのでした。
「平田篤胤による仏教排撃とモノノケ否定」として、篤胤が大乗仏教を強く否定する立場をとっていたことが紹介されます。それによって篤胤の主著『霊能真柱』でも、死霊が現れる事例をほとんど用いていません。それのみではなく、仏教的な文脈における事例を積極的に退けてもいます。『霊能真柱』では、地獄と極楽を見たという女に篤胤が薬を与えると、女が「仏法」を信じていることを「妖鬼」がからかってつけ込んだものにすぎなかった、とばっさり切り捨てています。
吉田真樹『平田篤胤――霊魂のゆくえ』によれば、せっかく死後の世界を追究し得るかもしれない人物と対話しているにもかかわらず、そのことは語っていないのです。モノノケ調伏は、仏教の加持や修法によって行われていませんでした。すべては「法師ども」の謀略によるものであると、モノノケの実在自体を捨象したのです。著者は、「『稲生物怪録』によって『物怪』の実在を証明しようとする行為と、かつての貴族社会で恐れられたモノノケを否定し『法師ども』の謀略だと結論づける行為は、矛盾する。仏教を否定するあまりの、なんとも皮肉な結果である」と述べています。
「双六やカルタにされたおばけ」として、近世後期には、「百種怪談妖物双六」や「おばけかるた」「化物づくし」などの玩具が人気を博すようになることが紹介されます。たとえば、累やお菊、お岩は一枚の絵が折り方によって何種類もの絵になるように作られる変わり絵に描かれています。「新板化物尽」(天保年間〔1830〜44〕頃。国立歴史民俗博物館所蔵)には、一つ目小僧やムカデの化物、雪女とともにこれらが描かれているのでした。これについて、著者は「近世によく知られた累、お菊、お岩は、変わり絵に描かれ、楽しまれた。それにしても、累やお菊、お岩が、一つ目小僧やムカデの化物、雪女とともに「化物」として描かれているのは、興味深い」と述べます。
「吸収されたモノノケ」として、平安貴族を震撼させたモノノケは、近世になると妖怪、化物、幽霊、お化けの類と明確な区別がなされなくなり、娯楽化させられていくことを指摘。その上、「物怪」(物気)という語は、『源氏物語』や『栄華物語』といった古代の物語を論じる文脈以外では、古代や中世前期ほどには頻繁に使用される語ではなくなくなりました。著者いわく、モノノケは、妖怪や化物、幽霊に吸収されていったのです。
モノノケは、中世後期に入り、医療の発達に伴い病気の原因とされる割合が減少していきました。それによって、モノノケへの恐怖は、薄れていきました。一方、怪異を表す語であった「妖怪」は、中世後期に、化物と重ね合わせて捉えられるようになり、怪異を引き起こす存在そのものとしての意味も付与されていきます。さらに、死霊や死者を指す語であった「幽霊」は、怨念を持ち現れ出る恐ろしい死霊としての性質を新たに持たされるようになったとして、著者は「新しく出てきた『妖怪』『幽霊』に、消えかけた古い語『物気』は、『物怪』とされて飲み込まれていったのではないだろうか」と述べるのでした。
第五章「西洋との出会い――近代」の一、「迷信の否定と根強い人気を誇る怪談」では、「淫祠邪教と迷信の撲滅」として、江戸幕府滅亡の前後で、陰陽師や憑祈禱などに対する公の扱いが大きく変わったことが紹介されます。高木博志『近代天皇制の文化史的研究――天皇就任儀礼・年中行事・文化財』によれば、近世後期における宮中の正月行事や即位式では、在地の陰陽師が奉仕していました。それによって、朝廷と特別な関係を持っていた彼らには、国名や苗字、呼名、帯刀が許されていたのです。ところが、遷都後、陰陽師らは、東京の宮中正月行事から排除されることになったのでした。その上、明治3年(1870)には、「天社神道廃止」の太政官布告が発令されます。全国の陰陽師を管轄していた土御門家は諸国の陰陽師を支配することを禁止され、陰陽師は歴史の表舞台から姿を消していきます。明治政府の神道国教化政策による神仏分離令や修験道廃止令などの先陣をきるものでした。
「『お化け博士』井上円了」として、近代に様々な不可思議な現象を収集し、多くの迷信を否定した代表的な人物の一人に、「お化け博士」や「妖怪博士」の異名を持つ井上円了(1858~1919)が紹介されます。円了は、迷信や怪奇現象を解明することにより、それに怯える人々の不安や恐怖を拭い去ることができると考えました。竹村牧男『井上円了その哲学・思想』によれば、円了は、西洋視察ののち、明治20年(1887)に哲学館(のちの東洋大学)を開設して妖怪学の講義を設けたり、全国で妖怪学に関する講義を行ったりし、明治26年(1893)には『妖怪学講義』を刊行して研究の成果を公にしました。
井上円了とは目的を異にして妖怪を研究する学者もいました。民俗学者の柳田國男(1875~1962)です。柳田は、民俗学の中での妖怪学の必要性を説き、『遠野物語』(明治43年〔1910〕)をはじめとする多数の著作を残したことで知られていますが、著者は「柳田は、もはや妖怪(お化け)の有無は問題ではないと主張し、妖怪や幽霊などを研究対象とすることにより、それを信じた人々の思考構造を知ろうとしたのであった」と述べます。
また、怪談や迷信は、明治政府や知識人から否定される中、大衆向けの読み物で語られ続けました。民俗学者で妖怪研究者の湯本豪一(1950~)は、明治年間に発行された新聞を調べ、『明治期怪異妖怪記事資料集成』(2009年、国書刊行会)にまとめました。本書に取録された怪異や妖怪に関する記事は、約4400件に上ります。怪異や妖怪は、明治政府の政策とは逆行するものの、相変わらず求められ続けたのでした。
「西洋の幽霊研究とその影響」として、日露戦争(明治37~38年〔1904~05)後、戦争による大量死を背景に、霊魂の実在や死の問題が人々の興味関心を集めるようになったことが紹介されます。夏目漱石(1867~1916)の『琴のそら音』(明治38年)には、主人公が、「幽霊と雲助」は明治維新以来「廃業」したと信じていたのに、知らない間に「再興」されたようであり、心理学者が幽霊を「再興」していると思うと馬鹿にはできなくなる、と困惑する場面があります。この頃は、欧米の幽霊研究の影響を大いに受けた時期で、英学者の平井金三(1859~1916)らは、欧米の科学的心霊研究の影響を受けて、幽霊研究会(心霊的現象研究会)を発足させました。
西洋の心霊写真なども、新聞に取り上げられて話題となりました。著者は、「文明開化により幽霊などの否定がなされた一方で、西洋における幽霊や霊魂の実在を肯定する研究が紹介され、その影響も大いに受けたのであった」と述べています。しかし、江戸以来のモノノケを好む作家もいました。「おばけずき」を自認し怪異に関わる小説も多く書いた泉鏡花(1873~1939)です。鏡花の作品にも、モノノケが出てきます。明治41年(1908)、泉鏡花は、『稲生物怪録』に深い関心を寄せ、『草迷宮』を刊行。『草迷宮』で語られる秋谷邸の怪異は、『稲生物怪録』をもとにしています。
三、「西洋文化受容の影響」では、日本古代の霊魂に関する研究も、西洋文化の影響を大いに受けたことが指摘されています。国文学者・民俗学者の折口信夫(1887~1953)は、人間に災いをもたらす低級な神を「デモン」あるいは「スピリット」として捉えました。保坂達雄「折口名彙の生成」(『神と巫女の古代伝承論』所収)によれば、「たま」や「かみ」「もの」といった古代の霊魂信仰を整理した折口の所説に従うと、「デモン」や「スピリット」は「もの」に相当することになります。つまりは、モノノケの「もの」なのです。学問の世界でも、モノノケは西洋文化と無縁ではありませんでした。
終章「モノノケ像の転換――現代」では、戦後のモノノケには、人里離れた自然に棲むとされるものが多いことが指摘されます。高度経済成長期になり、妖怪を楽しむ余裕が出たこともあり、妖怪が流行するようになります。その火付け役は、水木しげる(1922~2015)でした。平林重雄『水木しげると鬼太郎変遷史』によれば、水木しげるの代表作「鬼太郎」は、昭和29年(1954)に紙芝居作品『墓場鬼太郎』によって誕生し、漫画版『ゲゲゲの鬼太郎』のルーツとなる『幽霊一家 墓場鬼太郎』(昭和35年〔1960〕に貸本専門誌『好奇伝』に掲載)、さらには兎月書房から怪奇専門誌『墓場鬼太郎』が創刊され、水木の鬼太郎も『墓場鬼太郎』シリーズとして連載された。その後、兎月書房版『墓場鬼太郎』シリーズの続編にあたる『鬼太郎夜話』が三洋社から出されました。
「社会から取り残されたアウトサイダー」として、戦前に引き続き、戦後のモノノケのイメージは、実に曖昧であることを指摘し、著者は「興味深いことに、水木しげる『鬼太郎夜話』からは、モノノケは必ずしも人間を脅かすのではなく、人間社会とは隔絶した自然の中にひっそりとすむイメージでも捉えられるようになっていたことが分かる。妖怪や幽霊が多く語られる一方で、奇しくも水木の「物の怪」が嘆くように、モノノケは華々しい表舞台から裏方に追いやられ、絶滅が危惧される状況となっていた。そのような状況によって、モノノケは、孤島、森、といった自然の中に追いやられるようになったのだろう」と述べています。
「人間との対立と共生」として、現在、モノノケというと、平成9年(1997)に公開された宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」のイメージが強いことが指摘されます。「もののけ姫」は、公開から翌年夏までに1300万人もの観客を集め、配給収入113億円という記録的大ヒット映画となりました。日本の中世後期を舞台に、森に棲む荒ぶる神々(もののけ)と森を侵略しようとする人間の壮絶な闘いと共生が描かれた物語ですが、著者は「『もののけ姫』の『もののけ』は、人間の侵略から森を死守しようとする太古からの神々である。『泥汽車』のモノノケとは、荒ぶる性質を持つ点で異なるものの、通じるものがある。モノノケは、怨念を持つ霊として認識される一方で、人間世界とは一線を画す森に生きる精霊、神としての定着したイメージを持たされるようになったのだと言えよう」と述べます。
「拍車がかかるキャラクター化」として、妖怪のキャラクター化は、妖怪ウォッチの登場によって拍車がかかったことが紹介されます。妖怪ウォッチは、レベルファイブ制作のロールプレイングゲームです。ゲームに先行して平成24年(2012)に『月刊コロコロコミック』で連載されました。著者は、「ゲームでは、猫や犬などの生き物が妖怪となったものが、妖怪の種族の一つである『モノノケ族』として分類されている。ちなみに、『モノノケ族』には、トラックに轢かれて死んだ猫の地縛霊、ジバニャンも分類されている」と説明します。
「モノノケの歴史的意義」として、古代から中世にかけては、モノノケは病や死をもたらす死霊であることが多かったことが指摘されます。著者は、「病気の原因を現在のようには明らかにし得なかった時代、モノノケを病気の原因として捉えることによって、治療法を編み出すことが可能になった。また、虐げられ怨念を抱いて死んでいく人間に、死後の復讐という希望を与えることにもなる。それによって、モノノケは、共同体の不調和を是正する役割も担っていたことだろう。他者を害する極端な言動は、被害者の親族の霊などを意識することによって、多少なりとも自重されることもあったと考えられる」と述べます。
近世になると、モノノケは幽霊や妖怪と混淆し、主に文学作品の中で語られ、娯楽化していく傾向にありました。その実在は否定されつつも、比較的平和な時代であったが故に刺激が求められ、語られたのです。近代から現代にかけては、西洋文化の影響を受けたこともあり、モノノケの意味するところは多様となったとして、著者は「モノノケは、人間に取り憑く霊としての性質も残しつつ、自然を守る神としての意味合いまで持たせられるようになったのである。また、モノノケは、妖怪と重ね合わせて捉えられる傾向が強まり、キャラクター化され、人間に寄り添い、時には人間には持ち得ないパワーで人間を助けるものとされるようになっていった」と述べるのでした。
「あとがき」では、本書を書いた動機について、「古代から現代まで途切れることなくモノノケに関する事柄が記録され、あるいは語られてきた以上、一度は通史で概観しておく必要があるのではないか。その作業は、日本人の心性を考察する上で不可欠なのではないか」と述べています。モノノケに関する史料の読解・分析は、各時代における人間の心奥の変遷をのぞき込む作業に他ならなかったとして、著者は「モノノケあるいは妖怪は、人間に寄り添い助ける役割まで担うようになってきている。核家族化が進み個を重んじる現代社会では、人間関係は稀薄になりがちである。このような時代だから、人間以外のモノによる癒やしが求められているのかもしれない」と述べます。
2020年、新型コロナウイルスが世界中を震撼させました。新型コロナウイルスが恐れられる中、日本では、半人半魚の姿をしたアマビエの絵を描けば(もしくは見れば)疫病に罹患しないとする伝説が話題となり、妖怪アマビエが人気を博しました。まさに、人間が人間以外のモノに癒やしを求めたのです。著者は、「その効果を心から信じる人は少ないだろうが、混沌とした状況の中、アマビエには、不安な心に平安や和らぎをもたらす効果がある。先が見えない現代には、不可思議なモノの持つ超人間的なパワーが、求められているのである」と述べるのでした。この著者の言葉に100%共感します。「死霊、幽霊、妖怪の1000年」を綴ったモノノケの通史を、これから何度も読み返したいと思います。