- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2018 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『忘れじの外国人レスラー伝』 斎藤文彦著(集英社新書)
2021.03.19
『忘れじの外国人レスラー伝』斎藤文彦著(集英社新書)を紹介します。著者は1962年東京生まれのプロレス・ライターです。プロレスラーの海外武者修行にあこがれ17歳で単身渡米。1981年より取材活動。「週刊プロレス」(ベースボール・マガジン社)創刊時から契約記者として参画。外国人選手のインタビュー記事、巻頭特集記事、別冊編集長などを担当しました。一条真也の読書館『プロレス入門』、一条真也の読書館『ブルーザー・ブロディ 30年目の帰還』で紹介した本の著者でもあります。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、ダイナマイト・キッド、ザ・ロードウォリアーズ、アンドレ・ザ・ジャイアント、ビッグバン・ベイダーの在りし日の雄姿の写真とともに、「レジェンド10人の黄金時代と、知られざる『最期』」「ゴッチ、デストロイヤー、アンドレ、ロビンソン、キッド、ゴーディ、ビガロ、ベイダー、ホーク、ウィリアムス」とあります。
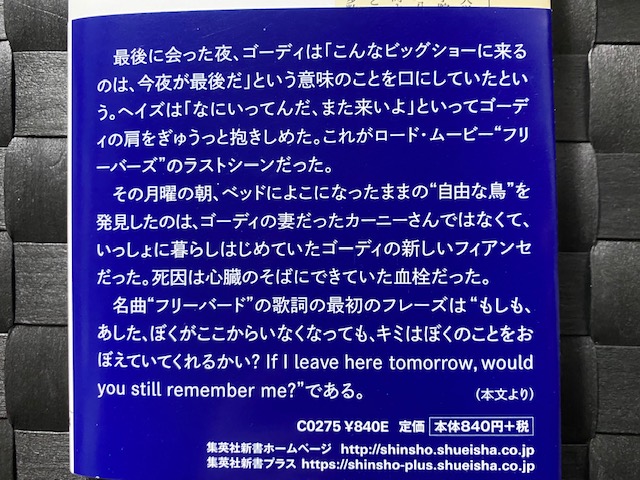 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。「最後に会った夜、ゴーディは『こんなビッグショーに来るのは、今夜が最後だ』という意味のことを口にしていたという。ヘイズは『なにいってんだ、また来いよ』といってゴーディの肩をぎゅうっと抱きしめた。これがロード・ムービー‟フリーバーズ”のラストシーンだった。その月曜の朝、ベッドによこになったままの‟自由な鳥”を発見したのは、ゴーディの妻だったカーニーさんではなくて、いっしょに暮らしはじめていたゴーディの新しいフィアンセだった。死因は心臓のそばにできていた血栓だった。名曲‟フリーバード”の歌詞の最初のフレーズは”もしも、あした、ぼくがここからいなくなっても、キミはぼくのことをおぼえていてくれるかい?If leave here tomorrow,would you still remember me?”である。(本文より)」
本書のカバー前そでには、「カール・ゴッチ、ザ・デストロイヤー、アンドレ・ザ・ジャイアント、ビル・ロビンソン、ダイナマイト・キッド、テリー・ゴーディ、スティーブ・ウィリアムス、バンバン・ビガロ、ビッグバン・ベイダー、ロード・ウォリアー・ホーク――。昭和から平成の前半にかけて活躍し、今はもう永遠にリング上での姿を見ることが叶わない伝説の外国人レスラー10人。本書は今だから明かせるオフ・ザ・リングでの取材秘話を交え、彼らの黄金時代はもちろんのこと、知られざる晩年、最期までの『光と影』を綴る」との内容紹介があります。
本書の「目次」は、以下の通りです。
プロローグ In Memoriam
第1章 “神様”カール・ゴッチ
第2章 “白覆面の魔王”ザ・デストロイヤー
第3章 “大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアント
第4章 “人間風車”ビル・ロビンソン
第5章 “爆弾小僧”ダイナマイト・キッド
第6章 “人間魚雷”テリー・ゴーディ
第7章 “殺人医師”スティーブ・ウィリアムス
第8章 “入れ墨モンスター”バンバン・ビガロ
第9章 “皇帝戦士”ビッグバン・ベイダー
第10章 “暴走戦士”ロード・ウォリアー・ホーク
エピローグ At the end of the day
「プロローグ「In Memoriam」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「ぼくはプロレスラーはヒーローHeroなんだと考えている。ヒーローは英雄だったり人気者だったり物語の主人公だったりする。歴史上のヒーローがいて、スポーツのヒーローがいて、文化や芸術、科学や思想のヒーローもいるだろう。実在の人物の場合もあるし、架空のキャラクターの場合もある。プロレスのヒーローたちは、英雄であり人気者であり物語の主人公である。もちろん、スポーツのヒーローだし、プロレスを文化や芸術とカテゴライズするならば、プロレスラーは文化的なヒーロー、芸術的なヒーローだととらえることもできる」
続いて、著者は「プロレスラーはみんな実在の人物ではあるけれど、リング上で起こることや観客のまえでディスプレイされる人格についてはフィクションだったり架空のキャラクターであったりする場合もある」と述べ、さらには「プロレスとは虚実皮膜――芸は実と虚の皮膜の中間にある、事実と虚構の微妙な接点に芸術の真実がある、という近松門左衛門の論――のジャンルといわれ、ファクトとフィクションの境界線がわかりにくい。もっとわかりやすくいえば、現実とファンタジーがごちゃ混ぜになっていて区別がつきにくい。そして、そのなんだかよくわからないところがプロレスなのである、というコンニャク問答そのものがプロレスの醍醐味だったりする」と述べます。
著者は、今はもうこの世にはいない10人のレジェンド・レスラーの名前を挙げ、「ヒーローは死んでも生きている、なんていうとずいぶんヘンな日本語になるけれど、この本に登場する10人の外国人レスラーたちはぼくたちの心のなかにちゃんと生きている。古いVHSのビデオを引っぱりだしてくれば彼らの試合をまた観ることができるし、ユーチューブで検索すればいろいろな映像にもめぐり逢える。ぼくはいつもこう感じている。プロレスラーには、‟この世”と‟あの世”の境界線はないのかもしれないと――」と述べるのでした。
本書は外国人レスラーたちの墓碑銘のような内容ともなっていますが、1人づつレスラーを取り上げた各章の最後には、葬儀や墓について紹介しています。たとえば、第1章「”神様”カール・ゴッチ」の最後、ゴッチは生前から火葬を希望しており、遺言どおりその遺骨は亡妻の遺骨とともに、愛弟子ジョー・マレンコの手でタンパのキーストーン湖に散骨されたことを紹介し、著者は「ゴッチの没後10年にあたる17年、アントニオ猪木、ゴッチとゆかりの深い木戸修、藤原喜明、西村修が発起人となり『カール・ゴッチ墓石建立プロジェクト委員会』が立ち上げられ、分骨されていた遺骨の一部を手にジョー・マレンコが来日。命日にあたる7月28日、東京・南千住の回向院に納骨された。ゴッチを”神様”として尊敬し、またゴッチ自身も心を許した友人たちの住む日本の地に、”神様”のお墓が建てられたのである」と書いています。
第3章「”大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアント」では、アンドレを投げたプロレスラーたちについて、「公式記録のようなものはなく、映像に残されている試合とそうでない試合とがあるが、モントリオール時代はブッチャー・バションが、日本では国際プロレスのリングでストロング小林が、新日本プロレスでアントニオ猪木と長州力が、メキシコではカネック、ヨーロッパではローラン・ボックがそれぞれアンドレをボディースラムで投げた。アメリカ人レスラーでは70年代後半から80年代にかけてハーリー・レイス、ハルク・ホーガン、スタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディ、アルティメット・ウォリアーらスーパースターがタイトルマッチやビッグマッチで、あまり知られていないところではブラック・ジャック・マリガン、マスクド・スーパースター、ジャイアント・キマラらスーパーヘビー級の男たちが”大巨人”をボディースラムでキャンパスに叩きつけた」と紹介しています。
同章の最後には、”大巨人”が1993年1月27日にパリで亡くなったことを紹介し、著者は「アンドレは顧問弁護士に託していた遺書のなかで『死後48時間以内の火葬』を希望していたため、アンドレの最後の滞在先となったパリのホテルは葬儀場を探したが、身長7フィート4インチ、体重500ポンドのアンドレの体を火葬する場所が見つからず、”大巨人”の遺体は300ポンドの特注オーク材の棺に納められ、貨物用エアカーゴでアメリカに送り返された。大きな骨つぼに納められた19ポンド(約8.6キロ)の遺骨は、アンドレが所有していたノースカロライナ州エラビーの敷地面積200エーカー(約24万5000坪)の広大なぼくじょうの土となったのだった」と書いています。
カール・ゴッチやアンドレ・ザ・ジャイアントをわたしが初めて知ったのは国際プロレスのテレビ中継。わたしが住む九州では放送されていなかったと記憶しているのですが、千葉にあった父の実家に帰省したとき、祖父が興奮しながら、テレビで国際プロレスの試合を観ていたのです。当時、アンドレはモンスター・ロシモフという名前でしたが、カール・ゴッチ、ビル・ロビンソンというヨーロッパ流のテクニシャンを相手に三つ巴で闘っていました。3人の中で、わたしが一番好きだったのはロビンソンでした。
一条真也の読書館『最強の系譜』で紹介した名著には、‟蛇の穴”こと英国マンチェスター郊外ウィガンのビリー・ライレー・ジムでゴッチやロビンソンが修行したことが詳しく書かれていますが、本書の第4章「”人間風車”ビル・ロビンソン」でも、「‟神様”カール・ゴッチは、50年代前半にロビンソンの伯父アウフ・ロビンソンの招きでウィガンに移り住み、‟蛇の穴”でサブミッション(関節技)の技術を身につけた。この道場でゴッチがロビンソンをレスリングのケイコでぐしゃぐしゃにしたという‟伝説のスパーリング”がおこなわれたとき、ロビンソンはまだ15歳で、すでにプロレスラーとしてデビューしていたゴッチは29歳だった」
現在のプロレスのルーツであるレスリングは、中世以降にヨーロッパのイギリス語圏とフランス語圏で大きな発展をとげたとして、著者は「イギリスには大きく分けて4種類から5種類のフォーク・レスリング――その地方ごとに発祥・伝承させる伝統的なレスリング。これをどう分類するかは民俗学の領域とされる――が存在した。カンバーランド・スタイル、ウェストモーランド・スタイル/デボンジャー・スタイル、コーニッシュ・スタイル、そしてランカシャー・スタイルがその源流である」と紹介しています。
ロビンソンが生涯の学習としたランカシャー・スタイルのキャッチ・アズ・キャッチ・キャンは、イギリスのフォーク・レスリング群の中でも最も実戦的なフォームであるという著者は、「ここでいう実戦的とは、どんなスタイルのレスリング(あるいは異文化の格闘技)との闘いにも対応できるひとつの型を指す。21世紀のMMA(ミックスト・マーシャル・アーツ)にもつながっていく。‟なんでもあり”の闘いの範ちゅうでは、最終的には体と体を密着させての関節技が戦意喪失の意思表示(ギブアップやタップアウト)を導きだすという結論はいまも昔も変わらないということなのだろう」と述べています。
第9章「”皇帝戦士”ビッグバン・ベイダー」では、61歳になったベイダーが、16年11月、おそらくおぼえたてであろうツイッターで「先天性の心臓疾患でドクターから‟余命2年”を宣告されたこと」を全世界に向けて発信したことを紹介し、著者は「それども、翌年の17年4月には藤波辰爾主宰のドラディションのミニ・シリーズ興行のために来日。シリーズ最終戦の大阪大会では藤波、長州とトリオを組んで藤原喜明&越中詩郎&佐野巧真と6人タッグマッチで対戦した。これが生涯最後の試合となった。領国国技館での”暴動”デビュー戦から30年の歳月が経過しようとしていた。ビッグバン・ベイダーというプロレスラーは日本のリングで生まれ、日本のリングでその命をまっとうした。まるで日本のファンにお別れを告げにきたような短い旅だった」と書いています。
エピローグ「At the end of the day」では、本書に登場するロード・ウォリアー・ホーク、バンバン・ビガロ、テリー・ゴーディ、スティーブ・ウィリアムスらと著者はほぼ同年代で、彼らがプロレスラーとして最も輝いていた時代をリアルタイムで目撃することができたと告白しています。著者は1962年生まれなので、わたしの1つ年長であり、わたしも同世代と言えるでしょう。しかしながら、著者の場合は彼らと友だちとしてたくさんの時間を過ごすことができたそうです。この4人の他にも、デイビーボーイ・スミス、ダグ・ファーナス、クリス・ベンワー、エディ・ゲレロといった同世代のスーパースターたちが若くしてこの世を去ったことを紹介し、著者は彼らの死を悼みます。
しかし、著者は「ちょっとカッコよすぎるかもしれないけど、彼らが歩んだそれぞれの道――それが長かったか短かったかはわからないけれど――をずっとすぐそばで見ることができたぼくは‟生”というものと‟死”というものをできるだけ客観視しようと考えるようになった。もちろん、トシをとらずに死ぬよりも1日だって長く生きたほうがいいに決まっているけれど、肉体的な‟死”は必ずしも‟死”そのものではないのではないか。偉大なるプロレスラーの‟生”は、プロレスを愛する人びとのなかで永遠の命として生きつづけているのではないか。そして、ぼくたちは、彼らのプロレス、彼らのリング上の姿、彼らが生きた時代をしっかりと記憶しておくことで、彼らとずっとずっと‟生”を共有することができるのではないだろうか――」と述べるのでした。本書から、著者の限りないプロレス愛を感じました。