- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.07.05
『易経入門』氷見野良三著(文春新書)を読みました。「孔子がギリシア悲劇を読んだら」というサブタイトルがついています。著者は、1960年富山市生まれ。83年に東京大学法学部卒業、大蔵省入省。ハーバード・ビジネス・スクールMBA。バーゼル銀行監督委員会事務局長、金融庁証券課長、銀行第一課長、金融庁総務企画参事官(国際担当)を経て、2016年に金融国際審議官、19年に金融安定理事会規制監督上の協調に係る常設委員会議長、そして2020年に金融庁長官に就任しています。「霞が関一の教養人」と呼ばれているそうです。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、孔子とギリシャ悲劇の登場人物のイラストが描かれ、「こんな時代だからこそビジネスマン必読」「丹羽宇一郎 中国大使推薦」「人生、人智の及ばぬこともある――その解は『易経』にあり」と書かれています。
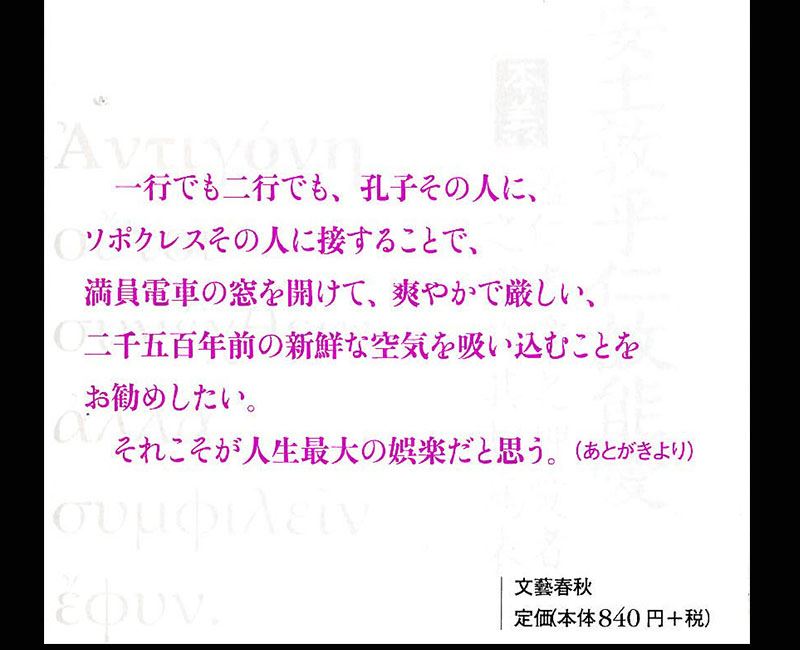 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「一行でも二行でも、孔子その人に、ソポクレスその人に接することで、満員電車の窓を開けて、爽やかで厳しい、二千五百年前の新鮮な空気を吸い込むことをお勧めしたい。それこそが人生最大の娯楽だと思う。(あとがきより)」と書かれています。また、カバー前そでには、「性格の異なる人びとが互いにどう反応しあうか、そのパターンを分類し、その人、その場に応じたアドバイスを与える経典『易経』。ギリシア悲劇の登場人物に易経のアドバイスを聞かせてみたら?東西思想の対話を試みる、比較文学の冒険」との内容紹介があります。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 対話の方法
一 易経の構成
二 対話の方法
三 「占いの書」か「義理の書」か
四 予言の力? 後知恵? 人類の共通感覚?
第二章 テーバイ王家の物語
一 オイディプス
二 コロノスのオイディプス
三 アンティゴネ
第三章 ヘラクレス夫妻の最期
四 トラキスの女たち
第四章 トロイア戦争の物語
五 アイアス
六 ピロクテス
七 エレクトラ
第五章 ソポクレスと孔子
「あとがき」
「はじめに」の「易経とは何か」では、今から5000年ほど前、中国の皇帝・伏羲(ふぎ)が64の卦(か)を作ったとして、著者は「伏羲から2000年を経て、今から3000年ほど前、周の文王とその子周公旦が、64通りの卦のそれぞれの意味を説明した経文を作った。それから更に500年を経て、今から2500年ほど前には、孔子が経文の注釈である十篇の文書『十翼』を書いた。2500年の間に出現した聖人中の大聖人四人の思索が、こうして時を隔てて呼応し合い、結晶したのが、現在伝わる『易経』である、という」と述べています。
易経は、しばしば占いの本として用いられていますが、原典は必ずしもおみくじ集のような体裁にはなっていないと指摘し、著者は「まず、ある状況下の6人の主要登場人物の特性が、それぞれ陰か陽かを検討し、その六つの組み合わせによって、状況の特性を判断する仕組みになっている」と説明します。また、「闘い苦しむ人びとのための詩篇」では、孔子が十翼を作ったころ、ギリシアでは偉大な悲劇詩人たちが、理科の実験のように明晰な劇を作っていたとして、著者は「登場人物は限られていて、それぞれが明確な性格を持ち、必然的な化学反応を起こして、結末へと流れ込んでいく。これも易経同様、複雑な現実から骨格のみを抜き出した一種の抽象化であり、私たちの住むこの現実世界の持つ特性を理解するための簡素な模型のような姿をしている」と述べます。
「ソポクレスと孔子は対話する」では、ある秋の夜、著者がベッドに腹這いになってソポクレスの『アンティゴネ』を読み終え、様々な印象を心の裡に整理できずに悶々とするままに、気まぐれに手近の反故の隅に登場人物を並べて易の六爻に対応させて、易経の「渙」の卦のところの経文を開いてみたときの驚きが書かれ、「驚きは『オイディプス王』、『コロノスのオイディプス』と続いた。なぜ、易は、『アンティゴネ』の物語に対して「国がばらばらになる」と答えるのか。『オイディプス王』に対して『娶るな』と答えるのか。『コロノスのオイディプス』に対して、困苦を通じて得られる徳のことを語るのか。主要登場人物6名の吉凶をそれなりに言い当てるのか。64の卦、384の爻の中から、いかにもこれしかないと思われるような卦・爻に一発で辿り着き、そして、それが読む作品、読む作品と続くことの衝撃」と述べています。
こうした実験の結果の報告が本書であるとして、著者は「現存するソポクレスの作品7篇全てについて、作品の主題に沿って、易経の卦でいえば何に当たるかを臆断し、易の言うところに耳を傾け、各登場人物に易のアドバイスを聞かせてみる。ソポクレスの作品は、『6名程度の主要人物の相互作用が1つの纏まった運命事象を構成する』という易経の枠組みと似た構造を有している。『主人公を運命の超越的な力と戦わせることによって人間の自由を讃える』(シェリング)というギリシア悲劇の性格を最も明確に示しており、運命との付き合い方を研究した経典である易経との対話に適している。易もギリシア悲劇も、現実世界の法則を非情にありのままに見つめるところでは似通っており、甘いことを言わないギリギリ核心の強さで数千年を生き抜いてきた古典同士である。結構話が合ったって、おかしくないではないか」と述べています。
「本書の実験結果」では、易経の言葉は謎めいていて分かりにくいが、ギリシア悲劇の状況に当てはめてみれば、その意味するところの具体的なイメージが得られるとして、著者は「易の384爻が、あるいは砂嵐の後の荒野に一人立って青銅の水差しを高く掲げるアンティゴネの姿となって、あるいは花の飾りをつけた小枝を手に宮殿の祭壇に祈る豊かで大きなイオカステとなって、あるいは森の奥へとぐいぐい歩みを進める盲目の廃王オイディプスとなって、浮かび上がってくる。逆に、ギリシア悲劇における登場人物間の力学や運命の構造も、易経への当て嵌めを通じてくっきりと見えてくる。7篇を精読し易に当てはめていけば、年代を追ってソポクレスの思想がどう変化したか、易とギリシア悲劇の考え方の違いが孔子とソポクレスの生涯の違いとどのような関係にあるかまで見えてくる。そう主張する」と述べるのでした。
第一章「対話の方法」の「現存ソポクレス全7篇を読む」では、著者は以下のように説明しています。
「ギリシアの三大悲劇作家は、早く生まれた順に、アイスキュロス、ソポクレス、エウリピデスである。それぞれ90篇、123篇、92篇もの作品を著したが、現存するのはアイスキュロス7篇、ソポクレス7篇、エウリピデス19篇の計33篇だけである。以下では、このうちから、ソポクレスの現存作品7篇全篇を読む。7篇を、テーバイ王家の運命に関するもの3篇、ヘラクレス夫妻の最期に関するもの1篇、トロイア戦争に関わるもの3篇に分け、描かれている物語の時系列の順に読み、易経との対話を試みる。作品の成立順とは一致しない」
一「易経の構成」の「当たるも八卦、当たらぬも八卦」では、「中国の儒者は、経文の全体を一字一句そらで覚えていたのみならず、孔子以降、2500年に亙って、解釈の工夫を積み重ねてきた。諸家の説を整理した書物も各時代に編纂されている」として、孔子が、易の総論で、易の内容の広大であることを「易という書物は、広大無辺な天地にぴったりと符合しており、従って、天地の間の道に遠く行き渡り、天地の間の道を筋道を立てて整理することができる(易は天地と準う。故に能く天地の道を弥綸す)」(繋辞伝)と述べたことが紹介されます。
「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず」では、易の経文は、一見謎めいており、古来様々な解釈がなされてきたことが指摘され、著者は「どうとでもとれる言葉を都合よく解釈して恣意的に対話を成り立たせるのであれば、易とギリシア悲劇の対話ではなくて、易の解釈者とギリシア悲劇の対話になりかねない。そんな作業に意味があるのだろうか。易経は無限に多様な現実を一旦抽象的な陰と陽の関係に整理し、その抽象的な関係に共通な特性を象徴的に表現することにより、再び無限に多様な現実への適用を可能にする」と述べます。
このあたりの事情を孔子は易経の中で、「書は言を尽くさず、言は意を尽くさず。然らば即ち聖人の意は其れ見る可からざるか。聖人、象を立てて以って意を尽くし、卦を設けて以って情偽を尽くす(書物は人の言葉を残らず書き尽くせるものではないし、言葉は人の思っていることを残らず言い尽くせるものではない。では、我々には聖人の思想の全貌を知ることは許されていないのか。いや、〔易経で〕聖人は象徴的な表現で思想を包括的に表現し、64の卦を作り出してそれであらゆる事情をカバーできるようにしたのだ)」(繫辞伝)と述べています。
三「『占いの書』か『義理の書』か」の「明治の元勲と易」では、易経は、「占いの書」として生まれ、孔子によって、「出処進退の道を説く義理(道理)の書」として読み替えられたと指摘し、著者は「宋の程伊川は『義理の書』としての読み方を大成したが、南宋の朱子は両側面を見つつ、『占いの書』としての側面に重点を置いた。多くの人は現在に至るまで『占いの書』として読んでいる」と述べています。
四「予言の力? 後知恵? 人類の共通感覚?」の「ユング的な予言の力」では、易経に予言の力があるという説を展開した代表選手にユングがいることが紹介されます。ユングは、易経をドイツ語に訳した中国学者リヒアルト・ヴィルヘルムとの思い出を語って、「私のように、ヴィルヘルムとの精神的交流によって『易経』のもっている予言的力能を経験するというめったにない幸運を得た人間にとっては、われわれがここで、西洋の精神的態度を根底からくつがえしてしまうアルキメデスの点にふれているのだという事実は、もはや隠れたままでいることはありません。(中略)われわれが、『易経』の今もなお生きてはたらいている力を体験するかぎり、われわれは単におどろいたり批判したりする傍観者の立場にとどまることなく、東洋の精神に参与する者になっているのです」と述べています
「ギリシア悲劇は易だ」では、ソポクレスと易経を突き合わせて読んでいると、この世界の諸現象の背後で運命の進行を司っている生命体の粘膜に触れるような奇妙な感触を覚えることがあると告白し、「ソポクレスと易経は同じ生き物のことを描いているから話が合うのではないか。そういう風にいうと、ユング的、オカルト的に聞こえるかもしれないが、例えば、『人間が運命に対して持つ共通の感覚が、類似の物語を東西の古典双方に取り上げさせた』とは考えられないだろうか。我々は、ギリシア悲劇に近い筋のドラマを見ると、ギリシア悲劇のことを全く知らなくても、何か古典的なものに触れているという感じを受ける。偶然や恣意で出来た物語にではなくて、何か大事な基本類型に触れている、という感じを受ける」と述べます。
これは、人間というものに、人の運命の典型的な展開についての共通の感覚があるからではないのかと考える著者は、「ギリシアの都市国家でも、中国の都市国家でも、長い歴史の中で、そうした感覚に沿って幾つもの典型が神話なり物語の形に精錬されていった。そうした物語を、ソポクレスは悲劇の形に生かし、中国の聖人たちは64の卦に整理した。易経の経文は謎めいているものの、背後には神話的な物語があり、その物語は人間の持つ共通の感覚によって選ばれたものなので、ギリシア悲劇の選んだ神話的な物語と類似した構造を有している。このため、ギリシア悲劇の基本的な構造を示す信号をもとに卦を探していくと、似たような物語に辿り着く。……こうした仮説は考えられないだろうか」と読者に問いかけます。
さらに、「予言の力か、後知恵か、人類の共通感覚か」と問う著者は、比較文学の泰斗ジョージ・スタイナーは、一握りのギリシア神話が、20世紀の芸術や思想のなかでも、ほとんど強迫観念のように繰り返し議論され、翻案され、模倣されている理由を問い、「ギリシア神話は人類史における基本的な生物学的および社会的な対立と自己認識のいくつかを記号化したものである。それは集団的記憶と集団的認識のなかで、生きた遺産として生き続けているのだ」「ギリシア神話は一種の速記記号であり、簡潔であることから無限の変化を生むが、それ自身はわざわざ再発明する必要がない」と答えたことについて、「わたしには、スタイナーが『ギリシア悲劇は易だ』といっているかのように聞こえる」と述べます。
「君子、楽しみて玩ぶところのものは爻の辞なり」では、著者は「ギリシア悲劇と易の共通の感覚は、運命の動きに関する真実の法則までを捉えたものか。予言の力を持つものか」と問い、孔子が繫辞伝で、「宇宙の真実を見出して易経を立てるのは聖人の仕事、立てられた易経の言葉を玩ぶのは君子の楽しみだ(「聖人、卦を設け、象を観、辞を繫けて、而して吉凶を明らかにす」「君子、居りて安んずる所の者は、易の序なり。楽しみて玩ぶ所の者は、爻の辞なり」)」と述べていることを紹介し、「本書では、聖人の仕事よりは君子の楽しみを目指し、真にオカルト的な、より刺激的な問題の検討の方はとりあえず脇において、まずは比較文学的な東西の対話、考え方の比較に専念することとしたい」と述べるのでした。
第二章「テ―バイ王家の物語」では、易経は、「占いの書」として生まれ、孔子によって、「出処進退の道を説く義理の書」として読み替えられたと指摘し、著者は「宋の程伊川は『義理の書』としての読み方を大成したが、南宋の朱子はむしろ『占いの書』として読んだ。多くの人は現在に至るまで『占いの書』として読んできた」と述べます。また、「『オイディプス王』も、占いの物語ということができる。先王への神託、コリントス時代のオイディプスへの神託、今回クレオンが貰ってきた神託、そして予言者テイレシアスの予言。神託通りになるまいとする人間のあがきが神託の実現をもたらしていく。そして、易経も、この物語の中に置かれると、占いの書物として語り始めた。たとえば、全ての終わった後にオイディプスが東洋の賢者の言葉を思い起こすならば、易の力に底知れぬ畏怖の念を覚えたことだろう。易が占いの書物として読み継がれて来た背景には、数千年来、同様の経験をしてきた数知れない人々があったものと想像される」と述べています。
ドイツ人宣教者と易経の出会いの物語を描いたこともある新田義之は、オイディプスの物語について、「ギリシア悲劇は、人間がどんなに努力しようとも自分の運命をほんの少しも変えることができないという恐ろしい真実を、『神の意志』という形で私達に示します。そしてそれと同時に、まったく自分の責任ではないのに、思いもかけない不幸せな運命に襲われたとき、偉大な人間はそれに対してどのような態度をもって臨むかを、単純明瞭な形で描きます。オイディプスは自分の運命を変えることこそできませんでしたが、しかし運命を誤魔化してすり抜けようとはしませんでした(中略)。人間は運命に絶対的に支配されているにもかかわらず、人間としての誇りと行動の自由を守り通すことができるのです」と語っています。
これについて、著者は「『オイディプス王』のこうした思想と、『運命を誤魔化してすり抜け』るに近いことまで助言する易経の思想は食い違っているように見える。『悲劇と易経の対話は成り立ったが、考え方は違った』ということになろうか」と述べます。また、古代中国の都市国家では、帝王の統合力は祭祀の主宰者としての役割に根ざしていたと指摘し、著者は「伝統的な祭祀をきちんと行わなければ、国がばらばらになってしまうのである。古代ギリシアの都市国家も事情は同じであったろう。祭祀を禁じて国をバラバラにしてしまう物語『アンティゴネ』を前にして、易経は国がバラバラになりそうな状況に処する道を説き、三度繰り返して祭祀の大切さを語る」と述べます。
第五章「ソポクレスと孔子」の「亡命と放浪の人生」では、著者は「非道な現実はあくまで許せない。孔子は、オデュッセウスやクリュソテミスのように、現実とうまく折り合いをつけることができる人物ではなかった。非道な現実を嘆き憤りこれと戦うことにおいては、孔子は、兄の葬礼を禁じた王と戦うアンティゴネにも、父を屠った母と戦うエレクトラにも劣らなかった」と述べ、孔子の実人生はむしろソポクレス劇の発展に近いと指摘し、「アイアスや、アンティゴネや、エレクトラのように生きて、コロノスのオイディプスのような放浪の末、50歳にして天命を知った。それでも59歳までは、人の言葉を黙って聞いてはいられなかった。69歳までは、心の欲するところに従えば、矩を踰えた。そう自ら語っている。根はエレクトラのような人だったのではないか」と述べています。
「家柄と名声と富と権力」では、著者は「ソポクレスの人生は、むしろ易経の教えに近かったように思われる。富貴の家に生まれ、高い教育を受けた」と述べ、「旅の終わりに」では、「瓦全を説いて現実には放浪の人生を送った孔子と、玉砕を描いて現実には顕職と名声と富に満たされた人生を歩んだソポクレスは、最後には同じ道を説くに至った。ギリシア悲劇と易経の対話が、ある時には噛み合い、ある時には微妙に、あるいは激しく食い違う所以は、こうしたところにあるように思われる」と述べるのでした。
「あとがき」では、著者は「易経を読むと役に立つか? ギリシア悲劇を読むと役に立つか? 立つかもしれないが、実用的なノウハウを手に入れるためであれば、他に効率的な手段もあるだろう。古典を読む理由は、普段接することのないような、見上げるように巨大で、とてつもなく魅力的で、しかも、一人の人間として等身大で生きている、過去の貴重な人格と接することにある。そのためには、著しく非効率だが、原文に当たるしかない。パラフレーズした瞬間に、言葉は力を失う。古典ギリシア語を学んで5年、依然殆ど読めず、漢文も華音では発音できないのにこんなことを言うのはおこがましいが、音律を含めた、その人たちの言葉そのものに接するしかない」と述べています。
そして、著者は「お互い顔を見合わせて、毎日、凡庸さを嘆きあっていても仕方がない1行でも2行でも、孔子その人に、ソポクレスその人に接することで、満員電車の窓を開けて、爽やかで厳しい、2500年前の新鮮な空気を吸い込むことをお勧めしたい。それこそが人生最大の娯楽だと思う」と述べるのでした。わたしも、孔子や儒教関係の本はかなり読んできましたが、本書は非常にわかりにくいというか、読みにくい本でした。独特の文章は、著者が金融官僚であることと関係があるのでしょうか。それは知りませんが、『易経』という書物に興味を持つきっかけになりました。『易経』に関する他の本も読んでみたいです。
