- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.07.06
『孝経 全訳注』加地伸行著(講談社学術文庫)を再読。著者は1936年、大阪生まれ。京都大学文学部卒業。専攻は中国哲学史。大阪大学名誉教授。わが国における儒教研究の第一人者です。7月7日、わたしは著者と大阪で「儒教と日本人」をテーマに対談させていただきます。
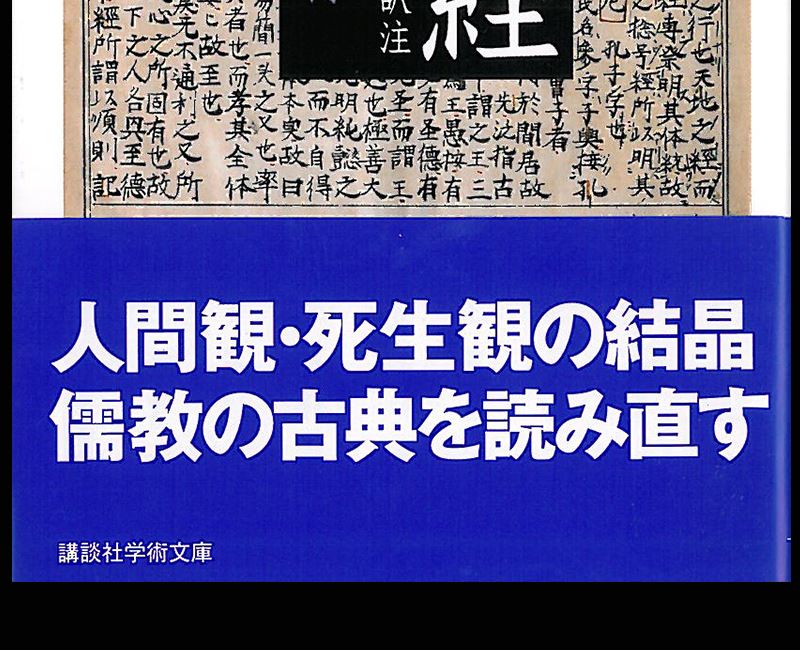 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「人間観・死生観の結晶 儒教の古典を読み直す」と書かれ、帯の裏には「従来、『孝経』と言えば、子の親への愛という、いわゆる親孝行と、孝を拡大延長した政治性という、いわゆる統治思想と、この両者の混在といった解釈がなされることが多く、それが『孝経』の一般的評価であった。そうではない。『孝経』全体としては、やはり死生観に関わる孝の宗教性が根本に置かれている。その上に、祖先祭祀・宗廟といった礼制が載っているのである。(本書「『孝経』の主張」より)」とあります。
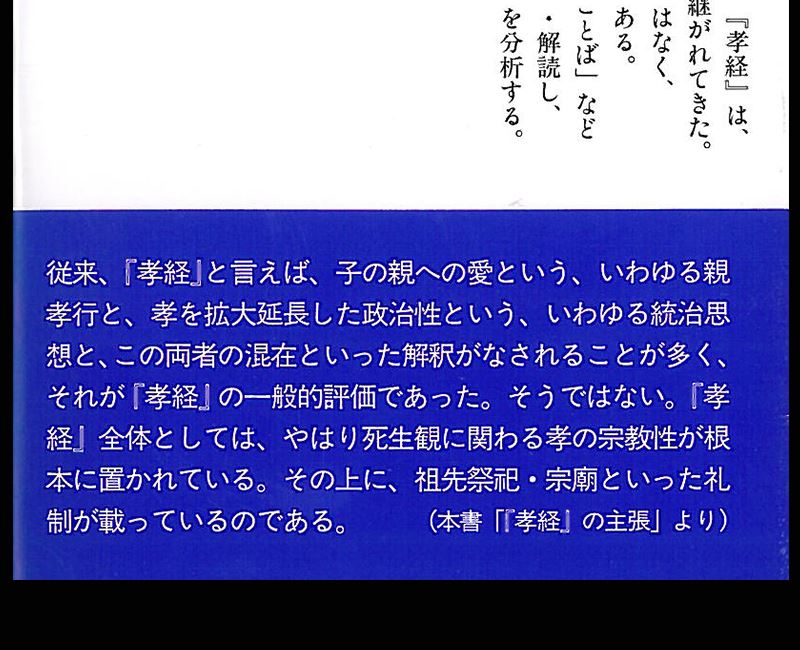 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「本文18章と付篇1章から成る小篇である『孝経』は、孝道を論じた儒教の経書で、古来永く読み継がれてきた。しかし、単に親への孝行を説く道徳の書ではなく、中国人の死生観・世界観が凝縮された書である。『女孝経』『父母恩重経』「法然上人母へのことば」など中国と日本の『孝経』周辺資料も多数紹介・解読し、精神的紐帯としての家族を重視する人間観を分析する」
本書の「目次」は、以下の通りです。
「序」
第一部 『孝経』訳注
凡例
引用・参考文献
第二部 『孝経』とは何か
一 はじめに
二 『孝経』の構成
三 『孝経』各章の特色
四 『孝経』の主張
五 『孝経』の成立
六 死と孝と『孝経』と
第三部 『孝経』の歴史
一 テキスト(今文・古文)の問題
二 『孝経』の注解
1『古文孝経孔伝』一巻
2『孝経正義』三巻
3『孝経刊誤』一巻
三 中国・日本における『孝経』とその周辺
四 忠について
第四部 『孝経』・孝に関連して
一 『孝経』・孝の参考文献
二 『孝経』の周辺資料
1 正史の中の孝物語
2 孝の教科書
3 『女孝経』
4 『忠経』
三 孝と宗教と
1『弘明集』
2『仏説孝子経』
3『仏説父母恩重経』
4『孝論』
5『論仏骨表』
6『儒仏問答』
7 法然上人
8 孝とキリスト教と
四 孝と日本人と
1 孝子について
2 不孝者について
3 十種の「孝」字の教え
4 孝子の表彰
附編『孝経』関係テキストの図版
「序」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「仰げば尊し我が師の恩――小学校唱歌の一節である。かつては卒業式の最後に、卒業生が涙とともに歌ったものである。この唱歌の中に、『身を立て名を揚げ、やよ励めよ』とある。このことば、多くの人はこう理解している。すなわち立身出世を勧めていることば、と。それは誤解である。『身を立て名を揚ぐ』とは、『孝経』の中のことばで、その意味は、『身を立てようと思えば、まず孝道をしっかりと行い、さらには世の道徳を大切にと実践していると、しぜんと世間の評判となって名を揚げることになる。その結果、そのような人物を育てた両親の名誉となる』ということなのである。そのように、立身揚名とは、修養を積んで人格を高め、道徳的に生きる人間になるということであって、断じて金儲けや高い地位を求めて狂奔する、いわゆる立身出世ではない」
著者によれば、江戸時代初期の宮本武蔵は『孝経』をきちんと学んでいませんでした。しかし、同じ武士でも『孝経』を学び、その主張を実践した者も当然いるとして、江戸時代中期、武士のありかたを記した『葉隠』(山本常朝述、田代陣基編)を例に挙げます。『葉隠』では主君への諫言が肯定されていますが、この諫言こそ、『孝経』の重要な主張の1つであったとして、著者は「葉隠武士はよく理解していたと言うべきであろうしかし、儒教において、『孝経』が諫言の重要さの理論的根拠となっていることなど、今ではほとんど知られていない」と述べています。
それだけではありません。孝それ自体についても、単純に道徳としての孝としか理解されていないとして、著者は「そのため、孝はなにか古めかしい過去のお説教といった目で見られているのがふつうであろう。それもまた誤解である。『孝経』は、儒教文化圏、東北アジア地域の人々――中国人、朝鮮民族そして日本人等の死生観・宗教観と、実は深く関わっているのである。もちろん、家族道徳とも深く関わっている。すなわち、『孝経』は儒教文化圏における、道徳性と宗教性との両面の根底となっているのである」と述べるのでした。
第一部「『孝経』訳注」の最初にある「開宗明義(宗を開き義を明らかにするの章)第一の現代語訳で、第一章「問題提起と総論と」として、著者は「老先生(孔子)がゆるり悠々としておられ、曾先生がそのお側に控えておられたときのことである。老先生がおっしゃられた。『古の王者は、孝〔・悌〕という正道を体得して、それによって天下を統治したのである。だから、〔共同体や横の関係の〕人々はお互いに親しく、また〔組織の〕上下関係においても円満だったのだ。お前はこのわけが分かっておるかの』と」書いています。
聖治章(聖の治むるの章)第九の第九章「孝による大偉人の政治」の「父子の道は天性なり、君臣の義あるなり」で始まる(三)を、著者は「父と子とのありかた(親子のありかた)とは、〔ことばを超えた〕天成のものである。その上、君と臣と(組織の指導者とその部下と)の〔理に適った〕ありようが含まれている。父母は子を生む。〔生命のこの〕連続、それより価値あるものはない。〔父母が子に対するときに類似して〕君主が臣下に対して親愛の気持ちで接する。そのような厚遇(手厚いもてなし)、それより尊重されるものはない。だから、自分の親を愛さないでいて、他人を愛すのは、道徳に悖ると言うのだ。自分の親を尊ばないで、他人を尊ぶのは、世の規範(礼)に悖るのである。このように順序を踏めば、民はそれを手本として従う。その逆であると、民は従わなくなる。孝の愛や敬に拠らなければ、たれしも背徳者となるのだ。〔そのようなことであれば、〕たとい高い地位を得たとしても、教養人はそれを重んじない」と現代語訳しています。
紀孝行章(孝行を紀すの章)では、「子曰く、孝子の親に事うるや、居れば則ち其の敬みを致し、養えば則ち其の楽しきを致し、病めば則ち其の憂いを致し、喪には則ち其の哀しみを致し、祭には則ち其の厳そかなるを致す」で始まる第十を、著者は「第十章 孝行自体について」として、以下のように現代語訳しています。
「老先生の教え。孝子であるならば、親にお仕えする態度は、ふだん家で親と接するときは敬意を尽くし、食事や衣服のふだんにおいては常に歓ばせ、病気のときは心より心配し、亡くなったときは哀しみの極みを尽くし、その亡きあとを弔い祭るとき厳粛に行う。この五者が十分であって、はじめて親にお仕えすることができるのだ。親によくお仕えする者は、〔そのような謙虚な態度の人格であるからこそ〕指導者となっては他者に対する謙虚な気持ちを忘れないので〕傲岸にならず、部下であるときは同じく慎み深く〕秩序を乱すようなことをしないし、世の人々の間にあっては、争い合うなどということをしない。〔つまり、〕指導者となって傲岸であれば、必ず亡んで〔財産をはじめ、宗廟までなにもかも失って〕しまう。部下でありながら反乱を起こせば、必ず刑を受ける。人々の間で争い合っておれば、必ず凶器で殺される。〔これは、自分自身の身体を傷つけるだけではなくて、親の身にも災いが及ぶこととなる。〕この三者(驕・乱・争)を除かなければ、毎日、親のために、どんなに贅沢な食事を提供しようと、親不孝というものなのだ」
広要道章(要道を広むるの章)では、「子曰く、民に親愛を教うるは、孝より善きは莫し」で始まる第十二を「第十二章 正道とは何か」として、こう現代語訳しています。
「人々に親愛の情を教えるには、孝を教える以上のものはない。同じく長上の者に礼儀正しく順うことを教えるには、〔孝に附随し、長上を尊敬する〕悌を教えることが最高だ。人々のならわしを変えつつ善きように作り上げるには、音楽〔を通じての教化〕ほどよいものはない。指導的地位にある人を安泰にし、人々をその指揮に従って安定させるには、礼以外にはない。この礼〔の精神〕とは、敬意なのである。〔その敬とは、孝の二本の柱〈愛・敬〉の一つである。〕だから、〔或る人の場合、〕その人の父を他者が尊敬すると、その人(子)は喜ぶ。〔同じく〕その人の兄に敬服すると、その人(弟)は喜ぶ。〔同じく〕或る君主に敬事すると、その臣下は喜ぶ。〔すなわち〕一人に対して敬意を払うと、多くの人々が喜ぶという結果となる。敬意を払う相手は少なく、〔それによって〕喜ぶ者が多い。これを正道(要道)と言うのである」
喪親章(親を喪うの章)では、「子曰く、孝子の親を喪うや、哭して偯せず」で始まる第十八を「第十八章 親の喪に服す」(一)として、著者はこう現代語訳しています。
「父母の死去を迎えた子は、〔喪礼としての〕哭声も〔悲しみで〕息が途切れて続かない。〔気持ちが動転していて、喪礼としての〕作法も所作が不十分なままに行い、〔受け答えの〕ことばも短く型どおりである。衣服は喪服でないと落ち着かないし、音楽を聴いてもそれには乗れないし、珍味のものを食べたとしても美味しいとは思わない。これは、〔親を失った〕悲哀の真情なのである。〔父母が亡くなったあとは、食欲がなくて、近所の人が作ってくれるおかゆをすする程度の食事の〕3日を経て普通の食事に戻る。〔これは、いつまでもおかゆをすすっていては〕死者を悼んで、かえって生者(遺族)の健康を害ってしまうことになるので、〔悲しみの生活のため〕たとい痩せ衰えることとなっても、天から与えられた生命を〔損ない、死亡に至るほどに〕消滅させてはならないということを人々に教えている〔規範であり慣行である〕。これは、大偉人の定めた政教(礼教〈礼制による教え〉に基づく政治)である。喪に服する期間は、〔父母への服喪という、たとい最長の期間を持つ場合にしても〕3年を越えないという礼制は、人々に〔心の悲しみは尽きないとしても、それは心という内面の問題であり、外形としての喪服には期間という区切りがあり、そのときをもって〕終わりがあることを教えているのである」
続いて、「之が棺槨衣衾を為りて之を挙ぐ」で始まる(二)は、「第十八章 親の喪に服す」(二)として、著者は以下のように現代語訳しています。
「亡き親に棺・槨・衣・衾を準備し、遺体を納棺する。供え物を並べて悲しみの気持ちを表わす。[喪礼が進み、しだいに出棺・葬送のときが近づくにつれ]足で地を打ち、胸を叩き、声を挙げ涙がとどまらず、哀しみが極まり葬送となる。その埋葬の日と墓地とについては、卜って最善を期し、[喪礼の終わるまで]宗廟に神主を立てて墓穴に柩を安置し、[慰霊を続け]祭祀を欠かさない。また[喪礼が終わったあと]春夏秋冬の変わる折々に、宗廟において慰霊鎮魂の祭礼を続け、亡き方々を偲ぶ。父母在せるときは愛・敬のまごころを尽くし、百歳の後には悲哀のまごころを尽くす。これが人間の本務を尽くすことであり、死生に対する人間のありかたを全うしたことである。すなわち子が親に仕える道、孝を完結したことになる」
第二部「『孝経』とは何か」の一「はじめに」では、孔子らの語録の編集である『論語』と異なり、『孝経』は組織的に作られていると指摘して、著者は「もっとも、『論語』もただ単に語録を並べたのではなくて、配列に或る種の意図が見られる。しかしそれは、古代人の特殊な排列感覚に基づくものであって、現代の観点からすれば、いわゆる〈組織的〉とは言えない。それに比べて、『孝経』は今日の観点から見ても極めて組織的なのである。因みに、当時の多くの文献が、語録や記録などであるなか、『荀子』は中国古代において作者による最初の撰述であるとされている。この『荀子』の文体は際立って筆述的である。同じく、『孝経』もまた作者による撰述的性格が強い。そこには一本、立場が通っている」と述べています。
三「『孝経』各章の特色」の「第十六 応感章」では、著者は「宗廟において祖先祭祀を行うとき、敬を尽くせば、鬼神は感応し、現われると述べる。これは、家の宗教である儒教における祭祀の真髄であるシャマニズムを最もよく物語る。『祭れば〔祖霊は〕在すが如し』(『論語』八佾篇)は、中国古代において実感として生きていたのである」と述べています。また、「第十八 喪親章」では、「親の喪という、儒教の喪礼において最も基本となるものについて、一章を充て、孝子のありかたを記して、『孝経』の最後を締めくくっている。この喪礼は、それこそ天子から庶人に至るまで、本質は同じであり、儒教――〈家の宗教〉の根本となっているのである」と述べます。
四「『孝経』の主張」では、「『孝経』に、礼制ならびに『論語』の影響が相当にある」と指摘し、著者は「『論語』における孝であるが、そこには儒教における孝の意味が全面的に現われている。その第一は、祖先祭祀を行うこと、それを通じて生命の連続を意識し自覚することである。それはまた、死者と生者との関係を示す宗教的性格を有している。いま一歩、踏みこんで言えば、それは死の不安・恐怖を克服しうる方法であった。すなわち、祖先祭祀を享けて祖先の霊魂が、かつて生きてあったときの家に帰来するとき、祖霊は生者の記憶による回想によって自分たちは忘れられていないという安心感を抱ける。それは、精神的安心である。生者も、漠たる死に対する不安において、自己の死後、生き残った者たちによる祖先祭祀によって、霊魂ながら自己が再びこの家に帰りうると思うとき、精神的安心を得られるのである。そのように、祖先祭祀とは、生者における死の不安中、精神的安心を得させる大きな意味を有している。比喩的に言えば、儒教という〈家の宗教〉における一種の〈解説〉の方法なのである」と述べています。
祖先祭祀によって〈精神の解脱〉、子孫一族の存在によって〈身体の解脱〉、つまりは〈己の解脱〉をし、死の不安・恐怖を乗り越えることを可能とするのであるとして、著者は祖先祭祀と子孫一族と――生命の連続の自覚が、人間における死の不安・恐怖を乗り越えうる方法であることを、また、それが孝であることを儒教は説いているのである。しかし、祖先は過去であり実見できない。同じく遠い子孫は未来であり実見できない。すると、過去と未来とをつなぐ中間にある現在が大きく浮上する。すなわち、祖先祭祀を精神的柱として、現実の親子、あるいは拡大して祖父母から孫、2ないし3世代の家族の日々の生活が行われているということである」と述べます。
従来、『孝経』と言えば、子の親への愛という、いわゆる親孝行と、孝を拡大延長した政治性という、いわゆる統治思想と、この両者の混在といった解釈がなされることが多く、それが『孝経』の一般的評価であったとしながらも、「そうではない」として、著者は「『孝経』全体としては、やはり死生観に関わる孝の宗教性が根本に置かれている。その上に、祖先祭祀・宗廟といった礼制が載っているのである。ただし、単なる制度ではない。その礼制が形骸化することなく、内実のある生きた規範でなくては意味がない。しかも、孝は道徳として、家族道徳という根本的なものである。こうした根本道徳が確立されたならば、その上に載る礼教的道徳(社会道徳ひいては政治的国家的道徳、全世界的道徳など人間社会の諸規範)との連関性が必要となる。そこで、孝とその上に載る諸道徳との関係が問題となる。その媒介者となったのが、孝の中身としての2本柱〈愛と敬と〉なのである」と述べます。
人間関係の場合、血縁関係と非血縁関係とに大別できるが、血縁関係の場合、その道徳を基礎づけるのは、愛、もちろん無償の愛であるとして、著者は「元来、血縁というのは、先天的、宿命的、非合理的関係である。生まれたときから定まっている関係であるから、その人間関係は愛のような極めて身体的な感覚によって成り立つ。理屈を越えたものである。そのように、血縁関係における道徳は比較的分かりやすいし、直覚的に肯定される。これに対して、非血縁関係における道徳は自然に成立するわけではない。そこには、身体性でなくて精神性がないと結びつけるのは困難である。そこで儒教では、他者同士を結びつけるものとして〈まごころ〉を重視した。その応用として、例えば友人関係の場合、〈信〉を友情の核としている。『孝経』の場合、孝と他の道徳との関係づけを考え、孝の2本柱(愛・敬)のうち、非血縁関係につながるものとして、敬を出してきている」と述べるのでした。
六「死と孝と『孝経』と」では、近代以前の時代の感覚や意識や常識などを現代人は捨ててきたため、もはや忘れ去られ、今となっては、かつての時代のそれを再び得ることは難しいとして、著者は「仮になんとか得たとしてもせいぜい文献的知識、それも一部のそれでしかない。たとえば、古代ギリシアでは、祖先崇拝が当然であったにもかかわらず、キリスト教が普遍化するとともに、完全に忘れ去られ、今や文献の上からその昔のことを知るのみとなってしまっている。『孝経』全般に流れている、一族による祖先祭祀の観念や実行の重視は、『孝経』成立期の人々にとっては当然のことであったとしても、それを現代人が実感することはなかなか困難である。しかし、ヨーロッパと異なり、キリスト教が普及しなかった東北アジアにおいては、まったく断絶しているわけではない。そこは歴史であり伝統であり文化であり、一定の感覚や意識が継承されてきていることは言うまでもないし、その継承において、細かい点は脱落してきたとしても、本質は変わるものではなく、核となるもの自体は存続してきている。すなわち、儒教全体の歴史において、祖先祭祀を中心とする〈家の宗教〉は受け継がれてきた。 そのことを最もよく示すのが、『孝経』最終章の喪親章である」と述べています。
漢語(漢文・現代中国語あるいは古文・現代文)の特性として言えば、具体的個物を表わす場合も、それを抽象化した場合も、同一の漢字で表わします。だから、例えば「白」という漢字の場合、それは「白い」という具体的状態をも、また「白さ」という抽象的状態をも意味しうる。そのため、「白」という漢字だけでは、そのどちらなのかという判断が困難であり、その解釈は、文脈によらざるをえないということを説明し、著者は「そこで中国人は、抽象的議論に代わって、その抽象的議論に最も近く入りやすい現実的材料を選んで、その議論を尽くそうとする。いま問題とする死の場合も同様で、死そのものの議論をするのではなくて、死の問題を最もよく語りうる材料を選び出し、それについての議論を通して、死そのものの問題についての議論の代替をしようとするのである」と述べます。
では、どのような現実的材料が、死自体という抽象的議論の代替者となりうるのでしょうか。著者は、「そういう材料はありうるのか。有る。それは〈親の死〉である。人間は、己が死を迎えるまで、死について本当は分からない。しかし、他者の死と接することによって、死の一定の現実感を得ることとなり、やっと死について考えることができるようになる。もっとも、実感は依然として稀薄である。しかし、ほとんどの人間が必ず実感を得る機会がある。それは、親しい者の死である」と述べます。
儒教では、「親しさに比例して愛しなさい」と教えています。そして、一般的には、その最も愛する人は、親であるということです。こうした人間観があるので、すなわち、最高の哀しみは、最高に愛した人の死となるのです。著者は、「親の死は最高の哀しみであるがゆえに、その哀しみの表現を最高にすることとなる。具体的には、すなわち、親に対する喪儀(「葬」は、喪儀の行為の中の一つである。全体的には「喪」であり、その過程の一つとして柩を土中に埋めるが、それが「葬」であるから、「喪儀」と「葬儀」とは異なる)を他の喪儀と比べて最高にするということである。ここで誤解なきようあえて記せば、喪儀を最高にすると言うと、規模を大きくし、華美にすることのように受け取られかねないが、それはまったく違うということである」と述べています。
さらに、著者は以下のように述べています。
「儒教はこう考える。親が亡くなると哀しみが溢れて、日常生活が日常生活でなくなってしまう。たとえば、哀しみで食事が十分にできなくなる。哀しみで身だしなみなどに気持ちがまわらない。哀しみで他人とのつきあいなどできない。まして、洒落た綺麗な衣服を着ることなどできない・・・・・・というふうに。そこで、身を慎み、〈喪に服する〉こととなる。その場合、可能なかぎり、質素な生活をすることとなる。それが、哀しみの精神的内面的表現ということである。だから、喪儀にはまず喪服を着る。〈喪に服している〉ことの表現である。この喪服には種類がある。最も粗末な作りのものが最高の哀しみを表わすのであり、この喪服は親の喪儀のときに着る。以下、〈哀しみの三角形〉に従い、自分との関係で親しさが遠くなるに従って、喪服が徐々に日常衣服に近づいてゆき、縁もゆかりもない人に対しては、哀しみがないのであるから喪服は着ない。第一、喪儀に参列する理由がない」
今日では、喪儀となると、参列者全員がほぼ同一の喪服を着用していますが、それは儒教的には誤りであるとして、著者は「遺族は、当然、喪服を着るが、死者と縁が遠い者が遺族と同格の喪服を着用することは、遺族の哀しみと同等であるということを表わすこととなる。それは、遺族に対して僭越な行為である。参列者は、死者と自己との関係を勘案して、それ相当の服装(たとえば、(1)平服、(2)平服に地味なネクタイ、(3)色は問わず無地の服に黒ネクタイ・・・・・・)であってしかるべきなのである。なお、喪服として黒色の衣服を使うのは欧米流である。東北アジアでは、白色である。『白式』とは喪儀のこと、『紅式』とは婚儀のことである」と述べます。くのくだりを初めて読んだとき、わたしは衝撃を受けました。そして、日本の冠婚葬祭の初期設定とアップデートについて想いを馳せました。
儒教では、親の喪儀が礼制の規準となります。著者は、「人間はその一生においてさまざまなことに出会うが、結婚しない人もいるし、あるいはいろいろな理由で一族の祖先祭祀に参列できない人もいる。冠礼(成人式)も行わない人もいる。しかし、人間は必ず死と向き合う。特に親の死に遭遇する。生前に親を亡った人もいるがそれは例外である。だから、『冠婚葬(「喪」字が正しい)祭』と言っても、喪が規準となる。冠・婚・祭は、喪における諸規準の反映である。その喪において、規準となるのが親の喪儀である。ここにも〈哀しみの三角形〉が現われる。つまり、冠婚葬(喪)祭という、人々にとって大切な儀礼の規準は、親の喪礼にあるということなのである」と述べるのでした。すべての冠婚葬祭に携わる人々が知っておくべき基本知識であると言えるでしょう。
第三章「『孝経』の歴史」の一「テキスト(今文・古文)の問題」では、漢王朝(前200年)ははじめは儒教を重んじなかったものの、前200年(劉汝霖『漢晋学術編年』中文出版社復刊版。以下、年代は同書に依る)には、儒教の諸儀礼を宮中に導入し秩序づけました。叔孫通という人物によります。すると、秦王朝の始皇帝による「焚書坑儒」(前213年)から13年後には、儒教は弾圧されるどころか、政権の中枢の一角に食い込むこととなります。しかも、叔孫通が儒教の儀礼を導入するには、礼の体得者が必要であるので、魯(孔子の出身地)の儒生や弟子たち計130余人を首都に連れてきている(『漢書』叔孫通伝)のです。
これについて、著者は、「つまり、焚書坑儒によって、儒教の書籍がすべて焼滅し、学習者がいなくなってしまい、絶滅したわけではない。狩野直喜は、早く朱子がそのことを指摘していたことなどを紹介しつつ述べている(『中国哲学史』260ページ、岩波書店、1953年)。なお、前191年には発禁書とする挟書律が廃せられ、このあたりから、難を逃れ隠されていた文献が少しずつ世に出るようになる。実状はそういうことである。実質的には、儒教文献は生き残り、復活していったのである。そこへ、ある大きな事件が起こった。魯国(これは、前代の周王朝期の独立的な魯国と異なり、漢王朝期に、いわば所領を与えた臣下としての国)を統治していた恭王が、孔子の旧宅を破壊して邸宅を建てようとしたが、その旧壁中から儒教文献が出てきたのである(前141年)。その中に『孝経』もあった。この『孝経』は焚書を避けたものとされている」と述べています。
三「中国・日本における『孝経』とその周辺」では、「経」について言及されています。「経」とは、布地を織るときにおける縦糸のことを表わします。同じく布地における横糸のことは「緯」と言います。そこで、漢代から儒教における古典学を経学と称するようになります。著者は、「儒者個人の思想は儒教思想であるが、儒教における主要古典(経書と称するようになる)の解釈学が経学である。儒教における主要古典(漢代のころはたとえば易・詩・書・礼・春秋、あるいは楽・書・礼・易・詩の五経であったが、しだいに増え、唐代になると最終的には易・書・詩・周礼・儀礼・礼記・春秋左氏伝・春秋公羊偏・春秋穀梁伝・論語・孝経・爾雅・孟子の十三経)が儒教における共通の学習文献であった。この古典について「述べて」(つまりは注解を施し)、みずからは「作らず」が儒家の心得であった」と述べています。『孝経』は、成立以後、広く読まれました。
後漢時代、インドから仏教が中国に伝来します。インド宗教(インド仏教はその一種)は、解脱した者以外、死後は輪廻転生するという死生観を持っていますが、現世から来世に転生するとき、現世の人間は必ずしも来世において人間となる保証はありません。六道すなわち神・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄のどこに転生するかは、現世におけるありかたの道徳的高低によって定まります。著者は、「そのため、来世の行き先が不明な以上、現世における肉体には意味を認めないので、火葬にして骨灰は棄て、墓は作らない。一方、現世における精神は四十九日(中陰)後に転生して別のところ、別のものへと離れてゆくので、中陰を満たした四十九日(満中陰)以後、祖先祭祀(先祖供養)はしない。けれども、儒教文化圏の死生観はそうではなく、生きてある状態を魂(精神の支配者)と魄(肉体の支配者)との融合状態と考えるので、死を魂と魄との分離と考える。魂とは、事実上は雲のことであり(「魂」字の中の「云」は「雲」)、魄とは、事実上は白骨である(「魄」字の中の「白」)。この分離した魂と魄とを呼び寄せて融合させれば、再生すると信じた」と述べます。
魂魄を呼び寄せる。香のよい植物を焚いて煙が昇ると、その煙に乗って魂が降りてきます。香のよい酒を地上にまくと、その酒の香に乗って魄が上ってきます。呼び寄せられて帰ってきた魂魄が憑りつく先は、もともとは呼び寄せる霊魂の持ち主であった死者の頭蓋骨をかぶった人間(依り代)でしたが、それを象徴化した木主(四角い木の台に長方形の板を差し込んだもの。神主とも言う)に憑りつきます。木主は大切なものとして代々祭られる(因みに、後に中国仏教・日本仏教は、それらを焼香や位牌として取り入れる)として、著者は「これが儒教の死生観の表現であり、シャマニズムの展開された形である。当然、その死者を祭祀するのは子孫一族であるから、祖霊信仰であり、祖先祭祀を最重視する」と述べています。
さらに言えば、自分の身体は「父母の遺体(遺した体)」とする身体観があります。著者によれば、「遺体」という言葉の元来の意味は、死んだ体ではなく、文字通り「遺した体」という意味だといいます。つまり本当の遺体とは、自分がこの世に残していった身体、すなわち子なのです。孔子が開いた儒教における「孝」は、「生命の連続」という観念を生み出しました。祖先崇拝とは、祖先の存在を確認することであり、祖先があるということは、祖先から自分に至るまで確実に生命が続いてきたことになります。また、自分という個体は死によってやむをえず消滅するけれども、もし子孫があれば、自分の生命は存続していくことになります。わたしたちは個体ではなく1つの生命として、過去も現在も未来も、一緒に生きるわけです。つまり、「孝」があれば、人は死ななくなるのです。
自分の死後、子孫一族(だれでもいい、血のつながる者)が自分に対して慰霊してくれることによっ て、現世の人々に忘れられていないということで精神的に安定します。また子孫一族が存在することによって死後も自己の(個体は滅ぶものの)生命は存在し続けることになり、そのことによって肉体的に安定します。著者は、「精神・肉体ともに安定して死を迎えることができる。これは一種の解脱でもある。そのような考えで死の恐怖・不安を乗り越えうる。こうした死生観の文化圏に、祖霊信仰でない宗教(具体的に言えば、祖先祭祀や墓のない宗教)のインド仏教が入ってくると、当然、激しい文化衝突となった」と述べます。儒教vs仏教の宗教衝突です。
仏教における僧侶は剃髪すなわち髪を剃り落とします。この行為は『孝経』開宗明義章の「身・体・ 髪・膚 之を父母に受く。敢えて毀傷せざるは孝の始めなり」に反します。『孝経』ははっきりと「髪」の字を記しており、それを故意に剃り落とすのは、父母からいただいたこの身体(父母の遺体)を毀うことになるのです。また、儒教文化圏では土葬して、身体を完全な形のままに残します。ところが、インドでは輪廻転生説に従い、死後、火葬にし、散骨すると指摘し、著者は「現代日本では、『土葬』以外は『火葬』と表現するものの、それは法律的なことばであって、宗教的意味としての火葬かつ散骨という意味ではない。今日の日本では、大半の場合、火葬するが、そのあと遺骨から象徴的に足の部分に始まり、順番に上部に向かって拾い、必ず喉仏(その形が仏の座像に類似)を収め、最後は頭蓋骨をかぶせる。残りの遺骨は処理する。つまりは棄てる。これは、身体の象徴的収集であり、その意識は〈遺骨式土葬〉である。だから、遺骨のすべての散骨にまで至らない。まして、日本でもつい最近まで土葬であり、中国・朝鮮半島では今も主流は土葬である儒教文化圏において、インド式の火葬して散骨するなど、とんでもないことであった」と述べます。
儒教では祖先を敬愛するとして、著者は「その祖先が地獄に落ちるなどということは、ことばに出すも不謹慎な話である。とりわけ、父母が没後に苦しむなど、ありえない話とする。祖先祭祀を厳粛に行い、命日に祖霊と再会している中国人にとって、祖霊がさまよい苦しみ続けると考えることすら憚られる。
また、実を重んじる中国人の現実主義的感覚主義的立場からすれば、極楽・地獄はもとより、仏教の抽象的な概念(空とか因縁とか)は、虚なるものであり、感覚として受け入れがたかった。それは、終局的には霊魂観の問題であった」と述べています。
仏教学者はよく仏教は霊魂の存在を認めていないと言いますが、仏教が起こる西暦前5-前6世紀のころ、輪廻転生の思想があり、仏教はこの輪廻転生の思想を基礎としていると指摘し、著者は「その輪廻転生は、霊魂の存在を認めることなくして成り立たない。いや、仮に仏教学者が仏教は霊魂の存在を認めないと〈学問的〉に述べたところで、また、輪廻転生は仏教にない思想だと言ったところで、それは仏教という〈宗教〉において何の説得力もない。宗教としての仏教は、学問としての仏教を尻目にして、一般大衆の中へ霊魂の存在を認める輪廻転生の思想に基づいて東北アジアにおいて普及し普遍化していったのである。それは既成の歴史的事実である」と述べるのでした。
第四部「『孝経』・孝と宗教に関連して」の三「孝と宗教と」では、西暦1世紀に、中国へインド仏教が流入したとき、それは学問としての仏教〈学〉ではなくて、あくまでも宗教としての仏〈教〉であったと指摘し、著者は「だから、インド仏〈教〉は、中国流入の最初から、輪廻転生や死の問題とセットだったのである。それを誤りだと現代仏教〈学〉の立場からいくら言っても、歴史の展開した現実を否定することはできない。また、逆に言えば、輪廻転生・死を抜きにした仏教〈学〉が流入したとしても、それは中国人にとって、単なる異国の一(学〉説として見るだけのことに終わり、おそらく、1世紀に流入の時点でどこかへ消えてしまったことであろう。輪廻転生・死とセットの宗教であったがゆえに、インド仏教は、残り続けえたのである。第一、儒教文化から見れば、後漢時代は経学(儒教古典解釈学)が最高点に達した時代であり、それからすれば、インドから伝えられた〈学〉的内容など問題にならなかった異端であったからである)と述べています。
最後に、「孝とキリスト教と」では、文化的、宗教的、死生観的に、儒教とキリスト教とは、すくなくとも古代においては、関係はないとしながらも、キリスト教の教勢が増すにつれ、キリスト教が東北アジアにも流入してくると指摘し、著者は「仏教の場合と同じく、祖先祭祀を第一とする儒教とは、対立することとなる。しかし、中国人にとって祖先祭祀を捨ててキリスト教に入信するのは、並大抵のことではできない。また、キリスト教にとっても、祖先第一の信仰では、唯一最高絶対神のエホバ(ヤーベ)への信仰の絶対化ができないので、祖先祭祀を最高とすることは認めがたい。この大問題は今日に至っている。東北アジアにおいて、キリスト教が今もってどのようにしても広がらないのは、祖先祭祀が最大の壁だからである」と述べるのでした。著者の主張には、100%賛同いたします。
 著者の加地伸行先生と
著者の加地伸行先生と
今回、改めて本書を読み返してみて、再発見したことがたくさんありました。日本の葬儀の本質にも迫っており、大変勉強になりました。やはり、著者は、心から尊敬する師です。著者は日本を代表する中国哲学者で、わたしが私淑する儒教の師です。いよいよ翌日には著者と対談させていただくことになっており、大変光栄に思っております。
