- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2055 論語・儒教 『論語――心の鏡』 橋本秀美著(岩波書店)
2021.07.17
『論語――心の鏡』橋本秀美著(岩波書店)を紹介します。岩波の「書物誕生 あたらしい古典入門」の1冊で、高い評価を得ているにもかかわらず長らく絶版となっており、古書価が高騰している本です。著者は、1966年福島県生まれ。1999年、北京大学大学院中文系博士課程修了。東京大学東洋文化研究所助教授、中国北京大学歴史学系教授などを経て、現在は青山学院大学 国際政治経済学部国際コミュニケーション学科教授。
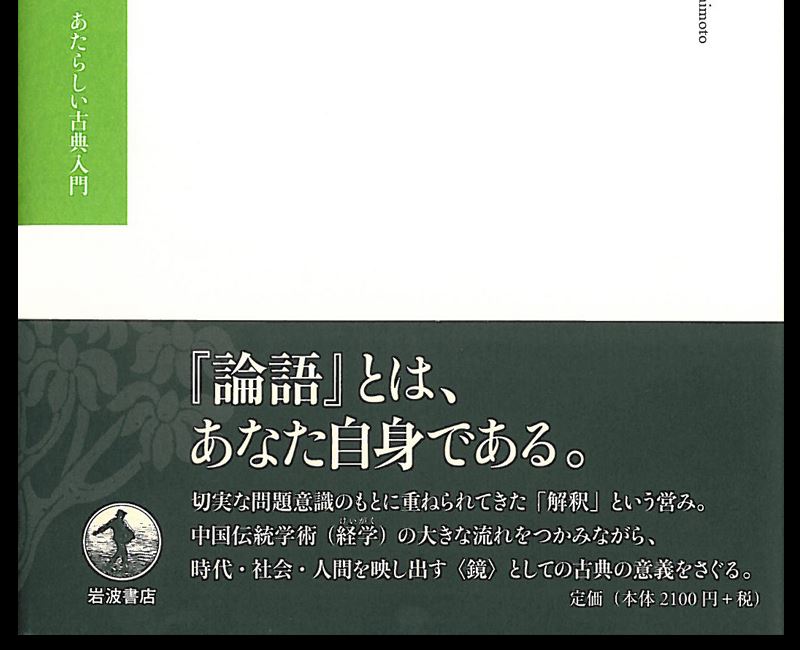 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「『論語』とは、あなた自身である。」と大書され、「切実な問題意識のもとに重ねられてきた『解釈』という営み。中国伝統学術(経学)の大きな流れをつかみながら、時代・社会・人間を映し出す〈鏡〉としての古典の意義をさぐる」とあります。
カバー前そでには、以下のように書かれています。
「李康子『若し道に外れた人を殺して道を守る人を育てたらどうですか』。孔先生『あなたが政治をなさるのに、どうして殺す必要があるのです。あなたが善を望まれるなら人民もよくなってゆきますよ。君子の徳は風で、小人の徳は草です。草は風が吹けばきっと靡きます』。――『論語』顔淵篇」
「混迷の時代に自らの理想を追求しつづけた孔子。彼と弟子たちの言行録である『論語』は、二千年以上にわたって最も親しまれてきた古典であると同時に、その成立と解釈をめぐって、最も意見が分かれてきた書物でもある。いつ、だれが編纂したのか。なぜ『論語』と名づけられたのか。少ない言葉数に込められた孔子の真意は何か?――歴代の学者たちは、『論語』の一言一句について、おびただしいまでの解釈を展開した。それらは単なる議論ではなく、たとえば孔子の唱える『礼』をいかに理解して実現させるのかという、読み手自身の切実な問題意識の表出でもあった。漢代から近代にいたる中国伝統学術(経学)の大きな流れをつかみながら、時代・社会・人間を映し出す〈鏡〉としての古典の意義をさぐる」
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに――『論語』はどこに在るか?」
第Ⅰ部 書物の旅路
「解釈」という営み
第一章 『論語』の始め
第二章 『論語』の展開
第三章 経学の時代
第四章 脱経学と経学の並行
第五章 宋学と朱熹『集注』
第六章 清代の『論語』研究
第Ⅱ部 作品世界を読む
私の『論語』、あなたの『論語』
第一章 異なる解釈で読む『論語』
第二章 『論語』と中国社会
「おわりに」
「参考文献」
「はじめに――『論語』はどこに在るか?」では、著者は「そもそも『学而時習之』(『論語』学而篇)が孔子の言葉だという保証はどこに在るのか? 『子曰く』、孔子が言ったのだ、というのは誰の証言なのか? 空間にして3000キロメートル以上、時間にして2000年以上の距離を想像力だけで埋めてしまってよいものか? 1000年前の京都の『源氏物語』でさえ非常に難解であるのに、2000年前の中国の『論語』がすんなり読めてしまってよいものか?」と、さまざまな疑問を示しています。
手にとって見ることのできる『論語』の本というものは、『論語』の長い複雑な歴史の中の一側面を示す写真のようなものと思っていただきたいという著者は、「1枚の写真を繰り返し眺めても、その人を理解したことにはならないのと同様、図書館や本屋に並んだ1冊の『論語』から『論語』の全てを知ることもできない。『論語』には『論語』の過去がある、ということだ。『論語』に対する理解を深めるためには、2000年来の『論語』の各種の本や注釈と、『論語』に関する歴史上の記録を幅広く見ていくこと が必要なのである」と述べるのでした。
第Ⅰ部「書物の旅路――『解釈』という営み」の第一章「『論語』の始め」の冒頭の「『論語』の体裁と編者」を、著者は「『論語』の面倒なところは、孔子一門の言行録として、断片的な記載が寄せ集められている体裁にある。一面では、この簡潔さのために、『論語』は儒学入門の書として非常に広く普及したが、その反面、記載が簡単すぎて意味がはっきり確定できない文句も少なくなく、後世各種の異なる解釈を生む原因の一つとなった」と書きだしています。
「書名はいつ付けられたか」では、著者は「孟子は、孔子の時代から百余年のち、自分こそは聖人孔子の後を継ぐ賢人である、と自任し、その思想が『孟子』という書として遺されている。『孟子』という書も、孟子が書いた原本が現在に伝わっているというわけではなく、我々の知っている『孟子』が孟子自身が考えていた内容とどこまで一致しているのかは確認しようもないが、現在の『孟子』には、『論語』を参考にしたと思われる内容が沢山ある一方、『論語』という書名は使われておらず、引用された孔子の言行も、現在の『論語』と完全に同一ではない。孟子はおそらく、単に口承の伝聞として孔子一門の言行を聞き知っていただけではなく、文字で記録されたものを見ていただろうと想像されるが、それがどの程度まで編集されたものであったのか、現在の『論語』からどれほど遠いものであったのか、またそれが『論語』と呼ばれていたのかどうか、等はいずれも不明と言わざるを得ない」と述べます。
続いて、著者は『礼記』を取り上げます。
『礼記』は戦国時代に萌芽し、漢代に各種の整理が加えられましたが、著者は「後世に伝えられているのは、後漢末期に鄭玄という学者――この学者はこれから本書でたびたび登場するので、憶えておいていただきたい――が最終的な編訂を加えたものである」と説明します。また、「鄭玄以降も、細部の変化は起こっており、『礼記』は完全に固定してしまったわけではないが、鄭玄版がその成長の最高点であったことは間違いない。したがって、『礼記』に見える孔子一門の言行が現在の『論語』と完全に一致しないのは、それが『論語』がまだ現在のような姿にまとめられる以前に書かれた内容だからだと考えられ、1カ所だけ見える『論語』という書名は、やや遅く、『論語』が『論語』として成立してから書き入れられたもの、ということになる」と述べています。
つまり、『礼記』を根拠に『論語』という書名の成立時期を推論すれば、結論は「後漢末(鄭玄)以前」となるわけです。著者は、以下のように述べています。
「あまりにも漠然として意味が無いが、『礼記』の中には『論語』の原型が発生してから次第に変化してきた痕跡が残っている、と言うことはできるわけだ。また、『史記』は前漢武帝の時代(前141-87年)に司馬遷がまとめたものだが、その中の仲尼弟子列伝(孔子の弟子たちの伝記)は『論語』を参考にして編纂した、とあるから、前漢の早い段階で『論語』は既に『論語』という書名で広く伝えられていたに違いない」
では、『論語』という書名は、どういう意味か?
前漢末に古代文献の大整理を行った劉向・劉歆が作成した目録をもとに書かれた典籍目録『漢書』藝文志によれば、「『論語』は、弟子や他の人々の問いに孔子が答えたり、あるいは弟子たちが互いに会話している際に孔子から聞いたりした『語』である。弟子たちがそれぞれ記録しておいたものを、孔子の没後、門人たちが集めて『論篹』したものなので、『論語』という」そうです。『論語』という書名の由来には諸説がありますが、この『漢書』藝文志の説は説得力がありますね。
第三章「経学の時代」の「六経と孔子」では、「礼楽」に言及しています。著者は、「日本で礼というと、堅苦しく意味の無い行儀作法や、一対一の絶対服従が連想されるが、中国古代の礼は、人間関係のあるべき姿、とでもいったもので、社会制度などを含めて客観的に考えられている。個人にとって外在的基準という意味を持つ礼に対して、個人の感情に働きかけて、礼に適った人間関係を更に安定させるのが、楽の役割と言える」と述べています。
孔子が理想とした周代の礼を全面的に記述した書物は存在せず、『詩』『書』や、『論語』『礼記』などの記載から推測する以外ないと指摘し、著者は「後の時代には、『周礼』(『周官』ともいう)『儀礼』と呼ばれる2種類の書が経典とされるようになるが、『儀礼』は数種類の個別儀礼の行い方を記したものに、服喪の制度を通して人間関係の遠近を規定した部分が加わったもので、礼の全てを網羅したというには程遠く、また、『周礼』は実際の周代の制度ではないばかりか、孔子が見たはずも無い戦国時代の作品だと言われている。楽については、古くは『楽経』というものがあった、という説もあるが、現在には伝わらず、本当に存在したのか、存在したとしたらどのようなものであったのか、いずれも不明である(したがって、「六経」の代わりに、経典が存在しない『楽』を除いて「五経」という言い方もなされる)」と述べます。
「『三礼』をいかに体系化するか――鄭玄経学の焦点」では、五経のうち、『易』は占いの書に宇宙論などが加えられたもので、その哲学的要素が重視される場合が多く、また『詩』『書』『春秋』は上古以来の政治を反映したものだが、好いことも悪いことも混ぜて書いてあるから、聖人の理想的政治・社会制度が直接的に示されているのは「礼」ということになると指摘し、著者は「このため、鄭玄の政治・社会制度に関する理論体系は、『礼』を中心に構築された。鄭玄は、当時伝えられていた『礼』の経典の中の『周礼』『儀礼』『礼記』を『三礼』と呼び、これらを総合的に研究し、統一的な解釈を可能とする理論体系を創出している」と述べています。
 「くさみ三礼庵」の外観
「くさみ三礼庵」の外観
ちなみに、わが社は紫雲閣とは別ブランドで「三礼庵」という冠婚葬祭施設を展開していますが、この「三礼」とは「慎みの心」「敬いの心」「思いやりの心」という小笠原流礼法における3つの「礼」を意味しています。しかし、本来の「三礼」とは『周礼』『儀礼』『礼記』のこと。著者は、「『周礼』は周王朝の体系的官僚組織を描写したもの、『儀礼』は一般貴族の儀式を説明したものだったから、『周礼』『儀礼』だけで理想の政治・社会制度像を理論として構想しようとするのは材料不足だが、『礼記』には断片的ながらその不足を補う内容が沢山あるので、『三礼』を上手く合わせて解釈すれば、礼の理論を全面的に構築することが可能になる」と説明しています。
第五章「宋学と朱熹『集注』」の「『四書』を重視する朱熹の経学」では、「四書」の成立由来が明かされます。『論語』『孟子』は五経にも増して根本的に重要な経典とされるようになりました。朱熹たちは、ここに更に『礼記』の中でも彼らにとって最も重要な理論を含む『大学』『中庸』を取り上げ、これを『四書』としたのです。著者は、「あたかも鄭玄が『周礼』『儀礼』『礼記』を『三礼』として、彼の経学理論体系の核心をなす経典としたのと同様、朱熹も『四書』を彼の経学理論体系の核心と位置づけた。したがって、朱熹は『四書』を極めて重視し、その注を編纂することには最大限の努力を傾注した。その結果、朱熹の『論語集注』は、歴代『論語』注釈の中でも最も丁寧で、しかも論理明晰なものとなっている。200年に亡くなった鄭玄と、1200年に亡くなった朱熹と、ちょうど1000年を隔てるこの2人は、経学の歴史において、その他諸人を遠く引き離して突出して重要な位置を占めている」と述べています。
朱熹の集大成した宋代の思想体系は、元・明・清三朝に亘って朝廷が堅持する中国の正統思想となり、『四書集注』も科挙の必修教科書となったことを紹介し、著者は「明・清から20世紀に至るまで、膨大な数の学者が性理学や朱子学の研究に没頭し、大量の著作を遺しているが、『四書集注』の影響の深さは、単にこれらの専門の研究の範囲に限られるものでは到底無い。何しろ、中国の士大夫は例外なく子供の頃から『四書集注』を勉強したのであり、それによって、朱熹が集大成した宋代の社会思想体系は、人々の心に深く根を張り、無自覚のうちに思考を強く規定することとなり、現在に至るまで、人々の道徳判断に深い影響を与え続けている。この意味で、元・明・清から現代に至る中国の人々の思考を理解しようとする時、『四書集注』はまず必ず読まれなければならない最重要文献なのだと言わなければならない」と述べます。
第六章「清代の『論語』研究」では、近代以前の経学者は、『論語』から聖人の教えを読み取ろうとし、どのように解釈すれば聖人の本義(本来の意図)を正しく理解したことになるのかを研究したとし、「近代以降の学者は、聖人の教えなど封建道徳に過ぎないと否定し、『論語』は春秋時代の書物であると考え、正しい客観的解釈によって、春秋時代の孔子一門の史実を明らかにすることを目指した。魯迅が引用したある詩人の有名な言葉に、『絶望が虚妄であるのは、まさに希望と同じである』という。私はこれを借りて、『歴史の事実が虚妄であるのは、まさに聖人の本義と同じである』と言いたい」と述べるのでした。
第Ⅱ部「作品世界を読む――私の『論語』、あなたの『論語』」の第一章「異なる解釈で読む『論語』」の「孔子の時代」では、厳しい世情に現実的に対応するというだけではなく、人々がどのように考えてどのように行動すればよりよい社会になるかを考えたのが孔子であったとして、著者は「孔子は理想の社会を追求したが、堯・舜・周公といった過去の聖王の時代には理想社会が実現していた、としたので、宗教的空想を説くことは無かった。目先の現実にいかに対応すれば個人にとって有利か、という現実的個人主義は採らなかったが、かといって社会を超越した個人の解脱も追求しなかった。理想社会を考えながら、常に個人の道徳倫理を根本としたので、個人を超越した社会制度の設計を研究することもなかった。このように考えれば、ありきたりのお説教ばかりと見られがちな孔子の考えに、その他の古代の思想家・宗教家とは異なる特徴があることが分かるだろう」と述べています。
「『礼』の本質と変容」では、古代の「礼」とは「人間(社会)関係のあるべき形」とでも言うべきものであったから、それを濫用して、媚び諂いの手段とする人がいたとしても、それは礼そのものが問題なのではないとして、著者は「つまり、『礼』という言葉には、心がこもらない形式という含みは本来全く無いのである。だから、礼は後回しだとか、礼よりも真心が大切だ、というような考え方は、古い時代にあっては、何とも理解しがたいものであったに違いない。南宋ではそのような考え方が可能であった、ということは、『礼』が既に形式的儀礼を意味する概念に成り下がっていたことを意味する」と述べます。
続けて、著者は「勿論、このような言い方は精確ではない。何故なら、朱熹も『礼』なるものを非常に重視し、『論語集注』の中でも繰り返し『礼は天理の節文』というような解説を述べているから、朱熹が『礼』を単なる形式的儀礼と理解していたなどとは、間違っても言えない。それでも、社会関係が固定的になるにつれて、人間関係も形式化され、現実的には『礼』が日常生活における固定的形式儀礼に矮小化されていったことは想像に難くなく、だからこそ朱熹の注の解釈が受け入れられたと考えざるを得ない」と述べています。注目すべきは、「礼」という概念に関する異なる理解が、『論語』の解釈を左右する大きな要素の1つであったということです。
また、「楽の形」として、「礼」と「楽」は、常に一組として考えられるとして、著者は「例えば、子路篇に『名が正しくなければ言葉も順当でなく、言葉が順当でなければ仕事も出来上がらない。仕事が出来上がらなければ礼楽もおこらない。礼楽がおこらなければ刑罰も的をはずれる(名不正則言不順、言不順則事不成、事不成則礼楽不興、礼楽不興則刑罰不中)』と言い、季氏篇に『天下に道があれば礼楽や征伐は天子から出ますし、天下に道が無ければ礼楽や征伐は諸侯から出ます(天下有道則礼楽征伐自天子出、天下無道則礼楽征伐自諸侯出)』と言うのを見れば、『礼楽』が刑罰や征伐と並ぶ重要なものとして語られていることが理解できよう」と述べています。
「古典とその意味」では、『論語』に代表される古典は、単に古い時代に書かれた文献というだけでなく、1000年2000年と多くの人々に読み継がれ、多くの人々の思考に深い影響を与えてきたとことに重大な価値があるとして、著者は「100年前の人も、500年前の人も、1000年前の人も、2000年前の人も、皆『論語』を読んだ。そういう人たちによって、この社会、この文化が作られてきた。2000年前の人も500年前の人も、我々が理解・共感することのできる同じ人間であり、我々の社会・文化は500年・2000年の歴史の沈澱の上に成り立っている、と考えるならば、我々は『論語』に非常に大きな興味を持たずにはいられない。このような興味から考えるならば、2000年以上も地中に埋もれていて、近年突然発見された竹簡・帛書などは、2000年前の現実を現在に伝える珍しい資料である一方で、正にその2000年の歴史の重みを欠く点で、古典としての意義は無いと言える」と述べます。
 湯島聖堂の「孔子の木」の前で
湯島聖堂の「孔子の木」の前で
また、著者は『論語』を巨木に例えます。それは、正に2000年以上の時間を経ることによって、始めて現在の巨大な姿となって我々の目の前にあるとして、著者は、「栴檀は双葉より芳し、2000年前の若木の時にも、既に他の雑木とは違っていただろう。しかし、若しある人が、様々な手段を用いてその若木の姿を復原し、それこそが『論語』の本来の姿であり、2000年後の現在、『論語』は随分老化し歪曲して本来の美しさを失っている、と主張するならば、私はその人は歴史を知らない、と言うだろう。私の前にあるのは蒼然たる巨木であり、その巨木が形成してきた周辺の風景である。我々は、そのような風景の中に生きている。巨木の2000年前の姿は、あくまでも可能な幻想に過ぎない。それを真実として追求するのは、迷信的狂気だ。私は、現在の巨木の姿をありのままに観察し、その肌膚の間に2000年の滄桑を感じ取ることを喜びとする」と述べます。木といえば、一条真也の新ハートフル・ブログ「孔子の木」に書いたように、今から約100年前、湯島聖堂、足利学校、閑谷学校、多久聖廟の4カ所に楷の木すなわち「孔子の木」が植えられました。わたしは、そのすべてを訪れ、わが社の小倉紫雲閣や天道館の庭にも「孔子の木」を植樹しました。とても巨木には育っていませんが。
 小倉紫雲閣の「孔子の木」の前で
小倉紫雲閣の「孔子の木」の前で
古典は、とりわけ『論語』のように表現が簡単な古典は、色々な意味で理解される可能性を持っています。しかし、わたしたちは、その全てを聞き取ることはできず、自分の心の琴線と共鳴する部分だけを聞くことになると指摘し、著者は「同じ『論語』を聞いている筈でも、私に聞こえている音と、あなたに聞こえている音は、同じではない。それは、どちらが正しい音なのかという問題ではなく、私の琴線とあなたの琴線が違っているという問題なのである。ということは、『論語』の音を聞くということは、実際には聞く人それぞれに異なる心の琴線の音を聞くことに他ならない。本書を書くに当たって、まず『心の鏡』という、何とでも解釈できそうな漠然とした副題を付けた。『論語』が小さな本であることも、『鏡』という言葉を選んだ理由の1つだが、もっと直接的な理由は、色々な人が『論語』を読み、『論語』を解釈することが、あたかも人が鏡を覗き込むようなものだと思われるからだ」と述べます。
第二章「『論語』と中国社会」の「同心円型社会関係」では、著者は以下のように述べています。
「思うに、西洋の法秩序や、日本の道徳秩序は、社会共通の信仰ともいうべき抽象観念に頼る部分が大きい。西洋の社会秩序は、神あるいは国家の公正を信仰する所に成り立っていた。西洋が団体中心固定関係社会ならば、日本は個人抹消全体主義社会である。搾取もするが保護もする、というのが日本の上下関係であり、下位者は不公正な処遇を受けても、上位者がいつかは事情を理解し、自分を救ってくれるはずだ、と信じて我慢した」
しかし、西洋においても日本においても、そのような信仰は、既に揺らぎつつあると言うべきであろうとして、著者は「既成秩序の崩壊は、誰の目にも明らかである。信仰の箍が完全に外れてしまえば、西洋や日本の社会は全くの混乱に陥らざるを得ないのであるが、この時、孔子の教えは、我々に最低限の道徳と社会秩序を確保する道を示してくれるであろう。何故なら、孔子の説く道徳は、そのような信仰が完全に否定された状況に立脚して考えられているからだ。人間みなそれぞれ自分を中心に考えて生きている、それを認めて、そこを出発点として、何とか社会をより善いものにしていこう、というのが孔子の考えである。正に、これからの西洋・日本が参考にすべき思想であると言えよう」と述べます。
また、「近代国家と『論語』の思想」では、大勢の人間が、お互いそれぞれ個人の生活を全うできることが、社会に求められる条件であると指摘し、「個人に生命・財産を差し出させ、資本家や政治家の生活を保障するだけの国家などは、あってはならない。国家や集団を個人の上に置こうとする許術を否定するには、孔子に習って、地に足をつけて、個人の生活を根拠に、そこから各種国家・集団の存在価値を評価しなおす必要がある」と訴えるのでした。
さらに「正常な生活を全うすること」では、著者は「孔子の信念を示す最も切実な言葉は、これだ」として、以下の言葉を紹介します。
子畏於匡。曰、「文王既没、文不在茲乎? 天之将喪斯文也、後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也、匡人其如予何?」(子罕篇)
この口語訳は、「先生が匡という所で難儀をされた時の言葉に、『文王はもう亡くなられたが、文はここに残っているぞ。天がこの文を滅ぼそうとするなら、後まで生き残ったものはこの文に携わることができないはずだ。天がまだこの文を滅ぼさないとすれば、匡の連中ごときに我等が参るものか』」となります。
そして、著者は「孔子は、伝統文化の体現者を以て自任した。そして、その文化理念の価値を疑わなかった。これは信念であり、そこには私欲は無い。ここで私が死ぬとすれば、この伝統文化はそれで滅んでしまう。そんなことは起こりえないであろう、というのである。このような確信があれば、どこへ行っても生きていけるであろう」と述べるのでした。
「おわりに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「100年ばかり前から、近代化への動きに伴って、中国では儒教的封建道徳が激しく批判されるようになった。それは、儒教的封建道徳が、確かに人間の自由を著しく抑圧していたからで、魯迅が『人を食う礼教』と言ったとおりである。それでは、『論語』を代表とする儒教の経典が本質的に『人を食う』、つまり非人間的なものであったのか、といえばそうではなく、そのような非人間性は朱熹の注を直接の起源としている」
本書では敢えて詳しく紹介しなかったそうですが、著者は「朱熹の解釈は、官僚・士大夫に対して、忠君愛国・滅私奉公の禁欲的自己規律を呼びかけるものであった。実際にはそんな真面目な考えの人が少なかったからこそ、朱熹は一生懸命訴えたのである。それが高潔な理想である間はよかったのだが、後世には朱熹の教えが朝廷を支える基本思想となったから、必然的に教条化への道を歩み、科挙の必修内容となったために、社会下層にまで浸透することとなった。ここにおいて、儒教は中国社会全体を覆う『人を食う』猛獣となったのである」と述べます。
1990年代から、日本政府の政策は明らかな変化を見せ、現在かなりの程度で弱肉強食・無法無天の荒廃した社会となっていますが、混乱は今後も更に長く続くように思われるとして、著者は「この荒廃の感覚は、どうも孔子の時代に近いように感じられてならない。孔子が繰り返し強調する『仁』は、明確な定義を与えるのは不可能だが、人と人の間の望ましい結び付きを言っている。人は一人では生きられない。荒廃した社会であればあるほど、他人との結び付きは切実に重要なのである。生きていくためには、よりよく生きるにはなおさら、他人との結び付きを確かなものにしておく必要がある」と述べています。
著者は、本当に困った時に「役所が助けてくれる」などと思ってはいけないと訴えます。そして、「もちろん、政府には弱者を助け、市民の安全を保障する義務があり、我々はその誠実な履行を要求し続けるだろうが、それを当てにしてはいけない。そんなものを当てにしようとすれば、言われるまま次々と自由を奪われて、知らない間に身動きも取れなくなってしまう。本当に頼りになる可能性があるのは、身近な人間である。だから、身近な人間との関係を大事にしなければならない。もちろん、近くにいれば誰でもよい、ということではなく、互いに信頼しあえる人間が大事なのである。そう考えた時、一般的に言って、一番身近で信頼しあえるのは親子の関係であり、兄弟の関係である」と述べています。
そして最後に、著者は「孔子は、子供は親の奴隷になれ、と言ったのではなく、周りの大事な人間との結び付きを固めよ、その第一歩として親子の絆を固めよ、と言っているのだ。そして、同様に兄弟や義兄弟や友人との絆を固めていく。そのような固い絆こそが、個人の自由と独立を守る砦となるのである。これこそが、乱世を生きる道である」と述べるのでした。本書は、わたしがこれまで読んできた『論語』の研究書とはまったく違った一風変わった内容でしたが、北京大学の教授まで務められただけあって、著者は本当に深く『論語』を研究されているという印象を持ちました。『論語』が「人を食う礼経」と呼ばれる責は孔子には一切なく、朱熹にあるというのはまったく同感です。