- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2059 論語・儒教 『天皇と儒教思想』 小島毅著(光文社新書)
2021.08.04
『天皇と儒教思想』小島毅著(光文社新書)を読みました。「伝統はいかに創られたのか?」というサブタイトルがついています。著者は1962年生まれ。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は中国思想史。東アジアから見た日本の歴史についての著作も数多くあります。著書に一条真也の読書館『儒教が支えた明治維新』で紹介した本(晶文社)をはじめ、『増補 靖国史観――日本思想を読みなおす』 『朱子学と陽明学』(以上、ちくま学芸文庫)、『近代日本の陽明学』(講談社選書メチエ)、『父が子に語る日本史』『父が子に語る近現代史』(以上、トランスビュー)、『「歴史」を動かす――東アジアのなかの日本史』(亜紀書房)、『足利義満――消された日本国王』(光文社新書)、『儒教の歴史』(山川出版社)などがあり、監修したシリーズに『東アジア海域に漕ぎだす(全6巻)』(東京大学出版会)があります。
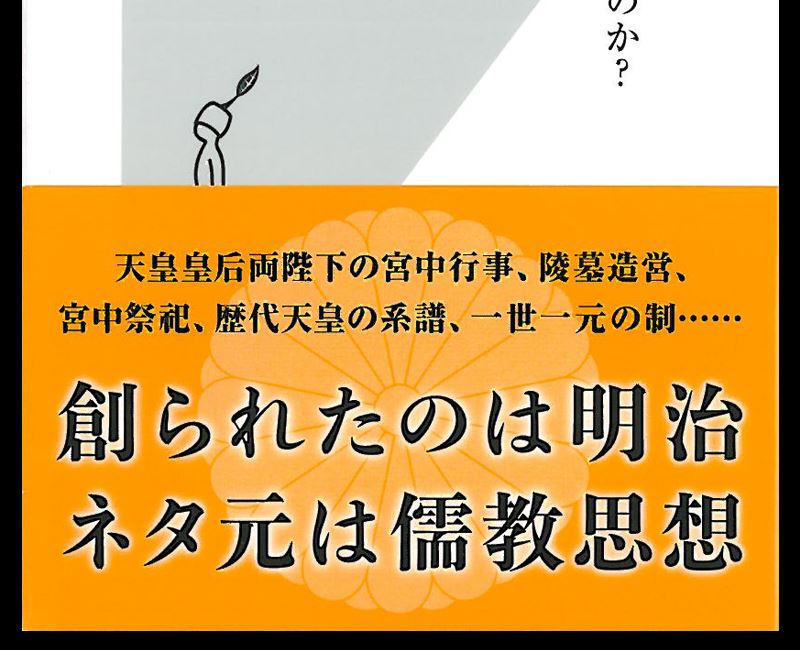 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「天皇皇后両陛下の宮中行事、陵墓造営、宮中祭祀、歴代天皇の系譜、一世一元の制……」「創られたのは明治 ネタ元は儒教思想」と書かれています。帯の裏には、「天皇や皇族の日常生活が、明治維新のあとは洋装にお変わりになり、洋館にお住まいになり、洋食を召し上がるようになったというたぐいのことは目につきやすく、『近代化』を象徴する行為として認識されていよう。しかし、じつは祭祀・儀礼といった、古くからの伝統に由来しているはずの行為も、その多くがやはり明治維新の前後に新しく始まったものだった。洋装・洋館・洋食といった西洋化とは異質ながらも、それらもまた明治時代の近代天皇制を支える装置だった。すなわち、古制という名目によりながら、近代天皇制にあわせて改変されたものだった。(「はじめに」より)」と書かれています。
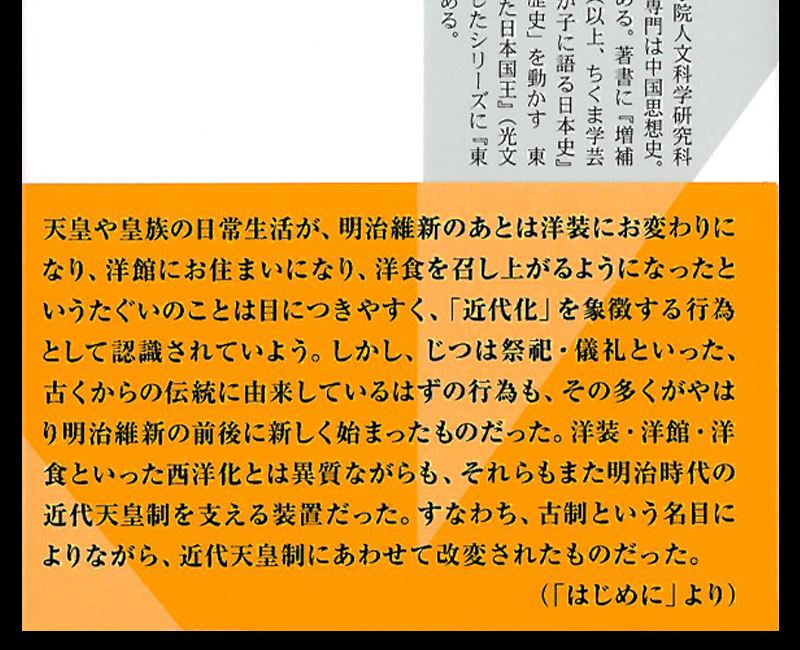 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「8世紀の日本で、律令制定や歴史書編纂が行われたのは、中国を模倣したからだ。中国でそうしていたのは儒教思想によるものだった。つまり、『日本』も『天皇』も、儒教を思想資源としていたといってよい。その後も儒教は、日本の政治文化にいろいろと作用してきた。8世紀以来、天皇が君主として連綿と存続しているのは事実だが、その内実は変容してきた。江戸時代末期から明治の初期、いわゆる幕末維新期には、天皇という存在の意味やそのありかたについて、従来とは異なる見解が提起され、それらが採用されて天皇制が変化している。そして、ここでも儒教が思想資源として大きく作用した。本書は、その諸相を取り上げていく」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
〈巻頭コラム〉本書の内容をよりよく理解するための儒教の基礎知識
第一章 お田植えとご養蚕
第二章 山陵
第三章 祭祀
第四章 皇統
第五章 暦
第六章 元号
「より詳しく知りたい人へ」
「おわりに」
「はじめに」の「天皇をめぐる諸制度は明治時代に改変された」では、「天皇をめぐる諸制度の多くは、じつは明治維新の前後に新たに創られたものである。本書はこれらのなかから、農耕と養蚕、陵墓(皇族の墓。みささぎ)造営、宮中祭祀、皇統譜、一世一元を取り上げる。また、新しい制度だとすでに広く認識されている太陽暦の採用についても扱う」と書かれています。
また著者は、「『日本古来の伝統の維持』を声高に唱える論者たちが、江戸時代までの天皇制(この語はもともと左翼用語だが、これに代わる適切な語を思いつかないのでそのまま用いる)を支えてきた暦制をいとも簡単に捨て去った明治の改暦について、反省的言及を行っている形跡がまったく無いのが、私には不思議でならない。ローマカトリック教会の教皇グレゴリウス13世が、彼らの紀年法で1582年に決めた暦を使うことは、天皇制にとって由々しき事柄であったはずである。仏教や神道の信者たちがその宗教行事にこのキリスト教の暦をいまや平然と用いている姿が、私には理解できない。その逆(キリスト教会が旧暦でクリスマスを祝う等)を想像してみれば、事柄の異常さがわかってもらえるだろうか。そんなことはありえないからである」と述べています。
「明治維新は日本の近代化を推進した」という歴史認識がひろく行きわたっているわりには、天皇制もまた明治維新によって近代化されたことについては、あまり知られていないとして、著者は「天皇や皇族の日常生活が、明治維新のあとは洋装にお変わりになり、洋館にお住まいになり、洋食を召し上がるようになったというたぐいのことは目につきやすく、『近代化』を象徴する行為として認識されていよう」と述べます。しかし、じつは祭祀・儀礼といった、古くからの伝統に由来しているはずの行為も、その多くがやはり明治維新の前後に新しく始まったものだったと指摘し、「洋装・洋館・洋食といった西洋化とは異質ながらも、それらもまた明治時代の近代天皇制を支える装置だった。すなわち、古制という名目によりながら、近代天皇制にあわせて改変されたものだった」と説明します。
「『日本』の自明性を疑う」では、沖縄や北海道を除いて、この国土は古来一貫して「日本」だったとする言説があることを紹介します。高校の「日本史」という科目は、この国号が生まれるよりも前から日本の一体性を自明の前提とすることで成立しているとして、著者は「縄文式土器についても、日本列島のなかで似た様式の土器が焼かれ、その土器をふくめて交易の痕跡が見られるという。このことから、縄文時代にまだ国家はなかったものの、すでに地域としての日本が成立していたとみなすことは可能かもしれない。しかしながら、たとえ縄文文化が列島において広域的な同質性を持っていたとしても、縄文人たち自身がそのことを『我々は同じ民族であり、仲間だ』と自己認識していたわけではない」と述べます。
日本はこの国号が定められて以来、1300年間にわたって一度も外国の直接統治を受けていません。例外的に1945年からの6年間は、米国を中心とする戦勝国の間接統治下にありました。そして、この間はずっと、天皇が君主として連綿と存続しています。つまり、「日本」の歴史は「天皇」の歴史でもあったとして、著者はそこに儒教の多大な影響がったことを指摘し、「律令制定や歴史書編纂をおこなったのは中国を模倣したからだが、中国でそうしていたのは儒教思想によるものだった。つまり、『日本』も『天皇』も、儒教を思想資源としていたといってよい」と述べています。
その後も儒教は日本の政治文化にいろいろと作用してきました。本書が取り上げるのは、19世紀における天皇をめぐる諸現象であるとして、著者は「8世紀以来、天皇が君主として連綿と存続しているのは事実だが、その内実は変容してきた。江戸時代末期から明治の初期、いわゆる幕末維新期には、天皇という存在の意味やそのありかたについて、従来とは異なる見解が提起され、それらが採用されて天皇制が変化している。そして、ここでも儒教が思想資源として大きく作用した。本書はその諸相を取り上げていく」と述べています。
「本書の立場について」では、著者が述べようとしている内容は、「神道の信者ではないひとりの思想史研究者が、おのれの学術的良識から披露する『史実はこうだった』という見解である。それは『イエスは神の子ではない』とか『ムハンマドは神のことばなど聞いていない』と同様、対象とされる宗教(ここでは神道)の信者が不快な思いをする内容であろう」と述べ、さらには「孟子やソクラテスがかつてそうしたように、人々にとっての常識的通念とは異なるものの見方を示すことから、哲学は始まった。本書が、みなさんが思い込んできた天皇の『古来のありかた』と異なる像を示しているならば、それは私の試みが成功した証である」とも述べます。
巻頭コラム「本書の内容をよりよく理解するための儒教の基礎知識」の【儒教の成立】では、儒教の開祖として、今はふつう孔子(前552頃~前479)の名をあげますが、この言い方には二つの点から留保が必要であるとして、著者は「1つには、史実として儒家思想の基礎を据えたのは孔子だが、かつての儒教のなかでは孔子はあくまでも伝統的価値の祖述者だった。孔子より遥かに昔から、聖人とされる王たちによって儒教が理想とする統治がなされており、孔子は、彼の時代に失われつつあった、この正しい伝統を継承・復活させようとした人物として位置づけられた。したがって、本書に登場する日本の儒学者たちはみな、儒教の教説を孔子の思想としてではなく、太古の中国に実在していた社会秩序だと認識していた。そして、もう1点、そうした儒教教義が成立するのは、孔子の活躍から500年後、前漢末から後漢はじめであった。つまり、史実として孔子が説いたことと、漢代に儒教として体系化された教義とは別のものである」
【四書五経】では、漢代に編集整備された経は5種類あり、五経と呼ばれることが紹介されます。ふつう、これを易・書・詩・礼・春秋の順に並べていいます。著者は、「易とは占いだが、自然界のしくみを解き明かした書物とされた。書は堯・舜・三代の為政者たちの記録(尚書、書経ともいう)。詩は周代に宮廷や民間で歌われた歌詞。礼は社会秩序や行為を規定したもの。春秋は魯という国の年代記である」と説明します。朱子学では、五経の前に学習すべき書物として、大学・中庸・論語・孟子の四つをあげ、まとめて四書と呼びました。いずれも聖賢の発言や行為を記録していますから、後世の学習者にとって手本になると考えたのです。四書は経として扱われました。
【三礼】では、本書で扱う天皇にかかわる祭祀や儀礼、暦の制定などは、儒教で「礼」と呼ばれる分野であるとして、著者は「礼の経としては、西暦2世紀になって3種類が並び、三礼と呼ばれるようになった。『周礼』は周王朝の官制とされ、歴代王朝が典範とした。日本の律令官制もその間接的影響を受けている。『儀礼』は冠婚葬祭などの式次第を記したものだが、規定どおりに遵奉するのはなかなか困難であったため、後世これを簡略化した本が多く作られた。なかでも、朱子学の大成者である朱熹(1130~1200)の『家礼』は、規範として作用し、日本でも一部の大名がその実践を試みた」と説明しています。
三礼の最後の1つである『礼記』は、さまざまな文献を寄せ集めた書物で、內容が礼の全般にわたるため、実際の祭祀・儀礼を定めるときに活用されました。著者は、「もともと相互に独立して書かれたため、『礼記』諸篇や『周礼』・『儀礼』の記述内容には相互にそれぞれ矛盾する記述が多く、これらを総合的に解釈して礼学を体系化するのが儒学者の腕の見せ所だった。吉備真備(695~775)らが唐で学んだ礼学によって日本の律令体制は確立したため、神道の諸制度には、儒教の三礼を思想資源とするものがもとから存在していた」と説明しています。
【葬祭】では、三礼には正しい葬儀の仕方が規定されており、古代中国の実態を反映しながらも儒学者たちによる理想化が施されていることが紹介されます。儒教では、人間の生命活動を魂と魄に分けて捉えるため、死者についてもその両方を対象とした扱いをします。著者は、「孝の思想(祖先がいたから自分がいるという考え方から、親や祖先を大事にする思想)によって祖先を祀りつづけることが重視されたため、その一連の祭祀のやりかたが経学上の議論の対象にもなった。ただ、儒教である以上は、礼に従った墓を設けてそこに土葬すること(遺体を火葬することは親不孝として排斥された)、歴代の先祖を祀る施設(廟)を設け季節ごとの定期祭祀を行って供物を捧げることが大原則だった。そのため、火葬(荼毘)を推奨したり、仏像への礼拝を広めたりする仏教は、儒学者たちにとっては教義上敵対する宗教だった。ところが、日本では、律令制定の際の天皇だった持統天皇からして火葬されているくらいで、当初から儒教のこの面は受容されないまま江戸時代を迎えている」と説明しています。
【皇帝】では、儒教においては、経の中に登場する三代の「王」たちは、自分たちの君主として君臨している「皇帝」に相当するとしたことが紹介されます。したがって、皇帝が行う祭祀・儀礼は、経のなかの王についての規定を遵用して定められましたが、著者は「その際、経学上の相違が『本来の正しいやりかた』をめぐる論争となった。中国や韓国ではしばしばこれが政争と結びついた。なお、韓国では自国の君主を皇帝より一段低い『王』としたため、経に登場する諸侯に相当する祭祀・儀礼を行うことが多かった。日本では律令制定と同時期に、皇帝と同格の君主号として『天皇』を創案した。そのため、儒学者たちは天皇の祭祀・儀礼を、経のなかの王や漢代以降の皇帝になぞらえて議論してきた」と説明しています。
【王朝交代】では、中国では古来、王(皇帝)の家系(姓)が変わるにともなって王朝の交代が生じてきたとして、著者は「経には堯・舜・三代が交代した歴史が書かれており、儒教は易姓革命(天命が革まって、君主となる人を世襲で輩出する家の姓が易わること)の理論を内包することになった。禅譲と放伐である」と説明しています。放伐とは、殷の紂王が暴君だったために、聖人だった周の武王が取って代わったことをいいます。ただし、1人の諸侯として殷王朝に臣従していた周の武王が武力をもって殷の紂王に挑戦した史実は、臣下が君主にそむくことになるため、儒教の教理上は異例の措置だったと解釈され、実際には行わないのがよいとされました。
とはいえ、宋代以降は平和的な禅譲方式ではない、軍事力による放伐形式の王朝交代となりました。明は1368年に蒙古(元)を中国から追い出し、清は1644年に軍事侵攻して中国を支配下に置きました。著者は、「朱子学の理念として王朝交代は無い方がよいため、日本の儒学者・国学者たちはこの点から同時代の中国に対して優越意識をもっていた。記紀以来、日本は万世一系で天皇家が統治してきたとされていたからである」と述べています。
第一章「お田植えとご養蚕」の「お田植えは昭和天皇から」では、日本国の象徴たる天皇が日本人を代表して稲を育てるのは、『日本書紀』にいう「豊葦原千五百秋瑞穂国」にふさわしく、古式ゆかしいという形容句がぴったりに思えると述べられています。その一連の作業は、天皇が代々実践してきた、いかにも伝統行事のように見えますが、天皇みずからお田植えをなさるのは、ご先代の昭和天皇がお始めになった行為にすぎないとして、著者は『SAPIO』2015年2月号の以下の記事を紹介します。
「天皇陛下がお手ずから行なう『お田植えとお稲刈り』は昭和天皇が始められたもので、昭和2年から続く。今上陛下は田植え(5月)と稲刈り(9~10月)だけでなく、4月の種撒きからされている。さらに、昭和天皇が前年の種籾から育てた苗2種類を自ら5株ずつ植えられていたのに対し、今上陛下は改良品種も毎年5株ずつ加えるようになった。現在、その数は200株に達する。収穫の時、稲は6株を残し刈り取られ、残した6株は根付きのまま掘り起こして伊勢神宮の神嘗祭に奉納される」
「皇后によるご養蚕」では、明治4年(1871年)、皇后(昭憲皇太后)が宮中で養蚕を復活させたことが紹介され、「正月上旬の辛の日に行うのが、この豊作祈願の儀式の由来だったからだ。そして、玉箒の方も、儀礼上の用具とはいえ、蚕を育てる際に実際に用いる道具を表していた。つまり、この日の儀式とは、農耕と養蚕をもって国民の生業を象徴し、それを天皇が模擬的に実演することで神々に1年の平穏を祈願する意味があったのである」と書かれています。著者は、「遠いいにしえの儀式を久しぶりに復活するとは、神武創業への復古を掲げる明治政府の面目躍如である」と述べています。
平安時代以降、藤原氏本家たる名門五摂家出身の歴代皇后たちは、おんみずから蚕を飼ったという事実はありません。ところが、明治政府は皇后にそうしてもらいたいと考えました。その前例を『日本書紀』や『万葉集』に求め、新例としてではなく旧慣復興という口実にしたのです。著者は、「そうすることで、蚕の幼虫を宮中に持ち込むことへの抵抗感を排除したのだろう。その目的は殖産興業だった。生糸生産を王権の威信を借りて推進するという現実的政策である」と述べています。
この件には実業家として名高い渋沢栄一が関与し、宮中吹上御苑の茶室がその用に充てられました。渋沢は武蔵国榛沢郡(埼玉県深谷市)の豪農の出身、まさしく養蚕地帯に近接した場所であり、その流通に精通していた人物です。著者は、「国策として、輸出産業の主力となることが期待されていた絹織物生産の基礎となる養蚕を、皇后みずから推奨するかたちをとることが、明治政府の意図だった。その後、若干の曲折はあったものの、養蚕作業は代々の皇后に受け継がれていく」と述べています。
「中国の籍田と親蚕」では、著者は「中国では古くから、農耕と養蚕の両者が皇帝・皇后夫妻によって分掌されていた。明治時代の養蚕儀礼の再興には、直接・間接にその影響を想定することができる。つまり、現在日本で行われているこの一組の儀礼も、その起源は中国の儒教にあるのだ」と述べます。10世紀の宋代になると空洞化しますが、儀礼は廃止されることはありませんでした。著者は、「名目上だけでも存続したのは、農耕社会の生業を、君主夫妻が象徴的・視覚的に実演することが不可欠と思念されていたからであろう。『汚泥に御足をけがし』(細井平洲の表現)たり虫を愛でたりすることを全くしてこなかった日本の天皇・皇后とは、やはり異質であった。この点から見ても、明治時代の皇后のご養蚕・昭和時代の天皇のお田植えは、天皇制の変質、それも儒教への傾倒を物語る事例と言えそうである」と述べています。
「水戸学の祭政一致論」では、天皇が行う農業に関する儀礼として、収穫感謝の祭祀も存在したことが紹介されます。著者は、「儒教では、籍田が春に行われる豊作祈願の儀式であるのに対して、秋に収穫(豊作)を感謝する儀式として『享』が定められていた。経学解釈上、本来のその儀式については諸説あるが、やがて皇帝による明堂(君主が儀式を行う建物)での天の神への祭儀として制度化されていく。一方、日本では儒教の影響を受ける前から、王権による収穫感謝祭が独自の様式で行われていた。これが律令にも残存し、歴代天皇によって実施されていく。毎年の収穫感謝祭を新嘗祭と呼び、代替わり直後の年については大嘗祭という名が定着した」と述べています。
ここで、著者は会沢正志斎を取り上げます。会沢正志斎といえば、19世紀前半の後期水戸学を代表する思想家です。著者は、正志斎について「晩年は幕府に従順な態度を示したため、過激派(天狗党激派)から批判された。だが、彼が主張していた政治秩序構想は、祭祀・政治・教学(正しい教義として教育機関で伝授され、臣下・庶民を導く倫理とされるべき内容)の一致を掲げて、尊王攘夷運動の起爆剤になったと評価されている」と述べています。わたしは、「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生とWEB上の往復書簡「シンとトニーのムーンサルトレター」を満月の夜ごとに交わしています。その第176信で、わたしの考え方は会沢正志斎を連想させると鎌田先生から指摘されたことがあります。
さて、会沢正志斎は、大嘗祭の「嘗」の字義は、その年に収穫されたばかりの穀物を天神に供えることだと考えました。そして、ここに自注して、限定して天祖と呼び、群神の汎称として天神というのだとしました。著者は、「すなわち天祖は天照大神のこと、天神は記紀の用法どおり高天原に由来する神々全体、天神をさすというのだ。そもそも、天祖がめでたい種を得てそれを田で栽培し、天下万民の食糧とした。これと並んで天祖は口に繭を咥えて養蚕を開始し、万民の衣服のもととした。天孫降臨にあたって天祖が万民に稲を与えたので、嘗の祭儀をもってその恩に謝するのである、と」と説明しています。
さらに会沢は、収穫感謝祭としての嘗に、祖先祭祀としての性格も与えているとして、著者は「中国儒教の場合、収穫感謝は天神に対する祭祀・嘗は人鬼としての祖先(中国語で鬼は死者の霊であり、和語の「おに」とは異なる)への宗廟(祖先、特に君主を祀った建物)での祭祀であり、別物とみなされていた。ところが、日本では後述するように、古代に収穫感謝祭に『嘗』という漢字をあてた。このように、日本では収穫感謝祭に「嘗」という祭祀名を用いたため、中国の儒学者たちとは異なって、会沢のように収穫感謝祭と祖先祭祀とを結びつけて説明する議論が、可能になっていたのである」と説明しています。
新嘗の語義は、その年に新しく収穫された穀物を供えて神と共食することです。「嘗」は儒教経学上は秋に行う祖先祭祀の名称ですが、ここでは字の原義どおり「なめる」という意味です。そのため、会沢正志斎『新論』のように、後世になると神儒一致の立場から、儒教経学上の嘗の礼で、説明を試みる論者が現れることになると指摘し、著者は「つまり、7~8世紀の律令制定の頃に儒教用語を借用し、その意味を変容させて土着の王権祭祀に漢字名称を与えていたものが、江戸時代の神儒一致論のなかで『文字が同じなのだから意味も同じはず』という理屈を呼び出すことになったわけである」と述べています。
第二章「山陵」の「大王古墳と皇帝陵」では、兵馬俑で有名な秦の始皇帝陵がそうであるように、中国においては皇帝の陵墓は広大な面積を有していたことが紹介されます。前漢最大の武帝陵(茂陵)は、一辺に230メートルあまりの方形墳、唐最大の太宗陵(昭陵)にいたっては、180余の陪葬墓(臣下の墓)をともなった、面積約200平方キロ、九嵕山と呼ばれる標高約1200メートルの自然の山を利用した山陵です。邪馬台国女王卑弥呼の使節が朝貢したのは魏の明帝ですが、その父文帝(曹丕、皇帝在位220~226)は、巨大な陵墓造営を自制すべく薄葬(簡略化した葬儀)を指示して崩御しました。
魏は儒教王権だったから、その陵墓制も儒教の教義的影響を受けていたとして、著者は「薄葬は、一般に死者を厚く葬ることをよしとする儒教の教えに反するようだが、始皇帝や漢の武帝のような巨大墓造営に国力・民力を消耗することは仁政ではないとする、儒教の理念にかなっている。皇帝の陵墓が人工的に造られたものではなく、自然の山を用いた山陵であったりするのも、そうしたところに一因があろう。儒教の墓は、その元祖とされる孔子の墓がそうであるように、遺体を棺に入れて埋め、さらに外枠(椁)で覆い、その場所に盛り土をする。墓の前には墓参に際して供物を並べる場所があらかじめ確保され、必要なら墳墓に至る参道も整備する。皇帝をはじめ高貴な身分の人の場合には、参道に石像を林立させて威厳を示す造りになっていた」と述べています。
著者は、以下のように述べています。
「儒教では親に対して死後も孝養を尽くすことが求められており、また伝統中国の死生観(生命活動のはたらきは、死後は空中に遊離する魂と、遺体にとどまる魄とに分かれる)もあって、遺体は土葬していた。仏教のように火葬するのは論外で、親不孝な行為として教義的に批判された。こうした考え方に道教的な不老不死思想が加わると、遺体を生前同様に保存すべく工夫するようになる」
1972年に発見されて翌年から発掘された馬王堆漢墓では、化学的な処理技術を用いたために、2000年前の遺体がきわめて良好な状態で遺っており、発見当時は押すと皮膚がくぼんだそうです。現在は腐敗が進んでしまいましたが、著者は「毛沢東の遺骸が生けるが如くに、北京天安門広場の毛主席紀念堂に永久に安置されているのも、社会主義国の先輩ロシアのレーニン廟を模したとともに、中国古来の死体観念にもとづく面を具えている」と述べます。
「江戸時代の山陵治定」では、平安時代には、『延喜式』で遠陵・近陵(遠い祖先の陵墓と、比較的近い祖先の陵墓)を定め、使節を派遣して祭祀を行う対象としたことが紹介されます。しかし、室町時代ともなると陵墓は顧みられなくなって、どれが誰を埋葬しているのかさえ不明となったとして、著者は「現在、仁徳天皇陵とされている古墳も、本当のところは誰の墓かわからない。そのため、考古学的に厳密には大仙古墳(大山古墳とも)と呼ばれている。幕府も朝廷も仏教を尊崇していたから、長いこと陵墓の考証を志す御用学者も現れなかった。そうしたなか、江戸時代なかばになってようやく陵墓への関心が生まれ、松下見林『前王廟陵記』(1696年)や蒲生君平『山陵志』(1801年)が著された」と述べています。
第三章「祭祀」の「時令の聖典『礼記』の『月令』」では、前3世紀なかば、秦の丞相(首相)呂不韋が編纂させたと伝えられている『呂氏春秋』が取り上げられます。『呂氏春秋』には『十二紀』と称される部立てがあり、毎月の天文・気象、生物の様子といった自然界の特徴と、その月に行うべき人間界の諸行事が列記されていることを紹介し、著者は「これを継承するものとして編纂された『月令』という文章がある。伝承では、漠の文帝(在位前180~前157)のときに、朝廷の博士たちの編纂によるという。その後、前1世紀に戴聖という人物が編纂した、礼に関する諸文献の集成書に収録された」と述べます。この集成書は、礼の経典に対する解説書という意味で、やがて『礼記』と呼ばれるようになり、鄭玄(127~200)によって三礼の一つに認定されました。
三礼とは、礼の経典として『儀礼』と『周礼』、それにこの『礼記』の三つの書物のことですが、やがて『礼記』は他の二書を押しのけて礼経を代表するものとなり、科挙試験の出題対象教材となりました。著者は、「今でも歴史の教科書などで四書五経という語を説明する注に、礼からは『礼記』をあげているのはそのためだが、経学の解説としては正しくない。本来の礼の正統な経審(礼経)は、『儀礼』だったからだ。『礼記』は当初、あくまでもその解説書(「記」)として、雑多なテキストを集成して編纂されたものにすぎなかった。ただし、その諸篇が儒教教義を説いたものとして珍重されたため、経としてのあつかいを受けるに至った。こうして『礼記』の一篇である『月令』は、王朝国家が遵守すべき時令の聖典とみなされるようになった」と述べます。
「祈年祭の盛衰」では、神祇令において、仲春の祈年祭に始まる全部で19ある1年間の諸祭祀を列記したあと、それらの礼式・祭日は「式」によれと命じ、祈年祭と月次祭(季夏・季冬、すなわち6月と12月の年2回ある)については、文武百官が神祇官に集って参列すべきことを規定していることを紹介し、著者は「この『式』とは、中国で律令格式と呼ばれる四種の法令のうちの1つで、法の細則を規定したもの。日本でも編纂開始時の年号を用いて『弘仁式』・『貞観式』・『延喜式』と3回編纂された。このうち本文が現存するのは『延喜式』で、その巻九・巻十に記載された神社一覧、いわゆる神名帳は、今でも神道において重視されている」と説明しています。
『延喜式』が重視される理由は、ここに記載された神社、全2861社は「式内社」と呼ばれ、古くから存在する由緒正しい神社の肩書きとして、今も通用するからです。著者は、「一方、『貞観式』(871年)の本文は散佚したが、この頃の編纂とされる『貞観儀式』(編纂の時期については異論もある。以下『儀式』と呼ぶ)は現存している。この二つの書物は、まぎらわしいが別物だ。『式』が律令全体にわたる細則であるのに対して、『儀式』とは現在私たちが使う意味での儀式、すなわち祭祀などの事項に限定した内容を記載している」と説明します。
「宗廟で祀られる祖先の代数」では、著者は「儒教では、孝についての教義(親だけでなく、祖先に対しても感謝することが人間として当然だとする見解)から、祖先祭祀を重視する。王権儀礼としては、現在の皇帝から見て4代前の祖先までを定例祭祀の対象としていた。直系の場合、高祖父・曽祖父・祖父・父ということになり、これは、父系血縁原理たる宗法において、小宗の最大の範囲とされる祖先だった。(大宗は一族全体。)」と述べています。
「陰陽思想と廟陵」では、祖先に対する祭祀を行う施設である「宗廟」を日本では設けなかったので、その代替措置として近陵制が使われたことが指摘されます。しかし、廟と陵は中国ではまったく別の施設でした。これは中国における身体観に根ざしているとして、著者は「魄は遺体とともにあるので、遺体が埋葬された墓にとどまる。理論的には、墓参とは遺体そのものを拝むのではなく、この魄を祀る儀礼だった。一方、魂の方は遺体を離れて天空に飛び去っていく。子孫が祈ると魂が地上に下ってくるので、これをかたしろ(尸)に寄り付かせ、墓で魄に対してするのと同様に供物を捧げて祀る。そのための施設が廟だった。ところが、日本では、思想的に陰陽・魂魄の区別が導入されたにもかかわらず、祖先祭祀としての廟と墓の区別がなされなかった。後世、仏教の移入によってはじめて両者の区別が明確になる。すなわち、死者の位牌を寺院に置いてその冥福を祈る風習が定着し、遺体(もしくは荼毘に付して火葬した遺骨)を理葬した菩提寺とは、まったく別の場所でも供養の儀式を行うようになる」と述べています。
日本で、家の中に仏壇を設けて祖先の位牌を置く風習は、江戸時代に始まるとされています。すなわち、寺講制度のあと、仏教信者であって切支丹ではないことを証明するために仏像を家庭内に安置し、その仏壇に位牌を置いて、常に灯明をあげ供物を捧げるようになったとして、著者は「祖先各人の命日には僧侶を招いて仏壇前で読経してもらい、その霊を慰撫する。今でもつづくこの宗教儀礼は、釈迦自身の説教には無く、東アジア仏教が布教上の理由で儒教から取り入れたものにすぎない(加地伸行『儒教とは何か』、中央公論社、1990年)。そもそも、位牌自体、中国に仏教が伝わってから、儒教でかたしろに使う木製の板(神主)を模して発明されたものだった。明治時代、天皇の祖先祭祀に神仏分離を適用するにあたって、儒教による廟と墓の区別が意識され、かくして皇霊殿の発明となる。もちろん、教義上は神道であるという名目によって」と述べています。
「彼岸の起源」では、春と秋、年に2度の彼岸は、祖先の墓参りを行う期間とみなされているとして、著者は「日本人の多くが形式上は今でも仏教徒であり、墓も仏教教義(もちろん中国で変容した東アジア仏教の、その日本バージョン)で作られ、そこでの拝礼も仏式に合掌するから、ふつうは仏教に由来する行事と思われていることだろう。ところが、この習俗は日本独自のもので、中国や韓国には無い。中国人、厳密にいえば漢民族が墓参するのは、二十四節気の一つ清明節の日で、グレゴリオ暦では4月5日前後になる。この習俗は唐代の8世紀頃に始まったとされる」と述べています。
韓国では旧暦の8月15日、すなわち中秋の名月の日をチュソク(秋夕)と呼び、この日に一族が集まって儒式の祖先祭祀と墓参を行います。中国の清明墓参は春の行楽、韓国のチュソク墓参は秋の遠足で、その意味では日本の彼岸と共通するとして、著者は「年に2回も行う日本人は、最も祖先への孝心が深いとも、それにかこつけた行楽好きだともいえる。『彼岸』の語は『源氏物語』にも見える(行幸巻や蜻蛉巻)が、江戸時代までは春分・秋分のあとの数日間を指していた。彼岸墓参は、天皇が執行した祭祀に起源を求めることができる。『日本後紀』巻十三、延暦25年(806年)三月辛巳条に『崇道天皇を奉為し、諸国の国分寺の僧をして春秋二仲月別七日に金剛般若経を読ましむ』(崇道天皇こと早良親王の霊をたてまつり、全国各地の国分寺の僧に、春と秋のそれぞれの中の月〈2月と8月〉の7日に金剛般若経を読ませることにした)とある」と述べます。
春秋二仲月における金剛般若経読誦命令は、桓武天皇最晩年にその快癒祈願として出されました。ところが、命令を出した甲斐無く、桓武天皇はまもなく崩御してしまい、この命令が彼岸会の始まりとされているのです。著者は、「やがて浄土思想が普及すると、日輪が真西に沈む春分・秋分が、西方極楽浄土に往生するための作善(仏縁を結ぶための善事を行うこと)の日とされた。さらには極楽にいるはずの祖先を供養する日となり、浄土系以外の諸宗派にも広まって今日に至っている。これに対して、そもそも日本固有の伝統習俗が、崇道天皇の怨霊慰撫行事などを通じて仏教化されたとの見方もある(堅田修「平安貴族の仏事について」、『大谷学報』43巻3号、1963年)。ところが、『春秋二仲月』すなわち旧暦の2月(仲春)と8月(仲秋)に祖先を祀る慣習は、仏典にではなく、儒教経典にその典拠を求めることができる」と述べます。
儒教では、四季の仲月に祖先祭祀を行うことを定式化しました。儲式の国家祭祀一覧は、歴代中華王朝によって成文化・法典化されました。なかでも唐の玄宗が編纂を命じた礼典は、当時の年号をもって『大唐開元礼』と呼ばれ、律令の血肉化のために礼の受容を進めていた日本にも伝わったとして、著者は「ただ、日本では中国と違って宗廟が造営されなかったため、四季の祖先祭祀は定着せず、やがて仏教の祖先供養に取って代わられる。延暦25年の桓武天皇最晩年の命令は、こうした背景をもっていた。春と秋の年2回、祖先の霊を供養する行為が、こうして始まる」と説明しています。現在、「春分の日」・「秋分の日」と呼ばれているこの二つの祝日は、昭和23年(1948年)までは「春季皇霊祭」・「秋季皇霊祭」という呼称の祭日でした。
「皇霊殿の創設」では、宮中三殿での儀礼は、現憲法体制下では、天皇の国事行為もしくはそれに准ずる公務とはみなされず、天皇家の私的な宗教行為とされているとして、著者は「所管部署も正規の官庁たる宮内庁ではなく、掌典職という特別な部署を設け、天皇の私的使用人という位置づけで担当している。賢所は八咫鏡(神鏡)を神体として皇祖天照大神を、皇霊殿は初代神武以来の歴代天皇と近代の皇族を、神殿は天神地祇すなわち天神・国神を祀る。この天神・国神というのは、『古事記』の表記である。天神・地祇は『周礼』に見える儒教用語。日本古来の『あまつかみ・くにつかみ』を、これとは起源を異にする儒教の『天神・地祇』と表記した『日本書紀』の編者(もしくはこれに先行する文献の著者)は、実に巧妙な理論化を施したといえよう」と述べます。
つまり、神殿の祭神には、『古事記』の「天神・国神」ではなく、中国由来の「天神地祇」を用いているとして、著者は「天神・地祇は、もともと儒教で人鬼(死者の功績を称えて神として祀る対象)以外の自然界の神々を指す総称として使われた用語だ。実態としては日本特有の神々であるにしても、その扱いには儒教風の変貌を窺わせる。『神殿』という呼称は、明治5年(1872)からで、それまでは八神殿と呼ばれ、神産日神・高御産日神ら八柱の神だけを祀っていた。天照大神とは血縁関係にない、しかし皇室にとって枢要な神々である。明治5年(1872年)の改制と改称で、天神・国神たちも八神と同じくこの『神殿』に祀られ、現在に至っている」と述べるのでした。
「春季皇霊祭・秋季皇霊祭の誕生」では、皇霊殿が取り上げられます。律令制の時代に淵源する賢所や神殿(八神殿)と違い、歴代天皇の神霊を一箇所で並べて奉安する施設は、明治維新まで存在しませんでした。この施設は儒教の宗廟に相当するとして、著者は「日本の律令制では宮中に宗廟が設けられなかった。その代替施設として、伊勢神宮や石清水八幡宮が雅語表現として『宗廟』と呼ばれていた。前者は天照大神、後者は応神天皇、どちらも天皇の祖先を祭神にしているからである。武家政権の棟梁たる三将軍家(鎌倉・室町・江戸の三つの幕府の長)が、いずれも八幡神を氏神とする源氏だったことも作用していよう。
一方、仏式で天皇の霊を祀る場所として、宮中には黒戸と呼ばれる施設があった。清涼殿の北、滝口の西に設けられた仏間のことで、護摩の煤で黒ずんでいたためこの俗称があるといわれている」と述べています。宗廟と別に、皇帝の祖先たちを祀る施設は、中国にもありました。宋では景霊宮、明では奉先殿と呼ばれるのがそれで、儒教教義にはない偶像・遺物崇拝を行う施設として設けられていました。歴史学者の井上智勝は、琉球国の例に倣って「内廟」と呼んでいます(井上「東アジアの宗廟」、原田正俊編『宗教と儀礼の東アジア――交錯する儒教・仏教・道教』、勉誠出版、2017年)。黒戸はこれに相当すると、井上は述べます。
「天智天皇から神武天皇へ」では、日本は律令継受にあたって宗廟を設けなかったとして、著者は「平安時代の十陵四墓制は、しだいに四親廟の性格を帯びていくが、あくまでも陵であって廟ではなかった。そのため、明治維新での皇霊殿設置が、四親廟による本格的な祭祀規定のはじまりということになる。ここにも、明治時代における儒教の再受容を見ることができるだろう。天皇が行う祖先祭祀は、かくも歴史の浅い『創られた伝統』なのである」と述べるのでした。
第四章「皇統」の「明治3年の諡号追加」では、著者は以下のように述べています。「平成の当今の帝は、第125代であらせられる。譲位の儀が執り行われてめでたく皇太子殿下が皇位にお即きになったあかつきには、第126代ということになる。(本書は平成30年に出版された。)これは記紀の記載にもとづいて、神武天皇を初代としているので、現在の実証史学では否定されている代数だ。つまり、科学的な数値ではなく、宗教的な伝承にすぎない。ローマ教皇が、イエスの弟子のペテロを初代として連綿と続いているとしたり、禅宗の法統が、釈迦如来から達磨大師を経て師資相承(師匠から弟子へと法・道を伝えていくこと)で受け継がれてきたとしたりするのと同断である」
「南北朝正閏問題」では、後醍醐上皇が京に帰還すると、鎌倉幕府が擁立していた光厳天皇(持明院統)を廃位して、ふたたび皇位に即いたことが取り上げられます。これは実質的な重祚です。ただし、斉明天皇や称徳天皇の時と違って、後醍醐は光厳の即位自体を認めず、彼が建てた正慶という元号も無かったことにしたことを紹介し、著者は「元号をいったん自分が使っていた元弘に戻し、その翌年、あらためて建武と改元したのである。そのため、光厳は、現在の皇統譜で天皇代数に算入されていない」と述べています。
ところが、建武の新政は、すぐに武士たちの反感を買って失敗したとして、著者は「後醍醐に反旗を翻して光厳上皇に接近するに及んで、持明院統と大覚寺統との対立は、二つの政権・朝廷が長期間並存するという未曾有の事態をもたらした。この分裂は、形のうえでは持明院統(北朝)の明徳3年、大覚寺統(南朝)の元中9年、西暦1392年に再合一することで収束した。ただ、分裂期間の正統な天皇をどちらとみなすかという問題を残すことになった」と述べます。
「喜田貞吉の憂鬱」では、持明院統の陵墓も宮内庁がきちんと管理しているし、皇霊殿の祭祀対象には、いちおう北朝天皇も含まれていることが紹介されます。わたしたちがこの南北朝正閏論争から学ぶべき教訓は次のようなものではなかろうかとして、著者は「すなわち、歴史の歪曲は、国家権力が主導するわけでは必ずしもなく、一般の人たちの間に浸透する、素朴な史観による場合があるということである。国家・政府が常に悪いことをするという単純な認識は、勧善懲悪主義という点で、朱子学・水戸学の大義名分論と同質・同水準にすぎない。真に恐るべき悪は、私たち自身の中に、しかも善かれと思ってふるまう行為の中にこそ潜んでいるのだ。単純でわかりやすい図式的理解に喜んで飛びついてしまう私たちの心と頭の弱さこそが、本質的に大事なものを喪失してしまう危険性をもたらす、真の敵なのである」と述べるのでした。
第五章「暦」の「七夕の思い出」では、本来、七夕は、東アジア温帯モンスーン地帯の梅雨があけ、戸外で真夏の夜空を仰ぎながら、天の川を挟んで輝く2つの一等星(西洋式の名前でアルタイルとベガ)を愛でる習俗だったとして、著者は「1ヶ月以上にわたって梅雨前線によって覆われ、見ることのできなかった星空を観賞し、また真夏という若い男女の恋の季節にふさわしい話として、あの伝承が作られたのだということを、私は知ったのである」と述べています。
「改暦の歴史」では、キリスト教の教義で最も重要なのは、イエスという人が処刑後復活して、天に昇った(つまり、彼は神の子だった)と信じることであるとして、著者は「それを祝う復活祭は『春分の日の次の満月のあとの最初の日曜日』と決められていた。ところが、太陽運行上の春分と、ユリウス暦の上での春分の日(3月21日)が10日も喰い違えば、復活祭の日付も本来のものとずれてしまい、典礼上の大きな問題となるこれが改暦の大きな理由だった。新しい暦が、当時のローマ教皇(グレゴリウス13世)の名で公布されていることが、カトリック教会の必要で定められたことを示している。そのため、プロテスタント諸国や東方正教会諸国は、この改暦に従わなかった。ロシアがグレゴリオ暦を採用するのは、なんと1918年、ロシア革命で帝政が倒れた時である。ことほどさように、ヨーロッパでも暦は宗教と密接だった。かつてイスラム教を国教とする諸国では、ヒジュラ暦と呼ばれる純粋な太陰暦が使われたが、これもイスラム教の教義によっていた」と述べています。
東アジアには、儒教が君臨していました。儒教では、皇帝が天の意思を受けて、地上を統治していると説くとして、著者は「暦は、皇帝が単に地上を空間的に治めているだけでなく、そこの時間も支配・制御していることを示す道具だった。地上で生活している人間たちに、天体の動きを忠実に反映した正確な暦を提供することが、皇帝の権限であり、また責務でもあった。中国の歴代王朝は、天文観測や暦数計算の専門家を雇い、正確なデータと数値を収集して、常に暦の微修正を行っていた。日本でも中国で作られた暦を移入し、それを使っていた。神武創業の頃のことはさておき、きちんとした文献資料で確認できる最初の暦は、元嘉暦と呼ばれる。これは中国の南北朝時代、南朝の宋の元嘉22年(445年)に定められたもので、日本が導入したのは6世紀なかばである」と述べます。
「明治6年改暦」では、暦とは東アジアにおいて王権の威信を示すものだったとして、著者は「毎年の日付は、天文暦法の専門集団が科学的観測とそれにもとづく精密な計算手法によって定めた。その暦を使うこと、その暦に従うことが、国家としての威厳と一体性を意味していた。それを、明治政府は誰に強要されたわけでもないのに、みずから手放したのである。別段、西洋列強が『グレゴリオ暦を使わなければ不平等条約の改定交渉に応じない』と脅したり、貿易商人たちが西洋の暦を導入することを陳情したりしたのではない。また、政府部内に、非合理的な太陰太陽暦(私は決してそうは思わないが)を廃止して、近代的で単純な太陽暦の導入を推進する理論的・思想的な動きがあったわけでもない。改暦の理由は東西暦法の本質とは関わりない、きわめて表層的なものだった。政府の財政危機対策だったのである」と述べています。
七夕だけではありません。梅花を観賞しながらの桃の節句(3月3日)、促成栽培の菖蒲を湯にひたす端午の節句(5月5日)、残暑厳しいなかの菊の節句(重陽の節句、9月9日)もまた、この改暦がもたらした喜劇的慣習であるとして、著者は「仙台七夕が、月遅れにすることで、季節とのずれを解消していることは本章冒頭で紹介したが、その場合も、月齢との食い違いは如何ともしがたい。七夕とは、上弦の月が夜空に輝くなかで始まり、夜半に月が西に沈んで暗くなることによって、彦星・織姫が相対的に一段と明るさを増す風情を味わうものだったはずである。グレゴリオ暦8月7日固定では、年ごとに月齢が異なってしまい、こうはならない」と述べます。
盂蘭盆会も7月15日ですから、旧暦で行えば毎年かならず満月かそれに近い日でした。というか、そもそも季秋の満月の日を「中元」と呼び、死者を祀ったのです。仏教が中国に伝来すると、この日を祖先祭祀の日とし、仏教用語を用いて盂蘭盆と名付けました。日本では「お盆」として、正月と並んで親族が集う重要な日になったとして、著者は「これほど民俗的に大事な日を、単純に8月15日の敗戦記念日に重ねて死者を想えばすむという問題ではなかろう。各種の節句にして、桃の節句は三日月と、端午の節句はそれよりやや太い月と、重陽の節句は上弦すぎの月と、それぞれ一緒になって、はじめていにしえの風情が味わえるのである。なにせ、わが国は「神武創業」以来、ずっとそうしてきたはずなのだから。伝統文化を正しく継承することを声高に叫ぶのであれば、他の何にも増して、明治の改悪を排除すべく、まずは旧暦の復活から取り組むべきではなかろうか。同志たちの奮起を切に願うしだいである」と述べるのでした。
第六章「元号」も「元年春王正月」では、元号は東アジア独特の紀年法であるとして、著者は「元号は、武帝が『建元』という元号を始めてから2160年になんなんとする、世界無形文化遺産に登録されてしかるべき伝統文化である。もはや東アジアでも、日本一国だけに辛うじて生き残っている絶滅危惧種なのだ」と述べています。また「大化元号」では、「憲法といえば、その語源である『憲法十七条』も、『日本書紀』の推古天皇紀に見える(そして、ここだけが史料的根拠となる)文章である」と述べます。
「憲法十七条」冒頭の「以和為貴(和をもって貴しとなす)」からして、『論語』の「礼之用和為貴」や『礼記』の「礼之以和為貴」とよく似ているように、中国古典の文言を典拠とする語句をちりばめた、典雅な漢文で作成されていることを指摘し、著者は「その制定者だとされてきたのは聖徳太子。『以和為貴』に彼の独創性が表れていると高く評価されたりしているが、これも太子信仰という一種の宗教であって、文献実証主義に反する。以和為貴は、天壌無窮や八紘一宇と同じ性質の宗教教義というべきもので、しかも、これらいずれもが、日本語(やまとことば)ではなく中国語である」と述べます。
もし、天皇が公式に西暦を使うとしたら、どうなるか。著者は「それはイエスをメシア(救世主)として認めて、その降臨を寿ぎ、その生誕(降臨)の年を記念する作法である。わが国の天皇が、キリスト教に屈服することを意味する。もちろん、イスラム教のヒジュラ暦(最後の預言者ムハンマドの聖遷を紀元とする)でも、仏教の仏暦(釈迦生誕年を紀元とする)でも、事の性質は同じだ。天皇が用いる紀年法は元号以外にありえない。天皇が元号を定め、国民がこれを用いて年を数える。この方式は、中国の王権論が生み出した『時の支配者としての君主』を具現化している。念のため言っておけば、神道の教義によるものではない。元号は、東アジアが共有していた伝統であり、わが国でだけつづく貴重な遺風、文化遺産なのだ」と述べます。
「江戸儒者の提案」では、上田秋成の『雨月物語』の「白峯」で、『孟子』は亡国の危険思想の書なので、同書を日本に持ち運ぼうとすると、ことごとく船が沈没したと書かれていることが取り上げられ、「上田秋成の創作は、彼の国学者としての立場から、朱子学に対する厭味・批判として書き込まれたものだろう。日本は中国とは異なり、王朝交代が存在しない国だ。だからこそ、王朝交代という危険思想が述べられている『孟子』を尊重すべきではない。朱子学では『孟子』は、『論語』とならんで重視されていた。ただし、秋成のこの小説のなかで、話者が神社の神職ではなく、釈迦を慕っていた西行法師であるというところが、神仏習合の時代性を物語っている」と述べます。
「白峯」に登場する西行法師は、「願はくは花の下にて春死なん そのきさらぎの望月の頃」という辞世の歌を詠みました。「きさらぎの望月」(2月15日)は、釈迦入滅の日で、仏教寺院では涅槃会が催されます。著者は、「私が儒教側を代表して、上田秋成に厭味の仕返しをするならば、江戸時代の儒一致論者たちは、仏教を神道・儒教に共通する敵とみなし、仏典がインドから中国、そして日本へ伝わったことこそが、東アジアの人々に不幸をもたらした元凶とする。だから日本の神々は、『孟子』ではなく、仏典を積んだ船をこそ難破させるべきであった」と述べるのでした。本書を読んで、日本の天皇制というものに、いかに儒教の影響が強く反映されているかを知ることができました。それは知的にスリリングな冒険の旅であると同時に、「日本人の心の三本柱は、神道・儒教・仏教」であるというわが信条を確認する作業でもありました。