- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.09.23
『ニルヤの島』柴田勝家著(ハヤカワ文庫)を読みました。著者は、1987年東京都生まれ。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻所属。外来の民間信仰の伝播と信仰の変容を研究。本作『ニルヤの島』が第2回ハヤカワSFコンテスト大賞受賞作となり、ハヤカワSFシリーズJコレクションより単行本化されデビュー。一条真也の読書館『ヒト夜の永い夢』で紹介した気鋭のSF作家のデビュー作ですが、ものすごい密度で書かれています。非常に読みにくい小説でしたが、「死後の世界」と「葬儀」について書かれた物語なので、わたしにとっては興味深かったです。
カバー裏表紙には、「人生のすべてを記録し再生できる生体受像(ビオヴィス)の発明により、死後の世界という概念が否定された未来。ミクロネシア経済連合体(ECM)を訪れた文化人類学者イリアス・ノヴァクは、浜辺で死出の船を作る老人と出会う。この南洋に残る『世界最後の宗教』によれば、人は死ぬと『ニルヤの島』へ行くという――生と死の相克の果てにノヴァクが知る、人類の魂を導く実験とは? 新鋭が圧倒的な筆致で叙述する、第2回SFコンテスト大賞受賞作」と書かれています。
タイトルの「ニルヤの島」というのは、奄美・沖縄諸島方面における海の彼方にあるという死後の世界です。そこから年ごとに神々が人間のもとに訪れ、祝福を与えるという信仰もあります。神々が来訪してこの世の人々を祝福する儀礼や伝承は南島各地に見られ、稲や粟の種子も元来ここからもたらされたとされます。奄美では「ニルヤ」「ネリヤ」、八重山では「ニーラ」「ニール」「ニライスク」といい、よく知られている「ニライカナイ」という語は死語となっている地域もあります。
しかし、本作『ニルヤの島』の舞台は奄美・沖縄諸島方面ではなく、ミクロネシアということになっています。ここで4つのチャプターが入り乱れて話が進んでいき、最後にそれらが統合されるという形式ですが、そのチャプター内で一人称で語る主人公がぐるぐると変わり、時間も場面も変わります。それぞれのチャプターも時間軸が合っておらず、読んでいて困惑します。つまり、時間も空間も時間も登場人物もばらばらに配置されて物語が進んでいくわけで、とにかく読みにくい小説です。
4つのパートの内訳ですが、イリアス・ノヴァクという日本国籍の文化人類学について書かれたパート、ヨハンナ・マルムクヴィストというスウェーデン人の模倣子行動学者について書かれたパート、ポンペイ島でアコーマンという架空の盤上遊戯を続ける二人組についてのパート、タヤという橋上島で働く潜水技師と彼に付き従う黒い髪のニイルという娘についてのパートです。本書を最後まで読むと、バラバラだった彼らの行動が収斂されて、その意味がはっきりとしてきます。しかし、そこに行くまでが大変で、ちょっと油断すると、ストーリーがまったくわからなくなり、最初に戻って読み直す羽目になります。
それでも、この小説を読むのを途中で止めることができなかったのは、「死」「死後の世界」「葬儀」といった、わたしのメインテーマを扱っているからでした。まず、この世界では「死後の世界」がありません。「〈GIFT 1〉-贈与―」には、「誰もが知っていた。誰もがどこかでそれを認識していた。死後の世界という概念は人類にとって最も偉大な儀礼だった。死生観は倫理観であり、社会を安定させる為に必要なものだった。しかし、今や社会の平穏は科学という新たな倫理によって担保されている。だから死後の世界の非実在は新時代の地動説になり得なかった。やがて複雑な予定説と終末論の妄言の果てに、信仰と魂の救済という大分滑稽な題目だけを残して、宗教の世界から死後の世界は消えた」(P.26)とあります。
「死後の世界」については、こうも書かれています。
「死後の世界という概念は、そのままあらゆる宗教の信仰に直結する。生きている間の賞罰は死後に決し、悪人は裁かれ苦役を得て、善人は幸福の国へ誘われる。そうした観念は古くは法律として機能し、近代法が発展してからも倫理的なるものに姿を変えて生き延びた。だから今世紀に入ってからも、機能はしていたかもしれない。しかし、明確に死後に別の世界へ行くのだと信じる人間の数は減っていったのだ。また一部に残る、宗教に倫理と精神の充足を求める人々も、やがて登場した精神的に安定した人生(ESL)の概念に宗旨替えした」(P.27)
本書には、ロビン・ザッパという架空の人物が書いた『天国のゆくえ』という本が登場します。ここには「トパ・カタストロフ理論」というものが説かれています。それによれば、今から7万年前にスマトラのトパ火山の破局噴火で、現生人類の大半が死滅するという事象がありました。そのときに人類は成層圏に届く噴煙と、次いで訪れた冬の時代を経験します。そして現実としての地獄を経験することで、脳の奥にその模倣子(ミーム)を飼い始めます。種としての絶滅から身を守る本能として、そのときの記憶を、死後の世界の光景として受け継ぐ道を選びました。よって、人類はまず地獄を獲得し、その派生形として天国を想像したというのです。
わたしは多くの著書で死後の世界について書いてきましたが、その中に『「天国」と「地獄」がよくわかる本』(PHP文庫)という監修書があります。この本には、これまで人類が想像した、あらゆる天国と地獄が紹介されています。いま、天国や地獄を信じる人は少なくなりました。昔の人々は信じていました。心の底から天国に憧れ、震えあがるほど地獄を恐れていました。天国や地獄を信じなくなった結果、人間の心は自由になり、社会は良くなったのでしょうか。いや、反対に人間の心の闇は大きくなり、社会は悪くなったのではないでしょうか。犯罪はさらに残虐になっています。また、親が子を殺し、子が親を殺すような事件も多くなっています。同書が刊行された2009年当時、日本は未曾有の不況による貧困社会を迎えていました。日本人の心はますます荒廃するばかりであると憂えたわたしは、「良いことをすれば天国や極楽に行ける」「悪いことをすれば地獄に堕ちる」という素朴な人生観が再び必要なのかもしれないと訴えました。そして、「まえがき」の最後に、「何はともあれ、天国と地獄を信じよ!そして、限りある生を精一杯に人間らしく生きようではないか!」と書いたのでした。
『ニルヤの島』に描かれる死後の世界が亡くなった世界では、個人の意識は生体受像とかいうものを使って保存されて、死後も生前のログを引き出すことができます。「〈GIFT 2〉-贈与-」には、「死後の世界は、存在しない。今や、生体受像に残ったログと、それを並べ替えた主観時刻とで個人の人生は完全に叙述される。単純な話だ。生物としての死を迎えた個人は、その生前の記録が全て残され、様々な媒体を通して引用される。それだけではない。故人を偲ぼうと思えば、人は自らの生体受像をいじって自身の記憶の中の故人とつでも会える。何度でも記憶を再現し――そこに埋没するような人間が出るのは問題だが――自らの脳の中で死者と再会する。そこにいるのだから、死んだ人間がどこか別の世界に行くことなどない。馬鹿げた思想だ。そうして完全なる叙述は、死後の世界の喪失を招いた」(P.73)と書かれています。
 紫雲閣オンライン
紫雲閣オンライン
この生体受像を使って個人の意識を保存し、死後も生前のログを引き出すというアイデアはSF的なセンス・オブ・ワンダーではありますが、わたしは現実の葬儀において大きなヒントになると思いました。さらに言うと、わたしはオンライン葬儀の進化についてのインスパイアを得ました。コロナ禍の中で、わが社サンレーは、昨年11月1日より、福岡県エリアの紫雲閣にて、「紫雲閣オンライン」のサービスをスタートさせました。紫雲閣オンラインは、これまで主流であった電話での訃報連絡をスマートフォンからのメールやLINEで簡単に共有いただけるサービスです。最初は共有された故人ごとの専用訃報ページから供物のご注文や弔電、さらには香典も送ることができるといったサービスにとどまっていますが、いずれは故人の生前情報のデータベース化することも夢ではありません。
 手元供養の進化形とは?
手元供養の進化形とは?
『ニルヤの島』の生体受像に保存されたデータは機械端末に転送することもできます。それは小さな石板(タブレット)なのですが(巻物タイプもあります)、生前の生体受像の全データが刻まれて亡くなった方の全データが刻まれたタブレットは、そのまま故人の墓碑銘にして戒名となります。望めば、いくらでも生前の言葉をログとして引き出せるのです。本書には、「生体受像は人間の肉体を機械に見立てて、あらゆる感覚を数で表す。音や景色だけじゃない。味覚も触覚も、感情すらも数値化する。数にさえできれば、あとはそれを取り出せば良い。人間の記憶そのものが自由にアクセス可能なデータになるんだ」という登場人物のセリフが登場します。これなど、現在のさまざまな手元供養品の進化形と言えないでしょうか?
 ブログは記憶のログである!
ブログは記憶のログである!
また、本書のアマゾンレビューに興味深い投稿を見つけました。「二次元世界の調教師」という方のレビューに、「生体ログを記録しておくことにより、死後もログを読み込んで『復活』出来るとアイディアを読んでいて、実は私のブログも同じようなものか、と考えた。このブログは強制閉鎖と言う『死』を4回も経験しているが、その度に残されていた『ログ』を元に復活を遂げている。こんな状態だと『死後の世界などない』と言うのは説得力があるな」と書かれています。ブログが個人記憶のログになるというのは、毎日ブログを書いているわたしには納得できます。
 『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
しかしながら、『ニルヤの島』には、バーチャルではないリアルな葬儀の描写も登場します。それも、驚くほどたくさん登場します。まるで「葬儀小説」のようですが、拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館・サンガ文庫)の内容を物語化したような印象も受けました。「〈Transcription 3〉-転写―」には、ミクロネシア経済連合体(ECM)の葬儀について、「ECMでの葬儀は長いのだという。特にパラオは母系社会の名残りなのだろうか、親族集団が多く、それぞれが数多くの島に散っている。そうして各地にいる親族が、次に地域の氏族(リネージ)の有力者が、ぞろぞろと揃うのを待つ。彼らは彼らで供物を持ち寄り、それを調理しては振る舞い、振る舞っては新しく人が来るのを待つ。そういった祭事とも言えない日常の風景を繰り返し、ある程度揃ったところで再び全員で盛大に食べ歌い悼む。そんなことをひたすら繰り返すので、とても一日で終わるようなものじゃない」(P.123)と書かれています。
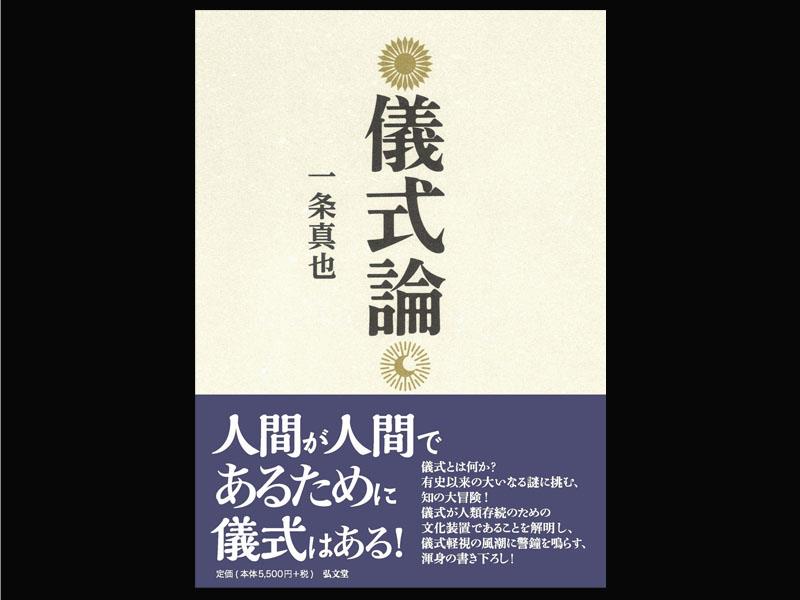 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
この物語に登場するのは葬儀だけではありません。結婚式の場面も出てきます。「〈Gift 5〉―贈与―」に、「振水灯の灯りは人々を静かにさせるというが、やはり結婚という祝福の場にあっては、抗い難いエネルギーのようなものがあるのだろう。この場に集った誰もが、熱に浮かされたように歓声をあげている。それは大教父によって祈りの言葉が捧げられ、新郎と神父がいつまでも変わらない愛を誓い合う段で最高潮となった。どれだけ時代を経ても、こうした古式の結婚の在り方を求める心は働くのだろう。人は儀式によって他者と集団から認められることを希求する。恋人から夫婦へと移り替わる瞬間に」と書かれていますが、まさにわたしが『儀式論』(弘文堂)で訴えた儀式の力を見事に表現しています。
生体受像さえあれば死後も、今は亡き愛する人と何度でも再会することができますし、主観時刻も制御できるので、自分の人生を何度でもやりなおすことができます。結婚式で「わが人生最高の瞬間」と思えば、その瞬間を何度も再生して楽しむこともできるわけです。この技術によって人間の存在は永遠のものとなり、結果として死が希薄化します。当然ながら死生観の変化が起こり、この世界に生きる人々は死後の世界に救いを求めなくなるわけです。それでも、人々は葬儀や結婚式を行い続けているというのが興味深かったです。本書でも紹介されていますが、イギリスの進化生物学者・動物行動学者であるリチャード・ドーキンスは、「模倣子学(ミーム)」というものを提唱しました。いわゆる文化的遺伝子のことですが、儀式とはまさにミームそのものです。いくら社会がIT化し、宗教が無力化しようとも、ミームがある限り人間は儀式をやめない。本書を読んで、そのことを再確認しました。

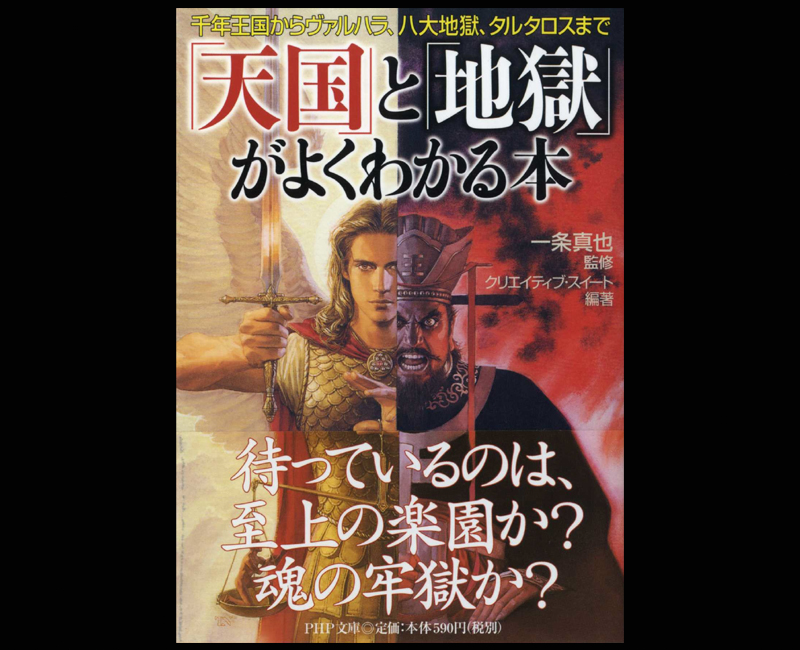 『
『