- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2021.12.26
『人類はなぜ〈神〉を生み出したのか?』レザー・アスラン著、白須英子訳(文藝春秋)を紹介します。一条真也の読書館『イエス・キリストは実在したのか?』で紹介したベストセラーの著者の最新作です。わたしの関心テーマと完全にマッチし、興味深く読みました。著者は1972年、テヘラン生まれ。イラン革命時に家族とともに米国に亡命。サンタ・クララ大学で宗教学を学び、ハーヴァード大学神学大学院で宗教史をテーマに修士号を取得、そのあとアイオワ大学創作学科小説部門で修士号、同大学でトルーマン・カポーティ基金小説部門の特別研究員および中東・イスラーム学の講師を務めたあと、カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校で宗教社会学の博士号を取得。現在、カリフォルニア大学リバーサイド校創作学科終身在職教授。CBSニュース、ナイトラインなどのTV番組の中東アナリスト。
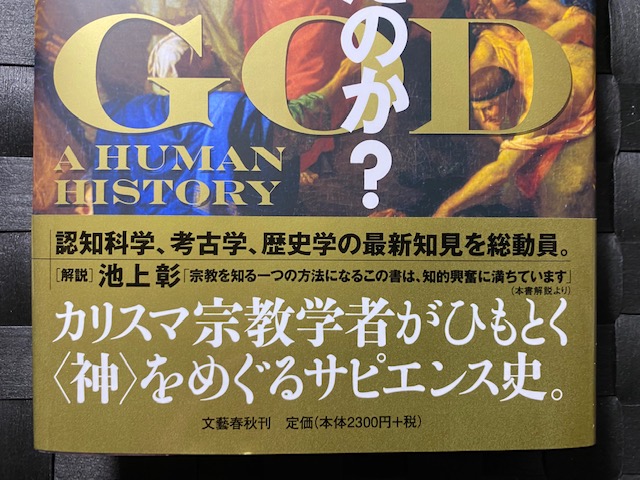 本書の帯
本書の帯
カバーには宗教画が描かれ、本書の帯には、「カリスマ宗教学者がひもとく〈神〉をめぐるサピエンス史」と大書され、「認知科学、考古学、歴史学の最新知見を総動員」「[解説]池上彰『宗教を知る一つの方法になるこの書は、知的興奮に満ちています』(本書解説より)」と書かれています。
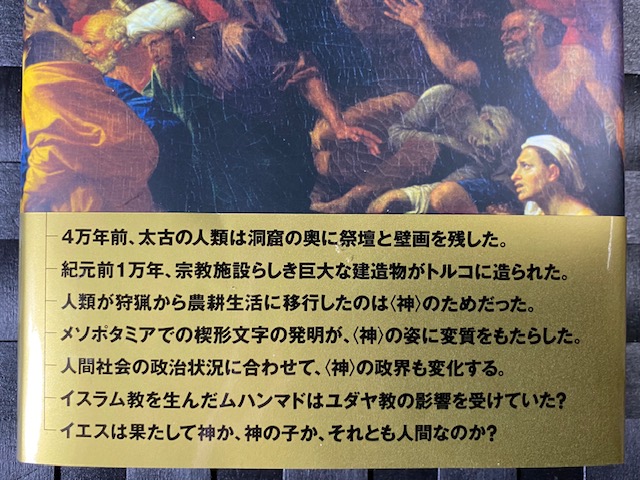 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「4万年前、太古の人類は洞窟の奥に祭壇と壁画を残した。紀元前1万年、宗教施設らしき巨大な建造物がトルコに造られた。人類が狩猟から農耕生活に移行したのは〈神〉のためだった。メソポタミアでの楔形文字の発明が、〈神〉の姿に変質をもたらした。人間社会の政治状況に合わせて、〈神〉の政界も変化する。イスラム教を生んだムハンマドはユダヤ教の影響を受けていた? イエスは果たして神か、神の子か、それとも人間なのか?」と書かれています。
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「人類と〈神〉との出会いから数万年。われわれの知る〈神〉はいかにして生まれたのか? いま最も注目される宗教学者が、考古学、歴史学、認知心理学を総動員し、サピエンスと〈神〉の歴史を鮮やかにひもといてみせる」「はじまりは4万年前、太古のサピエンスが洞窟の奥深くに残した壁画。それはなぜ今あるような”神”になったのか。ネアンデルタールの祭壇、初期サピエンスの壁画、メソポタミアでの文字の発明。エジプトとギリシャの神々を経て、ユダヤ教、イスラム教、キリスト教へ―。膨大な文献資料の分析から、キリスト教以前のユダヤ教やイスラム教までも取り込み、”神”の人類史を解明する」
本書の「目次」は、以下の通りです。
序章 〈神〉の似姿を求めて
第Ⅰ部 伏在する魂(こころ)
第1章 エデンの園のアダムとイヴ
第2章 獣たちの王
第3章 樹幹に見える顔
第Ⅱ部 人格化された〈神〉
第4章 狩猟民から農耕民へ
第5章 高位の神々
第6章 神々の中の最高神
第Ⅲ部 〈神〉とは何か?
第7章 一神教の〈神〉
第8章 三位一体の〈神〉
第9章 すべてに遍在する〈神〉
終章 万物の創造を司る「一なるもの」
「謝辞」
「参考文献」
「原注」
「訳者あとがき」
「解説」池上彰
序章「〈神〉の似姿を求めて」では、著者は「10代の頃、私はアメリカに移住したイラン人両親のあまり熱心ではないイスラームから、学校友だちが熱心に信じるキリスト教に鞍替えした。そしてたちまち、子ども時代にあこがれていた偉大な人物という〈神〉のイメージにぴったりの、『神の似姿』と言われるイエス・キリストを崇拝するようになった。最初、その経験は、それまでずっと痒くてたまらなかったところを搔けたような感じだった。何年も自分と〈神〉との間の隔たりを埋める手段を模索していた私は、ようやくその隔たりはないと主張する宗教に出遭ったのだ。〈神〉とはどんな存在かを知るには、もっとも完璧な人間を想像しさえすればよかった」と述べています。
続けて、著者は「なるほど、それなら合点がいった。〈神〉を一人の人間にしてしまえば、人間と〈神〉の間の垣根はなくなってしまう。キリスト教の〈神〉の概念がとてつもなく成功したのは、ドイツの有名な哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハが言っているように、『ただ全人を自己のなかにになっている存在者だけがまた全人を満足させることができるのである』からだ」と述べます。
また、「人間の脳は〈神〉を人格化せずにはいられない」として、著者は「実際、人間の心の世界の進化の歴史をたどってみると、神的存在が自分たちと同じ感情や個性を持つと考え、それゆえに自分たちと同様の習性や願望を持つことを当然とし、同じような強さや弱さを持った、姿形まで私たちそっくりの〈神〉をつくることによって、神的存在を理解しようとする、長い、長い、試行錯誤しながらも絶え間なく進化し、驚くほど一貫した努力の連続だったことがわかる。つまり、私たちの大半は、しばしば、意識しようとしまいと、信仰者であろうとなかろうと関係なく、〈神〉とは、自分たち自身を神的存在にしたような、超人的能力を持った人間と考えているというわけだ」と述べるのでした。
「なぜ人類は宗教を生み出したのか?」として、著者は「私は〈神〉が存在するか、しないかを証明することには興味がない。なぜなら、そのどちらの証拠も存在しないからだ。信仰には選択の自由がある。いや違う、と言う人にはあなたを転向させようとする下心がある。実在し、認識できるもの、形ある世界を超えたところにある存在を信じるか、信じないかを選べと。私と同じように信じるほうを選択するなら、自分に対してもう1つ別の質問をしなければならない。それを体験してみたいか? そういう存在と心の交わりを持ちたいか? それを知るにはどうしたらいいか? もしそういう存在を知りたいなら、きわめて神聖な体験を表現する独特の言語を知るのが早道かも知れない」と述べます。
そこで登場するのが宗教であるとして、著者は神話や儀式、神殿や聖堂、『するべきこと』や『してはいけないこと』をめぐり、人々は数千年も、しばしば意見が一致せず、自分の信仰する〈神〉を味方につけて陣営を構え、相争ってきた。宗教とは、言葉では言い尽くせない信仰体験を、信者同士で伝え合うためのシンボルや比喩だらけの”言語”にほかならない。宗教の歴史をひもといてみると、世界中のほぼすべての宗教で、〈神〉を象徴するシンボルや比喩として、普遍的かつ断然多いのが私たち、すなわち人間である」と述べています。
人格化された神々への信仰は、狩猟採集民だった人間を、数万年のちに農耕民に変え、神々を超人間的存在 と考えた人たちによって人類最初の神殿が建てられた――これが宗教の始まりであるとして、著者は「メソポタミア人、エジプト人、ギリシア人、ローマ人、インド人、ペルシア人、ヘブライ人、アラブ人らはみな、人間を表す言葉と人間のイメージを持った有神論的体系を考え出した。ジャイナ教や仏教のような無神論的思想においても同様に、『業の法則』に縛られた、人間で言えば超人のような存在として精霊や神霊が登場する」と述べます。
そして、「人間の『無意識の欲望』の歴史を繙く」として、著者は「本書は、人間がどのように〈神〉を人格化してきたかという歴史を綴るだけでなく、私たち人間の神的存在に対する妄念の介入を抑え、もっと汎神論的な〈神〉観〔〈神〉と森羅万象、または〈神〉と自然とは一体であるとみなす哲学的・宗教的概念〕の展開に読者を誘うつもりである。1つの〈神〉を信じるか、多数の神々を信じるか、あるいはまったく神を信じないかのいずれであっても、〈神〉の似姿を自分なりにイメージして来たのは私たち人間であって、その逆ではない。まさにその真理にこそ、いっそう成熟した、ずっと平和的で、この上なく本来の人間らしい心の世界のありようを探る手がかりがある」と述べるのでした。
第Ⅰ部「伏在する魂」の第1章「エデンの園のアダムとイヴ」では、「人類最古の宗教が生まれた日」として、著者は「来世はある、とアダムとイヴは確信している。そうでなければ、なぜわざわざ埋葬するのか? 死者を埋葬する実質的な理由はない。遺体はそのまま野ざらしにして、朽ちるに任せるか、鳥たちにきれいに食いつくしてもらうほうがずっと簡単である。それなのに、彼らは友人や家族の遺体を、死者にある程度敬意を表するように扱ったり、自然の猛威から守ったり、埋葬したりしたがる。たとえば、彼らは遺体をわざわざ大の字に広げたり、あるいは胎児のような形に曲げたり、日の出が見られるような姿勢にして東向きに葬ったりする。頭皮を剝いで二次埋葬の時にそれを取り付けたり、完全に人に見せることを目的にして、頭部を丸ごと切り離し、義眼を入れて対面相手を見つめるかのように設えたりすることもある。頭部をたたき割って脳みそを取り出し、それをがつがつ食べたりすることさえある」と述べています。
続けて、著者は「彼らは遺体を、花をちりばめた葬送用ベッドに横たえる前に、血の色(生命の象徴の色)に染め、ネックレスや貝殻、動物の骨、あるいは死者が大切にしていた道具など、来世で必要とするかもしれない品々で飾る。遺体の周りに明かりを灯し、供物をそなえる。小山の上に墓石を置き、何年もたってから再訪するときの目印にしたりもする。アダムとイヴもこのようなことをすると想定される。なぜなら、死者は、本当は死んでいるのではなく、別の境域にいて、生者は夢や想起を通して接触することができると信じているからである。肉体は朽ち果てるかもしれないが、肉体とは明らかに別の、霊魂としか言いようのないものは消えずに残っているのではないかと」と述べます。
さらに続けて、著者は「彼らがいつそう考えるようになったのかはわからない。だが、一番大事なことは、彼らが自分自身を認識するようになったことだ。アダムとイヴは自分たちの中に霊魂が伏在することを直観的に知っていたように見える。それは生まれ持った、本能的な、広く、深く行きわたった確信であるから、人間の経験の顕著な特徴と考えられていたに違いない。実際、アダムとイヴのこの確信は、自分たちの祖先であるネアンデルタール人やホモ・エレクトスと共通している。彼らもまた、さまざまな形の儀式的な埋葬をおこなっていたように思われる。彼らもまた、霊魂を肉体とは別のものと想像していたのかもしれない」と述べます。
そして、アダムとイヴはまだ、自分たちの霊魂――彼らを彼らたらしめているもの――が、形や質において、自分たちの周囲や目の前にある霊魂、そして樹木や山々に宿る精霊とそう違うものではないと一気に推断するには至っていないとして、著者は「霊魂がどんなものであろうと、本質的に何からできていようと、すべての被造物と共生している。霊魂は全体の一部である。人間であろうとなかろうと、あらゆる事物に”霊魂”は宿る――これこそ心の世界の本質の特性である――と信じることをアニミズムと呼ぶ。それはおそらく、人類最古の宗教と呼べそうな発想であった可能性が高い」と述べるのでした。
「4万年のホモ・サピエンスが描いた洞窟壁画」として、彼らは、ごく単純な意味で、私たちと同様、何から何まで完全に人間であると指摘し、著者は「何から何まで完全に人間であるということは、批判力もあれば、経験を生かすこともできるわけだ。彼らは実在の本質について複雑な理論を肯定的に仮定して、類推による推論をおこなうことができ、そうした理論に基づき、首尾一貫した信仰を形成することができる。しかもその信仰を保持し、何世代にもわたって伝えてゆくことができる」と述べています。
実際、ホモ・サピエンスの移動先のほとんどどこでも、彼らのこうした信仰の痕跡を発見することができる。それらの中には、野外の記念碑のような形をとったものもあったが、大半は長い歳月の間に消え去った。墳丘墓に埋葬されて何万年もたってから、儀式的行事が執りおこなわれていた痕跡をはからずも露呈するケースもある。だが、まるで人類の移動の経路を示す足跡のように、ヨーロッパやアジアに点在する洞窟の中に鮮やかに描かれた壁画ほど、太古の私たちの祖先の人間としてのありようをありありと身近に感じさせるものはない」と述べています。
第2章「獣たちの王」では、「ネアンデルタール人も‟祭壇”を造っていた」として、著者は「ホモ・サピエンスを含む世界最古の慣例に従った埋葬場所は10万年前ごろからあったとされていますが、50万年以上前のものかも知れない中国のホモ・エレクトスの墓地を含む、明らかに儀式的行為の徴を伴う墓所も発掘されています。それでも、宗教心の発露はどのくらい前からあったかを、こうした考古学的発見にのみ依拠することの問題点は、信仰心は化石化されないという点である。人間の観念というものは、地下に埋葬されて、のちに出土することはあり得ない。洞窟や埋葬場所に見られる儀式的な行為の証拠を突き付けられても、そのような行動が、突然に、そうせざるを得ない信仰と同時に生まれたと推定するのは馬鹿げているであろう。初期の人類は、宇宙の自然な姿とその中での自分の位置について、洞窟の壁にそうした信仰を刻み込み始めるはるか前から何らかの信仰を持っていた」と述べます。
また、「ダーウィンの進化論で宗教の起源を説明できるか?」として、わたしたちは、宗教的信仰とか教会とかを切に求めるのでもなく、特定の神々や神学に傾倒するのでもなく、〈神〉の超越性、すなわち明確に把握できる世界を超えた所にあるものに対して、生身の人間として努力せずにはいられない宗教的人間なのであることを指摘し、著者は「宗教的信仰を持つという性癖が、私たち人間生来のものであるならば、それは人間の進化の産物であるに違いないと学者たちは推論した。それは何らかの適応に有利であるに違いない。そうでなければ、宗教が存在する理由はないであろう」と述べます。
この問題に初めて決然と取り組んだ者の中に、19世紀英国の人類学者エドワード・バーネット・タイラーがいるとして、著者は「タイラーによれば、宗教感情の目覚めとそれから生じる行為の起源は、人類の属性である戸惑い、肉体を離れた魂への不可解な信仰――形は違うが、どんな社会のどのような文化にも、時代を超えて発生する信仰の中にあるという。そのような観念はどのように生じたのか、タイラーは疑問に思った。私たちの大昔の祖先に、自分たちは死ぬべき運命にある肉体の中に閉じ込められた永遠の魂であると確信させるものがあったとしたら、それは何だったのだろうか?」と述べます。
タイラーの権威ある研究書、Primitive Cultureの中で、タイラーは「個人の人格的存在の伝達手段、活気ある、分離可能な、生きている存在」としての魂という観念は、私たちが眠っている間にしか起こらないという。「私自身の見解では、夢と幻想以外に、肉体の永遠のイメージである魂というような概念が人の心に入り込むことができるものはない」と仮説を述べています。
タイラーは、夢の中で死んだ身内に駆け寄ることについて、「彼らは実際には死んでいないのではないか、彼らはここにいるのと少しも変わらぬ、触知できる存在として別の世界にいるのだとアダムは単純に推測しないだろうか? 死んだ者の魂は肉体が亡びたずっと後になっても精霊として存在し得ると、アダムは当時推断していなかったであろうか? そして、そう認識していたからこそ、彼は父や姉妹の墓に詣でて、自分の狩猟を助け、長雨を降りやませ、子供たちの病気を癒してくれと精霊に訴えたのではないだろうか? 宗教の始まりとは、このようなものだったに違いないとタイラーは推断している」と述べます。
「超自然力崇拝がやがて一神教へ」として、著者は「タイラーと同僚のドイツ人の比較宗教学者マックス・ミューラーは、人類の最初の宗教的体験は、自然との遭遇によって生じたと信じていた。ミューラーは、アダムが睡眠中に夢見たものではなく、目覚めているときに見たものが宗教的イマジネーションを搔き立てたのだという」と述べ、さらに「英国の文化人類学者ロバート・マレットは、こうした驚異の感情、「神秘的なものへの畏怖の念によって左右される心の姿勢」を超自然力崇拝と名付けた。マレットは、古代の人類は見えない力を、すなわち見える世界の裏側にある”遍在する魂”の一種を信じていたと論じた。彼はこの力を、古いメラネシア語で”力”を意味する”マナ”と名付けた」と述べます。つまり、人類は、未開な多神教時代からキリスト教の啓蒙主義運動へと必然的に前進して、一神教に移行していったと見るのが、19世紀末から20世紀初めのマレット、タイラー、ミューラーらのような、学者たちに共通した結論でした。
「信仰を持つことにどんな生存上の利点があるのか?」として、著者は「それが夢の中であろうと、自然との遭遇においてであろうと、他界した祖先への思慕であろうと、これらの説明すべてに共通しているのは、宗教は、人類の進化の過程で、答えることのできない疑問に答え、初期の人間にとって脅威で、予想不可能な世界に対処する助けとなるものとして勃興したという想定である。それは今日もなお、宗教的経験として多くの人々に語り継がれている」と述べています。
また、学者たちの中には、儀式的な慣行によって原初的な”信者”はある種の感情、例えば自分の不安を制御したり、”信仰のない者”に比べて狩猟の獲物が多くなったりするような感情が搔き立てられるという説を唱える人たちもいるとして、「仮に超自然的なものを信じることが、肉体的にも心理的にも、進化による適性を増強する方向に導く(それは大いに疑わしいが)としても、そのような信仰を持たないことが進化的適性を減じることになると推定する理由はない。野牛に向う見ずに突進するのは、死を恐れないからではなく、進化的な生存のチャンスを生かすか、つぶすかの可能性を高めるに過ぎない」と述べます。
「宗教は団結と同じくらい紛争も生む」として、とりわけ社会学者エミール・デュルケームは、宗教が存在の神秘性への答えを求める原始時代の人類を助けるために生まれたという説を否定したことを紹介し、著者は「デュルケームは実際に、宗教とは超自然的なものと関係があるという説を頭から否定した。デュルケームにとって、宗教は「きわめて社会的なもの」であるがゆえに、人類の初期の発達段階において社会的な構築物として長いこと持続してきたのは、宗教が奇想天外な神話や突飛な空論ではなく、想像の産物でもなければ神秘的な信仰でもなく、現実的な目的や経験、つまり現実にしっかり根差したものであったからに違いないと論じている」と述べます。
人類の進化の過程における、社会的な結合力としてもっと強い、はるかに原初的なツールは血縁です。わたしたちの旧石器時代の祖先は、小規模な共同社会――1つのシェルターに同居できる程度の拡大家族で暮らしていたことを指摘し、著者は「彼らの連帯意識は、シンボルや儀式によってではなく、第一に誕生と血筋を通して生成されたものである。人類の進化の過程で宗教が生まれたのは、”信仰を持つ”共同社会のほうが、”信仰を持たない”共同社会より適応に有利だったからだと信じるためには、宗教の中に何かしらユニークな結合力のようなものの存在が必要だが、宗教にはそのようなものはない」と述べます。
共同社会が持つ特性が人類の歴史を通して、生き延びるために、宗教を許容してきた可能性は確かにあるとしながらも、。そのような共同社会の特質が、宗教に頼りがちな人間が生き延びるのに役立ったかどうかは疑わしいとして、著者は「夢は現実ではない。マナも現実ではない。霊魂も現実ではない。デュルケームのいう現実的なものとは、血族、親族を1つにまとめ、敵対的な環境に適応して生き抜くための社会がとる具体的な活動であるという。それゆえ、宗教感情の目覚めの起源は、1つのコミュニティに集団意識の形成を助ける祝祭や儀式、つまり社会生活に根差したものだと主張する」と述べるのでした。
第3章「樹幹に見える顔」では、「宗教感情の起源を脳内から調べてみる」として、認知宗教学では、「宗教は何よりもまず神経学的現象である」という単純な論理を前提にしていることを紹介し、著者は「宗教感情の目覚めというものは、換言すれば、人間の脳内の複雑な電気化学的反応の働きによるものである。もちろん、この事実自体が説得力のある観察結果によるものではなく、それが宗教感情の目覚めを減じたり、適法性を否定したりするわけではない。覚醒というものはみな――あらゆる覚醒が例外なく、脳内の複雑な電気的反応によって生じる。宗教感情の目覚めも例外であるはずはない」と述べています。
続けて、著者は「ロマンティックな魅力の化学的プロセスを知ることで、そうした感情を非現実的なものにしたり、愛の対象の価値を減じたりするわけではないのと同様、宗教感情の目覚めの神経的メカニズムを知ることは、宗教的信仰の正当性を蝕むものではない」と述べます。この分野での著名な思想家の1人であるマイケル・J・マレーは、「私たちが自然選択によって手に入れた知的ツール(脳)から生まれた信仰を持っているという事実だけで、その信仰を正当化するのはまったく見当違いである」と述べています。
「樹木やおもちゃを人間として知覚してしまう『心の理論』」として、「心の理論」とは、私たちが自分自身に対するのと同じように、他人を見たり理解したりする能力をもたらす脳の執行指令機能のことであることを指摘し、著者は「つまり、個々別々の人間も基本的には同じように感じ、似たような考え方をし、本質的には同じ存在と考える。「心の理論」は、私たちが自分自身について考えるときに使うのと同じ言葉で他人のことも考えざるを得なくさせるだけではない。自分自身を基本的なモデルとして、ほかのすべての人もみな同じようなものだという考えを助長させる」と述べています。
続けて、著者は「そのことについて少し考えてみよう。自分が感知できる唯一の意識は自分自身の意識だとすれば、森羅万象を自分なりに理解するには、自分自身をモデルとして選ぶほかない。ほかの人間が心の中で何を考えているかを察するには、自分自身の心の中の想いを基盤にすることになる。だが、『心の理論』で驚くべきなのは、相手が人間でなくても、人間的な特性を持っていさえすれば、私たちはその存在を人間と同じように知覚してしまうことである」と述べます。
そして、著者は「たとえば、頭と顔のようなものを持つ2本足の存在と出くわしたら、私は『こいつは自分に似ている』と思う。外見が自分に似ているなら、『心の理論』によって、それは自分に似た存在のはずだと考える。すると、その人間的な存在に対して、私は人間ならではの考え方や感情を当てはめる。子どもたちがある種のおもちゃを、まるで生きていて、人格も意志もあるかのように扱うのはそのためである」と述べるのでした。
第Ⅱ部「人格化された〈神〉」の第4章「狩猟民から農耕民へ」の冒頭を、著者は「『エデンの園』は、シリア北部の国境から数十キロメートルのところにあるトルコ南東部の先史時代の都市ウルファ(現在のシャンルウルファ)の近くのどこかとされている。あるいは少なくともこの市の住民はそう信じている」と書きだしています。「エデンの園」の神話に埋め込まれているのは、人類が骨の折れる仕事や争いとは無縁で、夜も昼も大地を重い足取りで歩き回る必要のない大昔の時代の集合記憶であるとして、著者は「換言すれば、私たちの太古の祖先アダムとイヴが、農業の勃興以前の、聖書にはあまり出てこない、狩猟採集民だった時代の話である。そしてこれが、古代都市ウルファがその住民の集合記憶の中で『エデンの園』の所在地とみなされるようになった由縁である」と述べます。
ウルファは、聖書にあるエデン同様、チグリス川、ユーフラテス川を含む4つの川の間にあり、これまた聖書でいう”東”とは、古代アッシリアの西を指しているという事実を信仰者は指摘するであろうとして、著者は「だが、世界中の多くの人々がそう信じている大きな理由は、エデンの園の廃墟の跡地にできたというこの都市が、ウルファと関係があるというよりもむしろ、「ギョベクリ・テペ(太鼓腹の丘)」と呼ばれるそこから15キロほど北東の高い山の尾根の頂と関係があるからである。荒涼とした台地を見渡せる山頂の天辺に人間の造った土塁の、その下に埋もれていたのは、この地を発掘した考古学者のチーフ、クラウス・シュミットが冗談半分に”エデンの神殿”と呼んだ、人類最古の宗教がらみの神殿と広く認められている建造物の遺跡である」と述べます。
また、「我々は神々をも人格化させたがる」として、著者は「神々をもっとよく知るために、私たちは、唯一、十分に知ることが出来る私たち自身を基盤にした申し分のない心構えを構築する。神々には食べ物が必要だ。なぜなら、私たちに食べ物が必要だからだ。そこで私たちは神々に犠牲を捧げる。神々には私たちと同じように住まいが必要だ。そこで神々のために神殿を建てる。神々にも名前が必要だから、名前を付ける。私たちに個性があるように、神々にも私たちと同じような個性を与える」と述べます。
続けて、著者は「神々には私たちの現実社会を根拠とした神話的な歴史や、神々が私たちの世界を経験できるような、一定の形を持った祭儀も必要だ。神々の願いごと(それは私たちの願いごとにほかならない)を成就するための奉仕者や従者、神々の居心地のよさを保つためのしきたりや規制も必要だし、神々の怒りを招かないように祈りや嘆願もしなければならない。つまり、神々が必要としているのは、一言でいえば宗教である。そこで私たちはそれを発明することになる」と述べます。
「人類は250万年近く、狩猟採集民として生きてきた」として、わたしたちの、神的存在に人間の特性を付与せずにはいられない衝動がもたらした最重要な結果の1つは、ギョベクリ・テペの建設の直接の結果から生まれたように思われる「農業の誕生」であると指摘し、著者は「なぜなら、それは、人間の姿をした個々の神々の概念化であり、そのようなプロセスに伴う神話や祭儀の制度化であり、それが私たちを旧石器時代から脱出させ、放浪をやめて定住化を余儀なくさせ、それが農業を発明することによって生じる利点へと地球を変えていこうという起動力を私たちに与えることになるからである。つまり、天界の神々を人間に変貌させていくことによって、私たちは人間を地上の神々へと変貌させていくことになる」と述べています。
続けて、著者は「私たちの儀式やしきたり、神話や伝説、地下聖域、宇宙についての概念などは、狩猟者と獲物の間に存在した不思議な連帯意識によって醸成されてきた。そうした連帯意識が、私たちが殺した動物から道具へと広がるにつれて、私たちは動物を殺すことに慣れた。骨で作った銛、木製の槍、魚を釣る鈎針、網などは神聖な力を持つようになった。私たちの生存のためのこうした武器への依存は、やがてそれらを単なる物体から霊的世界の幻影へと変えていった」と述べるのでした。
第5章「高位の神々」では、「家の床下から発見された人間の頭蓋骨」として、新石器時代の人々は、頭(というよりは脳)が魂の在処であると考えていたことを指摘し、著者は「なぜなら、彼らが人間の頭蓋骨を集めたり、保存したりしていたケースが実にたくさん発見されているからだ。だが、家庭の床下などに、その意図や目的からして個人の家庭内神殿を思わせるこのように大きな隠し場所があったということは、新石器時代の初期にマニズム――一般には”祖霊崇拝”の信仰出現の兆しがあったのではないかと思わせる」と述べています。
すでに見てきたように、祖霊崇拝の念は旧石器時代にまでその痕跡を遡ることができますが、それは死者の魂が霊としてこの世に存在し続けると信じるアニミズム的信仰によるものであるとして、著者は「だが、農耕の誕生により、祖霊崇拝がいっそう複雑で顕著なものになった。死者が葬られる大地は、その頃には私たちの生存を支える糧食が育つ土壌であった。それゆえ、最近の死者を、心をこめて葬ったのは、死者が生者に代わって自然の威力との仲介をつとめ、穀物の保持、健康の維持、家畜の成育などを助けてくれるよう期待したからであろうことはうなずける。時代が移るにつれて、このような死亡した祖先の一部が自然の威力の仲介者としてよりふさわしい神々に進化し、やがていわゆる仲介人は除去され、自然の威力そのものが神格化されるようになった」と述べます。
「純粋な『唯一神』を求めたギリシアの思想家たち」として、ギョベクリ・テペの柱、ヴォルプ洞窟の壁に彫り込まれた呪術師の姿、宗教感情の目覚めの起源にまでさかのぼる数万年前から形成されてきた人間の心の世界についての前提を疑問視したのはクセノファネスだけではなかったことを紹介し、著者は「ミレトスのタレス、エフェソスのヘラクレイトス、プラトン、ピタゴラスなど、ここに名を挙げた数人以外にも、多くのギリシア人思想家たちもまた、神々の基本的な性質について再考し始めた」と述べます。
続けて、これらのギリシア人は神々に単なる親しみやすさ以上のものを求めていたとして、著者は「彼らはゼウスとその家族のうんざりするような放縦ぶりではなく、外観にしろ、本性にしろ、まったく人間とはちがう神――すべての被造物を司る統一された行動の基準――、不変の、変わることができない、姿形のない、何にもまして特異な神という思想によって組み立てられた宗教を切に求めた。クセノファネスの言葉を借りれば、『姿形においても、思想においても、命に限りある人間とはまったく違う唯一神』である」と述べます。
第6章「他の神々を否定する一神教の強い排他性」として、人間の宗教感情の目覚めが、魂、祖霊崇拝、諸霊の創造、神々と万神殿の創生、寺院や神殿の建設、神話や儀式の制定という過程を経て、数十万年かけてたどってきた中で、私たちが今日、唯一絶対神観――唯一の特異な〈神〉への信仰――として認識している宗教の歴史は、そのうちのわずか3000年にすぎないというのは驚くべきことであるとして、著者は「それは一神教体制というものが宗教史の中で散発的にすら台頭しなかったということではない。アクエンアテンやザラスシュトラの運動がそれを証明している。台頭はするが、たいていの場合、時には激しく拒否されたり、否定されたりしたのである。長い宗教史の中で、大体において一神教を寄せ付けなかった理由は何だったのだろうか?」と述べています。
続けて、著者は「それは、排他主義者的な考え方と少々関連づけてみる必要がある。一神教とは、単に一人の神を単独崇拝することを意味しているわけではない、と理解する必要がある。一人の神を崇拝するのは拝一神観〔他の神の存在を前提とする〕と呼ばれ、宗教史の中ではかなりありふれた現象である。一方で一神教とは、一人の神を単独崇拝し、他の神々を否定することを意味している。それは他の神々は偽物であると思えと要求する。もし他のすべての神々が偽物なら、それらの神々への信仰に基づいた真理もみな偽物であることになる。実際、一神教は付随する真理の可能性までも拒絶する」と述べるのでした。
第Ⅲ部「〈神〉とは何か?」の終章「万物の創造を司る『一なるもの』」では、「原初的なアニミズムや仏教にも通じる『汎神論』」として、神的存在の概念を、現代語では「〈神〉はすべて」あるいは「すべては〈神〉」を意味する「汎神論」と呼んでいることが指摘されます。著者は、「この単純極まりない表現形式でいう汎神論とは、〈神〉と森羅万象はまったく同一のものである――したがって〈神〉の必然的存在以外には何一つ存在しないと信じることである」と述べています。
西欧社会に汎神論を広めたとされる合理主義哲学者ベネディクトゥス・スピノザ(1632~1677年)は、無限の特質を表す森羅万象の中に唯一の”実体”があるとすれば、その実体は〈神〉と呼ばれようが、「自然」と呼ばれようが、それは唯一、不可分の現実として存在しているはずであると言いました。著者は、「あるいは〈神〉をまったく無視し、科学知識をもとに、自然界を単純にエネルギーと物質という2つの不可分なものから成る一体と見てみよう。すると、今日、存在しているものはみな、これまでずっと存在していたのであり、森羅万象自体が存在する限り、これからもずっと存在し続けるであろうことは不変の事実だとわかる」と述べます。
さらに、「魂への信仰は〈神〉への信仰よりもはるかに古い」として、「ギリシア人ならプシュケー(心)、ヘブライ人ならネフェシュ(魂)、中国人なら楚辞(楚の精神)、インド人ならブラフマン(世界の根本原理)。それを『仏性』あるいは森羅万象と共存しているものと考えてもいい。死後に〈神〉と再統合する、あるいは魂が別人の身体に入ると想像してもよい。あなたならではの本性の中枢、あるいは被造物すべての根底にある特定の個人とは関係のない力としてそれを感じ取ってもいい。あなたがそれをどう定義しようと、肉体とは別個の魂への信仰は人間の普遍的特質である。それは私たち人間が持つ最初の信仰で、〈神〉への信仰よりもはるかに古くから見られる。その信仰が〈神〉への信仰を生み出したのである」と述べます。
人間に普遍的な魂を、考え違いや間違った推論から生まれたもの、心に浮かぶ錯覚、進化の過程での偶然のいずれかだと見ることもできることを指摘し、著者は「実際、人は何でも、ビッグ・バンであろうと、時空間分布であろうと、質量とエネルギーのバランスであろうと、すべて単なる原子の偶然のぶつかり合いにすぎないと信じることもできる。天地創造はおそらく、もっとも基本的な物質とエネルギーの属性を、理由も意味も目的もなく明確に反映するにすぎない物理的プロセスを通して生まれてきたのであろう。森羅万象とその中に含まれるあらゆるものの存在の、これほどもっともらしい説明はない。実際には、あなたと私、そのほかのすべてのヒト、おそらくすべての物に潜む魂をつなぎ合わせ、生命を吹き込む生き生きとした霊は、証明するのは不可能だが、久遠の昔から今に至るまで確かに存在している」と述べるのでした。
「訳者あとがき」では、翻訳家の白須英子氏が「本書は、太古の昔から人間の宗教感情が覚醒して行くプロセスを、認知科学、考古学、宗教史などの比較的近年の資料をもとに、カリフォルニア大学リバーサイド校創作学科の終身在職教授ならではの、序章と3つの楽章による交響詩のようなみごとな構成で描かれている。終章では、イラン・イスラーム革命直後、7歳で両親とともにアメリカに亡命し、イスラーム世界とキリスト教世界の狭間で、戸惑い、迷いつつ歩んできた自分自身の”心の旅路”の終着点で、〈神〉を知ること,は、自分を知ることだと告白する」と述べています。
続けて、白須氏は「人間には、肉体は死んでも、魂は別の境域で生き続けると信じようとする本能的性向があり、この人間の普遍的特質は、〈神〉への信仰よりもはるかに古く、太古の昔からあるという。では、『あなたにとって魂とは何か?』。それを何と呼ぶかは、時代や地域、歴史や文化的背景によって異なるであろう。その存在を信じるか、信じないかはあなた自身の選択である、と強烈にして、深く、鋭いいくつもの問いを投げかける」と述べるのでした。
解説「神が人間を創造したか、人間が神を創造したか」では、ジャーナリストの池上彰氏が、「人間の宗教意識は、何万年も前から存在したと著者は指摘します。たとえば約4万1000年前にスペイン北部の洞窟に描かれた壁画は、居住空間ではない場所にありました。当時の人々が、宗教行事として使っていたとみられる空間に描かれていたのです」と述べ、さらに「私たちの祖先であるホモ・サピエンスが出現する以前の17万6000年以上前に、フランスの洞窟にネアンデルタール人が祭壇のようなものを築いていたことがわかりました。では、どうして人類は宗教心を生み出したのか。著者は、過去の多くの学者の説を紹介しながら、「神の誕生」を紐解いていきます。そこで登場する神々は、残忍で粗暴で、平気で人間たちを大量虐殺する存在です。『慈悲深き神』が登場するのは、ずっと後になってからなのです」と述べています。
アメリカでは、いま「福音派」と呼ばれるキリスト教徒が増加していますが、彼らは「キリスト教原理主義」とも呼ばれることを紹介し、池上氏は「聖書に書かれたことは一字一句真実だと考える人たちです。彼らにとって、ダーウィンの『進化論』など唾棄すべきもの。人間は進化の過程で生まれたのではなく、神様が創造したと聖書に書いてあるではないかというわけです。彼らは、聖地エルサレムに「イスラエル」という国が存在してこそ、『この世の終わり』に救世主イエスが再臨して人々を導いてくれると信じています。それゆえに彼らは、『イスラエルの首都はエルサレムだ』と主張するドナルド・トランプ大統領を支持するのです。日本から見て驚くことが多い言動を繰り広げるトランプ大統領の支持率がなぜ下がらないのか。現代アメリカを宗教の観点から見るとわかることが多いのです」と述べるのでした。本書は非常に骨太の宗教論で、「人間とは何か」という問題の本質を衝く内容だったと思います。
