- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2109 グリーフケア 『ケアの倫理とエンパワメント』 小川公代著(講談社)
2022.02.22
『ケアの倫理とエンパワメント』小川公代著(講談社)を読みました。著者は1972年、和歌山県生まれ。上智大学外国語学部教授。ケンブリッジ大学政治社会学部卒業。グラスゴー大学博士課程修了(Ph.D.)。専門は、ロマン主義文学、および医学史。著書に『文学とアダプテーション――ヨーロッパの文化的変容』(共編著、春風社)、『ジェイン・オースティン研究の今』(共著、彩流社)、訳書に『エアスイミング』(シャーロット・ジョーンズ著、幻戯書房)、『肥満男子の身体表象』(共訳、サンダー・L・ギルマン著、法政大学出版局)など。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「自己と他者の関係性としての〈ケア〉とは何か。」として、「強さと弱さ、理性と共感、自立する自己と依存する自己……、二項対立ではなく、そのあいだに見出しうるもの。ヴァージニア・ウルフ、ジョン・キーツ、トーマス・マン、オスカー・ワイルド、三島由紀夫、多和田葉子、温又柔、平野啓一郎などの作品をふまえ、〈ケアすること〉の意味を新たな文脈で探る画期的な論考」と書かれています。
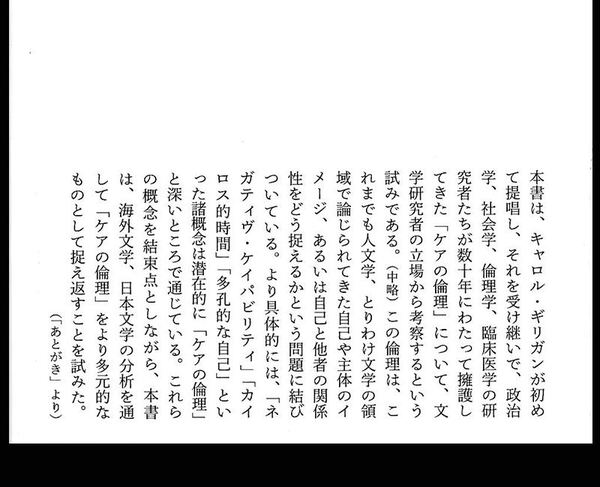 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「本書は、キャロル・ギリガンが初めて提唱し、それを受け継いで、政治学、社会学、倫理学、臨床医学の研究者たちが数十年にわたって擁護してきた「ケアの倫理」について、文学研究者の立場から考察するという試みである。(中略)この倫理は、これまでも人文学、とりわけ文学の領域で論じられてきた自己や主体のイメージ、あるいは自己と他者の関係性をどう捉えるかという問題に結びついている。より具体的には、『ネガティブ・ケイパビリティ』『カイロス的時間』『多孔的自己』といった潜在的にケアを孕む諸概念と深いところで通じている。本書は、これらの概念を結束点としながら、海外文学、日本文学の分析を通して『ケアの倫理』をより多元的なものとして捉え返そうという試みである。(本書「あとがき」より)」とあります。
本書の「目次」は、以下の通りです。
序章 文学における〈ケア〉
1.〈ケア〉の価値が看過されるわけ
2.ネガティヴ・ケイパビリティと共感力
3.善の「過剰」を留保する
1章 ヴァージニア・ウルフと
〈男らしさ〉
1.病気になるということ
2.負の「男らしさ」を手放す
3.カイロス的時間の能動性
4.『オーランドー』における両性具有性
むすび
2章 越境するケアと
〈クィア〉な愛
1.ケアの倫理と民主主義
2.同性婚が認められない社会とオスカー・ワイルド
3.ワイルドの『獄中記』と童話におけるケア
4.三島由紀夫の”同苦”
5.多和田葉子の言葉のケア
むすび
3章 弱さの倫理と〈他社性〉
1.ケアの倫理が問い直す正義論
2.ロマン主義時代におけるケアの倫理
3.コウルリッジの鳥メタファー
4.エリオットとコンラッドの《近代》
5.平野啓一郎『日蝕』から『本心』まで
むすび
「あとがき」
「註」
序章「文学における〈ケア〉」の1.「〈ケア〉の価値が看過されるわけ」の冒頭、著者はジョアン・トロント著『ケアするのは誰か?――新しい民主主義の形へ』(岡野八代訳、白澤社)から、「ケアはわたしたちの身近な活動であり、しかも、ケアを受けてない者はいないと断言できるほど人間存在にとって重要な活動であるにもかかわらず、なぜその活動とそれを担う者たちが、長い歴史のなかで軽視、あるいは無視され、価値を貶められてきたのだろうか」との岡野八代氏の「訳者まえがき」を引用します。
欧米でも日本でも、個が「自律/自立する」ことを重んじる価値観が多数派である一方、「依存する」あるいは「関係性をむすぶ」というケアの価値観はまだまだ少数派のものであるとして、著者は「資本主義社会において新自由主義的な文化が支配的な文脈では、〈ケア〉の価値が貶められてきたからだ。1960年代のフェミニズム運動によって、女性の経済的自立が推奨されるようになったことも、その傾向に拍車をかけた」と述べています。そんな中で、「ケアの倫理」の重要性を訴えた人物として、キャロル・ギリガン(Carol Giligan,1937―)が紹介されます。彼女は1982年に『もうひとつの声』(In A Different Voice)を発表し、長らく看過されてきた〈ケア〉の復権を主張しました。ギリガンの研究は、当時の状況を明るみにし、社会科学の進展を推し進めたのです。
2「ネガティヴ・ケイパビリティと共感力」では、著者は、が『V・ウルフの病跡』でヴァージニア・ウルフは「日常生活の表面的な現象の背後に、何かもっと本当のもの、真の現実というべきものがあるのではないか」という内面に関する問いに心を突き動かされたと指摘したことを紹介し、「自分は何者だろうか」といった問いに向き合い、ひたすら「人生とは何か」「人間とは」「愛とは」「時間とは」について考え続けたウルフのカイロス的な時間感覚はじつは〈ケア〉の営為とも関係すると述べます。
また、神谷によれば、ウルフが「人生のもろもろの事実――結婚したり、子どもを生んだり、埋葬したりすることは最も重要でない事柄である」と考えていたことを紹介し、著者は「ウルフが「人生のもろもろの事実」を重要ではない、あるいは〈家庭の天使〉を殺したいと言ったりしたのは、決して〈ケア〉の価値を否定していたからではない。ウルフの文学作品はむしろケア精神で貫かれている。子育て、看護、介護といった物理的な『ケア労働』の背後にある内面世界を包括しようとするのが、ウルフにとっての〈ケア〉なのである」と述べます。
ウルフの『自分ひとりの部屋』には、文学の傑作はかならず両性具有的な性質を備えていると書かれています。著者は、「男性であっても、女性的な視点を備えている文豪たちは『多孔的な自己』(porous self)のイメージをもっているからだ。ウルフは、シェイクスピアを両性具有的だとし、さらに、ジョン・キーツ、ローレンス・スターン、ウィリアム・クーパー、チャールズ・ラム、サミュエル・テイラー・コウルリッジ、パーシー・B・シェリーの名前を挙げている。『とにかくその種の混合がなければ知性ばかりが支配的になり、心の他の能力は硬化して不毛になるのですから』、ウルフはそう書いている」と述べています。
ロマン主義時代に生きたジョン・キーツ(John Keats,1795―1821)の「ネガティヴ・ケイパビリティ」(negative capability)という概念は、共感力をもつ自己像を表しているといえるとして、著者は「『ケイパビリティ=capability』とは、何かを達成する、あるいは何かを探究して結論に至ることのできる力を意味する。しかし、キーツのこの概念は、知性や論理的思考によって問題を解決してしまう、解決したと思うことではない。そういう状態に心を導くことをあえて留保することをさす。『ネガティヴ・ケイパビリティ』とは、相手の気持ちや感情に寄り添いながらも、分かった気にならない『宙づり』の状態、つまり不確かさや疑いのなかにいられる能力である」と述べます。
3「善の『過剰』を留保する」では、ロマン派詩人のサミュエル・テイラー・コウルリッジ(Samuel Taylor Coleridge,1772―1834)のお気に入りの比喩を用いて、ケアとは、「人の精神は羅針盤であり、外界のすべての本質的なものの法則や働きは、その針のぶれとして示される」、そういう心の状態をじっくり見極めることであると述べます。著者によれば、「ケアの倫理」は与えられたシチュエーションにおいて人間がいかなる葛藤を感じ、そこからどのように行動するかについて考えていく方法論であり、コウルリッジの言葉にも〈中動態〉に通じる精神が宿っていると述べるのでした。
1章「ヴァージニア・ウルフと〈男らしさ〉」の1「病気になるということ」では、ウルフの代表作『灯台へ』に登場するラムジー夫人が体現した「家庭の天使」は、ウルフの母親ジュリア・スティーブンをイメージして書かれたことを紹介し、著者は「2020年に始まったコロナウイルスのパンデミックの世界には、ラムジー夫人(あるいは、ジュリア・スティーブン)のように毎日誰かのケアに追われて疲弊する人々が数多くいるのではないだろうか。コロナ禍により想定外の需要に直面している医療介護従事者たちにも、かつてないほどの重圧がかかっている。そして、その影響は男女間で大きな差がある」
全世界の医療現場でも、医療従事者のほぼ70パーセントは女性で、その彼女らは感染に晒されるリスクが高いです。また、長期介護施設の労働者も女性が大半を占めており、OECD諸国平均で90パーセントを超えています。著者は、「外出制限措置や学校、保育施設の閉鎖により、家事などの無給労働の需要も高まり、専業主婦(夫)はもとより、共働きの女性やシングルマザー(ファーザー)への皺寄せは、もはや看過できない社会問題となっている」と述べます。
ケア従事者の職業によって、期待される「ケア」の程度は異なるだろうという著者は、「たとえば、看護師は医療の実践の他に職務の内容として感情労働が大きな位置を占める。ファミリー・レストランやコンビニの店員と違い、看護師に求められるのは、表面的な笑顔や『思いやる仕草』ではなく、『本物の笑顔』や『心からの思いやり』であることが多い。患者に対して怒りや屈辱を感じたときには、深呼吸して気持ちを鎮め、患者の状況を考えて無理もないと思わなければならない。看護師にとっての職業倫理と考えられているものの多くが、たとえば『患者に対して「共感的」でなければなら』ないなど、感情に関する規則となっている」と述べています。
女性が病人を「看護」するものだという社会のステレオタイプは、日本の看護師の9割以上が女性という事実からもうかがえます。著者は、「ウルフの母親ジュリアは、この『看護』という『使命』をまっとうした。その母親の死後、ウルフは彼女を思慕しながらも、人をケアしなければならない、喜ばせなければならないと囁く『家庭の天使』の亡霊に取り憑かれ、苦しめられた。家庭の天使は『私を悩ませ、私の時間を無駄にし、私をたいへん苦しめたので私はとうとう彼女を殺してしまいました』と書いている。そして、文芸の仕事に就いていた父のように、女性でありながらも文学の世界を探究した」と述べます。
2「負の『男らしさ』を手放す」では、ウルフは、自分と同様に両性具有的な精神を作品注ぎ込んだ男性作家として、シェイクスピア、サミュエル・テイラー・コウルリッジらの名前を挙げたことを紹介し、著者は「これらの文豪たちのなかに、ロマン派詩人ジョン・キーツがいる。価値判断を留保する、あるいは2つの価値基準の間で宙づりになることを表す『ネガティヴ・ケイパビリティ』という概念で知られるキーツは、ウルフにとって『両性具有的』であった」と指摘します。
ネガティブ・ケイパビリティは、「短気に事実や理由を手に入れようとはせず、不確かさや、神秘的なこと、疑惑ある状態の中に人が留まることができるときに表れる能力」を意味しますが、著者は「彼らとは対照的に、『ミルトンとベン・ジョンソン』『ワーズワースとトルストイ』は、『少しばかり男性面が過剰』と指摘している。反対に、プルーストにいたっては完全に両性具有でかつ『たぶん女性部分が少し過剰かもしれ』ないという評価を下している」と述べています。ヴァージニア・ウルフは文芸評論家でもあったのですね。
3「カイロス的時間の能動性」では、アマゾンの倉庫、訪問介護、コールセンター、ウーバーのタクシーといった仕事に自ら就いてその体験を赤裸々に報告したジェームズ・ブラッドワースの『アマゾンの倉庫で絶望し、ウーバーの車で発狂した』というルポルタージュ本に言及し、現代の低賃金労働の現状を批判した上で、著者は「ブラッドワースの現代社会に対する批判の眼差しは、身体的、精神的経験が資本主義システムによって無力化されることを暴いている」と述べています。
また、ブラッドワースの批判は、一条真也の読書館『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』で紹介した本でデヴィッド・グレーバーが指摘していることとも響き合うといいます。グレーバーによれば、すべての労働はケアリング労働だとみなすこともできます。というのも、たとえば橋をつくるのであっても、つまるところ、そこには川を横断したい人びとへの配慮があるからです。「マネージャーのケアリング労働は本来同僚への配慮から成り立つのではないだろうか」という著者は、「ひとたび計算可能で確実なものとなってしまったなら、そのときにはその経験はただちに権威を失ってしまう」というアガンベンが『幼児期と歴史』に書いた言葉を連想させるような事例であると指摘しています。
2章「越境するケアと〈クィア〉な愛」の1「ケアの倫理と民主主義」の冒頭を、著者は「コロナ禍が長期化するなか、『ケアするのは誰か?』という問題提起がなされている。レーガン元米大統領やサッチャー元英首相が『小さい政府』を掲げてから、日本もそれに追随し、新自由主義の路線をひた走ってきた。レーガンは『政府は解決を与えない』とまで言ったが、臨時国会の所信表明演説で菅義偉首相が述べた『自助・共助・公助』は、まさにレーガンの言葉をそのまま継承しているようである」と書きだしています。
菅首相の「自助・共助・公助」演説にはさまざまな反応はありましたが、SNS上でひときわ目を引いたのが、「せやろがいおじさん」のYouTube投稿にある核心を突く言葉でした(2020年11月22日)。菅首相に対して、「あんたらの仕事は公助することやろ、自助を呼びかけんでええねん!」と言っていたのです。さらには、現政権が「溺れてる人に向かって、ライフセーバーが、はい! まずは自分でやってみる!」と言っているようなものだと見事な喩えを用いていました。
「ケア」という言葉が用いられるとき、その意味は、病人へのケアや看護、子どもの育児、あるいは高齢者に対する介護などにおける女性の営為だけに限定されるわけではないとして、著者は「勿論、私的、公的領域においてケアを提供する人に女性が圧倒的に多いのも事実であり、ケアという実践活動の社会的属性が、ジェンダーにより不均等配分されていることは明らかである。しかし、”自立した自己”を前提としたリベラリズム的な「正義の倫理」(the ethics of justice)が看過してきた側面を補って生まれたのが、キャロル・ギリガンの『ケアの倫理』(the ethics of care)である。『もうひとつの声』で、ギリガンが想定するのはそもそも男性に対して反論する女性という(自己対自己の)構図ではない。そこで想定されているのは『自己』が互いに”依存し合う関係性”であり、それぞれの『自己』がいわばやせ我慢しながら”自助”して生きていく主体でもない。つまり、苦しんでいる、あるいは弱っている人は、1人で抱え込まずに家族、近隣の人たち、地方自治体や関連団体に助けを求めてもよいという倫理としても解釈されうる」と述べています。
『ケアするのは誰か?』を書いた米国のフェミニスト政治学者トロントは、「ケア」という概念が、家庭内のケア、あるいは、女性の性役割だけに限定されず、より広い公的領域のなかで捉え直されることを提案しています。著者は、『ケアするのは誰か?』から「もっとも一般的な意味において、ケアは人類的な活動 a species activity であり、わたしたちがこの世界で、できるかぎり善く生きるために、この世界を維持し、継続させ、そして修復するためになす、すべての活動を含んでいる。世界とは、わたしたちの身体、わたしたち自身、そして環境のことであり、生命を維持するための複雑な網の目へと、わたしたちが編みこもうとする、あらゆるものを含んでいる」(岡野八代訳)という言葉を引用しています。
ブログ『ケア宣言』で紹介した2020年9月に原著が刊行されたケア・コレクティヴの著書(The Care Manifesto:The Politics of Interdependence)では、「ケア」という概念が”多様性”を含んで理解されなければならないと指摘されています。『ケア宣言』は「関心を向けること」や「配慮すること」だけでは十分でないと強調するのです。「ケア」(care)の古英語の”caru”には、「関心、不安、悲しみ、嘆き、そして困惑」(concern,anxiety,sorrow,grief,trouble)という意味があり、さらに、最後の”trouble”は「苦悩」とも捉えることができます。著者は、「つまり、『ケア』の議論には、不安を抱える社会的弱者の視点からの認識も包括されるべきであるということだ」と述べています。
鳥瞰的な視点から語られる文学作品と「ケア」を繋げてみたいとして、著者は「ワイルドは、寓話的な童話で異形の姿の『美』を模りながら、逆説的に人類共通の苦悩を浮き彫りにしている。三島もまた、『金閣寺』のなかでヘテロノーマティヴな分類から外れた主人公が『美』の象徴に自分の魂を重ねて感じる疎外感や苦悩を描いた。『美しい星』(1962年)では、SF世界のなかの宇宙的視点から現代人が浸りきっている家父長的な制度を異化している。これらの作品に加えて、特定の地域や文化に縛られない「地球人」の視点から描かれる多和田葉子の『献灯使』(2014年)や『星に仄めかされて』(2020年)もまた、ケアという観点から読み直すことができるだろう」と述べています。
2「同性婚が認められない社会とオスカー・ワイルド」では、性的マイノリティがヴァンパイアとして表象されることはある意味で常套なのかもしれないが、「感染」というテーマはもっと慎重に扱われるべきだろうとして、著者は「ブラム・ストーカー(Bram Stoker,1847―1912)の小説『吸血鬼ドラキュラ』(Dracula,1897)でも、『感染』はマジョリティの人間の領域がマイノリティによって侵食される恐怖と結びついているが、原作では、マイノリティの声を含む複数の声も掬い取っている。量産されてきたヴァンパイア映画のなかには、マイノリティとして表象された吸血鬼を怪物化して抑圧するものもあるが、1960年代以降には女吸血鬼のセクシュアリティが主体的に描かれ、女性や性的マイノリティの解放を示唆するものも数多くある。ストーカー自身、アイルランド独立運動が盛んだった時代のアングロ・アイリッシュ作家であり、最近では彼の同性愛的傾向も指摘されている。『吸血鬼ドラキュラ』は、じつは帝国拡張、ホモフォビア、外国人への嫌悪などを批判的に捉えた”多様性”のイギリスを描いているのである」と述べます。
19世紀の抑圧された同性愛は、作品の至るところに「偽装されたかたちで忍び込む」こととなりましたが、代表的なのは童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセン(Hans Christian Andersen,1805―1875)の『人魚姫』(Den lille Havfrue,1837)だろうと指摘し、著書は「アンデルセンの親友エドヴァード・コリンに対する抑えきれない愛と失恋がインスピレーションとなり、『人魚姫』の物語が生まれた。人魚――クィアな存在――が人間を愛しても報われることはないというエンディングは、作者自身の体験をなぞっているかのようだ。その『名づけえぬ愛』を実践したのはアンデルセン自身であり、彼が愛した『人間の王子』エドヴァードは、女性と結婚することを選び、彼のもとを去っていった。現実世界の苦しみを寓意的に表現した物語として読むと、不思議と心に迫ってくるものがある。アンデルセンに影響を受けていたワイルドも、やはり近代社会の『異性愛』『夫婦』『家族』では包括しきれない愛を描こうとした」と述べます。
3「ワイルドの『獄中記』と童話におけるケア」では、『ケアするのは誰か』の中から、「真に平等な社会では、人びとに良くケアされ、ケア関係を作り上げる平等な機会が提供されます。真に正義に適った社会は、現在や過去の不正義を隠すために、市場を利用したりしません。経済的な生活の目的とは、ケアを支援することであり、その逆ではありません。生産とは、目的それ自体ではありません」というトロントの言葉を引用します。著者によれば、社会の「ケア」の認識が時代によって変容するということを、もっともよく理解していたのはオスカー・ワイルドであり、それが如実に表現されているのは『獄中記』であるといいます。
5「多和田葉子の言葉のケア」では、著者は、「『なんのために?』という問いが失効するところで、ケアはなされる。こういうひとだから、あるいはこういう目的や必要があって、といった条件つきで世話をしてもらうのではなくて、条件なしに、あなたがいるからという、ただそれだけの理由で享ける世話、それがケアなのではないだろうか」という鷲田清一氏の「ケア」と「倫理」の両方の本質を捉えた言葉を紹介しています。
「倫理」というのはいわゆる「道徳」とは異なり、具体的な状況に対してどう振る舞うかに関わります。伊藤亜紗氏がこの2つを区別するためのきわめつけの例を挙げているとして、「伊藤氏が息子を連れて渡米したときのこと、街を散歩しているときに向こうから『40代くらいの太った女性がふらふらと揺れながら』近づいてくる。『乱れた身なりと手を差し伸べている様子から、物乞いをしようとしていること』はすぐに分かったという。危険を察知したため、息子の手を引っ張ってその場から離れたのだが、その直後に『息子がパニックを起こしたように大泣きをし始めた』」と紹介しています。
伊藤氏の息子は「物乞いをしているかわいそうな人をなぜ助けなかったのか」「ぼくがもし病気になったり障害を持ったりしたら、みんなに冷たくされるのか」と言いながらパニックになったというのです。著者は、「たしかに『困っている人がいたら助けましょう』と学校の道徳の授業では教わっている。自分の母親がそれと反対のことを目の前でしたら、パニックになるのも分からないでもない」と述べます。伊藤氏はこの状況を、「道徳と倫理のあいだで引き裂かれていた」と言語化します。彼女は、人をいかなる状況でも助けるというモラルの規範が「絶対的ではない」ということも「従うのが最善ではないかもしれないということ」も倫理的に考えていたのです。
3「弱さの倫理と〈他者性〉」の5「平野啓一郎『日蝕』から『本心』まで」では、平野の芥川賞受賞作である『日蝕』は、キリスト教と異端の思想の融合を志す神学僧ニコラの物語ですが、ケアの倫理論を踏まえて考えると、ここに、きわめて重要なテーマが浮かび上がると指摘し、著者は「彼は、キリスト教という《制度》とそこから逸脱する両性具有者を信仰する《異端》とのあいだで揺れ動きながらも、決して『貴重な他者』を『破滅させ』てまで制度に靡くようなことはしないケアの人である。彼は制度や地位ある人間に媚びへつらい出世を果たすギョオムとは異なり、最後まで自分の倫理を貫く。男女の性が混在する生物を目撃しても、『魔女』として彼/彼女を迫害することもなく、その驚嘆せしめる事実に対して価値判断を下さない」と述べています。『日蝕』には「両性具有者は私であったのかも知れない」とも書かれていますが、これは「2つの価値観のあいだで揺れる彼自身を指す言葉でもあるのだろう。つまり、彼は《ネガティヴ・ケイパビリティ》の人でもある」と著者は述べるのでした。
「あとがき」の冒頭を、著者は「本書は、キャロル・ギリガンが初めて提唱し、それを受け継いで、政治学、社会学、倫理学、臨床医学の研究者たちが数十年にわたって擁護してきた『ケアの倫理』について、文学研究者の立場から考察するという試みである」と書きだしています。また、一般的にケアが結びついてきた「ケア労働」(=物理的なケア)というイメージを越えて、内面世界を包括する「ケア」(配慮、愛情、思いやり)というより広範な意味として流通してきた歴史を再認識できたと述べます。
そして、著者は「オスカー・ワイルドも『社会主義下における人間の魂』で、物理的な他者のケアはもちろん大切だが、軽視されがちな精神的なケアは最重要事であると言っている。ワイルドをはじめとして、ヴァージニア・ウルフ、S・T・コウルリッジ、三島由紀夫、多和田葉子、平野啓一郎らが内面世界を包括する「ケア」の営為を生き生きと作品に描き出してきたことを、拙論が少しでも示せたとしたら幸いである」と述べるのでした。本書には、わたしが読んできた本もたくさん登場しますが、「ケア」と「文学」に橋を架けるきわめて興味深い内容でした。