- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2127 歴史・文明・文化 『ファンタジーランド』 カート・アンダーセン著、山田美明・山田文訳(東洋経済新報社)
2022.04.25
『ファンタジーランド 狂気と幻想のアメリカ500年史』上下巻、カート・アンダーセン著、山田美明・山田文訳(東洋経済新報社)を読みました。「新世界を信じた夢想家たちとその末裔が創り上げた、狂信者の国家の物語」を描いた全米ベストセラーです。ブログ『世界史とつなげて学ぶ 中国全史』で紹介した中国史の本が面白かったので、次は中国と並ぶもう1つの超大国であるアメリカの歴史の本が読みたくなり、アマゾンで本書に出合いました。「狂気」と「幻想」という視点から俯瞰したアメリカ史は信じられないほどスリリングで面白かったです!
著者は、ベストセラーとなった小説『Heyday(絶頂期)』『世紀の終わり――ニューヨーク狂想曲』(早川書房、2000年)『True Believers(狂信者)』の著者。『バニティ・フェア』誌や『ニューヨーク・タイムズ』紙に寄稿し、『タイム』誌や『ニューヨーカー』誌で文化コラムや評論を担当しているほか、ラジオおよびポッドキャスト番組『スタジオ360』(ピーボディ賞受賞)の共同制作者兼ホストを務め、テレビや映画、舞台の脚本も担当。『スパイ』誌の共同創設者、『ニューヨーク・マガジン』誌の編集長でもあります。ハーバード・カレッジをきわめて優秀な成績で卒業しており、在学中は『ハーバード・ランプーン』誌の編集に携わっていました。現在はブルックリン在住。
 上巻の帯
上巻の帯
本書の上巻の帯には、「ニューイングランド幻想、ジェファーソン:独立宣言、西部開拓:フロンティア精神、フォード:大量生産モデル、ディズニー:夢の王国建設、ケネディ:宇宙計画」「狂信者の国家の物語。全米で話題のベストセラー!」と書かれています。
 上巻の帯の裏
上巻の帯の裏
上巻の帯の裏には、「絶賛の声、続々!」として、「卓越した洞察に満ちた歴史書。既知の出来事が斬新な文脈で描かれる」ウォルター・アイザックソン(『スティーブ・ジョブズ』著者)、「絶対的に面白い。読めば興奮で脳が踊り出す」スティーブン・ダブナー(『ヤバい経済学』共著者)という賛辞が紹介されています。
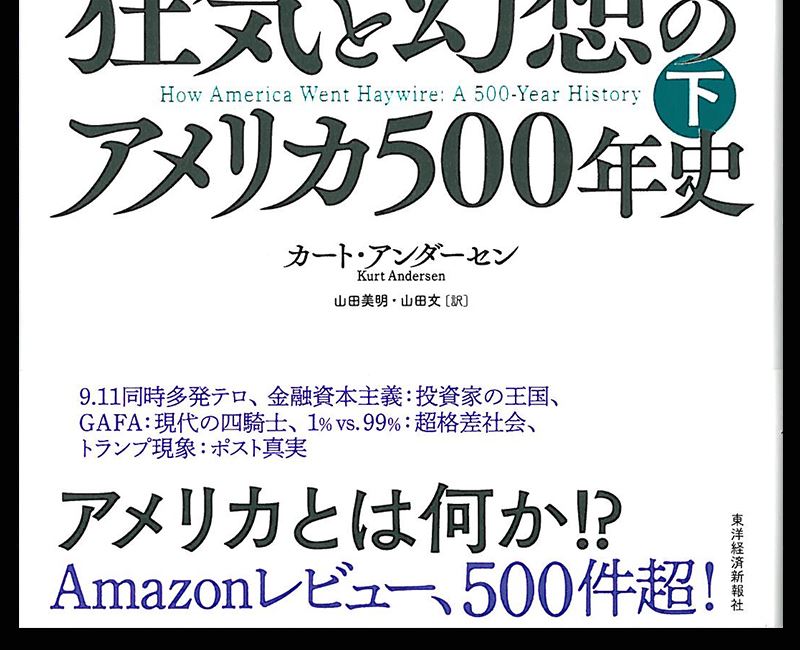 下巻の帯
下巻の帯
また、下巻の帯には「9.11同時多発テロ、金融資本主義:投資家の王国、GGAFA:現代の四騎士、1%vs.99%:超格差社会、トランプ現象:ポスト真実」「迷走するアメリカはどこへ向かうのか!?」「Amazonレビュー、500件超!」と書かれています。
 下巻の帯の裏
下巻の帯の裏
下巻の帯の裏には、「絶賛の声、続々」として、「トランプ政権誕生に関する圧倒的に優れた記述。2017年に読んだ最も重要な本」ローレンス・オドネル(政治ジャーナリスト)、「すばらしいライターによるベストセラー。深呼吸して、この本に飛び込め」トム・ブロコウ(ジャーナリスト、キャスター)という賛辞が紹介されています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
【上巻】
第1章 「ファンタジーランド」と化しつつアメリカ
第1部 アメリカという魔術
【1517~1789年】
第2章 私は信じる、ゆえに私は正しい
(プロテスタント)
第3章 最初の移住者(一攫千金を求める人々)
第4章 ニューイングランド幻想
(ピルグリム・ファーザーズの想い)
第5章 神を信じる自由
(個人主義、反知性主義の芽生え)
第6章 架空の仲間と敵(悪魔信仰と魔女裁判)
第7章 宗教のアメリカ化 (偉大なキリスト教思想家たち)
第8章 知識人たちの思想(18世紀の啓蒙主義)
第2部 狂信者たちの合衆国
【19世紀】
第9章 第一次大狂乱期
(合理的なヨーロッパ、狂信的なアメリカ)
第10章 実にアメリカ的な二次創作小説
(預言者ジョセフ・スミス)
第11章 いかさま療法好きな国民
(擬似科学と宗教の相互作用)
第12章 幻想に満ちた仕事
(ゴールドラッシュという転換点)
第13章 破滅する怪物を求めて(陰謀説への偏愛)
第14章 南北戦争(心理と心理の戦い)
第15章 1000万もの大草原の小さな家
(開拓時代への郷愁)
第16章 幻想の産業化
(メディア、広告、娯楽産業の胎動)
第3部 理性への傾斜の時代
【1900~1960年】
第17章 進歩と反動の時代(1920年代のアメリカ)
第18章 理性vs.信仰(装いを新たにした古い宗教)
第19章 娯楽ビジネスこそアメリカの本分
(映画、ラジオ、出版)
第20章 郊外のユートピア(陽光降り注ぐ理想の地)
第21章 アメリカの黄金時代 (まともに見えた1950年代)
第4部 狂気と幻想のビッグバン
【1960~1970年】
第22章 ヒッピー(60~70年代の若者文化)
第23章 知識人(科学は信仰の一形態)
第24章 キリスト教(異端派、急進派の巻き返し)
第25章 現実か、フィクションか(20世紀の陰謀論)
第26章 幻想・産業複合体(子ども化する大人たち)
第5部 拡大する
「ファンタジーランド」
【1980年代から20世紀末まで】
第27章 空想を現実に、現実を空想に
(巨大テーマパーク化する社会)
第28章 いつまでも若く(「みんな子ども」症候群)
第29章 レーガン政権とデジタル時代
(ウェブの世界に広がる
「ファンタジーランド」)
第30章 20世紀末以降のアメリカの宗教
(縮小する伝統的宗教)
第31章 狂信化するキリスト教
(科学を疑問視するアメリカ人)
第32章 ”アメリカ”vs. “神のいない文明世界”
(なぜアメリカは例外的なのか?)
第33章 キリスト教とは異なる魔術、宗教とは異なる
精神世界(ニューエイジ運動の広がり)
第34章 代替医療(再び魔術化する医学)
第35章 主流派エリートの敗北
(軟弱者、冷笑家、信奉者)
第36章 何でもありの世界
(最大の関心は人生を楽しく過ごすこと)
【下巻】
第6部 「ファンタジーランド」は
どこへ向かうのか?
【1980年代から現在、
そして未来へ】
第37章 甦るフロイト(20世紀の悪魔崇拝)
第38章 現実は陰謀である
(X-ファイル化するアメリカ)
第39章 猛烈な怒り、人々の新しい声
(エリート不信と陰謀論)
第40章 共和党が道を踏み外したとき
(なぜ狂信者を統制できなくなったのか)
第41章 科学を否定するリベラル派
(ワクチン恐怖症の弊害)
第42章 ガン・クレイジー(銃に熱狂する人たち)
第43章 デジタル・ゲーム、VR、SNS
(拡張する幻想・産業複合体)
第44章 大人になるのは悪いこと?
(ディズニー化するアメリカ)
第45章 経済の夢の時代
(繰り返される「根拠なき熱狂」)
第46章 トランプ政権を生んだ国
(ファンタジーランドと国民は歩みをともにする?)
「謝辞」
「索引」
第1章「『ファンタジーランド』と化しつつアメリカ」では、アメリカの歴史は、知的自由という啓蒙主義的概念を初めて具体化する実験の歴史でもあったと指摘し、著者は「誰にでも、好きなことを信じる自由がある。だが、その考え方が手に負えなくなるほど力を持ってしまった。わが国が奉じる超個人主義は最初から、壮大な夢、あるいは壮大な幻想と結びついていた。アメリカ人はみな、自分たちにふさわしいユートピアを建設するべく神に選ばれた人間であり、それぞれが想像力と意志とで自由に自分を作り変えられるという幻想である。つまり、啓蒙主義の刺激的な部分が、合理的で経験主義的な部分を打ち負かしてしまったのだ」と述べています。
続けて、こうしてアメリカ人は、数世紀の間に少しずつ、そしてこの50年の間に急速に、あらゆるタイプの魔術的思考、何でもありの相対主義、非現実的な信念に身を委ねていったとして、著者は「私たちを慰め、わくわくさせ、恐怖させる大小さまざまな幻想である。しかも国民の大半が、今や標準となったこの奇妙な思考がどれほど広範囲に及んでいるかに気づいていない。その状況をたとえて言うなら、火にかけられた鍋の中のカエルだ。手遅れになるまで、その運命に気づかない。アメリカ人は、ほかの先進国に暮らす10億~20億の人々よりもはるかに強く、超自然現象や奇跡、この世における悪魔の存在を信じている。最近天国に行ったとか、天国から戻ってきたという話や、数千年前に生命が一瞬にして創造されたという数千年前の物語を心から信じている」と述べます。
21世紀が始まるころには、わが国の金融産業が、危険な負債がもはや危険ではないという夢想に陥り、何千万ものアメリカの国民が、不動産の価値は上昇していくばかりだという幻想を植えつけられ、誰でも富裕層のような暮らしができるという空想に耽ったとして、著者は「私たちアメリカ人はさらに、政府や政府に共謀する者たちが、あらゆる類の恐るべき真実をひた隠しにしていると思い込んでいる。たとえば、暗殺、地球外生物、エイズの起源、9・11、ワクチンの危険性にまつわる真実などだ。また、銃を買い込んでは、過去の開拓時代を懐かしんだり、凶悪犯やテロリストとの銃撃戦を期待したりしている。軍の服や装備を購入しては、兵士になりきって誰も死なない戦闘に参加したり、とてつもなく現実的な仮想現実で同じようなことをしたりしている(妖精やゾンビになりきる場合もある)」と述べ、「私たちはいつの間にか、鏡の向こう側の世界、ウサギの穴の先にある世界に来てしまった。アメリカはおとぎの国、『ファンタジーランド』に変わってしまったのだ」と述べるのでした。
「ポスト真実におおわれるアメリカ」では、アメリカは、熱狂的な信者と情熱的な夢想家によって、あるいは詐欺師とそのカモによって生み出されたとして、著者は「そのため国民は4世紀にわたり、幻想の影響を受けやすくなった。セイラムの魔女裁判、ジョセフ・スミスが創始したモルモン教、興行師のP・T・バーナム、超越主義を主張したヘンリー・デヴィッド・ソロー、異言(訳注:学んだことのない異国の言葉を話すこと)、ハリウッド、サイエントロジー、陰謀論、、ウォルト・ディズニー、福音伝道師のビリー・グラハム、、ロナルド・レーガン、オプラ・ウィンフリー、ドナルド・トランプなど、いずれも幻想の影響を受けている。つまり、アメリカの歴史をレシピ風に説明するとこうなる。壮大な個人主義を極端な宗教と混ぜ合わせる。また、ショービジネスをほかのあらゆるものと混ぜ合わせる。その2つを鍋に入れて数世紀の間煮込む。そしてそれを、何でもありの1960年代とインターネット時代にくぐらせる。こうしてできたのが、私たちが現在暮らしているアメリカだ。そこでは、現実と幻想が危険なほどあいまいになり、異様な形で入り交っている」と述べるのでした。
第1部「アメリカという魔術【1517~1789年】」の第2章「私は信じる、ゆえに私は正しい(プロテスタント)」では、アメリカは、何もないところから設計・創建された初めての国だとして、著者は「壮大な物語を書くようにして生み出された最初の国である。たまたまそのころは、シェイクスピアやセルバンテスが近代的なフィクションを生み出しつつあった時期にあたる。新世界にやって来た最初のイングランド人たちは、刺激的な冒険に出た意欲的な英雄に自分をなぞらえていたことだろう。実際、魅力的な信念や、大胆な希望や夢、真実かどうかわからない幻想のために、慣れ親しんだあらゆるものを捨て、フィクションの世界に飛び込むほど向こう見ずな人たちだったに違いない」と述べています。
第6章「幻想をいれるうつわとして」では、一般的にプロテスタントの思想といえば、金儲けや資本主義を推進するのに都合のいい理由を与えた点が強調されると指摘し、著者は「たとえば、勤労は神を称える行為であり、成功は神の恵みの証だ、といった具合である。だがアメリカでは、プロテスタントの思想の別の一面が、それ以上に深く、広く、永続的な影響を与えた。それは、超自然的な現実認識、あるいは虚偽の現実認識を新たに考え出し、それを熱狂的な確信を持って信じることを認める考え方である」と述べます。
また、著者は、以下のように述べています。
「科学では、絶えず真実を疑う。真実は、部分的あるいは一時的な現実認識、少なくとも現段階では最高の現実認識として理解されているにすぎない。一方、プロテスタントの狂信者たちは、自然世界を丹念に調べ、あらゆる奇妙な現象を神もしくは悪魔に起因するものと考えた。彗星、ハリケーン、先住民の襲撃、珍しい病気、死など、すべてがそうだ。彼らにとって、真実は目の前にあった。あらゆるものには目的があり、その目的を理解するのはさほど難しいことではない。この国は、一攫千金やユートピアや永遠の命などの幻想を入れる空っぽの容器として始まった。新たな幻想を無限に生み出しても収められるほど大きな容器である。こんなことは以前にはなかった。また、ごく普通の人々が主導して荒野から国を造り上げ、その世界を作り変えていった。こんなことも以前にはなかった」
第2部「狂信者たちの合衆国【19世紀】」の第9章「第一次大狂乱期(合理的なヨーロッパ、狂信的なアメリカ)」では、南北戦争前の初期アメリカは多様な思想を培養する「精神の温床」だったというイェール大学の宗教史家ジョン・バトラーの説を紹介し、著者は「秘儀、千里眼、まじないによる治療、予知夢など、古い迷信や魔術への民間信仰が、もはやピューリタンの教義や規則に制約されることなく、キリスト教信仰と自由に混じり合った。その結果アメリカに、あらゆる種類の魔術的思考があふれ返った。19世紀の前半は『第二次大覚醒』期と呼ばれているが、私はこれを、もっと大きな『狂乱』期の一部にすぎないと考えている。この『第一次大狂乱』期の間に、宗教に限らず、文化、擬似科学、ユートピア、政治など、あらゆる分野で喜びや恐怖に満ちた種々雑多な幻想が爆発的に生まれ、アメリカというるつぼの中で互いに刺激し合いながら発展した」と述べています。
第11章「いかさま魔法好きな国民」の「魔法と科学と」では、19世紀半ばの驚異的な新テクノロジーが登場してきた時期には魔術的信仰が復活したことが指摘されます。著者は、「そのころになると、高速で旅行ができるようになり、機械で一瞬にして映像をとらえたり通信を行ったりすることが可能になった。1844年には、サミュエル・F・B・モールスが最初の電信を送った(最初に送ったのは、旧約聖書の「神のなせし業」という言葉である)。すると、それからわずか4年で、メイン州とミズーリ州、シカゴとサバンナを結ぶ電線が敷設された。その電線は、白熱光を発し、火花を散らしながらメッセージを送受信した。ニューヨーク・ヘラルド紙にはこうある。『キリスト教紀元1848年1月1日、奇跡の新時代が始まった』」と述べています。
1848年には、有名なハイズビル事件が起こりました。ニューヨーク郊外のハイズビルに住むフォックス家の12歳と15歳の姉妹が、モールス信号のような音を使い、家に出没する幽霊と会話をしたと公表すると、多くのアメリカ人がそれを信じたのです。ちなみに本書に登場する19世紀の人物の多くが、ニューヨーク州西部出身であす。フォックス姉妹は、末日聖徒イエス・キリスト教会(モルモン教)の設立者であるジョセフ・スミスが最初に神と話をした場所の隣町に住んでいました。姉妹は霊媒師として有名になり、死者と交信する「降霊術」運動が全国的に広まるきっかけとなりました。
スピリチュアリズム(心霊主義)の誕生にきっかけとなったこのハイズビル事件について、著者は「当時は、社会的地位のある人々でさえ降霊術の会に参加した。著名ジャーナリストのホレス・グリーリーも姉妹を擁護し、宣伝まで行っている(姉妹は40年後すべてが嘘だったと認めたが、幸運にもグリーリーはすでに他界していた)」と述べ、さらに「当時シェーカーは、精霊や幽霊との交信を詳細に記録していたが、ある記録にはやや興奮気味にこう記されている。大西洋を横断する電信が証明しているように、『生者の世界と死者の世界の間には電信が確立されている』。さらに、『終末』を予言し、『携挙』という概念を生み出したダービは、電信を『ハルマゲドンの前触れ』と考えた」と述べています。
「信徒は科学者となる」では、19世紀に多く生まれた擬似科学と宗教の相互作用から、新たな宗派が生まれ、やがてまったく新しいアメリカの宗教へと発展したことが紹介され、著者は「1830年代、メイン州に住んでいた時計職人・発明家のフィニアス・クインビーは、メスメリズムの効果に気づくと、すぐさま開業医に転身し、催眠術を駆使して病気に苦しむ患者の治療を行った。クインビーの業績や考え方は、やがてニューソート(新思考)運動を引き起こした。これは、20~21世紀のサイエントロジーやニューエイジ運動(訳注:20世紀後半に現れた精神世界を重視する自己意識改革運動)の先駆けとなる運動である。ニューソート運動の信奉者は、信念がすべてを支配するのであり、不幸も幸福もすべては頭の中だけのことだと考えた。信奉者の中には、キリスト教徒もそうでない人もいたが、彼らは一様に、自分たちは科学的であると同時に神秘主義的であり、個人を完成に導く実用的なツールを提供すると主張した」
第15章「1000万もの大草原の小さな家」の「開拓者の気分を味わう」では、ニューソートの重要な思想家であるヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817年~1862年)やラルフ・ウォルドー・エマーソン(1803年~1882年)らが登場します。『ウォールデン(森の生活)』の著者として知られるソローは、占星術や妖精の存在を信じ、満月には幽体離脱をさせる力があると思い込み、エマーソンとともに超越主義を主張しました。著者は、「超越主義とは、啓蒙主義に由来する知性に基づいた味気ないプロテスタント主義に、私が初めて『ウォールデン』を読んだときに感じたような、ありあわせの精霊信仰と神秘主義を結びつけ、それに少しアジアのスパイスを効かせたような思想である」と述べています。
ソローが『ウォールデン』を出版する少し前、エマーソンは聴衆に向かって「裸の大地に立ち、朗らかな大気に頭を浸していると、心は何もない空間へと上っていく。すると、卑しいうぬぼれがすっかり消える。私は透明な目玉になる。もう何ものでもない。すべてが見える。普遍的存在の流れが、私の中を循環する。そのときの私は、神の一部、あるいは神の粒子なのだ」と語りました。著者は、「超越主義思想は言う。人間は本質的に善である。あらゆる創造物は、壮大な網を構成する目のように相互に結びついている。自然は神であり、神は自然である、と。これでは、自然を好きにならないわけがない」と述べます。
第16章「幻想の産業化」の「フィジーの人魚」では、興行師として有名なP・T・バーナム(1810年~1891年)が登場します。 一条真也の映画館「グレイテスト・ショーマン」で紹介した映画の実在の主人公です。バーナムは、心躍る世俗的な幻想や真実まがいのものを売り込んで有名になったアメリカ人の草分け的存在であるとして、著者は「その大成功の原因は、『ファンタジーランド』の基本的な考え方にある(逆に、その大成功によりこの考え方が助長されてもいる)。つまり、ある想像上の見解が刺激的であり、それが正しくないことを証明できる人がいなければ、アメリカ人にはそれを正しいと信じる権利がある、という考え方だ」と述べ、さらに「偽物と本物を組み合わせたアメリカ博物館の公演や展示物は、それを余興としてのみ提示する場合に比べ、きわめて有害な影響を及ぼした。それは数十年間にわたり、新たな大衆文化の中心として堂々たる地位を占め、嘘を楽しみたい、見せかけと本物との明確な相違を無視したいというアメリカ人の欲求を満たし、助長した」と述べています。
「宗教とビジネス」では、その頃すでに人気を博していた擬似製薬産業も、大衆文化に対する同じような考え方に基づいており、それを限定的かつ広範囲に展開しました。つまり、特定の製薬会社の売薬の販売のみに専念しながら、全国各地のとりわけ小さな町を巡回してメディスン・ショーの公演を行ったのです。著者は、「バーナムのビジネスモデルは、チケットを購入して楽しんでもらうという従来型のシンプルなものだが、メディスン・ショーのビジネスモデルは、広告に頼る安価なタブロイド紙に近い。つまり、音楽家や手品師、芸人やノミのサーカスの公演を無料で楽しんでもらい、その見返りに、公演の合間に行われるいかがわしい医薬品の実演宣伝も見てもらうのである」と述べています。
「想像上のノスタルジー」では、1870年代に興行師として活躍したバッファロー・ビル(1846年~1947年)が登場します。著者は、「バッファロー・ビルがあのシャイアン族の戦士の頭皮をはいだ事件を舞台化したのは、アメリカが独立100周年を迎えた年だった。その年には、建国100年を記念して、アメリカで初めての大規模な国際博覧会が開催されたが、このフィラデルフィア万国博覧会もまた、コディのショー同様、現実と非現実を混ぜ合わせたものだった。展示物には、17世紀のものらしく見える『ニューイングランドの農家』の複製、ジョージ・ワシントンが実際に使った野外テントを入れたとされる革袋、植民地時代の風車の模造品が並んだ」
その17年後の1893年に開催されたシカゴ万国博覧会も、幻想的な擬似現実が前面に押し出され、事実上それが博覧会のテーマと化していました。中心となるヨーロッパ風の地区は「ホワイトシティ」と呼ばれ、新古典主義建築の建物がいくつも並ぶ都会的な夢の国でした。ただしそのほとんどが、焼石膏で一時的に塗り固めた、使い捨ての実物大の複製にすぎず、5か月の開催期間後には解体処分されました。著者は、「『ホワイトシティ』は、舞台装置のような偽物ではないが、本物でもないという点で斬新だった。幻想でもあり現実でもあったのだ」と述べています。また、博覧会の本会場の西に広がった催事会場では、ハンガリーで生まれウィスコンシン州で育ったハリー・フーディーニ(1874年~1926年)と名乗るユダヤ人の若者が、インド魔術を操るヨガ行者として奇術を披露していました。彼は後に世界最高の「魔術王」として有名になります。
「アメリカ史の第一期の終わり」では、当時のアメリカの人口は6500万人でしたが、シカゴ万博には2700万人以上が訪れたとして、著者は「彼らはその展示物や催事を見て、こう思ったに違いない。現実よりも幻想のほうが優れているような気がする。そもそも幻想と現実の間に重大な違いがあるのか? 現実の番人を自称してきたまじめな人々も、この『ファンタジーランド』を是認していたようだ。それは、シカゴ万博の会場が、数学・天文学会や世界宗教会議、アメリカ歴史学会年次総会の会場となった事実からも明らかだろう」と述べています。
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「19世紀の間に、多くのアメリカ人が、奇跡の妙薬や、月面に棲むコウモリ人間の文明や、161歳になるジョージ・ワシントンの乳母の話を信じるようになった。フリーメイソンやカトリックの陰謀説が勃発しては消え、また再発した。数百万人がにわかに、「終末」が間近に迫っているという預言を信じ、神やサタンが自分の肉体や精神を支配していると思い込んだ。新たな教会から、あっという間にまた別の教会が分離・誕生した。そんな19世紀に、現代のアメリカのキリスト教、あるいは現代のアメリカのニュースメディア、広告、娯楽、政治、製薬産業がすべてスタートを切った。そのいずれもが、幻想と現実を自由気ままに混合したものを基にしている。こうして、全国的な規模で夢のような嘘を売るのが、当たり前のことになり、アメリカの生活の一部になった。つまり、幻想と産業が永続的かつ相乗的に結びついた幻想・産業複合体の基礎が築かれたのだ」
第3部「理性への傾斜の時代【1900~1960年】」の第17章「進歩と反動の時代(1920年代のアメリカ)」では、20世紀に入ってから1920年代に至るまで、新たな降霊術ブームや常軌を逸した宗派が現れるとともに、大量の移民への反感が高まったことが紹介されます。1920年代、ギルバート・セルデスは、もはやわずかな痕跡を残すにすぎない19世紀アメリカの滑稽な魔術的思考への墓碑銘として、『不可解な世紀』を執筆しました。著者は、「当時はすでに、合理主義者がこうした思考を厄介払いしていた。確かに、霊能者や降霊集会は一時的に復活した。ボストンの社交好きな医師の若妻が、霊媒師として有名になったこともある(ただし彼女が有名になったのは、降霊集会でよく服を脱ぐからでもあった)。だが、降霊術は結局、1920年代にフーディーニなどの懐疑派により、徹底的に虚偽を暴かれた。その結果、19世紀後半から現れた大規模な降霊術コミュニティのほとんどが、姿を消した。オカルト、神秘主義、天文学、錬金術、魔術をごちゃ混ぜにした神智学も、19世紀末から20世紀初頭にかけて流行したが、やがて分裂し、こちらも1920年代には忘れ去られた」
ユダヤ人がアメリカを動かしているのではないかという不安は、ユダヤ人の人口が2パーセントを超えるころから本格化しました。1世紀前には、カトリックの人口が2パーセントを超えたころに反カトリックのヒステリー症状が始まっているとして、著者は「ちなみに、アメリカで大成功を収め国民の尊敬を集める実業家ヘンリー・フォードは、『シオンの議定書』(邦訳は四王天延孝・天童竺丸訳、成甲書房、2012年)の熱烈なファンだった。これは、もともとフィクションとしてロシア語で出版された本だが、現在では、世界征服を企むユダヤ人指導者たちの秘密会議の議事録、つまりノンフィクションだと言われている」と書いています。
1920年代、フォードは、アメリカで『シオンの議定書』を50万部出版するための費用を負担した。それどころか、『The International Jew:The World′s Foremost Problem(国際ユダヤ人――世界最大の問題)』と題する4巻本を構想・出版してもいます。著者は、「青年時代のヨーゼフ・ゲッベルスやアドルフ・ヒトラーがドイツ語訳で読み、ヘンリー・フォードの熱烈なファンになったという、いわくつきの書籍である。だが、アメリカでフォードを非難する声が上がり、不買運動が始まると、フォードはただちに謝罪・回収した。こうしてアメリカにおける反ユダヤ主義は、20世紀の間に着実に下火になっていった」と述べています。
「KKKの復活」では、ノスタルジーは再び一種の病気と化していたとし、1915年には、映画監督のⅮ・W・グリフィスが、かつてないほど野心的、感動的で洗練された大作映画『国民の創生』を公開したことが紹介されます。この作品は、その年どころか1910年代を代表する映画として、大成功を収めました。著者は、「だがこれは、神話的な『古きよき南部』やクー・クラックス・クラン(KKK)(訳注:白人至上主義を唱えるアメリカの秘密結社)の復興を3時間にわたり訴える、恥知らずなプロパガンダ映画だった」と述べています。続けて、著者は「『国民の創生』は、ホワイトハウスで上映された初めての映画となり、ニューヨーク市でおよそ1年間上映された。すると、やがてそれが現実となった。続く10年間、復興したKKKが爆発的な人気を博したのだ。この機会にKKKは、絶対的な白人優越主義への醜いノスタルジーのほか、不気味で奇抜な衣装(白いローブ、円錐形の帽子)や幻想的な用語体系(警官は「帝国の魔法使い」や「グランド・ゴブリン」、KKKの地元組織は「クラバーン」)により、組織としての統一を進めた」と述べるのでした。
第19章「娯楽ビジネスこそアメリカの本分――映画、ラジオ、出版」では、20世紀になると、アメリカ人は無意識的にフィクションを信じる傾向を強めていったことが紹介されます。著者は、「アメリカは万国博覧会に夢中になり、数年ごとに別の都市で、1年近くに及ぶ大規模な祭典を開催した。また、キリスト教の二大祝日であるクリスマスとイースターでは、それぞれサンタクロースとイースターバニーという超自然的・幻想的(かつ商業主義的)キャラクターの採用が、宗派を超えて公式に認められた。手品や奇術が黄金時代を迎え、五指に余るスーパースターのほか、よく知られたマジシャンが何十人と登場した。その中でも、20世紀最初の四半世紀に世界的な名声を博したのが、フーディーニである。彼のショーは、真実と虚構が途切れなく融合していた。(中略)また、1910年から1930年の間に、現在のブロードウェイにある劇場のほとんどが開館した。地下鉄が開通してアクセスしやすくなったコニーアイランドには、巨大なアミューズメントパークが矢継ぎ早に3つ現れた」と述べています。
しかし、それ以上に大衆文化に影響を及ぼしたものがありました。映画です。著者は、映画産業について以下のように述べています。
「これまでの1世紀の間、アメリカ国民は驚異的な新技術に何度もあぜんとさせられてきた。だが、見せかけを現実に見せる、魔法と区別のつかない先進技術により、映画という一大産業の基盤が築かれると、文化に飛躍的な変化が起きた。一気に、幻想と現実との差が縮まったのだ。映画を見れば、読み書きができない人も、さほど想像力のない人も、誰でも容易に魔法の世界に入れる。その世界では、どこへでも瞬時に移動し、何でも目にすることができる」と述べています。続けて、著者は「異国的な場所が絵で表現されているのでもなければ、想像上のキャラクターが文章で表現されているのでもない。実際の場所で実在の人間が、生き生きと動いている。これほど力強く、驚くほど現実らしく見えるメディアはそれまでなかった。映画は、演劇よりも容易に『不信の一時停止』ができる。単純に映画のほうが、舞台上で現実を装っている生身の人間を見るよりも、『驚き』が大きいからだ。また、映画館に行くのは、家で小説を読み、心の中で空想の世界を想像するのとも違う。それはむしろ、教会に行く行為に似ている。毎週、近所の人たちと連れ立って、特別な会場に1、2時間集まり、魔法のような、夢のような仮想現実を一斉に体験するのである」と述べます。
「幻想をニュースに――広告」では、アメリカの幻想・産業複合体は、映画をはるかに超えて拡大しつつあったとして、著者は「もはやアメリカ人は、さまざまな場面で幻想を提供され、それにだまされて楽しんでいた。たとえば広告である。『marketing(マーケティング)』という言葉は、そのころから現代的な意味で使われるようになった。『advertise(宣伝する)』も、かつては広く情報の公開を指す言葉だったが、やがて、事実や虚構、魅惑的な文句を組み合わせ、製品(や思想や人間)を有料で売り込むことのみを意味するようになった。広告がちまたにあふれ、それがほかの産業にとって欠かせないものになると、この事業は一大産業と化した。それを支配したのも、やはりアメリカである。確かに、かつての売薬産業も、深刻な症状に効く薬としていかがわしい製品を宣伝・広告していた。だが20世紀になると、その広告が、ありふれたものに新たな幻想的な意味合いを付与するようになった」と述べるのでした。
第20章「郊外のユートピア」の「望みの幻想の世界、カリフォルニア」では、カリフォルニアに人が集まった理由について、「まるで『エデンの園』のように暖かく穏やかな環境に恵まれ、豊かな土と芳香に満ちている。たとえ有望な金脈を掘り当てられなくても、ここでなら夢を実現できる。できないことなど何もない。こうして、ゴールドラッシュにより何十万もの夢追い人に満たされたカリフォルニアは、あらゆる類の幻想を育む場となった。その結果、サンフランシスコの初期ボヘミアン社会、ペンテコステ運動、ハリウッドなど、さまざまなユートピア的理想や完全主義的な生活様式が生まれた。さらに後には、ビート族、サイエントロジー、ビッグサー(訳注:カリフォルニア州モントレーの雄大な海岸地区で、20世紀半ばに作家や芸術家のコミュニティが生まれ、その後のヒッピー文化の拠点にもなった)、ディズニーランド、ロナルド・レーガン、サマー・オブ・ラブ(訳注:多くのヒッピーがサンフランシスコに集結した1967年夏のヒッピー・ムーブメント)、シリコンバレーがこの地で誕生している。これらがカリフォルニアで生まれたことに、必然性はないかもしれない。だが、この地球上に、常軌を逸したさまざまな夢や計画を信じ推進する人々にこれほど適した場所が、ほかにあるだろうか? アメリカ的発想が極度に凝縮されたところ、それがカリフォルニアだ」と書かれています。
第21章「アメリカの黄金時代」の「ディズニーランド構想」では、ディズニーが採用したのは1940年代にアメリカで誕生したばかりのモデルだったと指摘し、著者は「それは、本当に古いものと偽りの古いものとをごちゃ混ぜにして展示した、博物館のような観光施設である。(中略)復元された古い建物に、古く見せかけた新しい建物が何百と混在していた。同様に、ミシガン州ではヘンリー・フォードが、自動車工場の近くの土地に『グリーンフィールド・ビレッジ』を建設していた。ここには、スティーヴン・フォスターやライト兄弟、エイブラハム・リンカーンが実際に生活したり仕事をしたりしていた建物が、ペンシルベニア州やオハイオ州やイリノイ州から移築されている。この施設では、まったく新たな試みがなされていた」と述べています。また、著者はウォルト・ディズニーについて「彼は、この時代のスティーヴ・ジョブズだった。ほかの人が作り上げたものを組み合わせ、その単なる総和よりも価値の高い、輝かしい新ブランドを生み出すことのできる、先見の明を備えた興行師だった」と評しています。
「もう1つのアミューズメントパーク――ラスベガス」では、ディズニーランドと現代のラスベガスは、同時に誕生したとして、著者は「ディズニーランドは、『いかがわしい人物』や『歓楽街』的な雰囲気を否定したところから生まれている。一方ラスベガスは、そこからモハーベ砂漠を500キロメートル近く横断した先にある荒れ地に、いかがわしい人物たちにより、歓楽街として作られた。いわば、ディズニーランドの対極の位置にある。ディズニーがアミューズメントパークを壮大なものに作り変えたように、新たなラスベガスを生み出した人たちも、賭博場や居酒屋など、既存の怪しげな施設を壮大なものに作り変えた。その結果ラスベガスは、別のホルモンや神経伝達物質に飢えている人、いちかばちかの賭けを必要とする人にとっての「アドベンチャーランド」となった。一夜にしてお金持ちになって浮かれ騒ぐか、一文なしになって酒浸りになる場所である。ラスベガスとディズニーランドは、幻想・産業複合体の延長線上に別々に生まれた新たなブランドだと言える」と述べます。
「オルゴンエネルギー、ドラッグ、サイエントロジー」では、アメリカの「ファンタジーランド」化の一翼を担っているのがドラッグであるとして、著者は「1950年代、ビート族はドラッグを格好いいものと見なすきっかけを作った。バロウズはヘロインを、ケルアックはスピードを、ギンズバーグはマリファナを好んだ。当時は一般のアメリカ人も、新たに製造されるようになった合法的な向精神薬を受け入れていた。たとえば、合成アンフェタミンのベンゼドリンは、アメリカでは1959年まで店頭で購入でき、それよりも効き目の強いデキセドリンも導入されたばかりだった。驚くべきことに、1960年のアメリカ人の合法的覚醒剤の使用頻度は、1人あたり平均して週1回である。そのころからは、精神安定剤の大量服用も始まった。奇跡の精神安定剤と謳われたミルタウンが薬局に登場すると、それから2年後の1957年には、この薬がアメリカの全処方薬の3分の1を占めるに至った」と書いています。
第4部「狂気と幻想のビッグバン【1960~1970年】」では、1960年代には、アメリカ人1人ひとりが独自の旗を掲げたとして、著者は「超利己的なアイン・ランド主義者やニューエイジのシャーマン、根本主義や福音主義やカリスマ派、サイエントロジー信者やホメオパシー医、カルト信者や知識相対主義者、左派・右派問わず陰謀説を支持する人、過去の戦争の再演を楽しむ人、サタンや地球外生物に誘拐されたと主張する人、取りつかれたようにポルノやギャンブルや銃を愛する人・・・・・・。『好きなことをしろ』。これにより、認識論・存在論の堤防は木っ端微塵に砕かれ、以後修復されることはなかった。『権威を疑え』。その結果、現実らしく見える幻想が以前のように主流派から否定され、排除されることもなくなった。『自分だけの真実を見つけろ』。それ以降、自分が望むことが真実となった。1人ひとりが、侵すことのできない個人であり、権利を与えられたアメリカ国民であり、自分の宗教の司祭であり、自分の物語の著者なのである」と述べています。
「ここでは奇跡がいつでも起きる」では、サンフランシスコから南へ3時間ほどのところにある、海岸沿いの崖が延々と絶景を形作っているビッグサーと呼ばれる場所に、「エサレン協会」という施設がつくられました。1970年代までにニューエイジとして知られるようになるもののほとんどが、このエサレン協会で考案・開発され、世に広められたとして、著者は「この協会はいわば、教会や宗教は好きではないが、それでも超自然的なものを信じたいという人が信仰する、新たなアメリカの宗教の中心的教会となった。協会の参加者たちは、恍惚状態で聖なるものを体験することにより、自分たちの信仰の正当性が証明されることを願った。その点では、1636年にボストンで宗教活動を展開したアン・ハッチンソンの支持者、1801年にケーンリッジで開かれた伝道集会に参加した人々、1906年にロサンゼルスに集まったペンテコステ派の信者と同じである。エサレン協会の現在のウェブサイトにはこうある。『ここは、奇跡が起きるだけの場所ではない。いつでも起きる場所だ』」と書いています。
「神秘主義にとりつかれる科学者たち」では、1970年代には幻想的な信仰や信念が一般にまで及び、当時は大手の出版社やメディアまでが、幻想をノンフィクションとして宣伝・販売しようと躍起になっていたとして、著者は「1975年には、スプーン曲げや読心術を行う若き詐欺師、ユリ・ゲラーの自伝がベストセラーになった。同年にはそのほか、哲学の博士号を持つレイモンド・ムーディの著書『かいまみた死後の世界』(邦訳は中山善之訳、評論社、1989年)も話題となった。瀕死の状態に陥り、臨死体験をした数十名のエピソードを、死後の世界の直接的な証拠として紹介した本で、『これらの話が嘘だとはまったく考えられない』と断言している。この本が数百万部の売上を記録すると、間もなく国際臨死研究学会が発足し、その第1回会議がイェール大学で開催された」と述べています。
また、本物の科学者たちも神秘主義に取りつかれていったとして、著者は「1965年には、NASAが火星で予定していたバイキング計画のため、生命探査装置を設計していたある化学者が、突然ある確信に至った。大気、森林、海岸、生物を含む地球全体が、生命を育むよう完璧かつ神秘的に調整された単一の有機体と考え、これを『ガイア仮説』と命名したのだ。ガイアとはその『有機体』を指すギリシャ神話由来の名称である。彼はその後、微生物学者と共同でこの仮説を発展させて科学論文を発表し、1970年代にはオックスフォード大学出版局から大衆向けに『地球生命圏――ガイアの科学』(邦訳は星川淳訳、工作舎、1984年)を出版した」と述べます。
「『超』心理学」では、1930年代から40年代にかけて、植物学から心理学に転向したデューク大学の教授が、超心理学という学問分野を打ち立てたとして、著者は「超心理学とは、テレパシー、透視、サイコキネシス、生まれ変わり、幽霊が実在することを証明する学問である。この教授が超心理学協会を設立すると、1960年代後半には(マーガレット・ミードの勧めもあり)アメリカ科学振興協会への参加が認めれれた。そのころ、教授の若き弟子に、チャールズ・タートというカリフォルニア大学の心理学者がいた」と述べます。1937年生まれのタートは、1969年に発表した『変性意識状態Altered States of Consciounsness』で、一躍有名になった人物であり、サイ(超能力)の実験的研究に取り組んでいることで知られます。「変性意識状態」(日常的な意識状態、睡眠状態以外の意識状態)という言葉の生みの親でもあります。現在も、テレパシー、夢、予知、遠隔視、肉体離脱などの現象の解明に取り組んでいます。
第24章「キリスト教――異端派、急進派の巻き返し」の「宗教的な狂気の広がり」では、著者は以下のように述べています。
「現代から見た1960年代の一般的なイメージは、若者、衝突、快楽主義である。確かに1970年代には、ハレー・クリシュナ・マントラやマンソン・ファミリー、ジョーンズタウンでの集団自殺など、目を引く奇妙な宗教活動があちこちにあった。だがいずれも、常軌を逸したこの十数年の間に生まれては消え、大した重要性を持つには至らなかった。瞑想やヨガに、これといった信仰など必要ない。だが実際のところ、1960年代を特徴づけているのは、『セックス』『ドラッグ』『ロックンロール』『非理性的な超自然信仰』だけではない。この時代の遺産の中には、一般的なイメージから抜け落ちているものがある。それは、キリスト教の急進化である。宗教的な狂気がきわめて広範囲に、爆発的に広まったのだ」
第25章「現実か、フィクションか」では、1960年代前半からすでにワシントンの陰謀を描いたサスペンス映画『五月の七日間』や『影なき狙撃者』が公開されていたが、1970年代に入ると陰謀をテーマにしたハリウッド映画が大流行したとして、著者は「『チャイナタウン』『カンバセーション…盗聴…』『パララックス・ビュー』『コンドル』といった映画が、わずか2年の間に公開されている。現実世界の出来事が、こうした物語に真実味を与えていたことは言うまでもない。当時は、FBIや情報機関による左派グループへの潜入捜査が明らかになっていた。また、実際にホワイトハウスが犯罪的陰謀を企み、不法侵入および隠蔽を試みたウォーターゲート事件もあった」と述べています。
さらに、著者は以下のように述べています。
「アメリカ人は、フィクションと現実を意のままに混ぜ合わせ、何でも好きなことを信じる権利を新たに手に入れたような気になった。おそらく、そのころUFOの目撃例が前例のないほど増えたのも、地球に現れる地球外生物が増えたからではなく、魔術的思考が突如解放され、アメリカ人が何でも信じやすくなっていたからだろう。地球外生物が存在することを望み、それを信じた結果なのだ。だが、1960年代に始まるUFO熱は、ただ愉快なだけでなく、歴史的に重要な意味を帯びている。というのは、それをもとに、実に込み入った物語が作られるようになったからだ。飛行や着陸の目撃談だけではない。誘拐や政府の隠蔽、惑星間の極秘の盟約といった話まである。熱心なUFO信仰は、アメリカ人の途方もない陰謀思考の種をさらにまき散らした。その結果、20世紀の間に陰謀思考は隅々にまで蔓延し、きわめて有害な影響を及ぼすことになったのである」
第26章「幻想・産業複合体――子ども化する大人たち」の「『フォース』というエネルギー」では、それまではハリウッド映画にイエス・キリストが登場する機会はあまりありませんでしたが、聖書を文字どおり解釈する急進的なキリスト教が復興すると、かつてないほどイエス本人が注目を浴びるようになり、幻想・産業複合体が聖書の物語の再現に熱心に取り組むようになったことを指摘し、その一方で、同じキリスト教をテーマにした、現代のアメリカを舞台に展開される恐るべき幻想についても、新たな市場が開拓されたとして、著者は「サタンに取りつかれる『エクソシスト』、人間の女性がサタンの子を産む『ローズマリーの赤ちゃん』や『オーメン』など、身近なところにサタンがいるという幻想が、ハリウッド映画の1ジャンルとなった。こうして異様な超自然的信仰はますます一般化していった」と述べています。
「幻想が支配する場所」では、1970年代初めからは、中世後期の魔術的世界の戦闘や冒険に参加したいが、できれば普通の服装で、屋内でそれを楽しみたいという何百万もの若者が、テーブルゲーム『ダンジョンズ&ドラゴンズ』に夢中になったとして、著者は「このゲームでは、プレイヤーが特定の人物(ドルイド僧、蛮族、騎士、魔法使い)の役を演じる。いわゆるロールプレイングである(この言葉はもともと心理療法士や教育者が使う技法を指し、1960年代にはよく使われていた)。『ダンジョンズ&ドラゴンズ』を開発したのは、戦争シミュレーションゲームが好きな若者たちだった。ランド研究所やペンタゴンが戦争シミュレーションを復活・洗練させていたころには、一般のアメリカ人の間でも戦争シミュレーションゲームの人気が高まっていたのだ。彼らは、ミネアポリスのリビングルームでテーブルを囲みながら、自分たちの作った戦争ファンタジーは現実のようにスリリングだと感じていた。当時の一般人はまだ、実際の指揮官のようにコンピューターを使うことができなかった」と述べています。
第5部「拡大する『ファンタジーランド』【1980年代から20世紀末まで】」の「異常さに気づかなくなった国民」では、新たな超個人主義は、ライフスタイルの選択だけにとどまらないとして、著者は「アメリカ人は、自分だけの真実を見つけ、自分の好きなことをしているうちに、薬でハイになったりポルノを見たりするだけでなく、非宗教的な公教育を拒否したり、好きなだけ銃を所持したりするようになった。また、市場の力を絶対視し、それを宗教的信念にまで高めさえした。さらに、とても信じられない陰謀からありえない陰謀まで、極秘の巨大な陰謀を信じる人々が増え、それまで頭のおかしな傍流でしかなかった考え方が主流と化した。悪魔崇拝者による暴行や地球外生物による誘拐など、空想的な恐怖や不可思議な出来事を経験したと主張するアメリカ人も増え、そのような主張がまじめに取り上げられるようになった。心理学や精神医学などの学界、宗教、法執行機関など、一部の体制派も、大衆がこうした想像上の体験を信じるのに手を貸した」と述べています。
第27章「空想を現実に、現実を空想に――巨大テーマパーク化する社会」の「筋書きのある物語」では、プロレスが取り上げられます。プロレスは、1910年代から20年代にかけて娯楽産業が活況を呈していた時期に生まれましたが、著者の青春時代にあたる1960年代から70年代にかけて、プロレスは安っぽくばかばかしい作りものと見なされ、たちまち忘れ去られていきました。しかし、「疑いながらも信じる」では、以下のように書かれています。
「1980年代に入ると事情ががらりと変わる。ケーブルテレビが登場し、従来のテレビよりも節操なく、どんな番組でも積極的に放送するようになった。すると、空想を現実として提示することに良心の呵責を感じていた従来のテレビ局も、ケーブルテレビの攻勢を脅威に感じ、もう一度プロレスの放送を始めた。当時は、自由市場が業界を完全に支配していた時代でもあったのだ。一方プロレス界は、この自由放任主義経済のもとで、世界プロレス連合(WWF)の事実上の独占状態にあった。後の世界レスリング・エンターテインメント(WWE)である。この独占事業を展開したヴィンス・マクマホンは、みごとな洞察力の持ち主だったらしく、バーナム的な傾向が再びアメリカに蔓延してきたことに気づいていた」
プロレスは正真正銘のスポーツではないにせよ、プロレスラーの人生の現実の部分とフィクションの部分が混然一体となった、楽しいペテンと考えられるようになったとして、著者は「プロレスでは、ときどきお決まりで挿入される、台本にない本気の格闘部分を『シュート』という。これはもともと、昔の巡回ショーで、射的のライフルが正確に狙いを定めた状態を指す言葉だ。一方、台本どおりのやらせの格闘部分は『ワーク』という。それに対しWWFの興行主は、1980年代に『ワークト・シュート(ワーク化されたシュート)』なるものを考案した」と述べます。また、最もプロレス的な人物として、ドナルド・トランプの名を挙げます。トランプは政界に入る前、WWEのスポンサーとして自分が経営するカジノでプロレスのイベントを行っており、あるときにはリング上に登場し、マクマホンに平手打ちやボディスラムを食らわすふりを演じたこともあります。後にはWWEの殿堂入りを果たしています。
第28章「いつまでも若く」の「『みんな子ども』症候群に害はあるのか?」では、マイケル・ジャクソンが取り上げられます。彼は中年に入る直前、自分だけのファンタジーキャンプである「ネバーランド」を建設したことを紹介し、「そこに、ディズニーランドのような狭軌鉄道を敷き(長さではディズニーランドよりも長い)、古めかしい貨車を牽く蒸気機関車を走らせた。ディズニーランドのメインストリートUSAにならい、ビクトリア朝風のレンガ造りの駅も設置した。それだけではない。この遊園地には、ジェットコースターも、バンパーカー(訳注:バンパーをぶつけ合って楽しむ小型の電気自動車)も、動物と触れ合える動物園も、舵輪を備えたツリーハウスも、ロープの橋も、無料の駄菓子屋もあった。彼は突然、そこに本物の子どもたちを集めたが、子どもたちと一緒に寝るなと大人から言われ、泣きわめいた。それどころか失禁し、床に放尿した。結局ネバーランドではペットのチンパンジーと暮らした。このチンパンジーは、彼の隣のベビーベッドで眠り、レコーディングセッションにも参加し、一緒にワールドツアーをまわった」と書いています。
マイケル・ジャクソンが、子どものままでいたい、空想の世界にいたいと思えば思うほど、美容整形に駆り立てられたのは言うまでもないとして、著者は「1990年代の一時期には、数か月ごとに手術を受けていたという。それはちょうど、美容整形産業が大きく発展した時期と一致している。美容整形は主に、患者を若く見せること、そうでなければ、映画やテレビや雑誌に登場する夢の人物に似せることを目的にしている。女性の豊胸手術は、5年間で3倍に増えた。その結果今では、アメリカ人女性の25人に1人が、胸にシリコンや生理食塩水の袋を埋め込んでいる」「ポルノが供給過剰になり始めたころ、アメリカで陰毛の除去が流行したのは、決して偶然ではない。女性がポルノを見て、ビデオの中の女性のように手入れをすれば、異常に若く、思春期前の少女にさえ見えると思ったのだろう。2000年には、テレビドラマ『セックス・アンド・ザ・シティ』により、ブラジリアン・ワックス脱毛が話題になった」と書いています。
第29章「レーガン政権とデジタル時代」では、超常現象信仰やニューエイジ文化、キリスト教、政治的な右派・左派の中には、刺激的な秘密を暴くと豪語する急進主義者がいるとして、著者は「彼らは、ラジオ・テレビ放送やインターネットを通じて、無関係に見える思想や考えを結びつけた見解を広めている。いわば、さまざまな思想に戦術的な同盟関係を結ばせ、異種交配させている。その結果、ある思想がほかの思想につながっていく。複数の考え方が相互に結びつき、かたまりを形成していく。そのため、ある1つの幻想を信じると、別の幻想も信じる結果になりやすい。1970年代後半、アメリカ陸軍に超常現象の研究開発部隊が設置された。その部隊を指揮していた少将は個人的に、空中浮遊や非物質化、壁の通り抜け、気力による雲の消失を研究していたが、やがて9・11が発生すると、これはアメリカ政府の陰謀であり、ハイジャックされた飛行機はビルを破壊することもペンタゴンに衝突することもなかったと確信するに至った」と述べています。
第33章「キリスト教とは異なる魔術、宗教とは異なる精神世界」の「書籍に見る”ニューエイジ”」では、以下のように書かれています。
「ニューエイジはきわめてアメリカ的な、民主的で分権的な運動であるため、聖典とされる文献も無数にある。その中でもきわめて影響力が大きく、広く読まれている一冊が、ロンダ・バーンの『ザ・シークレット』(邦訳は山川紘矢・山川亜紀子・佐野美代子訳、角川書店、2008年)である。これは、10年ほど前に出版されると、ウィンフリーの力強い推薦を受け、たちまちニューエイジの聖典に仲間入りした。ウィンフリーは、バーンが自分の番組に出演した際にこう述べている。「何年も前から番組でこの本の話をしているの。これを”シークレット”にしようなんて思わなかったから」。
この『ザ・シークレット』の原型とも言えるのが、1950年代に出版されて大ベストセラーとなった『積極的考え方の力』です。著者は、「当時はまだ、こうした超自然的な力による成功を語るには、キリスト教との結びつきが必要だった。実際この本には、神への言及が数百か所、イエスへの言及が数十か所ある。ところが『ザ・シークレット』では、「繁栄の福音」の創始者としてイエスの名が一度登場するだけだ」と述べています。また、「『ザ・シークレット』は、『積極的考え方の力』同様、アメリカの基本原理(個人主義、超自然崇拝、「信念」への信仰)に沿った内容ではあるが、そこから宗教的装い(神やイエス、美徳、勤勉に対する報い、来世でのみ得られる至福)をはぎ取っている。その結果残ったのは、「引き寄せの法則」である。何であれ強く望みさえすれば、自分のものになる。信じることがすべてというわけだ」とも述べます。
「2012年のマヤの予言」では、ちょうど『ザ・シークレット』が出版されたころ、ニューエイジに関心がある人々の間で、2012年に関する噂が飛び交い始めたとして、著者は「古代のメソアメリカ人が、2012年に人類が別の段階に移行すると予言したのだという。そのような噂が広まった原因は、1960年代後半にさかのぼる。イェール大学のある人類学者が、何気ない思いつきから、マヤ人の暦の考え方についてこう記したのだ。現在の5125年にわたる周期が終わるとき、『ハルマゲドンが世界中の堕落した人々や全生物に襲いかかり」「現在の宇宙は滅びるかもしれない」。その日はどうやら、2012年12月21日になるという。これには、ニューエイジの新宗教家たちが喜んで飛びついた。彼らは、自分たちにもキリスト教と同じような、近未来のハルマゲドンやその後の信じられないほどすばらしい世界といった夢が欲しいと思っていた。そんなときに、それが起こることを示す古代の予言を見つけたのだ』と書いています。
第35章「主流派エリートの敗北」の「天国を旅する」では、1990年代には、大手出版社が天使や超自然現象についてのノンフィクションを出版するようになり、ほぼ毎年、死後の生について書かれた本がベストセラーになったことが紹介されています。たとえば、『90Minutes in Heaven(天国での90分)』『天国は、ほんとうにある』(邦訳は阿蘇品友里訳、青志社、2011年)『The Boy Who Came Back from Heaven(天国から帰ってきた少年)』『To Heaven and Back(天国への行き来)』『プルーフ・オブ・ヘヴン』(邦訳は白川貴子訳、早川書房、2013年)などです。一条真也の読書館『プルーフ・オブ・ヘヴン』で紹介した本の著者は脳神経外科医で、「美しい蝶の羽に乗って」天国を旅したといいます。
第6部「『ファンタジーランド』はどこへ向かうのか?【1980年代から現在、そして未来へ】」の第37章「甦るフロイト――20世紀の悪魔崇拝」の「『抑圧された記憶』というフィクション」では、心の科学の領域では、抑圧された記憶という概念ははるか昔に放棄されたが、一般の人はそれを信じるように仕向けられていたとして、著者は「1960年代から70年代にかけて、人々はセックスのことで頭がいっぱいで、陰謀論を信じ、自分が犠牲者だと感じる人はみな実際に犠牲者だと信じるよう教え込まれたのである。映画もまた、抑圧された記憶を信じるように人々を仕向けた。ハーバード大学医科大学院の精神医学教授によれば、『子どものころのトラウマが急に蘇るフラッシュバック』は、抑圧された記憶というフィクションの考えをリアルに見せるフィクションの手法だという」と述べています。
また、1980年代には、抑圧された記憶という概念が『回復記憶』という新しいフレーズによって再び人々の想像の中で大きな位置を占めるようになったとして、著者は「人はみな、自分の過去の隠された真実を解き放つ力を持ち、それを解き放つことを可能にする隠された鍵が明らかになったというのだ。不幸で精神的に病んだ人をケアする職業が大きく成長した。臨床心理士、臨床社会福祉士、カウンセラーといった仕事だ。その多くが十分な訓練を受けておらず、科学の知識も欠いていた。1970年代から80年代にかけてのアメリカでは、臨床心理士の数が3倍になり、その多くが抑圧された記憶や回復記憶やトラウマを探すセラピストになった。彼らは、患者が語る驚くべき物語をすべて真実と信じて認めただけでなく、ときには患者が想像力たくましくフィクションの記憶を信じるのを手助けした」と述べます。
「催眠術の裏にひそむ考え方」では、抑圧された出来事の記憶を掘り起こすいちばんのツールになったのは、催眠術でした。掘り起こされる記憶には、実際にあったかもしれない性的虐待にとどまらず、エイリアンによる誘拐や「前世」、その他のさまざまなフィクションも含まれました。実のところ、催眠状態は神経学的に空想状態と兄弟関係にあります。催眠術にかかりやすい人のほとんどは、心理学で「空想傾向」のある人格を持つのです。著者は、「1990年代にハーバード大学で始まった一連の実験では、前世やエイリアンによる誘拐の記憶を思い出せると信じている人たちを被験者に、そのような『記憶』とは関係のない場面でその人たちの心がどのように働くのかを明らかにしようとした。予想どおり、宇宙人に誘拐されたという人は常に『顕著な虚偽記憶効果を示して』いて、前世の記憶を持つという人は『虚偽記憶の度合いがきわめて高く』『魔術的思考の測定でも高い数値を記録した』。つまり、彼らは生まれながらの空想家だったのだ」と述べています。
第38章「現実は陰謀である」では、著者はテレビドラマ「X―ファイル」について以下のように述べています。
「『真実を求めて』『信は理解なり』『誰も信じるな』。1993年から放送がはじまった『X―ファイル 』のこういったキャッチフレーズは、ファンタジーランドのスローガンとしても完璧だ。『X―ファイル』の制作者は、番組の内容が正しいと証明することは求められない。純粋なエンターテインメント番組であり、台本のあるフィクションであり、役者たちがFBI捜査官や陰謀者やエイリアンを演じている。しかし『X―ファイル』も『コースト・トゥ・コーストAM』も、種類こそ違え、いずれもインフォテインメント(娯楽報道番組)であり、テレビとラジオという幻想・産業複合体内の隣接分野で作られていた。テレビとラジオはプロパガンダ装置としてタッグを組み、政府による強大かつ邪悪な極秘の陰謀や魔術的思考への信仰を広め、強化している。1910年代と20年代には、映画『国民の創生』が白人至上主義を美化し、KKKを実際に復活させることにもつながった。1990年代には『X―ファイル』が陰謀論の新たなパラダイムの重要分野に華やかな形を与えた」
第41章「科学を否定するリベラル派――ワクチン恐怖症の弊害」の「反ワクチン運動」では、かつてのアメリカでは毎年1000人近くの子どもがジフテリアや破傷風、百日咳で死亡しており、はしかのせいで毎年数百人が亡くなり、さらに多くの人が聴力を失ったり当時の言葉でいう「知恵遅れ」になったりしたことが紹介されます。しかし1950年代と60年代初めに、こうした病気を防ぐワクチンが登場し、子どもはみなその接種を受けるようになったとして、著者は「何千もの不必要な死や障害が、これによって予防された。当時、反ワクチンの運動はまだ存在しなかった。その後、ワクチンが自閉症などの恐ろしい病気を引き起こすという誤った考えが現れる。出所はいつも同じだ――昔のほうがよかったという根拠のないノスタルジー、専門家への過剰な不信感、悪いものの背後にはすべて邪悪な陰謀があるという確信、門番のいないインターネット。反ワクチンのヒステリーに火をつけた研究は、自閉症の診断例が増えていた1998年に現れた。はしか、おたふくかぜ、風疹のワクチンを接種されたあとに自閉症的行動を見せた10人の子どもを調べた医師が、その結果を医学雑誌に発表すると、たちまち反ワクチン運動が巻き起こった」と述べます。
第42章「ガン・クレイジー――銃に熱狂する人たち」の冒頭を、著者は「現在、ほかのどの空想よりも恐ろしい影響を現実世界に間違いなく与えている空想がある。銃所有は最も重要な権利であり、アメリカの自由と個人主義を体現するものだと考える空想だ。私が生まれてからこれまでの間に、アメリカ人の銃への愛は盲目的になった。銃は、私たちの金を奪い、確実に脚も骨折させている」と書きだし、さらには「アメリカでは、劇的な大量殺人がほかの国と比べてはるかに頻繁に起きるが、その理由は、大虐殺にぴったりの武器をきわめて簡単に買えるからだけではない。殺人者がクールな役柄を演じていたり、一夜にして有名になるという、アメリカに絶えずついてまわる夢に突き動かされたりもしているからだ。専門家によると、大量殺人者のほとんどは、病的な妄想を持つ精神異常者や妄想型統合失調症患者ではなく、ファンタジーランドの住民だ。欠点や失敗を、他者、システム、エリート、世界のせいにする不幸な人たちだ。彼らは不安を募らせ、憤りを準軍事的復讐という煽情的な空想に変える。この空想を実行に移せば、世界に大きな衝撃を与え、注目を惹くことができる」と述べています。
第43章「デジタル・ゲーム、VR、SNS――拡張する幻想・産業複合体」の「自分自身の真実を持つ」では、幻想・産業複合体は、映画、テレビ、劇場、広告、出版、テーマパーク、ギャンブルにとどまらないと指摘し、著者は「有名人にかかわるものだけでなく、インターネット、テレビ、ラジオ、活字など、情報メディアのほとんどがそこに含まれる。ゲームだけでなく、インターネットのかなりの部分が関係している。兵士やアニメキャラクターやスーパーヒーローやサンタの格好をして人前に出る大人たちや、プロ・スポーツチームのオーナー気分でいる人たち、凶悪犯罪に走る姿をオンライン上の他人と空想する人たちも含まれる。銃業界の多くも含まれ、政界も関与の度合いを増している。不動産業界のかなりの部分も含まれる――テーマ化された住宅開発、レストラン、ショッピングセンターなどである。アメリカの小売業界には、「リテールテインメント」や「エンターテイリング」(訳注:どちらも「retailing(小売業)」と「entertainment(娯楽)」を組み合わせた造語)によって、ありふれた商品を売り込む業者がたくさんいる。医療業界の一部(美容整形、向精神薬)や、時代と場所によっては金融業界も含まれる。巨大産業から職人的なものまで、幻想・産業複合体はアメリカの心を握るセクターだ。経済面での重みをはるかに超えて、アメリカ人の生活を支配している」と述べます。
「現実と非現実の境目」では、デジタル革命によって、非現実に熱を上げる傾向がさらに強まったとして、著者は「中には最近のフェイク・ニュース・ビジネスなど明らかに有害なものもあるが、概して真実と非真実の境目はあいまいになりつつある。私たちは、インスタグラムやフォトショップで加工した写真を非現実だとはもはや思わない。グーグル・フォトでは、自動的にさまざまな写真を組み合わせて新しい写真を作ることができる。つまり、実際に起こったのとは違う形で出来事を記録する、リアルタイムの修正主義だ。幻の騎士たちや超ナチス主義者たち、地球外のロボット戦士たちと交流することもできれば、こういったソフトウェアによる創造物(あるいは、オンラインでの姿とは異なるかもしれないが私たちのような実際の人間)と交流しながら、自らフィクションのキャラクターになりきることもできる。今は人間同士のやり取りはほとんどがデジタル上でなされており、匿名の場合もあるので、好きなときにこっそりとどんな役でも演じられる。『キャットフィッシュ』や『ソックパペット』という新しい単語も誕生した。それぞれ、オンラインで架空の人物になりすまして異性を引きつける人、自分のファンになりすます人を指す」と述べています。
「なんとなくリアル」では、ファンタジー小説が爆発的に増えたことと、わたしたちが全般的に変化したこととが無関係だとは思えないとして、著者は「過去10年間の大ヒットテレビ番組が、ドラゴンや魔法が登場する過去の世界(『ゲーム・オブ・スローンズ』)や、吸血鬼(『トゥルーブラッド』)やゾンビ(『ウォーキング・デッド』)に悩まされる近未来のアメリカを舞台にしたシリーズだったことは偶然ではない。キリストについてのミニシリーズ『THE BIBLE――選ばれし者たちの歴史物語』(2013年)が、リアリティ番組(『サバイバー』や『アプレンティス』)の考案者によってヒストリー・チャンネルで放映され、1億人のアメリカ人が視聴したのも偶然ではない。同番組のプロデューサー、マーク・ブルネットは、NBCで放送されたその続編『AD――聖書の時代』を「『ハウス・オブ・カード』と『ゲーム・オブ・スローンズ』を合わせたもの」だと言う」と述べます。
大ヒットした映画の内訳を見ると、1970年代にはどの年も、ファンタジー映画はせいぜい2、3本でした。それが今では、1、2本を除いてすべてファンタジー映画です。トールキンの小説が登場して半世紀経った2000年代には、ハリウッドがそれを巨大映画シリーズに仕立て上げたとして、著者は「ここ10年で最も多くのアメリカ成人が読んだ小説が『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』だったこと、それがファンタジー小説『トワイライト』をポルノ化した娯楽小説だったことは偶然ではない。過去半世紀で最も読まれた本は、聖書と『毛主席語録』を別にすれば、『トワイライト』『ハリー・ポッター』シリーズ、『アルケミスト』『ダ・ヴィンチ・コード』『指輪物語(ロード・オブ・ザ・リング)』だ」と述べます。
「時間とお金を使ってバーチャルで生活する」では、完全に新しいメディアであるデジタル・ゲームは、1960年代と70年代に誕生し、90年代に巨大な存在になり、今や不気味なまでに擬似現実的な没入型ゲームとなって広く普及していると指摘し、著者は「小説や映画の場合、どれだけ没入していても、そういった物語の中にはっきりと個人としての自分が存在しているわけではない。物語に自分が影響を与えられるわけでもなければ、自分がしたり言ったりすることにほかのキャラクターや周囲の架空の環境が反応するわけでもない。ゲームはまた空想のフィクションに支配されている。これはより大きな社会の変容と結びついているのだろうか? それとも、デジタル技術により巧みに現実を偽り変化させることができるようになったからなのか? 尋ね方が違うだけで、どちらも同じ問いだ。2000年以降、ブロードバンドのインターネットによって、多数のプレイヤーからなる巨大なオンライン世界を作ることが可能になった。そこには無数の住人がいる。空想の形式で存在する実在の人間、現実世界からの移住者仲間たちだ」と述べています。
デジタル・ゲーム、特にソーシャル・ゲームが普及する一方で、今でも多くの人が、顔と顔を合わせ、身体と身体を接して、肉体を持つ血の通ったほかの人間とともに空想を演じることに強くこだわっていとして、著者は「頭の中だけでなく身体的にも没入できる世界、クリック1つで逃れられたりしない世界へのこだわりだ。その原型とインスピレーションの元は、ビッグバンの期間を含む20年間、1950年代半ばから1970年代半ばにかけてすべて登場した――ディズニーランド、過去を再現した博物館、ルネサンス市、南北戦争の戦闘再現イベント、ライブRPG、あらゆるレトロなものへの執着、BDSMクラブ、ハロウィンでの大人の仮装。今は何百万ものアメリカ人がコスチュームを着て小道具を持ち、外の世界へ出て、数時間、数日間、あるいは1週間、自分でないふりをし、もっとスリリングな場所や時代で風変わりな生活を送るおもしろい人間であるかのようにふるまう」と述べます。
第44章「大人になるのは悪いこと?――ディズニー化するアメリカ」の「バーナム化、ディズニー化の系譜」では、アメリカの幻想・産業複合体の最初期である1850年代から、上から目線の批評家たちは「バーナム化」という言葉を軽蔑的な意味で使っていたことが紹介されます。そして今から数十年前に、その後継となる類義語が登場しました。それは「ディズニー化」という言葉で、アメリカの都市部がテーマパーク化してきたことを表すとして、著者は「ディズニー化はバーナム化とは異なり、一度きりのものではなく、ずっと続くプロセスや恒久的な状態のことで、例外ではなくルールを表す言葉である。今は、ほぼすべての大都市にメインストリートUSAやニューオーリンズ・スクエアが移植されており、アメリカ人はこの歴史的フィクションあるいは擬似フィクションの中で暮らしている」と述べています。
「子ども化する大人」では、アメリカの大人がより本質的な部分で子どものように考えるようになったのは確かで、これは実際、厄介な状況を引き起こすとして、著者は「大人になるということは、欲しいものを手にするまで待つということだ。今すぐ満足を得ようとするのは、7歳児の行動だ。インターネットが強い魅力を持つのは、その即時性と、インターネットによって可能となる『コミュニティ』のためである。今メッセージを送ることができ、今疑問に答えが得られて、今欲しいものを何でも買えて、今すぐに知らない人と会ってセックスできる。電気通信は、ある種の内なる子どもを満足させる。衝動的で待つことをまったく我慢できない内なる子どもだ。その結果、過去20年の間に、満足が遅れてやってくること自体がおかしいと見なされるようになった」と述べています。
第45章「経済の夢の時代――繰り返される『根拠なき熱狂』」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「1980年代から90年代を経て2000年代まで、大いに弾みのついた金融と経済の幻想は、とにかく幸福なものだった。アメリカは宗教に対して企業家的な独特のアプローチをとってきたが、同時にとりわけ1960年代以降、企業経営に対する異様に宗教的なアプローチも発達させた。アムウェイ、メアリー・ケイ、ウォルマート、チックフィレイ、アップル、オプラ・ウィンフリー帝国、全盛期のマーサ・スチュワート、ホールフーズ、アマゾンは、従業員の間にも顧客の間にも、カルト的で福音派的な雰囲気を醸成した。これはおそらく私が信仰するブランド、アップルにもっとも顕著に見られる。LSDでトリップした誇大妄想家スティーブ・ジョブズが『現実歪曲フィールド』を広げて、自分が信じさせたいことを何でも人々に信じさせた。この言葉を『スタートレック』から取ってきたアップル社員は言う。『ジョブズがいれば、現実は変えられます』」
第46章「トランプ政権を生んだ国」の「ようこそ、ファンタジーランドへ」では、著者はドナルド・トランプについて以下のように述べています。
「ツイッター以前の時代には、トランプが私たちに脅迫の手紙を送ってきたり、公の場で私たちの悪口を言ったりすると(『スパイ』については「あんなのはゴミだ」と言っていた)びっくりして現実ではないような気がし、まるでダフィー・ダックやロジャー・ラビットがスクリーン上のアニメの世界から飛び出して応答してきたかのように感じたものだ。アメリカの金持ちで力のある愚か者を記録する雑誌を作っていたときに、トランプがタイミングよく登場したのは、神意によるのかもしれない。落ち目にあるアメリカの歴史を私が書いている最中にトランプが注目の的になったのも、やはり神意によるだろうか?ドナルド・トランプは、生粋のファンタジーランド的存在、ファンタジーランドの権化だ。トランプが大統領選に出馬しなければ、私は彼にまったく触れなかったかもしれない。しかし彼はこうして登場し、本書の何よりもすばらしい証拠となった。トランプを描写すれば、実質上この本を要約したことになる」
「自分と同じ考えを信じる」では、著者は「空想上の陰謀論は、トランプが繰り返すモチーフであると同時に、ファンタジーランドの歴史上で繰り返されてきたモチーフでもある――魔女、カトリック、フリーメイソン、ユダヤ人、そして現在はイスラム教徒やリベラル派や国際主義者による想像上の陰謀……。そもそもトランプが政治活動を始めたのは、アメリカ人の心の奥底にある2つの気質と結びついた新たな陰謀論を信じたからだ。その気質とは、外国人や非白人への恐怖と嫌悪感である。2011年にトランプは、バラク・オバマ大統領がケニア生まれだという空想の一番の宣伝マンになった。そのせいで、取るに足らない奇説が主流と化し(ほかならぬドナルド・トランプが言うのだから!)、FOXニュースやCNNのニュースキャスターが繰り返し取り上げるようになった」と述べます。
「ファンタジーランドのなりたち」では、アメリカ人が発明し、支配してきた幻想・産業複合体は、急激に広がり、政治、不動産、小売、『もてなし』、ライフスタイル、生活など、考えうるあらゆる領域を取り込んでいったとして、著者は「私たちはあらゆる場所で、1日24時間、週7日、空想と空想的現実のコラージュに取り囲まれている。もちろん、ディズニーワールドやアイマックス・シアターや『モータルコンバット』では、私たちはフィクションの領域にいるとわかっている。けれども、ほかの場所ではどうだろう?生活の大部分を占める名目上は本物とされているもの、たとえば容姿や服装、住んでいる場所や食事をする場所、娯楽情報番組やニュースの解説者、インターネット上の発言など、さまざまなところで偽物と本物の区別が消し去られた。アメリカの現実の多くは、今やバーチャルだ。ファンタジーランドの中にいるのか外にいるのかわからないことも多い」と述べています。
「世界を『わかりやすく』する」では、半世紀にわたって、数世代のアメリカ人が二項対立の世界観のもとで暮らしたことが指摘されます。全体主義的な悪者と自由世界という二項対立ですが、ソ連が崩壊して中国が普通の国になると、世界の地政学的現実が入り組み混乱し、あいまいで複雑になったとして、著者は「世界を再びわかりやすくするため、1つの敵に焦点を絞ろうと、エリートの陰謀が存在するという考えが多くのアメリカ人を引きつけている。誰かが糸を引いているに違いないというわけだ。悪者に虐げられていると考えると、恐怖と同時に安心を覚える。だから、陰謀論者は目をこらして現実世界を見て、権力の行使を途方もなくシンプルかつ華麗なほど複雑に理解する。彼らは現実をフィクション化する」と述べます。
そして、本書の最後で、著者は「文化的な傾向や国民性は確かにあり、社会が岐路に立たされて重要な選択を迫られることがある。ただし、アメリカにファンタジーランドへ向かう傾向が初めからあったとしても、現在の状況は必然の結果ではない。歴史と進化に必然はないからだ。また、特定の未来に向かう必然性もない。国のバランスと落ち着きを取り戻すことは可能だ。過去数十年は結局のところ1つの段階、進行中の物語の奇妙な一幕、アメリカの実験の残念な1エピソードに過ぎず、やがて過去の出来事として記憶に留められることになるだろう。さまざまな国や社会が、はるかにひどい逸脱や激変を生き抜いて、そこから立ち直ってきた。つまり、米国は今、ファンタジーランドのピークにあるのかもしれない。そう願いたい」と述べるのでした。この面白過ぎるアメリカ史の本を一気に読破したわたしは、しばし放心状態となりました。コロナ禍が終息したら、またアメリカに行きたいです!