- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.05.22
『死ぬときは苦しくない』永井友二郎著(講談社)を紹介します。2006年7月に初版刊行された本で、第二次世界大戦における西太平洋トラック島での平安丸被弾による臨死体験で「死ぬときは苦しくない」と確信した著者の死生観が綴られています。著者は、1918年生まれ。1941年に千葉医科大学卒業後、1942年海軍軍医中尉として太平洋戦争に出征、九十九死に一生を得て生還。戦後、成田赤十字病院内科医長を経て、1957年永井医院を開業。医者中心ではなく、患者中心の医療を目指す。1963年に「実地医家のための会」、1978年に「日本プライマリ・ケア学会」を設立。1988年、日本医師会最高優功賞受賞。2017年5月8日没。享年98歳。
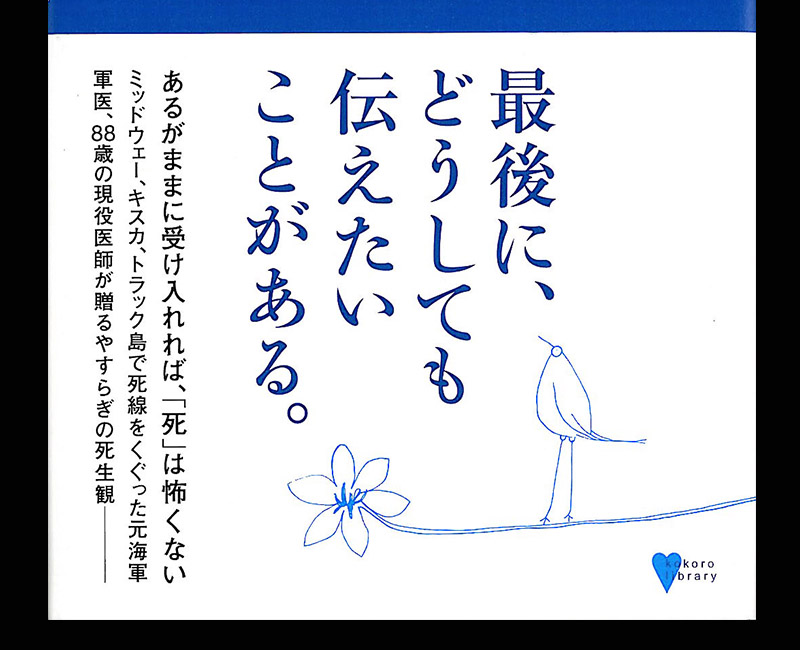 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「最後に、どうしても伝えたいことがある。」と大書され、「あるがままに受け入れれば、『死』は怖くない。ミッドウェー、キスカ、トラック島で死線をくぐった元海軍軍医、88歳の現役医師が贈るやすらぎの死生観――」「私は医師として六十年以上病人をみてきたほか、太平洋戦争で海軍軍医として多くの死に立ち合ったので、死にかかわった数は医師のなかでも、もっとも多い一人だと考えている。、あたさらに、戦中、私自身が負傷・失神するという臨死体験も経験した。それで、これらのこの体験にもとづき、人間の最後がどんな状況であるか、そしていままで誰もがおそれていた臨死の苦しみ、これがないことについて本書でゆっくり述べてみたい。――『はじめに』より」と書かれています。
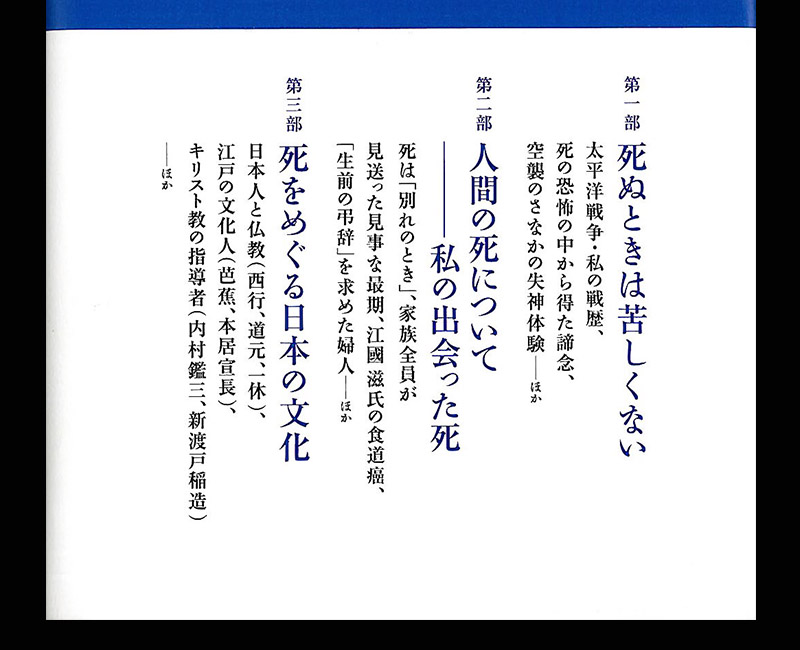 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一部 死ぬときは苦しくない
第二部 人間の死について
――私の出会った死
第三部 死をめぐる日本の文化
「おわりに」
〈参考文献〉
「はじめに」で、人間は多く、死ぬときは苦しいにちがいないと思い、最後のときを恐れているとして、著者は「病人の最期の様子を見れば、これは無理のないことであるが、はたしてほんとうにそうだろうか。呼吸や心臓が停止するとき、はたして痛いとか、苦しいという感覚、そして意識がまだあるのだろうか。人間の感覚や意識が心停止のぎりぎりまであるのなら、痛み、苦しみを感じるだろう。しかし最期のとき、この人間の感覚と意識とがすでになくなっていた場合には、心停止、呼吸停止のときには痛みも苦しみる、なにも感じないはずである。このことは、死を恐れるわれわれにとって、大変大事な、そして重要なことである」と述べています。
第一部「死ぬときは苦しくない」の「『あるがまま』に生きる」では、著者が太平洋戦争中、ミッドウェー海戦を皮切りに、ガダルカナル島の攻防戦、キスカ島撤収作戦、マキン・タラワ島玉砕戦、トラック島大空襲と2年余りにわたり修羅場を歩いてきたことが語られます。軍艦が被弾したことが3度、沈没して泳いだことが2度、一度は著者自身が被弾、負傷、失神しました。また潜水艦ではアメリカの駆逐艦に7時間も爆雷攻撃を受けました。著者は「生きていたことが不思議である」と述べます。また、「あるがままが自分にとって一番よいことであり、これを有り難く受け入れる」という心構えは、著者の体験では、戦争の修羅場でも、平和な時代の苦しいときでも、いずれでも心に安らぎを与える力があったといいます。
「『死ぬときは苦しくない』に対する反響」では、京都の小児科医で、『わたしは赤ちゃん』などの著作も多かった松田道雄氏が岩波書店から『安楽に死にたい』という本を出版した平成9年、著者は「実地医家のための会」で「死の準備」という講演をしたので、その別刷りを松田氏に送ったエピソードが書かれています。著者はこの講演で、松田氏の『安楽に死にたい』の中の「人間は自分の自由と尊厳のなかでの死は許されていい。そして医師は終末期には治療しないだけでなく、高齢者の意志にしたがって、楽に死ねるようたすけるところまですすむべきだ」というくだりを紹介しました。
著者もかねて、できるだけ自宅で、自然のなりゆきにまかせた最期を遂げたいと考え、死ぬときについては、著者自身の臨死体験から、死ぬときはすでに意識がないので苦しくないと考えていることを述べたそうです。またさらに、著者の尊敬する先輩医師の言葉である「私は死ぬとき、食べないことにきめた。水も飲まなければ2、3週間で周囲に迷惑をかけず、楽に終われるでしょう」という考え方に共感することもつけくわえたといいます。
著者は、岩波の「図書」1996年5月号に松田氏が書いた「お医者はわかってくれない」の中の「自ら死ぬことを日本の医者がみとめないのは、西欧の医学を移入するとき、それに付随しているユダヤ・キリスト教的倫理をも丸のみにしてしまったからである。西欧の医学の育った国ぐにでは、自ら死ぬことは、神への冒瀆であり、王への反逆であった。……自ら死を選ぶことは、日本では倫理的選択のひとつであった。……武士は責任を明らかにするために腹を切った。主君の愚行を諫めて腹を切った。町人でも、添いとげられない恋人たちは心中をした。心中は悪ではなかった。近松門左衛門は悲しくはあるが、美しいものとしてドラマにした。明治以前に西洋医学を学んだ日本人の医者は日本のモラルを失わなかった。たとえば杉田玄白がそうだ。彼は高齢の苦痛からのがれるために高齢者が死をえらぶのを是とした」という文章を紹介しています。
第二部「人間の死について」の「人間の死」では、著者は「人間の死はひとりひとりの人間にとって、もっとも大きな問題であり、厳粛なことがらである。人類の歴史と文化は、この人間の死によって深められ、育てられてきた。そしてだれもが、死を恐れ、また悲しんできた。死ほど人間的なことがらはないといってもいい」と書いています。また、残された時間の少なくなった人間の特殊な心情を「末期の目」と呼び、「人間はこのとき、すべての欲望からはなれ、親しかった人たちにはもちろん、まったく見ず知らずの人にさえ、心をよせ、手をにぎり、話しかけたくなり、別れを惜しみたくなる、そういう純粋な心の状態である。人間愛といってもいい。人間最後の別れのときは、医師も、看護師も、家族たちも、最期をみとるすべての人々はこの『末期の目』の心を大事にしてほしいと思う」と述べます。
「死への畏れ――堀秀彦氏」では、元東洋大学学長の堀秀彦氏が著書『死への彷徨』(人間と歴史社)で、思想家として、死の問題に取り組む最初に孔子の「死んだ人間をもはや一切のいのちのなくなった一塊の物質と考えることも、又反対に死んだ人間を生きている如く考えるのもいけない」という考え方を紹介したことに言及します。これに対して、堀氏は「孔子が生と死との境界、区切りについてにわかに断定しなかったことに、孔子の驚くべき正直さ、率直さが示されている、また、孔子は生死の区別を概念的に決定することを好まなかった」と記しています。そして孔子の「いまだ生をしらず、いずくんぞ死をしらむ」という言葉は、孔子の生と死に対する無知の告白であり、この考え方は生存そのものについての敬虔、謙遜、真摯の徳を生む力があるだろう、と、孔子の倫理性に注目している。さらに、「孔子は一貫してこの世の生を重視する、孔子のなかにはいかなる死の哲学もない、水を飲み、肘を枕としながら、道に従い、清廉に生きる、生への執着は強い」と述べています。
「おわりに」では、著者が先の太平洋戦争で「人間は死ぬとき、意識がすでになくなっているので苦しくない」という医学的事柄と、「どんなことがおころうとも、あるがままでよい」という死生観を心にすえるようになったことを述べ、「『死ぬときは苦しくないこと』については、本書で詳述したごとく、戦後、私が病人の最期をみとるたび、確認してきた。それでこのことは是非多くの方々に知っていただきたいと思う。戦死した仲間たちの願いでもある。一方、私は戦争中の死の恐怖から、『どのようなことがおころうとも、あるがままが一番よい』という諦観、死生観をもつに至った。そして戦後、私はその根源をたどり、わが国古来の死をめぐる数々の遺訓をしらべ、そこに多くの共通するものを見出した」と述べるのでした。
本書の著者である永井友二郎氏は2017年5月8日、自宅で家族が看守るなか永眠されました。うっ血性心不全、98歳でした。4月20日に介護ベッドが自宅に搬入されたわずか2週間後の旅立ちでした。亡くなる前日まで食事は完食したといいます。利尿剤などの心不全治療は拒否する一方、在宅酸素は喜んで受けたようです。延命治療は拒否し緩和ケアの恩恵には与りながらの大往生であったようです。「死ぬときは苦しくない」という持論を大切にしながら、生涯現役の医師として人生を全うされた著者の生き様は、多くの医師にとって大きな励みとなりました。また、本書を読んだ多くの読者は死の不安から解放されたことでしょう。著者の御冥福を心よりお祈りいたします。
