- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.07.13
『極孔神仮説で神話や遺跡の謎が解ける』斎藤守弘著、羽仁礼編(ヒカルランド)を読みました一条真也の読書館『教養としての神道』で紹介した島薗進先生の最新刊、『教科書で教えない世界神話の中の『古事記』『日本書紀』入門』で紹介した鎌田東二先生の最新刊を読んで、縄文の信仰に興味が湧き、アマゾンで調べていたら本書の存在を知りました。この手の本が玉石混交であることはよく知っていますが、なかなか興味深い内容でした。著者の斎藤守弘は1932年生まれ、2017年没。前衛科学評論家、SF作家、超古代文明研究家。日本考古学会会員、日本天文学会会員。超歴史学研究会理事。編者の羽仁礼はASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員。一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、「超常現象研究家・斎藤守弘が晩年に取り組んだ古代史研究の集大成!」「日本や世界の遺跡や土偶に残る『縄文三大至高神』『縄文記号』『縄文神聖数』の痕跡から、記紀や古代文明の謎を読み解く」と書かれています。
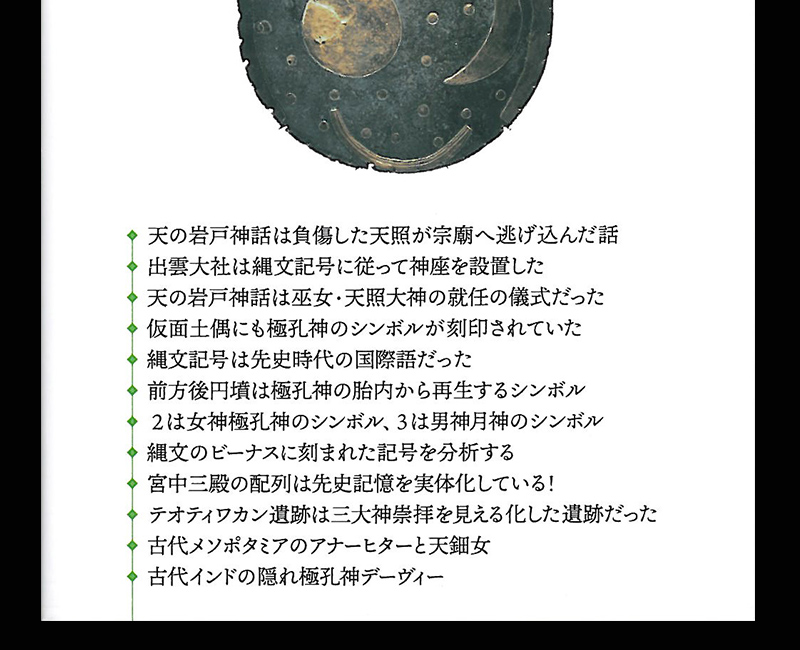 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書のカバー裏表紙には、以下のように書かれています。
◆天の岩戸神話は負傷した天照が宗廟へ逃げ込んだ話
◆出雲大社は縄文記号に従って神座を設置した
◆天の岩戸神話は巫女・天照大神の就任の儀式だった
◆仮面土偶にも極孔神のシンボルが刻印されていた
◆縄文記号は先史時代の国際語だった
◆前方後円墳は極孔神の胎内から再生するシンボル
◆2は女神極孔神のシンボル、3は男神月神のシンボル
◆縄文のビーナスに刻まれた記号を分析する
◆宮中三殿の配列は先史記憶を実体化している!
◆テオティワカン遺跡は
三大神崇拝を見える化した遺跡だった
◆古代メソポタミアのアナーヒターと天鈿女
◆古代インドの隠れ極孔神デーヴィー
カバー前そでには、こう書かれています。
「古代の人類が天の北極周辺の暗黒領域を女神として崇拝したという、極孔神信仰の根本部分と、そこから派生する縄文記号や縄文神聖数……旧石器時代の北半球の人類がそろって同じ神格を崇拝していたというスケールの大きな発想、その傍証として取り上げた数々の遺物の解釈は、しかるべき検証を行うべきではないかと思う。――編者解説より」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「編者まえがき」(羽仁礼)
第1章 斎藤守弘と極孔神
(羽仁礼)
第2章 極孔神神学で神名や古代遺跡の謎を解く
(羽仁礼)
第3章 縄文記号と縄文神聖数の謎を解読する
(斎藤守弘)
第4章 国宝・縄文ビーナスの謎を解く
(斎藤守弘)
第5章 極孔神と日本神話、天照大神の正体を明かす
(斎藤守弘)
第6章 極孔神から天皇制の起源をめぐる謎を解く
(斎藤守弘)
第7章 世界の神話・遺跡に残る極孔神信仰
(斎藤守弘)
「編者解説」(羽仁礼)
「編者まえがき」を、羽仁礼氏は「故斎藤守弘氏の講演録を入手したのは、2019年のことだった。一読して、そのスケールの大きさ、卓越した発想力、そして博覧強記ぶりに魅入られた。そこには、稀代の異才・斎藤守弘が晩年になってたどり着いた極孔神仮説を軸に、日本神話の真相や天皇家の祖先、さらには世界各国に残る壮麗な世界遺産などに関する、これまでにない斬新な理論が語られていた。このような斎藤理論を構築する上で重要だったのが、由緒ある神社の本殿の方角や盃状穴、そして縄文のビーナスといった、古代日本の遺品であった」と書きだします。
また、羽仁氏は「だいたい世界四大古代文明などという根拠のない文明論が常識としてまかり通っている国は、日本だけだ(厳密に言うと、韓国は多少この説に影響されているらしい)。邪馬台国論争などは、畿内説と九州説双方の陣営が相手の主張に耳を貸そうともせず、自らに都合のよい証拠のみを声高に主張しているとしか思えない。これではとうてい、建設的で学問的な論争とは言えないだろう」とも述べています。
第1章「斎藤守弘と極孔神(羽仁礼)」では、斎藤守弘について、羽仁氏は「大学卒業後は一時会社役員も務めたが、1959年に創刊された『SFマガジン』誌上では、1961年12月号から、世界の怪事件や奇現象について紹介する「サイエンス・ノンフィクション」を連載した。それ以後は『前衛科学評論家』を名乗って関係書を続々と刊行、豊富な科学知識と海外の資料を渉猟した情報を武器にテレビ番組にも何度も登場した。少年誌や少女漫画誌を中心に雑誌にも多くの記事を執筆した」と説明します。
また、斎藤守弘の記事について、羽仁氏は「その内容はUFO、心霊、超能力、古代文明、UMA、超科学や奇妙な事件など、現在超常現象とかオカルトとして総括されるすべての分野を含んでいる。中岡俊哉とともに1960年代から1970年代にかけての超常現象界を牽引したと言ってよい。世の中にこうした情報を提供するという意味では、黒沼健には遅れるものの、南山宏氏よりも時代的に先行している」と説明します。わたしも少年時代に、斎藤守弘の本はたくさん読みました。
「ネアンデルタール人は死を理解していた」では、その斎藤守弘が考古学研究から導き出したのが「極孔神」であると示されます。極孔神についてひと言で言うなら、天の北極近くの暗黒領域を神格化した女性神です。羽仁氏は、「この神に対する信仰がいつ頃生まれ、どのように発展し忘れ去られていったのか、いまとなっては詳しいことはわからない。しかし極孔神に対する信仰は太古の昔、北半球の大陸全土に存在していたようだ。そのことは、この神に関連するシンボルが世界中の至るところから発見されることから明らかである。古いものではハンガリーのタタ遺跡から出土した護符のようなものにもこの種のシンボルが刻まれているという。炭素14年代測定法を用いて調査した結果、この護符のような遺物はなんといまから5万年も前に製作されたという驚くべき結論が出た。5万年前というと、もしかしたら現生人類ではなく、ネアンデルタール人の遺物ということも考えられる」と述べています。
20世紀になってネアンデルタール人骨格化石が多数発見され、その住居跡などの研究が進むにつれ、ネアンデルタール人が人の死という現象を理解し、仲間の死を悼む感情を持っていたことが明らかになりました。このことは、1951年から調査が始まったイラクのシャニダールでの発掘で判明しました。ここである人物の骨の周辺の土壌を分析したところ、少なくとも8種類の花の花粉や花弁が含まれるとの結果が出たのです。これだけ多種類の花が一緒に見つかるということは、この人物が花の群落の中で死亡したとは考えられず、死亡したとき仲間たちが何種類もの花を手向けたのだと考えられています。彼らが芸術活動を行っていたことも明らかになりました。
ネアンデルタール人は現生人類と混血できないという考えもかつては支配的でしたが、2010年、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所のスヴァンテ・ペーボは遺伝子分析の結果、アフリカ以外の人類の約2.5%が、ネアンデルタール人のゲノムを持っていることを発見しました。つまりネアンデルタール人は現生人類と混血できるほど近縁だったのです。現生人類であるホモ・サピエンスは、約20万年前にアフリカで種として確立しました。そして、4万〜5万年前にヨーロッパに進出。つまり、先住のネアンデルタール人(ホモ・ネアンデルタールレンス)と一時共存していたのです。そのため、頭骨化石の分析に基づき、混血(交雑)があったという説も存在していたのですが、この研究結果により、種の文化には影響しなかったことが明らかになったと世界中に報じられました。
 『葬式は必要!』(双葉新書)
『葬式は必要!』(双葉新書)
「ネアンデルタール人と現生人類の間に混血なかった」という新聞記事を読んで、わたしは「まだまだ謎は多く残されている」と思いました。そして、DNAのバトンタッチがなかったとしても、わたしたちの「こころ」にネアンデルタール人たちの心が流れていると信じていました。現代の人類がネアンデルタール人とつながっていないのなら、現代人が「ホモ・フューネラル」であることの根拠をネアンデルタール人に求めることは非常に危険です。しかし、わたしは2010年4月に出版された『葬式は必要!』の27ページに「現代ではネアンデルタール人は、わたしたちの直接の祖先ではないとされていますが、まだまだ謎は多く残されています。わたしは、DNAのバトンタッチがなかったとしても、わたしたちの『こころ』にはネアンデルタール人たちの『こころ』が流れていると信じています。つまり、物理的な遺伝はなかったとしても精神的な遺伝があったと思っています。その最大の証拠こそ、今日にいたるまで、わたしたち人類が埋葬という文化を守り続けていることです」と書きました。
 世紀の大発見!!
世紀の大発見!!
しかしながら2010年になって、マックスプランク研究所とアメリカのバイオ企業などからなる国際チームが再度、ネアンデルタール人のゲノム(全遺伝情報)を骨の化石から解読したところ、現生人類とわずかに混血していたと推定されるとの研究結果が出たのです。その研究結果は2010年5月7日付のアメリカの科学誌「サイエンス」に発表されました。同年4月25日に『葬式は必要!』が刊行された直後に、人類史をひっくりかえすような大発見があったのです。しかも、それは人間にとって葬式が必要であることの根幹をなす大発見でした。わたしは、サムシング・グレートの存在を改めて思い知ったのです。
 『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
わたしは、人類は埋葬という行為によって文化を生み出し、人間性を発見したのだと確信します。ヒトと人間は違います。ヒトは生物学上の種にすぎませんが、人間は社会的存在です。ある意味で、ヒトはその生涯を終え、自らの葬儀を多くの他人に弔ってもらうことによって初めて人間となることができるのかもしれません。葬儀とは、人間の存在理由に関わる重大な行為なのです。ホモ・フューネラルは、わが主著の1つである『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館・サンガ文庫)の根幹をなす考え方といえます。最近ではネアンデルタール人は、「ホモ・サピエンス・ネアンデルターレンシス」、つまり現生人類と同類の人類と呼ばれるようになっていますが、わたしは「ホモ・フューネラル(弔うヒト)」と呼んでいます。
「星のない円形の暗黒領域の発見から極孔神は生まれた」では、現生人類とかなり近いネアンデルタール人であるから、極孔神信仰についても彼らが生み出したものが現生人類に伝わったという可能性も否定できないのだと羽仁氏は述べます。この信仰がネアンデルタール人の発明か現生人類のものかはさておき、それが夜空を見上げることから生まれたことは確かだろうというのです。極孔神信仰の誕生について、羽仁氏は以下のように述べています。
「彼らは一つ不思議なことに気付いた。天空のうち、天の北極を中心とする一定の範囲だけが、星のない暗黒空間となっているのだ。現在は北極星ポラリス、つまり、こぐま座アルファ星が天の北極から44分、つまり4分の3度ほどの位置にあるが、地球の歳差運動により、天の北極点近くにある星は長い年月の間に入れ替わる。たとえば紀元前1万2000年頃には、こと座のベガが天の北極に一番近い星であったが、天の北極からは5度ほど離れていた。紀元前1万年頃には、ヘラクレス座イオタ星がこれに代わるが、このときも天の北極から4・5度ほど離れていた。つまり、かなり長い期間、天の北極周辺何度かの領域に星明かりが存在しない時期が続いたのだ」と述べています。
また、羽仁氏は以下のようにも述べています。
「この暗黒空域は丸い形の闇として認識されたであろう。なぜなら夜空の星々は、その暗黒域を中心に回るから、その暗黒域はまるで一面銀砂のように輝く星空の中に、ポッカリと口を開ける暗黒のトンネルの入り口のように見える。このことは、カメラを天の北極へ向け、シャッターを全開にして設置し、そのまま5~6時間放置すれば明らかだ。こうすると、北極点を中心にして無数の巨大な光る同心円の円弧が撮影できるカメラを持たない古代人でさえ、満天の星々が天の北極を中心として、東から西へ、つまり北を向いて立つと反時計回りに無数の同心円を描いて移動していくことが認識できただろう。その様子を眺めていれば、天の北極周辺も、まるでカメラで捕らえた写真のように、ほとんど星のない円形の暗黒領域として認識できたのではないだろうか。同じ頃、古代人たちの意識に変化が生じ、自意識が生まれた。生命とは何かと考え始めたのだ。そこで、魂という観念が生まれた」
当時は死がごく身近にあったことでしょう。野の獣に襲われたり、獲物の追跡中に崖から転落したり、水に落ちてそのまま浮き上がってこないこともあっただでしょう。飢えも常に身近にありました。人間の脂肪細胞は、飢鍼状態においてもある程度の期間生き延びられるよう栄養を蓄えるために発達したといいます。さらに疫病があったことも指摘し、羽仁氏は「前日まで元気だった老人などは、翌朝になると眠るように死んでいたりする。肉体的には前日と変わらずまったく損傷がなく、死の原因が見当たらないのに、生命の兆候が消え、冷たくなっていたりする。当然、生命の源となる何らかの存在がそっと肉体を抜け出したように思えただろう」と述べます。
やがて、人間の死そのものが、肉体と魂の分離ではないかと感得されます。死者の霊と交信できる者も現れてきます。では、この魂はどこからやって来て肉体に入り、死後はどこへ行くのでしょうか。この疑問が、天の北極にある暗黒の孔と結びつきます。羽仁氏は、「あの黒い空間こそ、魂がやってくる出口であり、死後の魂が帰って行く死後の世界への入り口ではないか。そうした観念が生まれた。そしてこの空間自体が神格化され、崇拝の対象となる。いつの世でも、新しい生命を産むのは女である。新しい生命は、母親の産道を通って股間の出口から頭を出す。したがって魂をこの世に生み出す黒い孔の神も女性と想定された。極孔神の誕生である」と述べるのでした。
「天照大神は極孔神の巫女だった」では、古代人にとって、この暗黒領域こそ、誕生時にはそこから魂が地上に降り、死亡時にはそこに帰って行く女神の胎内だったのだとして、羽仁氏はさらに斎藤守弘は、古代の様々な遺物の研究から、極孔神のほかに、魂の輪廻を司る男性月神、そして魂を乗せて地上と暗黒領域を往復する翼あるヘビという、二体の神格の存在にたどり着く。この三神を『縄文三大至高神』と呼んだ。この三神にはそれぞれの役割に応じて固有の文様があり、また特定の数字と関連付けられた。こうした文様や数字の存在は、縄文遺跡で見つかったもので初めて国宝に指定された土偶『長野県茅野市棚畑遺跡出土土偶』通称『縄文のビーナス像』をはじめ、縄文時代の数々の遺物に刻まれている。その中でも縄文のビーナス像は、形なき極孔神を具現化したたぐいまれなものであり、極孔神神学それ自体を体現している、いわば極孔神信仰のロゼッタストーンとも言えるものである」と述べます。
「古代のユーラシア大陸全域で同一の信仰があった」では、極孔神信仰は日本だけのものではないことが指摘されます。斎藤守弘が極孔神の存在にたどり着いたのは、もともとは盃状穴(はいじょうけつ)という先史時代の謎の遺物の研究と、由緒ある神社の向きの研究からでした。盃状穴は、それが何のために作られたのか、明確な結論は出ていません。それが極孔神信仰との関係から、これまで誰も想像しなかったような目的が考えられるとして、羽仁氏は「この盃状穴は世界中で見られる。これが極孔神信仰に関連するとすれば、極孔神信仰もまた、世界中に遍在したことになる」と述べています。
実際、盃状穴以外にも、極孔神信仰の名残は世界中の遺跡の中に、それも古い時代のものに多く残されているとして、羽仁氏は「そうした証拠として斎藤守弘は、ドイツのネブラ・ディスク、テオティワカンの都市遺跡、イギリスのストーンヘンジなどの巨石遺構、そして世界中の神話に残るそれらしき女神の存在を指摘する。つまり極孔神は、東は日本から西はヨーロッパに至るまで、古代のユーラシア大陸全域で同一の信仰があったという壮大なスケールの仮説なのだ」と述べます。
「盃状穴は多重象徴図形」では、そもそもの始まりが古墳であったことが明かされます。かねてより古代史や日本神話に並々ならぬ関心を持っていた斎藤守弘は、古墳の主軸方向の設定には何か特別な意味があったのではないかという疑問を持っていたそうです。そこで若い頃から常に方位磁石を持ち歩き、所用で地方を訪れる際には必ず地元の古墳に足を運んだとか。羽仁氏は、「本来の調査対象であったはずの古墳の主軸についてはばらばらで、斎藤守弘は一定の法則を見つけることができなかった。ところが由緒ある社寺については、参拝者が真北より10度ほど東にずれた方向に向いて拝礼していることが多いのを発見した。ときには西に10度ずれている場合もあったのだが、この真北から10度程度のずれというものがずっと斎藤守弘の頭を悩ませていた。斎藤は謎が解けないまま、この方角をとりあえず『聖方位』と名付けたのだ。もう一つ、この10度ほどのずれを持つ社寺を訪れると、盃状穴を見る確率が高いことにも気付いた」と述べています。 盃状穴とは、石の表面に人工的に刻まれた真円の小さなくぼみのこと。日本だけでなく世界中で確認されており、海外では「カップ・マーク」と呼ばれています。大きさは様々で、直径2~3センチがほとんどですが、小は直径1センチからそれ以下、大きいものは30センチ以上のものもあります。しかも小さなものも、まるでコンパスを用いて描いたかのように正確な円形をしているとして、羽仁氏は「盃状穴を刻んだ目的については、いまだに定説がない謎の遺物なのだ。ただ、再生や不滅のシンボルとして信仰され、女性器と関係があるともいわれているらしい。斎藤守弘によれば日本の場合、盃状穴の真円は、あの世への入り口であり、女性原理であり、そして水との関わりも深い。つまり一つの形状で、いくつもの意味内容をそこに重ねて象徴する、いわば多重象徴図形だという」と述べます。
「極孔神」という言葉は、斎藤守弘夫妻の会話の中から誕生したそうです。この極乱神は、しばらくの間、斎藤守弘にとっても単なる仮説にすぎず、その信仰が実在したという具体的な証拠は見つかりませんでした。しかしあるとき、斎藤守弘はその存在を明確に示す縄文時代の遺物を発見したのです。その遺物こそ平成7年(1995年)に国宝に指定された「茅野市棚畑遺跡出土土偶」、通称「縄文のビーナス像」であったとして、羽仁氏は「このビーナス像に刻まれた様々な文様や縄文時代のほかの遺物を研究する中で、斎藤守弘は『極孔神』を中心とする縄文神学や、この信仰に関連する縄文記号の存在を想定するようになった」と述べるのでした。
第2章「極孔神神学で神名や古代遺跡の謎を解く(羽仁礼)」では、『古事記』の冒頭に登場する「造化三神」の高御産巣日神(タカミムスビノカミ)と神産巣日神(カミムスヒノカミ)が取り上げられます。この両神の名は『日本書紀』では高皇産靈尊と神皇産靈尊と表記されますが、羽仁氏は「二つの神名に『産』という字が使われるのは、いずれの神も出産に関わっているからだ。第二神・高皇産靈尊の神名に『皇』の字が含まれるのは男性月神が出産のイニシアティブをとることを意味する。なぜなら、『皇』の字は前述の通り、『玉光を放射する』という積極性を持つから、自ら働きかけることを意味する。すなわち、男性月神は出産の時刻を決定するというよりも、それ以前に受胎の際、すでに男性月神はその神力を作用させるということである」と述べています。
また、極孔世界と女性の子宮内部とは霊的超空間によってつながっており、そこに外部から神的エネルギーを作用させ、臨月の母体に出産を促すのが男性月神であるとして、羽仁氏は「男性月神はその満ち欠け・再生力により、極孔世界の霊体群に働きかける。そして新旧を問わず、そのときの偶然性により霊体を選別する。その霊体を翼あるヘビが地上に運び、受胎した女性に送り、胎内児に合体させるのだ。つまり二柱の神はいずれも出産という作業に関わるが、高い天井にあって魂を選別するのが『タカミムスビ』であり、地上、つまり下にあって体内児に魂を合体させるのが『カミムスヒ』なのだ」と述べるのでした。
第3章「縄文記号と縄文神聖数の謎を解読する(斎藤守弘)」の「縄文記号と縄文神聖数の発見とその解読」の2「縄文記号は地球上の各地に見つかる」では、縄文記号の解読のために人類学の導入を提唱します。斎藤は、「有名なアルタミラ洞穴(スペイン北部)などの例によっても明らかなごとく、人類ホモ・サピエンスが、何か目に見えない聖なるものを具体的な図像を描くことにより表示しようと初めて試みたのは新人クロマニヨン人の段階である。そして、まさしく縄文記号もまた図像の一種である限り、クロマニョン人の系譜、すなわち旧石器文化の伝統と不可避につながる。しからばアフリカで進化したクロマニヨン人がその後、全地球に移動、分布したのが現代人の祖先であるとするのが、今日の人類進化の常識である。だから当然、わが縄文人の遠いルーツもまたクロマニョン人にはかならない。したがって地球上に広がるクロマニヨン人が、その移動する道筋の各所に、文化の痕跡を残し、その文化の表現である固有の図像群を残したとて、なんら不思議はない」と述べています。
3「人類母権社会の伝統が記紀神話に保持された」では、およそ三柱の最高神がいて、その最高神を表示する記号と、それと関連する記号が何種類かあり、それらが複雑に組み合わさっていると思えばよいとして、斎藤は「まだ文字発明の以前のこと。社会的に神の名を表示しようとすれば、特定の図像や記号に頼るほかなかったのだ。世界の文明と交流のあまりない古代日本の場合、幸いにして縄文時代における最高三柱の神の名称が日本神話として伝承された。すなわち『古事記』における造化三神、天之御中主神、高御産巣日神、神産巣日神であり、『日本書紀』では巻第一、神代上、第一段一書第四が神名表記の仕方をやや異にするとはいえ、同一神を掲げる」と述べています。
これに対し、海外諸文明の神話では後世の父権制社会(すなわち現在の社会)確立の際、大きく歪曲され、再編成されたとして、斎藤は「クロマニヨン人以来、人類史の大部分を占める母権制社会の原神話の形をほとんどとどめていないそれに比べ、日本神話では島国である特殊事情のせいもあってか、人類母権制社会の伝統がほとんど原形のまま記紀神話の形で保持された。これは世界数百の諸神話の中で、女性をもって最高神とする唯一の神話が、日本神話であるという、その卓越した特質に表れている。この特質を尊重し、私はあえて縄文記号と命名し、クロマニヨン記号とか、グローバル・シンボル・システム(略してGSS)とかの名称を避けるゆえんである」と述べます。
6「月讀尊の意味は『月(齢)を讀む男』では、月の満ち欠けの周期性と狩猟動物の出没の規則性に真っ先に気付くのは男性であるとして、斎藤は「だから、獲物を狩る次の時期を定め待機するために、月の満ち欠けの夜間観測を利用する。つまり最初の太陰暦を発明したのは男性としなければならない。おそらく女性は男性の仕留めた獲物を解体・腑分けする作業を分担しただろう。とすると、太陰暦の発明者として、女性の可能性は男性より低いのではないか。太陰暦の発明といっても、実際には今日のようなカレンダーがあったわけではない。誰かが夜ごとの月の観測に専従しなければならない。すなわち月齢を数える役目である。これこそ、日本神話の神統譜に現れる月讀尊ではないか。まさしくその名称の意味は『月(齢)を讀む男』となっている。これほど見事に旧石器時代初期の月齢観測者の伝統を引き継いだ神の名称は、世界のほかの神話には存在しない」と述べています。
8「壮大な七星如意輪曼荼羅を構成した」では、縄文記号を有する仏像は他にもあることが紹介されます。大阪府河内長野市の本尊、国宝如意輪観世音菩薩像です。寺伝によると、観心寺を開基したのは修験道の開祖・役小角。その後各地を巡錫の際、弘法大師が足を止め、祈願して北斗七星を降臨させたといいます。そして再び弘仁6(815)年に来山し、今度は国家安康と衆生除厄祈願のために如意輪観世音菩薩像を刻んで、本尊としました。また唐より請来した秘密具を納めて、寺号を「観心寺」と改めたといいます。斎藤は、「実は弘法大師はそこに『宇宙の中心』を造り上げた。本堂の如意輪観世音を中心として、周囲の境内に星塚を北斗七星の形に配置。本堂、境内を合わせ、そこに壮大な七星如意輪曼荼羅を構成したのである」と述べています。
ちなみに星塚があるのは日本で観心寺のみだとか。この事実について、斎藤は「つまり、この曼荼羅(宇宙)では北斗七星の巡る天の中心に如意輪観音が座することになる。換言すれば、その座こそ縄文以来、極孔神の座する場所であり、それならば如意輪観音の衣服に縄文の神聖対記号が描かれていても何の不思議もない。そしてまた、ここでも野中寺の半跏像と同じく天皇家の影が差すのである。ときの天皇・嵯峨帝は弘法大師を厚く信任。ことに当寺を崇信し、天皇の命令によって国家鎮護などを祈願する社寺の一つと定めた」と推測します。
おそらく、弘法大師は天皇の内意を受け、インド仏教直伝の知識に従い、縄文伝統の極孔神宇宙を仏法化、新たな密教宇宙・七星如意輪曼荼羅を創り上げたのだろうと推測する斎藤は、「だからして、その中心に座するのは、即位のための大嘗祭により、極孔神の現人神となる天皇である。天皇以外に、誰がその位置につけよう。それこそが、野中寺を天皇家の勅願所と定めた理由であろう。かくして縄文の伝統(神道のルーツ)はまず聖徳太子により小規模な仏教化が行われ、次いで弘法大師により全国規模の広範囲な仏教化が行われた。そのことが、これら縄文記号を有す仏像の存在からいまや明らかになってきた。この観点からすれば、観心寺の如意輪観音は長野県茅野市出土、国宝『縄文のビーナス』の仏教化された変身の姿と言えようか」と述べるのでした。
9「装飾古墳を縄文記号で読み解く」では、福島県双葉郡双葉町の国史跡・清戸迫横穴古墳奥壁の彩色壁画が取り上げられ、その絵柄の中央の大きな朱線の渦巻文(外径74センチ)とその左右に一人ずつ大きな人物がいて、さらに下方の5頭の動物(馬、大小の鹿、猪、犬、ほか)および鹿を射る人物らしい小像などで構成されていることが紹介されます。斎藤は、「この彩色画が何を意味するか、多くの考古学専門家がいまだに任意解釈で手こずっている。壁画の右側部分、ひときわ大きい人物は男性であり、中心の極孔神へ巻き込む七重の渦巻文(北斗七星を表す)の端が右腕とつながっている。そこからして、霊魂導師であるようだ」「犬を描くのは狩りの光景でなく、葬送儀礼の一部である犠牲獣であり、この絵柄からすると、たぶん月神に捧げたもので、極孔神には雄地雌鹿が奉納されたのだろう。猪は山神の使い姫であり、山は常に霊魂導師が待機する場所である。まるで判じ物じみているにしても、まだ文字の普及していない古墳社会において、これらこそが万人に通じる古墳時代独特の絵解きコミュニケーション方式なのである」と述べています。
14「前方後円墳は極孔神の胎内から再生するシンボル」では、前方後円墳は縄文記号の円記号(○)と方記号(口)の組み合わせで成立するとし、斎藤は「円記号は縄文人の崇めた至高神・天御中主尊こと極孔神のシンボルであり、方記号は男性表示の鋭三角形と女性表示の逆三角形の融合型、すなわち両者の接合形態をシンボルとする。ずばりいえば、前方後円墳の後円部は縄文の円記号の立体化であり、死者の魂のすみやかな極孔神のもとへの葬送のシンボル、そして、前方部は縄文の男女接合型のシンボルの立体化にほかならない。したがって前方後円墳という命名は間違いである。方形が前ではないし、円形が後ろでもない。実は、前方後円墳とは両者を対等に真横から見るべき存在だった。近年、墳丘を取り巻く埴輪の列が真横で1か所途切れ、そこが後円部への登り口になっているのが見つかったからだ。つまり、古墳上で祭祀を行う人は前方部からでなく、真横のくびれ部のあたりから後円部に上がっていたのだ。では真横から見たその形は何を表すのか。極孔神の胎内から死者の魂がこの世へ生まれ変わり再生する道、生命誕生の場をシンボルとする」と述べています。
第4章「国宝・縄文ビーナスの謎を解く(斎藤守弘)」では、縄文ビーナスの頭のてっぺんの形が特徴的であると、斎藤は「似たような土偶はほかにもいくつか類例があるが、縄文ビーナスほど見事なのは千葉県の余山貝塚出土土偶のほかにない。丸く、平らに作った頭部は『天』をシンボルとする。古代中国『殷』の甲骨文字では人型の上に丸を描くことにより、『天』を表したのだ。『天』の字の起源は紀元前1500年頃らしいから、国宝土偶より1000年以上後のことだが、縄文中期も古代中国も、全世界的な『天を円と観ずる見方』を共有したのだろう。さらに重要なのが、その平坦な頭部に大きな左回りの渦巻きが描かれ、その中心部が指先で押したようにへこんでいることである。これはまさしく盃状穴であり、星空の周極運動によりできる、星の少ない中心の暗黒穴状の部分をシンボルとする。その夜空の中心の暗い穴こそ、死者の霊魂が飛んでいく天上界の入り口である。これは自己を取り巻く環境宇宙と、死後の世界を結びつける人類最初の信仰行為なのだ。唯一神信仰の始まりでもある。私はこの先史時代の人類が考えた最初の最高神を『極孔神』と命名した。盃状穴の研究から理論的に極孔神の存在を予言したが、縄文のビーナスの出現により、はしなくも実証された」と述べます。
第5章「極孔神と日本神話、天照大神の正体を明かす(斎藤守弘)」の1「縄文時代に太陽神崇拝はなかった」では、斎藤は「天照大神は太陽神ではない。なぜこんな社会常識に反するようなことを言うのか。私は決して奇をてらっているのではない。過去半世紀余にわたる縄文時代研究の結果、次のように結論せざるを得なくなったのである。すなわち『縄文時代に太陽神は存在しなかった』と。にもかかわらず、その縄文時代の伝統を引き継ぐわれわれ日本人の最高神が、なぜ縄文時代に存在しなかった太陽神なのか。そんなことはあり得ない。たとえ現在の社会常識に反しようと、あえて私はそう断言する」と述べています。まことに大胆な意見ですね。
3「アマテラスの名前の意味を本名から読み解く」では、一般に太陽神アマテラスとして知られる女神が生まれたときの名は「大日孁貴(オオヒルメノムチ)」であったと主張しています。また、文化勲章を受賞した白川静の『字統』における「靈」の字は「霝」と「女」に従い、レイは請雨の儀礼を示す字で、孁はその巫女を指すそうです。つまり、霝は本来降雨儀礼なのです。斎藤は、「『日』の字が『靈』の置き換えであるとすれば、靈と孁はいずれも降雨を行う巫祝と巫女となる。つまり、晴天に雨雲を呼び、太陽そのものを隠してしまう者の意味になる。そんな神名を持つ神の、どこがいったい太陽神なのか。そもそも上代の母系制社会において、生まれた子供の命名権は父親でなく、母親にあった。だから大日孁貴なる神名を付したのは、広く西日本を宗教的に統治した女王格・伊弉冉尊(いざなみのみこと)であった」と述べています。
伊弉冉尊は自分たちとは反対の父系制下にあった東日本に対立意識を持っていたので、西日本から見て東の太陽の昇るクニに反感を抱き、その反感を後継者となる長女の名前に反映させました。その他に西日本に多かった干ばつの雨乞いも、もちろん欠かせぬ役目だったと、斎藤は推測します。また、斎藤は「靈(霊)の文字には、神霊の降下を求める意味もある。つまり、手っ取り早くいえば、恐山(青森県むつ市)の巫女(イタコ)のようなもの。死者の霊を呼び出し、自分の身に依りつかせ、死者の言葉を取り次ぐのだが、依頼者から見れば、その降下した霊は自分の親族、亡き父や母、つまり祖霊であることが多い。これは上代においては祖霊祭祀そのものだった」と述べます。
第6章「極孔神から天皇制の起源をめぐる謎を解く(斎藤守弘)」の4「天皇霊が太陽神でないことは大嘗祭からもわかる」では、昭和天皇御即位の大嘗祭に参列した民俗学者・折口信夫の著書『大嘗祭の本義』によれば、天皇が一度真床追食にくるまり、それを取り除いたとき天皇霊がその身体に入り込むことで天皇になることが紹介されます。斎藤は、「しかし、その天皇霊が太陽神であるならば、大嘗祭の儀式はすべて陽の高い昼間に執行されてしかるべきだろう。それなのに、悠紀殿で行われる『夕の儀』はもう夜半近い亥の刻(午後10時)から始められるのだ。太陽神の祭祀をなぜ夜中に行うのか。いかに祭祀であろうとも不合理である。そうした不合理に陥るのは大嘗祭の儀式に対する、これまでの理解が間違っていたからと考えるほかない。では天皇霊はどこから飛来するのか。天皇霊とは、国宝土偶の頭頂にシンボルされた極孔神そのものである。これまでそうした至高神の存在が、何千年も忘却されたままだったために、研究者の誰一人気付かなかった」と述べています。
第7章「世界の神話・遺跡に残る極孔神信仰(斎藤守弘)」の1「縄文人の他界観と世界遺産」では、先史時代には、地球上の各地方が共通して同一の他界観を有していたことが紹介されます。その他界観のルーツはさらに新石器人の狩猟採集時代にさかのぼり、一万数千年前、人類の脳構造に共通して自己意識が発生した。同時に、人類は初めて自己の死を自覚したとして、斎藤は「それまでの無自覚状態を脱し、自己の霊魂観念を獲得し、死後における霊魂の行く末を考えるようになったのである。『自分のことを考える自分とはいったい何者か。目に見えないけれど、この身体の内にそんな〈見えない何か〉が潜んでいるのは間違いない』そう考えたところで、霊魂観念が芽生える。では、その霊魂は死後どうなるのか。肉体から遊離した霊魂は、目に見えないくらい希薄であり、それだけに軽い。したがって、次第に人体の形を失い、丸まって風船のように上昇する」と述べています。
日本では上代からそれを「人魂」と呼びました。西欧では、特に心霊学の面で、アストラル・ボディと名付けられた。アストラルとはアストロノミー(天文学)の語があるように、「星体」の意。超常現象研究家という立場から心霊学にも詳しい斎藤は、「人体の60兆の細胞が機能を止め、死滅したあと、そこに重なっていたアストラル・ボディはどうなるか。そこから先は各国、各宗教の学派により解釈が異なるけれども、歴史的に価値観の定まらぬ先史時代には、地球上各地の人類が期せずして、同時多発的に同じ観念・同じ結論に落ち着いた。同一の脳構造のもと、同一の満天の星空を眺めて、同一の認知観念(他界観)に達したのだ」と述べます。
頭上をおおう降るような満天の星空。地球の自転(右回り、時計の針の方向)と相対的に左回転するその星空の回転の中心となる場所は、北極星の他に星が少ない。回転する満天の星空の中で、そこだけ動かぬ暗黒のトンネル口のように見えるとして、斎藤は「1万年以上さかのぼる先史人たちは、そうした同一生活環境にあった。頭上の満天の星空と、そこを日ごと姿を変えて横切る天体・お月様の姿の変化から、自己の霊魂の将来像について、同じ認知的結論に落ち着いた。すなわち死後の霊魂の行く末について、同一の脳構造のもと、同一の結論に至った。自己の霊魂の将来について、先史人の出した結論は、その後の人類の歴史の歩みに絶大な影響を及ぼした。その結論は、紀元前、地球上の各地に壮大な巨石文化を生み出す強力な心理的動因となった」と述べるのでした。
5「古代エジプトの土偶や木偶に刻まれた女神」では、エジプトの最初の天となった女神ヌトが極孔神の名残と思われると書かれています。斎藤は、「いまのアカデミズムでは先史時代の女性を大地母神と呼称し、大地の豊穣をシンボルとする神と見なすが、それは農業が開始されて以後のことである。それ以前には、女性は天であり、極孔神こそが人類最初の神であった。その太古の痕跡が、先史エジプト神話には損なわれることなく原始の宇宙構造として、奇跡的にも残存したのである」と述べています。極孔神の名残として、エジプトが女神ヌトなら、メソポタミアは女神アルルです。女神アルルとは、古代バビロニアの英雄物語『ギルガメッシュ叙事詩』の主人公ギルガメッシュの無二の親友エンキドゥを粘土から作った女神として知られます。6「古代メソポタミアのアナーヒターと天鈿女」で、斎藤は「この女神アルルこそメソポタミア極孔神のわずかに面影をとどめる女神ではないか」と推測しています。
7「古代インドの隠れ極孔神デーヴィー」では、斎藤は「ヒンドゥー教に極孔神の面影を残す大女神はいないかといえば、これが奇跡的に生き残っていた。もちろん、本来の形を変えていて、それとわかりにくいが、女神デーヴィーである」と述べています。8「黄河文明にも先駆大女神がいた」では、最初の中国人女媧、すなわち伝説の女媧こそ、中国太古の極孔神であろうと見当がつくとして、斎藤は「『媧』の字を漢字分析すると、旁である咼(媧の右の部分)の意味は死者が残した骨に祈り、死霊を操ることである。死霊を操るとは、死者の魂をつつがなく極孔神の世界、すなわち、死後の天上界へ送るためにひたすら祈ることだ。そのようにして極孔神である女媧はその最高神力により、生と死を司る存在であった。中国にもまぎれもなく極孔神が存在したのだ」と述べるのでした。
「編者解説」では、かつて斎藤守弘が発見したという極孔神信仰について、羽仁礼氏は「極孔神仮説がどうなったのか、個人的には非常に気がかりであったが、2019年になって、斎藤守弘氏が2001年9月から2013年9月まで、神奈川県歴史研究会において、極孔神関連で14回の講演を行っていたことが判明し、遺族の方からその講演録を入手することができた。日本の超常研究界にあれだけ大きな足跡を残した人物の遺作である。これは何としても世に問うべきだと考えていろいろと可能性を探ったところ、このたび何とか刊行の運びとなった。本書は、前述の講演録の内容を再編集したものである(そのため、例を挙げる場合、神奈川県の例が多い)。講演録そのものは、斎藤守弘氏が口頭で語ったそのままが記録されているから、ときに話が飛躍したり、あまり関係のない話題が挿入されたりする部分もあったが、読みやすさを考えて、14回の講演から同じテーマについて語る部分をまとめ、重複する内容を削るなどして整理し、章立てをした」と述べます。
さて、本書に書かれている内容は非常に興味深いものではありますが、根拠が不明確・不十分な箇所も見られました。たとえば、「極孔神」の前提について本書では極孔神が、ある程度の過去から現在までの北極星周辺に明るい星がなく、そこを長時間観察し続けた場合、カメラで長時間露光した時のように暗くなることから北極星周辺を星空の孔と見なし、ここから極孔神の観念が発達したと述べています。確かにこれら北極星の周辺は比較的暗い星が多くはありますが、光害の激しい現代ならともかく光源が存在しない先史時代において、ここが孔と認識される程の暗い空間であったのか、また、同時代には現在と星の動きや配置が異なったと考えられる(例えば5000年前の縄文時代前期頃には北極星と北斗七星が現在よりも近い距離にあったなど)ため、先史時代に現代ほど整った孔を星空に見出せるかは疑問が残ります。
また、盃状穴についてですが、発見もしくは形成された時間的・空間的や、穴の直径・深さや両者の比率などの形質的な内容に差があるものを一括で同じ意味を有していると断定することは難しいのではないでしょうか。特に当該事項につきましては「丸い穴をあける」だけと再現が容易であるため、現在、盃状穴の学術的な研究はほとんど行なわれていない状況を踏まえると、これを資料として用いるためには、まず事例の集成と分析が必要かと思われます。縄文記号についても、著者が例示しているもの○・□・△・×や渦巻きなどはいずれも単純な図形とその組み合わせであり、芸術的なレベルが高くない文明・文化圏でも再現可能と思われ、意匠上も偶然の一致の可能性を否定できません。また、土器であれば制作者のサイン等の可能性も想定できる上、こちらも資料の集成・研究が進んでおらず、現段階でこれによる意味の判読は困難と思われます。
観心寺の寺伝を史実と捉えている点も違和感があります。社伝や寺伝はあくまで伝承であり、これを歴史事実として捉えるには相応の論拠が必要になります。特に、観心寺の寺伝には役小角や弘法大師といった後世の仮託が多い人々が登場するため、より慎重な論証が必要です。さらに、「大日孁貴」の解説についてですが、漢字の字義をもってオオヒルメノムチが太陽神でないことを解説していますが、日本の神を漢字の字義のみで解説することには違和感をおぼえます。またヒと霊、メの孁をもって降雨を願う巫女と解釈していますが、ヒ=日、ル=「~の」の古語、メ=孁=巫女的存在とする従来の解釈の問題点を具体的に指摘できておらず、批判の内容に不備があると思われます。
折口信夫の「真床追衾」論に基づいた天皇と極孔神の説明も気になりました。真床追衾を介した天皇霊と天皇の関係については現状では実証する手段がなく、今日でも議論がわかれている箇所です。当該議論においては折口論を肯定・否定のどちらにするにせよ、「折口がこう述べているので~」という記述は、今日では不十分ですね。
本書には、明らかな誤解も見られます。
「由緒ある社寺については、参拝者が真北より10度ほど東にずれた方向に向いて拝礼している」という記述がありますが、「由緒ある」という基準が不明確であるとともに、神社の社殿でいえば時代的変遷による社殿の変化や地理的な背景を考慮すると成立しないのではないかと思われます。例えば、日本有数の「由緒あるお宮」である出雲大社・鹿島神宮・宗像大社辺津宮の社殿は全く別の方角を向いており、このため拝礼の方角もそれぞれ異なります。
『日本書紀』第一巻一書第四にみえる「タカミムスヒ・カミムスヒ」の解説も疑問を感じました。当該箇所では「皇」をもとに高皇産霊尊を男神であると述べていますが、直後の箇所では(現存するいずれの写本でも)女神とされるカミムスヒも「神皇産霊尊」と表記されており、この解説は成立しません。なお同箇所を「神明表記の仕方をやや異にする」と述べているページもありますが、意図的にこの箇所を無視した可能性があります。月読尊の神名解説にしても、月読尊は一般的に男神と考えられていますが、その神名にはツキ(月齢)をヨム(数える)といった意味しかなく、神名が男神であること表わしているという表現は明らかな誤りです。
前方後円墳の成り立ちと意味についてですが、本書では縄文記号である□と○をもとに解説していますが、前方後円墳が円形墳丘墓が最初に存在し、それに対して架けた橋が変形して前方部になったという成立過程を考えれば、前述の図形をもって前方後円墳を理解することは難しいのではないでしょうか。特に前方部を後円部とひとつなぎの意味を持っていたのであれば円形墳丘墓に隣接して方墳状の構造物を建設したのではないかとも考えられます。また、古墳への登り口については、前方と後円の接続部ではなくほとんどの前方後円墳で前方部の後円部と逆側の端部のいずれかに設けられており、同接続部からの登攀は傾斜の関係から困難であったと考えられます。
天照大神が太陽神ではない=古代日本に太陽神信仰が存在しなかったという大胆な仮説はナンセンスです。天照大神の成立に関しては、以前より自然神をそのまま日本書紀等の伝承に反映したものではなく、日本各地の様々な太陽神に関する伝承等が皇祖神でもある天照大神のもとに統一されていったとの説が有力であり、仮に著者が言うように天照大神が太陽神でなかったとしても、それが即太陽への信仰がなかったことにはつながりません。
太陽神の祭祀が行われるのは昼間であるべきというのは、柳田國男の「祭のさまざま」にある「神の降臨はたゞの人の眼には見えず、殊に其夜中の暗闇のうちに、御出でになるといふ祭も少なくは無い。それを日中の照り輝く路を、渡御なされるやうにしたのは中古からの変化で、その為に特に道中を花やかにするやうな、動く舞台といふものが考へ出されたのだつた。」や、同じく柳田の著書『日本の祭』に「我々の祭りの日もその日の境、すなわち今なら前日という日の夕御饌から始めて、次の朝御饌をもって完成したのであった。…つまりこの夕から朝までの間の一夜が、我々の祭りの大切な部分であって、主として屋内において、庭には庭燎を焚いて奉仕せられたのであった。」とあります。柳田の指摘は民俗学の視点からのものであり、どの時代まで遡れるかは検討の余地がありますが、少なくとも祭祀が夜間に行われることは祭神の如何を問わず一般的なことであることは理解できます。よって、天照大神が太陽神でないと結論づけることは論理の飛躍があると思われます。
 皇産霊神社の瀬津神職と
皇産霊神社の瀬津神職と
以上の考察は、國學院大學で神道学や日本民俗学を学んだ皇産霊神社の瀬津隆彦神職の意見を参考にさせていただきました。ここで指摘した根拠が不明確・不十分な箇所、あるいは明らかな誤解を見ると、本書はいわゆる「トンデモ本」ではないのかと思う人もいるかもしれません。しかし、著者は超常現象の懐疑的調査のための会である「ASIOS」の創設会員であり、その著者が注目した仮説ですから、本書の内容はあくまでも真面目であると思います。けっして、「トンデモ本」ではありません。
また、じつは「トンデモ本」というのも馬鹿にしたものではありません。一条真也の読書館『下山の思想』で紹介した五木寛之氏の本によれば、なんと、国民作家として有名な著者は、「トンデモ本」の愛読者であるというのです! 同書の「夏の夜の小さな娯しみ」というエッセイに「寝苦しい夏の夜を、どうすごすか。私たち旧世代は、活字を読む。DVDとか、テレビを見ていると、眠気が訪れてこないのである。こういう夜に、私がもっとも愛用する本は、いわゆる『トンデモ本』と称される一連の出版物だ。『トンデモ本』というのは、現実世界の反面鏡だ。黒白逆転し、画像がデフォルメされているところがおもしろい。ケネディ暗殺の真相やら、9・11の陰謀やら、マリリン・モンローの死の推理やら、外国ネタは数々ある。フリーメイソンをはじめ、歴史を動かす秘密結社の話も楽しい。キリスト教に対する仏教の影響や、その反対の仏教へのキリスト教の影響などを述べた本もある」と書いています。
また、本書の内容のような古代史についても、五木氏は「日本の古代史は、『トンデモ本』の宝庫だ。旧満州国に関する本もおもしろい。日本国が遠からずギリシャ化する、という本もよく目にする。こういう本を『トンデモ本』と呼んで、ひとくくりにするのは間違いかもしれない。なかなか説得力があり、それぞれ一面の真実が行間に埋まっているからだ。書き手の筆力と、想像力がすぐれていると、じつにおもしろい。いわゆるジャーナリズムや世論などと、まったく正反対の主張がくりひろげられるからである。日本国は大借金国である、という本もあり、いやまったく借金などないんだ、という説もある。夏のむし暑い夜には、この手の本が一番だろう」と述べます。
天下の五木寛之が「トンデモ本」を愛読していたとは驚きです。わたしも嫌いなほうではなくて、中高生の頃などは大陸書房などから出てきた超文明系の「トンデモ本」を貪り読んでいたクチですが、社会人になってからはなるべく読まないように努力してきました。「トンデモ本」はあまりにも面白いので、現実の解釈に悪影響を与えるのではないかと思ったからです。また、フリーメーソンに代表される陰謀論の類が多く、社会的にも非常に有害であると思ったからです。詳しくは、一条真也の読書館『陰謀論にダマされるな!』をお読み下さい。
そして五木氏は、「真実は必ず一種の怪しさを漂わせて世にあらわれる」と喝破し、「堂々たる真実などはない。『トンデモ本』と称される本のなかに、大事なことが隠されている。それがおもしろくて私たちは『トンデモ本』を手にするのだ」と述べるのでした。それを踏まえた上で、本書『極孔神仮説で神話や遺跡の謎が解ける』は、先述したように「トンデモ本」ではないことを力説したいと思います。どんな新説でも最初は「トンデモ」扱いされることもありますが、それが認められて歴史を塗り変えることも珍しくありません。何より、本書に書かれていることにはロマンがあります。あらゆる神話や遺跡の謎が解ける統一仮説とは、なんと素晴らしいロマンでしょうか! これはもう、あまりにもあまりにも、ロマンティックです!
