- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.07.24
『プーチンの野望』佐藤優著(潮新書)を読みました。著者は作家で、元外務省主任分析官です。特にロシア問題に詳しいことで知られており、ロシアのウクライナ侵攻以来、著者の最新刊が出るのを心待ちにしていました。そして、ようやく6月3日に本書が出版されましたが、内容は著者が論壇デビューした2005年から発表したプーチン論を再編集し、新たにウクライナ情勢を加えて大幅に加筆・修正したものでした。
 アマゾン「出版社より」
アマゾン「出版社より」
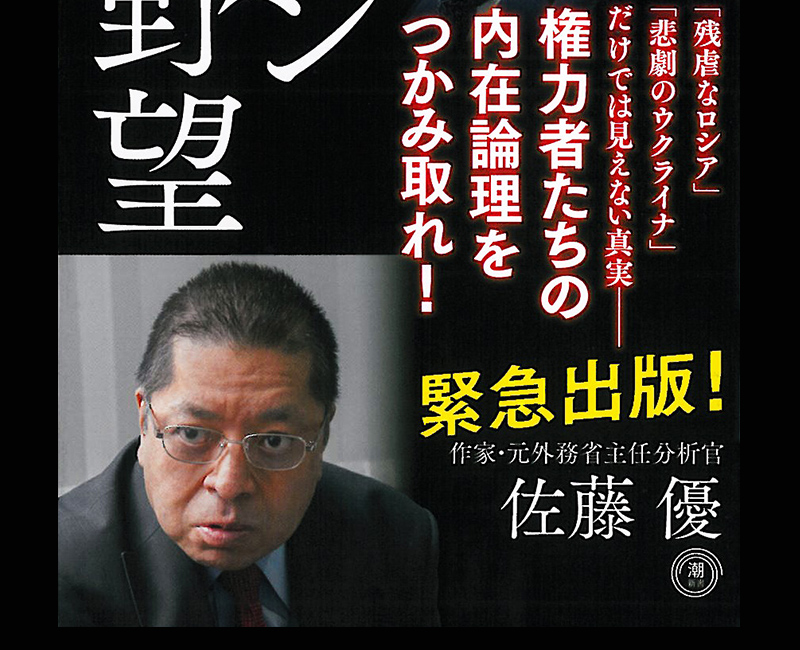 本書のカバー表紙
本書のカバー表紙
本書のカバーには、プーチン大統領と著者の顔写真が使われ、「『残虐なロシア』『悲劇のウクライナ』だけでは見えない真実――権力者たちの内在理論をつかみ取れ!」「緊急出版!」と書かれています。カバー裏には、「『死神がやってきた』プーチンとの最初の出会い」として、「インテリジェンス(諜報)の世界で、お人好しは生き残っていくことはできない。だからインテリジェンス・オフィサー(諜報機関員)は、職業的におのずと陰険さが身につく。ただし、プーチンのように、陰険さが後光を発するほど強い例は珍しい。『プレジデントホテル』で死神の姿を見たときから、私のプーチン・ウォッチングが始まった。(本文より)」と書かれています。
 本書のカバー裏表紙
本書のカバー裏表紙
アマゾンの「内容紹介」には、「独裁者・プーチンを徹底解明! その内在的論理を理解しなければ、ウクライナ侵攻を理解することはできない。外務官僚時代、大統領となる前の若き日のプーチンにも出会った著者だからこそ論及できる、プーチンの行動と思想」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第1章 仮面のプーチン
第2章 プーチン 独裁者への系譜
第3章 20年独裁政権構想と
ユーラシア主義
第4章 北方領土問題
第5章 クリミア併合
第6章 ウクライナ侵攻
終章 平和への道程
「初出一覧」
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書き出しています。
「2022年2月24日は、歴史の転換点になった。この日、ロシアがウクライナに軍事侵攻した。ロシアは『特別軍事行動』と呼んでいるが、客観的に見て戦争だ。ロシアの行為はウクライナの主権と領土の一体性を毀損するもので、既存の国際法に違反する。ヨーロッパにおいて第2次世界大戦後、最大規模の戦争が起きたことに欧米と日本の政府も国民も驚愕するとともに、ロシアに対する怒りの感情の渦に巻き込まれている」
このような状況で、ロシアのプーチン大統領の悪魔化が進んでおり、他方、ロシアにおいてはウクライナのゼレンスキー大統領とアメリカのバイデン大統領に対する悪魔化が進んでいるとして、著者は「私は大学と大学院で神学を学び、社会に出てからも(当初は外交官、その後、作家)キリスト教の研究を続けている。実は他者を悪魔化する発想の背景にはキリスト教の影響があることが私にはよく見える。人間は罪から免れない。罪が形をとると悪になる。悪を人格的に体現したものが悪魔なのである。この思考を採ると、一旦、悪魔のレッテルを貼られた者は、打倒するするしかないという結論になる」と述べています。
こういう思考を鈍化させると核兵器を使用してでも悪魔(敵国)を殲滅しなくてはならないということになりかねません。しかし、そのような発想は、イエス・キリストの教えに反すると考えるという著者は、「イエスは、『あなたがたも聞いているとおり、「隣人を愛し、敵を憎め」と言われている。しかし、私は言っておく。敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい』(「マタイによる福音書」5章43~44節)と述べた。憎しみは人の目を曇らせる。敵を愛する気持ちをもつことで、われわれが敵と目している人が何を考えているかを理解する可能性が生まれる」と述べています。
著者によれば、この点で仏教から学ぶべきことが多いといいます。仏教ではすべての人間に仏性があると考え、当然、国家指導者にも仏性があるとして、「法華経によると人間の生命の状態(境涯)は、変化する。ある国家指導者の生命の状態が現在、地獄界や修羅界にあるとしても、それが仏界に到達することは可能なのである。戦争の興奮から距離を置いて、プーチンのそしてロシア人の内在的論理をとらえることが本書の目的だ」と述べます。また、「本書は、私が職業作家になった05年以降、さまざまな媒体に発表したプーチン論を再編集し、加除修正を加えたものだ。この機会に昔の原稿を読み直してみたが、基本線について変更することはなかった」と述べます。
戦争の熱気に包まれて、われわれは無意識のうちに国家と自己を一体化しようとしてしまうとして、著者は「その結果、戦争に苦しむ民衆の姿が見えなくなってしまう」といいます。創価学会の「精神の正史」である池田大作著『人間革命』第1巻(聖教出版社)には「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない。だが、その戦争はまだ、つづいていた。愚かな指導者たちに、率いられた国民もまた、まことに哀れである」と書かれていることが紹介されます。
第1章「仮面のプーチン」の「独裁者プーチンとジャーナリストの対話」では、プーチンを非難してきた著名なジャーナリストの1人であるマーシャ・ゲッセンが登場します。彼女はユダヤ系ですが、プーチンは、ゲッセンが彼を独裁者だと激しく非難し、不正蓄財やジャーナリスト暗殺疑惑について書いていることを知らなかったことを紹介し、著者は「ちなみにエリツィンは、新聞を読まず、テレビを観なかった。自分を非難する不愉快な情報を知りたくなかったからだ。ニュースについては、報道担当の大統領補佐官がA4版3~4枚にまとめたサマリー(要約)を毎朝渡していた。私がこの補佐官から直接聞いた話だが、『大統領は良いニュースだけを知りたがる。悪い話については、それへの対策を記しておかないと機嫌が悪くなるので、この作業には神経を使う』ということだった。プーチンもエリツィンと同じような状態になっていたのだろう」と述べています。
第2章「プーチン 独裁者への系譜」の「インテリジェンス・オフィサーの掟」では、ロシア人は自分の甲羅に合わせて相手を見るとして、著者は「私は東京地方検察庁特別捜査部に逮捕され、有罪が確定し、外務公務員(外交官)としての身分を失った経緯がある。だから今は外務省とはまったく関係ない。民間人の作家として発信しているにもかかわらず、ロシアの大統領府、首相府の関係者はそう受け止めない。『佐藤は日本版の特別予備役のようなものだ。日本政府、特に首相官邸の意向を受けて発信をしているに違いない』と勘違いしている。『日本は、ロシアとは国家制度や政治文化が異なる。そもそも独立した対外インテリジェンス機関も存在しない』と説明するのだが、ロシア人は『いや佐藤さん、表面上の機構が問題ではなく、実質的な機能が重要です』と言って、私の説明を額面通りに受け取らない。実に迷惑な話だ。もっとも、ロシア側の誤解によって、私のところにモスクワからときどき機微に触れる情報が入ってくる。これはロシア情勢を分析し、評価するうえでとても役に立つ」と述べます。
「中堅官僚がトップまで成り上がれた理由」では、プーチンが38歳でKGB第一総局を退職したときの役職は中佐だったことに言及し、著者は「この年齢で中佐ということは、KGBにおけるプーチンの出世が遅いほうだという事実を意味する。ロシア(旧ソ連を含む)では、警察、SVR、FSBなども軍隊と同じ階級組織になっている。モスクワの路上で交通整理をしている警察官には、大佐がいる(交通警察は、違反や事故のもみ消しによって給与以上の賄賂を得ることができる。だから大佐級の幹部が路上勤務を希望するという要因もある)。KGB退職時のプーチンの階級は、交通整理を行っている同年代の警官よりも低かった。にもかかわらず、中堅官僚に過ぎなかったプーチンは10年強で出世街道を駆けのぼり、ロシアのトップになった。端的に言うと、プーチンは小さな出世や利権にはとらわれなかった。そのことが、大統領という大きな出世をつかむきっかけになったのだ」と述べます。
「絶対に人を裏切らないプーチンの生真面目さ」では、エリツィンがプーチンの生真面目さを評価したことを紹介。「この男ならば俺を裏切ることはない」という印象をエリツィンは持ったとして、著者は「1998年5月、プーチンは大統領府第一副長官に昇進する。このポストは、政府ならば第一副首相級に当たる。その先のポストは、首相か大統領府長官しかない。当時、エリツィンは後継者を探していた。ロシア憲法では、大統領に次ぐポストは首相だ。キリエンコ(98年3~8月在任)、チェルノムィルジン(98年8~9月在任)、プリマコフ(98年9月~99年5月在任)、ステパーシン(99年5~8月在任)が首相に任命されたが、いずれも後継大統領には不適任とエリツィンが考え、次々と解任された」と述べます。
「カリスマ性と指導力」では、著者は「2000年3月の大統領選挙でプーチンが当選した直後、私はモスクワに出張し、政治エリートと踏み込んだ意見交換をした。このときのブルブリス連邦院(上院)議員の見方が興味深かった。ブルブリスはエリツィン政権初期の知恵袋であり、ソ連崩壊のシナリオを描いた人物だ」と述べます。そのブルブリスが語るところによれば、エリツィン時代の寡占資本家や「家族」と比較すると、富や権力が集中していないそうです。寡占資本家は法による縛りを嫌い、エリツィンに影響力を行使して自らに有利な大統領令や政府命令を策定させ、利権を追求してきました。「法の独裁」を掲げるプーチン政権下では、このような恣意的な支配ができなくなったとして、著者は「プーチンの周辺の政治エリートは、議会に対するロビー活動を通じて、自らに有利な法律の採択を企てる。ただし、ひとたび成立した法律には従う。その結果、ロシアの社会が安定した」と述べるのでした。
「ツァーリ=皇帝としての自覚」では、大統領に就任し1年半を過ぎてからプーチンの自己意識にさらに変化が生じたとして、著者は「3~4年前まで中堅官僚に過ぎなかった自分が、ロシア国家の元首になったのは、エリツィンから権力を譲り受けたとか、選挙によって国民から選ばれたということを超える天命であると思うようになった。ロシア正教会を重視し始めたのも、自らの権力が神によって与えられたという意識が芽生えてきたからだ。国家の指導者になるためには、超越的な使命を自らがもっているという自己意識が不可欠になる。同時にロシアの場合、こういう自己意識をもつ指導者は、皇帝に近い発想をもつことになる」と述べています。
「インテリジェンス・オフィサーとしてのプーチン」では、プーチンはKGB第一総局の出身であると指摘します。プーチンの政治家としての行動様式には、インテリジェンス・オフィサーがもついくつかの特徴があるとして、著者は「最も重要なのは、独自の方式でシグナルを出すことだ。インテリジェンス・オフィサーは言葉を大切にする。無駄なことは言わない。プーチンにもその特徴がある。このことを私に初めて指摘したのもブルブリスだったそうです。エリツィンとプーチンの政治スタイルの相違について著者が尋ねると、ブルブリスは「プーチンが、1970年代にKGBで基礎教育を受け、実践を積んだインテリジェンス・オフィサーであることを忘れてはならない。プーチンは、さまざまなルートで、情報の入手に努める。しかし、それぞれの情報に対する評価について、いちいちコメントしない。だから側近たちは、プーチンが何を考えているかわからずにやきもきする。しかし、プーチンは真剣に考えている。そして、発言するときはプーチンはすでに基本方針を決めている。自分が何を考えているかがわかるようにシグナルを出す。SVR(ロシア対外諜報庁)と相手国のインテリジェンス機関が、信頼できる関係をもっているときは、このチャンネルを用いる。それに加えてマスメディアを通じてシグナルを出すこともある」と答えたといいます。
「プーチンから学ぶ具体的な5つの流儀」では、KGBの中堅官僚に過ぎなかったプーチンが独裁者に駆け上がった5つの理由として、その1「タイミングを待つ」、その2「人間関係を大切にする」、その3「サードパーティー(第三者)・ルールを守る」、その4「無責任な発言をしない」、その5「天命を信じる」が挙げられています。その中でも、「天命を信じる」について、著者は「プーチンは信仰心が厚い。プーチンの別荘が失火で全焼したことがある。別荘の壁に十字架の首飾りを掛けていたが、不思議なことにこの十字架の周囲の壁は焼けず、十字架は残った。プーチンはこの十字架を大切にしているというエピソードを時々口にする。また、ロシア正教会との関係を重視し、個人的にも親しい神父が何人かいる」と述べます。
ちなみに著者は外交官時代、仕事でSVRの幹部と宗教や神について話し合ったことが何度もあるとか。SVR幹部は、KGB時代にマルクス・レーニン主義に基づく科学的無神論の教育を受けていたにもかかわらず、例外なく神を信じていたとして、著者は「ソ連崩壊前後、ほんの小さな要因が、出世の明暗だけでなく文字通り生死を分けることになった。そういう強烈な経験をしているので、彼らは人知を超えた天命を信じるようになったのだ。天命を信じる人は、実力を最大限に発揮できる」と述べるのでした。
第3章「20年独裁政権構想とユーラシア主義」の「スターリンの正統な後継者」では、ある時期、著者は「ロシアで政局を見るコツは、男と男の愛と嫉妬である」ということに気づいたとして、「エリツィン大統領を本気で愛した政治家は、私が見るところでもブルブリス、ソスコベッツ(元第一副首相)、ガイダル(元首相代行)、キリエンコ(元首相)などたくさんいる。だが、これらの政治家の愛に対する見返りは、ほとんどなかった。結局エリツィンは、自分に愛情を注いだ政治家を全員退け、家族だけの閉鎖的な世界をつくった。後継には、愛情物語とは無縁のプーチンを指名した。大統領になった後、エリツィンは誰のことも愛さなくなったが、他人の愛は受け容れた。これに比べてプーチンは他人を愛することも、他人の愛を受け容れることもない。ロシアの帝王学では、最高権力者は愛することも愛を受け容れることも禁止されている。プーチンは帝王学を学んでいないが、エリツィン周辺の男と男の愛と嫉妬を嫌というほど見る過程で『自習』したのであろう。その結果、他人を愛さず、誰の愛も受け容れなかったスターリンの正統な後継者になった」と述べています。
「日露の首相が同日に辞任 2007年9月の政変」では、世界史でもきわめて稀な出来事でしょうが、2007年9月12日、日本とロシアで安倍晋三首相、ミハイル・フラトコフ首相が同時に辞意表明をしたことに触れ、著者は「もちろん、その政治的意味合いには違いもある。日本の場合、首相は文字通り最高権力者であるが、ロシアの場合、最高権力者は大統領であり、首相は行政府の長に過ぎない。要するに、大統領から『お前、これをやれ!』と言われたら、『はい、わかりました』と言って、執行しなくてはならない立場だ」と述べます。
続けて、著者は「07年の政変の細かい違いについて述べれば、プーチン大統領はフラトコフ首相の辞任を直ちに受け入れ、内閣を総辞職させ、9月12日中にヴィクトル・ズプコフ(金融監視庁長官)を後任首相に指名した。9月14日、国家院(下院)が大統領によるズプコフ首相の指名を承認し、正式に首相に就任した。ズプコフは、08年3月の大統領選挙を円滑に行うための『選挙管理内閣の長』として首相に指名された。この間、政局の空白はまったくない。すべてがプーチン大統領の描いたシナリオ通りに進められたのだ」と述べています。
「『民族の理念』の探求」では、プーチンに2つの魂があることが指摘されます。著者は、「これは、インテリジェンス(諜報)の世界で生きてきた人間に特有の傾向である。まず、冷徹な分析家として、民族という意識は、近代に入ってからの流行現象に過ぎず、特に後発資本主義国であるロシアにおいては百数十年の歴史しかもっていないことをプーチンは十分理解している。同時に政治家として、ロシアを統合し、国民を動員するためには、政治的変化や体制転換を経ても変わることのない永続する『民族の理念』なるものを称揚することが効果をあげることをよく理解している。プーチンが追求する『民族の理念』とは、表面上は19世紀のロマン主義的言説のように見えるが、それとは本質的に異なる。民族を超克しようとしたソ連の実験は失敗した。その歴史を踏まえ、民族主義を刺激すると、チェチェンの分離独立運動のようにロシア連邦を内側から破壊する危険性をはらんでいることをプーチンは十分認識する。所与の条件では、民族以外に大衆を動員する『物語』を構築する理念を見出すことはできない。従って『民族の理念』として、ロシア正教や文化理論よりも、非ロシア人や非正教徒を包摂しやすい地政学をプーチンは重視する。一種の消極的選択として、プーチンは『民族の理念』による統治を追求しているのだ」と述べるのでした。
「ロシア『中興の祖』としての自画像」では、ロシアに対して帝国主義的野心をもつアメリカやヨーロッパ、さらに巨大な多国籍企業からロシア国家とロシア国民を防衛する基盤を強化するために、自分には歴史によって与えられた使命があるとして、著者は「今もなお、プーチンはそう確信しているのであろう。21世紀のロシア国家とロシア国民を安定的に発展させる『民族の理念』を構築した『中興の祖』となるという課題をプーチンは自らに課しているのだと、私は考えている」と述べています。
「『一般の物差しで測ることができないロシア』では、ロシアという国家を成り立たせているのは信仰であると指摘し、著者は「この信仰は、国家指導者の人格に体現される。ロシア的伝統で、国家指導者に対する信仰が生じるのは、ごく自然なことなのだ。もっとも、ロシア人の大統領に対する信仰は、新宗教の教祖に対する崇拝とは異なる。ロシア人の内輪では、大統領に対する辛辣な批判や、誹謗中傷を平気でする。しかし、外国人が批判に加わると、それまで激しく大統領を非難していたロシア人が『お前はわが国の大統領を侮辱するのか』と食ってかかってくる。日本人でも、家族の間では父親の悪口を言っていても、他人がそれに同調すると嫌な思いをする。これと同じ感覚を、ロシア人 は大統領に対して無意識のうちにもっているのだ」と述べます。
第4章「北方領土問題」の「第1次チェチェン戦争とハサブユルト合意」では、1994年12月に第1次チェチェン戦争が始まった時点では、チェチェンがロシア連邦からの分離独立を求める運動だったとして、著者は「96年8月のハサブユルト合意で、5年間の停戦合意がなされる。さらに『ロシアは、チェチェンは独立国であると主張していることに異議を唱えない』『ロシアが「チェチェンはロシア連邦の構成員である」と主張していることに、チェチェンは異議を唱えない』という玉主色の合意がなされた。実質的にチェチェンの勝利である」と述べます。
さらに、著者は「チェチェンを実効支配しているのは、独立派だった。現状を維持することを認めたハサブユルト合意によって、ロシアが実態を追認した。しかし、その後チェチェンでは静かに変化が生じた。反ロシアという形で団結していたチェチェン人の間で、民族独立を主張する独立派とイスラーム世界帝国を建設しようとする原理主義者の間で対立が生じたのだ」とも述べています。
チェチェン人は、伝統的に祖先崇拝、聖者崇拝を重視するが、原理主義者はそれを認めないとして、著者は「チェチェン人内部で武装対立が起き、死傷者が発生するようになった。過去にロシア軍と戦った独立派の有力者アフマド・カディロフたちが、『原理主義者よりはロシア人のほうがまだましだ』とモスクワに接近した。カディロフはチェチェン共和国首長に就任したが、2004年5月9日、チェチェンの首都グロズヌィで行われた対独戦勝記念式典の席上で、爆弾テロによって殺害された」と述べます。
「プーチンが柔道家としての仮面を前面に押し出した理由」では、北方領土問題解決に関して、プーチン大統領の仮面を剥がすことは不可能だとして、著者は「仕事に絡むことでは、プーチンは仮面を外さない。従って、われわれにできることは、日本の国益にとって最適の仮面をプーチンにつけさせることだ。そこから本気の話し合いを、膝をつき合わせて始めればいい。鈴木宗男氏が水先案内人として最適の役者だったため、森喜朗総理はプーチン大統領に、日本にとって役に立つ仮面をつけさせることに成功したのだ」と述べます。
また、「プーチン大統領は柔道家だから親日的だ」と言う人がいることに触れ、著者は「私はこの見方は完全にずれていると思う。ソ連時代、柔道協会会長は常に内務次官が務めていた。ソ連・ロシアの内務省、諜報・防諜機関関係者は、柔道が職務の役に立つから使っているだけだ。柔道を知っていることを『親日家』という表象に使うことができるから、プーチンはそれを最大限利用しているに過ぎない。柔道を北方領土問題解決の手掛かりにしようというのは、私の見立てではまったくカテゴリー違いの議論だ」と述べています。
さらに、著者は「東京宣言」にも言及します。1993年10月13日、エリツィン大統領が細川護熙総理と署名したのが東京宣言ですが、北方四島の名前をあげて、四島の「帰属の問題」が平和条約交渉の土俵であることを定めた点で重要な外交文書です。四島(択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島)の帰属に関する問題を解決して平和条約を締結することに、日露両首脳は合意しました。著者は、「首脳が合意したということは、国家が合意したということだ」と述べます。
「『東京宣言至上主義』の呪縛」では、そもそも1956年日ソ共同宣言第9項後段で、平和条約締結後の歯舞群島と色丹島の日本への引き渡しは約束されていることが紹介されます。著者は、「だからこれら2島の日本帰属については、既に日露間で合意済みであるという立場で、日本はエリツィン大統領に臨むべきだった。従って、東京宣言では残る『択捉島、国後島の帰属に関する問題を解決して』平和条約を締結する、とするのが筋だった。ここであたかも歯舞群島、色丹島が係争問題であるかの如き外交文書を作ってしまったのは、ロシアに対する日本の大きな譲歩だ。当時、外務次官を務めていたクナッゼ氏が2001年に私に『あそこで日本側があんなに簡単に譲歩するとは思わなかった』と述べた」と書いています。
「プーチンがもつ政治家の顔、戦略家の顔、歴史家の顔」では、プーチン大統領にはいくつかの顔(Персона、ペルソナ)があると指摘されます。政治家の顔、戦略家の顔、歴史家の顔です。「歴史的ピンポン」に終止符を打つとの発言は、政治家としての顔が顕在化した発言だとして、著者は「会見でプーチン大統領は日露関係の歴史について、1855年(安政元年)の日露通好条約から説き起こした。つまり、江戸幕府と帝政ロシアの平和的な交渉の結果、この条約で択捉島とウルップ島の間に国境線が引かれ、北方四島が日本領になったという日露関係の歴史的起点を示唆するものだ。1956年の日ソ共同宣言で、ロシアは歯舞群島と色丹島の日本への引き渡し義務を負っているに過ぎない。そのうえで歴史的、道義的に、日本が国後島と択捉島の領有に固執することには理解を示すという発言だ。ここでは、国後島、択捉島について、日本に引き渡すことはないが、何らかの譲歩をすることを示唆している。これは歴史家としてのプーチンの顔が顕在化した発言だ」と述べています。
第5章「クリミア併合」の「ウクライナでの歴史的な宗教対立」では、16世紀にドイツで始まった宗教改革の影響は、ポーランドやチェコ、ハンガリーにも波及したことを紹介し、著者は「特にチェコ地域では、カルヴァン派の影響が強かった。この流れに危機感を強めたカトリック側、つまりローマ教皇庁は、トリエント公会議を開いてカトリックの立て直しを図る。その中心的な役割を果たしたのが、フランシスコ・ザビエルやイグナチウス・ロヨラを中心としたイエズス会だ。イエズス会は実質的に軍隊と言ってもよく、その軍事力を背景にプロテスタントの打倒を目指して『プロテスタント征伐十字軍』を仕掛ける。ところが彼らは強すぎて、プロテスタントをすべて駆逐した後に、ロシア正教の領域まで侵攻してしまった」と述べます。
いくらイエズス会から圧力をかけられても、ロシア正教徒は自らがとりおこなってきた伝統や儀式をそう簡単に改めようとしませんでした。イコン(聖画像)を掲げて拝む、お香を焚きながら儀式を行う。下級司祭の結婚を認めるなど、ロシア正教の習慣を残そうとして、必死に抵抗したとして、著者は「ロシア正教には、司祭に『キャリア組』と『ノンキャリア組』がある。ノンキャリアは婚姻可能であり、結婚して各地域に勤務する。キャリアは修道院や大教会に勤務するが、結婚はできない。ちなみにカトリック教会では、聖職者全員が結婚できない。プロテスタント教会は牧師全員が結婚できる」と述べます。
ロシア正教が自らの習慣を残そうと抵抗を続けたため、ローマ教皇庁は妥協案として特別の宗派を創設しました。著者は、「新しい宗派では、結婚も儀式は従来通りでかまわない。ただし「ローマ教皇が一番偉いという教皇の首位権」、そして『聖霊が父および子(フィリオクエ)から出ずるのかという神学上の議論を認めること』、この2点のみが求められた。要するに、形はロシア正教のままだが、バチカンとつながっている特殊な教会を使って、ロシア全域への影響を強めようとした。こうして誕生したのが『東方典礼カトリック教会』あるいは『ユニエイト教会』などと呼ばれる教会だ。ロシアとバチカンが今日でも緊張関係にあるのは、こうした歴史上の経緯があるためだと知ってほしい」と述べるのでした。
「ウクライナ=正義なのか」では、ネットの一部には、中途半端な知識と、ウクライナ民族主義者が展開する実証性の低い物語を真実と信じ込んで主張する人がいるとして、著者は「私はモスクワの日本大使館では民族問題を担当し、ロシア語を学ぶだけでなく、ベラルーシ語の研修を3年、ウクライナ語の研修を1年受けた。またロシア科学アカデミー民族学人類学研究所では、東スラブの民族研究にも取り組んだ。日本では、ウクライナの専門家が非常に少ない。こういう地域の問題について、当該語学(ウクライナ語だけでなく、ロシア語で文献を読む力が不可欠)の基礎知識もなく、民族学的基礎訓練を受けていない人の言説が想定外の影響を与えることがあるので要注意だ。もちろんロシアによる制限主権論的なウクライナ政策は弾劾されるべきであるし、国際法違反、国連憲章違反にあたる行為は是認することはできない。しかしそのことは、キーウの現政権を手放しで支持することにはつながらない」と述べています。
第6章「ウクライナ侵攻」の「コメディアンが大統領に化けた ゼレンスキー大統領誕生劇」では、著者は以下のように述べています。
「そもそもゼレンスキーとは、どういう人物なのだろう。元コメディアンであるゼレンスキーの芸風は、あえて日本の例をあげるならば『志村けんのバカ殿様』を想起させるものだ。開けっぴろげな芸風は、裏返して言うと庶民にきわめて近い。15年、ゼレンスキーはウクライナのドラマ『国民の僕』に出演して人気を博す。ゼレンスキーが扮する主人公は高校教師だ。現職大統領の腐敗政治に憤慨する高校教師が『ウクライナの政治はおかしい』と言っているうちに、反体制派と見なされて投獄されてしまう。腐敗した大統領は、明らかに15年当時のポロシェンコ(14~19年在任)を当てこすっている」
「国民の僕」というドラマはテレビで爆発的な人気を得て、高視聴率を獲得しました。その勢いに乗ってゼレンスキーは19年3月の大統領選挙に出馬し、4月の決選投票でポロシェンコを破って当選を果たした。得票率は73%を超える。フィクションであるはずのドラマが、現実を上書きしてしまったのです。著者は、「なおウクライナ戦争が始まって以降、オレクシー・アレストーヴィッチという大統領府長官顧問が記者会見に毎日出てくる。彼も元コメディアンであり、かつては女装で笑いを取っていた人物だ。アレストーヴィッチはジョージア(旧称・グルジア)生まれのウクライナ人で、キーウ国立大学を卒業し、俳優になった。またカトリックの高等教育機関で神学を学んだ。その後、ウクライナ軍の諜報部門で勤務した。ゼレンスキーの側近のほとんどが、ドラマ『国民の僕』に出てきたスタッフによって固められている」と述べます。
「ナチス支持者ステパン・バンデラの影」では、2月24日にロシアがウクライナに侵攻したあと、プーチン大統領、ラブロフ外務大臣らの政治家、ロシアのマスメディアは「ナツィスティ」(ナチス主義者)、「ネオナチスティ」(ネオナチ)、「ナアツィオナリスティ」(民族排外主義者)という言葉でウクライナのゼレンスキー政権を非難したことに触れ、著者は「ロシアは、ウクライナの民族主義者ステパン・バンデラとその系統の武装集団が、ナチス・ドイツと連携してウクライナ独立を図った事実に焦点を当てる。そして『バンデローフツィ』(バンデラ主義者)=『ナツィスティ』(ナチス主義者)という図式をつくっている。ロシアは今回の戦争の目的を「非ナチス化」と主張する。日本では『ウクライナの政権内部にナチス支持者がいるというロシアの主張は言いがかりだ』と決めつけるが、バンデラを英雄視する人々がウクライナ政権内部にも国内にも存在することは事実だ」と述べます。
「経済制裁で戦争が止められた試しはない」では、見落としてはいけないのは、ロシアは意外と孤立していないという事実であると指摘し、著者は「西側諸国は、厳しい経済制裁によってロシアを締め上げ、音を上げさせようとしている。前にも述べたが、経済制裁によってプーチン政権が倒れることはない。考えてもみてほしい。経済制裁によって、体制が倒れた国がこれまでどこにあるというのか。世界中から激しい経済制裁を受けてきた北朝鮮もイランも、体制は転覆していない。少なくとも今のロシアは、北朝鮮やイランよりはよほど体力がある」と述べています。
ウクライナからのロシアの即時撤退を求める決議が、3月2日の国連総会で行われました。決議には193ヵ国中141ヵ国が賛成しました。ロシア、ベラルーシ、シリア、北朝鮮、エリトリアの5ヵ国だけが反対し、中国やインドなど35ヵ国が棄権しました。人権理事会におけるロシアの理事国資格を停止させる4月7日の決議では、賛成が93ヵ国に減りました。中国など24ヵ国が反対し、58ヵ国が棄権に回ったのです。著者は、「自由と民主主義を掲げる陣営は、この数がもつ意味を深く考えていない。4月7日の決議で反対に回った国は、中国、北朝鮮、イラン、キューバ、シリアなど、一昔前の言葉を用いるならば、いわゆる『ならず者国家』だ。ただし、中立的な立場を取ろうとする国を加えると、世界の約半分を占めたことになる。さらに国家の人口で言うならば、アメリカの立場に賛成する人々のほうが少ないのだ。ちなみに、1933年に日本が国際連盟を脱退したとき、リットン調査団の報告書採択に反対したのは日本だけだ。棄権はシャム(タイ)だけだった」と述べます。
終章「平和への道程」の「平和のための『闘う言語』」では、著者は「私たちは、ウクライナ戦争で苦しむ人たちの痛みに想像力を及ぼしながら、少しでも早く戦争を終わらせなければならない。日本社会が戦争の熱気で興奮状態にある状況で、平和を望む人々が大きな声を出すことができなくなっている。しかし、少し勇気を出せばできることがあるはずだ。心の中で『平和』『対話』『核廃絶』を望むウクライナ人、そして同じく平和を望むロシア人たちに思いを寄せて、平和のための『闘う言論』を展開することが、日本で生活する知識人の責務と私は考える」と述べています。
そして、創価学会のシンパとしても知られる著者は、「ウクライナ戦争への創価学会の対応は十分合格点に達しているといえる。日本の若者が保守化していると言われる中、創価学会青年部は戦争の熱狂に引きずられることなく、小説『人間革命』『新・人間革命』という『精神の正史』からブレずに、『闘う言論』を展開している。その意味で創価学会とSGIが存在することは、戦乱の世界における大きな希望といえるだろう」と述べるのでした。ここまで著者が創価学会および池田大作氏に心酔しているとは思いませんでしたので、ちょっと驚きました。現在、著者はガン闘病中だそうですが、1日も早く元気になられることをお祈りいたします。
