- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2179 プロレス・格闘技・武道 『純度100%! 有田哲平のプロレス哲学』 有田哲平著(ベースボールマガジン社)
2022.10.06
アントニオ猪木のいない世界を生きるプロレス・ファンたちに、『純度100%! 有田哲平のプロレス哲学』有田哲平著(ベースボールマガジン社)を紹介します。著者は、1971年熊本県生まれ。1991年に上田晋也とお笑いコンビ「海砂利水魚」としてデビュー。2001年にコンビ名を「くりぃむしちゅー」に改名。主なレギュラー番組に「世界一受けたい授業」(日本テレビ系)、「賞金奪い合いネタバトルソウドリ~SOUDORI~」(TBS系)、「全力! 脱力タイムズ」(フジテレビ系)、「くりぃむナンタラ」(テレビ朝日系)などがある。2022年2月には自身初となるYouTubeチャンネル「有田哲平のプロレス噺【オマエ有田だろ!! 】」を開設し、プロレス番組を配信中。ちなみに、タイトルに「プロレス哲学」と入っているわりにはライトな内容でした。動画のタイトルと同じく「プロレス噺」の方が内容に合っていましたね。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、ロダンの「考える人」風のソファーに座った著者の写真が使われ、帯には「なにかプロレスに恩返しができれば。常に、そう考えているんですよね……」と書かれています。
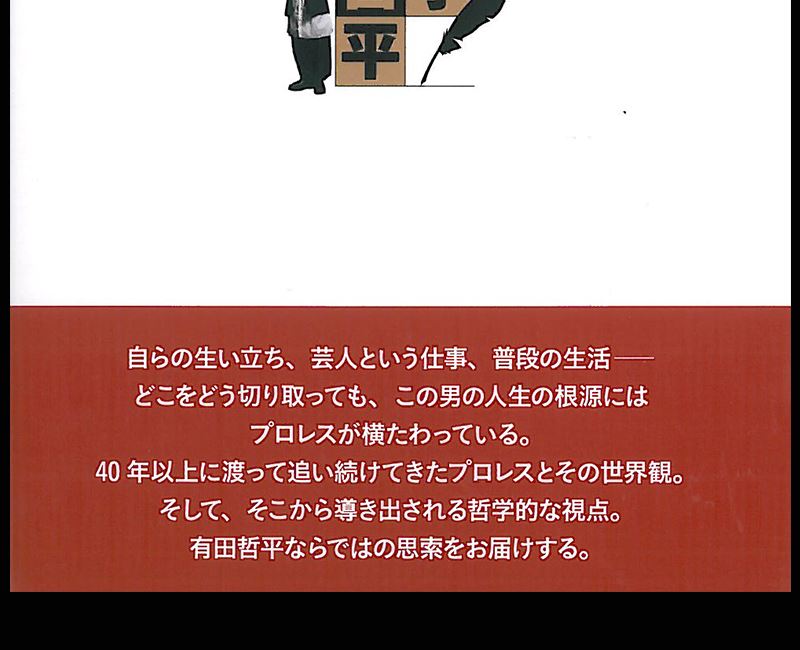 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「自らの生い立ち、芸人という仕事、普段の生活。どこをどう切り取っても、この男の人生の根源にはプロレスが横たわっている。40年以上に渡って追い続けてきたプロレスとその世界観。そして、そこから導き出される哲学的な視点。有田哲平ならではの思索をお届けする」と書かれています。
本書の「CONTENTS」は、以下の通りです。
1章「プロレスって何だ?」
・メジャー/インディー
・チャンピオン
・一撃必殺
・プロレスLOVE
・地方興行
・プロレスメディア
・後楽園ホール
・X
2章「プロレスラーの道」
・道場
・入場テーマ曲
・対抗戦
・武者修行
・サブミッション
・マスク
・マイクアピール
・引退
3章「思い出の中のプロレス」
・金曜8時
・街頭テレビ
・名勝負数え歌
・噛ませ犬
・未知の強豪
・UWF
・ストロングスタイル
・暴動
4章「プロレス・ダークサイド」
・毒霧
・裏切り
・凶器
・デスマッチ
・ヒール
・大量離脱
「おわりに」
1章「プロレスって何だ?」の「一撃必殺」では、著者は、プロレス界に「一撃必殺」という文化が必要であると言います。以前、「有田と週刊プロレスと」という番組で四天王プロレスを解説する中で、「四天王プロレスは二度と復活させちゃダメ」と発言しています。なぜなら、四天王プロレスはエンドレスだからである。同じことは一時期の新日本ジュニアにも言えることで、それらのプロレスでは、必殺技が炸裂しても、一発で試合が終わることはほとんどありません。その攻防はエンドレスなので、最終的には首が折れたり骨が折れたり、どちらかがぶっ壊れるまでやるしかないということになります。著者は、「やがては取り返しのつかない大ケガが起きかねないし、選手たちへの肉体へのダメージも確実に蓄積していきます。だから、これでもか、これでもかという試合はよくないと思うのです」と述べています。
「X」では、プロレス界独特のやり方としての「X」発表というものを取り上げます。「アントニオ猪木vsX」というように、対戦相手の名前を伏せて発表するやり方ですね。著者は昔から、この「X」という発表にものすごく弱いそうで、「X」と発表されると、抗いきれずに会場に行ってしまうというぐらいだとか。「効果的ですよね、あれは、何であんなにワクワクしてしまうんでしょう」と述べています。1984年、全日本プロレスの「世界最強タッグ決定リーグ戦」の際は、ジャイアント馬場のパートナーが「ミステリアスパートナー」として発表されました。ポスターもシルエットになっていましたが、開幕戦に登場したのは、まさかのラッシャー木村でした。著者は、「これは本当に各団体にお願いしたいことなんですが、決まっていないだけの時は『X』とせずに、素直に『未定』『交渉中』と書いてほしいです。『X』だと中身が気になって、会場に行ってしまいますから。それで期待外れの選手が出てきたら、その団体にはもう行かなくなってしまうぐらいガッカリします」と述べます。
「X」で失敗した有名な例に、1979年2月にアントニオ猪木と格闘技世界一決定戦で戦ったミスターXの例があります。連載中の梶原一騎原作マンガ「四角いジャングル」でさんざん「中身は大物空手家だ」と盛り上げましたが、実際に登場したのはとてもそうは思えないブクブクに太った弱い選手でした。著者は、「これは早すぎたメディアミックスの例でもありますし、そう考えると『X』の歴史は古いですね。ミスターXというマスクマンは力道山時代からいましたが、これは『名前は明かせないけど中身は大物』という触れ込みで、日本に来たミスターXは実際に大物のビル・ミラーの返信だったりしました。『X』発表は便利な手段ですが、乱用すると『X』自体への興味が薄れます。特に決まっていない場合の『ごまかしX』は本当に信用をなくすので、ぜひやめていただきたいと、繰り返し言わせていただきたいところです」と訴えるのでした。まったく同感であります!
2章「プロレスラーの道」の「対抗戦」は、プロレス団体同士の対抗戦がテーマです。1979年の新日本・全日本・国際の3団体による「8・26夢のオールスター戦」、1990年の新日本と全日本の「2・10東京ドーム」、2022年の新日本とノアの「1・8横浜アリーナ」など歴史に残る対抗戦に言及しながら、著者は「僕らお笑いの世界で言うと、対抗戦とはちょっと異なりますが、思い出すのは『笑っていいとも!』の最終回でしょうか。いまだに『凄かった』と語られるのは、長寿番組のラストということで、ダウンタウンさん、とんねるずさん、明石家さんまさん、ウンナンさん、ナインティナイン、爆笑問題という顔触れが一同に会した様子は、本当に壮観のひと言でした。彼らはそれぞれが自分の団体を率いているようなもので、仲が悪いと言われている組み合わせもあります(実際どうなのかは知りませんが……)。それが1つの番組のために集まったんですから、驚きを産むのは当然でした。それこそ一度きりの「夢のオールスター戦」ばりの興奮がそこにはありました」と述べています。
「サブミッション」では、昔のUWFで関節技の取り合いになると会場中が「シーン」となって、みんなが固唾を呑んでリング上の攻防に注目していたことを取り上げ、著者は「その時代に戻れというわけではありません。でも、『サブミッションは一瞬で極まることもある』『関節技が極まったら、時間が早かろうが、それまでの攻防が少なかろうが、否応なく決着がつく』というのも見せてほしいんですよね。ましてや僕たちはPRIDEやRIZINも見ているわけですから。『安心して盛り上がれるプロレス』というのは楽しいのも確かですが、よくないなどとも思っています。どうなるか分からないという緊張感がある場にいたいなと。そう考えると、武藤敬司選手はやっぱり天才だなと思うんですよ。UWFインターナショナルとの対抗戦のメイン、髙田延彦さんとの一戦でドラゴンスクリューと4の字固めを復活させて、それで勝ってしまうんですから」と述べています。
著者は、「従来のプロレスの技を否定していたはずのUWF、そこを代表して乗り込んできた髙田さんが、その技でタップを余儀なくされるという場面は衝撃的でした」とも述べます。その髙田が統括本部長を務めたPRIDEでは、ミルコ・クロコップvsアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ戦に言及し、著者は「ミルコのハイキックか、ノゲイラの柔術技か。スタン・ハンセンのウエスタン・ラリアットとアントニオ猪木の卍固めみたいなものですよね。全くタイプの違う得意技を持った2人が対決して、どちらで決めるのかをお客さんがジッと集中して見つめている。その中で、しっかりとその技が出て勝負が決まるわけですから、あれは最高のプロレスでした」と述べるのでした。
「マイクアピール」では、プロレスラーはすべてをマイクに頼る必要はないという著者は、「言葉にしなくても、ちょっとしたアクションで十分思いが伝わる場合もありますし。昔、スタン・ハンセンがブルーザー・ブロディの追悼試合で、ブロディの技を使うことでその気持ちを表現した場面などは、今でも覚えています。一番の親友でタッグパートナーだったブロディへの思いを、マイクで語るのではなく、あくまで態度で示した姿はカッコよかったですね。それから長州力さんの場合は、マイクで言っていることの内容は今一つ聞き取れないことが多かったですが、区長と態度で、『とにかく怒っているんだな』というのはいつも伝わってきました。そういうことでいいと思うんですよ」と述べています。
3章「思い出の中のプロレス」の「未知の強豪」では、ビリー・ジャックとかヘラクレス・ローンホークとかロード・ウォリアーズ、サルマン・ハシミコフらの「レッドブル軍団」などの名前を挙げた後、著者は「最後の『未知の強豪』は『400戦無敗』と言われたヒクソン・グレイシーだったのかもしれません。彼はプロレスラーではありませんが、『400戦って、誰が数えたんだ?』とかいうツッコミどころがあったのも含めて、久々にプロレスっぽい幻想に満ちていました。もっと後になるといろんな情報が多くなってきて、未知の強豪はなかなか生まれなくなってきました。特にインターネットやSNSが定着してからは、日本にいても世界中のリングの情報がすぐに届いてしまいます。これはいいことか悪いことか分からないですよね。こんな時代に『ジャングルから出てきた男を紹介するぜ!』とか『今日、俺はストロング・マシンを連れてきたぜ!』って言っても、それはもう呆れられることでしょう。プロレス幻想という意味では、本当にやりづらい時代になったものです」と述べています。
「UWF」では、著者は「UWFがすごい! と言いつつ、大仁田厚が電流爆破マッチをやれば『これはすげえな!』と思い、今は亡き東京ベイNKホールで武藤敬司がムーンサルトプレスをやれば、『うわ、これカッコいい!』みたいな。結局はUWFを通じて、プロレスのよさを再確認させてもらっているんですよね。さらにUWF系3派(リングス、UWFインターナショナル、藤原組)を我慢してコツコツ見ていたら、PRIDREというものに行き着くわけです。誤解してほしくないのは、UWFを『面白くない』とか『我慢して見た』と言っているのは、決して蔑んでいるわけではないんです」以下のように述べています。これには、非常に共感しました。わたしも、まったくその通りだったからです。
著者によれば、闘いなのだから、つまらない時もあって当然であり、リアル・マドリードの試合だって凡戦が存在するのと同じだというのです。著者は、「僕たちは、どの試合でも必ず延髄斬りやウエスタン・ラリアットが見られるプロレスに慣れすぎていたんだと思います。『そういうのはないこともあるんだよ』ということを示してくれたのも、UWFだったんだと、今になってみれば思います」と述べ、さらには「あえてまとめるなら、僕にとってのUWFは『いいオンナ』だったのかもしれない。いいように振り回してくれて、ウソもついたし、熱くもなったし、髙田vsヒクソンみたいな絶望感も味わわせてくれて、今まで付き合ってきた中で一番のいいオンナ……そんな感じですかね」と述べるのでした。
この「王様は裸だよ!」と叫んだ子どもみたいに幻想に彩られていたUWFに対する率直な著者の発言は、とても共感できました。「フェイク」という言葉があります。ニセモノという意味ですが、この言葉がよく使われるジャンルが2つあります。オカルトと格闘技です。超能力者とか霊能力者というのは基本的にフェイクだらけです。わたしも、以前よくその類の人々に会った経験がありますが、はっきり言ってインチキばかりでした。でも、スウェデンボルグとか出口王仁三郎といった霊的巨人は本物であったと思っています。わたしが実際に会った人物では、清田益章さんのスプーン曲げや東急エージェンシー時代のの先輩であるタカツカヒカルさんのヒーリング・パワーは今でも本物じゃないかと思っています。ですから、すべてがフェイクではなく、本当にごく少数ですが、なかには本物の能力者もいるのでしょう。
次に格闘技。わたしは子どものころから格闘エンターテインメントとしてのプロレスをこよなく愛し、猪木信者、つまりアントニオ猪木の熱狂的なファンでした。でも、何千という猪木の試合のなかで、いわゆるセメント(真剣勝負)はかのモハメッド・アリ戦とパキスタンの英雄、アクラム・ペールワン戦の2回だけと言われています。だから良いとか悪いとかではなく、それがプロレスなのです。でも、わたしは逆にその2回に限りないロマンを抱きます。また、力道山vs木村政彦、前田日明vsアンドレ・ザ・ジャイアント、小川直也vs橋本真也といった試合は一方の掟破りでセメントになったとされ、今では伝説化しています。フェイクだらけの中にある少しの本物に魅せられる。オカルトも格闘技もフェイクという大海の中にリアルという小島があるわけです。それらの世界に魅せられる人々は、小島をさがして大海を漂う小舟のようですね。
ついでに言えば、スナック、クラブ、キャバクラなどの水商売も同じです。水商売の女性との心の交流は、はっきり言って、擬似恋愛であり、ホステスが演技をして恋人ごっこをしてくれるわけですが、時々、ホステスさんが本気で客と恋愛することがあります。この数少ないロマンを求めて、男たちは懲りもせず飲みに出かけるのですな。つまり、「オカルト・プロレス・水商売」はオールフェイクではないのです。それらのジャンルは限りなく胡散臭くて、基本的にウソで固めています。しかしながら、中には紛れもない「リアル」が隠れている。霊能力者もプロレスラーもホステスも、中にはガチンコの本物が実在する。オカルトもプロレスも水商売も「リアルさがし」のゲームであり、冒険の旅であると考えるのなら、「ダマサレタ!」と腹も立たないのかもしれません。本書を読みながら、そんなことを考えました。