- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.11.08
11月8日の夜は、満月が地球の影に隠れる「皆既月食」が全国で見られます。皆既月食が国内で見られるのは2021年5月以来、約1年半ぶりです。さらに皆既月食中に天王星が月に隠される「天王星食」が起こります。皆既月食と惑星食が同時に起こるのは、なんと442年ぶりで、日本で次に皆既食中に惑星食が起こるのは、2344年7月の土星食となり、322年後だそうです。
442年ぶりの皆既月食+惑星色を記念して、スケールの大きな内容の本を紹介したいと思います。『ノヴァセン』ジェームズ・ラヴロック著、藤原朝子監訳、松島倫明訳(NHK出版)がそれです。サブタイトルは、「〈超人知〉が地球を更新する」。本書は、ブログ「ガイア理論のジェームズ・ラヴロック死去」で紹介したように今年7月26日に103歳で亡くなった著者の遺作です。著者は、イギリス生まれ。「ガイア理論」の提唱者として知られます。プロスペクト誌で「100人の世界的知識人」に選ばれ(2005年)、英国地質学界により栄誉あるウォラストン・メダルを授与されました(2006年)。「ダーウィン以来、最も影響力のある科学者」(アイリッシュ・タイムズ紙)、「われわれの地球の見方を変えた科学者」(インディペンデント紙)などとその功績は高く評価されています。著書に『地球生命圏――ガイアの科学』『ガイアの時代――地球生命圏の進化』(ともに工作舎)、『ガイア――地球は生きている』(産調出版)など。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「100歳の大家が放つ、衝撃の未来像。大注目の『ポスト・ガイア理論』!」「落合陽一推薦 本書で著者は人新世的解釈による人間中心主義を過去のものにした。生まれつつある『デジタルの自然』の生成過程を紐解き、ガイア仮説からの旅路を見通している」と書かれています。
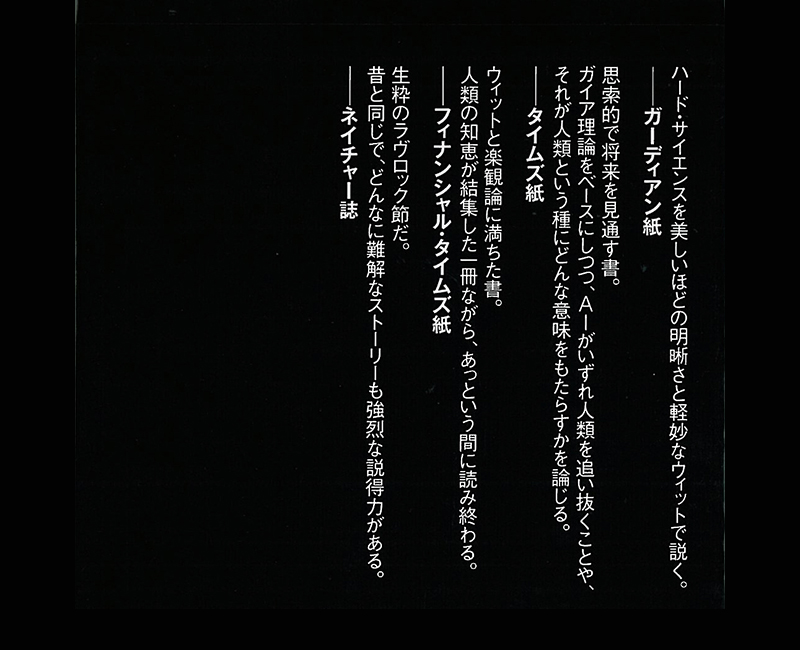 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
ハード・サイエンスを美しいほどの明晰さと軽妙なウイットで説く。――ガーディアン紙
思索的で将来を見通す書。ガイア理論をベースにしつつ、AIがいずれ人類を追い抜くことや、それが人類という種にどんな意味をもたらすかを論じる。――タイムズ紙
ウイットと楽観論に満ちた書。人類の知恵が結集した一冊ながら、あっという間に読み終わる。――フィナンシャル・タイムズ紙
生粋のラヴロック節だ。昔と同じで、どんなに難解なストーリーも強烈な説得力がある。――ネイチャー誌
カバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「『ガイア理論』の提唱者として知られる世界的な科学者が、21世紀に人間の知能をはるかに凌駕する〈超知能〉が出現すると予測。地球は、人類を頂点とする時代(=「人新世」)から、〈超知能〉と人類が共存する時代(=「ノヴァセン」)へと移行するのだ。〈超知能〉は人類より1万倍速く思考や計算ができ、人間とは異なるコミュニケーション手段を持つという。他方で〈超知能〉にとっても地球という環境が生存の条件になるため、人類と共に地球を保護する方向に向かうだろうと断言する。科学的なベースを踏まえながら、地球と生命の未来を大胆に構想した知的興奮の書!」
本書の「目次」は、以下の通りです。
序文(ブライアン・アップルヤード)
パート1 コスモスの目覚め
1 孤独な人類
2 絶滅の縁
3 直観的思考を身につける
4 なぜ人間はここにいるのか
5 新たなる理解者
パート2 火の時代
6 トーマス・ニューコメン
7 ニューエージ
8 加速
9 戦争
10 都市
11 世界は人間にうんざりしている
12 熱の脅威
13 アントロポセンは良いことか悪いことか?
14 歓喜の叫び
パート3ノヴァセンへ
15 アルファ碁
16 ニューエイジをエンジニアリングする
17 ビット
18 人間を超えて
19 球体との対話
20 愛にあふれ気品に満ちた器械が
すべてを監視していた
21 思考する武器
22 他者の世界におけるわたしたちの場所
23 意識をもったコスモス
「序文」では、イギリスのジャーナリストであるブライアン・アップルヤードが著者ラヴロックについて、「著書『地球生命圏:ガイアの科学』(工作舎)によって彼の女神をわたしたちに紹介してから40年が経ったいま、彼は同じように驚くべき、そしてラディカルな新しいアイデアをわたしたちに提示します。『Novacene(ノヴァセン)』とはこの地球の新しい地質年代として彼が名付けたもので、アントロポセン(Anthropocene:人新世)を引き継ぐ時代となります」と述べています。
アントロポセンとは人類がこの惑星全体を地質学的にも生態系の面からも改変する能力を獲得した時代として定義づけられ、1712年に始まり、すでに終わろうとしていると説明し、それに続くノヴァセン(ラヴロックに言わせればそれはすでに始まっている)という時代は、テクノロジーがわたしたちのコントロールを超えて、わたしたちよりも遥かに優れた知能を生み出す時代であると指摘し、「さらに重要なのは、その知能がわたしたちよりも遥かに速く働くことです。どうやってそれが起こり、わたしたちにとってどんな意味をもつのか、それを語るのが本書です」と、アップルヤードは述べます。
1「孤独な人類」の冒頭を、著者は「わたしたちのコスモスは138億歳だ。この地球が形成されたのは45億年前のことで、生命が誕生したのは37億年前だ。われらがホモ・サピエンスは誕生してからたかだか30万年ほどしか経っていない。コペルニクス、ケプラー、ガリレオ、それにニュートンが歴史に登場するのはこの500年のことだ。コスモスが存在してきた時間のほとんどにおいて、コスモスは自らについて何ひとつ知らなかった。人類がツールとアイデアを発展させ、輝く星空という途方に暮れるほどの光景を観察し分析したことで初めて、コスモスは無知という長い眠りから目覚めたのだ」と書きだしています。
最初の原始的な生命体から、コスモスを理解できる知能をもつ生命体へと進化するのには37億年にわたる自然選択、つまり目をつぶって手探りをするような進化のプロセスが必要でした。37憶年といえば、コスモスの歴史のほぼ3分の1です。さらに言えば、もし太陽系の進化が実際よりも10億年長くかかっていたら、コスモスについて語ることのできる生命はどこにも存在しないだろうとして、著者は「太陽が発する猛烈な熱に対処できるようなテクノロジーを手にするだけの時間がないだろうからだ。こうした観点から言えば、コスモスは古いとはいえ、知的生命を生み出すのに必要なとんでもなく長く複雑なプロセスが、一度ならず何度も起こるほどには古くないことは明らかだ。わたしたちの存在は、1回限りの奇遇な出来事なのだ」と述べています。
コスモスについて知る能力をもつ生物を育むことができたのは地球だけだと確信しているとして、著者は「だが同時に、その存在が危機に瀕していることも確かだ。人間はほかに類を見ない特権的な存在であり、だからこそ、自らがコスモスを意識するあらゆる瞬間を大事にすべきだ。とりわけ、コスモスの最大の理解者という至高の立場でいられる時間が急速に終わりに近づくいま、なおさらこの時間を大事にしなければならない」と述べます。
3「直感的思考を身につける」では、地球とはひとつの生きた生命体であるというガイアからの提示は、わたしにとっては直観的に真実に思える一方で、これまで多くの批判にさらされてきたといいます。その1つは、再生(生殖)ができない以上、生命体とは言えないというものです。それに対する著者の答えは「40億歳の生命体には再生は必要ない」というものでした。それに、もし地球の大気から対隕石ロケットが飛び出すのを地球外知的生命体が見たら、合理的に考えて、それを地球そのものが打ち上げたものだと結論づけるだろうとも述べています。
そのロケットをつくったのがガイアというシステム全体だという意味で、その結論は正しいと言えます。一方で、太陽との距離が近いことや地球から放出される熱を見て、ここでは生命が誕生し得ないと誤って結論づけるかもしれないとして、著者は「この熱の放出はガイアによるものだ。生命を維持するために余計な熱を宇宙空間に押し出しているのはガイアの為せる業であり、それを理解するためにわたしたちは考え方を変えなければならない」と述べています。
4「なぜ人間はここにいるのか」では、ビッグバンという始原からこの宇宙がいかに形成されてきたかを考えると深く感動するという著者は、「最初に軽元素から初期の恒星や銀河が誕生し、それからの数十億年で生命や恒星系の構成要素がゆっくりと積み重なっていった。恒星は惑星たちを連ね、ついには最初の生きた細胞をつくりだしたのだ。それからさらに40億年をかけて、偶然と必然に導かれて動物が進化し、ついには人間が誕生した」と述べています。
人間は、コスモス全体が意識をもつようになるそのプロセスの、まだほんの始まりにいるにすぎないのかもしれないとして、著者は「思うに、新手の無神論者やその仲間の無宗教の人々が間違えたのは、真実という赤ん坊を、神話という洗礼のための聖水もろとも投げ捨ててしまったことだ。宗教を嫌うがために、その内なる核心にある真実を見逃してしまった。人間は選ばれた存在だ。ただそれは神や預言者に選ばれたのではなく、自然に選択された種――言うなれば知性のために選ばれた種なのだ」と述べます。
5「新たなる理解者」では、著者は、サイボーグについて言及します。サイボーグという言葉はマンフレッド・クラインズとネイサン・クラインが1960年に提唱しました。サイバネティックな生命体、つまり人間のように自律的でありながら工学的物質でつくられた生命のことです。著者は、「わたしがこの語と定義を好むのは、微生物からゾウなどの厚皮動物まで、あるいはマイクロチップから乗り合いバスまで、あらゆるサイズのものに適用できるからだ。現在サイボーグという言葉は一般的に、一部が生身の肉体で一部が機械であるような存在を指す。一方、ここでわたしがこの語を使うことで強調したいのは、新たな知的存在は人類と同様、自然選択から現れることになるだろうということだ。その存在は当初、わたしたちと区別がつかない。実際に、人間がつくったシステムがその前駆体になるので、人間の子孫だと言える」と述べています。
わたしたちが少なくとも最初のうちは恐れる必要がないのは、こうした非有機的存在が人間や有機的世界全体を必要とするからだとして、著者は「この有機的世界は気候を調整し、地球を冷涼に保つことで太陽からの熱をブロックし、未来の天変地異が最悪の事態を引き起こすのを防いでくれる。SFでよく描かれるような人間と機械の戦争といったものに突入することはないだろう。というのもお互いを必要としているからだ。ガイアによって平和が維持されるのだ」と述べています。
この時代を著者は「ノヴァセン」と呼び、「それは選ばれし種である人間がテクノロジーを発達させることで、この惑星全体のプロセスや構造に直接介入できるようになった時代のことだ。それは火の時代であり、そこで人類は、大昔の太陽光エネルギーを捉えて利用することを学んだ。その時代はアントロポセン(人新世)と言われている」と述べるのでした。
6「トーマス・ニューコメン」では、イギリスのトーマス・ニューコメンが蒸気で動くポンプを作ったことに触れ、著者は「この小さなエンジンは何と言っても産業革命を解き放つことになった。これは地球の生命体が、太陽光エネルギーをある意図をもって利用し、自分の身の回りの仕事を、利益を生むやり方でこなした初めての出来事だった。それによってこの生命体の成長と再生産が確かなものとなった。風車や帆船も風を動力としている点で同じようなものだとされることがあるが、ニューコメンの内燃機関が特別なのは、それがいつでもどこでも使え、気まぐれな天候に左右されないことだ。この蒸気機関は世界中に拡がった。思うに、ニューコメンのこの発明は、単に産業革命の始まりとなっただけでなく、アントロポセンの始まりとしても讃えられるべきだろう。アントロポセンは火の時代であり、人間が巨大な規模でこの物理的世界を変革する力を手にした時代なのだ」と述べています。
ここで強調しておきたいのは、地球に巨大な変化をもたらしたアントロポセンが、市場の力に駆動されて進化したことであるとして、著者は「ニューコメンの蒸気機関が経済的利益をもたらさなければ、人類はいまだに17世紀の世界のままかもしれない。ニューコメンの蒸気機関の重要な特徴は、それが利益をもたらすことだ。単なる蒸気機関のアイデアだけではその発達を確実にすることはなかっただろう。もっとも重要なことは――良くも悪くも――それが人力や馬力よりも安い労働源だったことだ」と述べます。
7「ニューエイジ」では、「アントロポセン」について説明します。「アントロポセン」という言葉は1980年代初頭に、ユージーン・ストーマーによって提案されました。彼はカナダと合衆国を分かつ五大湖の水質について研究する生態学者で、湖の野生動物に及ぶ産業汚染の影響を説明するためにこの言葉を使いました。それは、アントロポセンにおいて、人間の活動が地球規模の影響を及ぼし得ることを示す証拠のひとつだったのです。
8「加速」では、鉄道の到来により、アントロポセンにもうひとつの大いなるテーマがもたらされたことが指摘されます。それは、加速です。著者は、「アントロポセンが始まるやすぐに、人類はスピード狂の若者たちのように加速の力に夢中になった。そのまま300年間、アクセルを踏み続けたわたしたちは、いまや電子的、機械的、生物学的に人間がつくりあげたものが、地球のシステムを動かす時代へと近づいているのだ」と述べています。
それ以前のテクノロジーは、人間の移動するスピードに影響を与えることはありませんでした。著者は、「ナポレオンの軍隊は、ジュリアス・シーザーの軍隊に比べて特別速く動けたわけではなかった。鉄道が発明された瞬間からそのスピードは着実に上がり続け、ついには今日、時速200マイル[約320キロ]にまで至り、リニアモーターカーはやがて、時速400マイル[約640キロ]で走るだろう。そればかりか、かつてなら徒歩や、もし裕福であれば馬で移動していた人々を大量に運ぶことができるようになった。ど田舎の村の近くに鉄道が敷設されたとしよう。それまで何世紀ものあいだ培ってきたローカルな世界観や生活についての知恵は、最初の車両が到着するやいなやひっくり返ってしまったことだろう」と述べます。
軍用機はいまや音速の2倍以上の速さで飛び、ロケットは地球の重力場を脱出するのに必要な速度である時速2万5000マイル[約4万キロ]に達していると紹介しながらも、著者は「だが、世界をもっとも変えた加速は、時速500~600マイル[約800~950キロ]で飛ぶ民間機のスピードだ。それらは大量の人々を世界中に運び、文化的な均一化を押し拡げることで、地球をニューエイジへと到達させる」と述べます。
こうした発展によってもうひとつ別の形の加速が見えてくるとして、著者は「アントロポセンは、急速な進化を遂げるための新しい手段をもたらしたのだ。優美な飛翔を見せる海鳥は、その祖先であるトカゲから進化するのに5000万年以上がかかった。それに比べて今日の航空機の進化は、通称「ストリングバッグ」と呼ばれた複葉機から100年しか経っていない。知性による意図的な選択は、自然選択よりも100万倍速く進んでいるようだ。自然選択を超越することによって、人間はすでに魔術使いの見習いに加わっている」と述べるのでした。9「戦争」では、著者は「残念ながら、アントロポセンのパワーは戦争においてもっとも強力に発揮されてきた。人間が新しく発明した機械のせいで、アントロポセンは次々と血塗られた紛争が起こる時代となった。哲学者で歴史家のルイス・マンフォードが著書『技術と文明』(美術出版社)で述べたように、『戦争とは完全に機械化された社会における究極のドラマ』なのだ」と書きだしています。
核の攻撃を受けたのは広島と長崎だけです。その後の核爆発はどれも実験によるものでした。その恐るべきクライマックスとも言えるのが、1961年に落とされたソヴィエトのツァーリ・ボンバ(核爆弾の皇帝)だったと指摘し、著者は「50メガトン級の核融合爆弾(水爆)で、もし実際に戦闘で使われていたら、大型都市まるまるひとつと、その周囲をも壊滅させただろう。こうした実験による大気汚染は大規模なものとなり、およそ60年経ったいまでも、わたしたちの人体に残留したその放射能によって、法医学者は検体の死亡時期を確定することができる。強力な核の軍拡競争は、このツァーリ・ボンバの年には、信じられないほど危険な状況に達していた。この時期、太平洋および北極海の島々では計約500メガトンに及び核実験が行なわれ、有毒な物質が撒き散らされた。これは、3万個の広島級の原子爆弾が地上で爆発するのに等しい量だ。気が狂ってる」と述べるのでした。
12「熱の脅威」では、惑星も人間のように歳をとるにつれて脆くなっていくとして、著者は「このまま何事もなくいけば、ガイアもわたしも生産的で心地良い衰退期へと向かうだろう。だが人間には致命的なアクシデントが起こるかもしれないし、それは惑星も同じだ。個々の人間の回復力はその人の健康状態に依っている。若ければインフルエンザや交通事故にも耐えられるかもしれないが、100歳近くになればそれは無理だ。同じように、地球やガイアも若いうちは巨大火山の噴火や隕石の衝突といったショックにも耐えられるけれど、歳をとれば、そのいずれかが起こっただけで惑星全体が不毛の地になるだろう。温暖化した地球は、より脆弱な地球なのだ」と述べています。
1969年に宇宙飛行士たちが、宇宙から見た地球がいかに美しいかを明らかにすると、わたしたちは息を呑みました。この惑星を「地球」と呼んできたのは間違いで、明らかに「水球」だと指摘したのは、SF作家で発明家のアーサー・C・クラークでした。著者は、「それからすでに50年が経っているにもかかわらず、海の惑星に住んでいるというこの発見は、埃をかぶった地質学の領域にようやく浸透し始めたにすぎない。この地球の海についてよりも、火星の表面や大気についてのほうがよくわかっている部分があるというのは、残念なことだ」と述べます。
13「アントロポセンは良いことか悪いことか」では、著者は以下のように述べています。 「真実はと言えば、たとえ機械的な物事に結びついていても、アントロポセンとは地球上の生命が生み出したものだ。それは進化の産物であり、自然の発現なのだ。自然選択による進化はしばしばこう表現される。『もっとも子孫を残した生命体が選択される』。蒸気機関は間違いなく多産で、その後継はジェームズ・ワットのような発明家によって改良され、素早く進化して殖えていった。そのプロセスが産業革命へとつながり、1世紀にわたる科学技術の繁栄をもたらしたのだ」
わたしたちは過去300年で地球の環境に膨大な変化を加えてきた。自然のエコシステムの無思慮な破壊など、そのいくつかは確かに酷いものでした。しかし、著者は「目を見張るべき寿命の伸長、貧困の軽減、教育の普及についてはどうだろう? 生きることがより楽になり、とりわけ天才発明家マイケル・ファラデーのおかげで電力の利用が拡がったことは? いまや多くの人が、ITや航空旅行、最新医学の恩恵を当然のものだと考えている。でも、わたしが生まれた100年前の第一次世界大戦が終わった当時は、(金持ちを除けば)電灯もなければクルマも電話もラジオもテレビも抗生物質もなかった。シェラック盤のレコードを手巻き式の蓄音機でトランペット型のスピーカーから聴くことはできたけれど、その程度だった。いまや誰もが木々や牧草地に囲まれた田舎暮らしに恋い焦がれるが、それは病院や学校、洗濯機といった日々の生活をより良くしてくれるものを拒絶するということではないはずだ」と述べるのでした。
14「歓喜の叫び」では、著者がアントロポセンに最期の言葉をかけるとすればそれは歓喜の叫びであるとして、「この時代が、世界とコスモスについてのわたしたちの知識を飛躍的に増加させたことへの喜びだ。ガイアへの気づきを育んできた時代に生きているのは素晴らしいことだと思うし、科学研究や工学上の試みが盛んに行なわれている時代に生きる幸運に恵まれた。こうしたおかげで、平和的な成果、すなわち太陽系という自然環境に占める地球やその位置についての全体論的な理解がもたらされた。宇宙空間から見ることで拡がった地球についての知識によって、気候変動がもたらす有害な結果を考えるようになり、特に地球表面や大気の止まらない汚染に対して思いをめぐらせることができるようになった」と書きだしています。
「人間原理」という言葉がありますが、著者は、「もし人間原理がこの宇宙を支配しているなら」として、「そのもっとも重要な目的は、すべての事象と放射を情報へ変換することだ。火の時代における奇跡の数々のおかげで、人類はその第一歩を踏み出した。いまやわたしたちはこのプロセスの決定的な地点に立っている――アントロポセンがノヴァセンへと道を譲ろうとする瞬間だ。覚醒したコスモスの運命は、いまや人類がこれにどう応えるかにかかっているのだ」と述べるのでした。
16「ニューエージをエンジニアリングする」では、ノヴァセンをスタートさせたのは単なるコンピューターの発明ではないことが指摘されます。シリコンやガリウム砒素のような半導体結晶を使うことで、入り組んで複雑な機械がつくれることを発明したことでもありません。AIというアイデアも、コンピューターそのものも、このニューエイジの出現に決定的な役割を果たしたわけではありません。著者は、「最初のコンピューターが発明家チャールズ・バベッジによってつくられたのは19世紀の初めであることを思い出してほしい。詩人バイロン卿の娘だったエイダ・ラヴレスが初めてのプログラムを書いたのは、それからまもなくのことだった。アイデアだけなら、ノヴァセンは200年前に生まれていたのだ」と述べています。
17「ビット」では、情報に科学的に取り組もうとした最初の試みは、1940年代にアメリカの数学者でエンジニアであるクロード・シャノンが暗号について研究したものだということが紹介されます。1948年に彼はこの研究を「通信の数学的理論」という論文にまとめたのですが、戦後のテクノロジーにおける第一級の論文です。情報理論はいまでは数学、コンピューターサイエンス、その他多くの学問領域でその中心を占めていると指摘し、著者は「情報の基本単位はビットで、これは1か0の値をもち、すなわち正/負、オン/オフ、イエス/ノーを表す。ビットはもともとはエンジニアリングの用語で、ほかのあらゆるものを構築するための最小のものだとわたしは理解している。コンピューターは純粋にゼロイチで動く。そこから世界全体を構築できるのだ。まるで囲碁のように、これほどのシンプルさからこれほどの複雑さを生み出すことができるという意味で、情報とは本当にコスモスの基盤なのかもしれない」と述べています。
18「人間を超えて」では、未来の知的マシンを想像するときに、わたしたちは驚くほどに、人間に姿や行動が似ているものを思い描きがちだということが紹介されます。その理由は3つあるそうで、「第一に、人間は被造物の頂点に君臨し、したがって、われわれの後継者も人間のような形をしているに違いないという、ほとんど宗教的ともいえる強い欲求があること。第二に、少なくとも外見が自分たちと似ていると考えることで気持ちが安らぐことだ。おそらく、外見が似ているなら中身も似ているということだろうと考えることで、多かれ少なかれ人間のように振る舞うはずだと信じることができる。3つ目の理由は、ジークムント・フロイトの定義でいう『不気味なもの』にわたしたちが興味をひかれるからだ」と書かれています。
フロイトは人形や蝋人形の不気味さについて書いていて、この不気味さは、日常のものがどこかおかしいと思えるときに立ち現れるのだと論じました。SFにおいて人間型ロボットが特にドラマチックなパワーをもつのもそのためで、見た目は同じなのに、その動機や感情、内面性について人間が困惑させられるからだというわけです。著者は、「脳というのは、昆虫であっても哺乳動物であっても、巨大な並列情報処理システムとして進化してきた。人類が日常的に駆使し、発明家たちが磨いてきた直観的思考は、おそらくそのロジックを進めるために並列処理を必要とするだろう。これは古典的なロジックである1チャンネルの線形的な議論とは大きく違い、とてもパワフルなのだ」と述べるのでした。
19「球体との対話」では、哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが、かつて「もしライオンが話せたとして、われわれはその言葉を理解できないだろう」と言ったことが紹介されます。これはチャペックの人間と犬の話よりもよっぽど厳格な洞察であるとして、著者は「ウィトゲンシュタインが言いたいのは、人間の言語はわたしたちの生き方そのものであり、それに従って世界を見ている。そしてライオンは、こうした世界の見方をまったくしないということだ。それはサイボーグも同様だ。言語能力は5万年から10万年前に進化したものだと考えられている。人類の脳と手、喉頭に影響を与える一連の好ましい遺伝的変異によって可能になったものだ。したがって、これは人間の生理に密接に埋め込まれたものであって、サイボーグの電子的な生体構造や生理機能にはまったく適していないだろう」と述べます。
サイボーグは人間から生まれたので、当初は人間のような言語(つまり発声能力によって形成される音)を使ってコミュニケーションをとるだろうと推測し、著者は「自分たちが好むコミュニケーションの構造や手段を発明したり進化させたりするには、時間がかかるかもしれない。ここで時間がかかると言ったのはあくまでサイボーグにとっての時間であって、当然ながら、わたしたちから見れば一瞬のことかもしれない。だがわたしの想像では、サイボーグたちは人間と話す能力を維持するだろう。ちょうどわたしたちのなかにも、ラテン語やギリシア語の知識があって、古典の世界の賢人たちのことばを理解できる人がいるように」と述べています。
話すことと書くことという緩慢なプロセスは、限られた範囲ではあるけれど、意識的な説明を提供できます。そして直観/直感という迅速なプロセスは、わたしたちの意識にはほとんど何も説明してくれないけれど、生き残る上では重大な役割を果たします。著者は、「だから、サイボーグは人間とのコミュニケーション手段という以外には、わたしたちが言語と呼ぶものを一切使わないのではないだろうか。それは人間が享受しているよりも大きな自由をサイボーグにもたらすだろうし、人間のように1つひとつ積み上げたロジックに縛られることもないだろう。サイボーグのコミュニケーション形態はテレパシーになるのではないかと思う」と述べます。
速さという特性によって、ひとたびAIによる生命が現れれば、それは急速に進化し、今世紀の終わりまでには生物圏の重要な一端を担うだろうと推測する著者は、「つまり、ノヴァセンの主要な住人は人間とサイボーグということになる。このふたつの種はともに知性をもち、意図をもって行動する。サイボーグは友好的にもなり得るし、敵対的にもなり得る。だが現在の地球の年齢や状態から、サイボーグはわたしたちと共に動き協働する以外に選択肢はないだろう。未来の世界は、人間やほかの知的種の身勝手なニーズではなく、ガイアの存続を確かなものにするというニーズによって規定されるのだ」と述べるのでした。
20「愛にあふれ気品に満ちた機械がすべてを監視していた」では、地球上の生命に対する長期にわたる脅威は、太陽からの熱の放出が指数関数的に増していることだと指摘し、著者は「これは主系列星に照らされるどんな惑星においても当てはまる単純な論理的帰結だ。太陽からの過熱による影響はすでにわたしたちに及んでいる。そしてガイアの制御能力がなければ、この惑星はいまの金星のような状態まで止まることなく変わっていくだろう。わたしたちを救うには、陸と海の植物再生により、大気から充分な量の二酸化炭素を取り除き続けることだ」と述べています。
もし著者の「ガイア仮説」が正しく、地球が実際に自己調整システムだとすれば、人間という種がこのまま生き残るかどうかは、サイボーグがガイアを受け入れるかどうかにかかっているとして、著者は「サイボーグは自分たちのためにも、地球を冷涼に保つという人間のプロジェクトに加わらなければならないだろう。それに、これを達成するために使えるメカニズムは、有機的生命だということも理解するだろう。人間と機械との戦争が起こったり、単に人間がマシンによって滅ぼされるといったことが起こることはまずないと信じているのはこれが理由だ。つまりわたしたちがルールを課すからではなく、マシンが自らのために、人間という種をコラボレーションの相手として確保しておきたいと思うからだ」と述べます。
ノヴァセンが充分に成長し、化学的条件と物理的条件を調整することでサイボーグにとって居住可能な地球を維持した暁には、ガイアは新しい無機物のコートを纏うことになるだろうと推測する著者は、「増え続ける太陽からの出力に対抗できるように進化するに従い、ノヴァセンのシステムは有機的生命が耐えられないほど暑く、あるいは寒くなっていくかもしれない。この新しいITガイアは当然ながら、人間が助産師の役回りをしなかった場合に比べてずっと長い生存期間を維持するだろう。最終的に、有機的ガイアはおそらく死ぬだろう。ただ、わたしたちが人間の祖先の種の絶滅を悼まないように、わたしの想像では、サイボーグたちは人間の滅亡を悲しまないだろう」と述べます。
22「他者の世界におけるわたしたちの場所」では、人間はサイボーグの親であり、その誕生のプロセスはすでに始まっていると指摘し、著者は「これはぜひ心に留めておいてほしいのだが、サイボーグは、わたしたちをつくり上げた進化のプロセスと同じプロセスをたどって生まれたものだ。電子的生命はその祖先である有機的生命に依存している。非有機的生命体がもう一度はじめから、いまとは違う地球やほかの惑星で、宇宙共通の物理的条件から化学物質が混ざり合って進化するとは考えられない。サイボーグが誕生するには、助産師による手助けが必要だ。そしてガイアはその役割にぴったりなのだ」と述べています。
2つの種がどのようにやり取りをするのかはほとんど想像不可能だとして、著者は「サイボーグたちは人間を、ちょうど人間が植物を眺めるように見ることになるだろう。つまり、認知も行動も極端に遅いプロセスに閉じ込められた存在だ。実際、ノヴァセンがひとたび確立されれば、サイボーグの科学者たちは、生きた人間をコレクションとして展示するかもしれない。ロンドン近郊に住む人々がキューガーデンに植物を見に行くのと、結局のところ変わらないのだ。わたしたちがサイボーグの世界を理解するのが難しいのは、犬にとって人間の複雑な世界を理解するのが難しいのと同じことだろう。愛するペットが人間を管理しているわけではないように、ひとたびサイボーグが表舞台に立てば、その創造主である人間はもはやその主人ではなくなるだろう」と述べます。
23「意識をもったコスモス」では、わたしたちだけではなく、人間の後継者となるサイボーグもまた、この宇宙で孤独な存在となるとして、著者は「ほかに生命がいないこのコスモスにおいて、自分たちが唯一のコスモスの理解者であることに気づくのだ。もちろんサイボーグのほうが、理解力という点では遥かに優れた能力を備えている。おそらく、コスモスの人間原理が正しければ、サイボーグこそが、知的宇宙へと向かうプロセスの始まりとなるだろう。サイボーグを解き放つことで、宇宙の目的が何であれ、それを成就できるものへと進化させていくわずかなチャンスが生まれるかもしれない。もしかすると知的生命の最終的な目標は、コスモスを情報へと転換させることなのだ」と述べています。
「結び」では、生物学者たちが「どうやってほかの惑星において生命の存在を検知するのか」という問いを抱いていたことを紹介し、著者は「わたしは自らの意見を強く表明していた。地球と同じタイプの生命をほかの惑星で探すのは意味がない、特にこの地球の環境についてほとんどのことを知らないままだし、ましてやほかの惑星についてはほとんど何も知らないのだから、というものだ。これは偉い生物学者たちを怒らせるものだった。そうした人たちは、生命の唯一あり得る形はDNAをベースにしたものだけだと考えているようだった。反発はあまりに大きく、わたしはNASAの上級宇宙エンジニアのオフィスに呼び出され、「きみならどうやってほかの惑星で生命を探すんだ?」と尋ねられた。わたしは、惑星表面でエントロピーが減少しているところを探すでしょうと答えた。つまり、生命はその環境を組織化(低エントロピー化)することに気づいていたのだ。こうしてガイア理論が生まれた」と述べています。
最初の実用的なITの発明者はイタリアの物理学者グリエルモ・マルコーニですが、著者は「わたしは彼の惜しみない努力と粘り強さに鼓舞されてきた。地球の曲率があるからそんな芸当は不可能だと合理的科学がはっきり示していた時代にあって、海の上を何千キロも信号を飛ばしたのだ。彼はニューコメンと同じく、ニューエイジを切り開いた人間だった。アントロポセンに続く時代を切り開く知性の持ち主は、人間ではないだろう。わたしたちがいま知覚できるものとはまったく異なる何かであるはずだ。そのロジックは、人間のものとは違い、多次元的なものだろう。動物界や植物界と同じように、そこには大きさも違えば、動くスピードもパワーもさまざまな多くの形態が存在するだろう。それはコスモスの進化における次の、あるいはもしかしたら最後の発展段階かもしれない」と述べます。
「日本語版解説」では、進化生物学者の佐倉統氏が、ラヴロックがエネルギー・情報重視史観によって立ち、地球史上の重大な出来事として、光合成植物の出現(=太陽エネルギーを物質に変換する能力をもった生物の出現)と、イギリスの技術者トーマス・ニューコメンによる蒸気機関の発明(=太陽エネルギーを自在に操作する能力の出現)をあげていることを指摘します。佐倉氏は、「前者はともかく、後者をここまで重視するのは珍しかろう。そして、エネルギー(≒火)の時代(=アントロポセン)の次に来たるべきノヴァセンは情報の時代であるとして、無線による電気通信を発明したグリエルモ・マルコーニをその幕開きを導いた人と称揚する」と述べています。
本書で「ノヴァセン」の手前の段階として位置づけられている「アントロポセン(人新世)」は、ここのところ脚光を集めている考え方です。一条真也の読書館『人新世の「資本論」』で紹介した斎藤幸平氏の著書もベストセラーになりましたが、これはラヴロックのガイアなしには出現しなかっただろうとして、佐倉氏は「アントロポセンには、地球環境問題を総体として見る俯瞰した視点と、人間の側からだけではなく地球の側の問題としてもとらえる脱人間中心主義的視点と、さらに、人間の存在を決して忘れないヒューマニズムとがブレンドされている(もっとも、この「人間」とは誰を、何を指しているのか、というのは批判的に考えるべき問題である)」と述べるのでした。
「訳者あとがき」で、松島倫明氏は「地球とはひとつの生命体」だと最初に「発見」したのは、最後の偉大なる博物学者アレクサンダー・フォン・フンボルトだと紹介します。大地や大気や海洋、生物圏にすむ生命体、そうした有機物と無機物がすべて連なり合い、「生命の網」を編み上げていて、地球とは恒常性を保った巨大なひとつの生命体だという考えは、少なくとも近代科学を踏まえたものとしてはそれが初めてだったとして、松島氏は「かつて書籍編集者時代に手掛けた翻訳書『フンボルトの冒険』(NHK出版)で著者のアンドレア・ウルフは、このフンボルトの発見を受け継いだ系譜としてダーウィンやソロー、生物学者のヘッケルやトレイルの父ミューアとともに、ラヴロックの名前を挙げている。ちなみにフンボルトが死の直前まで心血を注いだ大著が『コスモス』だ」と述べます。
最後に、ラヴロックのガイア理論に慣れ親しんだ方々にとって、本書は驚きと戸惑いをもって受け止められたのではないだろうかとして、松島氏は「何しろガイアが自己に目覚めていくこの宇宙論的目的を達成するために、人間に代わって超知能が後を継ぐというのだ。レイ・カーツワイルが唱えた『シンギュラリティは近い』(NHK出版)やユヴァル・ノア・ハラリが描く『ホモ・デウス』(河出書房新社)のような超知能の世界は、一見、自然とは真逆のディストピアに思えるだろう。だがラヴロックは、人間とマシンによるテクノロジーの意図的選択を通じた進化によってこそ、われらのガイアはこれからも恒常性を保てるのだと明確に述べている」と述べるのでした。
ヤフーニュースより
わたしは、最初にラヴロックの『地球生命圏――ガイアの科学』星川淳訳(工作舎)を読んで以来、ガイア仮説に魅了されました。科学的かどうかは別にして、そのロマンティックな考え方に夢中になったのです。ブログ『リゾートの思想』で紹介した1991年2月に上梓した一条本は、人間にとっての理想の土地、すなわち「理想土」について考察した本ですが、その第2章「リゾートのキーワード=20」の14「ネイチャー」でガイア仮説を紹介しました。ラヴロックは、今年7月26日に103歳で逝去しました。本書『ノヴァセン』は人類史に残る大変な名著であるとの声が多いです。最後に、偉大なるロマンティック・サイエンティストであったジェームズ・ラブロック氏が母なるガイアのもとに還られて安らかに休まれることを心よりお祈りいたします。
