- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2189 歴史・文明・文化 『文明が不幸をもたらす』 クリストファー・ライアン著、鍛原多惠子訳(河出書房新社)
2022.11.23
『文明が不幸をもたらす』クリストファー・ライアン著、鍛原多惠子訳(河出書房新社)を読みました。「病んだ社会の起源」というサブタイトルがついています。著者は、カリフォルニア州セイブルック大学で心理学の博士号を取得。CNN、ニューヨークタイムズ、タイム、ニューズウィークなどのメディアでも紹介されています。共著に『性の進化論』などがあります。
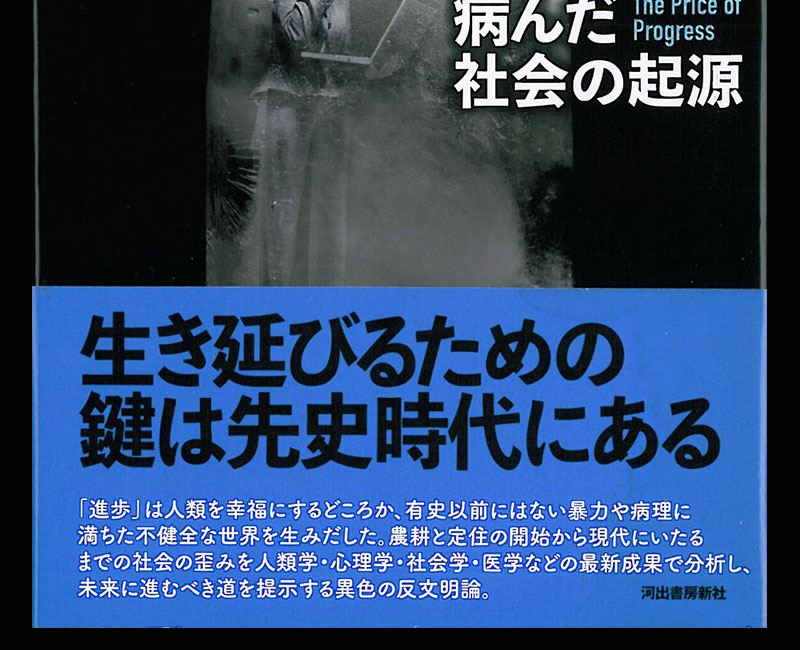 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、モバイルパソコンを開いたまま電話をかけている女性が氷詰めになっている写真が使われ、帯には「生き延びるための鍵は先史時代にある」と大書され、「「進歩」は人類を幸福にするどころか、有史以前にはない暴力や病理に満ちた不健全な世界を生みだした。農耕と定住の開始から現代にいたるまでの社会の歪みを人類学・心理学・社会学・医学などの最新成果で分析し、未来に進むべき道を提示する異色の反文明論」と書かれています。
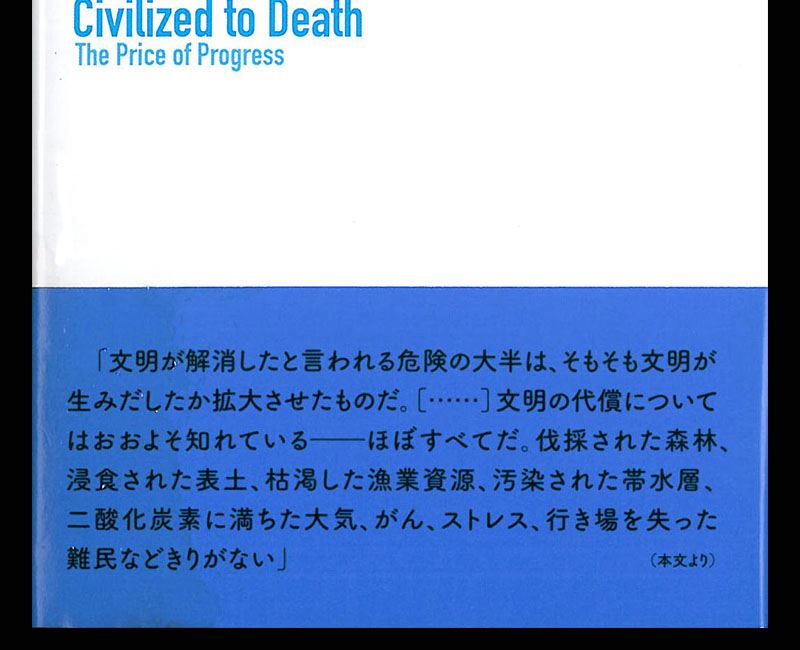 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「文明が解消したと言われる危険の大半は、そもそも文明が生みだしたか拡大させたものだ。[……]文明の代償についてはおおよそ知れている――ほぼすべてだ。伐採された森林、浸食された表土、枯渇した漁業資源、汚染された帯水層、二酸化炭素に満ちた大気、がん、ストレス、行き場を失った難民などきりがない(本文より)」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに「汝の種を熟知せよ」
第Ⅰ部 オリジン・ストーリー
第1章 先史時代を語るとき私たちが話題にすること
第2章 文明とその不調和
第Ⅱ部 永遠の黙示録
(現代の「不断の進歩の物語」)
第3章 野蛮な野蛮人の神話(平和への宣戦布告)
第4章 不合理な楽観主義者
第Ⅲ部 古代の鏡に映る自分
(人間であること)
第5章 自然主義的誤謬の誤謬
第6章 野生児になるべく生まれた
第7章 子育ての深い闇
第8章 荒れ狂う十代
第9章 不安な大人
第Ⅳ部 未来につながる先史時代の道
第10章 終わり良ければすべて良し
第11章 聖なるものが失われたとき
おわりに「ユートピアが必要である理由」
「謝辞」
「訳者あとがき」
「原注と参考文献」
本書は2020年6月に翻訳出版されました。世界中が新型コロナウイルスの猛威に晒されていた最中ですが、はじめに「汝の種を熟知せよ」では、著者は「現在ではワクチンのある感染症の大半は、人類が動物を家畜化して一緒に暮らしはじめ、家畜から病原体がうつるようになるまで一度も問題にならなかった。ほかにもインフルエンザ、水痘、結核、コレラ、心疾患、うつ病、マラリア、虫歯、たいていのがんなど、人類に大きな苦痛を与える病気は数知れない。だが、その2つに1つは、文明がもたらした家畜、過密状態の都市や町、開放下水、殺虫剤に汚染された食物、私たちのマイクロバイオーム〔ヒトの体内にいる微生物がもつゲノム情報の総体〕の攪乱などがなければ生まれることもなかった」と書いています。
カール・ユングは、人びとが過去との結びつきを失って「根無し草」となり、「現在より、未来が運んでくる黄金時代の幻想にふけるようになったが、その幻想に私たちの進化が追いついていない」と嘆いたとして、著者は「『ユング自伝 思い出・夢・思想』を読めば、人類がひたすら未来を夢見ていることを彼が嘆いたのは明白だ」と述べます。ユングは、「私たちは耐えがたい欠乏、不満、不安に突き動かされ、つねに新しいものを追い求める。自分の掌中にあるものではなく幻想に生き、現在の光の中ではなく未来の闇の中にようやく本当の夜明けが訪れると期待する。何であれ良いものは、悪いものによって購われるということを頑なに認めない」と書いているのです。
「孫世代の経済的可能性について」と題する1928年のエッセイで、著名な経済学者のジョン・メイナード・ケインズは1世紀後の世界を想像したことを紹介し、著者は「彼が予測したのは、すべてがいたって順調で、もう誰もお金のために働かずにすむ世界だった。人びとが直面するおもな問題は、じつに長い自由時間をどう過ごすかになる。『人類史上はじめて、私たちは永遠で真の問題に取り組むことになる』とケインズは記す。『どうすれば自由が経済を圧迫しないか、科学と複利によって得た余暇をどう過ごすかが問題になるのだ』」と述べています。
ところが、あれほど恋い焦がれた未来にいるというのに、現代の平均的なアメリカ人は過去にないほど疲弊して絶望し、1970年に負けないぐらいの長時間労働をこなし、1年に2週間の休日を取れれば幸運だと思うことを指摘し、著者は「世界の富がここ数十年で増加しているのは事実だ。しかし、少なくともヨーロッパとアメリカでは、余剰の富の大半はもっともそれを必要としない一部の人に集中し、残りの人びとはますます貧しくなる一方だ」と述べています。
進化生物学者のスティーヴン・ジェイ・グールドが、進歩という概念そのものを「毒のある、文化に根ざした、証明も実現もできない、手に負えぬアイデアであり、歴史のパターンを理解したいなら別の言葉で言い換えるべきだ」と述べたことを紹介し、著者は「グールドより口調は柔らかいが、ジャレド・ダイアモンドも進歩のプロパガンダを信じてはいない。彼によれば、『文明』や『文明の勃興』という表現は、『文明は善きものであり、集団で暮らす狩猟採集民は惨めな存在であって、過去1万3000年の歴史は人類のより大きな幸福に向かって進歩してきた』という誤った考えを暗示する」しかし、ダイアモンドはそんなことは信じないで、「私は工業国が狩猟採集社会より『優れている』とか、狩猟採集から鉄の文化へのライフスタイルの変化が『進歩』を意味するとか、それによって人類の幸福度が増したとか考えてはいない」と書いています。
わたしたちは現在に垣間見える遠い過去の姿、あるいは崖っぷちに向かって突進しているかに思えるときがあるとして、著者は「エデンの園を追放されて農耕を始めたときのような場所を、私たちは必死に探し求めているのだ。私たちが見るもっとも切迫した夢は、眠りに落ちる前の世界を映しているだけなのかもしれない。ことによると、快適さを追い求めた末に退歩した身体が、長時間見つめつづけている画面と一体化しようとして、いわゆるシンギュラリティがすでに現実になりかけているのだろうか」と述べます。
あるいは、他の惑星を植民地化することで、わたしたちの子孫はアップル、テスラ、ラスベガスを代表する高級ホテルのシーザーズ・パレスが提供する宇宙の果てのドームで暮らすことになるのだろうかとして、著者は「もしケインズのように、あなたが物を共有し長い自由時間を愛する人と過ごす平等な世界を望むなら、私たちの祖先がすでにそれに近い世界に暮らしていたことを考えてほしい。だがそれも農耕が始まり、『文明』と呼ばれるものが約1万年前に出現するまでの話だ。それ以来、私たちはその世界からみるみる遠ざかりつづけている」とも述べます。
ありとあらゆる文明は混沌と混乱のうちに崩壊してきました。著者は、「自分たちの文明だけがそのパターンにあてはまらないとなぜ思うのか。たしかに、違いはある。ローマ、シュメール、マヤ、古代エジプト、イースター島などは地域的な崩壊に終わったが、今私たちの目の前で起きている文明の崩壊は地球規模だ。カナダの歴史学者ロナルド・ライトの言葉を借りれば、『歴史が繰り返されるたびに代価は上がる』のである。世界の終わりが問題ではないと思うかもしれない。ベートーヴェンの後期の四重奏曲の崇高な美、宇宙から撮影した地球の写真、DNAの構造にかんする知識なら、その代価はどれほど高くともそれはあなたにとって払うに値するのだろう。地球上の私たちや他の生き物が払っている途方もない代価ですらそうであるに違いない」と述べています。
第Ⅰ部「オリジン・ストーリー」の冒頭を、著者は「この本は、物語――オリジン・ストーリー――の物語である。文明以前、洞窟の壁にオーカーで絵を描いたり、火を操ったりする前ですら、私たちの祖先は物語に魅せられていた。人類初の発明は今もって最強だ。物語を語る者が世界を創造する」と書きだしています。また、「私たちはみな自分たちが何者で、どこから来たかについて、次のように教えられた。先史時代、人類の祖先は飢え、病気、捕食者、隣人との戦いに明け暮れていた。もっとも強く、賢く、冷酷な者だけが、自分の遺伝子を未来に残すことができた。しかも、こうした幸運な者たちさえ、35年ほどしか生きられなかった。ところが1万年ほど前、名前すら残していない天才が農耕を発明し、人類を野獣のような暮らしから豊かな文明、余暇、洗練、充足へ導いた。以来、ときおり小休止はあったものの状況は良くなる一方だった」と述べています。
1651年、トマス・ホッブズは国家が成立する前の人の暮らしを、「孤独で、貧しく、惨めで、野蛮で、短かい」ものだったと評しました。このホッブスの発言について、著者は「3世紀半後、この評はいまだに英語で書かれたもっとも有名な言葉の1つであり、文明以前の人間の生活にかんするホッブズの文明観が文明物語の最大の前提となった。こうしてつくり上げられた『不断の進歩の物語(Narrative of Perpetual Progress〈NPP〉)』は、文明の優越性を当然の事実として認める」と述べるのでした。
第1章「先史時代を語るときに私たちが話題にすること」の「能力と傾向について」では、人間の本質について語るときには、能力と傾向を区別しなくてはならないとして、著者は「傾向は無視したり克服したりできるが、能力の多くは変えられない。海を恐れる傾向を無視することはできても、水の中では呼吸できないという能力の欠如は克服できないのだ。ベジタリアンになることを選択することはできても、草食動物にはなれない。何をどうしようが、私たちは雑食動物だ。どんな選択をするにしても、それは種としての私たちが本来もつ特有の性質の範囲内でなくてはならない。人類は明らかにさまざまな行動を取ることができるが、そのすべてが種としての私たちの性質と同レベルで対応するわけではない。たとえば、少なくとも一部の人は長期間にわたって1人でも生きられるが、人類は社会性がとても強い種であるため、孤立状態は明らかに私たちの性質と相容れない。このことは、独房がもっとも重い罪に対する懲罰であることからもわかるだろう」と述べています。
第2章「文明とその不調和」の「記憶にない門をくぐり」では、農耕の発明は、死に物狂いに生きようとする試みより愚かに思えるとして、著者は「一般に、文明は複雑で高密度な社会で暮らす利点を人類に与える、きわめて安定した良好な環境の当然の帰結と見なされる。しかし、歴史学者のニコラス・ブルックスは、文明の発達を『悲劇的な気候変動に対する無計画な適応から生じた偶然の産物』だと言う。文明は『最後の砦』――崩壊してゆく環境に対する反応だったのである。私たちの祖先は、快適な暮らしを求めて苦しい採食生活を捨てたわけではない。それは良い暮らしへの大胆な歩みとはほど遠く、世界人口が回帰不能点をはるかに超えて爆発するにしたがい、私たちが足を踏み外して悲劇的に落ち込んだ深い穴が農耕だったのだ。そして、その穴は私たち自身が何世紀もかけて掘ったものだった」と述べます。
ジャレド・ダイアモンドが1999年に発表した農耕への転換にかんするエッセイは、不吉にも「人類史上最悪の誤り(The Worst Mistake in the History of the Human Race)」と題されていました。やや時代が下って、歴史家のユヴァル・ノア・ハラリは農耕革命を「史上最大の詐欺」とまで呼んでいます。2014年〔英語版の刊行年〕のベストセラー『サピエンス全史――文明の構造と人類の幸福』に、ハラリは「農耕革命によって人類はたしかに余るほどの食糧を手に入れたが、そのことによって食生活が改善したり余暇が増えたりしたわけではなかった」と記しています。著者は、「豊かな食糧は『人口爆発と飽食のエリート』につながっただけで、農民はたいてい採食者より長く働き、粗末な食べ物に甘んじた。最後の砦として定住地に押し込められた農耕民は、社会的な不平等の激化、組織間の紛争という暴力、一神教を権力の独占に利用する自称エリートなどに耐えねばならなかった」と述べます。
1929年、フロイトは文明の謎を論文「文化への不満(Civilization and Its Discontents)」で、「人類は時空を支配する新たな力、自然のもつ力の征服、古くからの望みの実現を果たしたが、人生に対する喜びは増してはいないし、以前より少しも幸せになっていないことに気づきはじめた」と説明しました。著者は、「1920年代にフロイトがこう書いたとき、人類学、社会学、心理学はいずれも誕生したばかりで、人類が幸福でなくなったのか、そもそも幸福だった時代があったのか(遠く幼いころの記憶は除いて)について、データにもとづいた判断を下すことはきわめて難しかった。しかしフロイトから数十年にわたって集められた証拠を見てみれば、採食者はみずから進んで文明社会に仲間入りしたいと思うことはまずなく――たとえ、それが地上でもっとも厳しい環境に戻ることを意味しようとも、できるだけ早く文明の地を抜けだそうとすることがわかった」と述べています。
農耕は約1万2000年前から約7000年前の約5000年のあいだに世界の少なくとも8か所で芽生えました。肥沃な三日月地帯に加えて、考古学者は中国北部と南部、アンデス地方、中央メキシコ、ニューギニア、エジプト、ミシシッピ川流域、そして西アフリカで採食から農耕への移行を示す証拠を発見しています。肥沃な三日月地帯からこれらの土地に農耕が伝播した証拠はまったくありません。むしろ、似通った気候が農耕への転換をうながしたようだと指摘し、著者は「こうして農耕はさまざまな場所で独立して始まったが、それが人びとの暮らしに与えた影響は絶大で普遍的でもあった。農耕はたんに食べ物を得る手段にとどまらなかった。人間社会のほぼすべての要素(男女の関係、子育て、統治組織、階級制、軍国主義、他の動物や自然一般との関係など)に影響をおよぼしたのだ。物語が変わり、それにつれて世界も変わった」と述べます。
「文明の始まり」の地とされるギョベクリ・テペも登場します。トルコの遺跡には60を超えるT字形の石灰岩の石柱がありました。どの石柱も重さが数トンあります。大半の石柱にはサソリ、ヘビ、イノシシ、ライオンなど危険な動物の姿が浅く浮彫りにされています。著者は、「いずれにしても、ギョベクリ・テペのいちばん驚くべき特徴はそこにないものだろう。人間がそこに暮らした形跡がまったくないのだ。家も、たき火跡も、家畜や栽培植物の化石もない。誰も住んでいなかったのなら、神殿はこの地域で農耕が始まる前に採食者によって建設されたと思われる。そう考えると、採食者と形式的な宗教の起源にかんする定説が覆る。組織的宗教が農耕に先んじて生まれ、やがて農耕が必要になったことになるからだ」と述べています。
ギョベクリ・テペの遺跡を発見したドイツ人の考古学者クラウス・シュミットは、1989年から2014年に他界するまで発掘を指揮しました。遺跡について、シュミットは「ギョベクリ・テペは人の住まいではない。住居として使われた証拠がまったく見つからないのだ。そこで暮らしていたと考えられる人間の骨格化石は近くに1体もない。つまり、残る目的はただ1つ。宗教である。ギョベクリ・テペは世界最古の神殿だ。しかも、ただの神殿ではない。私はこれが集団墓地ではないかと考えている」と語っています。著者は、「シュミットは古代の狩人が死者をギョベクリ・テペに運び、いまだにチベットで行われている『鳥葬』のようにハゲタカなどに遺体を食べさせたと信じている」と述べます。
シュミットは、この地域を「元は天国のような場所だった」と述べています。著者は、「あれほど壮大な神殿を建設する人びとを養える食糧を供給したのだから、まさにその通りだろう。シュミットはジャーナリストのエリフ・バチューマンに、『彼らは大きな宴を催しただろう』と語った。ことによると、ビールやより強力な幻覚作用のある物質もあったかもしれない。そうした村落への移行は比較的楽だったと思われる。数世紀続いたこの長い夏のあいだ、暮らしは気楽で贅沢なものだった。獲物はたくさんいて、いたるところに果物、木の実、種子植物があった。ピダハンと同じように、これらの原初の村の人びとは周りの世界に感謝していたはずだ。ときには試練を与えることもあったとはいえ、豊かで多くを与えてくれたのだ」と述べます。
ギョベクリ・テペの環境は豊穣そのもので、人びとは移動して翌日の食べ物を探す必要がなかったといいます。著者は、「彼らが定住したのはもっとも豊かな谷や川の流域で、周りの丘で動物を狩ったり、食用の植物を集めたり、川に網を入れて夕飯を獲った。この豊かさから複雑な文化が生まれ、なかには定期的に集まって交易、結婚、物語をする人びともいた。ギョベクリ・テペでは、神聖な神殿で死者を弔う儀式が行われた。これらの神殿は、人類が発見したというより――おそらく史上はじめて――建設したものだった」と述べています。これを読んで、『唯葬論』や『儀式論』の著者であるわたしの胸の鼓動は高まりました。いつか、ギョベクリ・テペを見学しにトルコを訪れてみたいです。そうだ、トルコなら、かのアララト山にも行ってみたい!
いったん始まると、農耕は後戻りできない一方通行のプロセスでした。著者は、「それにしても、彼らに選択の余地があっただろうか。目の前の困難を生き抜こうと死に物狂いのときに、人類が踏み入れたことのない道を自分が選んでしまったと気づくのは、あとになってからだ。この道は、種の誕生以来親しんできたすべてから私たちを引き離す。農耕は単位面積あたりの食糧生産高を一時的に増やす――採食100倍になることもしばしばだ――ので、すでに人口過密となった地域にさらに空腹を抱えた人びとが殺到した。農耕は多くの労働者を必要とするため、土地所有者は安い労働者を大勢必要とした。所有権――それまでは好みの槍、首飾り、衣服などに限られていた――が、ほとんど魔法のような力を発揮した。いまや人は土地のみならず、余剰の食糧や種子、水源、動物を所有できるようになり、やがては人間をも所有するようになった。乳児は家畜の乳でも育つので、女性は出産後1、2年で妊娠可能になった。こうして、たいてい3、4年は母乳を与えるためその期間は妊娠できない採食者より出生率が高まった」と述べています。
人口流入と変動する食糧供給(収穫期と次の収穫期までの待ち時間)が意味したのは、厳格な階層性の早急な確立と労働の特化が不可欠であるということだったと指摘して、著者は「人びとの労働を管理し搾取する祭司と統治者が必要になった。毎年の収穫を守り、スケジュール通りに植えつけを行い、盗人を捕まえる警備の者を雇い、しかるべ給金を支払わなくてはならなかった。定住地に蓄積された富を略奪から守り、周辺の定住地を襲撃して富を盗むための兵士も必要だった。土地や動物を所有する者と、自分の時間と汗と苦しみ以外に売るものをもたない者を分ける経済格差は広がるばかりだった」と述べます。
定住地内でも定住地間でも、さまざまな争いが起きるのは避けようがありませんでした。農民の出生率がかなり高かったので、増える一方の人口を養うにはもっと土地が必要だったとして、著者は「こうして現代を支配する強欲な経済成長の神が誕生した。成長しつづける経済は強引に拡大した。まず、新たな世代の農民に土地を与える、次に、燃料のための森林伐採によって雨に浸食され、もはや土壌の流出を止められないかつては肥沃だった土地と入れ替える。基本的に、拡大しつづける農耕社会は土地を消耗し疲弊させる。『野蛮人』や『未開人』はことごとく殺されるか追い払われ、新たなサイクルが始まるのである」と述べます。
「世界一善良な人びと」では、歴史は文明人と先住民が出会うときに起きる類似の出来事に満ちているとして、著者は「他の文明が残虐性に欠けるわけでもない。アステカやマヤの人柱、古代ローマやアフリカの一部の帝国の奴隷制、モンゴルの遊牧民によるレイプや略奪など枚挙に遑がない。歴史を眺めてみると、自分たちを「文明人」と考える人びとは、その他の人びとを人間以下だから使い捨てていいと考える。力をもつ者にとっては力こそ正義なのだ」と述べます。また、「仮に、ありとあらゆる人間が実際に等しく人間的であると認めたとするならば、文明社会には組織的な残虐性が共通するのに反して採食社会に稀または皆無である理由を、人間の本質によって説明できないのは明白だ」とも述べます。
コロンブスの新大陸発見について、著者は「スペイン人に暴挙を許したのは人間の本質ではなかった。文明だったのである。文明ゆえに優れた武器をもつ自分たちは他に優れている、とスペイン人は信じ込んだのだ。文明は不衛生な都市を生みだし、結果的にスペイン人の祖先は病原体に対する免疫を獲得したが、北・中央・南アメリカでは、何百万もの人びとが病原体の前になすすべもなく死に絶えた。文明の影響によってコロンブスと部下たちは、黄金が、それを得るために殺した人びとの命より貴重だと確信した。文明は彼らの心を捻じ曲げ、愛と慈悲を説く救済者が、世界一善良な人びとを奴隷にし、殺し、傷つけることを認めた。いや、そう要求したとすら思わせた」と述べます。
さらに、文明人について、著者は以下のように述べます。
「『文明人』――アステカ人であろうがオーストラリア人であろうが――は、自分たちがいわゆる野蛮人よりましだとずっと思ってきた。実際には、文明社会の人が『先住民の暮らし』に戻った事例は何千も記録されているが、先住民が他の選択肢がある場合にみずから望んで文明社会を選んだ事例はほとんど記録にない。真に優れた社会であれば強制的に新たな住人を募る必要もないのだろうが、これから見ていくように、歴史は人を強制的に集めた事例に満ちている」
「マルサスの計算間違いとホッブズのホラーショー」では、トマス・ホッブズは鬱屈を内に抱えた男だったとして、著者は「生まれる前でさえ、母親の胎内で恐怖と共に過ごした。スペインの無敵艦隊がイギリス沖に迫り、今にも攻撃をしかけてきそうだと知ったとき、母親は産気づいて彼を早産した。ホッブズは『私の母親は私と恐怖という双子を産み落とした』と述べた。ホッブズはとうにこの世の人ではないが、恐怖はいまだに生きつづけている。その後も、ホッブズの人生はあまり生きやすいものにはならなかった。著書『リヴァイアサン』で展開した有名な議論で彼は、市民を自然の破壊と内なる野蛮な衝動から守ってくれる強い国家を支持すると述べた」と書いています。
「恐怖の機能」では、進化生物学者のリチャード・ドーキンスが取り上げられます。彼は存命中の科学者の中でももっとも有名な1人であり、過去に語られた中でいちばん暗い物語を熱心に語ると紹介し、「著書『遺伝子の川』で彼は、動物の生涯は飢えと、惨めさと、情け容赦のない無関心という試練の劇場なのだと記す。『自然界で1年間に起きる苦しみの総量はあらゆる予想をはるかに上回る』と手を震わせながら書く。『私がこの文章を書くあいだに、数千頭もの動物が生きながら食われ、多くの動物が恐怖に哀れっぽい声を上げながら逃げまどい、寄生体にゆっくり内側から貪り食われ、あらゆる種類の無数の動物が飢え、渇き、病気で死にかけている』」と書いています。
ドーキンスの物語では、最高の時も最悪の時につながります。著者は、「豊かな時代があったにしても、それが自動的に人口増につながり、やがて飢えと惨めさの自然な状態(…………)が戻ってくる」というドーキンスの言葉を引用し、「この言葉をよく味わってみよう。生き物の『自然な状態』は『飢えと惨めさ』なのだ。まさに旧約聖書そのものではないか!」と述べます。さらに、「死後を恐れる理由はあるだろうか」という問いに対して、マーク・トウェインの「私は死を怖いとは思わない。なぜなら生まれる前に何十億年も死んでいたし、それで不便だったことなど一度もないからだ」という言葉を紹介します。著者は、「しかし、NPPは警告する。そこにはジャングルがあって、『身体の内側から気味の悪い寄生虫に食われる』のを防げるのは文明が張りめぐらす壁のみで、自然は歯と爪を朱に染めて襲撃の時を待っている、と」と述べるのでした。
「原始的な力」では、20世紀にもっとも影響力のあったノンフィクションの1つである『利己的な遺伝子』のもっとも下線が引かれたであろうくだりで、リチャード・ドーキンスは自分の奥深くに潜む自然な傾向を出し抜いてほしいと読者に語りかけるとして、「『寛大さと利他主義を教え込んでみよう』と彼は書く。『なぜなら、私たちは利己的だからだ。利己的な遺伝子が何を企んでいるのか見てみよう。そうすれば、遺伝子のデザインを変えることができるかもしれない。そんなことを試そうと考えた種は他にいない』。扇情的な説だが、遺伝子が本質的に利己的で、私たちがチンパンジーとボノボと約98%の遺伝子を共有し――その他の哺乳動物とはやや少ない割合の遺伝子を共有し――ているのであれば、なぜ私たちの利他主義が遺伝子によってプログラムされた形質に対する勝利になるのか。アリ、イルカ、ハチ、群生動物、霊長類の多くに見られる利他性は、彼らの遺伝情報となぜか矛盾しないというのに」と述べています。
ドーキンスは存命中の科学者ではダーウィンの功績を世に広めた最大の功労者だろうが、2者の人間の本質にかんする考え方は正反対と言えるとして、著者は「ドーキンスが人間を特異な存在と考えるのに対して、ダーウィンを特徴づけるのは『人間と動物の精神の違いは大きいとはいえ、それは間違いなく程度の問題であって種類の問題ではない』という確信だ」と指摘し、さらに「ドーキンスにとって「他者の苦しみに対する無関心は自然選択の必然的な帰結である」が、ダーウィンはこれには異を唱えるだろう。ダーウィンは思いやりと利他主義が、社会的な動物に明らかな進化上の利点を与えると考えていたからだ。彼はノートにこう記している。『自然主義者は種々の哺乳類を見るように人間を観察し、人間には親となる本能、婚姻の本能、社会的な本能が備わっていると結論づけた……これらの本能は対象に対する愛情と善意から成る……共感は強く、人は我が身を忘れ、我が身を犠牲にしても他者を助け、守り、手を差し伸べる』。これがダーウィンの終生変わらぬ考えであり、他界する11年前に上梓した著書『人間の由来』におそらくもっとも雄弁に語られている」と述べるのでした。
寛大さと親切心は人間の本質であり、血に染まった床を覆う安物の敷物さながらに、私たちの生来の利己心を覆い隠すべく文化によって植えつけられた皮相的な道徳ではないと指摘する著者は、霊長類学者のフランス・ドゥ・ヴァールの「私たちが社会的になった時点というものはない。サルや類人猿などのきわめて社会的な祖先の子孫として、私たちははじめから集団で暮らしてきたのだ」という言葉を紹介します。ドゥ・ヴァールは、わたしたちは生まれつき互いに協力するようにもっとも深いレベルでできていて、ダーウィンと同じく道徳の基盤は進化のプロセスによって生まれると信じています。したがって、道徳は「人間がつくり出したただのうわべ」ではなく、「集団で暮らす動物としての人類史の一部であり、霊長類としての私たちの社会的本能に深く根ざしているのだ」と訴えるのです。
第3章「野蛮な野蛮人の神話(平和への宣戦布告)」の冒頭には、ドナルド・トランプの「人間はあらゆる動物の中でも邪悪な生き物の最たるものであり、その一生は勝利か敗北に終わる戦の連続である」という言葉が引用されています。1924年にアフリカで人類の祖先の化石人骨をはじめて発見した人類学者レイモンド・ダートは、初期人類について述べたときに、忘れがたいほど陰惨なイメージを「不断の進歩の物語(NPP)」につけ加えました。彼によれば、初期人類は「肉食性で、生きた獲物を力任せに捕まえ、死ぬまで打ちすえて……犠牲になった獲物のまだ温かい血をすすって渇きをいやし、土気色になって痙攣する肉体を貪り食う」というのです。
獲物の温かい血をすすり、動物の肉を貪っていないときは、我らが祖先は互いを見つめて舌なめずりしていたとして、著者は科学ジャーナリストのニコラス・ウェイドが『ニューヨーク・タイムズ』紙に寄せた記事を紹介します。その記事には、「国家以前の社会間では戦争がたえず起きていた。その容赦なき戦争は、たいてい敵の殲滅を目的としていて、その目的はしばしば達せられた」。共著『男の凶暴性はどこからきたか』で、人類学者のリチャード・ランガムとデイル・ピーターソンは、現生人類を『500万年続いた死闘の習慣の生存者』と形容した」と書かれています。
第4章「不合理な楽観主義者」の冒頭を、著者は「子爵にして、イギリス貴族院の世襲議員、イギリス大手銀行の元CEOの肩書きをもつマット・リドレーは、心配ないと言う。ハッピーでいよう、すべては順調で、良くなる一方だ、と。進歩への凱歌を手放しで謳い上げる著書『繁栄――明日を切り拓くための人類10万年史』でリドレーは、楽観主義者は不公平に扱われがちだと述べ、20世紀の保守的な経済学者フリードリヒ・ハイエクの次の言葉を引用する。『進歩に恩恵があるという暗黙の了解は甘い考えと見なされるようになった』」と書きだしています。
「国民の健康」では、リドレーが「大多数の現代人は……病気から守られている」という一般的な考えを繰り返すことについて、著者は「しかし実際には、私たちの大半は石器時代の人より厄介な病気にはるかにかかりやすい。理由はとても簡単だ。限られた例を除けば、人間にとってもっとも致死性の高い感染症は先史時代には存在してもいなかったからだ。感染症は文明の産物なのである。農耕以前には、人間が家畜と一緒に暮らすことはなかった。一緒に暮らすようになって、家畜から人間にとって危険に変異した病原体がうつるようになったのだ。農耕が始まってはじめて、結核、コレラ、天然痘、インフルエンザその他人間にとって悩みの種である病気の病原体が人間を宿主とするように変異し、人口密度の高い都市部で広まった」と述べています。
同じことは、感染症以外で人類にとって生死にかかわる病気の多くについてもあてはまるとして、著者は「これらの病気は、文明によって引き起こされたのであって、文明によって軽減されたわけではない。私たちの進化した肉体と、西洋文明の影響によって変化する食事やライフスタイルとの不一致が、文明病の多くの原因となった。冠動脈性心疾患、肥満、高血圧、2型糖尿病、多様ながん、自己免疫疾患、骨粗鬆症――これらはすべて採食者のあいだでは稀か存在すらしない」とも述べるのでした。たしかに、いわゆる成人病と文明との関わりは深いかもしれませんね。
1930年代に、ウェストン・プライスというアメリカの歯科医が世界中の民族を調べ、歯の健康にどのような条件が望ましいのかを知ろうと考えました。プライスは、アラスカ、カナダのユーコン準州、ハドソン湾岸、ヴァンクーヴァー島、フロリダ州、アンデス山脈、アマゾン、サモア諸島、タヒティ島、ニュージーランド、オーストラリア、ニューカレドニア、フィジー島、トレス海峡、東アフリカ、ナイル川流域を旅して回りました。著者は、プライスが「どの場所でも、彼は同じ現象に遭遇した。伝統食を食べている人の歯は健康そのものだった。ところが『現代的な食事』に移行するに従って、虫歯、抜けた歯、その他の異常が増えた」と述べています。
プライスの洞察は農耕以前の人びとの古人骨によって裏づけられたとして、著者は「現代人の多くが抱える虫歯や歯茎の病気は、文明発祥後に穀物中心の食事と単一栽培が始まるまでは存在しなかったことが古人骨によって確認されている。たとえば、現代のスーダンで発見された古人骨を分析した科学者たちは、当時この地域で暮らしていた狩猟採集民で虫歯のあった人は1%に満たないことを突き止めた。しかし農耕が始まると、この割合は見る間に約20%に増えた。食事が人類の進化と一致していれば、虫歯はできず、私たちの身体は虫歯を治せるようにできているという証拠すらある」と述べます。
第Ⅲ部「古代の鏡に映る自分(人間であること)」では、「人間の本質とは?」と問いかけることは、「水の自然な状態は何か」と問うようなものだとして、著者は「答えはあまりに多くの条件によって変わる。水が液体、個体、気体のいずれの状態であるかが温度や圧力によってはっきり変わるように、人間は平等主義にして利己的、暴力的にして平和的、協力的にして競争的でいられる。どちらに転ぶかは文脈によるところが大きい。そこで科学者の多くは、人間の本質について語ることを止める。『私たちはとても適応性が高い』と彼らは言う。『私たちの「自然な行動」は多岐にわたる』。それはある程度正しい。だが、それでは答えとして十分ではない」と述べています。
「文明は史上最大の詐欺だ」と訴える著者は、「それは私たちに無料のものを壊すように仕向け、代わりに高価で劣化したコピーを売りつけようとする。しかも、このプロセスはしばしば私たちが無料のものを壊して得たお金で動いている。小川、河川、湖、帯水層を、産業廃棄物、流出する殺虫剤、水圧破砕法で出る化学物質で汚染し、水を『きれいな泉の水』(ただの水道水であることが多い)と称してプラスチックボトルに詰めて売る。ボトルはマイクロプラスチックに分解されて海、クジラの胃、私たちの血液中に入り込む。今一生懸命働けば、あとで楽になる。友人や家族のことは忘れて頑張って金持ちになったら、いつかは誰かに愛してもらえる。文明の声は偽りの欲望を私たちに吹き込み、ほんのわずかな満足感をいっとき売り込むが、満足感は見る間に消え去ってしまう」と述べます。
第9章「不安な大人」の「勝って負ける方法」では、著者は赤ワインがとても好きだというエピソードが紹介されます。度を越すほどに好きだそうですが、それでも、いつもは10ドルのボトルで十分と思っているとか。著者は、「たまに友人の勧めで20ドルのボトルに手を出すこともある。私はワインに詳しくはないが、あまり頼りにならない舌で、その価格帯のワインをおいしいと思ったときのことは記憶している。たぶんその記憶は、そのとき食べていた食事、一緒だった友人、遠くの山並みに沈みゆく夕日、火から上る薪の燃える匂いと大いに関係しているだろう。それでも、そのとき飲んだワインより2倍おいしいワインがこの世にあるとはとても思えない。40ドルでも、4000ドルでも。それに、ワインを2倍飲んだら楽しさが倍になるとは限らない」と述べます。
そのときのリオハ産のワインの記憶が文脈によって強化されているとすれば、それこそ著者の言いたいことであるといいます。つまり、「問題はワインではなく経験なのだ。たいていの物にはその質に上限があり、そこには結構すぐに達する。もしそうでないとしたら、あなたが求めているものは、製品そのものというより、その製品によって満足すると確信していたあなたの心理と関連している。時計は時間を教えてくれるが、2万ドルのロレックスはあなたが問題を抱えていることを教えてくれる」というわけです。
第Ⅳ部「未来につながる先史時代の道」の第10章「終わり負ければすべて良し」の冒頭を、著者は「論文『文化への不満』でフロイトは、文明人に蔓延する病理は主として本能的な性欲の抑圧に帰すると主張した。蒸気機関の時代であることを考えるなら、封じ込められ、圧力をかけられ、自然なはけ口がなく、より生産的な目的に転用される根本的な欲望という概念にもとづいて、フロイトが文明を解釈したのも驚くには当たらない。フロイトにとって文明とは、快楽の拒絶、あるいは少なくとも先延ばしや転用によって生じるのだ。たしかに、それも大いに関係していようが、私に言わせれば、ピラミッド、聖堂、国防総省、ウォール街、中国の万里の長城も、私たちを人として定義する死の認識を拒否することによって生ずる、文明のもう1つのヒステリーの表れでもある」と述べています。
著者は、『死の拒絶』でアーネスト・ベッカーが述べた「自分が死ぬという考え、その恐怖が他の何より私たちの心を捉えて離さない。それが人間活動――おもに死の宿命を回避し、それが自分たちの定めであることを何とか否定して乗り越えるための活動――の動機なのだ」という言葉を紹介します。しかし、いずれ夜がやって来るように、死は避けられないとして、著者は「私たちは、死というものを、昼の光を翳らせる無数の小さな影に分けたにすぎない。死の闇を避けられない。私たちは、死というものを、昼の光を翳らせる無数の小さな影に分けたにすぎない。死の闇を避けようとパニックを起こすことで、私たちは人生を照らしてくれる光を台無しにしているのだ」と述べます。
死が身近にあった採食者は、最期のときはいずれ訪れると理解していました。著書『昨日までの世界――文明の源流と人類の未来』でジャレド・ダイアモンドは、高齢か末期症状の採食者が死の旅路に出る一般的な5つの方法について描写しています。「一部の社会では、彼らはただ放置されて死ぬ。野営地を変えるときに、死にゆく人を置き去りにする社会もある。イヌイット、クロウ、ヤクートなどの人びとは、死にゆく人に海に入ったり崖から飛び降りたりして自死するようにうながす。もっと積極的なやり方では、首を絞めたり後頭部をたたいたりして「自発的な」自殺に手を貸す。最後の方法では、その人がもう集団についていけなかったり、集団全体の繁栄に貢献できなくなったりしたときに、同じことを本人に知らせることなく、あるいは本人の同意なしに行う」というものです。
第11章「聖なるものが失われたとき」の「神の声が聞こえる」では、心理学者のスタンリー・クリップナーが変性意識状態(ASC)(日常と異なる意識の状態)が種々の文化でどう使用されるかを生涯かけて研究してきたことが紹介されます。彼によれば、研究者たちは次のような事実を発見したといいます。「488の社会で……89%が、何らかの形で[ASCを]多くは儀式か霊的な文脈で経験した。自発的なものもあれば(シャーマンが『天上世界』に『旅する』など)、部分的または完全に強制的なものもあった(肉体を離脱した実体が霊媒の身体に『乗り移ったり、支配したりして、霊媒の人格と入れ替わる』)」。クリップナーは、文化がどうASCを受容するかによってその状態が起きる頻度が変わると結論づけました。
クリップナーは、「幼児期の体験を自然に思いだす人がもっとも多いのは、輪廻を信じる文化集団だ。けれども、輪廻を信じない西洋諸国でもいくつか事例はある。そうした事例が西洋諸国で少ないのは、起きる頻度が少ないか、体験した人が異常な人格と決めつけられたり、信用されなかったりするのを嫌って話したがらないからだ」と述べます。クリップナーによれば、この考えを論理的に突き詰めると、「ASCに楽に入る能力は高い順応性をもつはずである――意識の状態によって活性化される偽薬などの癒しの力を増す――から、この能力をもつ人は先史時代の社会では、『選ばれし者』と考えられた」といいます。著者は、「このような意識の状態やその癒しの力を否定する現代社会では、それを選択する進化圧が減り、世代を重ねるごとにそのような能力が弱くなったのだろう」と述べています。
文明人は、危険を察知したらそれを排除するか弱めようとします。やられる前にやるのだです。著者は、「赤ちゃんを無菌の保育器に入れる。武器をもつ警備人が配備され、金属探知器が設置され、教師は泣く子に手を触れることすら法によって禁じられている学校に、自分の子どもを送り出す。地球上のあらゆる場所に爆弾を落として、殺した以上の数のテロリストを生みだす。問題行動のある子の言葉に耳を貸さず、薬を与えて黙らせる。これではうまくいくわけがないし、金輪際うまくいかないだろう。この事実に、私たちは少しずつながら気づきはじめているようだ。私たちの生存は、生命に対する危険を排除することではなく、私たちを恐怖に陥れるもの――ASCなど――を認知し受容することにかかっている」と述べるのでした。
「眼を覚ませ、自己を解放し、はみ出せ」では、ほとんどすべての社会で、幻覚剤は神が人類に与えたもうた最大の贈り物だと考えられてきたことを指摘し、著者は「アマゾンのアヤワスカ、メキシコのウィチョル人が使うペヨーテ、アフリカのイボガ、シベラやインドのベニテングタケ、1950年代に欧米の精神科医のオフィスにあったLSDなどの幻覚剤は、畏怖、儀式、尊敬の念を忘れずに使用すべき聖なる薬物と考えられてきた。唯一の例外は現代である。今日では、依存性も毒性もないこれらの薬物を所持しているだけで、残りの人生を檻の中で過ごす羽目になる」と述べています。
キリスト教が入ってきてその使用が禁止されるまで、ヨーロッパ先住民の祈祷師(ヒーラー)たちはベニテングタケやヒキガエルから採れる成分を含む水薬を用いていたと指摘し、著者は「ヒキガエルには、皮膚に2種の強力な成分――5-メトキシ‐N、N-ジメチルトリプタミンとブフォテニン――を含む種がある。ベニテングタケもヒキガエルも強力な毒性をもつため、水薬を飲むのではなく、身体の粘膜を通して血液中に取り込まれる。初期のヒーラーの多くは女性であり、歴史家の報告によれば、ファルス(ペニス)の形をした棒をこの『秘薬』に浸し、膣粘膜にこすりつけたり膣に挿入したりする摂取方法もあったという。こうした治療を止めさせようとするキリスト教の運動は、ヒーラーの女性を魔女呼ばわりしたため、『魔女』は今日でもファルスに似たほうきに乗っている」と述べます。
著者は、ニクソン大統領の薬物禁止政策にも言及し、「ヒッピーとアフリカ系アメリカ人を攻撃しようと急ぐあまり、アメリカ大統領でもっとも嫌われ者のニクソンは幻覚剤をすべて違法にすることで、数十年かけて積み上げてきたこれらの薬物の癒し効果にかかわる研究をドブに捨ててしまった。しかし、幻覚剤はアメリカと世界の文化に影響を与えつづけた。幻覚剤の存在がなければ、20世紀後半の数十年における音楽、絵画、映画、科学の飛躍的な発展を想像することは難しい。DNAの二重らせん構造を発見したフランシス・クリックは昼日中から薬物でトリップしていたし、サルの着ぐるみを着て『抱きしめたい』を歌っていたビートルズは『ストロベリー・フィールズ・フォーエバー』へと曲想を変えた。スティーヴ・ジョブズは、LSDを試したときの経験を『私の人生で2、3度あったもっとも重要な出来事の1つ』と述べた」と書いています。
「神聖な幽霊」では、「現実」の定義を聞かれたとき、有名なSF作家のフィリップ・K・ディックは、「現実とは、あなたがその存在を信じなくなっても消えないもの」と答えたことが紹介されます。著者は、「すばらしい答えだが、現実の重要な側面を忘れている。信じれば存在するが、だからと言って現実でないとも言い切れないものもあるからだ。幽霊がろうそくを倒すのを見たとしたら、幽霊の存在について議論する前に火を消すべきだ。不可思議な体験をしたら、まだその現象が起きるメカニズムを説明できないことはさておき、その現象の結果によって判断するのが賢明というものだ」と述べます。
幻覚剤研究を支持するヘフター調査研究所の設立メンバーのデイヴィッド・ニコルズは、「サイエンス」誌に掲載されたインタビューで、幻覚剤を用いる治療の「現実性」について尋ねられたとき、「もし、その治療によって患者が平穏な気持ちになるのであれば、あるいは枕元に駆けつけた友人や家族に見守られて安らかに逝くための助けになるなら、私はそれが現実であろうと幻想であろうと気にしない」と答えました。著者は、「その通りだ。それに、『現実』と『幻想』の区別はそのような場合には曖昧になる」と述べています。
そして、科学について、著者はこう述べるのでした。
「科学が、私たちにわかっている宇宙を照らす最強の光の1つであるのは間違いない。だが、科学の光には影があり、その存在は幽霊のように頼りない。科学で証明できるもの以外は存在しないと言う人は、目を閉じて耳を塞ぎ、目に見えないから世界は消えたと想像する子どものようなものだ。昨今のいわゆる新無神論者が熱心に説く信念の核心に巣食う虫は、人の宗教的信条にあるさまざまな要素が真実でないことは証明ずみなので(たとえば世界のあらゆる動物はノアの箱舟の子孫であるとか、地球はわずか7000年前に創られたとか、この神はあの神よりえらいとか)、彼らの宗教的な経験は現実ではないという確信だ。この見方の根本的な誤りはデジタルな世界観にある――物事はつねに真か偽である。イエスかノー。オンかオフ。死か生。0か1。しかしながら人生は、客観的な現実と経験が信念の渦巻きによってコーヒーとクリームのように分かちがたく、おいしい混じり合った瞬間に満ちている」
「ハルマゲドンの長所」では、著者は「文明が崩壊したとき、わたしたちは人間の本性を目の当たりにする。だが、私たちをホッブズが描いたような暗黒の世界から守っているはずの権力構造が破綻したとき、じつは天国が訪れるのだ」と述べます。著書『災害ユートピア――なぜそのとき特別な共同体が立ち上がるのか』で、レベッカ・ソルニットはさまざまな文化の人びとが災害時にどう行動するかを調べ、人はそういう状況で略奪行為に走るのではなく他者に手を差し伸べることを見いだしました。社会学の文献と災害を生き延びた何百人もの体験とを調べ、「人間が災害時に利己的で、パニックに陥り、野獣に戻ったかのように変わるというイメージは完璧に間違っている」と彼女は結論づけたのです。
災害のナラティブを180度転換し、ソルニットは「大半の場所では日常生活こそ災害であり、その日常が破られたときに変化を起こすチャンスが訪れる」と述べました。著者は、「おわかりだろうか。上が下で、黒は白、地震、津波、地滑りは真の災害ではないのだ。むしろ、これらの出来事は、たいていの人が『日常生活』と呼ぶ、いつも通りの、ありふれた災害が途切れる瞬間なのだ」と述べます。この大胆な見方は災害研究の創始者の1人、チャールズ・E・フリッツというアメリカの社会学者が提起したものです。フリッツは、自然災害(人為的災害も)はそれを生き延びた被害者を抑圧的な日常から解放すると考えました。災害時に自然に起きる人どうしの相互作用は、通常の狩猟採集民の生活に際立った類似性を見せるとフリッツは述べ、災害は「物理的には地獄かもしれないが、一時的とはいえ一種の社会的なユートピアを形成する」と主張します。
「すべての探求の行き着く先は」では、未来への一歩が過去への一歩であるという考えが矛盾して聞こえるなら、冬が一日過ぎるごとに夏の暖かさに近づくとともにそれから遠ざかってもいることを考えてみようと提唱し、著者は「啓蒙時代はきわめて進歩的な時代であったとともに、古代ローマと古代ギリシャに代表される過去への讃歌でもあった。ホモ・サピエンスの起源と本質を反映する人間の動物園をデザインし直す行為は、過去と共鳴する第二の輝かしい啓蒙時代の幕開けとなるだろう」と述べます。ラコタのシャーマンであるブラック・エルクは、「世界の力が成すことはすべて円を描く」と言いました。彼はまた、「空は丸く、地球も星もボールのように丸いという。いちばん強い風は渦を巻いて吹く……太陽は円を描いて昇って沈む。月の運行も同じだ。どちらも丸い……人生は子ども時代から子ども時代への円環であり、自然の力が宿るものはすべて円環なのだ」とも言っています。
「訳者あとがき」を、鍛原多惠子氏は「人類は進歩してきた。あらゆる困難を乗り越え、豊かで便利な今日の暮らしを手に入れた。私たちの多くはそう考えている。たしかに、世界は着実に進歩しつづけてきたかに見える。だが、人類は本当に進歩したのだろうか。進歩に深い信頼を寄せてきた結果、途方もない代償を払う羽目に陥っていないだろうか。本書の著者クリストファー・ライアンは、そう問いかける。また現在の窮状は私たちがみずから招いたというより、文明の本質がもたらしたものだとも言う。もちろん著者は文明が与えてくれた数多の恩恵を忘れてはいないし、ただ狩猟採集の世界に逆戻りしようと提案しているわけでもない」と書きだしています。
では、私たちが当然のこととして受け止め、疑いもしない「進歩」とはいったい何なのだろうと問いかける鍛原氏は、「著者によれば、進歩の概念はイングランドの哲学者トマス・ホッブズにさかのぼる。ホッブズは有名な国家論『リヴァイアサン』で、文明が誕生する以前の人間の暮らしについて「人生は孤独で、貧しく、惨めで、野蛮で、短い」と述べた。この文明観が、私たちが語る文明物語の最大の前提となった。そこから『不断の進歩の物語(Narrative of Perpetual Progress〈NPP〉)』が生まれ、『今日はかならず昨日に勝る』という考えが広まった。こうして生まれた進歩の概念は、著者が『ネオ・ホッブズ派』と呼ぶ人びとに受け継がれた。ネオ・ホッブズ派として著者は、マット・リドレー、リチャード・ドーキンス、スティーヴン・ピンカーなどの名を挙げる)」と述べます。わたしは「明日は今日より素晴らしい」と信じている人間なのですが、ネオ・ホッブズ派に属するのでしょうか?
わたしたちが文明のせいで苦境に立っているにしても、「一体どのような経緯でそうなってしまったのだろうか」と問う鍵原氏は、「著者によれば、始まりは狩猟採集から農耕への移行だった。農耕から富、権力、国家が生まれ、経済が人の暮らしを支配するようになり、科学技術の発達とともに新種の病気が生まれた。マーティン・ブレイザーやダニエル・リーバーマンなどが指摘するように、現代人は糖尿病、がん、感染症、うつ病など数々の病気に悩まされている。現在、世界を震撼させている新型コロナウイルスがまさにその典型だ。一般に、狩猟採集民に比べて現代人の寿命は延びたと考えられている。しかし、著者はこの考えは間違っていると指摘する。私たち現代人は長寿になったというより、死のプロセスを長引かせているだけだというのである」と述べます。
最後に、鍵原氏は「死の恐怖や痛みを緩和するため、過去には世界各地で種々の自然由来の薬物が用いられていた。だが現在ではその多くが違法とされている。これについても、著者はこれまでとは違った取り組みが望ましいと考えている。もちろん、こうした薬物の医学的使用には慎重な研究と法整備が欠かせないが、計り知れない恩恵が得られる可能性がある。しかし、古くから親しまれてきた薬物の使用が厳しく規制される一方で、過剰な医薬品投与や不要な医療介入に歯止めがかからないのが現状だ。文明が自然で安らかな死を迎えられないことを意味するのであれば、果たしてそれは真の進歩なのだろうか」と述べるのでした。本書全体の中で、この箇所が最も考えさせられました。思想的には、著者の考えとは違うマッド・リドレーやスティーブン・ピンカーに共感するわたしですが、本書は非常に面白かったです。これまでに文明が発展してきた果てに、現在の多死社会があることを忘れてはなりません。そして、問われるべきは「死」ではなく「葬」であると改めて思うわたしでした。