- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2022.12.14
『ブループリント』上下巻、ニコラス・クリスタキス著、鬼澤忍・塩原通緒訳(PUBLISHING)を読みました。「『よい未来』を築くための進化論と人類史」というサブタイトルがついています。「つながり」と「利他」こそが人間の本質だと訴える本書は、一般読書界や学術界のみならず、ビル・ゲイツ、エリック・シュミット、マーク・アンドリーセンらビジネス界のトップランナーからも熱烈に支持され、ニューヨークタイムズ・ベストセラーになりました。
著者は、イエール大学ヒューマンネイチャー・ラボ所長、およびイエール大学ネットワーク科学研究所所長。医師。専門はネットワーク科学、進化生物学、行動遺伝学、医学、社会学など多岐にわたります。1962年、ギリシャ人の両親のもとアメリカに生まれ、幼少期をギリシャで過ごしました。ハーバード・メディカルスクールで医学博士号を、ペンシルベニア大学で社会学博士号を取得。人のつながりが個人と社会におよぼす影響を解明したネットワーク科学の先駆者として知られ、2009年には「タイム」誌の「世界で最も影響力のある100人」に、2009年~2010年には2年連続で「フォーリン・ポリシー」誌の「トップ・グローバル・シンカー」に選出されるなど、アメリカを代表するビッグ・シンカーの1人。2020年の新型コロナウイルス感染拡大に際し、感染経路対策を「ネイチャー」誌で発表し、大きな注目を集めました。
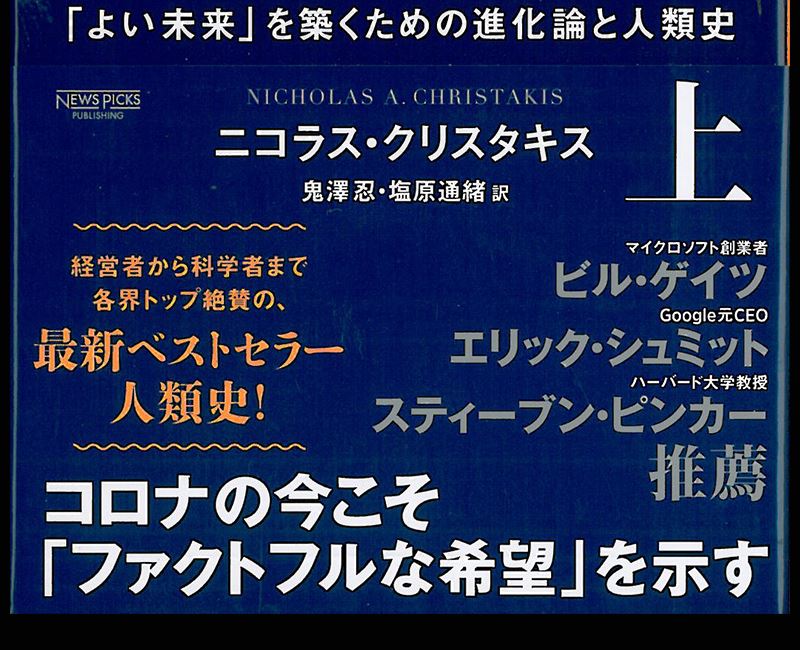 上巻の帯
上巻の帯
上巻の帯には、「経営者から科学者まで各界トップ絶賛の、最新ベストセラー人類史!」「コロナの今こそ『ファクトフルな希望』を示す」と書かれています。帯の裏には、以下の推薦の言葉が紹介されています。
「これほどの『希望』を感じて本書を読み終えるとは、予想もしなかった」――ビル・ゲイツ氏(マイクロソフト創業者)
「世界に蔓延している排外主義は、克服できる。本書はわれわれに何ができるかを教えてくれた」――エリック・シュミット氏(Google元CEO)
「人類の進化論的な本質は『善』であり、共感的な文明を生み出せる。これほどタイムリーかつ見事な本はない」――スティーブン・ピンカー氏(ハーバード大学教授、『21世紀の啓蒙』)
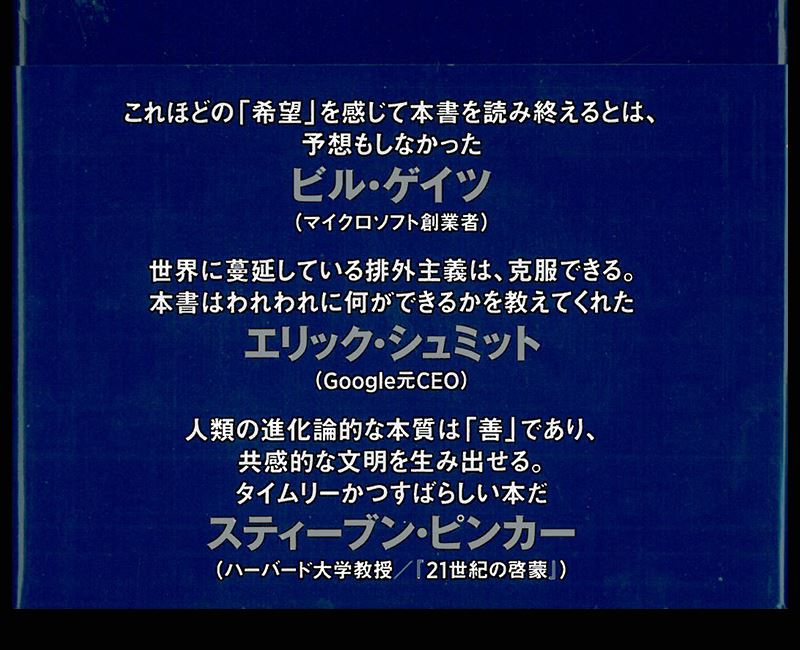 上巻の帯の裏
上巻の帯の裏
上巻のカバー前そでには、「『進化の設計図(ブループリント)』を知れば、『分断』は乗り越えられる」として、「経済格差、人種、国家間対立……。今ほど『分断』が強調される時代はない。だがちょっと待ってほしい。こうした分断はなぜ起こるのだろう? それは進化の過程で、私たちが『仲間』を愛し、尊重する能力を身につけたからだ。この能力こそが、世界の命運を握る最大のカギである。本書はそこで、南極探検隊の遭難者コミュニティからAmazon.comのスタッフコミュニティまで、古今東西のあらゆる『人間社会』を徹底検証する。さらにはサルやクジラなどの『動物社会』をも。繁栄するのはいかなる社会か? そこには驚くべき共通点があった――。科学界からビジネス界まで、全方面から絶賛されたニューヨークタイムズ・ベストセラー、待望の日本語版」と書かれています。
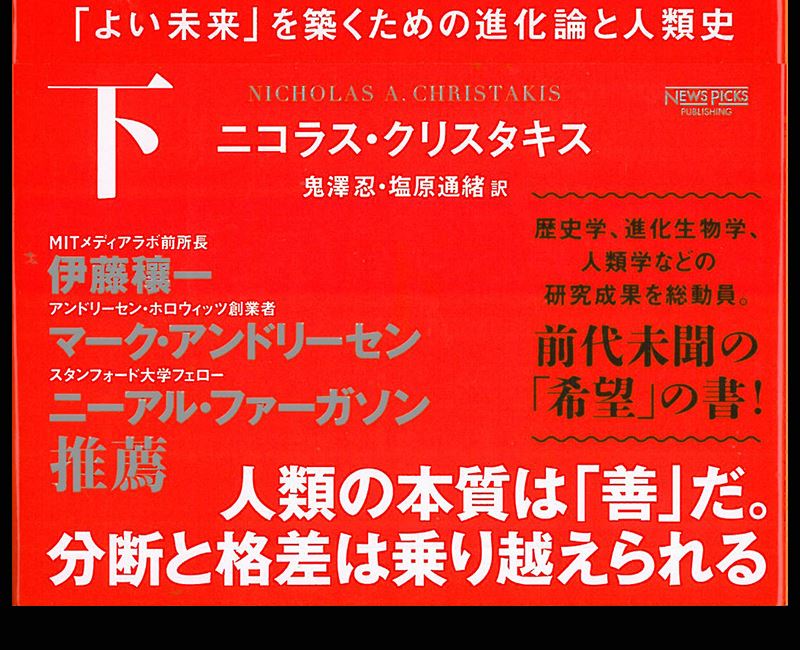 下巻の帯
下巻の帯
下巻の帯には、「歴史学、進化生物学、人類学などの研究成果を総動員。前代未聞の『希望』の書!」「人類の本質は『善』だ。分断と格差は乗り越えられる」と書かれています。帯の裏には、以下の推薦の言葉が紹介されています。
「分断と格差の時代において、本書は『科学』と『歴史』を『希望のメッセージ』に昇華させている」――伊藤穣一(MITメディアラボ前所長)
「人々がつながるウェブ時代の土台は『進化』がつくった。人間は『適者生存』を超えて助けあう種なのだということを、本書は教えてくれる」――マーク・アンドリーセン(アンドリーセン・ホロウィッツ創業者)
「本書は『人類』についてのあなたの見方を変えるだろう」――ニーアル・ファーガソン(スタンフォード大学フェロー/歴史学者)
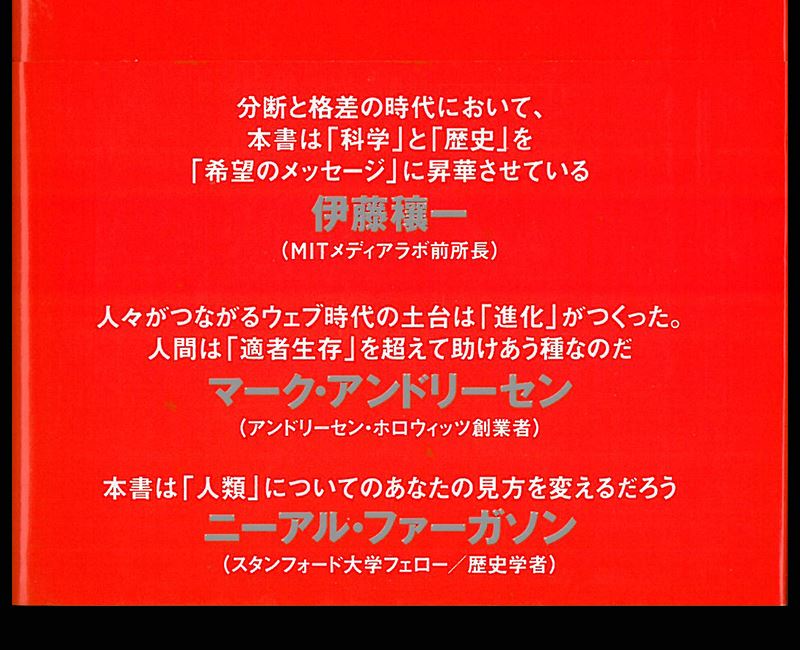 下巻の帯の裏
下巻の帯の裏
下巻のカバー前そでには、「『生物学』×『社会科学』が、コロナ後の世界を切り拓く。ラスト2章に瞠目せよ!」として、以下のように書かれています。
「社会が機能するために不可欠なものとは何か。その起源とは。本書によれば、カギとなるのは『社会性一式(ソーシャル・スイート)』だ。膨大なエビデンスに基づく楽観主義に、実に勇気づけられる」――『エコノミスト』誌
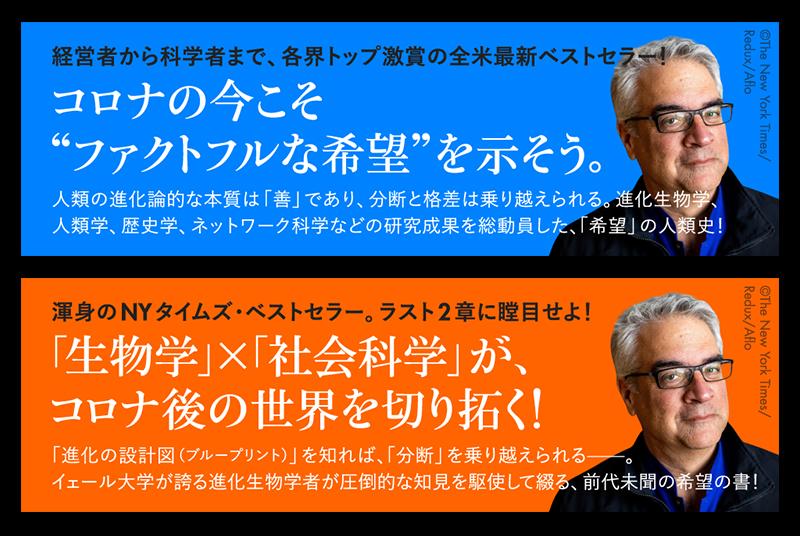
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
【上巻】
はじめに――私たちに共通する人間性
第1章 社会は私たちの「内」にある
第2章 意図せざるコミュニティ
第3章 意図されたコミュニティ
第4章 人工的なコミュニティ
第5章 始まりは愛
第6章 動物の惹き合う力
【下巻】
第7章 動物の友情
第8章 友か、敵か
第9章 社会性への一本道
第10 章遺伝子のリモートコントロール
第11章 遺伝子と文化
第12章 自然の法則と社会の法則
「謝辞」
「訳者あとがき」
「原注」
「図版クレジット」
「はじめに――私たちに共通する人間性」では、「他者を憎まず自集団を愛せるか」として、人間の本性には称賛すべき点がたくさんあることが指摘されます。たとえば、愛する、友情を育む、協力する、学習するといった能力だであり、それらはすべて、わたしたちが善き社会を形づくるのに役立つし、あらゆる場所で人間どうしの理解を深めてくれるとして、著者は「25年近く前、ホスピスの医師として働いていたころ、私はまずこの問題――人間は基本的にどのくらい似ているか――について考えはじめた。死や悲しみは何にもまして人びとを結びつける。死とそれに対する反応の普遍性を目にすれば、誰もが人間とはよく似ているものだという印象を抱かずにはいられない」と述べています。
著者は、あらゆる種類の背景を持つ瀕死の人びとの手を握ってきましたが、「人生の最後にまったく同じ願いを1つも共有していない人に出会ったことはないと思う。その願いとは、過ちをつぐなうこと、愛する者のそばにいること、耳を傾けてくれる人に自分の物語を語ること、痛みを感じずに死ぬことなどだ。社会的つながりや対人理解を求める気持ちはとても強いため、最後まで私たち一人ひとりのなかに存在するのである」と述べます。
「私たちに共通の人間性」として、著者は「私たち人間にかんする私のビジョン――すなわち本書の核心をなすもの――を述べれば、人びとは共通の人間性によって結びついているし、結びつくべきだ、となる。こうした共通性の起源は、人間が共有する進化にある。それは、私たちの遺伝子に書き込まれているのだ。人間は仲間どうしで相互理解を実現できると私が信じている理由は、まさにここにある」と述べます。また、「善き社会への青写真」として、「異文化間のこうした類似性はどこからやってくるのだろう? 人びとはお互いに――戦争さえ始めてしまうほど――大きく違うにもかかわらず、一方でとてもよく似ているなどということがどうすれば可能なのだろう? 根本的な理由は、私たち一人ひとりが自分の内部に『善き社会をつくりあげるための進化的青写真』を持っているという点にある」とも述べています。このあたりは、拙著『心ゆたかな社会』(現代書林)に通じます。
遺伝子は人間の体内で驚くべき仕事をしますが、さらに驚くべきなのは、それが体外でなすことだとして、著者は「遺伝子が影響を及ぼすのは人体の構造や機能だけではないし、人間の精神の、したがって行動の構造や機能だけでもない。そうではなく、社会の構造や機能にも影響するのだ。それは、世界中の人びとを眺めてみればわかる。私たちに共通する人間性の源泉はここにあるのだ。自然選択は、社会的動物としての私たちの生活を形づくってきた。また、愛し、友情を育み、協力し、学び、さらには他人の独自性を認めるといった人間の能力すらもたらす特徴からなる――この本の大事な概念であるところの――『社会性一式』の進化を先導してきた。現代の発明が、道具、農業、都市、国家といったあらゆる虚飾や人工産物を生んできたにもかかわらず、私たちは自己の内部に、人間にとっての自然な社会状態を反映した生まれながらの性向を持っている」と述べます。
著者によれば、こうした社会状態とは結局のところ、事実として、さらには道徳的見地からしても、何よりもまず善なるものです。人間がこうした前向きな衝動に反する社会をつくれないのは、アリが突如としてミツバチの巣をつくれないのと同じことなのだとして「私たちは、より残虐な性向にいたるのと同じくらいごく自然に、この種の善良さにいたるものだと思う。それは動かしがたい事実だ。人は他人を助けると実にいい気分になる。善行とは単なる啓蒙主義的価値観の産物ではない。もっと深遠な、有史以前にさかのぼる起源を有しているのだ。『社会性一式』を形づくる古来の性向は、一体となって働くことで、共同体を結束させ、それらの境界線を明確にし、メンバーを特定し、さらには、人びとが個人的・集合的目標を達成できるようにするが、その一方で、憎悪と暴力を最小限に抑える」と述べるのでした。
第1章「社会は私たちの『内』にある」では、「社会性一式(ソーシャル・スイート)とは何なのか」として、一致団結して社会を形成する能力は、実は人類の生物学的特徴であり、この点は直立歩行の能力とまったく同じであると指摘し、著者は「動物界ではめったに見られないこの生得的能力は、進化生物学者のE・O・ウィルソンが『地球の社会的征服』と呼ぶ事態を可能にした。私たちが地球を支配できるのは、脳のおかげでも強靱な筋肉のおかげでもないのだ。また人類が生き延び、繁殖する助けとなってきたほかの行動と同じように、社会を構築する人間の能力は本能となっている。それは、私たちにできる何かというだけではない――しなければならない何かなのだ」と述べています。
著者によれば、あらゆる社会の核心には以下のような社会性一式が存在するといいます。
(1)個人のアイデンティティを持つ、
またそれを認識する能力
(2)パートナーや子供への愛情
(3)交友
(4)社会的ネットワーク
(5)協力
(6)自分が属する集団への好意
(すなわち内集団バイアス)
(7)ゆるやかな階級制
(すなわち相対的な平等主義)
(8)社会的な学習と指導
第2章「意図せざるコミュニティ」では、「難破事故の生存者コミュニティ」として、難破の後に建設される生存者キャンプが提供するデータが紹介されます。生存者のコミュニティでは、さまざまな面で協調性が見られたとして、著者は「食べ物を平等に分け、ケガや病気の仲間を世話し、協力して井戸を掘り、死者を埋葬し、防備を整え、狼煙を上げつづけ、さらには、小舟を建造したり確実な救助を求めたりする計画をともに練った。こうした平等主義的行動を示す歴史的資料に加え、考古学的証拠からわかるのは、下位集団(たとえば将校と下士官兵、旅客と使用人)が別々に暮らすことはなく、全員が力を合わせて井戸や狼煙を上げる石台をつくったということだ。その他の間接的な証拠が、生存者にかんする情報、たとえば、すぐれたリーダーシップを見込まれた乗組員が危険な引き揚げ作業に加わるよう説得されたという報告などにも見いだされる。また、こうした状況で友情や仲間意識が育まれたことを示すたくさんの手がかりがある。暴力や殺人は当たり前のものではなかったのだ」と述べています。
第3章「意図されたコミュニティ」では、「アメリカにおけるユートピア建設の試み」として、1516年、トマス・モアがギリシャ語の単語を基にして「ユートピア」という言葉をつくったことが紹介されます。そのギリシャ語は「どこにもない場所」を意味しますが、英語では「良い場所」のルーツのような響きもあります。ユートピア社会をつくる試みの多くが失敗したことを考えると、こうした両義性は実に印象深いとして、著者は「コミューン的ユートピアを築こうとする取り組みにとって、アメリカはとりわけ肥沃な土壌であり、その取り組みは社会に足跡を残してきた。多くの人びとがそれらを知っているのは、その種のコミュニティでつくられた製品、たとえば、シェーカー家具、アマナ器具、オナイダ銀器などを通じてのことだ。マサチューセッツ州のフルートランズやブルック・ファームといった観光地を訪れて、自給自足の過ぎ去ったライフスタイルに驚いた人もいるかもしれない。1960年代的なコミューンや『ブランチ・デビディアン』のように終末論を信じるカルト集団さえ頭に浮かぶ人もいるだろう」と述べています。
「ブルック・ファーム」として、著者は、マサチューセッツ州のボストン郊外のウェスト・ロクスベリーに1841年4月に開設した理想主義農場にも言及します。「ブルック・ファーム」と名づけられたその農場は、当時を代表するユートピア的コミュニティでした。アメリカの超越主義(トランセンデンタリズム)の信奉者であるジョージ・リプリーが創設したもので、彼は1836年にソローやエマソンもメンバーだった「超越クラブ」をすでに発足させていました。この事業の目的は「頭と手の労働の間に現在よりも自然な統一を確保すること」でした。著者は、「ブルック・ファームは、私たちが意図されたコミュニティに結び付けてきた多くの性質を持っていた。すなわち(相対的な)男女同権、ゆるやかな階級制、カリスマ的リーダーなどだ」と述べています。
また、著者は「超越主義運動を先導した多くの人びと、すなわち、ラルフ・ウォルドー・エマソン、ブロンソン・オルコット、ヘンリー・デイヴィッド・ソロー、セオドア・パーカーといった面々がブルック・ファームを通過していった」と述べています。初期のフェミニストで作家のマーガレット・フラーもしばしば来訪し、住民となりました。フレデリック・プラットは、「子供たちはとても楽しい時間を一緒に過ごし、男の子たちの手押し車や荷車で女の子たちをあちこちへ運んだものです。15年から18年のちに、私の兄弟のジョンがアニー・オルコットと結婚し、ルイーザは作家となり、ジョン・ブルックスと『若草物語』は有名になりました」と回想しています。
「何がコミュニティの成功を決めるのか」として、著者は社会学者のマックス・ウェーバーの言葉を紹介します。ウェーバーは1918年、現代生活の規模に対する人びとの対応や、世界に対する彼らの幻滅について説明しつつ、「究極にして最も崇高な価値が、一般の生活から退いて、神秘的な生活という超越的領域や直接的で個人的な人間関係という親密さのなかに引きこもってしまった」と述べました。著者は、「アノミー(社会的規範や価値観が崩壊した混沌状態)や懐疑に対する唯一の解決策は、信頼および現実との深い接触である。コミューンに参加する人びとが求めているのは『ゲマインシャフト』、つまり、個人的な交流から生じる集団的一体感や連帯意識だ。彼らは規模の縮小を通じて信憑性を追求するのである」と説明しています。
ユートピアにおけるセックスの問題は重要です。さまざまなユートピア的コミュニティが、セックスに対して矛盾したアプローチをとったと指摘し、著者は「メンバー間の自由な性交渉を強調したコミュニティもあった。シェーカー教団のように完全な禁欲を求めたコミュニティもあった。しかし、これらの戦略はともに、結婚制度をくつがえし、個人のペアのあいだの深い人間的つながりを壊すという共通の目的を持っていた。これらの戦略の目的は、集団全体との連帯感を養うことにあった。これこそ、多くのコミュニティが、キブツで行なわれたような集団育児や親子の別居によって核家族を破壊しようとした理由である。しかし、これまで見てきたように、こうした試みはほとんどつねに失敗する。人間が持って生まれた愛の本能をむしばんでしまうからだ」と述べるのでした。
第4章「人工的なコミュニティ」では、「架空の社会」として、SF作家は、まったく異なる――「地球上のものではない」と言いたくなるような――社会の仕組みを思い描くという仕事にかけては、人類学者よりもすぐれていたことが指摘されます。想像はできても実際に目にすることはない社会の形を探究してきたのだとして、著者は「SF作家は人間の集団を意図的に極端な条件下に置いたうえで、彼らがどう対応するかに思いを巡らすことが多い。数百世代にわたって宇宙船に閉じ込められた人間社会には何が起こるだろう? 女性が男性を必要とせずに子供を産めるとしたら、社会組織はどう変化するだろう? 愛や友情のない世界はどう見えるだろう? 社会の不平等や社会階級が世襲になったり極端になったりしたら、何が起こるだろう?」と述べています。
しかし、人間の想像の翼をせいいっぱい広げたとしても、代わりとなる社会秩序は驚くほどありふれたものだとして、著者は「ディストピアを描くための一般的な設定と言えば、国家による生殖のコントロール、思想や感情の抑圧、厳格なカースト制のあるアリのような社会などである。実際、SF作家がまったく非現実的なディストピア社会を描こうとすれば、彼らは社会性昆虫をメタファーに選び、人間をアリ、狩りバチ、シロアリにいっそう似せようとすることが多い。言うまでもなく、人間からすればこれは――悪夢ではないとしても――とんでもない逸脱である」と述べます。
対照的に、ユートピアが描かれる場合、人間は、公正、安全、健康な世界で束縛されずに自由に生きているものと想像されます。しかしながら、こうしたストーリーには、現実の世界には欠けているが、作家が自分の描くユートピアにはあってほしいと切望するある要素が含まれていることが多いとして、著者は「それは、人びとのあいだの独特の親密な関係だ。虚構のユートピア社会は社会性一式を特徴とするのが普通だが、一種の共感や信頼の感情が付け加えられている――ときには、人びとがテレパシーでつながっているという極端な空想が繰り広げられることもある」と述べます。わたしは、1974年のSF映画「未来惑星ザルドス」を連想しました。
こうしたわけで、『アンナ・カレーニナ』の法則(幸せな家庭はどこも似たようなものだが、不幸な家庭はそれぞれに不幸だ)を実証するかのように、ユートピアの世界は驚くほどよく似ているが、ディストピアの社会はそれぞれに悲惨なようだとして、著者は「これはエントロピーの古典的理解に一致している。つまり、何かがうまく機能する方法よりもそれが破壊される方法のほうが多く、自然は秩序ある状態よりも無秩序な状態のほうが多く、社会組織の形は機能的であるより機能不全であることのほうが多い。それでも、SFの世界は依然として驚くほどよく理解できる」と述べるのでした。
第5章「始まりは愛」の冒頭を、著者は「いまにしてみればおめでたい話だが、私はほんの数年前まで、愛情のキスや性的なキスは、全人類が自然に楽しんでいるものだとばかり思っていた。ところが実は、アフリカ南部に住むツォンガ族は違うようだ」と書きだしています。民族誌学者のアンリ・ジュノーの「ヨーロッパ人のその習慣を見ると、彼らは笑ってこう言った。「この人たちときたら! お互いに口を吸い合っている! お互いのつばと汚れを食べているよ!」。ツォンガ族は、夫が妻にキスすることさえ決してなかった」という言葉を紹介した後、著者は「これはうっかりしていた。私は、人類学者のあいだで『自民族中心主義』として知られている昔ながらの罠にはまり、自分の文化で当然ならば他者の文化でも当然だと思い込んでいた。キスは私の文化ではしごく当たり前なので、ほかの人の文化でそうではないなどとは、よもや思いもよらなかった。実際、これまでキスを異常だとみなす人と話したこともないと思う。だから、愛情のキスや性的なキスは万国共通ではないと知って驚いた」と述べます。
著者が慣れ親しんでいるヨーロッパ、中東、インドの文化には、たまたまキスの習慣があります。キスを神秘的とみなす集団さえあるとして、著者は「3000年以上も前に記されたヒンドゥー語の文章には、キスは人間の魂を『吸い込む』行為とある。しかし、世界全体を対象にした文化横断型のある調査によると、キスの習慣が見られたのは168カ国のうち46パーセントにすぎなかった。最も一般的なのが中東とアジアで、反対に最も一般的でないのがアフリカ、南アメリカ、中央アメリカだった。サハラ以南のアフリカ、アマゾン川流域、ニューギニア島の狩猟採集民や農耕民に詳しい民族誌学者からは、愛情のキスや性的なキスを目撃したという報告は一度もない」と述べます。
「なぜ人間はパートナーに愛情を感じるのか」として、キスだけにとどまらず、セックスや結婚にまつわる多くの規範や慣習は世界中で異なっていることが指摘されます。しかし、異なってはいない別の特徴もあるとして、著者は「オーガズムの生理といった不変の特徴は、地域にかかわらず同じはずであり、人類の進化した生態や心理から生じるものだ。こうした普遍的特徴のなかでもカギとなるのが『夫婦の絆』を結ぼうとする傾向だ。これは、パートナーと強固な社会的愛着関係を築きたいという生物学的な衝動であり、ますます理解が進んでいる分子と神経のメカニズムによって促進される。進化は文化に対して連携して機能すべき「原料」を提供し、その基盤のうえに配偶システムが築かれる」と述べます。
「なぜ一夫一婦制が現在『主流』になったのか」として、結婚制度は社会規範であり、信念であり、制度であって、パートナーの選択、生殖行動、婚姻における義務、配偶者への愛情を規定すると指摘し、著者は「これらの文化的慣習が、許容される配偶者の人数やタイプ、新しい家庭を築く方法、それぞれの配偶者が相手に期待できること、死亡や離婚にともなう財産分与、さらには結婚式の費用を誰が払うかといったことまでを決める。あらゆる社会で、結婚には社会的、経済的、性的、規範的な期待がついて回るし、たいていの社会で、ある程度の家父長制がともなっている。世界的、文化横断的、かつ歴史的な(もしくは有史以前の)観点からすると、一夫一妻制は決して絶対的なものではない。現在優勢になっているヨーロッパ流の一夫一妻制は、結婚の一形態にすぎない」と述べます。
人類学的・歴史的記録のなかで一夫一妻制をとっていた少数派の社会は、両極端の2つの大きなカテゴリーに分けられるとして、著者は「かたや、男性間の身分格差がほとんどなく、生態的に厳しい環境にある小規模な社会、かたや、ギリシャやローマのように繁栄をきわめた大規模な古代社会。『生態的に押しつけられた』一夫一妻制が採用されるのは、環境のせいでほかの選択肢を選ぶのが難しい場合だ。これは、食べ物が手に入らないせいで痩せてしまう人に似ている。ギリシャ・ローマのような『文化的に押しつけられた』一夫一妻制は、一つの規範として採用される。これは、容貌や健康上の理由で痩せているほうが好ましいため、体重を落とすことを選ぶ人に似ている。文化的に押しつけられた一夫一妻制は、現在主流となっている形だ」と述べるのでした。
第6章「動物の惹き合う力」では、「夫婦の絆」と「一夫一妻制」という用語は互換的に使われることが多いが、まったく同じものではないとして、著者は「『夫婦の絆』は愛着の認知と感情を反映した内的状態であり、『一夫一妻制』は外的な慣行あるいは行動である。人間で言えば、恋愛と共同生活の違いに近い。動物の場合、オスとメスが交尾をしたいだけなら、配偶子(卵子と精子)が出会ったあとまで一緒にいる必要はない。それにもかかわらず、夫婦の絆を結んだ動物たちは一緒にいる。夫婦の絆は複婚(一夫多妻制あるいは一妻多夫制)の種にさえ存在することがある」と述べています。
1頭のオスと数頭のメスがそれぞれに結びつくゴリラはその一例です。カギとなるのは独占ではなく、愛着であるとして、著者は「つまり、人類のみならずどんな動物でも、夫婦の絆は必ずしも独占的ではないが、ある程度の期間にわたる安定的、相互依存的、性的な関係だ。また、行動的、生理的、ときには認知的な、そして(人間の場合は)情緒的な愛着をともなう。こうした絆を結ぶのは動物界で人間だけではないものの、現実の行動としては霊長類でさえ珍しい。ごく平たく言えば、夫婦の絆とは、パートナーが誰なのかに無頓着でないことを意味する」と述べます。
一夫一妻制への進化は、単身生活をしていた祖先を持つ種で多く起きたことがわかっていると指摘する著者は「哺乳類だけでも、そうした進化が少なくとも61回あったことが知られている。一夫一妻制が目的にかなったゆえに、動物系統樹の異なる枝がそれぞれに一夫一妻制を発見した。これは「収斂進化」の一例だ。収斂進化とは、遺伝子上別個の生物が別々に同じ形質を、しばしば遠く離れた場所で進化させることである。とはいえ、ほかの多くの種で夫婦の絆が交尾にまつわる難問を解決するものであるのはたしかだが、こと人間にかんしては、夫婦の絆を出現させた進化のメカニズムはまだ研究の途上にある。しかし、重要なのは、(人類も含めて)動物どうしのつきあい方にかかわるこの社会的慣行は遺伝子に書き込まれており、自然選択によって形成されるということだ」と述べます。
「そして人間は『パートナーへの愛』から『自集団への愛』に進んだ」として、他の霊長類と比べると、人類の社会組織の顕著な特徴は、血縁関係のない大勢の個体と共に暮らすことだと指摘する著者は、「正確に言えば、人間はオスもメスも複数いる集団で生活し、配偶者との間に夫婦の絆を結ぶため、その集団は厳密には複数家族集団だと言える。さらに、ほかの霊長類とは異なり、人間の家族は父系のみ、母系のみの親族と共に過ごす必要はなく、いわゆる多所居住の形をとって一方から他方へ移ることができる。そうした住み方の特徴の起源は複雑だが、1つの経路として、夫婦の絆と両親による子育てへの共同投資の結果、両性が特に居住にかんする意思決定でより平等になったことが挙げられる」と述べています。
母親と父親の双方が、自分の親族と一緒の生活を――別々の時期にかもしれないが――選択できるのです。長きにわたって各集団の多くのメンバーがこの選択権を行使した結果、かなり混成された、おおむね血縁関係のない一連の集団ができ上がったのだろうと推測し、著者は「ようするに、狩猟採集民の野営集団内に見られる血縁関係の度合いの低さは、男性と女性がそれぞれの親族と共に時間を過ごそうとするうちに、自然に生じたのだ。こうして、夫婦の絆と共同の子育てが、血縁関係のない人たちとの協力と友情の土台となったのである」と述べます。また、人間の集団にとって大切な協力の方法である食物の分かち合いについて考えてみると、「食物を入手したその場で一緒に食べるだけでなく、他者と分け合うためには、ある場所から別の場所へと運べなくてはならない。したがって、分け合う目的での食物の採集はおそらく、二足歩行と共進化したのだろう。二足歩行により、両手が空いて、パートナーや子のもとへ食物を持ち帰ることができるようになったからだ」と著者は述べます。
そうした行動が霊長類の夫婦の絆を背景として出現すると、次いで、より幅広い他者との分かち合いが行なわれるようになります。余分な食物は、近くにいる、たいがいは血縁関係のないほかの個体に与えられ、あるいは引き取られました。また、霊長類の間にすでに広まっていた共食も前適応の1つでした。個体どうしが互いの近くで食べることに喜びを感じたのであるとして、著者は「まとめると、夫婦の絆と原初的家族の出現が核となって、集団生活にかんするより広範な特徴が育まれ、社会性一式のほかの側面が現れてきた。私たちは、パートナー、子、親族への愛着と愛情の輪の外へ出て、自分の友人と自分の集団への愛着と愛情へと歩を進めていったのだ」と述べるのでした。
第7章「動物の友達」では、社会的つながりへの欲求は非常に強く、友達をつくる傾向があるほかの種にまで届くことがあるとして、著者は以下のように述べています。
「天才科学者ニコラ・テスラがハトとのあいだに結んだ関係を考えてみよう。テスラは居室にハトを引き寄せるために工夫を凝らしていた。机の上には小さな鳥用の寝床を点々と置き、窓の下枠に粒餌を置いて、窓はいつも開けっ放しだった。あるとき、投宿していたニューヨーク市のホテル・セント・レジスの部屋への鳥の出入りがあまりに迷惑だとして、ホテル側はテスラにハトの餌付けをやめるか、さもなくば出ていってくれと申し入れた。彼が選んだのは後者だった。テスラは生涯独身でほぼ孤独な人生を送ったが、ハトとの交流が心の隙間とつながりへの渇望を満たしたと、1929年のインタビューで語っている」
可愛がっていた鳥が死んだとき、テスラは大いに嘆きました。そして、「何かが私の人生から失われた。人生でなすべきことが終わったのだと悟った」と痛切に語りました。著者は、「彼自身も数カ月後に亡くなった。86歳だった。テスラの悲嘆と、ペットの死後に生命の危機が増大したようだという事実は、人間のカップルに(動物種の一部にも)広く見られる「傷心による死」という現象にも通じる。人間の愛着は(ペットに対するものでさえ)実に根源的で有益であるため、人びとの健康を増進することもあれば、その喪失が死をもたらすことさえある」と述べています。
「人間と動物の絆」では、ペットは一緒に飼う人間同士の関係も強化することを指摘し、著者は「家族で犬を飼っている人なら誰でも知っているように、ペットはつねに家族が共有する興味と、ユーモアと、逸話の源であり、ほかの多くの話題につきものの圧力や期待とは無縁だ。ペットの存在は人間の交流をうながすうえに、共感を増す可能性さえある。自閉症の子供にはモルモットとの遊戯療法が効果を発揮するし、負傷した退役兵はウマと触れ合うホースセラピーにより心理的症状が軽減される。ロサンジェルスのセレニティ・パークという鳥類保護区では、依存症、精神疾患、心的外傷の後遺症に苦しむアメリカ人退役兵たちが、遺棄されたオウム、コンゴウインコ、キバタンとのあいだに固い絆を結んでいる」と述べます。
「配偶者から友達へ、そして社会へ」として、友情は動物界ではめったに見られないことを指摘し、著者は「人間が友情を結ぶ性向は自然選択によって形成され、私たちのDNAに書き込まれている。動物種の友情は、相互援助と社会的学習というきわめて有用な目的に役立つ。そして、個体を超越し、時空を超えて情報を伝える恒久的な文化を育む能力の基盤となる。人間の心理の多様な側面も、友情に関係している。たとえば、友人といるときに感じる喜びや温かい気持ち、友人に対して抱く義務感などだ。ここから今度は、人類における友情の役割についてのより深遠な見解が示唆される。私たちが友情の絆のネットワーク内に集まることで、道徳感情が出現する土台が築かれるからだ」と述べます。
道徳的悔恨の核心は、他者とのつきあい方に関わっています。ことに血縁者でない相手、血縁関係の絆や包括適応度の厳然たる働きだけに導かれるのではない相手とのつきあい方に関わっているとして、著者は「私が言いたいのは、人間の美徳の大半は社会的美徳であるということだ。人は、愛、公正、親切を大切にするかぎり、それらの美徳をほかの人びとにかんしていかに実践するかを大切にする。あなたが自分自身を愛しているか、自分自身に公正であるか、自分自身に親切であるかは、誰も気にかけない。人が気にするのは、あなたがそのような資質を他人に対して示すかどうかだ。それゆえに友情は道徳の基盤となるのである」と述べるのでした。
第8章「友か、敵か」では、友達は、自分のために命を投げ出してくれるばかりか、他にも重大な自己犠牲的行為をしてくれるとして、著者は「たとえば腎臓を提供してくれたり、戦時中の捕虜収容所で乏しい食料を分けてくれたりといったことだ。このように、人間は性的パートナーや血縁者だけでなく、それ以外の人に対しても、とほうもなく強い愛着を感じることができる。ハーヴァード大学の心理学教授で、『明日の幸せを科学する』(早川書房)という著作を持つ私の友人ダニエル・ギルバートなどは、友情こそが幸福の主要な決定因であり、むしろ婚姻よりも重要だと論じているぐらいだ」と述べています。
「類は友を呼ぶ」として、人間は一般的には「ホモフィリー」(「似たもの好き」を意味するギリシャ語)を志向し、自分に類似した人を仲間にしたがるが、この傾向と並んで、ある属性においては「ヘテロフィリー」(基本的な意味は「逆のものに引きつけられる」)への志向が生じることもあると指摘し、著者は「ルームメイトには音楽の趣味や室温の好みが自分と同じであってほしいと思うかもしれないが、数学の宿題を手伝ってほしいときには、自分とまったく違った誰かがいてくれたほうがいいかもしれない」と述べます。
「利他行動と自民族中心主義」として、著者は述べます。
「命さえ落とすような極端に激しい集団間対立は、私たち人間のあいだには――まさしく全面戦争というかたちで――見られるが、動物界ではきわめてまれである。したがって、人間がいたって友好的で親切な人にもなれるのに、いたって忌々しい暴力的な人にもなれるというのは一種の謎だ。この二元性に近いものを持つ種はチンパンジーしかいない。そう考えると、実は親愛と憎悪にはなんらかの結びつきがあるのかもしれない。人間の進化モデルの数理解析が示すところでは、かつては利他行動と自民族中心主義の両方が出現する条件が整っていた。だが、その場合は――ここに落とし穴があって――つねに両方が出てきていた。この二つは互いに互いを必要としたのだ」
自分の命を犠牲にしてでも内集団のメンバーを助けるのが利他行動であり、一方、外集団のメンバーに対して敵意を向けるのが自民族中心主義(あるいは区域内至上主義)であす。著者は、「定期的な資源欠乏――たとえば旱魃や洪水による――は、現代の狩猟採集集団における主要な対立予測因子だ(そして原油などの資源の欠乏は、現代世界においてもいまだ有効な戦争予測因子である)。更新世のあいだ(約258万年前から1万年前まで)、気候は絶えず変動していたことがわかっているから、私たちの祖先が生きていた環境は、乏しい資源をめぐる争いがときどき起こって、その争いが勇敢で自己犠牲的なメンバーのいる集団を選り好みする環境だったということになる。外集団との対立に勝つために内集団の利他行動を育むことが有益だったのだ」と述べています。
「普遍的なバイアス」として、著者は「人間はしばしば自然界を二項対立で解釈する(これ自体が生来的な傾向なのかもしれない)。人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは二項対立的な捉え方のことを(男性/女性、善/悪、熱い/冷たい、保守/リベラル、人間/動物、肉体/魂、生まれ/育ち、等々)、人間が自然界の複雑さと折り合いをつけるための最も単純で、最も広く行き渡った方法の一つであると論じていた。当然ながら、このカテゴライズ傾向は社会生活にも適用されて、われわれとかれら、友と敵とが、はっきりと区別されることになる」と述べます。
友情関係は基本的なカテゴリーであり、哲学者のラルフ・ウォルドー・エマソンなどはいみじくも、「友は自然のつくった最高傑作とみなせるだろう」と語っています。しかしながら、これまで科学者は、人類という種の生活に友が果たしてきた役割をないがしろにしがちだったとして、著者は「血縁関係と婚姻関係に注意が集まりすぎて、それらよりもずっと数が多いにもかかわらず、血のつながりのない友との関係がぼやけてしまっていたのだ。だが、そもそもこれらの友達は、私たちが形成し、そのなかで暮らす社会集団の主要メンバーなのである」と述べます。
第9章「社会性への一本道」では、「『悲しみ』の進化論的説明」として、著者は「アイデンティティと個別性については、『悲嘆』の表出を通じて理解することもできる。人間以外の霊長類にしろゾウにしろ、自分にとって近しい存在だった動物が死ねば深く嘆き悲しむが、特別の愛着がない動物が死んでもそのような嘆きを見せることはない」と述べます。また、「悲嘆はめったにない、特別な感情だ。これは特定の、誰であるかを識別できる人の喪失に結びついているからである。人は見知らぬ他人に対して怒りを抱くことはあっても、通常、見知らぬ他人の死に対して悲嘆を感じることはない。強烈で、とてもつらく、なかなか消えてくれない悲嘆は、ある種の身体的な感覚として多くの人が表現してきた。胸を押しつぶすような感情がこみあげ、肩がうずき、顔が痛くなるぐらいに大量の涙が出る」とも述べています。
実際、悲嘆が生理学的に有害で、その後の死亡リスクを高めさえすることについては多くの証拠があるとして、著者は「ならば私たちの祖先において、悲嘆を感じない人のほうが感じる人よりも生存しやすかったに違いない。それなのに、なぜこの感情が進化したのだろう?」と問いかけ、「ある仮説では、悲嘆は人びとに、その痛みをやわらげるために他人とつながろうとする動機を与えると説明される。社会的な種である人間を孤独にさせないようにしているのが悲嘆であり、だから悲嘆は適応的なのだという見方である。熱い鍋を触ったときに感じる痛みが、そのいやな刺激からとっさに手を離させる効果があるという理由で適応的であるというのと同じことだ」と述べます。
「動物の悲しみ」として、著者はこう述べています。
「ある研究では、ボツワナの8頭以上のヒヒの群れから採取した糞便のサンプルを使って、グルココルチコイド濃度(ヒヒにおいても人間においてもストレスの指標にされるホルモン)がひときわ高かったのは死んだヒヒに最も近い類縁のメスだったことを確認した。さらに興味深いことに、これらのメスのストレスは、毛づくろいの回数を増やし、毛づくろいをする相手の数を増やすことで軽減されているようだった。これはヒヒのあいだでは人間の通夜のようなものにあたるのかもしれない。それで思い出すのだが、人間の多くの文化では、身内と死別した女性が髪型を変える(髪を切り落としたり、引き抜いたりする)儀式に臨んでいる。嘆き悲しむメスのヒヒは、毛づくろいのネットワークを拡大すると、そうしないメスにくらべて大幅にグルココルチコイド濃度が下がっていた」
クジラ類、霊長類、ゾウもまた、人間と同じように、愛するものの遺体を丁寧に取り扱うように見受けられるとして、著者は「彼らにとっても、それはただの動かない物体ではないのだろう。あるシャチの母親は、群れの仲間に支えられて、死んだ赤ん坊を3日のあいだ水に浮かせているところを観察された」と述べます。そのときの様子を、ある専門家は「幼獣が死んでいることは彼らも知っている。私が思うに、これは母親が行なう追悼とか葬式の類なのだろう。……母親は手放したくないのだ」と語りました。著者は、「霊長類学者は、チンパンジーやゴリラやシシバナザルのおとなのメスが死んだ幼児を(類縁でもそうでなくても)ずっと放さず、遺体が腐りはじめてからも長いこと抱えているのを目にしてきた。チンパンジーが死体の歯を掃除する、葬儀のような行動を記録した映像もある。これらを見ると、シバと呼ばれる7日間の喪に服すユダヤ教の伝統や、埋葬前の準備として遺体を洗い清めるイスラム教の(および、ほかの多くの宗教での)慣例など、人間の追悼儀式になんとよく似ているものかと驚かされる」と述べます。
「なぜ人間は、安全な日でも利己的ではないのか」として、人間という種は、つい200年ほど前まで、つまりその歴史の大半において、ずっと死と隣りあわせで生きてきたと指摘し、著者は「進化的に言えば、私たちはいまだにこの歴史を背負っている。だから疑問が生じるのだ――なぜ利己的な裏切り者がこの個体群を乗っ取って、協力者を駆逐してしまわなかったのか? 言い換えれば、なぜ私たちは今も利己的ではないのだろうか?」と問いかけます。1つの仮説として、著者は「家族に関係している。わが子を救うために冷たい川に飛び込む母親は、個人的なコストを払って(みずからの命さえもかけて)自分の子供に利益をもたらすが、そうした英雄的な母親が一人死ぬごとに、そのような行動は――その行動に寄与する遺伝子とあわせて――いっそう希少になる方向に進んだだろう」と述べます。
たとえ母親が死んだとしても、その遺伝子は彼女の子供のなかで生き続けます。これが血縁選択というプロセスです。しかし実際、人間の交流のほとんどは、血縁とではなく、血のつながりのない個人との間でなされているとして、著者は「社会的な種は、友情、協力、知能、そして社会的学習を通じた知識の伝達など、互いに関連する一連の特質を進化させてきた。こうした種における知能とは、集団のほかのメンバーのアイデンティティをたどれて、社会的に生活していけるという必須の要件に関連しているだけでなく、特定の記憶を呼び覚まし、仲間に教え、仲間から学ぶ能力とも関連しているのかもしれない」と述べます。
「人間と動物」として、他人とのつながりや協力があるからこそ、人間は他人から学ぶことができ、それをまた土台として、次は自分から他人に教えることへの興味と意欲を進化させることを指摘し、著者は「教えることは教える側にコストを負わせる一方で、必ずしも利益をもたらさないから、これはまさしく一種の利他行動だ。このすべてがあってこそ、一つの最終的な奇跡が可能になる。すなわち文化の才能だ。文化は人間においては非常に複雑で、累積的なものにもなる。私たちはみな、人類という種が長い年月のあいだに生み出して、時間と場所を超えて人から人へと伝えてきた、そして今では私たちとともにある集合的な知識の受益者だ」
第10章「遺伝子のリモートコントロール」では、「わつぃたちの遺伝子は世界を平和に導く」として、著者こう述べます。
「動物は――網を張るクモであれ、バワーを築く鳥であれ、アリを操る菌類であれ、社会的ネットワークを広げる人間であれ――世界をもっと心地よい場所にして、自分の生存の見込みを高められるよう、世界に働きかけ、世界のありようを変えるべく遺伝的にプログラムされている。人間がつくりだす社会環境は、ある程度までは私たちの遺伝子の制御下にある。そして次にはその環境がフィードバックして、私たちに影響を与え、『社会的に生きる』ことを生存に有利な条件にして、そうした社会性につながる遺伝子変異を選び取っていく。人間として、私たちはみずからを変化させている。長短さまざまな進化期間を通じて、私たちの遺伝子は――そして私たちの友達の遺伝子も――より安全で、よりおだやかな世界を築くべく働いているように見えるのだ」
第11章「遺伝子と文化」では、「ルービックキューブとしての人間社会」として、文化の維持と進化は、社会的ネットワークにおける個人間のつながりの数と構造、および情報がどれだけ容易に、かつ自由にやりとりされるかによって決まることを指摘、著者は「文化の伝達は、その集団がどれだけ協力的で、どれだけ友情にあふれているかにかかっていることになる。つまり文化を育む私たちの才能は、社会性一式の要素を基盤として成り立っているわけだ。そこから文化についての皮肉な結論が導かれる。まさにそれらの揺るぎない普遍的な人類の特徴――協力、友情、社会的学習――のおかげで、文化は驚異的なまでに多様になれるのである」と述べています。
「文化は社会性一式を補強する」として、著者は宗教に言及し、「宗教的な信仰(恵まれなかった人も天国で報われるという約束を含め)、規則、伝統、制度などには、血のつながっていない大勢の人びとを一致団結させる機能があり、これらを持っている集団は、もっとばらばらな相反するイデオロギーが広まっている集団を打ち負かしやすくなる。さらに第2の機能として、宗教という文化の産物は、類縁関係にない個人間で協力の輪を広げさせ、品物の交換をさせ、分業を維持させる。こうした集団が、他の集団との競争にめでたく勝てた(そしてみずからの集団内の対立を軽減できた)あかつきには、その成功が遺伝子に反映されるようになるかもしれない。実際、ある特定の遺伝子変異は、最初から協力が求められるようにできている環境で相対的にうまくやれるという見方もある」と述べます。
第12章「自然の法則と社会の法則」では、「『生まれか育ちか』という二分法を超えて」として、人間相互の違いや、人間の遺伝的な類似性に言及し、著者は「私の意見を言うならば、私たちがこの先にとるべき道として、人間の類似点の太古のルーツを特定するために、人間の誰もが共有する進化的遺産をしっかり調べるほうがよほどいい。遺伝子とはまさにそれで、私たちの誰もが持っているものである。そして全人類のDNAの少なくとも99パーセントは、完全に同じなのだ。人間を科学的に理解することは、私たちが共有する人間性の深い源を特定することによって本当の正義を育むことにほかならない。ようやく理解されるようになってきた社会の基盤――私たちの青写真であるところの社会性一式――は、人間相互の違いではなく、人間の遺伝的な類似性にかかわっているに違いないのだ」と述べています。
「この社会を弁護する」として、著者は「人間の歴史を見返すと、なんと悲惨な窮状と機能不全に満ちたものであったかと嘆きたくなる。百年単位で切り取っても千年単位で切り取っても、見えてくるのは恐ろしさばかりだ。たしかに18世紀には、啓蒙運動の到来とその哲学的な価値観の広まりや、数々の科学的な発見によって状況が劇的に上向きになった。寿命は延び、生活は豊かになり、自由度も増して、平和にもなった。しかし、こうした最近の歴史上の発展だけに頼らずとも、人間は世界をよりよくすることができる。もっと古い、もっと強い力がつねに働いて、よい社会をさらに前へと進めていくからだ」と述べています。
そして、昔も今も、人間は競争的な衝動と協力的な衝動を併せ持ち、暴力的な傾向と情け深い傾向を併せ持っているとして、著者は「DNAの二重らせんの2本の糸のように、これらの対立する衝動が絡みあっている。人間は衝突し、憎みあうようにできている一方で、愛情や、友情や、協力を育むようにもできている。現代の社会は言うなれば、この進化的な青写真の表面を『文明』という緑青で覆っているようなものなのだ」と述べるのでした。本書には、わたしたちが「よい未来」を築くための進化論と人類史が平易な言葉で語られています。さまざまな諸学の研究成果を総動員して、人類の未来に希望の光を見出そうと言う姿勢は、やはり拙著『心ゆたかな社会』によく似ていると思いました。ちなみに、著者はわたしより1歳上で、ほぼ同世代です。
