- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2199 芸術・芸能・映画 『この1本!』 馬場康夫著(小学館)
2022.12.26
『この1本!』ホイチョイ・プロダクションズ 馬場康夫著(小学館)を読みました。「超人気映画シリーズ、ひとつだけ見るならコレ」というサブタイトルがついています。サブスク時代を迎えて、ある意味では「映画の洪水」の中を生きている現代人にとって大変役に立つ本であり、内容も情報満載で面白かったです。
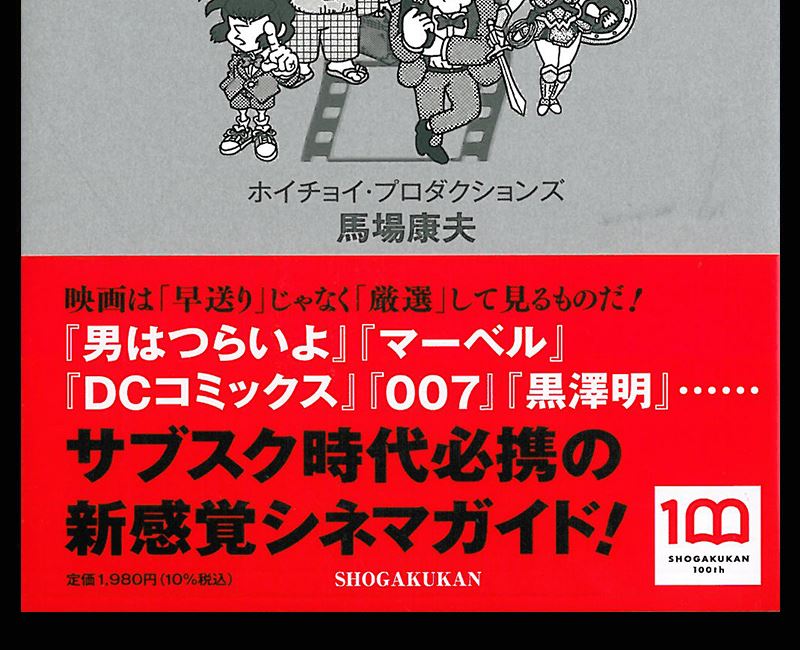 本書の帯
本書の帯
カバー表紙には、名探偵コナン、フーテンの寅さん、ジェームズ・ボンド、ワンダーウーマンのホイチョイ風イラストが描かれ、帯には「映画は『早送り』じゃなく『厳選』して見るものだ!」「『男はつらいよ』『マーベル』『DCコミックス』『007』『黒澤明』……」「サブスク時代必携の新感覚シネマガイド!」とあります。
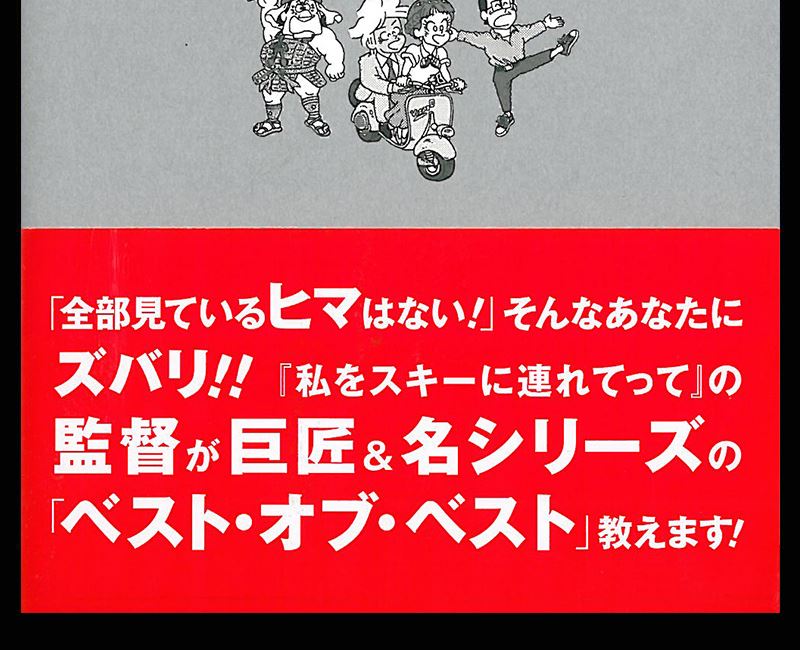 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には、「七人の侍」「ローマの休日」「ウエスト・サイド物語」のホイチョイ風イラストが描かれ、帯の裏には「『全部見ているヒマはない!』そんなあなたにズバリ!! 『私をスキーに連れてって』の監督が巨匠&名シリーズの『ベスト・オブ・ベスト』教えます!」と書かれています。
また、アマゾン「編集者からのおすすめ情報 」として、「大人気コミック『気まぐれコンセプト』でお馴染みのホイチョイ・プロダクションズの馬場康夫氏は、『私をスキーに連れてって』『彼女が水着にきがえたら』『波の数だけ抱きしめて』などを送り出した映画監督でもあります。そんなプロフェッショナルな視点とミーハーな視点が同居する、サブスク時代必携のシネマガイドです! あなたの『ベスト作品』とはたして一致するか、そんな視点で楽しむのもアリかもしれません」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに」
CHAPTER1
「男はつらいよ」ならこの1本
CHAPTER2
「007シリーズ」ならこの1本
CHAPTER3
「スター・ウォーズ・シリーズ」ならこの1本
CHAPTER4
「マーベル・シネマティック・ユニバース」ならこの1本
CHAPTER5
「名探偵コナン」ならこの1本
CHAPTER6
「ピクサー・アニメ」ならこの1本
CHAPTER7
「ゴジラ・シリーズ」ならこの1本
CHAPTER8
「黒澤明監督作品」ならこの1本
CHAPTER9
「オードリー・ヘップバーン作品」ならこの1本
CHAPTER10
「ハリー・ポッター」ならこの1本
CHAPTER11
「裕次郎とルリ子のムード・アクション」ならこの1本
CHAPTER12
「ロッキー・シリーズ」ならこの1本
CHAPTER13
「スピルバーグ監督作品」ならこの1本
CHAPTER14
「東野圭吾原作映画」ならこの1本
CHAPTER15
「21世紀のミュージカル映画」ならこの1本
CHAPTER16
「クリント・イーストウッド監督作品」ならこの1本
CHAPTER17
「ⅮCコミックス映画」ならこの1本
CHAPTER18
「山崎貴監督作品」ならこの1本
CHAPTER19
「ジャッキー・チェン映画」ならこの1本
CHAPTER20
「高倉健任侠映画」ならこの1本
CHAPTER21
「角川映画」ならこの1本
CHAPTER22
「フランス不倫映画」ならこの1本
CHAPTER23
「若大将シリーズ」ならこの1本
「あとがき」
本書の「はじめに」を、著者はこう書きだしています。
「映画はサブスクリプションで見る時代。ネットには、Netflix、Hulu、AMAZONプライム、U-NEXT等々、定額見放題のサブスクが溢れている。雨降りの日曜の午後、出かけるのもおっくうだし、家で一日まったり過ごそうか。そうだ、せっかくサブスクに入ったんだから、映画を見よう。マーベルにしようか、007にしようか、ピクサーの新作もいいが、昔の寅さんも見てみたい。いっそ3本立てにするか――自宅に居ながらにして好きな3本立てを組める現代は、昔、『ぴあ』のページを血眼でめくり、目当ての映画を上映している遠くの名画座に駆けつけていた我々にとっては、夢のような時代である。しかも今は、どの作品が面白いかを教えてくれる意見がネットやSNSに溢れている」
CHAPTER2「『007シリーズ』ならこの1本」では、映画「007シリーズ」が、イギリスの作家イアン・フレミングが書いた12の長編小説と9つの短編を原作としていることを紹介します。著者は、「フレミングの小説の特徴は、ボンドのこだわりの悦楽生活を、すべて実際の商品名やブランド名を用い、ことさらに細かく描いた点にある」として、イギリスのある書評家が『女王陛下の007』に登場する具体的な商品名を数えたら、10ページめに登場するキャドバリーのミルク・チョコレート・フレークスから、280ページに登場するシュタインヘーガーのダブルまで、全部で56あったそうです。著者は、「こうしたハイ・エンドなライフ・スタイルを活写したイアン・フレミングの小説は、1960年代の日本のアッパー・クラスにとって、愉悦の生活の唯一の教科書だった」と述べています。
CHAPTER4「『マーベル・シネマティック・ユニバース』ならこの1本」では、ⅮCのヒーローがメトロポリスとかゴッサムシティとかいった架空の町に住んでいたのに対し、アベンジャーズのヒーローは、全員がリアルなニューヨークの町に住み、恋愛、貧困、人種問題、学生運動といった当時の若者の悩みや生活感を共有していたため、若者の圧倒的な支持を得たことが紹介されます。わたしは、「映画を愛する美女」こと映画ブロガーのアキさんのブログ「映画が好き」の「『スパイダーマン』シリーズ7作品のロケ地14選in ニューヨーク!」という記事で、「スパイダーマン」の舞台がわたしの大好きなニューヨークであり、ニューヨーク公共図書館、タイムズスクエア、ブルックリン・ブリッジなどの名所が次々に登場することを知ったことを思い出しました。DCとマーベルの違いについて、著者は「象徴的なのが当時の編集者の服装で、ⅮCの編集者が全員ネクタイにスーツ姿だったのに対し、マーベルは全員が長髪にジーンズのビートニクス・スタイルだったという」とも書いています。
1970年代以降、マーベルは、有力な作家が次々に抜けて人気を落とし、『スパイダーマン』や『X-メン』の映画化権を切り売りしてかろうじて食いつないでいましたが、1998年についに倒産。そして、経営者が替わって再起動した際、起死回生を狙って、権利を残していた虎の子の10作品の映画化を条件に投資銀行メリルリンチから融資を受け、2008年、プロデューサーのケヴィン・ファイギを社長に迎えて『アイアンマン』を映画化。その成功に目を付けたディズニーが2009年に同社を買収してから、快進撃が始まります。著者は、「同じマーベル・コミックの映画化でも、『X-メン』と『スパイダーマン』は権利が違うので、MCUには含まれないが、『スパイダーマン』は、権利を保有するソニー・ピクチャーズが2015年にディズニーと提携したため、『シビル・ウォー』からMCUに参加。スパイダーマンが『シビル・ウォー』で初めて登場した場面では、劇場で大歓声があがったという」と書いています。
CHAPTER6「『ピクサー・アニメ』ならこの1本」では、ピクサー・アニメの素晴らしさについて書かれています。全盛期の黒澤明監督の映画の脚本は4~5人のチームで書かれていたといいますが、ピクサー作品は、脚本家が1本につき12人いて、シーンごとに分担していると言われるそうです。さらに、最初のストーリーの検討には、別作品で動いている12人も加わって、厖大な人数が関わるのとか。著者は、「完成後にラセターが、試写を見て作り直しを命ずることもしばしばで、『トイ・ストーリー2』は公開9ヶ月前でゼロからやり直し、『アーロと少年』は、公開予定を1年半延期して作り直し。そのたびにスタッフは阿鼻叫喚の毎日を経験する」と書いています。
CHAPTER7「『ゴジラ・シリーズ』ならこの1本」では、怪獣映画の歴史に輝く名作『ゴジラ』を含め、東宝の怪獣・特撮映画を24本監督し、世界の映画オタクから「モンスター・マスター」として崇められている本多猪四郎が取り上げられます。彼は、1931年に設立された日大芸術学部映画学科の第1期卒業生でした。卒業後は、東宝の前身のP・C・L(Photo Chemical Laboratory 写真科学研究所)に入社し、1歳年上の黒澤明とともに、名監督山本嘉次郎に師事します。著者は、「P・C・Lは、プロデューサーが圧倒的な力を持ち、監督に予算や日程を守る職人性を求め、今のテレビ局のように『監督』を『演出』と呼んだ会社だったが、そんな中で、山本嘉次郎は上から命じられた企画をせっせと映画化する職人仕事の傍ら、『馬』『綴方教室』等、ドキュメンタリー・タッチの作家性溢れる作品を残した、したたかな監督だった。ざっくり言えば、山本から作家性の部分を受け継いだのが黒澤明で、職人性の部分を受け継いだのが本多猪四郎ということになろう」と述べます。
CHAPTER8「『黒澤明監督作品』ならこの1本」では、かつて松竹に野村芳太郎という名監督がいたことが紹介されます。かの山田洋次の師匠で、『張り込み』や『砂の器』といった数々の傑作をものした大監督です。同時に彼は、黒澤が松竹で撮った『醜聞』『白痴』で助監督を務め、黒澤明をして「日本一の助監督」と言わしめた人でもありました。黒澤映画の脚本を7本手がけた脚本家・橋本忍は、野村芳太郎から「黒澤さんにとって、橋本忍は会ってはいけない男だったんです。そんな男に会い、『羅生門』なんて映画を撮り、外国でそれが戦後初めての賞などを取ったりしたから……映画にとって無縁な、思想とか哲学、社会性まで作品に持ち込むことになり、どれもこれも妙に構え、重い、しんどいものになってしまったんです」と言われたそうです。また、野村監督は1974年、キネマ旬報のインタビューで「黒澤さんは、何か言ってやろうという気持ちの強いときと、見せてやろうという気持ちの強いときでは、作品の種類が変わってくるんじゃないでしょうか」とも語っています。
著者は、「世の中には、黒澤作品は難解で面白くないと思い込んでいる人がいるが、それは野村芳太郎の言う『何か言ってやろう』という作品しか見ていないからであって、『何か見せてやろう』という気持ちで作った作品の方は、理屈抜きに滅多やたら面白いのである」と述べます。そして、「何か言ってやろう」という作品とは『一番美しく』『わが青春に悔いなし』『静かなる決闘』『醜聞』『羅生門』『生きる』『生きものの記録』『蜘蛛巣城』『どん底』『悪い奴ほどよく眠る』『どです家でん』『デルス・ウザーラ』『影武者』『乱』『夢』『八月の狂詩曲』『まあだだよ』など。「何か見せてやろう」という作品は、『姿三四郎』『続 姿三四郎』『虎の尾を踏む男達』『素晴らしき日曜日』『酔いどれ天使』『野良犬』『七人の侍』『隠し砦の三悪人』『用心棒』『椿三十郎』『天国と地獄』『赤ひげ』などです。このように全30作品を書きだすと、黒澤明がいかに映画界の巨匠であったかがわかりますが、わたしはやはり『七人の侍』が一番好きですね。
CHAPTER9「『オードリー・ヘップバーン作品』ならこの1本」では、今、オードリーの作品を見直すと、相手役の俳優がみんなとんでもなく年上であることに驚かされるといいます。ハンフリー・ボガートとフレッド・アステアは30歳年上、ゲイリー・クーパーは28歳、ヘンリー・フォンダは24歳、レックス・ハリソンは21歳、最も若い部類のウィリアム・ホールデンでも11歳年上。著者は、「そして、オードリーはこの全員と映画のラストで結ばれる。昔の若い娘にとっての幸せは、若いイケメンよりも金持ちのオッサンと結ばれることだったのだ」と述べています。 一条真也の映画館「オードリー・ヘプバーン」でも紹介したように、わたしはオードリーの大ファンですが、とんでもなく年上の俳優とばかり共演していることには気づきませんでした。でも、その事実をもって「昔の若い娘にとっての幸せは、若いイケメンよりも金持ちのオッサンと結ばれることだったのだ」と決めつけるのは、ちょっと行き過ぎですね。いかにも、『東京いい店、やれる店』とか『不倫の流儀』を書いた著者らしい見方ではありますが……。あと、オードリー・ヘプバーンの最高の共演者は、やはり彼女の代表作である『ローマの休日』のグレゴリー・ペックでしょう。ちなみに、この2人は13歳差です。
CHAPTER11「『裕次郎とルリ子のムード・アクション』ならこの1本」では、昭和の大スター石原裕次郎が、生涯で104本の映画に出演したことが紹介されます。そして、彼が最も多く共演した相手は浅丘ルリ子で、共演作は37本にものぼります。著者は、「中でも、2人が1963年から67年にかけて連続共演した『ムード・アクション』と呼ばれる作品群は、今では完全に失われてしまったジャンルだけに、新鮮な面白さがある」と述べます。1955年の時点で、のべ8億6891万人だった日本映画の観客動員数は、そこから裕次郎・ルリ子の人気と歩調を合わせるかのように急速に伸び、ピークの1958年には11億2745万人を記録しました。現在のじつに10倍です。著者は、「日本人が全員、毎月1本ずつ見ていた勘定である。そして、その年の日本映画の興行収入ベスト10のうち、裕次郎主演作は4本。石原裕次郎は、まさに日本映画の絶頂期を作ったスターなのだ」と述べるのでした。
CHAPTER12「『ロッキー・シリーズ』ならこの1本」では、昔からボクシング映画には傑作が多いことが指摘されます。邦画なら、石原裕次郎の『勝利者』、赤木圭一郎の『打倒(ノックダウン)』、加山雄三の『銀座の若大将』、赤井英和(この人は元々「浪速のロッキー」と呼ばれたJウェルター級世界8位のプロボクサーである)の『どついたるねん』、山下智久の『あしたのジョー』、洋画ならポール・ニューマンの『傷だらけの栄光』、アラン・ドロンの『若者のすべて』、あるいは『チャンプ』『レイジング・ブル』『ミリオンダラー・ベイビー』『シンデレラマン』などなど。著者は、「いずれ劣らぬ名作・快作だが、万人が認めるボクシング映画のNo.1は『ロッキー』に違いない。ロッキー・シリーズは、題名に『ロッキー』とつく作品が6本、スピンアウトの『クリード』が2本あるが、全8作を通したストーリー展開は、まさにバトル物の少年マンガのお手本である」と述べています。ちなみに、ボクシング映画といえば、一条真也の映画館「レッドシューズ」で紹介した朝比奈彩主演の日本映画が2023年2月24日から全国公開されます。わたしもチョイ役で出演していますので、よろしく!
CHAPTER13「『スピルバーグ監督作品』ならこの1本」では、1960年代末のアメリカ映画は、アメリカン・ニューシネマ一色だったことが紹介されます。アメリカン・ニューシネマとは、反体制色が濃い、アン・ハッピー・エンドのシビアな映画のことです。著者は、「当時、ベトナム戦争の反戦運動が全米に広がり、大衆は夢物語を見る気分ではなくなっていたから、それまで人気だったミュージカル・西部劇・ラブコメ等の娯楽映画のジャンルは一気に衰退し、『俺たちに明日はない』『イージー・ライダー』『いちご白書』等のメッセージ性の強い社会派映画がもてはやされていた。もてはやされたと言ってもそれは若者だけの話で、大衆は映画にメッセージなど求めていなかったから、1970年代前半のアメリカでは映画の興行収入がガタ落ちになった。そんな中、純粋な娯楽映画をひっさげて登場したのがスピルバーグである」と述べています。なるほど、ハリウッドの巨匠スピルバーグ誕生の背景がよくわかりました。
かつて、哲学者ニーチェがあらゆるクリエイターをディオニソス的とアポロン的の2通りに分類したことを指摘し、著者は「ディオニソス的クリエイターとは、過去の他人の作品を否定・破壊し、全く新しいものを作ろうとする人。アポロン的クリエイターとは、過去の作品に強い影響を受け、それを研究して自分なりの再現を図る人。日本の映画監督で言えば、是枝裕和、北野武、河瀨直美といった芸術色の強い監督はディオニソス的で、山崎貴、福田雄一、三谷幸喜といった娯楽色の強い監督はアポロン的と言える。スピルバーグは言うまでもなくアポロン的クリエイターだ。彼の作品は、彼が見た作品の過去ログで成り立っている」と述べています。また、スピルバーグが最も強い影響を受けているのがディズニーであることを指摘し、「アメリカでディズニーのTVショウ『ディズニーランド』の放送が始まったのは1954年。8歳のスピルバーグ少年がこの番組にハマったことは想像に難くない。『A.I.』のストーリーは完全に『ピノキオ』だし、『フック』は『ピーター・パン』の後日譚。『レイダース』の出だしはロサンゼルスのディズニーランドのアトラクション「ジャングルクルーズ」だし、『魔宮の伝説』のクライマックスは『スペースマウンテン』にしか見えない」と述べます。これまた、テレビの『ディズニーランド』をリアルタイムで観ていたという著者ならではの見方ですね。
CHAPTER14「『東野圭吾原作映画』ならこの1本」では、著者は「いつの時代にも、書く小説、書く小説、片っぱしから映画化される人気作家というのはいるもので、映画黄金期の昭和30年代には、映画化総数82本の石坂洋次郎、80本の源氏鶏太という、とてつもない記録の持ち主がいた。ミステリーに絞れば、46本の江戸川乱歩、42本の横溝正史、36本の松本清張が歴代ベスト3で、さらに現代に絞れば、これは国内で22本、海外で6本の計28本が作られている東野圭吾がダントツである(2022年9月公開予定『沈黙のパレード』を含む)。これにつづく赤川次郎が16本だから、東野圭吾がいかに抜きんでているか、おわかりいただけよう」と述べてから、東野圭吾の小説の映画化作品の話を展開します。そんな東野もデビューから13年間はヒットに恵まれませんでした。ブレークのキッカケは、1998年の『秘密』です。この作品は、母娘がバス事故に遭い、意識を失った娘の身体に亡くなった母親の魂が入り、夫がそのことを世間には秘密にして、娘の外見をした妻と暮らす、という性的にゾクゾクする話で、本もよく売れ、翌年、広末涼子・小林薫主演で映画化。フランスでリメイクもされました。わたしも大好きな作品です。
CHAPTER15「『21世紀のミュージカル映画』ならこの1本」では、世の中には、タモリを筆頭に、ミュージカルが大嫌いと広言する人が大勢いるとして、著者は「それまで普通に喋っていた役者が突然歌い出すなんて、恥ずかしくて見てられない、というのだ。だが、『ウエスト・サイド物語』の作曲者でクラシック界の高名な指揮者でもあるレナード・バーンスタインが定義した通り、歌でドラマが進行するのがオペラ、ドラマの結果として感情を歌に託すのがミュージカル――つまり、よくできたミュージカルは、人間が自然に歌いたくなるようなドラマ的お膳立てがキチンと設定されているもので、それが自然に見えないようでは、ミュージカルとは呼べないのである。だが、いくらお膳立てがあっても、いきなりドヤ顔で歌い始めるなんて、引っ込み思案の日本人には至難の業だ」と述べています。
そして、21世紀ベスト・ミュージカルとして、著者は、ミュージカルがアメリカ発祥の文化であることを踏まえ、アメリカ映画界が自国の音楽に絶大な自信を持って世に送った『ドリーム・ガールズ』『ヘアスプレー』『ジャージー・ボーイズ』の3本を推します。この3本について、著者は「いずれも、ヒットチャートで黒人と白人の壁が取り払われ、ポピュラー音楽が変わり始めた1962年という年をピン・ポイントで描いた作品。ちなみに、ミュージカルではないが、2019年にアカデミー最優秀作品賞を受賞した『グリーンブック』も、その前年に最優秀作品賞を受賞した『シェイプ・オブ・ウォーター』も、さらにその前年に作品賞候補になった『ドリーム』も、舞台は1962年。もしも『ドリーム 』が受賞していたら、アカデミー作品賞は3年連続で1962年を描いた作品が受賞したことになる。アメリカ人は、本当に1962年という年が好きなのだ(おそらく世界が最も輝いていた年だからだろう)」と述べます。わたしが生まれる前年ですね。
CHAPTER16「『クリント・イーストウッド監督作品』ならこの1本」では、アメリカには、映画館主がその年一番儲けさせてくれたスターを投票で選ぶ「マネー・メイキング・スター」という顕彰制度があることが紹介されます。著者は、「クリント・イーストウッドは、1972年、73年、83年、84年、93年と5度1位に輝き、アメリカ最大の人気スターの座に駆け上がっていく(ちなみに、クリントがトップ10入りをした回数は21回で、これはすべての時代の俳優を通じて、ジョン・ウェインの25回に次ぐ2位である)」と述べます。そして、彼の「この1本」として、78歳で撮った『グラン・トリノ』を勧めます。著者は、「最後に殴り込みがある高倉健の任侠映画みたいな話で、適度なユーモアもあり、なじみやすい作品だ。この後、88歳で『運び屋』(実在の90歳の運び屋を描いた作品)、91歳で『クライ・マッチョ』(最後のカウボーイ映画という感じだった)にも主演しているが、その役は『グラン・鳥の』の老人とほとんど同じキャラクターなので、続けて見るのも手だ」と述べます。
CHAPTER17「『ⅮCコミックス映画』ならこの1本」では、アメリカでは、スーパーマン・バットマンの2大ヒーローの人気を受け、1940年までに150のコミック誌が乱立したことが紹介されます。この年、ⅮCコミックスは、フラッシュ、ワンダーウーマン、グリーン・ランタン、アクアマンが出揃い、黄金時代を迎えました。1941年には、キャラクターをまとめて売り出すためのヒーロー連合「ジャスティス・ソサエティ・オヴ・アメリカ」が登場。このヒーロー連合は1961年に「ジャスティス・リーグ」としてリブートされ、それに触発されたマーベルが『ファンタスティック・フォー』を世に送り、これが後の『アベンジャーズ』の構想につながることになります。ユニバーサルも、2017年のトム・クルーズ主演の『ザ・マミー』を筆頭に、かつて同社の十八番だったモンスター物の半魚人、ドラキュラ、フランケンシュタインを、時間軸と舞台を共有した「ダーク・ユニバース」としてリブートさせることを発表しました。しかし、『ザ・マミー』の興行的失敗で、計画は棚上げ。著者は「今のところ、マーベル以外、ユニバース化に成功した会社はないようである」と書いていますが、「ダーク・ユニバース」を楽しみにしていたわたしとしては残念でなりません。
CHAPTER18『山崎貴監督作品』ならこの1本」では、著者は「こと、実写映画に限って言えば、21世紀の日本映画界の4番打者は山崎貴監督である――このことに、どなたも異存はあるまい。2020東京五輪の開閉会式の統括ディレクターに任命されたのも、妥当な人選と言える。その五輪の開催がコロナで延期され、山崎監督も参加していた開閉会式の制作チームが解散させられたとき(何があったかは知りませんが)、週刊文春が『山崎貴は、風船で作った実物大のゴジラが新国立競技場を覗く、などの非現実的な提案をして、他のメンバーからダメ出しされていた』と書いていたが、もしそれが本当なら、素晴らしいアイディアだったと思う。新国立競技場を覗く実物大のゴジラ、本当に出せば世界中でウケたと思うけどなぁ」と書いています。わたしは東京五輪の開催そのものに反対だったのですが、この「風船で作った実物大のゴジラが新国立競技場を覗く」という山埼貴のアイデアは面白かったと思います。ちなみに、著者の山崎貴の「この1本」は、『ALWAYS 三丁目の夕日』。わたしも、まったく同意見です!
CHAPTER20「『高倉健任侠映画』ならこの1本」では、最初に「任侠」という言葉の定義がされます。著者は、「辞書的な意味は、『弱きを助け、強きをくじく気性に富むこと』。そうした生き方を建前とする人を、『侠客』と呼ぶ。任侠映画の第一人者、マキノ雅弘監督は、『侠客』を『やくざな稼業をしていても、やくざな生活はしない人』と定義した。たとえば、賭博を生業にした渡世人でも、普段は貧乏長屋で暮らし、近所の人から頼まれた仕事は何でもやってやり、周りから粋な男と思われるために、角帯をピシッと結んだり刺青を入れたりしている――そうしたストイックな生き方をしているのが、本物の侠客。ところが今の暴力団は、運送業とか土建業とか稼業の方がまともで、生活がやくざだから困ったものだ、とマキノ雅弘は嘆く」と書いています。
マキノ雅弘監督といえば、「次郎長三国志シリーズ」で知られます。著者は、「漫画家・尾田栄一郎は、この『次郎長三国志シリーズ』の大ファンで(『ONE PIECE』の仲間感は、明らかにマキノの次郎長一家の影響を受けている)、同じくファンだというスタジオジブリの鈴木敏夫と共に東宝に直談判してDVDを再発売させ、ジャケットの絵を描いた」と紹介しています。また、それだけでなく、尾田栄一郎は「黒澤明という名前は誰でも知っていると思います。世界中が知っている日本映画の巨匠です。例えばボクシングにおいて大スターが生まれた時代、脚光を浴びる大スターの陰には階級違いのチャンピオンが存在します。マキノ雅弘という監督がまさに、若い世代に受け継がれ損ねている日本映画の偉大なチャンピオン、その1人です」という一文も寄せています。
CHAPTER21「『角川映画』ならこの1本」では、日本映画界の最盛期は1958年であり、この年、日本人はのべ11億2745万人が映画館に足を運び、全国民が1年間に1人平均12.3本の映画を見ていたことが紹介されます。しかし、テレビの普及により、映画人気は急速に下降。特に下降ぶりが著しかったのが邦画で、邦画全体の配給収入は1958年の299億円から、14年後の1972年には148億円と、半分以下に減少しました。著者は、「この間、物価は5倍に上がっているから、物価換算すれば10分の1以下に下がったことになる。さらに、1958年には洋画の3倍以上稼いでいた邦画が、観客動員を洋画に逆転されたのが、1975年。1970年代半ばは、日本映画のドン底期だった。そんなドン底期に登場した人物が、角川春樹である。角川春樹は、1976年10月公開の第1作『犬神家の一族』から、1993年7月、自らが監督した『REX 恐竜物語』の公開中に麻薬で逮捕されて角川書店社長を辞任するまでの17年の間に、550本の実写、15本のアニメ、1本のドキュメンタリー映画を制作し、日本映画に新風どころか台風を送り込んだ」と述べています。
CHAPTER23「『若大将シリーズ』ならこの1本」では、東宝の大ヒットシリーズが取り上げられます。若大将を演じたのは加山雄三です。1956年にデビューして日本映画全盛の1958年に主演作を連打した石原裕次郎に比べれば、3歳年下ですでに映画が下降期に入り始めた1960年にデビューした加山雄三は、遅れてきた映画スターであり、マネーメーキング的にはいささか見劣りするとしながらも、著者は「こと、音楽に限って言えば、加山雄三は石原裕次郎をはるかに超えた巨人である。石原裕次郎もスロー・バラードなんか歌うと味があって捨てがたい名歌手なのだが、なにしろ加山雄三は、演歌と歌謡曲しかなかった日本の音楽シーンにポップスという概念を打ち立てた日本初のシンガー・ソング・ライターである。しかも、日本で最初に半音階を使いこなし、エレキ・バンドを率いて日本中にバンド・ブームを起こしたロック・ミュージシャンであり、武道館で初めてコンサートを行い、来日したビートルズと日本人で唯一個人的に食事をした歌手でもある。エルビス・プレスリーを筆頭に映画の中で歌ったスターはたくさんいるが、自分の主演シリーズで自分が作曲した歌を歌いまくったスターは、加山雄三しかいない。そして、その楽曲は、桑田佳祐、松任谷由実、山下達郎といった後のミュージシャンに浅からぬ影響を与え、Jポップの原点となった」と述べています。
本書の著者であるホイチョイ・プロダクションズの馬場康夫氏は、『私をスキーに連れてって』『彼女が水着にきがえたら』『波の数だけ抱きしめて』などを送り出した映画監督でもあります。『私をスキーに連れてって』は、わたしの処女作である『ハートフルに遊ぶ』(東急エージェンシー)でも取り上げました。でも、わたしが一番好きな馬場監督の映画は『波の数だけ抱きしめて』です。冒頭の結婚式のシーンで中山美穂の花嫁姿が登場するのですが、ミポリンのあまりの美しさに、わたしは恍惚状態になりました。1970年代半ば、渋谷の消防署の向かいのビルの2階に「メルス」というカフェがあり、そこがホイチョイの仲間のたまり場になっていたそうです。本書の「あとがき」で、著者は「1991年、ボクは、自分が『メルス』に出入りしていた1982年の若者たちを描いた映画『波の数だけ抱きしめて』を撮った。あの映画で、中山美穂や織田裕二たちがバイトしている茅ケ崎のサーフショップを『サンデービーチ』、松下由樹が働いていた辻堂のカフェを『メルス』と名づけたのは、ボクのささやかな感傷だ」と書いています。
 松下由樹さんに花束を贈呈
松下由樹さんに花束を贈呈
ああ、そう言えば、『波の数だけ抱きしめて』には松下由樹さんも出ていたのでした。ブログ「花束贈呈と舞台挨拶」で紹介したように、わたしは2022年12月7日の映画『レッドシューズ』の北九州先行公開記念舞台挨拶で松下さんに花束をお渡ししましたが、そのとき、思わず「昔からファンでした」と言ってしまったのですが、無意識に彼女が『波の数だけ抱きしめて』という大好きな映画に出演していたことを思い出していたのかもしれません。いつの日か、憧れのミポリンにもお会いしたいものです。それにしても、映画の記憶というのは、本当に人生の思い出そのものだなと思います。そして、映画は観る者を「心ゆたか」にしてくれます。
最後に、「あとがき」で著者は「ボクが一番好きな映画は、ある日は『大空港』だし、別な日は『冒険者たち』だし、また別な日は『おかしな二人』だし『アメリカン・グラフィティ』だし『ラッシュ』だし『グリーンブック』だし――気分によって、一番になる映画は他にもたくさんある」と述べるのでした。わたしは、学生時代に『TeLePAL』という小学館のTV雑誌に連載されていたホイチョイ・プロダクションズの「酒とビデオの日々」という映画コラムを愛読していました。単行本化を切望していたのですが、叶いませんでした。しかし、そのホイチョイ・プロダクションズの馬場康夫さんが書いた本書には映画への愛情が溢れていました。拙著『心ゆたかな映画』(現代書林)を本書と同じ2022年に上梓できたことは、わたしにとって大きな喜びであります。