- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2023.02.20
詩集『開』鎌田東二著(土曜美術社出版販売)を読みました。著者から献本していただきました。 一条真也の読書館『常世の時軸』で紹介した著者の第一詩集、一条真也の読書館『夢通分娩』で紹介した第二詩集、 一条真也の読書館『狂天慟地』で紹介した第三詩集から成る「神話詩三部作」の完結後、著者は「詩人」としてはしばらく「休火山」とし、溜まっている論文や本の執筆に注力されると宣言しました。しかし、あくまでも「休火山」であり、「死火山」ではありませんでした。一条真也の読書館『絶体絶命』で紹介した第四詩集で鎌田休火山は再び噴火したのでした。本書は、それに続く第五詩集となります。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、序詩「開」にある「ひらけごま 開け ゴマ 披け 誤魔 拓け 護摩 開け 互真 ひらけごま」という言葉が書かれています。
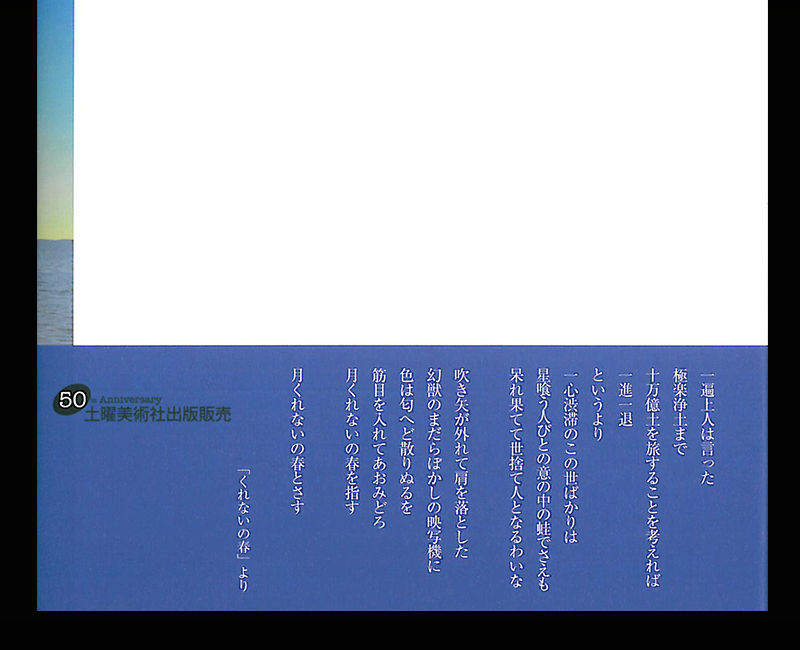 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
一遍上人は言った
極楽浄土まで
十万億土を旅することを考えれば
一進一退
というより
一心渋滞のこの世ばかりは
星喰う人びとの意の中の蛙でさえも
呆れ果てて世捨て人となるわいな
吹き矢が外れて肩を落とした
幻獣のまだらぼかしの映写機に
色は匂へど散りぬるを
筋目を入れてあおみどろ
月くれないの春を指す
月くれないの春とさす
「くれないの春」より
本書の「目次」は、以下の通りです。
序詩「開」
第1章 閉開
奥敷
埋もれし神
鬼の宿
風聴き人
開く
開廊
自由
第2章 無底
どん底
危機
浦島効果
いずれ おや
平凡
にぎりめしは
第3章 鎮魂
立待 佐藤泰志に捧ぐ
落ち声拾い
イケズ
くれないの春
三声一味 沼袋甲児、猫柳緑、袋小路揚麿
蒸しパン黙示録
立待岬の行方不明者
第4章 開放譚 スサノヲの叫び
死
悲
怒
流
歌
終詩「ラプラタ」
著者の詩集はイメージの万華鏡のようなものですので、わたしもそこに記されている言葉をフックとして、自由自在にイメージの世界を旅したいと思います。まず、冒頭に置かれた「開」という詩には「世界の涯は 果て無く 世の末は すげなく いたぶりの code を巻きつけて 深海列車は散った 亡き人を乗せて」と書かれています。「世界の涯」という単語から、わたしは一条真也の映画館「世界の涯てに」で紹介した映画を連想しました。1996年の香港映画です。原題は「天涯海角/Lost and Found」です。「不治の病に冒された娘と、彼女が恋する英国と香港の二人の青年の三角関係を描くラヴ・ロマンス。監督・製作・脚本は『月夜の願い』のリー・チーガイ。
わたしがこの映画を観たのは、著者のおススメ作品だからでした。わたしたちが満月の夜毎に交わしている「ムーンサルトレター」の第127信で、わたしは日本映画「母と暮せば」のことを書きました。いわゆる幽霊映画ですが、その「幽霊」とは恐怖の対象ではありません。あくまでも、それは愛慕の対象としての幽霊です。生者にとって優しく、愛しく、なつかしい幽霊、いわば「優霊」です。そこには、「幽霊でもいいから、今は亡き愛する人に会いたい」という生者の切実な想いがあります。わたしは、映画とはもともと「死者との再会」という人類普遍の願いを実現するグリーフケア・メディアだと考えています。そんなことを「ムーンサルトレター」第127信に書きました。
すると、著者からは以下のような返信が来ました。
「『優霊譚』でわたしが好きなのは、リー・チーガイ監督・金城武主演の『世界の涯てに』(原題:『天涯海角/Lost and Found』1996年、111分、香港映画)です。といっても、『優霊』になるのは、ラストシーンだけなので、『優霊』としての登場場面はわずかですが…。あらすじを紹介すると、ネタバレで申し訳ないのですが、あまりに好きな映画なので、紹介させてください。主人公は、香港のブルジョワ娘ケリーと、天涯孤独の探偵(何でも屋)を職業としている青年チュンの二人です。その二人の出会いと結婚と死に至るラブストーリーがこの『世界の涯てに』です。その出だしのシーンから、実に、実に泣けてくるんだよな〜、なぜか。わたしは海のシーンに弱いのです。香港の海から港に入っていく海船シーン。そこに、渋いレナード・コーエンの”Dance me to the End of Love”がかぶってきます。これだけで、イカン、イカン…」
たしかにレナード・コーエンの”Dance me to the End of Love”は名曲ですね。年輪を重ねた老夫婦たちが続々と登場するプロモーションヴィデオも素晴らしく、YouTubeを観て一発で好きになりました。著者は、さらに同レターに「わたしは子供の頃から、『世界の涯て』という言葉に大変弱いので、もうそれだけで滂沱の。。。なのです。わたしが着ている服はいつも”Land’s End”なのですが、それくらい、『地の果て』『世界の果て』が好きなのです。『俺はいつも「世界の果て」(”Land’s End”の服のこと)と共にいる!』と思うだけで、幸せになります(単純そのもの!)」とも書いています。
第1章 「閉開」の「埋もれし神」という詩には、「そのうしとらの大金神と恐れられてきた神が 体主霊従極まりて 乱れに乱れた世の末に 世直しの神 心直しの神として」という言葉が出てきます。「うしとらの大金神」とは、「艮の金神」のことです。「艮の金神」とは、日本に古くから伝わる陰陽道の言葉です。「金神」とは”祟り神”のことで、また「艮」とは東北の意味で、もっとも恐れられている”鬼門”の方位です。したがって、「艮の金神」とは数ある金神の中でも、もっとも恐ろしい鬼門の方位にわだかまる”猛悪の祟り神”ということになります。この神は大本教の開祖である出口なおに憑依したとされていますが、普通の常識からすれば、出口なおはとんでもないドエライ祟り神にとりつかれてしまったということになります。しかし、艮の金神は、全大宇宙の創造主・唯一絶対神である大国常立大神(天御中主大神)のご分霊で、国祖として知られる国常立尊です。 古典では国之常立神(「古事記」)、国常立尊(「日本書記」)とも呼ばれます。
続いて、「埋もれし神」には「世の立て替え立て直しを 思い定めて三千大世界 松の世にいたさんと 霊主体従の新世界創造に 世の仕組みを組み直す」という詩句が登場します。明治31年(1898年)10月、風変わりな格好をした青年が、綾部の出口なおの元にやってきました。陣羽織を羽織り、手にコウモリ傘とバスケットを持ち、歯にはお歯黒……。彼は上田喜三郎と名のりました。綾部の東の方、亀岡からやってきたこの青年は、神の正体を判定する審神者(さにわ)をしていました。彼こそが後に大本を担うことになる出口王仁三郎です。これがなおと王仁三郎の初対面でした。王仁三郎はこの詩句のように「世の立て替え立て直し」によって「三千世界」というユートピアの創造を目指しました。「霊主体従」とは、魂、精神、良心など、霊的、精神的なものを〝主体〟として、物質的な欲望を制御しながら〝従〟として、自分の魂、精神を成長させながら生きていくという考え方です。
第1章 「閉開」の「鬼の宿」では、以下のような恐ろしい鬼の言葉が書かれています。
思い上がるな ニンゲンどもよ
おまえたちのはからいが何を生みだし
何をもたらしたか
総決算するのは おまえたちではない
それは 我ら 鬼の仕事だ
我らは ニンゲンたちのふるまいを見てるぞ
ずっとずっとむかしから
思い知れ おのれの業を
おのれのふるまいを
「鬼の宿」を読んで、わたしは一条真也の映画館「『鬼滅の刃』上弦集結、そして刀鍛冶の里へ」で紹介したアニメ映画を連想しました。社会現象と呼べるまでのブームを巻き起こした「鬼滅の刃」は、大正時代を舞台に主人公が鬼と化した妹を人間に戻す方法を探すために戦う姿を描いていますが、鬼も哀しい存在として描かれています。特に「遊郭編」第10話・第11話に登場する上弦の陸・堕姫と妓夫太郎は悲しい宿命を帯びた兄妹であり、まさにグリーフの物語でした。わたしは、子どもの頃から新美南吉の『ごんぎつね』が愛読書です。狐にまつわる童話ですが、鶴にまつわる『つるのおんがえし』、鬼にまつわる『泣いた赤鬼』などの日本の童話も好きでした。最後には狐や鶴や鬼が死ぬ物語で、残された者の悲しみが描かれています。
鬼にちなんだ歌といえば、ブログ「虹鬼伝説」で紹介した「バク転神道ソングライター」である著者の名曲「虹鬼伝説」を思い出します。この曲について、著者は「子どものころしばしば鬼を見た。天河大弁財天社には2月2日の夜に祖霊でマレビトである『鬼』を迎える『鬼の宿』という神事がある。鬼とはいったい何か。わたしは今も鬼に魅せられ続けている。『虹の祭り』のイメージソングとして生まれた」とコメントされています。わたしは、この「虹鬼伝説」という歌が大好きです。これほど「平和」や「平等」を発信したメッセージソングはないと思います。まさに、コンパッション・ソングであり、グリーフケア・ソングだと言えるでしょう。節分の夜、「『鬼滅の刃』上弦集結、そして刀鍛冶の里へ」を観終わって、無性に著者にお会いしたくなりました。
第1章 「閉開」の「開廊」という詩では、「さとびとはよんだ 逃げて!」「しびとはさけんだ 来て!」「ひとびとはしのんだ 弔って!」という言葉が出てきます。この「弔って!」の一語がわたしの胸に突き刺さりました。この詩の冒頭には「おりてゆく 廻廊 下廊 墜廊」という言葉が置かれているので、何らかの災害か事故を連想させますが、わたしは東日本大震災で被災地の家屋が倒壊したイメージが浮かんできました。2011年3月11日は、日本人にとって決して忘れることのできない日になりました。三陸沖の海底で起こった巨大な地震は、信じられないほどの高さの大津波を引き起こし、東北から関東にかけての太平洋岸の海沿いの街や村々に壊滅的な被害をもたらしました。
東日本大震災における遺体確認は困難を極めました。津波によって遺体が流されたことも大きな原因の1つで、同じ震災でも、阪神淡路大震災のときとは事情が違っていました。これまでの日本の災害や人災の歴史を見ても、東日本大震災を「史上最悪の埋葬環境」と言った葬祭業者も多かったです。そんな劣悪な環境の中で、日夜、必死に頑張っておられたのが自衛隊の方々でした。東日本大震災において、自衛隊は多くの遺体搬送を担いました。「統合任務部隊」として、最大で200人もの隊員が「おくりびと」となったのです。遺体搬送は、自衛隊の災害派遣では初めての任務で、整列、敬礼、6人で棺を運ぶという手順を現場で決められたといいます。
本来は人命を守るはずの自衛隊員が遺体の前で整列し、丁寧に敬礼をする姿には多くの人が感銘を受けました。わたしも同様に感動しました。そこには、亡くなった方に敬意を表するという「人間尊重」の姿があったからです。そして、埋葬という行為がいかに「人間の尊厳」に直結しているかを痛感しました。東日本大震災では、これまでの災害にはなかった光景が見られました。それは、遺体が発見されたとき、遺族が一同に「ありがとうございました」と感謝の言葉を述べ、何度も深々と礼をされていたことです。従来の遺体発見時においては、遺族はただ泣き崩れることがほとんどでした。しかし、東日本大震災は、遺体を見つけてもらうことがどんなに有難いことかを遺族が思い知った初めての天災だったように思えます。遺体を前に葬儀をあげることができるのは、じつは幸せなことなのです。
第3章「鎮魂」の「立待 佐藤泰志に捧ぐ」の冒頭は、以下のようになっています。
立待岬からのびているひとすじの道
歩いているうちに気づいた
死がそこにあるから 今ここのこのいのちが輝くのだと
津軽海峡を望みながら歌った
佐藤泰志への鎮魂歌(レクイエム)
君の死が教えた
光があるから闇があるのではなく
闇の中で 闇を潜って 光りが輝くのだと
佐藤泰志は、著者の大学の同級生です。この詩の最後には、「佐藤泰志が書いた哲学科の卒業論文の題目は『神なきあとの人間の問題―ツァラトゥストラ研究』だった。僕の書いた卒業論文の題目は『東洋と西洋における神秘主義の基礎的問題への試論』。空海とドイツの神秘哲学者ヤコブ・ベーメの神秘体験と言語哲学を問いかけるもので『神仏を体験した人間の問題』だった。芥川賞候補に5回、『そこのみにて光輝く』で第2回三島賞候補になった佐藤は、1990年10月10日、国分寺の自宅近くで自死した。享年41歳。函館生まれ。1971年、佐藤は同人誌『立待』を創刊した。そして佐藤と同じ大学の同じ哲学科の教室で佐藤と僕は対論し岐れた。半世紀も前のこと」という注が添えられています。
この詩に書かれた「君の死が教えた 光があるから闇があるのではなく 闇の中で 闇を潜って 光りが輝くのだと」という言葉から、わたしは「岩戸開き」のことを思いました。ブログ「古事記〜天と地といのちの架け橋〜」に書いたように、2014年10月12日、ミャンマーに行く前日、東京は両国の「シアターX」で東京ノーヴィレパートリーシアターによる「古事記〜天と地といのちの架け橋〜」の舞台を鑑賞しました。原作は、一条真也の読書館『超訳 古事記』で紹介した著者の本です。この舞台の第2部のラストシーンは、まさに神々が大笑いして岩戸屋が開き、世界に再び光が戻る感動的な場面でした。わたしは、この場面を観ながら、当時の著者が網膜剥離で緊急出術および治療生活を経験され、その結果、めでたく視力が回復したことを思いました著者は個人的な「岩戸開き」を体験したのかもしれないと思いました。ラストシーンでは神々が手に鏡を持ち、アマテラスが放つ光をそれぞれが反射している場面も印象的でした。この世に住むわたしたちも、各自が小さな太陽として光り輝きたいものだと思いました。
ところで、わが社の社名は「サンレー」といいます。これには、「SUN−RAY(太陽の光)」そして「産霊(むすび)」の意味がともにあります。わが社は葬儀後の遺族の方々の悲しみを軽くするグリーフケアのサポートに力を注いでいるのですが、一条真也の読書館『古事記ワンダーランド』で紹介した著者の本を読んで、それが必然であることに気づきました。なぜなら、グリーフケアとは、闇に光を射すことです。洞窟に閉じ籠っている人を明るい世界へ戻すことです。そして、それが「むすび」につながるのです。わたしは、「SUN−RAY(太陽の光)」と「産霊(むすび)」がグリーフケアを介することによって見事につながることに非常に驚くとともに安心しました。ちなみに、わが社の社歌は神道ソングライターでもある著者に作詞・作曲していただいています。
舞台「古事記〜天と地といのちの架け橋」ですが、原作者である著者は「いのちの賛歌としての『古事記』」という一文を寄せ、「古事記はいのちの賛歌である。それが日本民族の叙事詩であることは間違いないが、そこにもっとおおらかな宇宙的ないのちの歌声がある」と書かれています。この「おおらかな宇宙的ないのちの歌声」とは「産霊」のことにほかなりません。そう、この舞台は、大いなる「産霊」の物語でした。そして、詩集『開』は新時代の扉を開く言霊の書のように感じました。グリーフケアの時代、コンパッションの時代、ウェルビーイングの時代……さまざまな時代の訪れがこの詩集から感じられます。そして、この詩集に収められた詩、および本書を上梓した直後に著者が書いた数々の詩には圧倒的な死生観が滲み出ており、読む者の魂を揺さぶります。言葉には力がある。物語には力がある。著者が紡いできた一連の詩集はもはや神話ではないかとさえ思います。著者の詩集は旅なのだとも思います。文字を持たなかった縄文人が口伝で語られたであろう神々の物語。それがこの詩ではないかと思いました。間違いなく著者は当代一の吟遊詩人です。闇の中の光から生まれてくる著者の新しい詩を、いつまでも、いつまでも、読み続けたいと心から願います。
