- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2243 宗教・精神世界 | 心霊・スピリチュアル 『神智学と仏教』 吉永進一著(法蔵館)
2023.05.31
『神智学と仏教』吉永進一著(法蔵館)を読みました。著者は1957年生まれ。京都大学理学部生物学科卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程修了。専門は近代宗教史・秘教思想史。舞鶴工業高等専門学校人文科学部門教授を退任後、龍谷大学世界仏教文化研究センター客員研究員。共編著に一条真也の読書館『近代仏教スタディーズ』、『近現代日本の民間精神療法』で紹介した本があります。
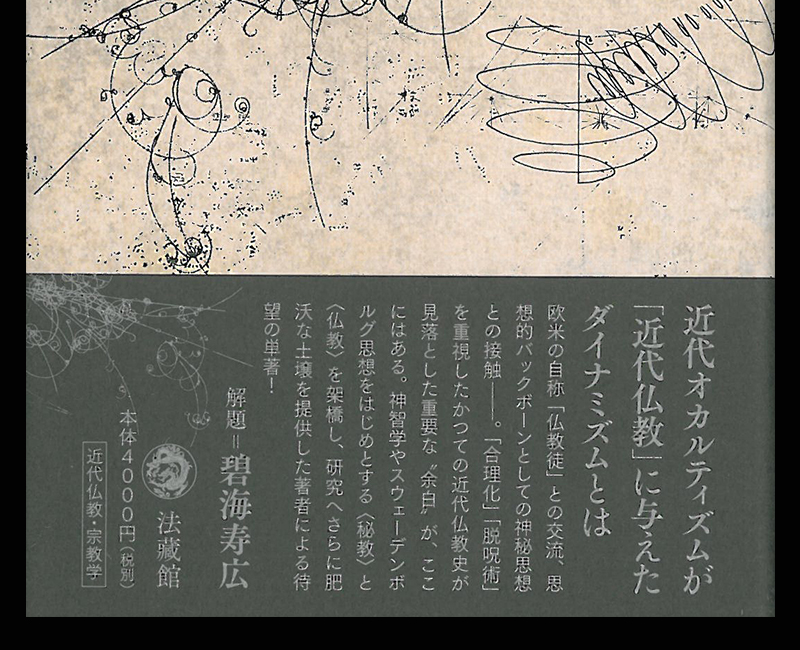 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「近代オカルティズムが『近代仏教』に与えたダイナミズムとは」として、「欧米の自称「仏教徒」との交流、思想的バックボーンとしての神秘思想との接触――。「合理化」「脱呪術」を重視したかつての近代仏教史が見落としてきた重要な〝余白〟が、ここにはある。神智学やスウェーデンボルグの思想をはじめとする〈秘教〉と〈仏教〉を架橋し、研究へさらに肥沃な土壌を提供した著者による待望の単著! 解題=碧海寿広」とあります。
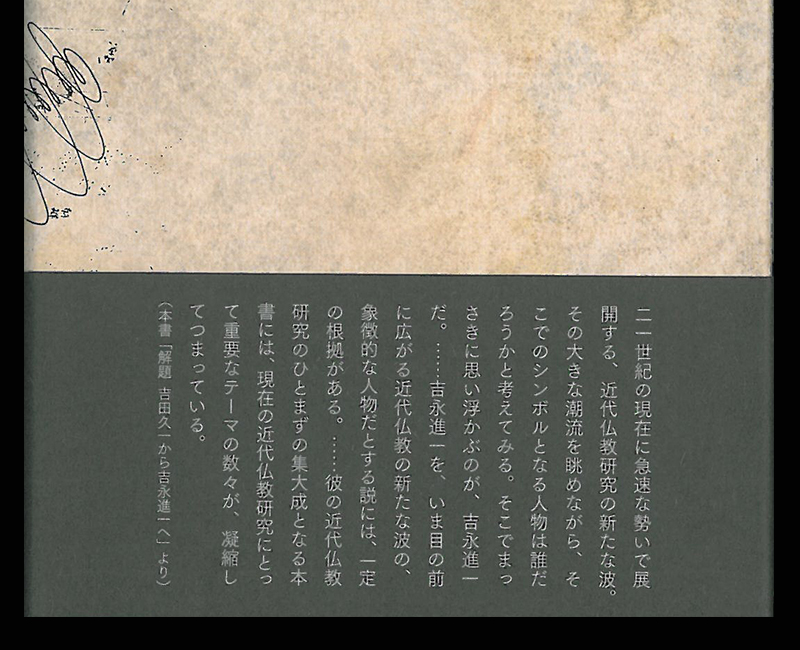 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「21世紀の現在に急速な勢いで展開する、近代仏教研究の新たな波。その大きな潮流を眺めながら、そこでのシンボルとなる人物は誰だろうかと考えてみる。そこでまっさきに思い浮かぶのが、吉永進一だ。……吉永進一を、いま目の前に広がる近代仏教の新たな波の、象徴的な人物だとする説には、一定の根拠がある。……彼の近代仏教研究のひとまずの集大成となる本書には、現在の近代仏教研究にとって重要なテーマの数々が、凝縮してつまっている。(本書「解題 吉田久一から吉永進一へ」より)」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
序 章 似て非なる他者
―近代仏教史における神智学―
Ⅰ 神智学の歴史
第一章 チベット行きのゆっくりした船
―アメリカ秘教運動における「東洋」像―
第二章 近代日本における神智学思想の歴史
第三章 明治期日本の知識
Ⅱ 仏教との交錯
第一章 仏教ネットワークの時代
―明治二〇年代の伝道と交流―
第二章 オルコット去りし後
―世紀の変わり目における神智学と〝新仏教徒〟―
第三章 平井金三、その生涯
Ⅲ 霊性思想と近代日本
第一章 仏教雑誌のスウェーデンボルグ
第二章 大拙とスウェーデンボルグ―その歴史的背景―
第三章 らいてうの「天才」
終 章 神智学と仏教、マクガヴァンとその周辺
「解題 吉田久一から吉永進一へ」碧海寿広
「初出一覧」
「あとがき」
序章「似て非なる他者―近代仏教史における神智学―」の「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「アメリカにおける仏教について、大変要領よく俯瞰したケネス・タナカ『アメリカ仏教――仏教も変わる、アメリカも変わる』によれば、2007年の仏教者数は推測で300万人、1970年代半ばから現在までで15倍の伸びであったという。しかもロバート・ウスノーの研究では、仏教に影響されていると自認する者はアメリカ全人口の12パーセントに及ぶ。ヴィクトリア朝時代の流行、戦後のビート禅の流行と異なり、もはやアメリカ社会に定着しつつあるようにも見える。このように数的にも社会的にも確立しているならば、当然、アメリカ社会への同化が行われる。タナカはアジア仏教と異なるアメリカ仏教の特徴として、平等化、メディテーション中心、参加仏教(エンゲージドブディズム)、超宗派性、個人化宗教を挙げている」
現在のインターネットとジェット機によるネットワークの原型は、19世紀後半、手紙、電信と蒸気船がすべてであった時代に存在していました。ただし、著者は「19世紀末から20世紀にかけての初期の接触は、必ずしも、ネットワークという語から連想するような予定調和的な場ではなく、さまざまな戦略の競い合う交渉の場であり、メアリー・プラットのいう『コンタクトゾーン』の定義を借用すれば、『さまざまな文化が出会い、衝突し、互いに取っ組み合う社会的空間』であったとしてそのような場の1つがシカゴ万国宗教会議であり、継続的に交流の接点を提供した運動の1つが神智学協会であった」と書いています。
神智学協会は、1880年代後半にはインド各地、ロンドン、ニューヨークなどに支部を持つ国際運動に成長していました。神智学は仏教を評価し、あるいは仏教を自称しましたが、欧米では仏教に興味を持つ人々をひきつけ、アジアでは仏教者と接触し、組織的に両者の間をつなぐ働きをしました。さらに会長のヘンリー・スティール・オルコットは、ヨーロッパ、スリランカ、ビルマ(ミャンマー)、日本などを訪問し、仏教復興に尽力しています。仏教側も、日本やビルマ、ロンドンを軸としたネットワークを構築するが、その誘因となったのは神智学の存在でした。
神智学への研究上での扱いは大きく変わってきていますが、著者は、それはさらに3つの学問領域に分けられるといいます。第一に、「秘教思想史」研究の進展があります。代表的な研究者であるW・ハネフラーフは、その論文「西洋秘教の研究」において、秘教思想研究で1980年代まで支配的であったフレームワークを「イェイツ・パラダイム」と呼んでいます。ルネサンス史研究者フランセス・イェイツは、近代科学の発達がジョルダーノ・ブルーノのようなヘルメス主義者に多くを負っていると主張し、進歩に関する近代主義の大きな物語を、その対極にあるオカルト的領域に結びつけることで喝采を浴びました。しかし、実証的な研究が進み、イェイツの研究は今日では批判を浴びています。著者は、「このパラダイムが消えた後、1990年代に登場したのは、18世紀秘教思想研究者アントワーヌ・フェイブルが秘教に与えた六つの定義にもとづくパラダイムである」と述べています。
ハネフラーフが問題視するのは、宗教学で今なお存続しているタイラー、フレイザー以来の「宗教、科学、魔術」の三分法です。合理性と科学に適合しない、宗教にも属さない、残余の部分が「オカルト」「迷信」「神秘主義」「非合理」などのさまざまな名称で呼ばれます。しかし、「宗教と魔術」を区別するのは困難で、「宗教―魔術的」といった用語があるように、実証的なものではないと指摘し、著者は「ハネフラーフの主張は、狭量な『宗教』カテゴリーによってはずされたものを、宗教研究へ取り戻すものである。イェイツのようなオカルトへの過剰な思い入れでも、フェイブルの本質主義的定義による歴史研究の硬直化でもなく、18世紀以前から現代までを視野に収めた実証作業の遂行が、彼の目指すものといえる」と述べます。
第二には、アジアの近代仏教史における神智学の役割です。第三に欧米の近代仏教史を扱う研究です。神智学が欧米に仏教思想を広める先ぶれとなったとしても、その後で伝えられたものは、伝統的な仏教とは限りませんでした。たとえば、スノドグラスの研究によれば、シカゴの万国宗教会議でアメリカにもたらされた日本仏教=「東方仏教」というカテゴリーが、日本仏教の戦略的な表象であり、その枠組みも西洋仏教学に負うところが多く、さらに伝えられた内容も清沢満之の『宗教哲学骸骨』のように、西洋の影響を受けた仏教言説が含まれていたのです。著者は、「初期の仏教シンパの抱いていた仏教(神智学あるいはダーサの「仏教」)がハイブリッドなものであったのはいうまでもないが、彼らが交流していた日本仏教徒たちの仏教も、明治維新以降、急速にハイブリッド化しつつあったわけである。欧米の仏教シンパたちが『永遠の東洋』を鈴木大拙に投影したとしても、実際には大拙は明治の仏教近代化の最先端である新仏教運動に属していた」と述べます。
1「ブラヴァツキーと仏教」では、神智学協会は、1875年、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキー(1831~91)とヘンリー・スティール・オルコット(1832~1907)を中心に、ニューヨークで結成されたことが紹介されます。思想面でのカリスマはブラヴァツキーであり、実務面の中心人物はオルコットと、その役割は分担されており、仏教とのかかわりも同一ではないとして、著者は「神智学は、スピリチュアリズムの流行から派生した運動である。ただし、スピリチュアリズムでは死者霊の働きで心霊現象が起こるとするのに対して、神智学(あるいはブラヴァツキー)は、スピリチュアリズムを批判したフランスの元社会主義者アルフォンス・ルイ・コンスタン(筆名エリファス・レヴィ)に影響を受け、魔術は意志の科学であり、心霊現象の原因は死者霊ではなく生者の意志であると主張する。さらにオカルティズムという用語を使い、カバラ、錬金術、占星術などさまざまな隠秘学(オカルト科学)に1つのシステムを与えようとした」と述べます。
1877年、ブラヴァツキーは最初の大著『ヴェールを剥がれたイシス』(Isis Unveiled)を出版します。彼女の思想の基本は2つあり、まず、魔術は科学であり、科学的法則を応用することで超常現象は起こるというもの、もう1つは、古代の普遍的な「知恵」からさまざまな宗教が発生し、ヘルメス、モーゼ、オルフェ、ピタゴラス、プラトン、イエスなどの賢者がその「知恵=宗教」の伝授者という宗教史観でした。ただしこの時点では、彼女の思想は基本的には西洋オカルティズムの範囲内にありました。ブラヴァツキーは1888年に第二の大著『秘密の教義』(Secret Doctrine)を発表し、『秘密仏教』で開陳された教えをさらに展開する。彼女の思想は2つの軸からなり、1つは人種と宇宙をつなげる進化の神話である。
彼女の説によれば、惑星も生物と同様に退化と進化を行い、7つの段階を経て霊的なものから物質的、そして霊的な存在へと戻っていく。これをラウンド(循環期)という。これを7回くりかえすとマンヴァンタラ、さらにその上にカルパ、ユガといった長大な時間区分がある。このラウンドにおいて、地球は現在最も物質的な段階にあり、その中で7つの根源人種が進化していくとされる。もう1つは、精神と身体を連続的にとらえ、7つの階層を立てている。人間は、肉体(ルパ)、生命力(プラナ)、アストラル体(リンガ・シャリラ、身体に重なる分身)、動物的精神(カマルパ)、知性(マナス、個人の自我意識)、霊的魂(ブッディ、アートマの容器)、霊(アートマ、神的原理)の7つからなるという説である。
多くの東洋学者からは無視されたものの、人種進化論、マハトマ説、心身の七構成説などの神智学思想という遺産は、その後も大きな影響力をふるいました。宗教学者ロバート・C・フラーはニューエイジへの影響について、「最盛期でさえ、神智学の会員数はアメリカ合衆国で1万人を超えなかった。世界での会員数も5万を超えるくらいではなかったか。会員数は比較的少ないが、神智学は教会を持たない宗教の歴史的発展にかなり影響を及ぼした。その最も重要な貢献は、教会外のアメリカ人の形而上的語彙に東洋宗教を結びつけたことである。神智学はヒンドゥー教や仏教への寛容を説いただけではない。それはさらに一歩進んで、私たちが神と神秘的につながる潜在的能力を、それらの伝統の方がよりよく理解していると提唱したのである。神智学以降の世代の教会外アメリカ人たちは、ヨガ瞑想、禅の悟り、梵我一如、あるいはクンダリーニ、気、プラナといった”精妙なエネルギー”の存在などを好きなように語ることができるようになったが、その主な原因は神智学にある」と述べています。
また、フラーは「神智学は、キリスト教正統派と真っ向から対立することで、メタフィジカル宗教の教理を推し進め、キリスト教の特殊啓示、原罪、身代わりの贖罪、自己犠牲などのキリスト教教義に満足できない人々を勇気づけた。神智学は、すべての宗教が共通の源泉を持つこと、神は自然に内在する非人格的な存在であること、すべての人の本来の自己は神的なものであること、私たちはこの世でも来世でも霊的に成長し続けることなどを説いた。そして、神智学は『ニューエイジ』という期待の言葉をもたらした。1980年代、90年代に広く知られた『ニューエイジ』運動は、その内容でも形式でも、神智学の影響を反映する。チャクラについての話から、昇天したマスターからのチャネリングによるメッセージに至るまで、ニューエイジ運動は、ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキーとその信奉者がアメリカの聴衆に向かって最初に紹介した語彙と霊的実践を自由に利用している」とも述べます。
ブラヴァツキー神智学の功績は、すべての宗教は太古の知恵に由来するという反セクト主義的な主張、「科学」の重視、そしてロペスの分析するように、魔術師の住むチベットという「神秘的東洋」像を欧米に定着させる原動力となったことでした。著者は、「他のアジア諸国と比べ、チベットがもの言わぬ国であることは、彼女のオリエンタリズム的幻想を投影するのに幸いした。それに対してオルコットは、生きた仏教徒を相手とした。そこには双方向のやり取りと戦略があり、特に、日本との交渉は一筋縄ではいかなかった」と述べています。
2「オルコットと仏教エキュメニカル」では、神智学と仏教の関係が要約されています。それによれば、第1にブラヴァツキーの神智学は、チベットのマハトマから伝授されたという触れ込みで「仏教」を称しました。第2に、神智学は、万教同根説をとり、原理的にはすべての宗教を等しく評価しながら、仏教の評価は高かったようです。第3に、1880年にブラヴァツキーとオルコットの2人は上座部仏教で受戒しているので形式的には仏教徒でした。第4に、オルコットの「プロテスタント仏教」の特徴である、科学的・合理的な仏教理解、仏教エキュメニカルを目指した点は神智学的でした。
四「日本仏教の国際ネットワーク」では、1892(明治25)年に渡米した平井金三(1859~1916)が取り上げられます。彼は、アメリカで一般市民への英語講演を行い、仏教伝道を最初に行った人物でした。平井は、実質的には在家居士でしたが、本人は臨済宗で得度出家して龍華という名を得ています。したがって、形式的には最初の臨済宗伝道ということになります。彼もまた、アメリカでは神智学徒、ユニテリアン、あるいはニューソート信奉者といった、「秘教主義者」「合理主義者」たちに歓待されています。シカゴ万国宗教会議は、この平井が活躍した最大の舞台であした。
5「オリエンタリズム、オクシデンタリズム、鈴木大拙」では、鈴木大拙が登場します。鈴木大拙は、西田幾多郎が採用したウィリアム・ジェイムズの「純粋経験」という概念を用いて、媒介のない不二の純粋な経験こそが悟りであり、その経験はすべての宗教経験に共通していると唱えました。しかし、経験を強調するのは近世以前の禅ではありえなかったとして、著者は「仏教経典では瞑想体験の記述が乏しい、個人の経験が仏教書には描かれていない、テーラワーダでも日本の禅でも瞑想は主な実践ではない、禅仏教でも儀式の方が重視される――こう指摘した上で、『経験』に根拠を置くレトリックは、近世以前から続くのではなく、近代のものであると強調する」と述べます。
Ⅰ「神智学の歴史」の第一章「チベット行きのゆっくりした船―アメリカ秘教運動における『東洋』像―」の一「エジプトからインドへ」では、19世紀の学者たちは、文献を比較検討していけば、東洋宗教の原像だけでなく、さらに、西洋や東洋の別を超えて、さまざまな宗教の共通の源泉まで遡ることができると夢想できたと述べられています。著者は、「世界中から図書館に文献を蒐集すれば、宗教発生の秘密などすぐに解明できるはずであった。この前提は神智学などの秘教運動でも共有されており、世界の諸宗教の背景には共通の真理が隠されていて、さまざまな神秘主義文献を検討していけば、その真理に到達できるはずであった。が、むろん、できなかったし、そもそも、それは東西の差を超えたものなのかどうか、その保証もなかった。しかし、紙の上の東洋に自己を投企することで、東洋と接近することはなくとも、自己と接近することはできたかもしれない」と述べます。
二「紙の上の東洋」では、19世紀アメリカの東洋指向は、こうした大陸のロマン主義を経由してのものであり、精神史の上から見れば、その先頭に位置するのはエマソンと超絶主義者たちであったことが指摘されます。エマソンは東洋学者ウィリアム・ジョーンズの著作や、バガバッド・ギータの翻訳を熱心に読んでいました。また、ブラーモ・サマージというヒンドゥー教運動の思想を高く評価していました。ただしエマソンは、ヒンドゥー教で思想形成を行ったわけでも、あるいは修行や儀式などを実践したわけでもなかったと指摘し、著者は「秘教史研究者A・ヴァースルイスは、その宗教的思想を『文字の宗教』と表現しているが、エマソンにとっては、いずれかの伝統に従うよりも、自由や自主性の方が重要であり、西洋と東洋の宗教や思想を取捨選択し、理想を語ることを好んだ。たとえば、超絶主義者ブロンソン・オルコットは、1839年の日記に次のように書いている」と述べます。
第二章「近代日本における神智学思想の歴史」の一「メタフィジカル宗教」の3「メタフィジカル宗教と神智学」では、メタフィジカル宗教について説明されます。メタフィジカル宗教とは、具体的にはクリスチャン・サイエンスやニューソート系諸団体、神智学とその分派、薔薇十字主義、人智学、スピリチュアリズムなどです。エマソンの超絶主義やインド思想、カバラ、神智学などがアイデアの源泉とされますが、大衆的オカルティズムのアイデアを網羅しています。著者は、「19世紀前半からの動きを追ってみると、催眠術からP・P・クインビーの精神療法とアンドリュー・ジャクソン・デイヴィスやスピリチュアリズムが出現し、前者の流れからはさらにクリスチャン・サイエンスのエディ夫人や、ニューソート運動の源となったエマ・カーティス・ホプキンズ、後者からは神智学が誕生する。これらの運動と、これらが折衷して誕生した運動の総称がメタフィジカル宗教である。ジュダーの指摘では、現実を超えた形而上的な原理と、その日常の問題解決への応用という、抽象的、実際的な両側面を合わせ持っている点が特徴とされる。19世紀末からはさらにヨガがアメリカに紹介された。有名なグルには1893年に渡米し、ヴェーダンタ教会を立てたヴィヴェーカナンダや、1920年に渡米してきて自己実現友愛会を創立したヨガナンダがいる。ただし、自称インド人も多く、日本に影響のあったヨガは、戦前はアメリカ白人のものが中心であった」と述べています。
第三章「明治期日本の知識人と神智学」の二「神智学と日本仏教」では、神智学が日本に最初に紹介されたのは、1886(明治19)年、オルコット『仏教問答』の翻訳に始まることが紹介されます。これは西本願寺派の最高幹部の1人であった赤松連城が、同派の僧侶と思われる人物の水谷涼然から原書を受け取り、翻訳出版に動いて実現したものでした。著者は、「この頃、明治維新以降冬の時代が続いていた仏教も、反キリスト教と国粋主義を旗印に、ようやく勢いを盛り返していた時期だった。京都の英語学校オリエンタル・ホールの主宰者である平井金三は、オルコットの招聘運動に乗り出し、オルコットは1889(明治22)年に初来日を果たす。この事件は、井上円了の『真理金針』出版(1886年)に始まる仏教復興の頂点ともいうべき華々しいものだった」と説明しています。
六「成瀬仁蔵」では、日本女子大学の創立者あるいは日本の女子高等教育の開拓者として知られる成瀬仁蔵が取り上げられます。彼は帰一協会の活動のような宗教的な活動から女子教育まで幅広く取り組んでいました。その中で霊的な人間観は教育の実践と渾然となっていたのです。彼が創設した日本女子大学校は、ミッション系でも仏教系でもありませんが、しかしある種の宗教性をたたえた学校として発足しました。「信念徹底」「自発創生」「共同奉仕」という日本女子大の三綱領は、「宇宙に遍満するところの、微妙不可思議な至高至大の活力、神聖な霊的生命という外に名づけようのない、実在の分化的発現たる人々の精神」といった宇宙観・人間観を前提としています。著者は、「それだけでは、当時は一般的だったエマソン主義を大きくはずれるものはない。しかし、彼が学生に向けて行った倫理講話には、より具体的に西欧秘教思想を語った部分がある」と述べています。
「結語――憑依を前にして」では、鎮魂帰神の法では、神主(=霊媒)が審神者によって制御されるという形式をとり、西欧のスピリチュアリズムよりも操作的な部分が多いことが指摘されます。しかし神智学徒、それも心霊現象を好まないポイント・ロマ派に属するスティーブンソンの目からすれば、いずれも危険な迷信と見えたに違いないとして、著者は「おそらく彼の批判は、生者の意志力によって超常現象を解明するオカルティズムと、死者霊を原理とするスピリチュアリズムの差異(そして前者の説明原理から引き出されるスピリチュアリズムの劣等性・危険性)を問題化しようとしたのだろうが、その批判はあっさりと受け流されてしまう」と述べています。
大本教で活躍した浅野和三郎は、ブラヴァツキーが『ヴェールを剥がれたイシス』『秘密教義』を、「中央亜細亜に根拠を有する所謂仙人から遠距離通報を受け」て書き上げたことを認め、日本の霊学に関する知識が欠けている点を除けば、神智学が立派な思想であると評価しています。あるいは、やはり大正期の大本教で活躍した谷口正治(後の雅春)も、「ブラバツキは、しかしながら泰西の霊覚者若しくは霊媒者の中では一頭地を抽いていた」ので、動物霊が懸かることも知って霊媒をやめて神智学を開いたと述べ、事情に通じていることを示しました。その後、大本を離脱して心霊研究者となった浅野は、エーテル体・メンタル体といった神智学系の霊的心身論を神道の一霊四魂論に結びつけて独自の霊魂論を唱え、ある意味で自らの神智学批判に応えることになるのでした。
Ⅱ「仏教との交錯」の第一章「仏教ネットワークの時代――明治20年代の伝道と交流――」の一「欧米仏教」では、19世紀アメリカで、仏教や東洋思想につながる霊的思想には、スピリチュアリズム、ニューソート、神智学の三種類があり、いずれもメスメリズム(催眠術の原点)を源泉とすることが紹介。著者は、「教義面で共通する点は、死者(スピリチュアリズム)にせよ生者(ニューソート、神智学)にせよ、人間の心(霊魂)には特別な力があること、そして神の恣意ではなく、合理的な規則が超自然も支配しているという前提があった。したがって、キリスト教ほど人格神は重要でない。運動としては、巨大な教団となった例もあるが(クリスチャン・サイエンス)、個人主義が強く、組織化を嫌う風潮がある」と説明します。
第二章「オルコット去りし後――世紀の変わり目における神智学と”新仏教徒”――」の冒頭を、著者は「1896(明治29)年8月2日付『反省雜誌』第93号の巻頭に、「新教勃興の機」と題する記事が掲載されている。無署名の社説なので、誰が書いたかは不明だが、この記事はかなり激しいものであった。仏教は腐敗し国民的信仰を得られていない、青年の間に自由討究、科学的研究を主張するものはいるが、信仰を得ていない、現今の日本国民を満足させえない、しかし人々は宗教を放棄したわけではなく、信仰を求めている。激烈な信仰を持った人物が登場して新宗教を唱えるべきだという主張である。このような精神的な問題を、明治20年代の仏教青年たちは痛切に感じていた。たとえば鈴木大拙も、渡米前に『新宗教論』(貝葉書院、1896年)と題した著作を発表し、そこですべての宗教が頼るに値しないのならば、自らこの宇宙での安心立命の場所を探すべきだと述べている。ただし、その宇宙とは有神論的宇宙ではなく、汎神論的宇宙である」と書きだしています。
トマス・ツイードは、19世紀末、アメリカ人で仏教に関心を抱いた人々を秘教主義者、合理主義者、ロマン主義者の3タイプに分けています。その中で、オカルト的関心を持つ秘教主義者と、道徳的で科学的な体系として仏教を評価する合理主義者が、特に日本宗教との関係では重要だとして、著者は「明治20年代、日本仏教と関係が深かった人物は神智学徒のヘンリー・スティール・オルコット、スウェーデンボルグ主義者のフィランジ・ダーサ、そして哲学者のポール・ケーラスであったが、前二者が秘教主義のタイプ、ケーラスは合理主義のタイプである。ただしこの類型論は理念形であり、実際には秘教主義者と合理主義者の共通する点は多い。いずれも資本主義社会の矛盾や自然科学の進展に対してキリスト教が応えていないという不満を抱く進歩的な人々であり、仏教は道徳的、科学的、合理的な、キリスト教の代替物として評価された。仏教に限らず平和主義、動物愛護と菜食主義といった生命愛にもとづく思想や、あるいは社会主義や女権運動など、当時のアメリカのキリスト教=男性優位社会への異議申し立て思想は、往々にして霊的な思想と結びついた。1890年代にも「中流階級の改革運動」において、心霊現象やニューソートへの信奉者が多かったと言われる」と述べます。
位置「仏教と秘教」の1「秘教主義者」では、1875年にニューヨークで結成された神智学協会は、最初は西洋オカルティズムの小さな研究団体でしたが、1879年にインドに本部を移転、それ以降は急速に会員を増やし国際的な組織に成長したことが紹介されます。フレデリック・ルノワールは、神智学の魅力が、「流行と異国趣味の活用」「寛容でドグマなき宗教」「チベットとオカルト的力」などにあり、転生の理論は仏教由来では西洋の進歩主義の投影であり、その教義はブリコラージュであると指摘しました。著者は、「神智学の内実が西洋オカルティズムと東洋宗教の寄せ集めであるという指摘は、正当なものである」と述べています。
たしかに、神智学の教義は、チベットのマハトマと交信したと主張するブラヴァツキーによって編集されたものでしょう。しかもそこに心霊現象と疑似古代文献で権威づけをしたという点で批判され、そしていまだに批判され続けているのも無理からぬ話であるとしながらも、著者は「ただし西洋秘教思想に東洋思想をもたらし、欧米人の東洋宗教への入口の役割も果たしてきたのも事実である。また、その教理もオカルト現象だけに覆われているわけではない」と述べます。また、「明治20年代前半、日本仏教の宗門側にとって神智学は利用するものであって、理解すべきものではなかった。しかし、神智学が体現していた折衷的な宗教性が何人かの新仏教徒に刺激を与えたのは確かである。さらに明治20年代後半になると、神智学によってもたらされた神秘経験という概念が重要性を帯びてくる」とも述べています。
二「明治20年代と『新仏教』」の1「明治20年代」では、20年代前半の日本仏教界は仏教結社の流行、仏教雑誌の創刊ラッシュ、宗門による普通教育など仏教の勢いを印象づけた時期であったと指摘し、著者は「反キリスト教の傾向は強く、1893(明治26)年の『宗教と教育の衝突』事件まで続いていく。神智学との接触によって、海外宣教会の発足、シカゴの宗教会議参加と、短期間ながら欧米人への布教熱が高まったのもこの時期である。普通教校内に仏教者の禁酒、綱紀粛正を計る反省会運動が発足し、西洋的学問を修めた青年層の仏教活動が始まっている。明治20年代後半には、仏教とキリスト教の関係は融和に向かい、1896(明治29)年、1897(明治30)年には神道、仏教、キリスト教の宗門代表者を集めての宗教懇談会が開かれた。あるいはその懇談会から、丁酉懇話会という倫理運動が開始されている。仏教宗派の合同やキリスト教宗派の合同、さらには仏教とキリスト教との合同を夢想する者もいた。またユニテリアンの活動も、このような宗教間の融和や対話に貢献したと思われる」と述べています。
2「新仏教」では、明治20年代の新仏教も、30年代の新仏教徒同志会も、基本的な仏教理解は科学的、合理的なものであり、その源は哲学や科学と仏教の一致を主張した井上円了であったことが指摘されます。円了について、著者は「その影響力は大きいが、とりわけ創造主を否定した意味は大きい。人格神が不在であっても唯物論に陥ることがない宇宙をどう説得的に弁証するかが、彼以後の知識人仏教者の課題となったが、そこで汎神論という哲学的批判に耐えうる言葉が用いられる。中西牛郎は仏教を汎神論と呼び、宗教は多神教、一神教、汎神論の三段階で進化する以上、仏教は未来の宗教であると主張した」と述べます。
中西牛郎に比べれば日本での影響力は低かったですが、平井金三も独創的な新宗教論を唱えました。平井はそれを「総合宗教」synthetic religionと称しています。それによれば、すべての宗教は偶像や人格を崇拝しているのではなく、真理を崇拝している、その点ではあらゆる宗教は共通している、その真理に到達するには心を磨き仏性を輝かせることが必要であり、その仏性は無生物を含めてすべての存在に備わっているといいます。しかし、反面、どの宗教も完全な真理を有していないので、さまざまな宗教を編集して理想的宗教に近づけることが必要ですが、そのような超宗教的な立場は日本の心学にすでにあると彼は主張します。著者は、「平井のレトリックはスペンサー哲学、大乗起信論、心学を混ぜ合わせたものであるが、真理を重視し、日本人を真理探究者と位置づける点では神智学の影響も考えられる。また彼も社会問題に関心が高く、1898(明治31)年に『宗教と政治』という著書を出版し、宗教者の社会活動や教育改善などを提言した。宗教と社会の両面におけるリベラルで進歩的な立場からすれば当然の結果といえるが、平井も1899(明治32)年にユニテリアンに参加している」と述べます。
第三章「平井金三、その生涯」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「平井金三(1859~1916)は、今まで日本の近代宗教史にほとんど登場することのなかった人物である。しかし、排耶運動、神智学協会会長オルコット、シカゴ万国宗教会議、ユニテリアン、新仏教運動、心霊研究、道会、禅的精神療法など、明治宗教史に目をやれば、その曲がり角ごとに平井の影が見え隠れする。国粋主義と仏教復興運動から出発し、最終的には個人宗教の実践に至った彼は、変貌し続けた明治宗教のダイナミズムを象徴する人物でもあり、宗教的知識人の1つの典型例でもある。しかし宗門、宗教、国境、政治思想などを超えて活動したために、その全体像はなかなか見えてこない」
三「シカゴ万国宗教会議――明治25年3月~明治27年6月」では、平井がアメリカ人に向かってどのような主張をしたかが紹介。著者は、「彼はまず、日本人が偶像崇拝者(すなわち野蛮人)ではなく真理探究者であると強調する。神道の御幣をはらう儀式も、心の汚れをとり真理と一致させる行に他ならない。神とは「カンガミ」つまり真理を考えることから来る。仏教においても、仏性(Buddh)とは、真理、真理認識、そして真理認識の可能性を含む。人間に意識がある以上、その構成物である無生物にも意識があり、したがって無生物を含めた万物に仏性がある。仏教とは真理の理解を意味しており、キリスト教の神も普遍的理性の本質であるなら、その両者に差はない。他方、信仰の対象は論理的には、理解されず、不可知である。あるいは、不可知の実在(entity)へのアプリオリの信仰がすべての宗教に共通し、その実在についてのさまざまな真理が各宗教の体系である」と述べています。
したがって、それらの諸宗教を総合することで、より完全な真理が得られはずです。このような総合宗教論を前提として、日本宗教の優位を主張するとして、著者は「仏教だけでなく神道も奨励した聖徳太子、仏教と神道を融和させた弘法大師、そして近世では心学をはじめて神、儒、仏を組み合わせた石田梅岩がいる。こうした総合主義(Syntheticism)が日本独自の知恵であり、それが日本主義(Japanism)である。まもなく万国宗教会議が開催される、そうなれば総合主義、日本主義が実現されるだろうという期待を述べて記事を締めくくっている」と説明しています。
六「道会と心象会――明治38年~明治45年」では、平井は、世界中に口寄や幽霊譚があることから、心智現象(心霊現象のこと)が存在すると断言したことが紹介されます。それがなぜ起こるのかといえば、分子レベルの意識が存在している以上、分子レベルの記憶も存在するとして、著者は「いわば蓄音機のように、分子に歴史的事件の振動が記憶される。それに感じて、幽霊を見たりするのであるという。霊魂とは物質の力であり、その死後存続はあるものの、来世といった、どこかの異郷としての来世は存在しない。その点を悟ることで安心立命が得られる、と平井は結論づける」と述べます。
分子レベルの意識や魂を物質の力やエネルギーなどとみなす霊魂論は、心霊現象への科学理論的アプローチと見ることもできれば、あるいは仏教的な一元論を西欧的な唯心論や唯物論の上に移植するための便法と見ることもできると指摘し、著者は「この魂=勢力論を用いたのは、平井には限らない。たとえば井上哲次郎は中江兆民の『統一年有半』への書評でこの論法を用いており(井上哲次郎「中江篤介氏の『統一年有半』を読む」〈『哲学雑誌』180号[1902年1月10日]〉)、黒岩周六(涙香)の『天人論』(朝報社、1903年)、そして精神療法の祖とされる桑原俊郎『精神霊動』(開発社、1904年)にも同様の議論が見られる。ただ、平井がこれを発表したのは『霊魂論』(『伝橙』第13号〈1891年1月21日〉)に遡り、かなり早い時期に属することはまちがいない」と述べるのでした。
このくだりを読んで、わたしは一条真也の読書館『死は存在しない』で紹介した田坂広志氏の著書の内容を連想しました。田坂氏は、永年、科学者と研究者の道を歩んできており、本来は「唯物論的思想」の持ち主でした。しかし、自身の人生において、「不思議な体験」、例えば、「直観」や「以心伝心」、「予感」や「予知」、「シンクロニシティ」や「コンステレーション」などの体験を、きわめて象徴的な形や劇的な形で、数多く与えられたために「死後の世界」が存在すると考えるようになったそうです。田坂氏は、「なぜ、我々の人生において、『不思議な出来事』が起こるのか」「なぜ、世の中には、『死後の世界』を想起させる現象が存在するのか」「もし、『死後の世界』というものがあるならば、それは、どのようなものか」を解き明かしたいと考えたそうです。そして、永年の探求と思索の結果、たどりついたのが、先端量子科学が提示する「ゼロ・ポイント・フィールド仮説」でした。
「結語」では、心身技法を軸にして仏教を再編集した『三摩地』も、原始仏教や真言宗、浄土真宗の技法をも取り込み、汎仏教的な精神療法というだけでなく、欧米の心霊研究やニューソートの影響も受けていたことが指摘されます。著者は、「東洋と西洋が出会い、互いに自己を規定しつつ収奪と対話と交流を行った近代は、同時に宗教という語が流通し、宗教と精神療法とが互いに自己を規定しつつ、ウィリアム・ジェイムズが『宗教的経験の諸相』で論じたように、宗教の救済と療法の救済に線引きがなされた時代でもあった。それに対して仏教は、一面では宗教的救済を行いながら、オルコットが道徳哲学であると述べ、原坦山は心性哲学と述べた(19世紀において両者は同一のものを指した)ように、その二種類の救済の区別を突破するような位置にあり、平井の『三摩地』も、その延長線上にあった。平井にもう少しの時間が与えられ、その技法を整理し筋道をつけることができれば、ゼンセラピー(Zen Therapy)の先駆けとして、さらなる仏教の国際化の第一歩となったかもしれない。ともあれ、その到達点は、原坦山の生理学的禅仏教、催眠術、心理療法、心霊研究を含めた井上円了の妖怪学に続く、日本の近代仏教の試みとして今に残っている」と述べるのでした。
Ⅲ「霊性思想と近代日本」の第一章「仏教雑誌のスウェーデンボルグ」では、明治20年代に入り次々と創刊された仏教雑誌には、ほとんど決まって海外の仏教徒からの通信や翻訳が載っていたことが紹介されます。著者は、「東洋の仏教に対して、欧米仏教という語さえ使われ始めた。とはいえ、その欧米仏教とは何であったのか。同時代(ヴィクトリア朝)の欧米社会では、キリスト教批判、新たな霊性思想の模索が始まっており、その中で仏教への関心も次第に高まっていた。エドウィン・アーノルドの仏陀伝『アジアの光』(1878年)がベストセラーとなり、ゴータマ・ブッダの名前は一般に知られるようになり、あるいは仏教を信奉する者も出現し始めた。ただし、アジア諸国の仏教宗派による布教が始まる前のことである。そのような仏教信者のほとんどは、翻訳仏典と西欧の秘教文献を読むことで仏教を理解した。端的にいえば、その多くは神智学徒であり、わずかな数の(しかし影響力の大きい)スウェーデンボルグ主義者であった」と述べています。
一「仏教徒西欧秘教運動」では、近代の霊的思想の誕生は、概念的にとらえれば2つの段階を経ていると指摘されます。第1の段階は、奇跡的なるものの解放と合理化と大衆化、つまりスピリチュアリズムの流行です。第2の段階は、「古代神学」といわれる西欧の秘教的伝統の再発見、そして東洋宗教への関心の高まり――こちらはオカルティズムと神智学の流行でした。著者は、「スピリチュアリズムの流行は、1848年のハイズヴィル事件に始まるとよくいわれるが、その前年、アンドリュー・ジャクソン・デイヴィスが催眠状態で霊的経験を持ったことに始まる。デイヴィスに続き、多くの霊媒が出現したが、その経験や思想の核にあったものは、スウェーデンボルグ思想であった。トマス・レイク・ハリス、ジョン・マリー・スピア、パスカル・ビヴァリー・ランドルフなど、いずれもスウェーデンボルグの影響を受けた霊媒たちが新しい宇宙観と救済を説き始めたのである。スピリチュアリズムとは、メスメリズムの文脈におけるスウェーデンボルグの再活性化から始まったといってもいいだろう」と述べます。
第二段階は1870年代から本格化し、多くの出版物が出されました。これらの出版物は、いずれも新たな霊的思想体系を構築しようとした試みであり、その題材には西欧の秘教思想(ヘルメス主義、薔薇十字主義、カバラ、古星術、神秘主義など)、そして仏教やヒンドゥー教などの東洋思想が多かったとして、著者は「つまり霊的な思想家たちは、真理を求めて西洋からオリエント、そしてインド、チベットへと、その関心を東へ向けていったのであり、神智学運動はその動きの最先端に位置していた。神智学が東洋思想への傾斜を強めるのは、1878年にブラヴァツキーとオルコットがインドへ神智学協会の拠点を移してからである。1880年にはスリランカで、2人は西欧人としては初めて受戒し、正式に仏教徒となっている。ただしブラヴァツキーが『秘密の教義』(1888年)などで伝えた秘密仏教なる思想は、西欧秘教と東洋思想を結びつけたもので、テーラワーダ仏教とはかなり異なるものであった」と述べています。
第二章「大拙とスウェーデンボルグ――その歴史的背景――」の二「明治20年代のスウェーデンボルグ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「日本人でスウェーデンボルグ主義に触れた最初は、森有礼を含む幕末の薩摩藩留学生らである。ローレンス・オリファントの紹介で、スウェーデンボルグ系霊媒トマス・レイク・ハリスの主宰するコミューン新生社(New Life)に参加している。新生社に滞在していた日本人の中で、帰国後も宗教活動を続けたのは、1899(明治32)年に帰国した新井奥邃だけである。最近になってその思想はようやく再評価されつつあるが、当時彼は隠者的生活をしていたので、そのスウェーデンボルグ思想は田中正造を含む少数の人々にしか伝わらなかった」
五「宗教から迷信まで」では、大拙にとって、スウェーデンボルグの著作の重要性は、描写が具体的で現実性のある他界観ということですが、その具体的な部分は明治の仏教者にとっては受け入れ難い部分であったとして、著者は「というのは、明治仏教の復興者となった井上円了は、仏教を合理的で近代科学とも合致する真理として主張し、さらにその合理主義的精神を引き継いだ仏教改革運動の新仏教徒同志会では、仏教の健全な信仰と迷信の根絶をその綱領に謳った。そして大拙自身は、この新仏教徒同志会の会員であった以上、霊界へ出入りしたなどという『所述、固より悉く之を信ずべからず』と主張するのも当然であろう。しかし、その上で彼はスウェーデンボルグを肯定的に論証することになる。それには宗教理解の大きな枠と、具体的な解釈の二つのレベルが考えられる」と述べます。
「結語」では、国家の統制による押しつけの道徳や死生観ではなく、大拙は各人の傾向に合致した宗教の自由市場を構想し、選択肢の1つとしてスウェーデンボルグを導入しておく必要性を痛感し、合理主義の風潮の中で喪われた他界の存在を証明し来世の問題に解決をつけてくれるものとして歓迎したことが紹介。しかし霊魂や来世の有無それ自体が、近代仏教の一部では否定された事柄であり、大拙にとってもその両方を調和させる視点が必要となったとして、著者は「『境涯』という言葉で示された、現実界も天界も同等視できる立場は、スウェーデンボルグの他界観に対する創造的な解釈であり、霊魂の有無を問うことのない新しい他界観を提出したともいえよう。あるいは、寺院内の特殊な状況における、時間的にも限定された心理状態としての神秘経験を、その限定をとりはらい、心理状態ではなく世俗的世界の中に読み込もうとした。それは、大拙の禅解釈にもつながるものである」と述べるのでした。
第三章「らいてうの『天才』」では、平塚らいてうが1933年(昭和8年)8月に大本教の「人類愛善新聞」に以下のような談話を寄せていることが紹介されます。それは、「私はスウェーデンボルグの『天国と地獄』という書物を読みまして、此北欧の神秘思想家が出口王仁三郎氏の書かれた霊界物語と符節を合する物多々あるを発見して驚かされました。それの天界篇を読みますと霊界物語中にある天地相応の理というような事がやはり説かれているのではありませんか。東西の神秘思想家が同じ天界を同様の眼で見ている点など甚だ面白い事と思われます。と同時に出口聖師のあのつかみ所なき大きな人格に私共とて同様に世人ももっと信頼を置いてよいのではないかと考えている次第で御座います」という興味深いものでした。
著者によれば、王仁三郎が大拙訳のスウェーデンボルグ『天界と地獄』を読み込み、その用語法や概念をさりげなく流用しているという事実はいくつかの資料(たとえば、池田昭編『大本史料集成』第三巻「事件篇」〈三一書房、1985年〉および西川武「皇道大本教事件に関する研究』〈東洋文化社、1977年、本書は司法省刑事局『思想研究資料』特輯第66号[1939年]の複製〉)からも確認できるといいます。もちろん、宗教思想のこうした貸借関係には借り手の側の創造的な解釈がそこに介在し、単なる死文の引用ではないわけですが。著者は、「王仁三郎が、真面目、不真面目でとらえきれない『つかみ所なき大きな人格』であったことは間違いないのであるにしても、らいてうは、王仁三郎の仕掛けにまんまと引っかかったのか、あるいは承知の上でリップサービスしたのか。また、王仁三郎の方はどう思って、この記事を自著に引用したのか、興味は尽きない」と述べるのでした。
解題「吉田久一から吉永進一へ(碧海寿広)」の「霊と術の近代」では、鈴木大拙は、禅(ZEN)のグローバル化を先導した仏教者として著名ですが、他方で、スウェーデンボルグの日本への熱心な紹介者でもあったことが指摘されます。碧海氏は、「日本の仏教者と西洋の神秘主義の思想家が、なぜ結びつくのか、現在では直観的にわかりにくい。だが、明治期にはスウェーデンボルグは西洋の仏教徒だという誤解があり、大拙も、そうした雰囲気のもとで青年時代を過ごした。そして、大正期の大拙は、衰えつつある日本人の霊性に活を入れるためにも、スウェーデンボルグの著作の翻訳や伝説の執筆に取り組み、その思想の普及に努めたのである」と述べています。
また、「大拙は、なぜスウェーデンボルグにそこまで入れ込んだのか」という疑問について、そこには、「他界の存在」への憂慮があったのだと、吉永進一が指摘したことが紹介されます。近代化の中、浄土のような他界の存在に対する懐疑の念が高まり、仏教者の中には、清沢満之のようにこれを「主観」の問題として片づけようとする人物も出てきたとしながらも、碧海氏は「だが、人は死んだらどうなるか、という問いは、宗教の存在意義にかかわる根源的な問題であり、個人の『主観』に押し込めただけで解決するようなテーマではない。そうしたなか、大拙はスウェーデンボルグの思想を独自に読み替えることで、近代社会においてなお、他界をポジティブに語るための手法を模索したのだ」と述べています。
一方、平井金三のようなマイナーな仏教者の活動にも、吉永進一は、これまでの研究では見えてこなかった独自の豊かさを発見したとして、碧海氏は「仏教やキリスト教の知識に基づく総合宗教論を構築した平井は、シカゴ万国宗教会議でのプレゼンテーションにより大絶賛を得た後、さらに心霊現象の研究に乗り出す。霊魂の死後存続などに関する、科学的な探究を試みたのだ。その延長で、平井はサイコメトリーなどの超能力の研究や、既存の禅の限界を突破するための新たな瞑想法の開発に乗り出したりもする。こうした平井の変遷を、吉永は、明治以降の禅の近代化や呼吸健康法の流行、それらと連動した民間精神療法の隆盛と関連づけて考察している。きわめて斬新な近代仏教史の叙述であると言えよう」と述べます。
「超宗派と脱宗派」では、1980年に雑誌『迷宮』第3号に碧海氏が書いた「霊と熱狂」という記事ですでに平井金三、神智学などについては触れられており、当時はこれを深める資料も知識もなかったことが指摘されます。その後は、当時の碧海氏の本業であるウィリアム・ジェイムズ研究と並行して、趣味で近代日本の精神療法(霊術)やオカルティズムの歴史を調べていたそうです。そこから一歩踏み出した契機は、まったくの偶然だそうで、碧海氏は「1999年頃、松本道別『霊学講座』という精神療法の本に引用されていた『瑞派仏教学』(博文堂、1893年)という書名を見つけたことから始まる。これを調べるために龍谷大学まで足を運び、カード式の目録をくっていくうちに、さらに偶然にも『海外仏教事情』を見つけた。そこからはジェット・コースターのように偶然が重なっている」と述べるのでした。『迷宮』はわたしも愛読していた雑誌で、「霊と熱狂」という記事も読んでいました。不思議な読書の「縁」に導かれて本書を読了したことは、何か目に見えない力が働いているようにも思えました。