- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2023.06.07
『死者と霊性』末木文美士編(岩波新書)を読みました。「近代を問い直す」というサブタイトルがついています。わたしが日頃から愛読している気鋭の学者や評論家たちの座談会を収録した本で、非常に興味深く読みました。多くの学びと気づきを得ました。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「若松英輔 中島隆博 末木文美士 安藤礼二 中島岳志」「5名による座談会を収録」「これからの哲学と宗教の再興に向けて、語り合う」と書かれています。
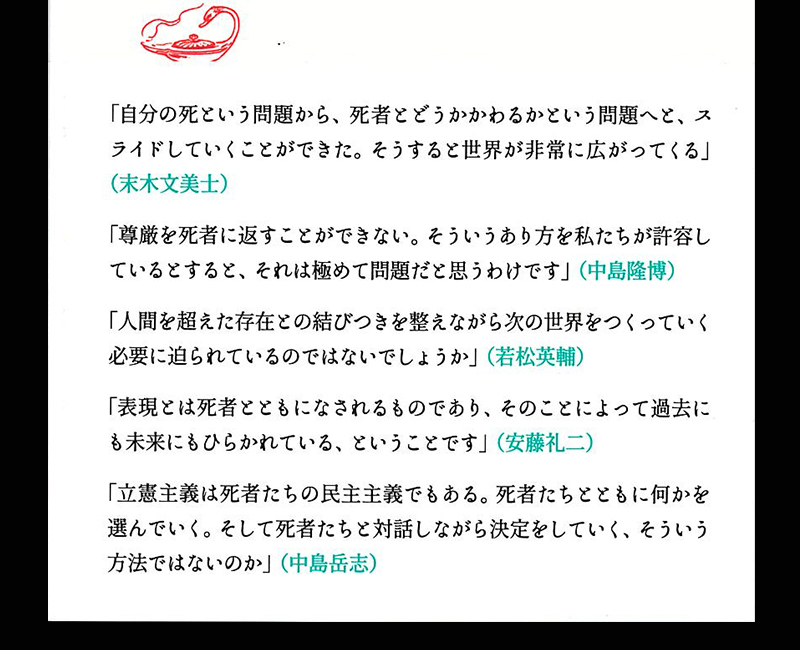 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「自分の死という問題から、死者とどうかかわるかという問題へと、スライドしていくことができた。そうすると世界が非常に広がってくる」(末木文美士)
「尊厳を死者に返すことができない。そういうあり方を私たちが許容しているとすると、それは極めて問題だと思うわけです」(中島隆博)
「人間を超えた存在との結びつきを整えながら次の世界をつくっていく必要に迫られているのではないでしょうか」(若松英輔)
「表現とは死者とともになされるものであり、そのことによって過去にも未来にもひらかれている、ということです」(安藤礼二)
「立憲主義は死者たちの民主主義でもある。死者たちとともに何かを選んでいく。そして死者たちと対話しながら決定をしていく、そういう方法ではないのか」(中島岳志)
カバー前そでには、「2つの大震災、原発事故、そしてコロナ禍は、否応なく見えざるものの血からを思い知らしめた。見えざるものである死者たちと私たちの関係にも、いま変化が生じている。末木文美士、中島隆博、若松英輔、安藤礼二、中島岳志、独自の思索を続けてきた5名が、死者と霊性をキーワードに、新たな時代の哲学と宗教の再興に向けて語り合う」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
《提言》近代という宴の後で
(末木文美士)
《座談会》死者と霊性
末木文美士(司会)・中島隆博・若松英輔・安藤礼二・中島岳志
第Ⅰ部
はじめに――コロナ禍のなかで
死者とのつながり方
転換期としての2000年代
2つの震災をめぐって
100年単位と1000年単位
第Ⅱ部
「近代」のとらえ方
19世紀のグローバル化と神智学
インドの近代と霊性
中国の近代と霊性
日本の近代と霊性
言語の余白について
第Ⅲ部
死者たちの民主主義
「政教分離」と「メタ宗教」
「宗教」と「国家」の再定義へ
「メタ宗教」の条件
天皇と国体をめぐって
哲学と宗教の再興に向けて
「死者のピオス」(中島岳志)
「死者と霊性の哲学――
西田幾多郎における叡智的源流」(若松英輔)
「地上的普遍性――鈴木大拙、近角常観、宮沢賢治」
(中島隆博)
「『霊性』の革命」(安藤礼二)
「あとがき」
「《提言》近代という宴の後で」の1「近代以後は始まっている」の「マルクス主義と近代の終焉」では、東京大学名誉教授の末木文美士氏が「私の基本的な見方は、コロナ禍をそれだけ切り離すのでなく、大きな時間的スパンの中で考えるべきだということである。その時間的スパンというのは、1980年代で近代は終わり、90年代以後は終わった近代の後で、新しい方向を見出せないままの混乱と停滞が続く時代と考えられる。このことは、日本に関しても、また、世界に関しても言える。コロナ禍は、その過渡的状態を終わらせ、否応なく近代以後、どのような方向を目指すかを決めざるを得ない状況に追い込んだとことができる」と述べています。
また、近代とはどのように定義できるかという問題について、末木氏は「ごく簡単に言えば、人類は合理的思考によって進歩し、それによって万人の幸福度が増加する方向へ向かうという楽観論が共通の前提となっていた時代ということであろう。合理的思考というのは、1つは科学技術による環境(人体を含めて)の制御である。それによって生産性を向上させ物質的な豊かさと安楽度を増すことができる。もう1つは人間社会の合理化である。それは民主主義の徹底により、人々の間の差別や不公平を取り除き、万人の幸福度を増すことができると考える」と述べます。
3「死者と霊性」の「死者の抹殺と復権」では、末木氏は、コロナ危機の現代と100年前のスペイン風邪の時代とを比較します。後者では西洋の危機が大きな問題になりましたが、多くの日本人にとって、所詮それは対岸の火事であり、切実な問題ではなかった。それ故、西洋の危機は東洋=日本の好機とばかり、日本こそが新しい世界史を作るリーダーだという主張がなされ、戦争遂行のイデオロギーとなった。末木氏は、「それに対して、今の時代はもはや近代を西洋という地域に限定することができず、世界中を巻き込むグローバルな危機とならざるを得ない」と述べます。
世界的に広がるパンデミック自体は類似しているとしても、交通も経済も全世界の関係は遥かに緊密になり、インターネットの情報は瞬時に世界を駆け回ります。各国はそれぞれ国境を閉鎖し、自己優先的な体制を取りながらも、同じ問題を世界中が共有せざるを得ないと指摘し、末木氏は「コロナはもちろん、原子力にしても、地球温暖化にしても、すべて一国や一部の人々だけの対応で済む問題ではなくなっている。それ故、その背景となる近代的世界観もまた、西洋に局限されるものではなく、対岸の火事として傍観することができない。そのまま我々自身の問題となっている」と述べます。
「近代/霊性/天皇」では、近代の理論の中で、見えざる死者はその正当な位置から追いやられてしまったとして、末木氏は「死者を排除することこそが、近代的として賛美された。仏教においては、葬式仏教が軽蔑され、仏教は本来生者のためのものだと論じられた。だが、現実には近代の仏教の経済的基盤は葬式仏教によって成り立っていた。その現実を見ずに、理論において死者を抹殺してきたのが近代である。その立場から、近代に先立つ近世も世俗化の時代として捉えられ、宗教の力を軽視することになった。だが、現実には、17世紀においてもっとも影響力を持った思想は仏教であった。17世紀前半の儒仏の論争においては、儒教側が理気説を提出して前世・来世を否定したのに対して、仏教は正面から三世の因果を打ち出し、前世・来世を説き、それを現世道徳の成り立つ根拠としていた」と述べています。このあたりは、中国哲学者の加地伸行先生とわたしの対談本『論語と冠婚葬祭』(現代書林)で詳しく語られています。
4「未来へ向かって」では今日、死者や霊性、宗教の問題を抜きにして、純粋に世俗的な社会というのは成り立たないことは明らかであるとして、末木氏は「より大きな宗教の世界観の枠の中に、世俗社会や政治も位置づけられるべきではないのか。そのことによって、逆に宗教の側も身勝手な論を振り回し、相互に対立するのではなく、協力しながら社会的に責任の持てる思想と活動を展開すべきではないのか。近代が終わった後で、理念なき覇権主義の暴走は絶対にあってはならない。もはや人類の存亡自体が問題となっている。お互いに争いあっている余裕はない。政治も宗教も協力しながら、この危機に正面から立ち向かわなければならないのである」と述べるのでした。
2022年12月19日に行われた「《座談会》死者と霊性」の第Ⅰ部の「はじめに――コロナ禍のなかで」では、東京大学東洋文化研究所教授で中国哲学者の中島隆博氏が「コロナ禍では、人との接触が禁止される傾向にありますね。きょうのお話にもかかわりますけれども、たとえば死者とかかわることも禁止されていく現実があります。無論、人と触れ合うとか、かかわると言っても、物理的に対面すればそれが可能かというと、なかなか人と人が本当に触れ合うというのはそう簡単なことではないわけです。そのことの意味が、問われていると思います。触れてはいけない。でも、触れ合わなければいけない。この二律背反的な要請ですね。本当に触れ合うとはどういうことかが、改めて問われています」と語っています。
また、コロナ禍が問うているのは、たぶん人だけの問題ではないとして、中島隆博氏は「コロナがもたらされた理由の1つは、人間の活動があまりにも伸張し過ぎて、自然界の奥深くにまで入り込んで生態系を徹底的に乱していることがあると思うのです。人間主義、もしくは人間中心主義という近代的な考え方を、見直さないといけない。動物や植物のあり方に、もう一回学ぶことがあってもよいのではないか。そんなことを考えさせられています。もう1つ言いますと、パンデミック(pandemic)の語源は、ギリシア語のpandēmos(pan〈全て〉、dēmos〈人々〉)ですから、全ての人にかかわるものです。しかし実際は格差がパンデミックにも反映していて、感染が特定の人々に集中するという現象が見られます。これは全ての人にかかわる問題なのだと考えなければいけない。そのためにデモクラシーのアップデートが必要なのではないか」と述べます。
東京工業大学科学技術創成研究院 未来の人類研究センター・リベラルアーツ研究教育院教授で評論家の若松英輔氏は、「死者と霊性」という問題はともに、見えないもの、ふれ得ないものと対峙することになるとして、「ある意味で感覚の彼方にあるものを世界に取り込むかどうかは、その人の世界観そのものだと思います。ウィリアム・ジェームズが『プラグマティズム』で語った言葉を借りれば、世界観というよりも宇宙観というべきかもしれません。私個人は、もともと「死者と霊性」を含み込んだ世界の中に生きてきたせいもあるのですが、見えないものが割り込んできたという感じはあんまりない。しかし、それが現代の常識的な見解でないことは理解しています」と述べています。
「死者とのつながり方」では、政治学者で東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授の中島岳志氏は、イタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンの「この国はいまエピデミックによって、死者に対する敬意さえもはやない倫理的混乱のなかへと投げこまれている。(略)死者――私たちの死者――は葬儀を執りおこなわれる権利がないし、愛しい人の死骸がどうなるのかはっきりしない。私たちの隣人なるものは抹消された」という言葉を紹介し、「人間には、ビオス(社会的政治的生)とゾーエー(剥き出しの生・生物的な生)があるというのがアガンベンの立場ですが、それで言えば、ゾーエーばかりを重視してどうするのか、と主張している。人間には社会的な生、ビオスというものが存在する。生者と死者の間にもビオスの交流というものがあるはずだ。しかし、死者がちゃんと葬儀もされず、死に切れていない。これはいったい何なのかという問いかけをしていたわけです」と説明します。
「100年単位と1000年単位」では、多摩美術大学美術学部教授で文芸評論家の安藤礼二氏が、東日本大震災が発生した2011年について、「2011年の100年前というのは、鈴木大拙がアメリカから帰国して(1909)、日本での生活を始めた時期です。柳田国男が『遠野物語』(1910)を発表した時期でもありますし、西田幾多郎が『善の研究』(1911)を発表した時期でもあります。南方熊楠が神社合祀反対運動に取り組んでいた時期でもありますし、折口信夫の場合は、大学の卒業論文として『言語情調論』(1910)を発表した時期でもあるんです。私が特権的な関心を持っている思想家たち、表現者たちが皆はかったように、一斉にこの時期に活動を本格化させている」と語っています。
「死者の霊性」について、若松氏はプラトンの『パイドン』と『論語』に注目します。プラトンの描き出すソクラテスにとって、死とは死者に出会うことにほかなりません。死者の国に帰っていくという時間がソクラテスにははっきりとあります。『論語』には一番弟子の顔回が亡くなったあと、孔子が嘆きに嘆く場面が記録されています。孔子は、片方で嘆きながら、片方では明らかに死者となった顔回を感じている。こうした身近な古典の中にも、「死者と霊性」を考えるヒントが多く、そして豊かにある。そして、近代で「死者と霊性」という問題を考えるときに注視したいのが、内村鑑三であるといいます。
若松氏は、内村鑑三について「彼は最初の著作『基督信徒のなぐさめ』から生涯を通じて、『死者と霊性』を語った。内村は、近代日本で『霊性』という言葉をもっとも早い時期に用いた人物の1人です。内村鑑三は無教会のキリスト教徒ですが、彼の父宜之は高崎藩きっての儒者でした。内村鑑三のバックボーンは儒教です。内村に限らず、「愛」や「義」、「霊」を含めてキリスト教を語る際、決定的に重要な言葉の多くは儒教に由来する。キリスト教が入ってきた時期を、仮に安土桃山時代としてもいいのですけれども、言葉そのものは、もっともっと古いところから来ている。ですから『死者と霊性』を考えていくための時間軸は、深くとっていく必要があるのではないでしょうか」と述べます。
この若松発言を受けて、儒教が専門である中島隆博氏は「内村鑑三の『代表的日本人』を読みますと、内村がどれだけ儒教に対して深い造詣をもっていたのかが、つくづくわかります。しかも、儒教に対する内村なりの新しい読み方もしていたという気がします。私は、儒教が日本で本格的に広まったのは明治だと思っていて、その一翼を内村も担ったのではないかと思います。顔回の死の問題ですが、あそこは『論語』の中でもハイライトの1つですよね。『子曰く、噫、天予を喪ぼせり、天予を喪ぼせり』というふうに孔子は嘆きます。そんな嘆き方はそれまでしていないわけです。いままでのトーンとは違う切迫したものがある。しかし、近代日本の解釈を見ると、そこのところが、あんまりちゃんと捉えきれていない」と述べています。
また、和辻哲郎も『孔子』という本の中でけっこうサラッと書いていることを指摘し、中島隆博氏は「孔子は人類の教師の中で死について語らなかった人物である、なんてことを言うんですよね。本当にそうなのか、という気がします。それが近代日本の儒教解釈の1つの大きな方向性であって、祈りの問題とか、死の問題を避ける方向に行くんですね。でも『論語』を読みますと、そうじゃないわけです。祈りの問題、死の問題は、決定的な場面で出てくる。だから『論語』を読み返す必要があるというのは、おっしゃる通りだと思いますね」と述べています。
さらに、中島隆博氏は井上円了に言及し、「井上円了は、国家のために死ぬことができる兵士、そのために霊魂不滅を言わなければいけない。ところが、それに対して中江兆民は、いやいや哲学を言うのだったら断じて霊魂なしと言わなければいけない。これはその背景で国家観が鋭く対立していた気がします。そこに南方熊楠が割って入るというかたちになって、熊楠は円了とは違う霊魂論をやり直そうとするんです。世紀末から世紀の初めにかけて、霊魂論争は1つの大きなトピックだったと思うんです。なぜそんなことに注目したのかというと、仏教が中国に入ってきた時の論争というのがあるんです」と述べます。
その論争とは六朝時代(220-589)のもので、「神滅不滅論争」といいます。「神」と書きますが、もともとこれは「精神」とか「霊魂」と訳してもよい、精神的な働きのことだそうです。人が死んだら、その「霊魂」は滅びるのか滅びないのかというのを、仏教と儒教の両者がさんざん議論していきます。中島隆博氏は、「とてもねじれた論争になっていて、儒教の方が、霊魂は滅びると言うんですよ。ところが祖先祭祀をしなければいけないから、それはおかしいですよね。滅びてはいけない。仏教の方は、滅びないと言うんですけれども、でも輪廻転生から最終的には解脱するんだから、滅びるわけです。すごくねじれているんですが、その論争が19世紀末にもう一回、日本で反復されるのを見ると、とても不思議な感じがしました。私たちにとっても、依然として重要な問題なのだと思います」と述べています。
死者を祀るというのは儒教にとっては最大の問題です。「礼」にとってまさに死者をどう祀るのかというのが1つの根幹ですから、中島隆博氏は「ここに我々は儒教的な『礼』の現代版を見ているわけです。今や、尊厳の失われた死に私たちは直面しています。死者を死者としてちゃんと葬ることがない。尊厳を死者に返すことができない。そういうあり方を私たちが許容しているとすると、それは極めて問題だと思うわけです。では、どうしたらいいのかという時に、ハイデガー的な方向で、死の固有性なんてことは言わないほうがいい。『死』というのは孤立した現象ではなくて、ともに『死』というものを経験するというか、そうやって『生きる』というのは変ですけれども、ともに経験することだと思うのです。だから、一人で死なせてはいけない、孤立した死を避けることが、私たちにとって決定的に大事なのではないか」と述べます。
第Ⅱ部の「19世紀のグローバル化と神智学」では、末木氏が「19世紀において、いま私が関心を持っているのは神智学ですが、その母体となった神智学協会は、ヘレナ・P・ブラヴァツキー、ヘンリー・S・オルコットらによって、1875年に設立されました。宗教・哲学・科学のある種の統合を目指して、人間の潜在能力を考究することが重要視されました」と述べれば、安藤氏が「2000年代ぐらいから、それまで非常に怪しいオカルティズムの運動ということで正面から論じられてこなかった神智学が、近代インドの独立運動ですとか、近代日本の神道改革運動や仏教改革運動、そういった広義の近代的な宗教改革運動にきわめて甚大な影響を与えているのではないかということで、ようやく真面目な研究の対象になってきたと言えます」と述べます。
ブラヴァツキーの一家は、ロシアのコーカサス地方を放浪する生活を送っていました。安藤氏は、「黒海からカスピ海にまたがるカルムィク草原です。ここにはロシア領内で唯一チベット密教を信奉する遊牧民たちが生活をしていました。つまりブラヴァツキーにとってチベット密教は幼少期から馴染みのある教えであったのです。しかも28歳でこの世を去るその母親(エレーナ・ガン)は、将来を嘱望された小説家であり、カルムィクの仏教徒たちを主題とした小説『ウトバーラ』を書き上げています。『青蓮華』のサンスクリット表記に通じていますが、どこまで意図していたかは判然としません」と説明しています。
また、安藤氏は「その初期、神智学は『秘密仏教(秘教的仏教)』、エソテリック・ブディズムを自称していました。その呼称はまんざら偽りではなかったのです。密教は仏教の人間的な始祖、ゴータマ・ブッダを重視しません。人間を含め森羅万象あらゆるものを産出する根源的な存在、法身を何よりも重視します。その上、カルムィク草原では、そのような大乗仏教の密教的な展開と、一神教の極であるイスラームが相互に浸透する状態にあったとも言われています。無神論の極と一神論の極が、あらゆるものを自身のうちから産出する根源的な存在、法身というヴィジョンのもとで一つに結び合わされていたのです」と説明します」とも説明します。
さらに、安藤氏は「ブラヴァツキーは、おそらくはそのような背景をもとに、一神論、多神論、無神論が生み出されてくる太古の根源的な宗教の教えが再発見されたと称しました。『一』と『無』の間で『多』がはじめて可能になるのです。そうした教義の再発見(実は創出なのですが)を、新たな世界交通の中心地、アメリカで宣言したのです。密教こそが新たな世界宗教、グローバルな世界宗教の骨格になる、と言う訳です。それだけではありません。現代によみがえった太古の根源的な宗教は、未来を切り拓いていく近代的な科学の教えとも背馳せず、逆にその未知の可能性を指し示すものだとさえ主張しています」と述べています。
続けて、ブラヴァツキーはマックス・ミュラーの『東方聖書』に結実していく諸著作を熱心に読み込んでいったことを指摘し、安藤氏は「世界のあらゆる宗教が、根源的な一者からの発生にして流出を説いている。新プラトン主義の流出論、つまりはプロティノスの哲学や、そこから一神教が発生したと位置づけ直されたユダヤのカバラ思想などを、ブラヴァツキーは自身の宗教体系に取り入れていきます。ユダヤ教、キリスト教、イスラーム、さらにはチベット密教、そしてアートマン(人間的な自我の奥底に秘められている真我)とブラフマン(大宇宙を生み出し大宇宙を統べる理法)が一致するというヒンドゥーの「不二元論」まで、世界のあらゆる宗教を生み出し、それゆえ世界のあらゆる宗教に総合を与えるものこそが神智学だと言うのです」と述べます。
神智学は、新たな世界宗教にして、新たな総合宗教でした。安藤氏は、「スウェーデンボルグ神学さえも消化吸収していきます。もちろんオリジナリティのほとんどない、折衷宗教でもあるわけですが、しかしその地点から力強く、人類はすべて平等であると発信していく。女性も差別しない。女性を差別しないどころか、動物も人間と平等であると考える。森羅万象あらゆるものは神の霊的な種子から生まれ、それゆえ、神の霊的な種子を共有しているわけですから。だから神智学協会は動物愛護運動や女性解放運動にも深くかかわっていく。神智学協会には、世界のあらゆる場所から、霊的な救いを求める女性たちが一気になだれ込んでくる。ブラヴァツキーを継いだアニー・ベサントは、社会主義運動と女性解放運動を経て、神智学に出会いました」と述べます。
神智学のヨーロッパ的な展開の中から、ルドルフ・シュタイナーの思想が生まれてきます。安藤氏は、「シュタイナーは神智学協会とは決裂するのですが、明らかに同じヴィジョンをもって自らの道、総合芸術運動にして総合教育運動の道を歩んでいきます。現在でもシュタイナー教育は全世界に広がっていて、一つのグローバルなネットワークを形づくっていますよね。ブラヴァツキーの神智学もシュタイナーの人智学も、近代的な意味での国境、国家という概念を超えてしまう、いわばトランスナショナルな運動を内包しています。神智学には、プラスの側面もマイナスの側面もあります」と述べるのでした。それにしても、安藤氏の神智学講義は6ページ以上にも及びます。明らかに座談会の中での発言としては異常なのでゲラに加筆したのではないかと思われますが、安藤氏の神智学への情熱には感嘆しました。
神智学の話題は、他の座談会メンバーも刺激します。若松氏は、神智学(テオソフィー)の起源をどこまでさかのぼるかは諸説あるとしながらも、「新プラトン主義の祖プロティノスに始まる霊性が、キリスト教の神秘主義の中に入ってきて、ヤコプ・ペーメを1つの頂点にしつつ、ある潮流を作っていきました。ヘーゲルそして西田幾多郎がヤコプ・ベーメを高く評価していたことはよく知られています。もちろん、神智学はキリスト教以外にも存在します。イスラーム神智学者で著名な人物には、井筒俊彦も論じたスフラワルディーがいます。歴史的な『テオソフィー』と神智学協会の運動のあり方でもっとも異なるのは、霊性的経験を『折り重ねる』か『混合する』かという点です。『折り重ねる』とき、それぞれの霊性は、その歴史と共に保持される。しかし、『混合』されるとき、霊性的事象は、ある流れの部分になっていく」と述べています。
また若松氏は、キリスト教神学の礎を作ったトマス・アクィナスがアリストテレスから甚大な影響を受けながらも、彼はキリスト教の霊性にギリシア哲学を折り重ねたのであって、二者を混合したのではないことを指摘します。もう1つ、ガンディーとアニー・ベサントがうまくいかなかったというエピソードに言及し、「ガンディーはブラヴァツキーともイギリスで会っています。やっぱりうまくいかないんです。ガンディーは、もちろん学べることは学ぶし、神智学協会の人たちからは、彼の生涯の聖典になる『バガヴァッド・ギーター』を学んだ。これはとても重要な出会いでした。しかし、最終的にはうまくいかない。ここに個の経験としての神智学協会と組織、あるいは共同体としての神智学協会の問題が顕著に現われています。このことをまさに象徴したのがクリシュナムルティによる、共同体の解散です」と述べます。
アニー・ベサントがクリシュナムルティを担ぎ上げて、「東方の星教団」をつくる。1911年でした。その時に離反したのがルドルフ・シュタイナーです。若松氏は、「シュタイナーと神智学協会はとても深い関係にあります。しかし、シュタイナーは共同体としての神智学協会を離れることによって、彼自身の独創的な仕事をしていくようになります。ただ、『神智学』や『いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか』『神秘学概論』も、彼の主著は神智学と密接な関係を持っていた時期に書かれています。神智学は、たしかにさまざまに影響を与えています。その影響は今東光の父親である今武平を通じても入っていて、若き川端康成にも流れ込んでいます。シカゴの万国宗教者会議は神智学協会の働きがなければ成立しなかったかもしれない」と述べるのでした。
「中国の近代と霊性」では、康有為たちの孔子教に日本側が非常に反発したことを紹介します。これについて、中島隆博氏は「儒教を宗教化させてはいけない。断固、いけない。東大の服部宇之吉なんかを中心にそう批判していったのですね。服部は、西田幾多郎や鈴木大拙よりは先輩で、3つぐらい歳が違うはずです。儒教の宗教化を徹底的に退ける。そのかわりに儒教の道徳化をするんです。井上哲次郎のような国民道徳論のほうにつながっていく議論なんですが、宗教化を退けることは道徳化していくことであったわけです。和辻哲郎なども、その系譜で孔子を読みます。さきほど和辻の『孔子』をご紹介しましたが、人類の教師の中で唯一死について問わなかった、これが孔子だというんですけれども」と述べています。
しかし、和辻哲郎の『孔子』についても、中島隆博氏は「あれも結局、宗教的ではなく道徳的に読むという、日本の近代の儒教読解の流れなんですね。でも、前近代の日本はまったくそんなふうには読んでいませんでした。服部は、しきりに荻生徂徠を批判します。徂来には、非常に宗教的に『論語』を読んでいるところがあるからです。ですから服部たちの闘いは、儒教の宗教化を批判しなければいけないと同時に、前近代の日本を批判して、宗教ではいけない、道徳としての儒教を立てなければいけないという感じなんですね。いまの私たちに道徳化された儒教のイメージが強いのは、こういった背景があるからです」と述べています。
「日本の近代と霊性」では、末木氏が神智学に踏み込み始めた理由として、「幸徳秋水が大逆事件で首謀者として処刑されるわけですが、獄中にまで持ち込んで最後に完成させたのが『基督抹殺論』です。いわゆる社会主義の系統の中でとらえられていたのですが、キリスト教批判、あるいはキリストの存在そのものを否定する議論をどこから持ってきているかというと、7、8割ぐらいが、さきほどから話にでているアニー・ベサントの本に拠っています。もっともベサントが神智学に入る前の著作ですので、それで幸徳秋水をただちに神智学と結びつけるのは不適切だと思いますが、幸徳は明らかに新仏教の人たちとも親しくしていました。そういうことを考えると、意外と神智学関係の議論は、日本の近代の奥深くにまで入ってきているのではないかと思います。折口信夫であるとか、南方熊楠、鈴木大拙、西田幾多郎、ほかに宮沢賢治や近角常観なども含めて、そういう人たちをトータルで考えたときに、従来の思想史の研究では無視されてきたような霊性論が、当時は大きく議論されていたことがわかります」と述べています。
末木氏の発言を受けて、安藤氏は「南方熊楠と鈴木大拙は、互いに非常によく似たバックグラウンドを持っているんですよ」と述べ、1893年のシカゴ万国宗教会議に言及します。南方熊楠の「曼陀羅」の重要な源泉であり、その文通相手となる土宜法龍も、大拙の「霊性」の重要な源泉であり、大拙に禅を実践的に教授したその師匠の釈宗演もともにそこに参加しています。安藤氏は、「熊楠や大拙は実際には参加してはいないのですが、熊楠の曼陀羅も、大拙の霊性も、その真の起源は、この万国宗教会議にあったと私は思っています。万国宗教会議には、仏教だけに限りますと、釈宗演(臨済宗)、蘆津実全(天台宗)、土宜法龍(真言宗)、八淵蟠龍(浄土真宗)の4人が参加します。非常に若く、同時にきわめて優秀で、各宗派を公的にというよりは私的に代表するような形で会場にやって来ました」と説明します。
シカゴ万国宗教会議に参加した日本の僧侶たちがまず立ち向かわなければならなかったのは「大乗非仏説」でした。安藤氏は、「ヨーロッパの研究者たちがサンスクリットの経典をどのような方向で読み解いていったかというと、キリスト教と同じで、なによりも始祖伝なんですよ。イエスと同じように、仏教の教えのエッセンスはブッダの始祖伝、その言行録(つまりは「福音」ですね)に帰着する、というわけです。ですから、いわゆる上座部仏教を仏教思想の中心だと考えた。文献学の成果からすれば、釈尊滅後500年以上経たないと現われてこない大乗仏典とは、完全につくりものである。ブッダが直接説いたものではない(このことを「大乗非仏説」と言います)。だから、そこに与えられた評価はきわめて低かった。しかし、それでは、その大乗仏教経典に依拠する極東の仏教の価値とは、一体どこにあるのか。熊楠の師、大拙の師にあたる若き仏教界の指導者たちが考えなければならなかったのは、その点に集約されます。彼ら、そして彼らを支援していた者たちは、自分たちの主張をコンパクトな形にまとめた小冊子を、日本語と英語のバイリンガル版としてつくっていきます。そこに『霊性』という言葉が現われます」と述べます。
「言語の余白について」では、末木氏が「ウィトゲンシュタインの場合、初期の『論理哲学論考』ですと、かなりはっきりした二元論をつくってしまうわけですね。ザーゲン(言う)ということと、ツァイゲン(示す)ということで区別して、言語で言えることだけを問題にする。その外は、示すことはできるけれども言うことはできないんだというかたちで、そこにはっきりした二元論をつくってしまう。私自身もずっと長くそれにとらわれていて、なかなかその二元論から抜け出せなかったんですが、死者の問題を考えていった時、死者の言葉みたいなものは、その二元論ではとらえられない。まさしく言語でありつつ言語じゃないような中間的なものであって、曖昧であり、『だから、そんな声はないよ』と言ってしまえばそれまでのもので、全部消されてしまう。にもかかわらず何かある。その中間的なものをどう生かしていけるのか。つまり、言語化できないはずなのに、何かそれが言語になっているものをどうとらえるのかというのが、ものすごく重要な問題ではないか。それがわかってきた時に、ある世界の構造みたいなものをとらえ返していくことができるようになったということがあります」と述べています。
それに対して、安藤氏は「ベルクソンですと、記憶そのものですよね。記憶というのは過去からまさに訪れてくる意味であり、声である。それこそ死んでしまった者たちの声であると同時に、もしかしたらこれから生まれてくる者たちの声であるのかもしれない。折口が『古代』について語っていることも同様です。記憶は過ぎ去らず、つねに現れ出でてくる。そうした点が、おそらくは今後、大きな問題として浮上してくるのではないでしょうか。言葉が発生してくるような根源、過去からの記憶であり、それは同時に未来につながっていく現在の認識そのものでもある。いま我々が議論している「死者と霊性」というテーマにとって、そのあたりに共通の地平があるのではないでしょうか。物質は記憶であり、記憶は物質であるという……」と述べます。
若松氏は、二宮尊徳の「天地の経文」に言及します。天地に不可視なコトバを読むとして、『二宮翁夜話』の「天地の文に誠の道は明らかなり、掛る尊き天地の経文を外にして、書籍の上に道を求る、学者輩の論説は取らざるなり」という言葉を紹介します。若松氏は、「二宮尊徳は、治山の人です。治山する力によって600の村を甦らせたのですが、この人は四書の『大学』に深く学んで、『論語』そして『中庸』まではいいけれども『孟子』は注意が必要だ、と言った。片方で学問を積みながら、実はとても大事なのは非言語的な『天地の経文』だと語る。こういう人を、内村鑑三は『代表的日本人』の1人に選んだ。あともう1点は、死者が過去の存在かどうかということです。私の実感は、死者は、いまの存在です。死者の声はいまの声です。過去に発せられた声がいま響くというよりも、死者との対話とは、いまの死者といまの自分との対話だというのが、私の強い実感なんです」と述べるのでした。
第Ⅲ部の「死者たちの民主主義」では、「民主」対「立憲」という問題が、政治学的に、あるいは憲法学的にはあって、「民主」というのは生きている人間に投票権が与えられ、その過半数によってさまざまなものが決定するシステムであるとして、中島岳志氏は「しかし『立憲』という考え方は、いくら多数派が多数決によってそれを是としても、それでもなお、やってはならないことがあるのが憲法である。たとえば、表現の自由というものは侵してはならないと憲法で定められている。いま生きている人間が、いやそういうものは制限していいのだと決議しても、憲法上それはだめだとなるのが『立憲』という考え方。『民主』と『立憲』には、どうしてもぶつかってしまうポイントがある。何がぶつかっているのかというと、僕は主語がぶつかっていると思うのですね。『立憲』の主語が死者であり、『民主』の主語は生きている人間、生者になる。これがぶつかることが問題であり、実はこの数年間、私たちが見ている政治の中で起きている現象だと思うわけです」と述べています。
中島岳志氏によれば、単に生きている人間だけで民主主義をやっているのかというと、そうではありません。柳田国男はそうでないことを強く確信をしていた人であったと指摘し、「かなり若い時から、『時代ト農政』の中でも彼は、民主主義は生きている人間だけじゃなくて、亡くなった人たちと一緒にやっているんだということを繰り返し強調しているわけです。僕たちが思い起こさないといけないのは、この立憲民主主義。あるいは別の言い方をすると、立憲主義は死者たちの民主主義でもある。死者たちとともに何かを選んでいく。そして死者たちと対話しながら決定をしていく、そういう方法ではないのか。それが欠けているがゆえに、『民主』が暴走してしまうというのが、私たちがこの数年の間に見てきた日本の政治なのだと思っています」と述べます。この「死者の民主主義」の問題は、宗教学者の島薗進氏との対談本『愛国と信仰の構造』(集英社新書)でも訴えています。
大戦中、道徳としての神道、国家神道としての統制の中で唯一死者を弔うことのできる宗教施設としてあったのが靖国でした。安藤氏は、「その他の神社はすべて死者を弔えないんですよ。道徳としての神道は宗教ではないわけですから。ただ靖国だけが死者を弔うことができた。招魂祭に参加した人たちは、まさに身近な死者たちを弔うために参加している。こうした靖国のあり方と、近代における天皇のあり方はパラレルだったのではないかと思います。近代的な天皇は宗教的であることを禁じられている。しかし、死者たちを弔う国家の儀式の祭主として唯一ふさわしいのは、死者を弔うことを禁じられている天皇でしかあり得ない。そこに生じる矛盾です。天皇と靖国、その存在と制度の矛盾。なぜその双方を容易に解体することができないのか。ここに私は、近代日本が持たざるを得なかった不可能性そのものの顕現を見る思いがします。この矛盾を解きほぐしていきながら死者たちの民主主義を打ち立てていく。そのときにこそ本当の意味で、天皇と靖国の呪縛から我々が解放されるのではないかと思います」と述べます。
靖国問題から天皇に言及した中島岳志氏は、「平成の時代の天皇、いまの上皇ですけれども、あのご夫婦は、靖国を介さないでも死者との対話は可能であると考えた人たちだと思います。各地に行き、そして祈るという、その姿ですね。宮沢賢治の『雨ニモマケズ』のようなところがあって、平成の時代の天皇というのは、とにかく災害があったら自分が行く。佇んだり祈ったりする。そういうかたちで、霊性とかかわろうとした。歴史を引き継ぎながら、重要な本質を引き継ぎながら、いまの時代にどうアクセスするのかという、大変な努力をされたんだろうな、と思います」と述べます。
死者を供養する問題について、中島隆博氏はハーバード大学の教授であるマイケル・ピュエットを紹介し、「彼は古代中国をフィールドにする人類学者という非常に面白いあり方をしているんですけれども、『礼記』の中にある面白いエピソードを紹介しています。ある国の王が亡くなるんですね。そのあとに当然、その国は不安定化する可能性がありますよね。どうやってその国を再び安定させるかというと、『礼』を実践するしかない。どうやって実践するかというと、その王の子どもと孫が登場するんですね。孫が亡くなった王の形代になって、ある種のパフォーマンスを行い、孫である亡くなった王に、息子である王が服従をする。こういう『礼』を行う。これによってかろうじて秩序というものが回復される」と述べています。また、何のために「礼」を行うのかというと、それはこの世界が非常に分断されて、対立の芽があちこちにある。それを全部きれいにするとまではいかないけれども、何とか暮らせるような社会にしていく。そういった要素が「礼」にはあると述べます。
中島岳志氏の議論では、死者というのが立憲主義の1つの根拠になっていることを指摘する中島隆博氏は、「『礼』もやっぱり死者なんですね。でも、死者をどうやって正しい先祖にするかという、これが問われるんです。そのためにはパフォーマンスをしなければいけない。さきほど安藤さんがおっしゃったように、戦前の日本では死者をある仕方で利用してしまう政治学が働いてしまった。我々がいま振り返ると、そうではない可能性も本当はあった気がします。戦後は、同じような仕方で死者を利用する政治学を作動させるわけには、もういかない。その代わりに死者を忘却する方向に行ったと思うのですが、やはりもう一度、死者にどう向かい合うのか、それをやり直さないといけない」と述べるのでした。
安藤氏は、柳田国男と折口信夫という民俗学の2人の巨人の死者をめぐる思考の差異に言及します。柳田の場合、死者は「祖先」になりますが、折口の場合は「まれびと」になることを指摘し、安藤氏は「その点が互いに相容れないところだと思います。『まれびと』というのは、共同体にとって、まったくの他者のことですよね。『祖先』には決してなることができない。共同体の外から訪れ、また共同体の外へと去って行く、神にして人です。『祖先』にも『子孫』にもなれない、あるいは決してならない者たちです。いま議論している死者たちの中に『祖先』、もしくは『子孫』だけではなくて、『まれびと』も入れていかないと、現代的な『礼』としての弔い、先の大戦の弔いの実現はきわめて難しくなるように思います」と述べています。
戦前は自国の死者だけしか天皇も靖国も弔うことができなかったことについて、安藤氏は「それが本当の意味での死者の弔いになるのでしょうか。そこに捻れが生じていると思います。戦争で生み落とされる死者の、少なくとも半数以上は、まったくの他者ですよね。そのような他者をも弔うためには、死者たちの中に『祖先』や『子孫』と同時に、その両者には決して還元されることのない『まれびと』を取り込んでいけるような『礼』、政治的な実践と言ったら大げさでしょうが、もう1つ別の仕組みが必要になってくるのではないかと感じました。折口最晩年の論考である『民族史観における他界観念』は、そうした祖先や子孫になることができない死者たち、悪霊となって荒野を彷徨うことしかできない死者たちをめぐる考察でした。動物や『もの』としてしか生きられない死者たちの魂の行方に想いをこらした鬼気迫る論考で、私にとっては今でも大きな問題提起であり続けています」と述べます。
「『政教分離』と『メタ宗教』」では、末木氏が「憲法の前文を読んでみると、あれはほとんど1つの宗教的理念の表明ではないか。我々が普遍的に求める世界はこうなんだ、人類すべてが求めていく理想を我々は求めていかなければならないという、一種の宗教性を持った理想主義がうたわれている。憲法研究者の古関彰一さんは、キリスト教、特にクエーカー系のキリスト教者たちが関与した、と指摘しています(『日本国憲法の誕生』)。実際に当時のGHQにもそういう人たちはいたのですが、日本側もそうだったのではないか。戦後の日本の知的リーダーになった人物は、ほとんどが無教会系のキリスト教者でした。南原繁がそうであり、南原のあとの矢内原忠雄がそうですね。あるいは大塚久雄もそうですし、丸山真男なんかもかなりシンパシーを持っていた。実は、長谷川町子の母親は矢内原に傾倒していました。マックス・ウェーバーの理論ではありませんが、プロテスタンティズムの宗教性を除いた世俗的な生活倫理みたいなものが、『サザエさん』には現われている」と述べています。
教育学者の岩間浩氏によれば、ユネスコの源流に神智学があるそうです。末木氏は、「神智学協会は教育を一生懸命やるわけです。それがシュタイナーにもつながっていくわけですし、クリシュナムルティの発見も、若い人を教育していく発想から出ている。そういう普遍的な教育理念がユネスコにつながっていると言われて、新しい視点から神智学の再評価が出てきているんです。憲法の前文を見ますと、ユネスコ憲章の前文とよく似ているんですよね。ユネスコ憲章は、要するに平和は人の心の中に砦を築かなければならないということで、心を重視する。だからユネスコ憲章はマルクス主義者なんかから批判されるわけです。そういう流れも、戦後憲法に注がれているのではないか。宗教性を取り戻してみたら、戦後憲法の読み方も変わってくるのではないかと考えております」と述べます。
宮沢賢治の「雨ニモマケズ」のモデルになったのは斎藤宗次郎だと指摘する若松氏は、「斎藤宗次郎は内村に最期までよりそった人です。だから、宮沢賢治が内村鑑三を知らなかったというのはあり得ません。いままで賢治のキリスト教からの影響も、カトリック、プロテスタント的に読まれてきたんですけれども、無教会的に読み直さなければいけないという問題がある。無教会のキリスト教で生きていたのにカトリック、プロテスタント的に読まれてきた文学者がもう一人いて、それが太宰治です。太宰治の持っていた聖書は無教会の聖書です。カトリック、プロテスタントの聖書ではない。「近代」をとらえ直す時に、キリスト教はキリスト教でも、違うキリスト教だということは重要な点だろうと思います」と述べます。
「『宗教』と『国家』の再定義へ」では、若松氏が言語学者でイスラーム学者の井筒俊彦に言及します。若松氏は、「井筒俊彦は終生、預言者性にこだわり続けた表現者だったと思います。そのことに関連して、安易に評価を下すにはきわめて危険な主題だと思いますが、あえてここで提起しておきたいことがあります。若き井筒が、おそらくは相当な情熱をもって取り組んだアジア主義の問題です。近年、大川周明が出版したものの中で学問的にもしっかりしたものだと評価される『回教概論』ですが、私はいくつかの根拠から、その骨格となる部分は大川ではなく、井筒が書いたのだと推定しています。井筒の中にも明らかに大川のアジア主義に深い共感を寄せている部分があった。二人をつないでいた一つの重要な要素が、預言者という特異な存在への関心であったと思います」と述べています。
また、若松氏は「世界大戦の予感の中、国家を超える信仰の共同体を組織する要として、明らかに、宗教的な預言性を持った者を政治的な指導者に据えて国家を改変(改造)していくというヴィジョンをさまざまな人々が抱いていた。政治的な革命は宗教的な革命としてしか生起しないと思われた。そのときに1つのモデルとなったのがイスラームの預言者ムハンマドであり、ムハンマドを範として宗教的かつ政治的に急進的な力を持たせた天皇であったと思います。大東亜共栄圏の宗教的かつ政治的な支配者たる天皇ですね。国家という枠組みを超えるための一つの手段です。しかし、それが本当に実現されてしまっていたら、現実に起こったこと以上の破滅が極東の列島にもたらされたかもしれません。本当にそれでよかったのか。預言者という存在を、近代日本の中で考えたとき、私はつねにその問題に立ち返ります」と述べます。
19世紀半ばに、バハー・アッラーを開祖にしてペルシャ(イラン)に生まれた新しい宗教運動に「バハーイー教」があります。これは、ムハンマドの後にも預言者はいるということを強調していく教えであり、いろいろな宗教をすべて認めるというふうに、ある種の「メタ宗教」であると指摘する中島隆博氏は、「そのバハーイー教に対して井上哲次郎が面白いことを言っていて、バハーイー教第二祖のアブドル・パハーが、日本の将来についてアメリカの西海岸で預言をした、と。何かというと、「今後の新たなる文化は日本より興るであろう」と言った。これをわざわざ書き留めているんですよね。日本のことをバハーイーの人たちが言及していたということは、その当時、非常に密接な知的ネットワークがあったという気がするんですね。井筒なんかも、こういったと無縁ではなかったと思います」と述べています。
そのバハーイー教について、安藤氏は「鈴木大拙の伴侶となったビアトリス・アースキン・レインの母親、エマ・アースキン・ハーンがやはりバハーイーなんです。当然ビアトリスもその影響を受けています。母であるエマは娘であるビアトリスを追って日本を訪れ、日本で亡くなっています。大拙とビアトリスは、そうした環境の中で出会っている。もう1つ、バハーイーを積極的に受け入れていたのが、出口王仁三郎率いる大本でした」「ビアトリス自身も大本に行っています。王仁三郎は大拙が日本語に訳したスウェーデンボルグの『天界と地獄』も読み込んでいますし(『霊界物語』の重要な典拠の一つになったと推定されています)、折口が理論的に突き詰めようとしていた国家神道以前の神道、神憑りの神道を文字通り実践しています。神憑りと預言者性は出口王仁三郎のうちで1つに固く結び合わされていた」と述べます。
国家を超える原理として預言者性を提起する安藤氏は、「それと対極に位置しながら、やはり確実に国家を超えていくためのもう1つの方法があります。国家を形成しない遊動性を、集団として生きることです。このことは折口信夫には、はっきりと分かっていたと思います。なぜなら、折口は『まれびと』を2つの極から考えていたからです。ミコトモチとホカヒビト、天皇と放浪する芸能民たち、つまりは、預言者性を突き詰めていく者と遊動性を突き詰めていく者たちです」と述べます。さらに安藤氏は、「折口は国家を超える原理として、預言者性と遊動性の2つを考えていました。それは『古代』の問題ではなく、折口が生きた時代、さらにはそこから連続している『現在』の問題でもあるはずです」と述べるのでした。
大本教について、中島岳志氏は「1920年代の第一次弾圧のあとに、バハーイー教とつながったり、紅卍字会とつながったり、人類愛善会というのを使って普遍宗教を説いたり、エスペラントを取り入れたり、いろいろとやるんですが、しかし30年代に入ると一気に昭和神聖会というものをつくり、日本で最も会員数の多い右翼団体になっていったりする。そこに内田良平とか頭山満がかかわってくるわけですね。普遍的なものを求める、メタ的なものへアクセスしようとすることが、なぜ日本の主体化という問題になっていったのか、そこをどういうふうにとらえ直すのかというのが、きょうの議論に入れておかないといけない重要な視点だと思いました」と述べます。
ここで「メタ宗教」という言葉がキーワードになります。「メタ宗教」とは新たな哲学でもあるのではないかという安藤氏は、「哲学は概念とともに刷新されていきますよね。きょうの議論で触れられていた表現者たちはみな、独創的な概念を発明するとともに、その概念にもとづいて自らの思索を深めていっています。たとえば、西田の『場所』や大拙の『霊性』。さらには熊楠の『曼陀羅』、柳田の『祖先』(あるいは「常民」)、折口の「まれびと」。そして井筒の『無』にして『無限」』神。いずれもそこから新たな哲学が展開されているとともに、やはり彼らが希求していたのはみな『メタ宗教』だったのではないかと思います。いずれの概念も、実は古くから用いられていた宗教的な術語を、独特な形で現代によみがえらせたものです」と述べています。
同時に、いずれの概念もまた「私」を超えた他者との共生を志向しているとして、安藤氏は「人間的な『私』を解体することではじめて他者との共生が可能になる。『近代』を否定するのではなく、『近代』を取り入れながら、いかにしてその『近代』に抗い、いかにして自分たちとは異なった者たちと共生していくのか。そこが賭けられている。異なった者たちの中には、未来の子どもたち、過去の死者たちも含まれている。冷静に考えてみればこれもまたきわめて当然のことなのですが、おそらく現代の『メタ宗教』は新たな哲学にならなければなりませんし、現代の新たな哲学もまた『メタ宗教』にならなければならない。そういうことではないでしょうか」と述べるのでした。あまりにも、あまりにも興味深い問題ではありませんか!
わたしも儀式の研究と実践を通じて「メタ宗教」というものを追求している人間です。そして、最も重要な概念を「礼」であると考えています。「『メタ宗教』の条件」では、なんと中島隆博氏が「すぐ思い浮かべたのは「礼」なんですよね」と述べているではありませんか。「礼」というのが、非常に実践的でありながら、他方で非常に抽象的なものであるという同氏は「実践がなければ意味がないんです。預言者の問題でも、実践の中で何を明らかにしていくのか、そこにかかわっていると思います。たとえば井筒自身の読解の特徴を見ていくと、シャーマンについて、『パーソナルなもの』というつかまえ方をするんですよ。これは非常に理解が難しいなと思っているんです。つまり、プライペートなものでもないし、パブリックなものでもない。それとはぜんぜん違う仕方で『パーソナル』というのを使っているんです。アンリ・マスペロから来ているという気がしているんですけれども、井筒はシャーマンあるいは預言者に対して、独特のアプローチをしている」と述べます。
「礼」といえば、わたしは葬礼に最も価値を置いています。「葬」こそは人間が人間であるための最重要条件であると考えているからですが、中島隆博氏は「若松さんがおっしゃった、死者というのは生者の記憶の中でどうこうするものではない、あるいは過去に属しているものではないということには、非常に考えさせられます。そうすると死者とかすかわる時に、井筒だったら『パーソナルな』というふうに言うと思うんですけれども、そういう独特の、しかし私たちにとってはある意味では非常に親しいかかわり方が出てくるのではないか、そんな気がしているんですよね。『礼』なんていうのも、パーソナルなところでやらない限り、意味がないわけです。単に一つの儀礼としてやれば、すぐ腐ってしまいますよね。そのあたりの、ある種の生き生きとしたものを取り戻さないといけないのかなと、思いました」と述べています。
「天皇と国体をめぐって」では、近代的な天皇の解体ということであれば、安藤氏にとって指針となるのは、折口信夫の理論と出口王仁三郎の実践だそうです。同氏は、「魂の永遠性と、その霊魂が賦与されることで有限である者の中に無限の者が顕現してくる。つまりは神憑りの理論と実践なのですが、それらを現代まで伝えてきてくれた人々がいる。修験道の行者たちに代表される宗教者たちであり、その源泉となった、『日本書紀』などに具体的に記された天皇たち、あるいは天皇のごく近くにいた女性たちへの神憑りの記録です。しかもその上、折口や出口の周囲には、霊魂の永遠性を現代まで伝えてくれている高貴な一族の末裔が、実際に存在していたのです。出雲国造家に連なる人々です」と述べています。
出雲国造家の祖先は、天皇家と同じく、アマテラスとスサノヲの誓約(うけい)から生まれた王子たちまでさかのぼります。天皇家と同じく神の血を引いているのです。しかし明治の革命の後、神道界の主導権争いで、出雲は伊勢に敗れました。安藤氏は、「スサノヲの血を引く一族は、国家神道の枠の外側に出ざるを得なかった。そこで、国造家に伝えられていた霊魂継承の秘儀の詳細を公表してしまいます。折口と出口がともに神道の基礎を学んだ國學院(出口は京都の皇典講究所)には、国造を継ぐべき人物も通っていた。おそらく二人は、そこで天皇家に伝わる霊魂継承の秘儀(正確にはそれと同等のもの)の詳細を知ったはずです。だから、『大嘗祭の本義』に結実する折口の理論も、鎮魂帰神法として整理される出口の実践も、決して荒唐無稽のものではありませんでした」と述べます。
「哲学と宗教の再興に向けて」では、末木氏が「私は思想史、宗教史をやっていますが、このところずっと考えているのは、幕末のことでして、特に平田派の系統です。そこでは霊魂論、死者の行方が大きな問題になっています。それまで死者というのは、地下の黄泉へ行って自分たちとは関係なくなると考えられていたのを、そうではない、この世界に死者はいるんだ、死者と生者が実は共存しているんだという、まったく革命的な考えを持ち出すんですね。これは篤胤門下でも大きいテーマになっていまして、したがって幕末神道の中核的な問題は、天皇論ではなくて、むしろ死者論であった」と述べています。また、「きょうは神智学のことがさかんに話題になりましたが、19世紀の後半ぐらいに、欧米とアジアとを行き来する神智学が出てきて、その中で死者の行方の問題が大きくクローズアップされる。それとほぼ同時代に、平田派でも同じような議論がなされているわけです。平田派というと視野の狭い国家主義みたいに思われているのですが、そうではない。実はグローバルな同時代的な現象として考えなければならないと思います」とも述べます。
中島隆博氏は、「中国の議論なんかを見ていますと、『礼』というのが本当に大事なんですね。ところが近代になって、『礼』なんていうのは中国の封建制、後進性の象徴だからやめてしまえと言って、乱暴に廃止される方向に行くわけです。それはそれで近代的な国民をつくっていくのに寄与したといえるのですが、それによっていろいろなものが失われたと思います。死者を誰がどう祀るのかという、この問題が見えにくくなった気がしています。日本の場合、19世紀末から20世紀初めにかけての霊魂論争では戦死者というのが浮上してきて、井上円了はそれを念頭に置いて霊魂不滅ということを言っていたわけですね」と述べています。
安藤氏は、「まずなによりも折口信夫が書いたもの、鈴木大拙が書いたもの、南方熊楠が書いたものを読まなければなりません。そして、この『私』が書く。そのような過程であらわになるのは、読み、そして書くということは、まさに死者との共同作業なんだということです。『私』に読まれている折口や大拙や熊楠は、おそらく生身の折口や大拙や熊楠とはまったく異なっているでしょう。分身にして鏡像のような存在しか描き出すことはできません。そのような形でしか、この『私』は、すでに死者となってしまった折口や大拙や熊楠の生とは触れ合えないからです。同時にまた、折口や大拙や熊楠を書くことによって、彼らの導きによって、『私』はそれまでの『私』とは異なった地平に出ることが可能になる」と述べています。
また、安藤氏は「批評という表現の場では、現実の生者である『私』が虚構(フィクション)としての死者となり、現実の死者である折口や大拙や熊楠が虚構の生者となる。『私』は死者とともに生きている。『私』は死者とともに変身し続けている。『私』は折口信夫とともに、鈴木大拙とともに、南方熊楠とともに読み、そして書いている。つまり、批評という営みそのものが、死者との共同作業だったわけです。そこで明らかになることとは、一体何だったのか。表現とは死者とともになされるものであり、そのことによって過去にも未来にもひらかれている、ということです。我々は死者とともに、あるいは他者とともに生きている。それは過去の記憶とともに、さらには未来の子どもたちとともに生きることでもあり、そのことによって新たな表現を創り出している」とも述べます。
中島岳志氏は、「僕は政治学をやっていて、ニュース番組に出たりしていたものですから、新聞記者の方から頻繁に、いまの民主主義をどうやったら立て直せますか、という質問をよくされるんですね。その時に僕は、仏事を立て直すことだと、言ってきたんです。葬式とか三回忌とか、そういった仏事を立て直すことだと言うと、政治記者の方はみんなキョトンとして、「は?」という顔をされるんです。僕にとっては大真面目で、それこそが立憲主義を立て直す、民主主義の根本にある問題だと思うんですが、世の中ではそうかんたんには通じない話になってしまっている」と述べます。
死者を誰が祀るのかという問題が本当に問われているという中島岳志氏は、「柳田の問いは非常に重要だけれども、しかし柳田が見ていた家制度というものに僕たちは固執するわけにはいかない。『何々家の墓』というもの自体が近代の創造物であって、明治民法と密着していることが言われています。それ以前に、日本の墓制において、ああいうお墓の形態というのはなかった。とするならば、この100年の墓制、つくられた伝統というものが崩壊の危機といいますか、瓦解していると見たほうがいい。僕たちは、『何々家の墓』という形態を守るのではなくて、柳田が『先祖の話』で唱えた死者と私たちの関係性というものを守るために何をリニューアルしていくべきなのか」と述べます。わたしは、そのリニューアルあるいはアップデートの方法について『葬式不滅』(オリーブの木)に詳しく書きました。ぜひ、中島岳志氏にも読んでいただきたいです。
エドマンド・バークはリフォーム・トゥ・コンサーブということを言いました。大切なものを守るためには変わっていかなければいけない、という言い方をしましたが、死者との関係を守るために何を変えないといけないのか。それについて、中島岳志は「いまは墓制の大転換の時期だと思います。亡くなる時に夫の家の墓に入りたいと思う女性は少なくなっていると思うんですね。そうではない墓制のあり方というものを、どういうふうにすればいいのか。あるいは家族の形態だって、非常に多様化している中で、死者という問題をどういうふうに継承できるのか。実際のところ、お寺のご住職とかそういった人たちは主体的に取り組まなければいけないわけです。実践的にあるいは哲学的に追求していくことが、とても重要であると思います。そして、その営みが、民主主義の課題と直結していると思っています」と述べるのでした。
「死者のビオス」で、中島岳志氏はイタリアの哲学者であるジョルジョ・アガンベンを取り上げ、「アガンベンは、古典古代のギリシアを継承し、「ゾーエー」と「ビオス」を区別する。「ゾーエー」は生物・動物として生きていることそのものを意味するが、「ビオス」は社会的政治的生を意味し、ポリスを担う市民の活動が重視される。アガンベンが問題視したのは、パンデミック下において「剥き出しの生」としての「ゾーエー」ばかりが重視され、人間の「ビオス」の次元が軽視されたことである。「自分の生が純然たる生物学的なありかたへと縮減され、社会的・政治的な次元のみならず、人間的・情愛的な次元のすべてを失っ」ている事態こそが、真の危機に他ならない」と述べています。アガンベンは、「ビオス」なき「ゾーエー」と化した典型が、パンデミック下で命を落とした死者たちの存在であると論じました。コロナ感染者は隔離を余儀なくされ、死の直前になっても、家族は面会を許されない。さらに、遺体を目にすることも触れることもできず、別離の儀礼すら行うことができません。
アガンベンは、「この国はいまエピデミックによって、死者に対する敬意さえもはやない倫理的混乱のなかへと投げこまれている」と言いました。また、「死者――私たちの死者――は葬儀を執りおこなわれる権利がないし、愛しい人の死骸がどうなるのかはっきりしない。私たちの隣人なるものは抹消された」とも言っています。中島岳志氏は、「アガンベンにとって、死者は『ゾーエー』を失っても、『ビオス』の次元において生きている。私たち生者は、『隣人』が亡くなった後も、その人と対話や交流を続ける。死者は存在しないのではない。死者として存在しているのだ。パンデミック下における隔離やトリアージによる死は、この死者のビオスを希薄化させる。死者もその隣人たちも、死のプロセスが暴力的に割愛されたことで、『あいまいな喪失』(ポーリン・ボス)に直面する。時間が凍結し、死者との関係構築が困難になる」と述べています。
3「柳田国男『先祖の話』」では、柳田国男が南多摩に住む老人と交わした会話を紹介しています。死を待つだけの老人はしきりに「御先祖になるつもりだ」ということを柳田に言い、柳田は「古風な、しかも穏健な心がけである」と感心したそうです。中島岳志氏は、「この老人は、死後にも仕事がある。しかし、その仕事を果たすためには、よき御先祖にならなければならない。子孫にとって規範となるような生き方をしなければ、御先祖としての役割を果たすことができない。彼にとって、先祖を供養し、現在を立派に生きることが、未来の他者との対話につながっている。死者となった先祖との協同生活が、自らの未来での臨在に直結している。死者とともに生きることは、過去に縛られて生きることだけではなく、死後の未来社会との共生へと開かれている。柳田にとって、国家とは今を生きる人間だけの専有物ではない。国土は、死者となった先人たちが積み重ねてきた営為や経験によって構成され、未来の国民と共有するものである。生者の多数派自分たちの利益だけを考えて都合よく利用してよいものではない」と述べています。
4「利他の構造」では、わたしたちの行為が利他的であるか否かは不確かな未来によって規定されているとして、中島岳志氏は「利他は常に事後的なものであり、私たちは利他を所有しコントロールすることはできない。利他はいつも未来からやって来る。一方、私たちの『今』は、過去の未来である。私たちは死者の未来に生きている。現在を生きる者は、過去になされた行為の受け手である。死者たちの行為が利他的であるか否かは、死者の未来に生きる我々の受け取り方にゆだねられている。私たちは利他的行為を行うことができない。しかし、利他のよき受け手になることはできる。死者の行為の受け手になることで、死者を贈与の送り主にすることができるのだ」と述べています。
5「死者の立憲主義」では、「民主」と「立憲」の緊張関係は主語の対立に起因しているとして、中島岳志氏は「『民主』の主体は、生者である。投票権を持っているのは生きている人間に限定されるため、多数派の構成員は、すべて生者である。一方、『立憲』の主体は、その大半が死者である。憲法は、長い人類の歴史の中で積み重ねられてきた失敗の経験が反映されたものである。『表現の自由』を保障する文言は、『表現の自由』が制限されたときに味わった先人たちの苦い経験によって構成されている。憲法の主語は死者であり、死者が関与する政治体制こそが立憲民主主義なのである。立憲民主主義とは、死者に制約されたデモクラシーである。『死者を含む民主主義』と言い換えてもいい」と述べるのでした。
「死者と霊性の哲学――西田幾多郎における叡智的源流」では、若松氏が「西田幾多郎(1870―1945)の生涯は、近親者の死とともにあった。襲い来る死のなかで彼の哲学は生まれ、育まれていった。若くして姉が病死、弟が日露戦争で戦死、6人の娘のうち4人(長女、次女、四女、五女)、長男も病死している。妻は長く患ったあと亡くなっている。西田にとって哲学とは、世界をどう認識するかに留まらない営みだった。それは真の意味における『人情』、人の情のありようを詳らかにすることにほかならなかった」と述べています。
死には人称があるという若松氏は、「一人称である我の死、これを経験した者はこの世に存在しない。しかし、誰もが必ず経験する。近しいと感じる者の死、これが二人称の死である。それは必ずしも肉親とは限らない。師友、あるいは実際に会わずとも私淑する人の死も含まれる。そして、人間の死、あるいは今日も世界では誰かが亡くなっている、というときの死を三人称の死と呼ぶ。さらに、すでに亡き者にとっての死を改めて考えるときそこに私たちは四人称の死というべきものを経験する。西田の哲学は、こうしたさまざまな異なる人称の死によって培われてきた」と述べます。死者を忘れることは、自らの生からも乖離することにほかなりません。若松氏は、「死者を憶うこと、過去のこととして顧うのではなく、今、ここにある実在として顧うこと、それが死者への供物になる」と西田は感じているといいます。若松氏は、「痛みは胸を走る。しかし、このときほど死者を近くに感じることはない。悲痛は死者が訪れる合図である、西田はそう感じていたのかもしれない」とも述べています。自らの愛妻を亡くされた若松氏ならではの感想であるように思いました。
若松氏は、「霊」は西田の哲学を読み解く最重要の鍵語であるといいます。西田にとって「心霊」とは、今日、心霊現象などというときのそれとはまったく次元を異にします。むしろ、西田にとって問題だったのは生きている人の「心霊」だったと指摘し、若松氏は「これまでは西田の哲学は『純粋体験』、『行為的直観』、あるいは『場所』などによって読み解かれてきた。もちろん、これらも無視できない。しかし、『霊』はそれらに勝るとも劣らない哲学的秘義がある。西田の代名詞といってよい『絶対矛盾的自己同一』の地平に辿りつくためにも『霊』という言葉の扉を素通りすることはできない」と述べます。また、いたずらに神秘を語る「神秘主義者」を西田は遠ざけたとして、若松氏は「『神秘的』という言葉は西田において積極的な意味を持たない。彼は大いなる謎を否定しない。そうでなければ、あれほど『神秘』を論究した鈴木大拙を生涯の友にすることはできまい。西田は、神秘に安易な帰結をもたらすような言説を嫌う」と述べています。西田は、神聖な謎に向き合う態度を「宗教的」という言葉で表現しました。西田がハーンに見ているのも狭義の宗教を超えた宗教性だったのです。
「地上的普遍性――鈴木大拙、近角常観、宮沢賢治」の2「宮沢賢治――『土地の精霊』と他人」では、中島隆博氏が、宮沢賢治とその父親である宮沢政次郎を取り上げます。仏教者の近角常観を崇拝した政次郎とは異なり、賢治とその妹のトシは常観とは相容れませんでした。トシは1915年4月に日本女子大学に入学し、上京すると、すぐに常観のもとを訪ねています。しかし、トシは常観の講話を聞いても、著書を読んでも、信仰を得ることができなかったのです。賢治も1919年1月に常観のもとを訪れたようですが、賢治は真宗の信仰を離れ、法華信仰とりわけ日蓮宗への信仰に入っていきます。中島隆博氏は、「もともと賢治は盛岡高等農林学校入学後の1915年8月に、盛岡にある真宗の願教寺で、島地大等(1875―1927)の講義を聴いていたが、その際に、法華経の話を聞き、徐々に法華信仰にのめり込んでいった。その後、賢治と政次郎との間に、信仰をめぐる深刻な対立が生じ、賢治は政次郎を改宗させようとする。それに失敗すると、賢治は花巻を捨てて上京し、1921年1月に国柱会に身を寄せることになった」と説明します。
「霊性の革命」の1「井筒俊彦の起源」では、安藤氏が「井筒俊彦は、折口信夫が提起した『憑依』の神道と、鈴木大拙が提起した『如来蔵』の仏教を1つに総合した地点に、自身の『東洋哲学』の体系を構築した。そうまとめることは充分に可能であろうし、そのための根拠も充分にあるだろう。荒々しい野生の神憑りが、いまこの場で、無限にして永遠の存在である如来、すなわち無限にして永遠である神へといたる道、神へと変身していく方法を明らかにしてくれるのだ。そこに井筒俊彦の学問と表現の核心が存在している」と述べています。以上、日頃からわたしが愛読する著者たちの祝祭のような本書は、それぞれの思想への共感とともに、彼らの思想が交錯する緊張感と炸裂感に大いなる刺激を受けました。
