- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2262 哲学・思想・科学 『シンクロニシティ 科学と非科学の間に』 ポール・ハルパーン著、権田敦司訳(あさ出版)
2023.08.16
『シンクロニシティ 科学と非科学の間に』ポール・ハルパーン著、権田敦司訳(あさ出版)を読みました。サブタイトルは「画期的な科学の歴史」です。著者は、アメリカ・ペンシルベニア州フィラデルフィアにある科学大学で物理学教授を務めています。ペンシルベニア州フィラデルフィア在住。 著書に『The Quantum Labyrinth(量子世界という迷宮)』『Einstein’s Dice and Schrodinger’s Cat(アインシュタインのサイコロとシュレーディンガーの猫)』など16冊があります。 本書にて「Physics Worlds Best of Physics in 2020!」を受賞。
 本書の帯
本書の帯
カバー前そでには、「ようこそ、量子世界の因果性をめぐる壮大な旅へ――」と書かれています。本書の帯には、「アリストテレスの物理学から量子もつれまで、何千年もの間、科学者たちが頭を悩ませてきた”シンクロニシティ(意味のある偶然)”を数々の科学者・哲学者と共に振り返る、画期的な科学の歴史書。」「Physics Worlds Best of Physics in 2020受賞!」「Forbes誌絶賛!」「光の速度よりも速く、瞬時にシンクロする。それが量子の世界。ずばり2022年ノーベル物理学賞の大テーマ。未来の世界はすべて量子の言葉で解釈されるようになる【生物学者 福岡伸一氏】推薦&寄稿!」とあります。
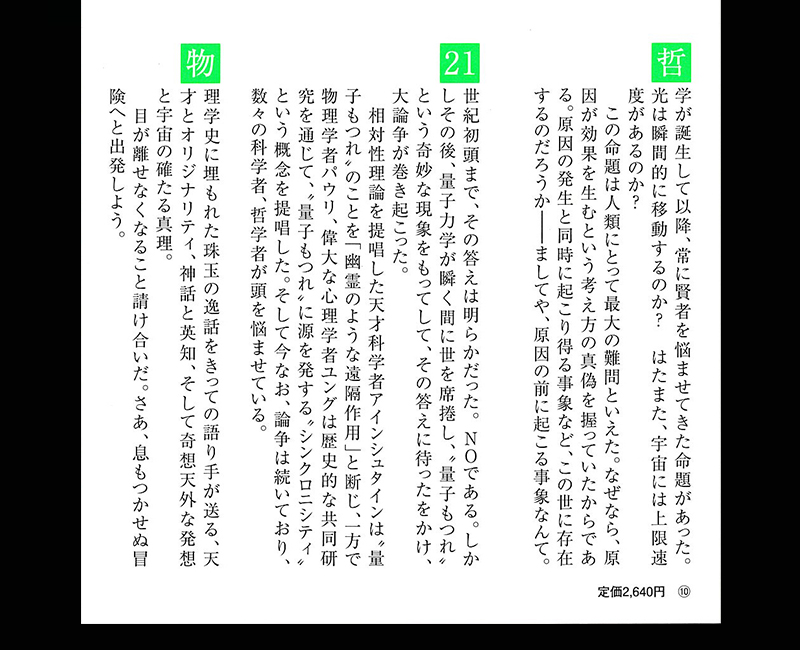 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「哲学が誕生して以降、常に賢者を悩ませてきた命題があった。光は瞬間的に移動するのか? はたまた、宇宙には上限速度があるのか? この命題は人類にとって最大の難問といえた。なぜなら、原因が効果を生むという考え方の真偽を握っていたからである。原因の発生と同時に起こり得る事象など、この世に存在するのだろうか――ましてや、原因の前に起こる事象なんて」
 アマゾンより
アマゾンより
また、帯の裏には以下のようにも書かれています。
「21世紀初頭まで、その答えは明らかだった。NOである。しかしその後、量子力学が瞬く間に世を席捲し、”量子もつれ”という奇妙な現象をもってして、その答えに待ったをかけ、大論争が巻き起こった。相対性理論を提唱した天才科学者アインシュタインは”量子もつれ”のことを『幽霊のような遠隔作用』と断じ、一方で物理学者パウリ、偉大な心理学者ユングは歴史的な共同研究を通じて、”量子もつれ”に源を発する”シンクロニシティ”という概念を提唱した。そして今なお、論争は続いており、数々の科学者、哲学者が頭を悩ませている」「物理学史に埋もれた珠玉の逸話をきっての語り手が送る、天才とオリジナリティ、神話と英知、そして奇想天外な発想と宇宙の確たる真理。目が離せなくなること請け合いだ。さあ、息もつかせぬ冒険へと出発しよう」
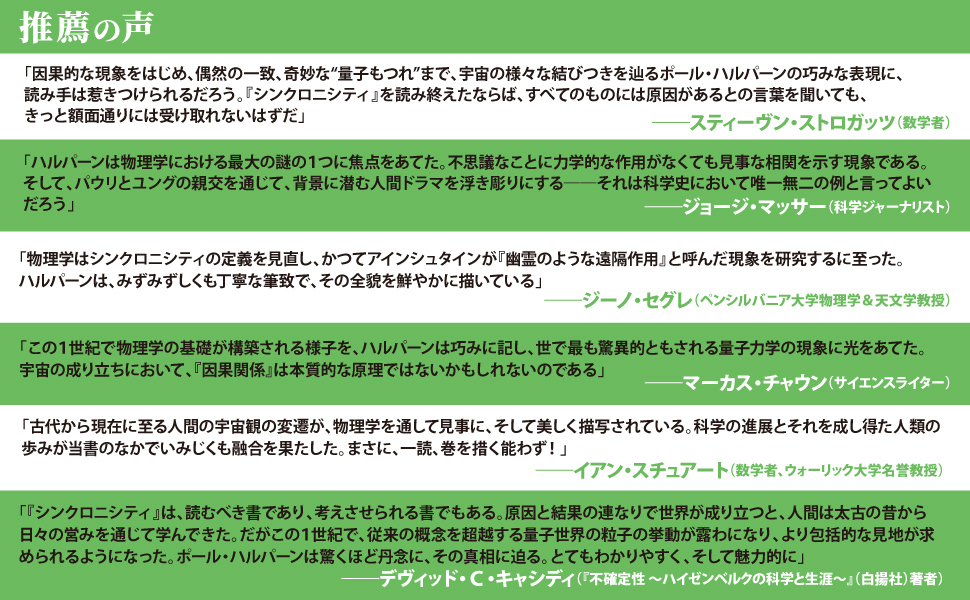
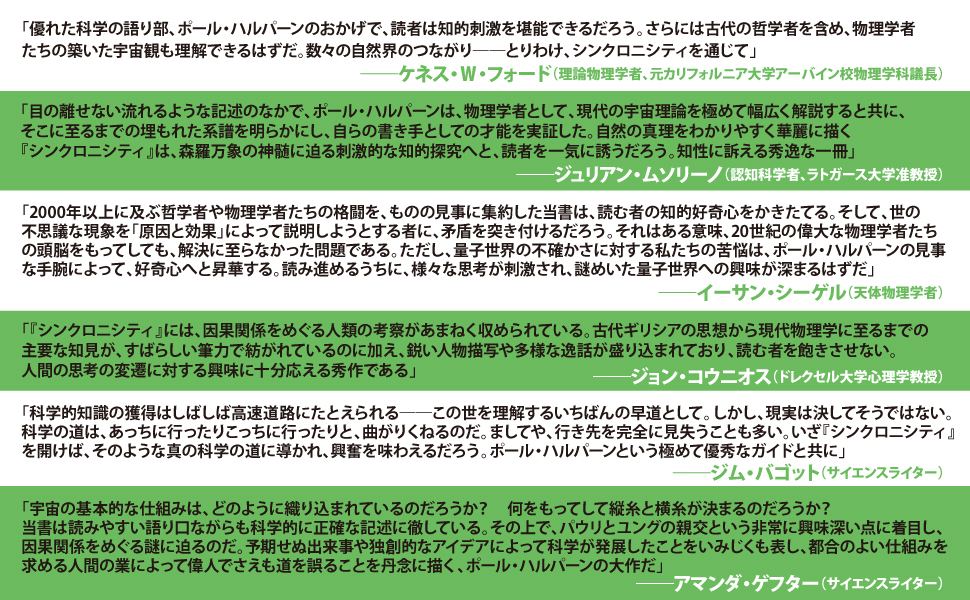 アマゾンより
アマゾンより
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「推薦の言葉」
「量子論の発展に寄せて」福岡伸一(生物学者)
序章 自然界のつながりを描く
第1章 天空へ挑む
~古代の人々が描いた天界像~
第2章 木星からの光が遅れる
第3章 輝きの源を辿る
~ニュートンとマクスウェルによる補完~
第4章 障壁と抜け道
~相対性理論と量子力学による革命~
第5章 不確定という世界
~現実主義からの脱却~
第6章 対称性の力~因果律を超えて~
第7章 シンクロニシティへの道
~ユングとパウリの対話~
第8章 ふぞろいの姿
~異を映す鏡のなかへ~
第9章 現実へ挑む
~量子もつれと格闘し、量子跳躍をてなずけ、
ワームホールに未来を見る~
終章 宇宙のもつれを繙く
「謝辞」「脚注」「参考文献」
本書の冒頭に置かれた「量子論の発展に寄せて」で、生物学者の福岡伸一氏は、「量子論は、普通の日常感覚が全く通用しない世界である。何か簡単なたとえ話に置き換えることもできない。どれも完全に現実離れしていて、あえて言えば、オカルトとスピリチュアルに近い、超常現象の世界なのだ」「量子論による世界解釈の展開はまさに今、大発展を遂げようとしている。量子論は、物理学だけでなく、生物学にも、化学にも、あるいは宇宙論にも画期的なパラダイム・シフトをもたらすことは間違いない」と述べています。
序章「自然界のつながりを描く」では、本書のテーマである「シンクロニシティ」について、「1930年にスイスの心理学者カール・ユングが唱えた言葉である。『非因果的連関の原理』という概念を表した言葉だ。アインシュタインとの夕食時に、就寝中の夢や日常における偶然の一致、文化の共通点に関する自らの考えや相対性理論などについて意見を交わしていた際に浮かんだという」と書かれています。しかし、実際にその概念が浸透するのは、古典力学の決定論(あらゆる出来事は、その出来事に先行する出来事のみによって決まる、とする哲学的な立場のこと)と一線を画す量子力学の先進的側面について、オーストリア生まれのスイスの物理学者ヴォルフガング・パウリと議論するようになってからでした。
続けて、著者は以下のように述べています。
「今にして思えば、科学における非因果的原理の必要性を見抜いたユングの洞察力は、非凡で先見性に長けている。だが残念なことに、意味のある偶然の一致、との言葉を鵜呑みにした姿勢は、彼の業績において大きな汚点と言ってよい。統計分析を用いることなく、いかがわしい相関も研究成果に含めたのだ。自らの直観を頼りに、相関の有無を判断したのである。時に、偽りの関連性をつくりあげる人間の心理を鑑みれば、自らの直観に頼るだけでは真の科学とは言えないだろう」
天文学や物理学の歴史を振り返った第1章、第2章に続いて、第3章「輝きの源を辿る~ニュートンとマクスウェルによる補完~」の「幻の終の棲み処」では、19世紀末の科学界では、自然界の振る舞いや人間の意志はすべて科学的に説明できると考えられたことが指摘されます。著者は、「いずれ非科学的な思想はあまねく淘汰され、予言や亡霊、悪霊、天啓などの介入する余地はなくなるとの見方が大勢を占めていた。いかなる自然現象も理論的に突き詰めれば、原因と結果の連鎖によって記述されるとの見地である」と述べています。
また、著者は「たとえ『奇跡』とされる出来事であっても、背景に原因が存在するか――自然物質に薬効があると後から判明するように、単に機序が解明されていないだけか――、もしくは希望的観測の生む単なる偶然の一致だとした。『因果関係をきちんと説明してくれ』との物理学者の要求に応えられなければ、『その考察は迷信に過ぎない』と一蹴されたのである。それでも超自然現象を信じる反対勢力は躍起になって古典力学の欠陥を探した。精神世界――死者の霊やテレパシー、奇跡的な偶然など――を排除するのではなく、超常現象も科学によって説明できるとの立場で味気ない機械的な世界像に命を吹き込もうとしたのである」と述べます。
中でも、錯視を専門とするツェルナーが心霊現象を許容した点は、皮肉と言えました。彼は、死者の思いを石板書記で表すと謳ったアメリカの奇術師ヘンリー・スレイドを支持したことでも知られていますが、著者は「ともあれ、精神世界の存在を示す貴重な『証拠』とされたのが、亡霊のような怪しい対象の写る写真だった。そのような『心霊写真』は、反射や二重露出といった撮影テクニックでつくることができるにもかかわらず、多くの著名人が、写真に写る亡霊のような対象を本物だと信じ込んでしまった。とりわけアーサー・コナン・ドイルは、心霊写真の信憑性の高さを強く主張した。また1896年にヴィルヘルム・レントゲンがエックス線を発見したことで――可視光線では見えない対象がエックス線で見られるようになり――、物質世界の裏に精神世界が潜むと信じる者たちは自らの考えに自信を深めた」と述べます。
自らの直観を頼りにして、科学的ではなく感覚的に精神世界の存在を訴える識者もいました。研究志向の強い学者は、精神世界の科学的根拠を見つけようと、光を伝える仮想の媒質である「エーテル」に注目したりしました。19世紀末の精神世界論者は、古典力学の抜け穴として、エーテルの他にも四次元の可能性を指摘して、自らの主張の正当性を訴えました。もし従来の縦、横、高さという三次元に加えて、未知なる空間を構成する4つ目の次元があるならば、テレパシーや超能力、降霊術などの超感覚的な作用も説明できるとの趣旨でした。その四次元に通ずる能力を訴求したスレイドを、当時、科学者として確たる地位を築いていたツェルナーも信じるようになりました。
その後、他界した親族や大切な人との対話がかなうと謳った奇術師スレイドは、富裕層を相手に詐欺を働いたとして、ロンドンで裁判にかけられました。著者は、「法廷において、彼は実際に降霊術を行い、『死者からのメッセージ』を石板に記した。だが疑いの目を向ける人たちによってトリック(たとえば石板を入れ替えるなどの行為)が暴かれ、被害者がいきり立つ結果となった。裁判の過程は世界中の新聞で報道され、心霊主義運動に理解を示す側と、一顧だに値しないと反対する側との対立が鮮明になった。そして、反対者の多くは、未知なる科学的作用を隠れた高次元などに求める考えを、一斉に否定するようになった。たとえば、1879年に生まれたアルベルト・アインシュタインは、因果律に従わない相互作用に対し、一生涯、懐疑的な姿勢を貫いた」と述べています。
アインシュタインはエーテル理論を不必要な仮説とし、エーテルの存在も信じませんでした。当該仮説を棄却して、物体の運動と空間に関して独自の理論を構築し、物理学の常識を覆したのです。20世紀に突入したばかりの時代、彼に比肩する驚異的な発想の持ち主はいなかったとして、著者は「アインシュタインの登場は、物理学にとって幸運だった。彼が純粋な目で自然の摂理を探究し、偉大な特殊相対性理論を築いたことで、エーテルは過去の産物となり、四次元が時間の尺度として日の目を見るのである」と述べるのでした。
第4章「障壁と抜け道~相対性理論と量子力学による革命~」の「光が持つ2つの顔」では、古代から19世紀末にかけて、物理学は明確さと現実主義を色濃くしながら進展したことが指摘されます。古代ギリシアから時を経て、ニュートンの古典力学が生まれ、マクスウェルの電磁気学によって理論が補完され、さらには熱力学の法則が誕生したと振り返り、著者は「要は現実こそがすべて、との立場に移行してきたのである。不可解でおぼろげな事象については、測定が難しいだけで物理的現象に変わりないとみなされるか、もしくは長く神学者に委ねてきた『死後の魂の行方』や『時間が動き出す前の世界』といった超越論の問題として片付けられるようになった」と述べています。
著者は、「波と粒子という光の二面性(光子の「波束」という形で、まるで2つの特徴を交互に表すかのように空中を進む光の性質)を証明したアインシュタインでさえも、自らの証明に端を発して、当時大学教育で教えられていた絶対的な物理法則が数十年のうちに瓦解するとは想像していなかっただろう。のちに、哲学者トーマス・クーンが『パラダイムシフト』と名付ける急激な方向転換が、やがて物理学に到来するのである。科学者の直観が正しい方向を示すとは限らない、と言わんばかりに」と述べます。
第7章「シンクロニシティへの道~ユングとパウリの対話」の章扉には、心理学者カール・ユングが1953年2月25日にカール・シーリグに宛てた手紙が陰陽されていますが、そこには「アインシュタイン博士を何度か夕食に招いたことがありました。……だいぶ昔のことで、特殊相対性理論が発表される頃の話です。……そのなかで非常に感銘を受けたのは、研究者としてのシンプルで端的な考察です。博士の考え方は、その後の私の研究活動に大きな影響を与えました。時間や空間の相対性、また超自然現象の条件について考えるようになったのも、博士との交流がきっかけです。そして30年以上経った今、パウリ博士との親交に結びつき、超自然現象のシンクロニシティの理論を著すに至ったのです」と書かれています。
現代物理学に関心を持ち、普段からその意義を認めるユングにとって、パウリは精神と物質の関係性について意見交換する格好の相手でした。対話を通じて、科学的考察を深めることができたからです。自然界における対称性の役割だけではなく、いわゆる超常現象と呼ばれる奇妙な出来事にも話題は及んだことを紹介しながらも。著者は「ただしパウリは、自らの超常現象への関心を他の物理学者に話そうとはしなかった(同じく超常現象に興味を持つ友人、パスクアル・ヨルダンだけは別だった)。一貫して自然界に客観性を求めるアインシュタインの存在が、その消極的な姿勢に拍車をかけた。当然、観測の影響を考慮すべきだとアインシュタインに助言することもなかった。そして、パウリの推察通り、アインシュタインは生涯、量子力学の表す奇妙な世界を自然の真の姿として認めなかったのである」と述べています。
「精神の偽らざる姿」では、ユングの活躍がやがてジークムント・フロイトの目に留まったことが紹介されます。ユングはフロイトに師事するようになり、盛り上がりを見せる精神分析運動の一翼を担いました。2人が初めて出会ったのは1907年、ウィーンでのことでした。その後6年間、お互いに連携しながら研究を進めるうち、2人揃って無意識の中に重要性を見出しました。1910年、フロイトが国際精神分析協会を創設した際には、発足を支援したユングが初代会長に就任しました。しかし1913年、精神分析の反対派に対するフロイトの狭量に耐えかね、ユングはきっぱりと袂を分かちます。その後、幼少期の性的傾向ではなく、「集合的無意識」に着目して、無意識の動機付けを説明したのでした。
集合的無意識とは、集団に共通する意識のことです。のちにユングは、「元型」と呼びました。源泉は1つですが、1人ひとりの人間によって個性化します。元型の例としては、童話や民族伝承、道徳的禁忌、象徴的表現、宗教儀式、精神的理想などがあげられるとして、著者は「一般に、解消されなかった幼少期の悩みよりも、元型のほうが成人後の人格にはるかに大きく影響するとユングは考えたのだ。彼は自らの主張を裏付けるため、超自然主義にまつわる文献の研究に乗り出す。錬金術やグノーシス主義、新プラトン主義の各教派、仏教、ヒンズー教などの書物を精読し、神話学の第一人者となった。そして、様々な超自然主義の間に、超越的真理の探究や神との一体化への渇望といった共通点を見出した。はたしてユングは、個人の感情と集合的無意識に潜む関係性を解明すべく、ウィーンを中心とする精神分析運動から離れ、分析心理学という新たな深層心理学の学派をスイスに立ち上げた」と説明します。
フロイトとの決別は、ユングにとって精神的不調の始まりでした。1903年に結婚した妻のエンマ・ユング・ラウシェンバッハと婚姻関係を続けながら、ユングは元患者で助手のアントニア(トニー)・ヴォルフと関係を持つようになりました。ヴォルフとのいわば愛人関係は40年続きました。追い討ちをかけるように、就寝中、強烈な夢を見るようになったことを紹介し、著者は「そのためユングは、無意識に対する探求心をより強くした。当時の内面の葛藤や幻想を綴ったものは2009年に『赤の書』として刊行された。数々の絵とあわせ、ユング自らカリグラフィー(訳注:字を美しく見せる書法)を用いて、鮮やかな筆致で綴った想像力豊かな日記が、死後ほぼ半世紀を経て初めて世に出たのである」と説明します。
ユングにはフロイトと別れる数年前、当時チューリッヒに住んでいたアインシ度にわたって対話する貴重な機会がありました。著者は、「のちに心理学と物理学の両面から精神と肉体を統一的に表した彼は、アインシュタインとの時間がその主な動機になったと話している。歴史に残る2人の共演は、アインシュタインがまだ科学者となって日が浅い、特殊相対性理論の加速度系への拡張を目指していた頃の話だった」と説明しています。
ユングによれば、会食の中でアインシュタインは、時空という相対的な概念を一同に説明したといいます。対してユングは、数式に苦手意識を持ちながらも、なんとか概要を把握しようと耳を傾けたそうです。しかし、その後、アインシュタインがチューリッヒを去り、プラハ、ベルンと居を移すと、2人の交流はすっかり途絶えてしまいました。著者は、「この意見交換を機に、ユングは現代物理学の表す世界に惹かれるようになった。そして量子もつれの概念が生まれる何年も前に、非局所的な作用について探究し始めた。局所性を前提とするアインシュタインとは対照的に、客観的現実の知覚に伴う非局所的なつながりに陶酔したのである」と述べます。
「シンクロニシティの登場」では、ユングは錬金術やオカルトに関する文献の中に、様々な元型や像の存在を認めたことが紹介されます。それらは彼にとって普遍性を意味していました。各個人の精神は、夢や幻想、反芻思考の中で、集合的無意識と通じることができます。そして集合的無意識は、状況に応じて知見や希望、恐怖を各個人にもたらします。著者は、「つまり『自己』の元型によって、夢の中の対象に投影されるのが、人間1人ひとりの精神なのだ。また、ユングによれば、『影』も元型の1つで、精神の闇を表す。善悪にかかわらず、人間の個性として表出するが、普段の生活において認知されることはなく、夢の描写の中で、非常に認識しづらい形で現れるのみだ」と述べています。
ユングは1923年、『易経』のドイツ語への翻訳で知られる中国研究家リヒアルト・ヴィルヘルムを、チューリッヒの心理学クラブに講演者として招きました。ヴィルヘルムによる翻訳書が擦りきれるほど、ユングは64卦による易占を繰り返し検証しました。何度もノコギリソウを集めては、符号の並びの意味するところを確かめ、その結果と自らの見た夢、反芻思考の内容、実際の出来事を照らし合わせました。著者は、「すると次第に、意味のある偶然の一致が見つかることが多くなった。だが、それは必ずしも、ノコギリソウによる占いが通常考えられるよりも高い頻度で的中するという意味ではなかった。単にユングが、的中ありきで見ていたのである。偶然の一致を意識して物事を捉えれば、何かしら見つかるものだ。それは、符合に敏感になった人間の脳のなせる業である」と述べます。
ユングは自伝の中で、「その年の夏の休暇中、私は常に頭を悩ませていた。『易経』の示す答えに、意味はあるのだろうか? もしあるならば、占術の表す事象と現実の出来事はどのように結びつくのだろうか? 私はこれまで驚異ともいえる偶然に幾度となく遭遇した。それは、非因果的な並行性を表すように思えるのである(のちに私はその現象をシンクロニシティと名付けた)」と書いています。著者は、「ユングは実際に、一部の患者を対象に検証に臨んだ。すると『易経』の示す予見が診療に役立つことがわかった」と述べるのでした。
「ノーベル賞」では、無事にチューリッヒに戻ったパウリが、1946年の終わり頃、後期ルネサンスの2人の天文学者の宇宙論に着目したことが紹介されます。ロバート・フラッドとヨハネス・ケプラーです。フラッドとケプラーの太陽系モデルは互いに相容れない内容であると指摘し、著者は「地球と太陽の2つの天体が――加えて神も――、宇宙の中心だと唱えたのがフラッドである。一方、ケプラーは、著書『宇宙の神秘』の中で、宇宙をキリスト教の三位一体説と結びつけ、数や図形をもとに宇宙像を描いた。だが、いずれも神秘主義に立脚しており、パウリはその点に惹かれたのである。両者の宇宙の描像を、ユングのように分析しようと考えたのだ」と述べています。
「非因果的連関の原理」では、パウリの後押しを受けて「シンクロニシティの一般化」という難題に挑んだユングは、最終的に精神的要素を排除した上で、非因果的な作用としてシンクロニシティを表現したことが紹介されます。ユングは純粋に物理的な相互作用として記述したとして、著者は「明記されてはいないが、『量子もつれ』の概念ももちろん含まれていた。皮肉なことに、ユングの一般化したシンクロニシティの定義は、ラインの実験結果が示すシンクロニシティとは一致を見なかったが、ユングとパウリの2人は双方とも事実として受け入れた。そして、非因果的連関としてのシンクロニシティの横断的な定義は物理学において、因果律の連鎖とは異なる対称性などの新たな機序に、宇宙の真理を求める潮流を生んだ」と述べます。
ユングは、自身の夢の内容を記したパウリからの手紙を読み、大いに関心を持ちました。著者は、「パウリの夢の内容については、精神と肉体のように対をなす対象同士の融合という解釈を与えた。また、弱い相互作用におけるパリティ対称性の破れに関しては、対称性を表出するために2者の間を取り持つ媒介者――ユングは『第3のもの』と呼んだ――に起因すると説明した。たとえば、第3のものが肉体よりも精神をわずかにひいきしたばかりに両者の対称性が崩れる、といった具合である。ユングの返書にはその他、新たな関心対象であるUFO(未確認飛行物体)について詳しく書かれていた。現実の物体(宇宙からの飛翔体)か、独自の元型を持つ新たな神話だろうと彼は結論付けていた」と述べます。
ユングの不明確な筋立てについて、パウリはボーア宛ての書簡で「ユングの思想は、フロイトに比べて幅広い領域を対象としますが、その分、明確さに欠けます。最も不満を覚える点は、『精神』という概念が、明確な定義のないまま曖昧に用いられていることです。論理的にも矛盾が認められるのです」と嘆いています。またパウリは、超能力を研究するラインの実験手法にも疑問を抱き始めていました。パウリとユングの2人の距離が離れたのは、ユングのUFOに対する強い関心も一因でした。パウリもUFOに興味を示しましたが、ユングが期待するほど、時間をかけて研究することはなかったのです。
終章「宇宙のもつれを繙く」では、かつて人類の描いた天空と地上とのつながりは、極めて直接的だったことが指摘されます。アンドロメダ銀河(M31)を中心とするアンドロメダ座(実際にはアンドロメダ座の恒星に比べて、アンドロメダ銀河は極めて遠方に存在する)に、鎖で岩礁につながれたエチオピア王女の姿を重ねたギリシア神話のように。著者は、「古典科学は、因果律を採用することで大きな進歩を遂げた――隣の牌を次々と倒していくドのように、作用が直接伝わることで自然現象が起こるという考えを土台にした。しかし、量子力学は語るのである。決定論的な因果律は世の理にふさわしいように見えるが、すべての自然現象を網羅するわけではない、と」と述べます。
「パウリとユングが残したもの」では、一連の物理学の潮流において、ユングの果たした役割は決して小さくないことが指摘されます。たしかに、彼の提唱した元型や集合的無意識といった概念は、独創的であり、また魅力的でもありますが、科学的に実証されているわけではないとして、著者は「夢に現れる象形が、代々受け継がれてきた原始的な型である証拠はどこにもないのである。よしんば東洋哲学や錬金術、神秘学を学んだことがあるならば、曼荼羅や錬金術記号などの象形が夢に出てきても不思議はない。夢に現れなくとも、日常で目にする記号から、そのような結びつきを連想するとも考えられる。漫画書籍の熱心な収集家が、ヒーローや悪役の夢を見るのと同じである。しかしながら、ユングは夢分析を通じて、自然の摂理に対するパウリの優れた洞察力に触れた。パウリと繰り返し相対したことで、自らの物理学的知識をより豊かにすると同時に、パウリの発想にも示唆を与えたのである」と述べます。
「セレンディピティvs.科学」では、「シンクロニシティ」という言葉が広く世に浸透したのは、1970年代であることが紹介されます。超心理学の枠組みの中でユングの学説を論じた、アーサー・ケストラーによる『偶然の本質』などの著作がきっかけとなったのです。著者は、「ケストラーは同書のなかで、非局所的な量子現象をとりあげ、超感覚的知覚(ESP)や超常現象の科学的根拠を示そうとした。だが、真の科学と非科学の線引きに関して厳密性に欠けるとの批判を浴びた」と述べています。
『偶然の本質』の中でケストラーが提唱したのは「フィルター理論」でした。テレパシーが実現し得ると想定した上で、他人の思考は通常、脳のフィルターでろ過され、己の思考のみが認知されるという考えです。あくまで推測の域を出ず、決して神経科学的に実証されているわけではないとしながらも、著者は「ただし、記憶に値しない己と無関係な情報が事前に遮断されるため、意味のある偶然が引き立つと逆に捉えれば、多少は理にかなうだろう。2人の同級生が異なる色のドレスを選んでも、同じ色のドレスを選んでも、もともとは等しく記憶されるべき情報だというわけだ。もし、頻繁に旅行する人であれば、地元と離れた空港や駅などの待合室で隣人や友人にばったり出くわした経験があるだろう。そのような予想外の場面は、待合室の席に座りながら見知らぬ人を眺める場面よりも、より深く記憶に残るはずだ。つまり、関連のない情報はフィルターによって排除されるため、まったく偶然の遭遇が際立つというわけである」と述べます。
シンクロニシティにとって最高の檜舞台は、間違いなくロックバンドのポリスのアルバムだろうとして、著者は「哲学的命題を音楽に反映させることの多かったポリスは1983年、アルバム『シンクロニシティ』をリリースした。週間ヒットチャートのトップを記録した同アルバムには、共時性の概念を賛美する『シンクロニシティI』と、ふとした瞬間に表出する密かな事象を未確認動物のネッシーになぞらえたポップな『シンクロニシティⅡ』が収録されている」と紹介しています。
ポリスのボーカルを務め楽曲制作も手掛けるスティングことゴードン・サムナーは、今でもラジオなどで頻繁に流れる「シンクロニシティⅡ」の制作背景について、「郊外に生きる人間の疎外感を彼の地の象徴的な出来事に結びつけて表現しようとしたのさ。早い話、日常における感傷的な場面を、ネス湖から現れるモンスターに投影したってこと。ユングのいう意味のある偶然の一致にストーリー性を持たせてみたんだけど、所詮はロックよ!」と述懐しています。ロックスターとして名を成す前に教師を務めていたほど博学なサムナーは、ケストラーの著作でユングの考えを知ったといいます。日本では、女性アイドルグループの乃木坂46の「シンクロニシティ」(2018年)が大ヒットしました。この曲によって、「シンクロニシティ」という言葉を知った日本人も多いでしょう。
「慎重に非因果性を受け入れる」では、すべての偶然の一致が真の非因果的相関というわけではないことが指摘されます。だからといって対極へと舵をきり、厳格な決定論と因果性だけに基づいて、すべての科学的現象を説明しようとする必要はないだろうとして、著者は「非局所的かつ非因果的現象の探究への道標は、ベルの不等式や、量子測定理論の現代的手法によって、すでに示されている。また、ワームホールといった一般相対性理論の表す時空の複雑な結びつきを考えれば、原因が結果に先立つとの概念が、量子系以外においても破れ得る可能性に目を向けなければならない」と述べます。
物理学者は現在、着実に、そして慎重に、因果性と非因果性の両者を許容する普遍的原理を築こうと力を注いでいるとして、著者は「一部は量子もつれの原理に従って一般相対性理論の再構築を目指し、また一部は一般相対性理論の時空連続体に基づいて量子もつれの記述に挑んでいる。アインシュタインやハイゼンベルク、パウリたちの統一的理論への情熱は、いつしか結実する日が来るだろう――おそらく、21世紀の科学が想像もできないような形で」と述べるのでした。本書は物理学を中心とした自然科学の歴史を追いながら、「シンクロニシティ」の本質や意味について考察する興味深い読み物でした。