- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2270 オカルト・陰謀 『鏡花と怪異』 田中貴子著(平凡社)
2023.09.23
彼岸の中日に、『鏡花と怪異』田中貴子著(平凡社)を紹介します。泉鏡花の文学における怪異性に焦点を当てた文学評論で、2006年5月に刊行されています。著者は、1960年京都生。奈良女子大学文学部、広島大学大学院文学研究科修了。博士(日本文学)。日本中世文学専攻。甲南大学文学部教授。
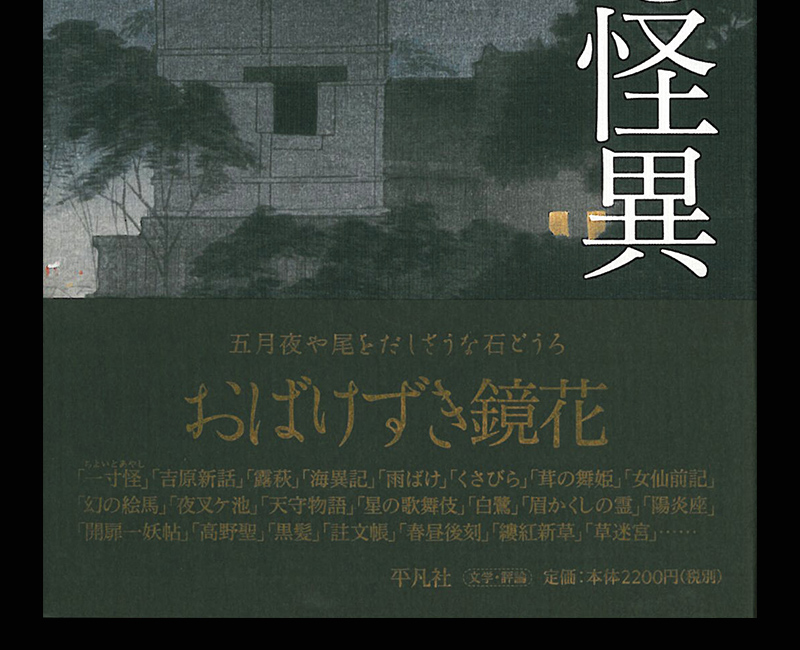
本書の帯
本書の帯には、「五月夜や尾をだしさうな石どうろ」「おばけずき鏡花」として、「一寸怪」「吉原新話」「露萩」「海異記」「雨ばけ」「茸の舞姫」「女仙前記」「幻の絵馬」「夜叉ヶ池」「天守物語」「星の歌舞伎」「白鷺」「眉かくしの霊」「陽炎座」「開扉――妖帖」「高野聖」「黒髪」「註文帳」「春昼後刻」「縷紅新草」「草迷宮」……と、鏡花の作品名が並びます。
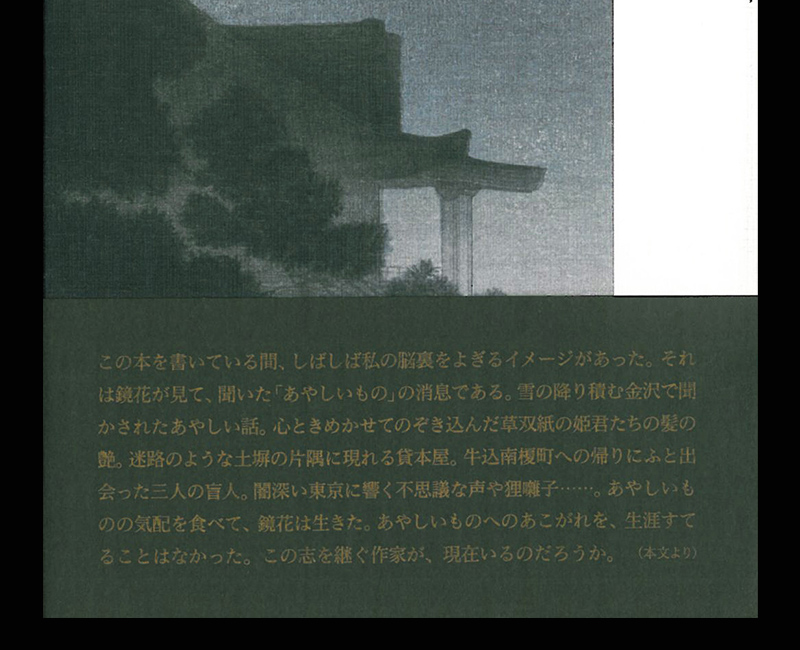
本書の帯の裏
帯の裏には、「この本を書いている間、しばしば私の脳裏をよぎるイメージがあった。それは鏡花が見て、聞いた『あやしいもの』の消息である。雪の降り積む金沢で聞かされたあやしい話。心ときめかせてのぞき込んだ草双紙の姫君たちの髪の艶。迷路のような土塀の片隅に現れる貸本屋。牛込南榎町への帰りにふと出会った三人の盲人。闇深い東京に響く不思議な声や狸囃子……。あやしいものの気配を食べて、鏡花は生きた。あやしいものへのあこがれを、生涯すてることはなかった。この志を継ぐ作家が、現在いるのだろうか。(本文より)」とあります。
本書の「目次」は、以下の通りです。
序章 なぜ今、鏡花と怪異を語るのか
第一章 「おばけずき」鏡花
第二章 百物語の黄昏
――強化の百物語二つ
第三章 「海異記」
――実話から怪異小説へ
第四章 茸の怪異
第五章 幻のユートピア
――女たちの異界へ
第六章 モダン東京に怪異あらはる
終章 鏡花にとって怪異とは何だったのか
「あとがき」
「参考文献」
第一章「『おばけずき』鏡花」では、鏡花の描く怪異にはほとんど因果因縁を持ったものはないことが指摘されます。これは、鏡花が親しんでいた江戸時代の草双紙のお化けとは少し異なっているとして、著者は「江戸時代のお化けはほとんどが恨みを飲んで死んでいった人の怨霊として現れる。もちろん、黄表紙には因果因縁のない今でいう『妖怪』の類が現れているのだが、これは江戸時代に『幽霊』と『妖怪』との区別がつけられ始めたせいだろう。鏡花が問題にしているのは、『幽霊』の方である」と述べています。
著者によれば、鏡花は江戸文学の「理由のある怪談」より、秋成のような「理由のない怪談」を推しているといいます。鏡花は「鬼神力」を「友」といいながらも、鏡花はやはり怪異を恐ろしいものとして受け止めたかったようです。また、「『妖怪』という用語は適正か」では、鏡花は「幽霊」と「妖怪」とを区別して使っています。著者は、「私も今まで、『怪異』とか『お化け』といった言葉を定義せずに使ってきた」として、「『妖怪』と『怪異』はかつて同じ意味で使われてきたが、「妖怪」が「ばけもの」という形あるものを称する言葉になったのは江戸時代から、ということになる」と述べます。
それ以前は、「あやしいもの」を示す言葉として「ばけもの」、「へんげ」、「あやかし」などが使われていましたが、それが江戸時代に黄表紙というメディアによって「妖怪」にほぼ統一されました。しかし、民俗社会では「ばけもの」やその幼児語である「お化け」も並行して用いられており、そうした錯綜した状況のまま近代に突入してしまった結果、研究者によって再度「妖怪」という漢語の見直しが始まったといいます。
第二章「百物語の黄昏」の「自然主義文学の波を受けて」では、著者は「なぜ鏡花は、百物語が形骸化してしまった明治44年にあって、このような『化け物の復権』を叫ばなければならなかったのだろうか。近代文学史の常識を鑑みれば、一つの解釈はすぐに思いつくだろう。すなわち、明治40年ころから隆盛をきわめた自然主義文学に対する鏡花なりの回答、という解釈である。鏡花の文学は写実を旨とする自然主義文学者から大きな反発を受けており、鏡花が明治39年に逗子に転居したのも、生来の神経症の悪化に加えて、自然主義文学からの圧力を避けるためだったといわれている」と述べています。
鏡花は「私がお化を書く事に就いては、諸所から大分非難がある様だ、けれどもこれには別に大した理由は無い。只私の感情だ。之に就いては在来風葉君などからも、度々助言を辱うしたのであるが、私の此の感情を止める事が出来ない」と書いていますが、これは、真っ向からなされた「おばけずき」の表明であると言えるでしょう。
「柳田国男との交流」では、鏡花の活動の後ろ盾となった重要人物として、柳田国男があげられています。いわずと知れた、民俗学の祖というべき学者です。鏡花と柳田との関係については従来よく取り沙汰されており、二人は年齢も近く、深い親交を結んでいました。鏡花臨終のとき、真っ先に駆けつけた一人が柳田であったこともよく知られています。明治43年6月、柳田の『遠野物語』が刊行されるや、すぐさま「遠野の奇聞」という一文で反応を示したのが鏡花でした。
「大正十三年の『怪談会』では、鏡花と同時代に同じく百物語を意識した怪異小説を書きながら鏡花とまったく違った方向性を示した作家として岡本綺堂があげられます。著者は、「岡本綺堂は、鏡花と比べると文学史上の位置づけが曖味な作家である。近年、文庫版で代表作が復刊されたことがきっかけで現代人にも親しい存在となっているものの、定本とすべき全集はなく、作品の初出年代も不明なものが多い。かろうじて昭和44年に『岡本綺堂読物選集』全8巻が刊行されているが、表記は現代仮名遣い、新字体に変えられており、あくまで『読物』として享受された形跡がうかがえる」と書いています。
戦時中、兵士の慰問袋に綺堂の小説がよく入れられていたといわれるように、綺堂は「流行作家」としての扱いを受けていたのでした。綺堂の怪異小説の代表作といえば、大正13年から14年にかけて『苦楽』に連載された『青蛙堂鬼談』でしょう。著者は、「大正15年に12篇の小説集としてまとめられたこの作品は、東雅夫が指摘するように、明らかに百物語の形式を意識して書かれたものである」と述べます。
綺堂が因果応報の理によらない怪談を目指していた背景には、関東大震災の体験があったのではないかと思われるとして、著者は「もちろん、震災は鏡花の身の上にもふりかかっていた。その日、鏡花が住む下六番町の家は倒壊をまぬがれ、鏡花夫妻と女中は近くの外堀公園に避難した。お昼時の地震だったので、火を使っていた家庭が多く、あちこちで火事が発生していた。鏡花は女中が持ち出した葡萄酒を気つけに飲み、二日二晩露宿したという(巖谷大四『人間 泉鏡花』)。鏡花は幸いなことに三日目に自宅に戻り、余震にふるえながら「十六夜」を執筆している」と書いています。
反対に不幸だったのは綺堂でした。元園町の自宅から着の身着のままでころがり出たものの、家は全焼。万巻の蔵書も、35冊の日記帳もすべて灰燼に帰しました。毎日の日記を欠かさなかった綺堂が日記を再開するのは、9月も23日になってからでした。著者は、「東京市民を恐怖のどん底に突き落とした大震災は、こうした作家たちに大きな精神的ダメージを与えたと見られる。それは、江戸から続いてきた東京の『昔』の瓦解であり、昭和というわけのわからない新しい時代の到来を予期するものだったからである」と述べています。
鏡花が江戸時代の草双紙を愛読しながらも、因果因縁話の踏襲をしようとはしなかったことは残された作品からも明らかです。池田彌三郎の『日本の幽霊』によれば、後年、訪ねてきた折口信夫に対して鏡花は「私は長い間お化けを書いて来たが、恨みを持たぬお化け、怨霊でないお化けを書こうとして来たが、それが書けなかった」と語ったといいます。鏡花の怪異小説を俯瞰すると、因果因縁を持ったお化けの数をあげることは難しいといいます。
著者は「すぐに思いつくのは『註文帳』の遊女の幽霊くらいであるが、これとて江戸の怪談のような因果因縁を主題としたものとはなっていない」と述べています。ところが、鏡花が晩年までこだわった「理由のない怪談」を、綺堂は易々と実現しているように思われます。そして、鏡花にはなかった「科学的解釈」を加えようともしています。著者は、「これは、綺堂が好んだシャーロック・ホームズ・シリーズの影響であろう」と推測しています。
第五章「幻のユートピア――女たちの異界へ」の「ユートピアを求めて」では、鏡花が好んだ異界の住人は、「女仙」のほか「姫(媛)神」とも呼ばれ、そういった超越的存在に研究者は色々な名前をつけていますが、いずれもほぼ同じものを指すと考えてよいといいます。「女たちの前世の物語」では、「高野聖」、「夜叉ヶ池」、そして「天守物語」の3作品を超越的女性=姫神の前世物語と見る著者は、「いずれもが、俗世において男性主導型共同体から何らかの侵襲を受け、それへの恨みによって姫神へと生まれ変わった女性たちであることが明らかになったと思われる。彼女たちのような過去を持つ姫神のバリエーションが、『前物語』を持つ湯湧谷の麗人や根津の天守様であることは間違いない」と述べています。
かつて男社会から手痛い仕打ちを受けた姫神たちだからこそ、現世で苦しむ女性たちを救済することができる力を持ち得たのであると指摘し、著者は「姫神たちの異界=ユートピア。そこは現世の苦から解放された女性たちと、『真の愛』に生きる恋人たちだけが住む『世間の外』、理想の時空間である。『ここではないどこか』へのあこがれを持ち続ける人々にとって、鏡花が作り上げたユートピアは本を閉じてもなお、その心を揺さぶり続けるだろう」と述べるのでした。
第六章「モダン東京に怪異あらはる」の「都市の演者と観客」では、都市の一隅から聞こえてくる音、それは異界が誘う魔の音であるとして、著者は「それを聞き分け、一幕の怪異劇を『見聞き』し、そしてまた再び異界の扉の鍵を閉める松崎。神楽の狂言方という大正時代にしては時代遅れの仕事につく彼は、その身分的な『ずれ』によって江戸的トポスと大東京市の都市空間をまたぐことのできる特性を持つ。『陽炎座』は、本所という江戸の伝承を残す土地の上に、子ども芝居とそれを包摂するもう一つの芝居(品子主演の人間劇場とでもいうべきもの)が展開されるという、二重三重にも重なり合った時空間の構造を持つ、巧妙にしくまれた物語なのだということができる」
終章「鏡花にとって怪異とは何だったのか」の「美しい幽霊たち」では、鏡花が描き続けた美しい幽霊について批判を加えたのが大佛次郎だったと指摘し、著者は「大佛は岡本綺堂の作品に『ほんとうの日本らしい文学は思いがけなく、ここいらに、まだ青い根を留めているのである』と賞賛を惜しまない(『岡本綺堂読物選集』第四巻序文)。そこで綺堂に対比させられるのが鏡花である」と述べます。大佛次郎は、「古い東京の文学というものを探したら、金沢から出て来た泉鏡花などの、生きている内から幽霊か妖精のような美しい芸者ではなく、綺堂が描いた町の遊芸師匠や、お旗本の生き残りや、裏町住いの職人に、体温の通った純粋な姿が見つかるのだと思う」と書いています。著者によれば、「金沢から出て来た」というのは田舎者といっていることと同じだとしながらも、「しかし、芝生まれの東京人である綺堂と比べられれば、鏡花の立つ瀬がなかろう。大佛の批判は、鏡花が確信犯的に美しい幽霊を書いていることを無視している点に問題がある」と述べるのでした。
「『稲生物怪録』と『稲亭物怪』のあいだ」では、心霊や妖怪の研究者であった幕末の国学者・平田篤胤が取り上げられ、著者は「鏡花と篤胤とが結びつけられたのは、何よりも折口信夫の文章によるところが大きい。折口には『鏡花との一夕』と『平田国学の伝統』という二つのエッセイがあり、どちらにも鏡花が出てくることで有名である。ここに鏡花と『稲生物怪録』との関係を示す部分が見えることで、今までの論者は鏡花が読んだのは平田本に違いないという先入観を持ったのだろう」と述べています。
「鏡花の怪異摂取」では、「草迷宮」が取り上げられます。「草迷宮」における鏡花の怪異の方法とは、不要なグロテスクさや珍奇な造形のお化けを避け、手毬唄によって幻想をつむいでゆくという鏡花独自の美意識にもとづいたものだったと考えられるとして、著者は「最後にお化けの首領が出てきて終わるのではなく、明の母の知己だという『美人』を登場させ、手毬をつかせるというのは、典拠としての『稲生物怪録』の世界から完全に離脱している。美しい怪異をめざすという鏡花のまなざしは、ここでも貫かれているといってよいだろう」と述べます。
「さいごに」では、鏡花の随筆や談話を読むと、いろいろな面で実に好みの強い人であったことが知れるとして、著者は「それは単なる好き嫌いではなく、作品世界を構築する力学となるようなものだったと思われる。彼は好みを貫くことによって、独自の世界を作り上げたのである。その『好み』の一つが怪異への志向であり、近代作家の中でこれほどまでに怪異を好んだ人はないといってもよかろう。鏡花の『お化け話』はすべてが成功しているとはいえないだろうが、周りの文学史的環境にも左右されず、ひたすら怪異を書き続けたことには充分意義を認めてよいと思う。近代文学という激しい運動の中で、鏡花の姿勢はほとんど変わることがなかった。それがいわゆる『近代人』として適当なのかどうかは別として(鏡花における「近代」という問題も閑却はできないが)、まれに見る素質と信念の人だったと私は思う」と述べるのでした。
「あとがき」では、著者が鏡花の全集を入手したのは、大学院に進学してからのことだと紹介され、「そのころ、荒俣宏氏の『帝都物語』が映画化されたのだが、そこに坂東玉三郎さん扮する鏡花さんの姿があったのである。似ていた。写真で見ていた鏡花さんの若いころに、玉三郎さんはそっくりだったのだ。玉三郎さんのファンであった私は、『店じまいにつき九割引』の広告を出していた古本屋に駆け込んで鏡花全集を手に入れた。それが、鏡花さんに本格的に親しむきっかけとなったのである」と述べています。映画「帝都物語」はわたしの大好きな映画で、玉三郎の鏡花は確かに似ており、はまり役であると思いました。
そして「妖怪学」が今後学問として立ちゆくかどうかは未知数ですが、もし「学」を立ち上げようとするのなら、基本的な事項についての了解は持っていなくてはなるまいとして、著者は「怪異・妖怪・怪談ブームはたしかに喜ぶべきことだろうが、たとえば、『新耳袋』という怪談集などを見ていると、おもしろければそれでいい、というような安易な態度を感じてしまう。もし、『新耳袋』に怪談を採取した年月日やインフォーマントの文化背景を示しておいてくれたなら、将来何かの役に立つものを、と思えてならない」と述べるのでした。本書は、鏡花文学を愛してやまないわたしにとって、「マニア垂唾の一冊」と呼べるような名著でした。