- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2273 人生・仕事 『映画を早送りで観る人たち』 稲田豊史著(光文社新書)
2023.10.11
11月11日、東京から北九州に戻りました。
今年もすでに120本の映画を映画館で観たわたしですが、『映画を早送りで観る人たち』稲田豊史著(光文社新書)を紹介します。「ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」というサブタイトルがついています。著者は、1974年、愛知県生まれ。ライター、コラムニスト、 編集者。横浜国立大学経済学部卒業後、映画配給会社のギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ)に入社。その後、キネマ旬報社でDVD業界誌の編集長、書籍編集者を経て、2013年に独立。著書に『セーラームーン世代の社会論』(すばる舎リンケージ)、『ドラがたりのび太系男子と藤子・F・不二雄の時代 』(PLANETS)、『ぼくたちの離婚』(角川新書)、『「こち亀」社会論 超一級の文化史料を読み解く』(イースト・プレス)、『オトメゴコロスタディーズ フィクションから学ぶ現代女子事情』(サイゾー)などがあります。

本書の帯
本書の帯には「現代のコンテンツ受容の実態を切り取った話題作!!」「2023年新書大賞 第2位(気持ち的には1位!)」「三省堂 辞書を編む人が選ぶ『今年の新語2022』タイパという言葉が大賞」「5万部突破!」と書かれています。
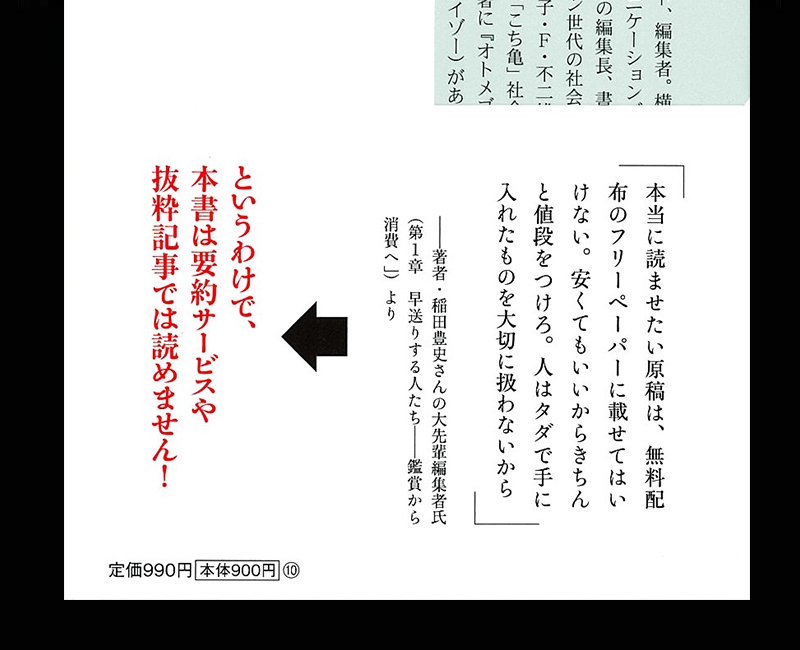
本書の帯の裏
帯の裏には、「『本当に読ませたい原稿は、無料配布のフリーペーパーに載せてはいけない。安くてもいいからきちんと値段をつけろ。人はタダで手に入れたものを大切に扱わないから』――著者・稲田豊史さんの大先輩編集者氏(第1章「早送りする人たち――鑑賞から消費へ」)より → というわけで、本書は要約サービスや抜粋記事では読めません!」と書かれています。
カバー前そでには、以下のように書かれています。
「なぜ映画や映像を早送り再生しながら観る人がいるのか――。なんのために? それで作品を味わったといえるのか? 著者の大きな違和感と疑問から始まった取材は、やがてそうせざるを得ない切実さがこの社会を覆っているという事実に突き当たる。一体何がそうした視聴スタイルを生んだのか? いま映像や出版コンテンツはどのように受容されているのか? あまりに巨大すぎる消費社会の実態をあぶり出す意欲作」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 大いなる違和感
第1章 早送りする人たち
――鑑賞から消費へ
第2章 セリフで全部説明してほしい人たち
――みんなに優しいオープンワールド
第3章 失敗したくない人たち
――個性の呪縛と「タイパ」至上主義
第4章 好きなものを貶されたくない人たち
――「快適主義」という怪物
第5章 無関心なお客様たち
――技術進化の行き着いた先
「おわりに」
序章「大いなる違和感」の「Netflixに実装された1・5倍速」では、米Netflix社が2019年8月に、Androidのスマホやタブレットで視聴する際に再生速度を選択できる機能を搭載したことが紹介されます。その後iOS端末やウェブにも導入が進み、順次各国が対応していきました。2022年2月現在の日本では、再生速度を0.5倍、0.75倍、1倍(標準)、1.25倍、1.5倍で選べます。著者は、「再生画面には他に『10秒送り』『10秒戻し』ボタンもある。クリックもしくはタップすれば、一瞬で10秒後・10秒前に飛ぶ(スキップする)。TVモニタでの視聴時に倍速視聴はできないが、対応するリモコンのキー操作で10秒送り、10秒戻しが可能。なお、Netflixと双璧をなす動画配信サービス、Amazonプライム・ビデオにも、10秒送り・10秒戻し機能がある」と述べています。
「映画やドラマを早送りする人たち」では、著者はかつて自身にも倍速視聴にどっぷり浸かった時期があったことを告白します。出版社でDVD業界誌の編集部にいた頃、毎月決まった時期に編集部総出で大量のVHSサンプルを視聴する必要があったのです。ある時、かつて倍速視聴した作品をDVDレンタルして観直し、著者は愕然としたそうです。作品の印象がまったく違ったからで、「初見の倍速視聴では作品の滋味を――あくまで体感だが――半分も味わえていなかった。ストーリーは倍速視聴時に把握していた通りだった。見せ場も記憶にある。だが、登場人物の細かい心情やその変化、会話からにじみ出る人柄や関係性、美術や小道具、ロケ地の美しさ、演出のリズムや匂い立つ雰囲気、それらを十全に味わえていたとは言いがたい。仕事で致し方なかったとはいえ、もはや懺悔に値する行為である」と述べています。
「倍速視聴経験者は若者に多い?」では、マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングによる2021年3月の調査結果が紹介されます。それによれば、20~69歳の男女で倍速視聴の経験がある人は34.4%、内訳は20代男性が最も多く54.5%、20代女性は43.6%。次いで30代男性が35.5%、30代女性が32.7%。男女を合算すれば、20代全体の49.1%が倍速視聴経験者だといいます。著者は、「ニュースや報道を『情報』だと割り切るなら、それらを倍速視聴することについて気分的には許容の範囲内だが、ここには『ドラマ』『映画』『アニメ』も入っている」と述べています。
なぜ、こんなことになっているのでしょうか。そこには、大きく3つの背景があります。「映像作品の供給過多」では、ひとつめの背景として、作品が多すぎることが指摘されます。著者は、「現在の人類は、今までの歴史のなかで、もっとも多くの映像作品を、もっとも安価に視聴できる時代に生きている」と述べます。2022年2月現在、NetflixやAmazonプライム・ビデオをはじめとした定額制動画配信サービスの料金は、月々数百円から千数百円という安価で「見放題」です。たったそれだけの出費で月に何十本、その気になれば何百本もの映画、連続ドラマ、アニメシリーズなどが観られるわけです。
「『コスパ』を求める若者たち」では、2つめの背景として、コスパ(コストパフォーマンス)を求める人が増えたことが指摘されます。倍速視聴・10秒飛ばしする人が追求しているのは、時間コスパです。これは昨今、若者たちの間で「タイパ」あるいは「タムパ」と呼ばれています。「タイムパフォーマンス」の略です。フォロワー数十万人を誇る、あるビジネス系インフルエンサーが、Twitter(現在は、X)で映画の倍速視聴を公言したときも、そこについたリプには「コスパが良くなっていい」といった好意的な意見が多かったようです。彼らは映画やドラマの視聴を、速読のようなものと捉えているのでしょう。
「作品とコンテンツ、鑑賞と作品」では、「鑑賞」に紐づく「作品」という呼称と、「消費」に紐づく「コンテンツ」という呼称の違いは、“量”の物差しを当てるか、当てないかだと指摘し、著者は「content(コンテンツ)が『内容物』や『容量』の意味であること、新聞などがいまだに『コンテンツ(情報の中身)』などと説明するように、また『コンテンツ』が電子媒体上の情報や制作物を指し示すことを皮切りに言葉として浸透した経緯からして、『コンテンツ』という呼び方には、数値化できる量(データサイズや視聴に必要な時間)に換算して実体を把握しようという意志が、最初から織り込まれている。それゆえ、『短時間』で『大量』に消費できることで得られる快感が、視聴満足度に組み込まれうるのだ」と述べます。
「すべてをセリフで説明する作品が増えた」では、3つめの背景として、セリフですべてを説明する映像作品が増えたことが指摘されます。TVアニメシリーズ『鬼滅の刃』(第1期)の第1話。主人公の竈門炭治郎は、雪の中を走りながら「息が苦しい、凍てついた空気で肺が痛い」と言い、雪深い中で崖から落下すると「助かった、雪で」と言います。しかし、そのセリフは必要でしょうか。著者は、「丁寧に作画されたアニメーション表現と声優による息遣いの芝居によって、そんな状況は説明されなくてもわかる。このセリフが原作どおりであることは承知だ。しかし、モノクロの静止画である漫画とカラーで動くアニメーションでは、情報量が格段に異なる」と述べるのでした。
第1章「早送りする人たち――鑑賞から消費へ」の「『観たい』のではなく『知りたい』」では、「知る」ために映画を観ることについて言及されます。ここでは、一条真也の映画館「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」で紹介したアニメ映画が取り上げられます。2020年10月に公開されて興行収入403億円(国内興行で歴代1位)を記録しました。著者は、「同作が世の中で大きな話題になり、ヒット分析記事がビジネス系サイトにあふれた当時、普段アニメには一切興味がないトレンドウォッチャーな中高年が、大挙して映画館に足を運んだ。彼らは原作を読んだこともなければ、TVアニメシリーズを観てもいない(同劇場版はTVシリーズの完全な続編である)。『なぜこんなにも流行っているのか』を知るために、観た。これを『情報収集』と言わずして何と言うのか」と述べています。
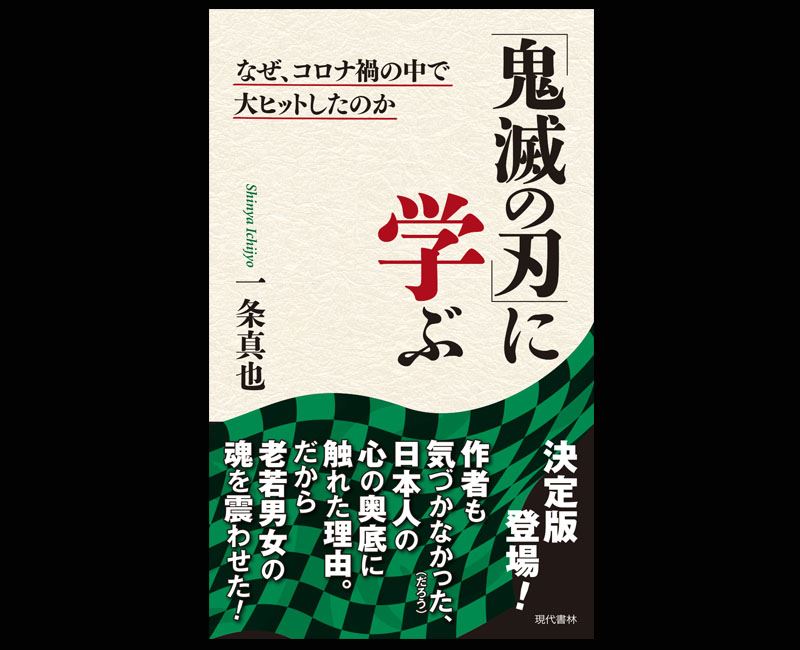
『「鬼滅の刃」に学ぶ』(現代書林)
ちなみに、わたしも『鬼滅の刃』が「なぜ、コロナ禍の中で大ヒットしたのか」に関心を抱き、漫画を一気読みし、アニメと映画も一気に観ました。その結果、物語の面白さに大いにハマるとともに、日本人の「こころ」の本質に関わる発見をしたのです。速読や倍速視聴では絶対に不可能な発見であったと思います。詳しくは、拙著『「鬼滅の刃」に学ぶ』(現代書林)をお読み下さい。さて、「サブスクは1作品ずつが大切にされない」では、視聴ごとに料金を支払うわけではないことが何をもたらすかについて、著者は「作品のありがたみを減らす。倍速視聴習慣のある若者に、そんなに時間がもったいないなら映画館で映画を観ている時も早送りしたくなるのでは、と聞いたら、そうはならないという答えとともに、こう言われた。『映画館はそのためにお金をいちいち払うから、早送りするのはもったいない。でもNetflixにはもう月額料金を払っちゃってるから、別にいい』この説明は非常に示唆的だ」と述べています。
定額制動画配信サービスは、1人でも多くのユーザーに、1円でも安く、1本でも多くの作品を、家にいながらにして楽しんでもらうべく生み出されました。著者は、「一昔前からすれば、文字通り夢のようなサービスである。しかしその夢のサービスは、作品を『鑑賞』する機会を増やすよりもずっと大きなインパクトで、コンテンツを『消費』させる習慣を我々に根付かせたのかもしれない」と述べます。また、第2章「セリフで全部説明してほしい人たち――みんなに優しいオープンワールド」の「『嫌い』と言ってるけど本当は好き、が通じない」では、状況やその人物の感情を1から10までセリフで説明する作品が近年増えてきたことが紹介され、著者は「そうした作品になれた視聴者は、セリフとして与えられる情報だけが物語の信仰に関わっている、と思い込むようになる」と述べています。
倍速視聴者たちは、人物が登場しなかったり、沈黙が続いたりするようなシーンは、物語が進行していないとみなし、10秒飛ばすそうです。著者は、「本来、10秒間の沈黙という演出には、視聴者に無音の10秒間を体験させるという演出的意図がある(はずだ)」と述べますが、そのような作り手側の意図は届きません。『ドラえもん』などのファミリーアニメ、『交響詩篇エウレカセブン』などのSFアニメほか、実写映画やドラマの脚本、ゲームシナリオを手掛ける脚本家の佐藤大氏は、「口では相手のことを『嫌い』と言っているけど本当は好き、みたいな描写が、今はつうじないんですよ」と嘆きます。著者も、とある作品のワンシーンで、男女が無言で見つめあっていますが、互いに相手から視線を外さないケースを取り上げます。明らかに好意を抱きあっている描写ですが、ある視聴者は、それが相思相愛の意味だとわからず、誰かから教えられると「でも、どっちも『好き』って言ってなかったから、違うんじゃない? 好きだったら、そう言うはずだし」と反論したそうです。
「製作委員会が『わかりやすくしろ』と言う」では、一条真也の映画館「この世界の片隅に」で紹介した2016年のアニメーション映画の名作などのプロデュース会社・ジェンコの代表取締役・真木太郎氏によれば、説明セリフの多い作品が増えた理由のひとつは、製作委員会(製作費を出資する企業群)で脚本が回し読みされる際、「わかりにくい」という意見が出るからだそうです。納得ですね。「より短く、より具体的に」では、「短くする」のは、わかりやすさへの近道だと指摘し、著者は「2010年代初頭から爆発的に普及したTwitter。その140字制限は、『できるだけ短く、シンプルに、誰にでもわかる言葉で、結論を最速で届けるべし』という流儀を、10年かけてネット空間に植え付けた。無論、ネット空間が言論空間のすべてではないが、多くの人にとって、もっとも身近な言論空間であることは確かだろう。PVを稼ぐ目的のネット記事が『結論を1行目に書け、タイトルにひねりはいらない、一言に要約できる内容にしろ』を金科玉条としているのは、よく知られた話だ」と述べています。
「自分の頭が悪いことを認めたくない」では、言葉による直接的な説明がない物語は、観客がその解釈を自分の頭で考える必要があることが指摘されます。真木太郎氏は、「当然、人によって受け取り方はさまざまになるけど、それでいいんです。受け手には“作品を誤読する自由”があるんだから。誤読の自由度が高ければ高いほど、作品の奥が深い。……というのは、僕の意見だけど」と述べています。しかし、セリフで全部説明してほしいタイプの観客は、誤読の自由を満喫しようとはしません。その自由度を奥の深さとは受け取ってくれず、「不親切だ」と怒り、不快感をあらわにするのです。
「SNSで『バカでも言える感想』が可視化された?」では、2000年代初頭から、ブログや匿名掲示板などはありましたが、まだまだ一部の人間が能動的に読みに行くものであり、まとまった数の“民意”にはなりえなかったことが指摘されます。それが2000年代後半以降、TwitterをはじめとしたSNSが誕生・普及したことで、どんな人も分け隔てなく、無料で気軽に、作品の感想をつぶやけるようになったのです。そこでもっとも言いやすいのが、「わかんなかった(だから、つまらない)」だとして、著者は「論理的な説明やエビデンスがいらない。そんな話を、映画宣伝マンの知り合いに投げてみたところ、毒舌家の彼は言った。『バカでも言える感想ですね、それ』と」と述べています。
さらに著者は、「かつては可視化されていなかった“幼稚な観客”、あるいは“思考を止めている観客”でも言える程度の感想が、不特定多数に向けて爆発的な拡散力で可視化されるようになった。そこに相応の人数が同調し、まとまった数になって製作委員会や制作スタッフの目に飛び込めば、彼らがその“民意”を完全に無視することはできないだろう。結果、『わかんなかった』と言われることを恐れるあまり、脚本の説明セリフが多くなっていく」と説明します。また、作品に賛同するよりも、クレームを言うほうがマウントを取れるといいます。「こんなわかりにくい作品をつくりやがって」と憤ることで、被害者になれるわけです。しかも被害報告はネット上で賛同を得やすいことを指摘し、著者は「SNSの誕生によって、どんな民度、どんなリテラシーレベルの人間も、事実上ノーコストで、ごく気軽に『被害報告』を発信できるようになった。それが、多くの人に『わかんなかった(だから、つまらない)』と言われない、説明セリフの多い作品を生みだした可能性は高い」と述べるのでした。
『鬼滅の刃』と「シャレード」では、「シャレード」というシナリオ用語が紹介されます。オードリー・ヘプバーン主演の映画『シャレード』(1963年)に登場するジェスチャーゲームを由来とする言葉で、「間接表現」のことです。目で見てわかることは、いちいちセリフにしなくていい、すべきではないという理論です。一条真也の映画館「『ローマの休日』 製作70周年記念 4Kレストア版」で紹介した古典的名作「ローマの休日」にも「シャレード」が使われています。著者は、「オードリー・ヘプバーン演じるアン王女が各国の要人たちと次々握手・挨拶をするが、明らかに退屈している。ただし、『ああ、退屈だわ』といったセリフやモノローグは言わせない。その代わりに、カメラが彼女のドレスの中、足元を撮る。彼女はうんざりして足をモジモジさせ、片方の靴を脱ぎ、足が靴を見失う。やがて着席時に靴をスカートの外に置いてきてしまうのだ。このシーンはアン王女がだらしないと言いたいのではなく、彼女が退屈していることを、セリフを使わずに表している。これがシナリオ技術というものだ。しかし『好きだったら、そう言うはずだし』と口にする視聴者が、どこまでその意図を解せるか」と説明します。
「『脚本』クレジットがない!?」では、『鬼滅の刃』には脚本家クレジットがないことが明かされます。著者は、「原作漫画のセリフ回しに極力忠実に映像化することの是非は、ここでは問わない。ひとつ言えるのは、昨今は映像化によってセリフなどを“改変”すると、それが適切な脚色の範囲内であっても、原作ファンが『原作レイプ』などと不満の声を上げるケースも見受けられるということだ。そういったリスクを根本から断つには、『原作どおり』が無難である」と述べます。また、博報堂DYメディアパートナーズのメディア環境研究所・森永真弓氏の「なぜテレビはテロップがやめれないのか」では、「テレビマンは常に、同じ放送時間帯の他番組や、番組全体として視聴率が良い番組を、非常に細かい時間単位に区切って研究しています」という発言を紹介して、著者は「ここで重要なのが、彼らは視聴率が上がるのはいろいろな要素が複合的に作用していると考えるが、視聴率が下がるのは自分たちの責任だと考える点だ」と述べています。
テレビマンは、「なぜ視聴率が落ちたのか」を特に研究することとなり、「最初からいた視聴者を、とにかく取りこぼさない」「番組の途中でやって来た視聴者は、絶対に逃さない」ための対策を講じるようになると指摘する著者は、「ここでテレビマンたちは、あることに気づいた。視聴者は、いま何が行われているかわからないと、再びチャンネルを変えて去ってしまう。それを防ぐには、テロップを常に表示させておいたほうがいい、ということに。それがいくら説明過多だったとしても。それに、常にテロップで説明されていれば、TVをぼんやり見ている、あるいは家事などをしながらテレビを見ている視聴者がふと画面に意識を向けたとき、すぐに内容に追いつける」と述べます。
「わかんなかった(だから、つまらない)」では、森永氏の「説明の多さに慣らされた結果、説明セリフの少ないドラマや映画を観ると、情報が少ないと感じて、物足りない気分になる。それで早送りするなり、ついスマホを見たりしてしまう」という発言を紹介し、著者は「実際、倍速視聴が習慣化している人はよく、『もはや普通の速度では物足りない。1.5倍か2倍くらいがちょうどいい』と口にする。また、若年層がTV以上に親しんでいるYouTubeの企画動画は、概して地上波TV番組よりも編集のテンポが速い。間はとことん排除され、インパクトのある発言だけで埋め尽くされている。その意味では「情報密度が高い」。その情報密度、そのテンポに慣れてしまえば、映画のワンカット長回しや、セリフなしでの沈黙芝居に耐えられなくなるのは、当然かもしれない。大学生たちが口々に言っていた『せっかち』という言葉が思い出される」と述べます。
積み重ねられた習慣こそが、人の教養やリテラシーを育みます。抽象絵画を一度も見たことのない人間が、モンドリアンの絵をいきなり見せられても、どう解釈していいかわからないとして、著者は「無論、抽象絵画など鑑賞しなくても人間は生きていける。同じように、セリフのないシーンに意味を見出すことができなくても、人間は生きていける。善悪ではない。ただただ、そういうことだ」と述べるのでした。また、「『わかりやすさ』と『作品的野心』の両立が求められる」では、映画を倍速視聴をする人に対して、真木氏が「そういう人たちを責める気はないよ。観客がどう観ようが、観客の勝手だもの。観客には、“誤読の自由”がある。だったら、早送りだろうが、10秒飛ばしだろうが、観る速度の自由があってもいい」という発言が紹介されます。
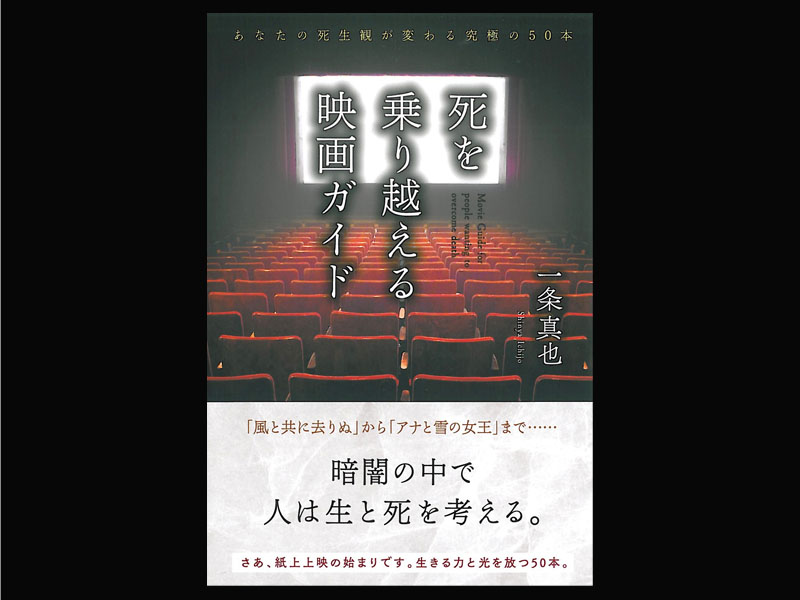
『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)
この真木氏の発言の中の「自由」という言葉から、拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)の内容を連想しました。「映画で死を乗り越える」というのが同書のテーマですが、わたしは映画を含む動画撮影技術が生まれた根源には人間の「不死への憧れ」があると思います。映画と写真という2つのメディアを比較してみましょう。写真は、その瞬間を「封印」するという意味において、一般に「時間を殺す芸術」と呼ばれます。一方で、動画は「時間を生け捕りにする芸術」であると言えるでしょう。かけがえのない時間をそのまま「保存」するからです。それは、わが子の運動会を必死でデジタルビデオで撮影する親たちの姿を見てもよくわかります。「時間を保存する」ということは「時間の束縛から自由になる」ことにつながり、さらには「死すべき運命から自由になる」ことに通じます。写真が「死」のメディアなら、映画は「不死」のメディアです。つまりは、究極の自由を得るためのメディアなのであって、倍速視聴もその一端であると考えることもできるのではないでしょうか。
「わからなければ、わからないなりに」では、「わかる人はわかる人なりに。わからない人はわからないなりに」というテーゼが示され、たくさんのスーパーヒーローが作品ごとにそれぞれ主役を張りつつ、数十本の作品群全体として複雑なストーリーと世界観を構築するハリウッドのアメコミ原作映画は、その最たるものだと指摘。「『オープンワールド化』する脚本」では、著者は、「一定以上の規模を有した商業作品である以上、つまり相応のビジネスサイズとマネーメイキング機能を求められているプロジェクトである以上、あらゆるリテラシーレベルの観客が満足する(誰もが気分を害さない)ものを作らなければならなくなった。否、そうでなければならない空気が、厳然としてある。それは制作者の配慮が必須、という意味で、『マイノリティの尊重』『多様性に寛容』といったポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)を想起させるほどの作法・規範にも思える。リテラシーが低い人を差別しない、という名のバリアフリー、『みんなに優しい作品』こそが『良い作品』なのだ」と述べています。
著者は、「物語の作り方というものを根本的に変えねばならない。大変な時代がやってきた」と言います。変えた、と言えば一条真也の映画館「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で紹介した2021年のアニメ映画が好例だとか。脚本家の佐藤氏は、「1995~1996年のTVシリーズから25年間、ずっと“説明しない”でおなじみだった庵野秀明監督でしたが、『シン・エヴァ』の終盤では、主要キャラクターが順番に登場して、心情をセリフで丁寧に説明してくれました。こんな親切な『エヴァ』は初めてです。庵野さんは常に時代に寄り添う人だから、“今はこういうターンだ”と思って、あえてそうしたんじゃないでしょうか」と述べています。わたしも、まったく同感ですね。
第3章「失敗したくない人たち――個性の呪縛と『タイパ』至上主義」の「LINEグループの“共感強制力”」では、友人や仲間から映画やドラマを薦められた場合に必ずチェックする人々について、著者は「なぜそこまでして、話題についていかなければならないのか。それは、若者のあいだで、仲間との話題に乗れることが昔とは比べ物にならないほど重要になっているからだ。それをもたらしたのがSNS、おもにLINEの常時接続という習慣である」と述べています。「2021年一般向けモバイル動向調査」によれば、10代の94.6%、20代の92.9%がスマホや携帯電話(ガラケー)でLINEを利用しています。
この数字は、同じSNSであるTwitter(10代の80.1%、20代の75.4%が利用)やインスタグラム(10代の68.0%、20代の63.4%が利用)を圧倒する利用率です。LINEの友達グループは四六時中つながっています。文字通り、朝起きてから夜眠るまで。いつでも連絡できるし、常に何かしらの反応を求められるのです。著者は、「大学生を中心とした若年世代にとっては、仲間の和を維持するのが至上命題。とにかく共感しあわなければいけない。博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所・森永真弓氏は、これを『共感強制力』と呼ぶ」と紹介します。
「友達の広告化」では、現代の若者は観なければならない本数がとにかく多いことが指摘されます。グループが5つあれば五様の、10個あれば十様のマストチェック作品が日々提案され続けます。しかも、それは現在放映中の番組や公開中の映画に限りません。10年前の連ドラも20年前の映画も、動画配信サービスでいくらでも観られるからです。ここにDVDレンタルやYouTubeなどで視聴可能な作品を加えれば、その数は膨大になります。著者は、「多くのグループ内で、新旧あらゆるジャンルの映像作品について『これ、おもしろかった』『これ、観たほうがいいよ』が飛び交う。本の積ん読のように溜まっていく作品リスト、ToDoタスク。半ば義務感として観ざるをえない」と述べます。
また、自分の内側から湧き起こる興味や欲望ではなく、グループの和の維持のために観る。だから倍速視聴で“やっつける”しかないとしながらも、著者は「ただ、それがおもしろければいいが、1話観ても2話観ても一向におもしろいと感じられない場合は、いいところで最終話に飛ぶ。大まかなストーリーと結末だけでも知っておけば、話には入れるからだ」と分析します。もちろん、友達がいない・少ない若者であれば、共感強制力やおすすめの洪水には無縁であり、彼らが早送る理由はコスパ意識から来る時短志向に概ね集約されます。ただ、LINEの利用率や常時接続という仕様特性からして、「つながっている友達が多すぎるゆえのToDo過多」に悩まされている若者のほうが多数派であるのは間違いないと言えます。
「生存戦略としての倍速試聴」では、話題作をコミュニケーションツールとして使う傾向は、昨日今日に始まったことではないといいます。「観ておかないと学校や職場で話題の輪に入れない」作品は、昭和の時代からありました。1980年代から1990年代なら、『8時だョ!全員集合』『ザ・ベストテン』『月9ドラマ』等々。特に40代以上なら、いくらでも番組タイトルが口をついて出てくるだろとして、著者は「ただ、当時の若者が友達と触れ合うのは、教室だけだった。教室を出たら逃げられた。我が道を行くことができた。しかし今は、LINEがどこまでも追いかけてくる。逃げられない。常にレスを求められる」と述べるのでした。
「Z世代の個性発信欲」では、著者は、“ナンバーワンよりオンリーワン”の洗礼を受けたゆとり世代以降で注目したいのが「Z世代」であると述べます。Z世代の定義には諸説ありますが、概ね1990年代後半から2000年代生まれ、2022年時点で10代後半から20代半ばくらいまでの若者を指します。Z世代は1960~1970年生まれのX世代、1980~1990年生まれのY世代(≒ミレニアル世代)に続く世代。Y世代が「デジタルネイティブ」、つまり社会人になる前からインターネットやパソコンのある環境で育ってきた世代であるのに対し、Z世代は「ソーシャルネイティブ」と呼ばれます。
マーケティングアナリストの原田曜平氏は、ゆとり世代とそれに続くZ世代との違いについて、「SNSで叩かれたくないという『同調圧力』と『防御意識』が強かった思春期時代の『ゆとり世代』と、周りから心象が悪くならない範囲で、SNS上で周りと同程度に自己アピールしたいという『同調志向』と『発信意識』が強いZ世代」と分析しています。著者は、「Z世代は、ゆとり世代と同じくLINEグループなどで和を乱さない意識が常に働いているが、それに加えて発信欲もあるのだ」と述べます。「メジャーに属せない不安」では、「多数派に属する」という選択は多くの若者たちにとって「安心」だったのだと指摘し、著者は「ところが、現在ではカルチャーシーンから多数派(メジャー)が消えてしまった。“ナンバーワンよりオンリーワン”が価値観の多様化を促進した結果、趣味や趣向の島宇宙化を招き、『圧倒的多数の、みんなが好きなもの』が激減してしまったのだ」と述べるのでした。
「自己紹介欄に書く要素が欲しい」では、属するだけで安心できていたメジャーが消えた状況下、彼らが探しているのは拠りどころであると指摘されます。自分が属しているだけで楽しいと思える場所を欲しているというのです。森永氏は、「それがオタクという属性です。オタクって、はたから見てて、すごく楽しそうじゃないですか」と述べますが、著者は「それが、『若者がオタクに憧れている』の正体だ。ただ、オタクと言っても博識を旨とするような研究系のオタクではない。アイドルやアニメのキャラクター、あるいはクリエイターの“推し活動”をしているオタクだ」と述べるのでした。
「『オタク』パブリックイメージの変遷」では、「オタク」あるいは「おたく」という呼称が一般的に普及したのは1980年代後半ですが、その後少なくとも20年余りは基本的にネガティブなイメージ一辺倒だったことが指摘されます。「内向的、教室では日陰者、社会性や異性交際経験に乏しく、ファッションに無頓着」といったものです。そのネガティブイメージを決定づけたのは、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人として1989年に逮捕された宮﨑勤(2008年に死刑執行)の存在であるという著者は、「彼のロリコン趣味とホラーマニアぶりがマスコミにクローズアップされ、その後『オタク=怖い存在』というイメージが広く定着したのだ」と述べています。
「オタクのカジュアル化と“にわか”問題」では、にわか批判が最も牙をむく空間がTwitterに代表されるSNSであるのは間違いないと訴えます。ぬるい感想や知識の浅さに対し、面識のないその筋のプロが容赦ないツッコミと訂正を入れてくる。いわゆる“ネット警察”というやつです。著者は、「10代前半からSNSの酸いも甘いも噛み分けるZ世代は、情け無用の戦場のごときTwitterに、ある種の恐れや苦手意識を抱くようになった。ハイレベルな議論や批評がオープンで行われているオタクの土俵には踏み込まないのが吉、と思うようになったのだ」と述べます。
「自分の上位互換がすぐに見つかってしまう地獄」では、オタクは「忌み嫌われる対象」から「奇人として嗤われる存在」となり、「個性のひとつとしてカジュアルに名乗れる」時代を経た後、敬意を払われる対象とさえなったとして、著者は「本来、趣味であれ個性であれ、その道のプロに追いつく必要などはないはずだ。そんなことを言い出したら、どんな趣味もどんな学問も、始める前から徒労感に押しつぶされてしまう。だが、Z世代は実際に押しつぶされている。真っ白なキャンバスを目の前に置き、筆と絵の具を準備しはじめた途端、周囲の同級生が次々と完成した絵を提出していく。しかも、その絵は自分の技量では到底到達しえないほど上手く、かつ自分が目指している画風と同じ方向性だったとしたら? それでも絵筆を握り続けるには、相当強いハートが必要だ。自分の“上位互換”を目視できてしまう地獄。下手は下手なりに、趣味としてお絵描きを楽しむなんて、できるわけがない。オープンであることを美点とするSNSは、あらゆる分野において全国レベルの猛者たちを『すぐ隣の存在』として可視化した。自分との圧倒的な実力差を、毎分毎秒、スマホ越しに突きつけてくる」と述べるのでした。
「ジェネラリストの時代はもう終わりました」では、一寸先は闇、先行きがわからない世の中で「石の上にも三年」なんて言っていられないとして、著者は「Z世代の育ってきた時代を見れば、その説得力は大いに増す。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災、2020年から続くコロナショック。その都度、好調だった業界がどん底に叩き落とされ、生活が振り回されてきた。世帯収入が減ったことで学費を払えず大学を辞める同級生、きついバイトをする友人たちもたくさん見てきた。理不尽な内定取り消しに泣き、両親が肩を落とす姿に心を痛めた」と述べています。そのため、「今この瞬間に圧倒的な個性で目立たなければ。社会にピックアップされなければ。急げ、急げ。早く、早く」というわけです。
「倍速視聴派のタイパ至上主義」では、Z世代は拠りどころが欲しく、個性的でありたいことが指摘されます。その結果、オタクに憧れます。カルチャーシーンからメジャーが消え、ゆとり教育のなかで「個性的であれ」と言われて育った若者たちがそうした傾向をもつことは理解できるとしながらも、著者は「ただ、憧れの存在であるオタクに近づくためには、本来たくさんの作品を観る必要がある。しかし、彼らはその過程を、『なるべくコスパ良く済ませたい』と願う。『観ておくべき(読んでおくべき)重要作品を、リストにして教えてほしい』と言う。そもそも、一般の人が費やさないほど膨大な時間を、自らの専門分野に投じたからこそオタクなのであって、オタクはコスパから最も遠いところにある存在のはず」と述べます。まったくもって、その通り!
「どんな気分になるのか正確に予測したい」では、目の前の商品や作品やサービスが、自分にとっていかなる満足を与えてくれるのか。それを前もって知りたいと思う気持ちは世代問わず誰もが抱くものですが、Z世代はこのような気質が他の世代に比べて抜きん出て強いと指摘しています。「予告編は出し惜しみなしがマスト」では、音楽の供給が配信に軸足を移して以降、特に若年層向けの歌謡曲はイントロからいきなりサビが流れる構成のものが多くなったとして、著者は「Aメロ→Bメロ→サビという、昔からの『展開』がまだるっこしいのだ。イントロの数秒を聴き、その曲を最後まで聴くかどうか(買うかどうか)を判断する。自分にとって価値があるかどうかを、最短時間で知りたい」と述べています。
「圧倒的に時間とカネがない今の大学生」では、コスパやタイパに走る今の大学生を「けしからん」と説教したり、「つまらない奴らだ」と憐れんだりするのは簡単ですが、そう説教したくなる年長世代が若かりし頃には、キャリア教育の圧もSNSもなかったと指摘します。もうひとつ同情すべき点があります。今の大学生には時間とお金がないのです。著者は、「仲間内でのコミュニケーションのため、LINEグループの和を保つため、30年前に比べればおそらく何十倍、何百倍もの本数が流通するコンテンツを、次々とチェックしなければならない。その量は早送りしなければ消化できないし、慎重にリスクヘッジしなければ、ただでさえ貴重なお金をドブに捨ててしまう。彼らはとにかく余裕がない。時間的にも、金銭的にも。そして何より精神的に」と述べるのでした。
第4章「すきなものを貶されたくない人たち――『快適主義』という怪物」の「ライトノベルの『快適主義』」では、「快適主義」とでも呼ぶべき傾向が幅を利かせているのが、アニメ作品の原作になることも多いライトノベル界隈であると指摘されます。その中でも人気を集める「なろう系」の基本フォーマットでよく見られるのが、「現代に生きる一般人が異世界に転生し、現代の知識・経験・テクノロジーをそのまま生かすことで、その世界で圧倒的な優位に立つ 」といった類いの構図だそうです。飯田一史氏の著書『ライトノベル・クロニクル 2010―2021』ではこの傾向を、「植民地主義的態度」と説明しています。「(優位に立つ)文明が(劣位にある)野蛮を支配・啓蒙する」というわけです。
2010年頃、『魔法科高校の劣等生』(佐島勤著、電撃文庫)という作品が大ヒットしていましたが、“最強の主人公”の先駆け的な作品だったそうです。主人公は頭から終わりまでずっと強い。1回も沈まない。当時も今も、そういうものが求められているといいます。ある大学生は、「癒しや安心を目的として作品を読む人、アニメなどを観る人が、つらい描写を見たくないと思うのは当たり前」とした上で、「そのつらい描写をあまり見ないための手段として、倍速視聴が使われてもいいと思う」。と言ったそうです。たしかに2倍速で観ればつらさは半分になりますね。また、なぜラブコメが好まれるのかというと、「主人公同士が絶対にくっつくとわかっているから」だとか。ハッピーエンドが完全に保証されているのです。この2人は絶対にくっつく、という前提で物語がスタートします。著者は、「つまり、結末の快適が最初から保証されている。ネタバレ考察サイトを読んでから安心して映画を観る行動に、近からずとも遠からず」と述べます。Z世代が嫌う「気持ちがアップダウンするストレス」も発生しようがないわけです。
「エンタメに『心が豊かになること』なんて求めていない」では、森永真弓氏が、視聴者のワガママ化、ある種の快適主義を「当然」と見て、「「エンタメに対して“心が豊かになること”ではなく、“ストレスの解消”を求めれば、当然そうなります。心に余裕がない、完全ストレス過多なんですよ、特に若い世代は」と述べていることを紹介します。このことは、「スポーツを観戦する若者が減っている」という事実からも明らかだとか。森永氏は、「ストレス解消が目的なので、応援しているチームが勝つ場面しか見たくない。でも、スポーツは応援したからといって必ず勝つわけではありませんよね。言ってみれば、“リターンの博打度が高い”。だから、勝った試合のダイジェスト映像だけを見る。もしくは、特定のチームを応援せず、ファインプレーや点が入った“かっこよくて気持ちいい”シーンだけを見る」とも述べます。もはやスポーツファンではない。スポーツユーザーだと言えます。
さらに、森永氏は「日本のサッカー観戦ファンは高齢化の傾向が心配されていますし、スポーツコンテンツ王国のアメリカですら、ファンの高齢化に悩んでいるのが実情です」とも述べています。まさに、快適だけを求める志向です。著者は、「1日中、したくもない仕事をしてストレスを溜め込んで帰ってきて、あるいはLINEグループの人間関係に疲れ果てているのに、考えさせられるドラマなんぞ観たくはない。だからこそTVドラマにもスポーツ番組にも、ストレス解消という機能を求める」と述べます。「見たいものだけを見たい」では、快適主義をより感覚的に言い換えるなら、「見たいものだけを見たい」になるとして、これはZ世代がとりわけ強く持っている生理だと主張します。原田曜平氏は、「スマホ第一世代である彼らは、スマホやSNSで企業やメディアからターゲティングされており、『自分の見たい情報』だけを見て生活するようになっている」とし、その結果「自分が絶対に共感する情報にしか触れずに生活しているZ世代は、自分にとって違和感のある情報に接すると、大きな拒絶反応を示す」と分析しています。
ユーザーが見たくない情報を遮断するフィルターのせいで、あたかも泡(バブル)に包まれたかのように、得たい情報しか見えなくなります。このようなインターネットの性質は、昨今「フィルターバブル」と呼ばれています。映像視聴習慣も同じ状況にさらされているとして、著者は「スマホやタブレットや個人PCが普及した社会の子供たちは、リビングのTVで親が見ている番組を一緒に観る必要がない。自分が観たいものだけを選び抜ける。選び抜くことが普通になっている状態では、最初から狙っていたコンテンツ以外に期せずして時間を割くことは無駄だと認定され、ストレスとなる」と述べます。
「好きなものだけつまみ食い――ピッキー・オーディエンス」では、著者は「インターネットの普及と浸透によって人々は――全世代的に――多すぎる情報とコンテンツに辟易している。心が疲れている。そこにきて、自分の好きな情報やコンテンツだけで視界を埋める術が、同じインターネットによって実現した。最初から同じ意見の人だけをフォローするSNS、興味のあるニュースが先頭に来るよう快適にカスタマイズされたニュースサイト。外野の無粋な異論・反論がシャットアウトされている有料オンラインサロン。多くの動画共有サイトや定額制動画配信サイトが、ユーザーひとりひとりの視聴履歴に応じて「おすすめ作品」「次に観るべき作品」をレコメンドしてくれる。趣味に合わない作品は、最初から選択肢から外しておいてくれる。その恩恵を享受しているのは、なにも若年層だけではないということだ」と述べています。
「共感至上主義と他者性の欠如」では、「心が揺さぶられる」状態を避けるメンタリティのバリエーションとして、昨今は「共感性羞恥」がポピュラーな感覚として共感者を増やしつつあると指摘し、著者は「他人が失敗したり、恥をかいたりしているのを見ると、それがフィクションの中の出来事であっても自分まで恥ずかしい気持ちになってしまうというものだ。共感性羞恥を強く感じる人は、TV番組のドッキリ企画すら見ることができない。楽しめないのだ。ある種の人々が映像作品に求める『快適主義』に近いものがある」と述べます。
「評論が読まれない時代」では、今、映画の評論本が売れないことが紹介されます。評論とは、作品について論じること。辞書の説明に倣うなら「物事の価値・善悪・優劣などを批評し論じること。また、その文章」。良い点も悪い点も指摘し、公平かつ客観性をもって論じることであるとして、著者は「評論本というものが、もともとすごく売れるジャンルではないにしても、それに輪をかけて売れなくなってきている現状がある」と述べます。
また、中堅出版社の営業マンの「高名な映画評論家の著書でも、初版は3000部。消化率(実売数)は良くて6割5分。だから編集から企画が上がっても、社会稟議の段階でストップしてしまう。プラスアルファの要因がないと、なかなか企画が通らないんですよ」という発言を紹介して、著者は「3000×0.65=1950。つまり2000部も売れない。名前は伏せるが、Q氏が例として挙げた映画評論家は日本で五指に入る大御所だった」と述べるのでした。
「映画評論は1980年代まで売れていた」では、1980年代半ばには、浅田彰、中沢新一を中心的な担い手とする「ニューアカ(ニュー・アカデミズム)」ブームが訪れたことが紹介されます。現代思想の啓蒙的な側面だけでなく、バブルに向かう日本の消費社会化と広告文化の発展機運を背景として、芸術やポップカルチャーといった従来の学問の外にまで批評の射程を伸ばしていたのが、このムーブメントの特徴だったと指摘し、著者は「そこには当然映画評論も含まれている。知的でありたいと欲求する若者たち(=消費社会および広告文化の担い手)の一部はこの流れに乗り、難解な言葉で文化を語る喜びに浸っていた」と述べています。
並行して1983年には、ミニシアター(独自性・作家性の高い作品を上映する映画館)の中核的存在であるシネ・ヴィヴァン六本木がオープンしました。ジャン=リュック・ゴダール作品、エリック・ロメール作品といったヨーロッパ映画が上映され、そこにカルチャー感度の高い若者層が集うことで、(ファッション的、表層的な側面は多分にあったものの)文化的・知的なテクストとして映画が取り扱われていきました。また、1980年代は、ヴィム・ヴェンダース、ジム・ジャームッシュ、スパイク・リー、アキ・カウリスマキ、ピーター・グリーナウェイ、エドワード・ヤン、ウォン・カーウァイといった、才能あふれる新進気鋭の監督が世界各国から次々と登場した、映画界にとっては超豊作期でもあったとして、著者は「彼らの刺激的で論じがいのある作品が若い観客に刺激を与え、評論空間を活性化させる」と述べます。
「体系的な鑑賞を嫌う若者たち」では、評論が読まれなくなった理由が主に2つ挙げられます。1つめは、作品を体系的に観る習慣をもたない、コスパ重視思考の若者が増えたからです。「体系的な映画の観方」でもっとも手軽なのが、監督名で映画を観ることです。しかし映画関係者は口々に「映画を監督で観る人が減った」とこぼします。 評論が読まれなくなったもう1つの理由。それは、評論家のような権威的な存在から、あるいは自信満々な気鋭の書き手から、上から目線で「正しい観方」なんて教わりたくないという反発心が、特に若年層のあいだで強いからだといいます。非常に説得力がありますね。
「『他人に干渉しない』Z世代の処世術」では、著者は「他人に干渉しない。すなわち批判もダメ出しもしないし、されることもない。これは一見して『他者』を尊重しているように見えるが、そこには『自分と異なる価値観に触れて理解に努める』という行動が欠けている。単に関わり合いを避けているだけだ。それゆえに、自分とは考えの違う『他者』の存在を心の底からは許容できない。異なる意見をぶつけられた時に、『あなたと私は意見が違いますね』で終わりにできない。自分に向けられる批判に耐性がない。流すことができない。心がざわつき、『不快だ』と遠慮なく悲鳴をあげる。これは多様性には程遠い、むしろある種の狭量さだ。Z世代が得意だとする『多様性を認め、個性を尊重しあう』には、『異なる価値観が視界に入らない場合に限る』という但し書きが必要なのかもしれない」と述べています。
第5章「無関心なお客様たち――技術進化の行き着いた先」の「『制約からの解放』が行き着いた先」では、本書がこれまで、倍速視聴・10秒飛ばしという習慣がなぜ現代社会に出現したのかの理由と背景を、さまざまな角度から考察してきたことを振り返り、著者は「その基底にあったのは、(1)映像作品の供給過多、(2)現代人の多忙に端を発するコスパ(タイパ)志向、(3)セリフですべてを説明する映像作品が増えたこと、この3点だった」とまとめます。
振り返れば、人類の映像視聴史は常に技術の進化と並走してきました。かつて映像作品とは、「上映時間に合わせ、映画館に行って観る」ものでした。それがTVの発明により、TV番組に限って言えば、わざわざ映画館に行かなくても映像を観られるようになりました。著者は、「ただTV番組とて、放映されている時間に人間が合わせる必要はあった。それを解消したのが、ビデオデッキである。家庭用ビデオデッキの登場は1970年代後半、一般家庭に普及しはじめたのは1980年代半ば。これをもって人類は、映像作品を好きなタイミングで観られるようになっただけでなく、視聴体験を思い通りに“制御”できるようになった。任意のシーンで一時停止し、目当てのシーンまで早送りできるようになったのだ」と述べます。
技術はいつの時代も、人間がより快適に生活を送るための手段として存在してきました。技術は人類不変の「楽をしたい」という希望を叶えてきたのだと指摘し、著者は「18世紀から19世紀に起こった産業革命にしろ、20世紀から21世紀に起こったIT革命にしろ、その目的は人々が『楽になる』ことだった。映像を観るという行為も、技術によってどんどん『楽』になった」と述べ、さらには「19世紀末、フランスのリュミエール兄弟によって、映像を有料で公開する世界初の映画館が誕生して以降、我々は100余年をかけて映像視聴習慣における『場所的・時間的・物理的・金銭的制約』を取り払ったのだ」と述べます。
著者は、「新しい方法というやつはいつだって、出現からしばらくは風当たりが強い。目下のところ、倍速視聴や10秒飛ばしという新しい方法を手放しで許容する作り手は多数派ではない。“良識的な旧来派”からは非難轟々である。しかし、自宅でレコードを聴いたり映画をビデオソフトで観たりといった『オリジナルではない形での鑑賞』を、ビジネスチャンスの拡大という大義に後押しされて多くのアーティストや監督が許容したのと同様に、倍速視聴や10秒飛ばしという視聴習慣も、いずれ多くの作り手に許容される日が来るのかもしれない」と述べるのでした。
「おわりに」では、倍速視聴について調査すればするほど、考察を深めれば深めるほど、この習慣そのものはたまたま地表に表出した現象のひとつにすぎず、地中にはとんでもなく広い範囲で「根」が張られていると確信したとして、著者は「その根は国境を越えて延び、異国の地ではまったく別の花や果実として地表に顔を出している。すなわち、一見してまったく別種の現象に思える現象同士(倍速視聴―説明過多作品の増加―日本経済の停滞―インターネットの発達、等)が、実は同じ根で繋がっている。そのような根を無節操に蔓延らせた土壌とは、一体どのようなものなのか。それが本書で明らかにしたかったことだ」と述べるのでした。本書は、いろんな意味で衝撃的な書でした。わたしも映画レビューを良く書きますし、それが高じて映画の本なども出していますが、現代日本における映画ファンの実態がよくわかりました。