- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2297 宗教・精神世界 | 心霊・スピリチュアル 『「日本心霊学会」研究』 栗田英彦編(人文書院)
2024.01.28
『「日本心霊学会」研究』栗田英彦編(人文書院)を読みました。「霊術団体から学術出版への道」というサブタイトルがついています。

本書の帯
カバー表紙には「山と積まれた日本心霊学会の会員名簿」の写真が使われ、帯には「霊術団体はいかにして人文系出版社へと姿を変えたのか」「日本近代の宗教、学知、出版を総合的に捉え直す画期的研究」「人文書院創立100周年記念出版」と書かれています。
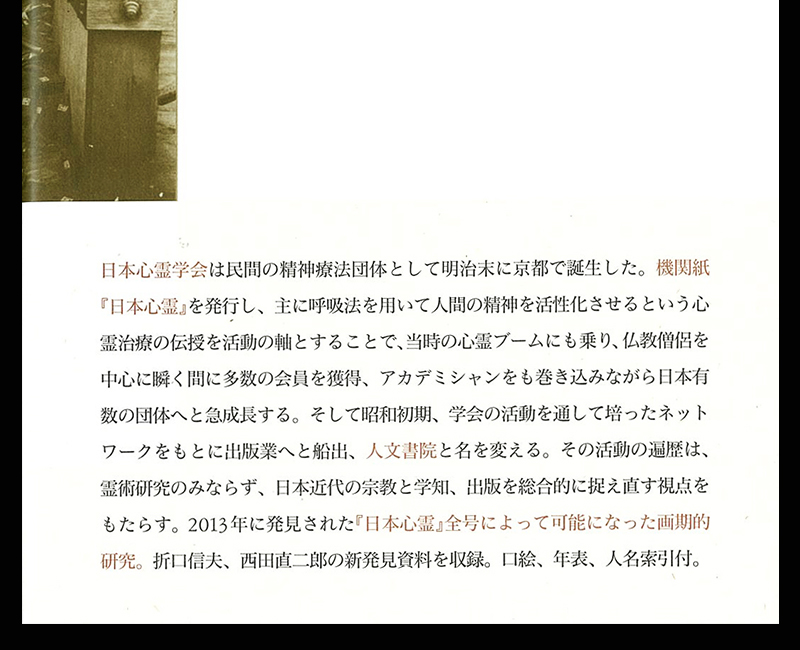
本書の帯の裏
帯の裏には、以下の内容紹介があります。
「日本心霊学会は民間の精神療法団体として明治末に京都で誕生した。機関紙『日本心霊』を発行し、主に呼吸法を用いて人間の精神を活性化させるという心霊治療の伝授を活動の軸とすることで、当時の心霊ブームにも乗り、仏教僧侶を中心に瞬く間に多数の会員を獲得、アカデミシャンをも巻き込みながら日本有数の団体へと急成長する。そして昭和初期、学会の活動を通して培ったネットワークをもとに出版業へと船出、人文書院と名を変える。その活動の遍歴は、霊術研究のみならず、日本近代の宗教と学知、出版を総合的に捉え直す視点をもたらす。2013年に発見された『日本心霊』全号によって可能になった画期的研究。折口信夫、西田直二郎の新発見資料を収録。口絵、年表、人名索引付」
本書の「目次」は、以下の通りです。
「はじめに」(栗田英彦)
第一章 日本心霊学会の戦略(一柳廣孝)
コラム1
民間精神療法のなかの日本心霊学会(平野直子)
第二章 日本の心霊研究と精神療法(吉永進一)
コラム2
H・カーリングトン『現代心霊現象之研究』
を翻訳した関昌祐の心霊人生(神保町のオタ)
第三章 大正期日本心霊学会と近代仏教
――「外護方便」としての心霊治療
(栗田英彦)
コラム3
句仏心霊問題(栗田英彦)
第四章 越境する編集者野村瑞城
――『日本心霊』紙上の「神道」と
「民俗」を中心に(渡勇輝)
コラム4
日本心霊学会編集部代表・野村瑞城(政造)
の作品と略歴(菊地暁)
第五章 編集者清水正光と戦前期人文書院
における日本文学関係出版(石原深予)
特別資料 西田直二郎・折口信夫講演録
(『日本心霊』より)
「年中行事と民俗研究」(西田直二郎)
「門 ◆ 精靈と大伴と物之部」(折口信夫)
「西田・折口講演解題」(菊地暁)
「あとがき」(栗田英彦)
「日本心霊学会~戦前期人文書院年表」
「はじめに」の冒頭を、佛教大学や愛知学院大学などの非常勤講師(近代宗教史、思想史)を務める栗田英彦氏が「人文書院は、東京中心の出版業界の中で、京都の出版社でありながらローカルな枠に閉じ込められず、東京の出版社に劣らない質の高い出版物を手掛けてきた。戦前は日本文学関係の文芸書を刊行し、戦後はサルトルやフロイトの思想書によって一時代を画したことでも知られている。保守的な傾向の強い京都の出版業界にあって、戦前からベストセラーを開拓し、一般向け出版物で出版業界をリードしてきた西日本を代表する出版社である。しかし、その人文書院の前身が日本心霊学会という霊術(民間精神療法)団体であったことはほとんど知られていなかった」と書きだしています。
人文書院初代社長、渡邊藤交(久吉)は明治40年前後に精神療法を学び、「心霊治療」を掲げて日本心霊学会を創始しました。この団体は人文書院と並行して昭和期までおよそ20年以上続き、当時、多数出現した霊術団体の中でも特に大規模な団体として知られていたそうです。栗田氏は、「東京帝国大学心理学助教授で千里眼実験や心霊研究で知られる福来友吉、福来の協力者でもあった京都帝国大学精神科初代教授の今村新吉、日本の推理小説文壇の成立に貢献した医学者の小酒井不木などとも交流があり、仏教僧侶を中心に会員を増やしていた。大正期は『心霊』が社会を風靡した時代であり、文芸への影響も大きなものがあったが、その一角を担っていたのが、この日本心霊学会だったのである」と述べます。
2013年、高台寺北門前の人文書院旧社屋(兼社長自宅)の土蔵から、日本心霊学会機関紙『日本心霊』がほぼ揃いで発見されました。加えて書簡・写真類、会員名簿や出納帳なども発見され、治療業と出版業の舞台裏にも光を当てる資料も見つかりました。栗田氏は、「これらの新資料の発見により、日本心霊学会の変容の過程を精緻にトレースし、全体的な視点からの研究が可能になった。本書は、この発見によって立ち上がった共同研究の成果である」と述べています。
日本心霊学会の興味深いところは、それが人文書院の前身だったということにあります。その点で日本心霊学会研究は、出版文化研究にも位置づけられると指摘する栗田氏は、「出版文化に関するモノグラフ研究には、改造社(『改造』)、博文館(『太陽』)、実業之日本社(『実業之日本』)、講談社(『キング』)を対象とした調査・研究などすでにいくつかの前例があるが、京都という地域性や宗教=精神文化との関係という点で、日本心霊学会および『日本心霊』はまったく独特の位置を占めている。出版史から見れば、京都の出版業界は、近世における仏書出版中心の業界から、思想書や学術書を特徴とする業界へと変容していったが、その際に、日本心霊学会を経由したということになる」と述べます。
伝統仏教/霊術・民間精神療法/文芸・アカデミズムという、従来であれば別々に把握されてきたであろう領域が、日本心霊学会=人文書院という場を経由して流通性を維持していたとして、栗田氏は「この流通性が大正期京都という時空ゆえに成立していたとすれば、それを可能にした文化状況はいかなるものだったのか。近代以降も京都が東京に対して一方の文化的発信源であり続けてきたことや大正期の「心霊」の広範な流行を踏まえると、むしろ日本心霊学会の特異性こそが、出版文化史全体を見直す窓口となりうる」と述べます。
宗教研究と文学研究を架橋する別の足がかりも見えてくるといいます。宗教社会学では、新宗教における「生命主義的救済観」――宇宙・世界・自然そのものを一個の根源的な生命と捉える世界観に基づく救済観――がたびたび指摘されてきましたが、それは民俗宗教に根差したものとして捉えられてきました。栗田氏は、「それゆえ、文学者などの知的エリート層を担い手とし、モダニズム文学につながるような文学研究の『生命主義』との接続が試みられることはほとんどなかった。しかし、民間精神療法は、技法的には修験道のような民俗宗教に根ざしつつ、思想的には心理学や哲学や心霊研究といった近代的学知に接続し、特に日本心霊学会は宗教・民間療法と文芸を越境する道を歩んだ。宗教研究と文学研究の『生命主義』の交錯を考えるうえで最適の研究対象だと言える」と述べています。
そもそも戦後の新宗教研究の「生命主義的救済観」は、柳田国男や折口信夫らによって提唱された民俗学を参照していたといいます。近年の研究では、19世紀末の心霊研究と民俗学は新興の先端的な学知として、現在考えられているよりもはるかに近い位置にあり、また柳田や折口の学問形成もまた新たな宗教運動(近代神道運動)の1つとして捉えるべきだという指摘がなされているそうです。栗田氏は、「この観点において特に重要なことは、民俗学が霊性思想や宗教運動から袂を分かっていくというより、むしろその1つの展開として形成されたということだろう。例えば、折口信夫の『産霊』神の概念は、心霊研究と密接な関わりのなかから構想されていた」と述べます。「産霊」について考え続けているわたしも、これは初めて知りました。非常に興味深いです。
こうしてみると、新宗教研究の「生命主義」もまた、大正期以来の「心霊」の系譜の戦後的展開ではなかったかと考える栗田氏は、「この検証は本書の課題ではないが、ここで考えようとしているのは、アカデミズムの学知と在野または民間の知にまたがる思想史、精神史の問題である。この点で、民俗学の形成過程であった大正末から昭和初期に、『日本心霊』誌上で柳田や折口らの説がたびたび引用されていたことは興味深い。今村新吉や小酒井不木ら医学者との交流も含め、日本心霊学会=人文書院は、アカデミズムと民間の知の媒介する場として機能していたことも注目に値する」と述べます。
そして、栗田氏は「日本心霊学会=人文書院は、精神療法/仏教/新宗教/神道/民俗学/文学/哲学といった諸領域を横断しながら、アカデミズムと民間の知に股をかけ、心霊治療と出版という2つの媒体(メディア)――霊的=精神的な〈エネルギー/メッセージ〉の媒体――を軸にして一つの組織を維持してきた。こうした脱領域性と組織性という矛盾した特徴を兼ね備えることで、分野横断的な共振の相を1つの団体とその刊行物に折りたたんできたのである。日本心霊学会研究とは、そうした共振の相の変貌――振幅を伴ったある1つの精神史――を、単なる観念の共通性や思想の構造的類似を超えて、具体的な組織と運動に定位して探求する足場を組み立てることに他ならない」と述べるのでした。
第一章「日本心霊学会の戦略」の「はじめに」の冒頭を、横浜国立大学教育学部教授(日本近現代文学・文化史)の一柳廣孝氏は「人文書院の前身が日本心霊学会出版部であり、日本心霊学会が大正期を代表する霊術団体のひとつだったことは、近年徐々に知られるようになってきた。ここでいう霊術とは、直接的には催眠術を用いた治療法に端を発する、民間精神療法の総称である(詳しくは第二章を参照)。この療法を用いた人々は、精神療法家・霊術家などと呼ばれた。彼らはそれぞれ独自の理論を唱え、組織を整えて患者の治療や後進の指導をおこなった」と書きだしています。
1「日本心霊学会の理念とその特徴」では、「念写」や「千里眼」で有名な福来友吉がかねてから観念生物説を唱えていたことが紹介されます。福来が書いた『観念は生物なり』(日本心霊学会、大正14年)によれば、生物とは生命の働きをするものであり、生命の働きとは、要求実現の活動であるといいます。また、「精神は活動するために物質を必要とし、物質もまた、活動するために精神を必要とする。よって生命とは、物質に即した精神の活動、物心相即から生み出された活動である。したがって宇宙一切の活動はすべて生命の活動であり、宇宙そのものがひとつの生物ということになる。宇宙の一切の活動は、すべて物質と力の相即から生まれたものであり、その力とは精神だからである」と訴えています。
この福来の観念生物説が、日本心霊学会の主宰者であった渡邊藤交の説く心霊治療法の論拠になっています。『精神統一の心理』(人文書院、大正15年)で、福来は「生きると云うことは、結局する所、要求が物質上に働きかけて、そこに自己実現して行く過程」であり「只単に物質の運動それ自身が命でない。要求が物質を通じて、自己実現して行く刹那々々のプロセスの流れ、それが生命」であると述べています。したがって、強い要求実現の念は、物質それ自体のありようも変えます。いわゆる「観念力」です。
渡邊は、「心霊治療法とは何ぞやとの間に対し一言に約めて答えればそれは観念力によるのである。即ち術者の念力が機縁となって、被術者の生命力の機能を本然に復帰せしめるのである。従って心霊治療法は観念療法であると云ってよい」と言いました。福来の理論を吸収することで、渡邊の心霊治療法は他の霊術理論と一線を画することに成功したのでした。ちなみに、日本心霊学会と福来の関係はきわめて密接であると指摘し、一柳氏は「千里眼事件の影響で東京帝国大学を退くこととなった福来友吉は、その後、在野にあっても旺盛な活動を展開していた。大正6年には三田光一を知り、各地で念写実験をおこなうなど、福来は心霊研究に情熱を燃やし続けた」と述べています。
その福来の執筆活動を支えたのが、日本心霊学会でした。『透視と念写』(東京宝文館、大正2年)以降に福来がまとめた心霊関係の著述である『生命主義の信仰』(大正12年)、『観念は生物なり』(大正14年)、『精神統一の心理』(大正15年)は、すべて日本心霊学会から刊行されています。福来の代表作といえる『心霊と神秘世界』(昭和7年)もまた、日本心霊学会出版部を前身とする人文書院の刊行なのです。
3「人文書院の出版戦略」では、日本心霊学会出版部が人文書院に改名したのは昭和2年であると紹介されます。それから3年後の昭和5(1930)年11月に、警視庁は「療術講ニ関スル取締規則」を公布しました。一柳氏は、「以後、同様の規制が全国でおこなわれるようになり、一方で物理的な代替療法や家庭医学的な療法が普及していくことで、昭和10年前後から、霊術は徐々にその姿を消していく。その意味で日本心霊学会は、絶妙のタイミングで出版社へスライドしたことになる」と述べるのでした。
第二章「日本の心霊研究と精神療法」の冒頭を、龍谷大学世界仏教文化研究センター客員研究員などを歴任した近代宗教史・秘教思想史研究家の吉永進一氏は、「超常現象を調査する超心理学(パラサイコロジー)が生まれたのは、1930年代のことである。統計を駆使し、人間心理に問題を限定したことで、超常現象を科学的に立証しようとした。これが成功したか否かは、意見の分かれるところだろうが、人が超常現象にこだわり続けてきたということは確かである」と書きだしています。
科学的な研究は18世紀末の催眠術の誕生に始まります。催眠術は、19世紀半ば、アメリカで心霊現象をもとにした信仰体系(スピリチュアリズム)をもたらし、1882年にイギリスで心霊研究協会が結成され、心霊現象の科学的研究が開始されています。欧米では、催眠術から超心理学まで、科学の境界線上での議論が続けられました。吉永氏は、「それ自身の成果は不毛であったとしても、エレンベルガーが論じたように、霊媒研究が多重人格研究や力動精神医学をもたらしている。一方、日本では、催眠術につづいて心霊研究が輸入され、科学的な実験も早くから実現している」と述べています。
催眠術論争が最盛期を迎えた1880年代は心の科学にとってスリリングな時代でした。この時期、イギリスではメスメリズムから派生したもうひとつの研究が生まれました。1882年、ケンブリッジ大出身者を中心として結成された心霊研究協会です。1848年にアメリカで発生したスピリチュアリズムはまたたくまに西洋社会に広まっています。吉永氏は、「テーブルターニングやプランシェットのような霊と交流する方法が流行し、霊媒による交霊会も盛んに開かれた。社会現象としてのスピリチュアリズムはアメリカ生まれであるが、霊媒による霊との交流は、すでに19世紀前半、ヨーロッパで始まっている。もとは催眠状態の透視能力者が霊界を透視し、死者霊との交信を伝えたことに始まるが、メスメリズムとスピリチュアリズムの大きな違いは、前者は生者の精神力を強調し、後者は死者霊の存続によって超常的現象を説明しようとした点にある」と述べます。
これについて、19世紀後半、学者たちの態度は2つに分かれました。ひとつはウィリアム・ベンジャミン・カーペンターをはじめとする生理学的な心理学者たちで、心霊実験を心理的、生理的現象として説明しようとした。超常的な原因を考えなくても、すべては既知の科学法則で解明できるという立場です。一方、心霊研究協会に集まった人々は、霊魂説には懐疑的、批判的でしたが、科学説にも完全には同意できませんでした。吉永氏は、「生者の精神にはテレパシーや透視などの超常的能力があり、宇宙には日常を超えた次元がある――そのメカニズムは解明できないにせよ、調査結果を積み重ねていくと、否定はできないのではないか、というのが彼らの主張であった」と述べます。
2「日本の催眠術と心霊研究、その濫觴」では、明治時代において最も熱心に催眠術を紹介した人物として井上円了が紹介されます。円了は、新潟県の浄土真宗の寺院に生まれ、東本願寺の援助で東大文学部哲学科に学んだ、宗門のエリートでした。彼は真理を求めて哲学を学び、最終的に仏教こそ最高の哲学という確信を得て、『真理金針』『仏教活論序論』などのキリスト教批判、仏教擁護論を発表しています。吉永氏は、「彼の仏教論は、ベストセラーとなり、その後の仏教改革運動に大きな影響を及ぼしている」と述べています。
円了はなぜ、催眠術や異常心理学に関心を抱いたのでしょうか。まず、東大ではすでに外山正一が、イギリスの心理学者カーペンターの著書を教科書として用いて、スピリチュアリズム、催眠術について講義しています。明治20年、円了は「こっくりさん」を調査して生理的、心理的な現象として解明して『釈門哲学叢誌』『哲学会雑誌』に発表していますが、その理論はカーペンターによるテーブルターニング理論の翻案でした。吉永氏は、「つまり、円了は外山の授業を受けて、カーペンターのようなイギリスの最先端の心理学を知り、それを日本の現象に応用したということである」と説明しています。
円了の両面作戦(迷信否定、心理療法)を支えたのは、科学的というよりは、祈禱を排除する浄土真宗のエートスに由来するともいえるとして、吉永氏は「彼は、仏教的な究極的な実在である真如こそが真の妖怪であり、それに対する信仰はゆるぎない安心立命をもたらす、最高の心理療法であるとも述べている。円了は、世界を脱呪術化し、近代的な『こころ』観をもたらし、宗教的治療を心理学で根拠づけようとしたのである。円了の心理療法研究は、東大の精神科教授であった呉秀三に影響を与えたと言われる。さらに呉は、森田正馬に影響を与えている。あるいは、円了の迷信批判は、若手仏教者に影響を与え、『新仏教』誌を中心とする仏教改革運動でも迷信否定をうたっていた」と述べるのでした。
4「催眠術の興隆と変容」では、明治時代に催眠術の第一人者として強い影響力を持った桑原敏郎が紹介されます。桑原は岐阜県和知村の生まれで、高等師範学校に学び、静岡師範学校の漢文教師となりました。明治32年(1899)、『魔術と催眠術』という本を偶然読み、実践し始めたところ短期間で熟達しました。それだけでなく、病気治しに成功します。催眠術被験者による千里眼実験にも成功、修験の危険術も精神力だけで成功、さらには念力で物体を動かすことができたといいます。吉永氏は、「少なくとも彼は、その著書『精神霊動』中でそのように書き、そして多くの読者がそれを受け入れた」と述べています。
5「催眠術師の勃興と衰退」では、「催眠術は危険だから、法律で取り締まるべし」という意見も多かったことが紹介されます。しかし、大審院判事であった古賀廉造は、桑原俊郎の教えを信奉し、催眠術への法的規制をまったく認めない立場でした。こうしたこともあり、催眠術取締の法制化は順調に進まず、明治41年(1908)、「濫に催眠術を行う者は30日以下の拘留に処す」という警察犯処罰令(軽犯罪法)に終りました。吉永氏は、「この法律のために、医学者、心理学者らは催眠術を避けるようになり、催眠術実験は低迷する」と述べます。
6「養生、修養、精神療法」では、「霊術」という語が、もともとは、桑原の術をさして「霊妙なる術」という意味で使われたのであり、霊魂という意味はなかったことが紹介されます。それが、次第にスピリチュアリズム的「霊」の意味が加わっていきます。そして、霊妙不可思議な存在としての人間精神が心霊現象を起こしうるか否かという問題はすでに明治の末に一大ニュースとなり、学術社会では否定されたものの、療法の世界では「精神」の霊妙不可思議さはその後も維持されたのでした。
7「心霊研究」では、催眠術の流行によって「現象」が生み出される一方で、どう実験するのかという心霊研究の「作法」が輸入されたことが紹介されます。ヨーロッパの心霊研究を最初に紹介した1人は、東大宗教学初代教授の姉崎正治でした。明治36年(1903)、ドイツから帰国した姉崎は東大での授業で心霊研究を講じていたといわれます。本格的な心霊研究を行った団体は、明治41年(1908)に結成された心象会(心霊現象研究会)です。中心となったのは、元キリスト教牧師で日本教会の松村介石と平井金三でした。松村は元キリスト教牧師で、明治40年(1907)にキリスト教、儒教などの諸宗教を融合させた日本教会(後に道会)を設立しています。
平井金三は京都出身の英学者で、姉崎正治の英語の恩師でもあり、当時は東京外国語大学の教授でした。彼は明治22年(1889)に神智学協会々長オルコットを招聘、明治25年(1892)に渡米して26年(1893)に開催された万国宗教会議で演説を行っています。このアメリカ滞在中、心霊実験に参加しており、平井自身もサイコメトリー(物体の由来を“霊視”すること)能力を発現しています。吉永氏は、「2人は明治40年(1907)に知り合い、松村は日本教会をはじめるにあたって平井の宗教論に影響を受けただけでなく、心霊研究への関心という点で意見が一致し、知識人、ジャーナリストなどを集めて、心象会の発足に至っている」と説明します。
福来事件に代表される心霊現象をめぐる決着を、アメリカの場合と比較してみるとどうか。福来が影響を受けたウィリアム・ジェイムズは、批判を浴びながらも最晩年まで心霊研究を続け、ハーバード大の教授職を全うしていますが、その一方で、心霊研究の科学性をめぐっての考察も最晩年まで続けており、必ずしも心霊現象の「信奉者」ではありませんでした。吉永氏は、「心霊現象が実在するか否かについての学問的議論が続いた点は、透視・念写事件のあとも議論が続かなかった日本の場合とはかなりことなる。福来事件の結果、東京帝大を頂点とする公的な教育システムでは、心霊現象は誤謬、迷信、詐欺であり、客観的に存在しないものとされた。しかし、これが単なる建前であり、迷信的とされた世界観はむしろ根強く続いたことは、大正時代に入って、スピリチュアリズム書の翻訳が最盛期を迎えたことからも分かる。太霊道などの精神療法団体はこぞって透視やテレパシーなどの心霊能力養成を謳い、また大本教が鎮魂帰神の法を盛んに伝授して、信者数を増やしている」と述べています。
第三章「大正期日本心霊学会と近代仏教」では、そもそもプラクティスは仏教だけの問題ではなく、仏教に留まらない「宗教」の近代的変容に棹差していると述べられます。日本心霊学会が、仏教を超えた文脈を持つことは、「新宗教としての日本心霊」(『日本心霊』大正5年8月15日)という論説を巻頭言としても掲げていることからも自覚されているとして、吉永氏は「ここで言う「新宗教」は、現代の新宗教(新興宗教)の意味とは異なる含意を持つ」と述べています。
自由主義神学や比較宗教学の導入を刺激として、明治20年代以降に仏教のみならずキリスト教や神道など諸宗教で改革派が起こり、それをラディカルに突き詰めて諸宗教を融合した新たな「宗教」を構想する改革派宗教者や知識人が現れたという吉永氏は、「その延長線上に1899(明治32)年、東京帝大哲学科教授井上哲次郎の『倫理的宗教』論が登場し、諸宗教の本質は、いずれも倫理の根拠を内面に起こすことにあり、諸宗教の特殊性は競争の結果そぎ落とされ、最終的に普遍的な倫理的宗教に到達するであろうと主張して大きな反響を起こしていた。井上の倫理的宗教論は、宗教者のみならず、民間精神療法や修養論にまで大きな影響を与える」と述べます。
仏教界は初めから心霊治療を忌避していたわけではありません。むしろ日本心霊学会のみならず仏教界もまた、句仏心霊問題を契機に民間精神療法と手を切り始めました。吉永氏は、「この結果、日本心霊学会は新たな顧客の獲得を余儀なくされた。だが、穏健な改革を旨とした日本心霊学会は、メディア戦略で衆目を集めることにおいては太霊道に遠く及ばなかった」と述べます。日本心霊学会は、「心霊」の世界や民間療法への理解を示す医学者や著述家の著作を発行する出版社へと転身していったのです。
こうしてみると、日本心霊学会とは、自らの術を売り込む以上に共鳴する業界や人物を間接的に支援していくことにこそ、自己の存在意義を見出していたのではないかとして、吉永氏は「初期は仏教界を、後期は民間精神療法業界に肯定的な学者や作家たちを、である。つまり、日本心霊学会は、一貫して『外護方』」の団体だったのである。このような志向性ゆえに単なる権威付けとして著述家たちを利用するのではない姿勢を持ったのであり、その姿勢こそが日本心霊学会に出版社としての道を歩むこと可能にしたのである。そして、これこそが手段が目的となるという、プラクティスの近代の一つの徹底でもあったのである」と述べるのでした。
第四章「越境する編集者野村瑞城――『日本心霊』紙上の『神道』と『民俗』を中心に」の「はじめに」では、佛教大学大学院文学研究科歴史学専攻博士後期課程(日本近代思想史、神道史)の渡勇輝氏が、「近年の宗教思想史研究は、オカルト研究との架橋によって飛躍的に進展した。かつてオカルト研近代の合理的世界に対する非合理的世界への注目から近代社会の様々な問題点をあぶり出した。しかし、近年では一見して非合理と思われてきたものが、実はすぐれて合理的な言説を伴いつつ近代社会に浸透していく様子が明らかにされ、二項対立をこえた複雑な状況を解くために不可欠な領域であると認識されるようになってきた。『現代思想』が『陰謀論』の特集を組んだことは記憶に新しい」と述べています。
また、渡氏は以下のように述べています。
「このような相補的な問題を提起した吉永進一は、これまでの合理と非合理の反動サイクルという社会モデルに対して、歴史的な視座から『呪術の近代化』を指摘し、その顕著な例を民間精神療法団体の活動にみた。民間精神療法団体は、その療術の理論を当時の先端的な学知と技法にもとめ、メディアを効果的に活用することによって、自らが最も『科学』的であろうと競争くりひろげた。その光景は『科学』と『宗教』という二分法に慣れた近代的な視点からは見えざる領域として位置していたが、栗田英彦はその闘争の政治性に着目し、霊術を好事家的対象から霊術を好事家的対象から現実社会の問題に解放している。こうして近年、『宗教』概念そのものの問いなおしが進むと同時に、『科学』とも「宗教」とも言えない豊穣な言説空間の存在が明らかになってきた」
心霊研究と民俗学の関係は、これまでも多くの議論がなされてきました。なかでも大塚英志は、柳田国男とオカルトとの関わりに注目し、その思想の近似性を指摘しています。しかし、渡氏は「ここには横山茂雄が指摘するように、心霊研究と民俗学がともに19世紀後半に勃興した新しい学知であったことが注意される。とくに柳田民俗学においては、岡安裕介が指摘しているように精神分析との交渉が色濃く示されており、心霊研究もまた心理学の成果を有効に援用したことが一柳廣孝によって明らかにされている。ここに両者は、世紀転換期に最先端の学知として流入した学問の鬼子として現出するのである」と述べます。
2「『シヤマニズム』の傾倒と『神道』の発見」では、そもそも柳田は、明治期から「天狗の研究をして居るといふ」噂が文学界でたつ「魔界の現象」の探求者であったと指摘します。柳田は大正7年(1918)には中村古峡の『変態心理』に「幽霊思想の変遷」を寄稿しており、この頃から本格的に心霊研究関係の編集者の目にも留まり始めたものと思われます。その中で、『日本心霊』の編集者であった野村瑞城は柳田を発見し、「ミコ」が太古に重要な職能をもち、病気治療も行っていたことを取り入れていくのでした。
ただし、渡氏によれば、この頃の野村は数多くの古代史研究者の1人として柳田を参照していたに過ぎませんでした。野村はある記事で、「土俗研究家として知られてゐる柳田国男氏」を引きつつ、「死霊恐怖の面影」として竹串を立てる風習に触れています。これは「幽霊思想の変遷」の内容であり、野村が『変態心理』の同論を読んでいたことを示すものであると指摘し、渡氏は「その目的は『未開人は未だ開けざる文化人であったに拘らず、神秘に対する感覚は遥かに我々より優れてゐた』ことを明らかにするためであり、西村眞次や喜田貞吉、久米邦武、木村鷹太郎など多くの古代史研究者の説が参照されている」と述べています。
渡氏は、西村眞次がはやく明治39年(1906)にメーテルリンクの『神秘論』を翻訳していたことは関係しているかもしれないと推測します。『日本心霊』は大正10年(1921)の第133号からしばらく、「本会の提唱する心霊治療法は英国心霊研究会及び世界的神秘哲学者メーテルリングの意見と合致する霊能現象たり」という宣伝文句を掲げており、大正9年(1920)には大阪毎日新聞社の高田元三郎がメーテルリンクの『永遠の生命』を訳したことを受けて、『日本心霊』でも改めてメーテルリンクの紹介がなされています。渡氏は、「野村にとって、西村は古代史研究の先端的存在であったのみならず、心霊研究の先駆者でもあったのである」と述べるのでした。
3「『フオクロリスト』の自覚と柳田国男への接近」では、「憑り代の髯籠」という折口信夫の言葉を意識した記事が認められることが紹介されます。渡氏は、「折口もまた近代神道へのするどい批判者であったように、こうして野村は主な参照軸を西村眞次から柳田国男らへと移すことによって、原始神道論を離れて現状批判的な立場を強めていくのである。一見して、西村眞次から柳田国男へという移行は、民俗学ないしは土俗学の内部での些末な問題に見えるかもしれない。しかし、この二人は昭和2年(1927)に『民族』誌上で「史実」をめぐって論争を交わしていた」と述べます。西村は後年「餘りにも粗放な推論」として「木村鷹太郎氏、柳田國男氏などの啓蒙運動」を並べて挙げますが、渡氏は「これはたんに柳田と偽史言説の近似性という問題以上に、彼らを新しい歴史叙述の運動の一環としてとらえる必要があることをよく示すものである」と述べています。
4「脱退、その後の『神道』と『民俗』」では、はたして心霊研究の過程で野村が辿り着いた民俗学とは、野村だけが見つけられた特異なルートだったのだろうかとして、渡氏は「おそらく、そうではないだろう。柳田は『変態心理』の中村古峡と交流があり、同誌の編集者であった北野博美は折口信夫と親密な関係にあったのみならず、野村とも接点をもっていた。また、柳田が重視したのは『心意』であり、自身の研究を『実験の史学』と称していたことは、この観点からもっと注目されてよい。民俗学と心霊研究は『実験』という体験の概念をもってすぐ隣に位置していたのであり、今後さらなる相互検証が必要であることを、野村の軌跡は教えてくれる」と述べます。
「おわりに」では、野村は仏教思想史、原始神道論、柳田民俗学と依拠する主軸を次々に移していきますが、これらはいずれも仏教者の社会進出、世界大戦後の学問潮流、神道批判と、時事的な批評性をもつ先端的なテーマであり、即座に摂取して紙面に反映させる敏腕な編集者としての姿がそこにあったと指摘します。そして、これらの記事のほとんどは野村の独力によって作られたものでしたが、野村の軌跡は民俗学と心霊研究の思想的近似性でもある点で、今後のより詳細な相互検証が求められるとして、渡氏は「とくに野村の活動で特筆されるのは、仏教や神道、歴史や民俗という枠組みをなんなく越えていく縦横無尽な越境性と超域性である。むしろ、そのような枠組み自体が、細分化された現在の学問がつくった領域であったことに気づかされる。この野村の機動力の源泉が心霊という領域にあるとすれば、この広大な領域をいかに研究の視野に入れていけるかが今後の重要な課題になるだろう」と述べるのでした。
「西田・折口講演解題」では、その冒頭を、京都大学人文科学研究所助教(民俗学)の菊地暁氏が「昭和5(1930)年5月17日、東京の民俗学会と京都の民俗学研究会の合同により、京都帝国大学楽友会館にて民俗学大会が開催される。参列者は200名を数え、西田直二郎『年中行事と民俗研究』や折口信夫『門』の講演が行われた」と書きだしています。菊地氏は、日本民俗学の歴史は雑誌で区分すると便利だとして、萌芽期の『郷土研究』(1913~17)、発展期の『民族』(1925~29)と『民俗学』(1929~33)、確立期の『民間伝承』(1935~57[発行・民間伝承の会])と紹介します。
このうち、昭和5年の民俗学大会を共同主催した民俗学会は『民俗学』を発行する団体でした。菊地氏は、「柳田國男(1875~1962)が若き同志と共に創刊した『民族』は、やがて、ゆるやかな全国的ネットワークを指向する柳田と、ディシプリンとしての自立を指向する岡正雄(1898~1982)ら若手学徒との方向性の違いにより休刊、それを受けて創刊されたのが『民俗学』であり、若手学徒たちに推された折口信夫(1887~1953)が代表を務めることとなる」と述べています。
折口と西田は大阪・天王寺中学の同級生として旧知の仲でした。2人の同級には、歴史学の岩橋小弥太(1885~1978)や国文学の武田祐吉(1886~1958)も在学。彼等は、図書館で記紀や万葉集を読み漁り、休日には南河内や大和の史跡を訪れていたそうです。折口『死者の書』には難波から二上山を経て飛鳥へ至る道のりの細やかな描写がみられますが、これは西田にとってはまるで中学時代の「旅の思い出の記録」だといいます。

『決定版 年中行事入門』(PHP研究所)
菊地氏は、「そのような二人が、昭和初年、奇しくも東西の民俗学団体の代表となり、合同大会を主催するに至ったわけだ」と述べます。西田「年中行事と民俗研究」は、民間に伝承される年中行事の研究意義を概説したものでした。葵祭や櫛の呪力など、古今東西の事例を扱い、フレイザーやマスペロにも言及しつつ、年中行事が古代生活や民族思想を示す有力な史料であることを論じています。じつは、拙著『決定版 年中行事入門』(PHP研究所)を書いたとき、わたしは柳田の『年中行事覚書』とともに西田の年中行事論を参照したことを告白します。
「あとがき」には、栗田英彦氏が吉永進一氏について次のように書いています。
「吉永先生は、学知と在野の知の越境者であった。といっても、ある種の体系化された知を市民的労働者の住まう世俗に注入するのでもなければ、逆にそうした世俗の動向に阿るのでもない。むろ、在野の深淵を、世俗化した学知と学知化した世俗に覗かせるような意味での越境者であった。その深淵に魅了された者を、論文や研究会だけでなくブログやSNSを駆使しながらオルグして同志を集め、さまざまな国内外の共同研究を通じて、まさに近代宗教史ひいては近代史を史観のレベルから塗り替えようとしていた」
その吉永進一氏が、本書準備中の2022年3月31日に亡くなられました。栗田氏は、「心の準備をしていたつもりだったが、今でも、言いようのない感情とともに「早すぎる」という言葉が頭をもたげてくる。本当に早すぎるのである。本書でも、病と闘いながらも『木原鬼仏から渡邊藤交への術の系譜』についての新稿を書き下ろそうされていた。その飽くなき知的欲求は、肉体の限界を超えて永遠であるかのようにも思えたのである」と述べています。わたしも、吉永氏の著書はすべて拝読しましたが、神智学の再発見など非常に学びを与えられました。謹んで、故吉永進一氏の御冥福をお祈りいたします。合掌。