- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2295 心霊・スピリチュアル 『日本最後のシャーマンたち』 ミュリエル・ジョリヴェ著、鳥取絹子訳(草思社)
2024.01.09
1月1日に発生した能登半島地震について、石川県は8日午後、死者が168人になったと発表しました。亡くなられた方々の御冥福を心よりお祈りいたします。遺された方の中には、霊であってもいいから故人と会話をしたい方もおられるはずです。『日本最後のシャーマンたち』ミュリエル・ジョリヴェ著、鳥取絹子訳(草思社)を紹介いたします。著者はベルギー生まれの日本学者で、1973年から日本在住。早稲田大学と東京大学で社会学を勉強、東洋学博士。上智大学外国学部フランス語学科の教授を34年間務めたあと、2017年から名誉教授。日本社会に関する著書多数。うち邦訳は『子供不足に悩む国、ニッポン』(大和書房)、『ニッポンの男たち』(筑摩書房)、日本向け書き下ろしに『フランス新・男と女』(平凡社新書)、『移民と現代フランスーーフランスは「住めば都」か』(集英社新書)などがあります。
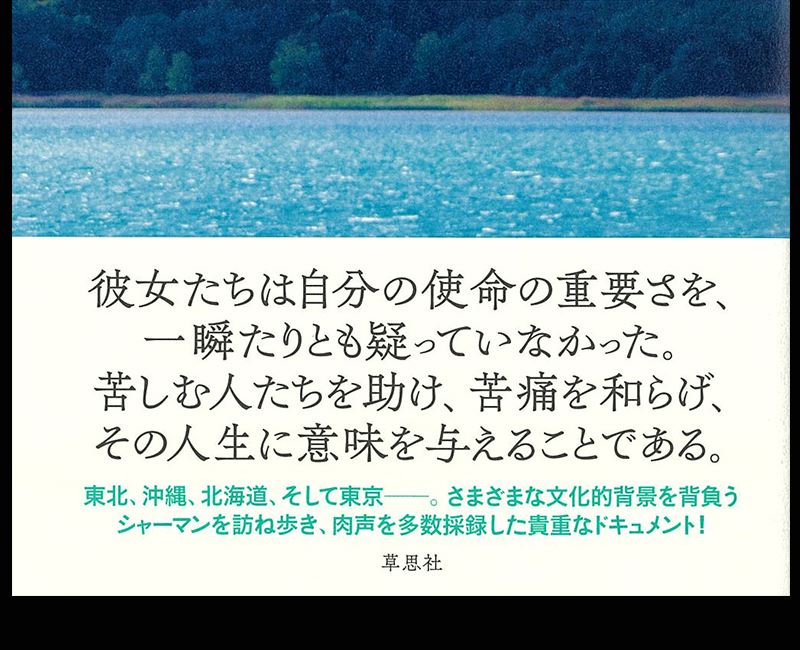
本書の帯
本書の帯には、「彼女たちは自分の使命の重要さを、一瞬たりとも疑っていなかった。苦しむ人たちを助け、苦痛を和らげ、その人生に意味を与えることである」「東北、沖縄、北海道、そして東京――。さまざまな文化的背景を背負うシャーマンを訪ね歩き、肉声を多数採録した貴重なドキュメント!」と書かれています。
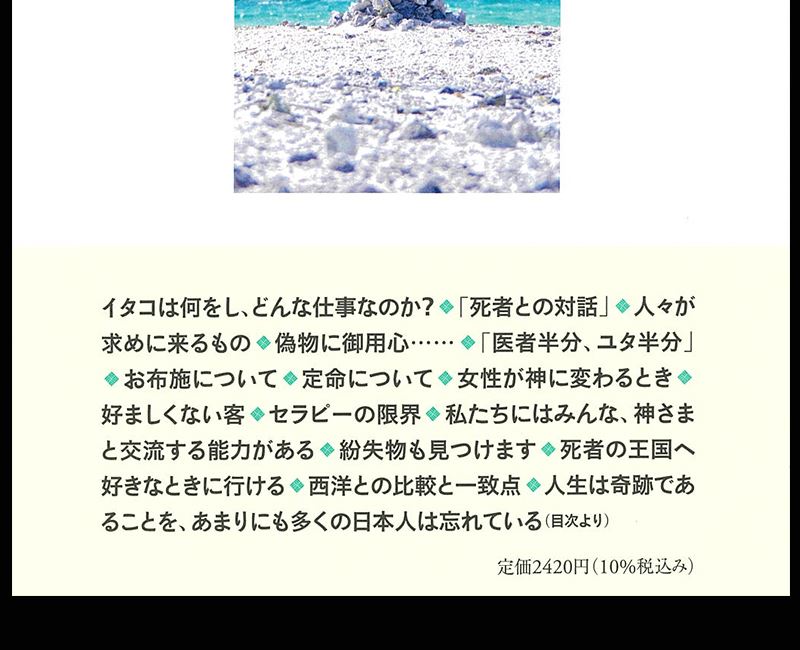
本書の帯の裏
帯の裏には、「イタコは何をし、どんな仕事なのか?◆「死者との対話」◆人々が求めに来るもの◆偽物に御用心・・・・・・◆「医者半分、ユタ半分」◆お布施について◆定命について◆女性が神に変わるとき◆好ましくない客◆セラピーの限界◆私たちにはみんな、神さまと交流する能力がある◆紛失物も見つけます◆死者の王国へ好きなときに行ける◆西洋との比較と一致点◆人生は奇跡であることを、あまりにも多くの日本人は忘れている(目次より)」と書かれています。
カバー前そでには、「私がこの本を心から書きたいと思ったのは、なによりシャーマンがいなくなると、日本人の魂の一部も消えることになると思ったからだ。今後しばらくは奄美大島や沖縄では生き延びるだろう、需要はいまも非常に多いからだ。しかしシャーマンは東北(青森県の八戸、恐山)でも、同じく北海道でも消滅の危機に瀕している。(本書より)」「半世紀にわたり日本に在住するベルギー生まれの日本学者が、不可思議な世界の人々との交流を綴ったユニークな記録」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序文
第1部 イタコ
第2部 沖縄
霊魂「商売」
新納和文さん、ユタ(51歳)
栄サダさん(79歳)
肥後ケイ子さん
沖縄――久高、伊平屋島、座間味
伊平屋島――神々と伝説がいまも息づく手つかずの島
2017年9月2日、座間味島で出会った
カミンチュ、サチコさん、72歳
第3部 東京ほか
鶴見明世さん
マリア――魂の傷を治す
コスモライト石橋
ミカさん:「自分を霊能者とは思っていないけれど、
人には見えないものが見えます……」
第4部 北海道
アシリ・レラ――平取のアイヌのシャーマン
結論 最後のシャーマンを称えて
「謝辞」
「参考文献」
序文の冒頭には、以下のように書かれています。
「『魔女』の本で、ミシュレが言っていたのは、中世前期の女たちは、一人で農場や森にいたということだ。(……)男は、十字軍や主の戦争に行っていた。それだから女たちは、一人で、キツネやリス、鳥たち、木々と話すようになった……。――マルグリット・デュラス『語る女たち』より」
「霧のロンドン」で、何をするにもきっかけとなるものがあるとして、著者は「私の場合、それは三浦清宏の著書『イギリスの霧の中へ――心霊体験紀行』(南雲堂、1983年)だった。1987年、『長男の出家』で栄えある芥川賞を受賞した小説家で心霊研究者の三浦は、特異な経歴の持ち主で、明治大学の教授時代、1年間の研究休暇をイギリスで過ごし、想像しうるかぎりの霊媒師の研究をした」と書いています。
日本とイギリスはお互い島国(車が左側通行なのも同じ!)という特徴があり、有名なロンドンの霧は墨絵に描かれる濃霧と比較することができるだろうとして、著者は「それとは別に、日本語は全体に霧のかかったような言語で、言葉に曖昧なニュアンスを入れたほうが日本語風になる。イギリスにいるとよく考えるのだが、島国であることが実際、精霊――またはゴースト――を出没しやすくしているのではないだろうか。イギリス人は自宅の庭に咲く花の話をするように妖精の話をする」と述べています。
「日本の霊に近づくのは難しい」では、三浦清宏から、同じテーマで研究を進めたいという手紙を送った著者を気落ちさせるような返信をもらったそうです。著者はそれを大切に保存していました。三浦の説明によると、この種の研究が難しいのは、日本にはイギリスの「心霊現象研究協会」や、「英国スピリチュアリスト協会」に相当する組織が存在しないからということでした。日本にあるのは「日本心霊科学協会」だけで、そこでは心霊現象や超心理学に関連する資料なら調べられるということだったのです。
三浦が難しいと考えているのは、日本では、見えない世界は神道や仏教に通じ、そこに各地方の民間伝承が加わるところにあるからでした。各地方にはそれぞれ特有の土着信仰や霊界、守護神、守護霊があるというのです。著者は、「たとえば『山伏』は、自然のなかで苦行や禁欲生活をして神秘的で精神的な力を取得するのだが、これらの修行は仏教や神道の秘教でも要求されている。修行僧は霊界の存在を信じており、それは彼らに固有のもので、門外不出とされている。その儀式は極秘で、秘密結社を連想させる。そして三浦は、これら3つの分野の共通点を観察する研究が不足していることを残念に思っていた」と述べます。
物事をさらに複雑にしているのは、三浦によると、日本には自然霊もあることです。最も知られているのは天狗霊や龍神、狐霊、狸霊で、他にもたくさんあります。著者は、「それゆえ『お祓い』のとき、霊媒師は霊に人間の霊なのか動物霊なのかを聞くのである。したがって見えない世界は、日本では仏教の密教や神道、アニミズム、自然霊や動物霊に属するものとなる。それはそれとして、三浦が考えるのは、精神世界は人間によって想像または創作されたものだとしても、そこには固有の実態があり、短絡的に空想上の分野に追いやるべきではないということだ。まずはこれらの霊の実態を認めることが望ましく、私が社会学や精神分析学の枠組みに縮小して研究するのは残念なことだと考えていた」と述べます。
「非常に広い意味でのシャーマン……」では、著者は「シャーマン」を非常に広い意味でとらえ、著者の研究は超感覚や超知覚能力のある人をすべてカバーしていることが明かされます。ちなみにほとんどのシャーマンは他の職種で仕事をしているとして、著者は「タロット占い、催眠療法、写真カウンセラー、人生相談、神の媒介者―-沖縄では、ずばり『カミサマ』――、チャネラー、口寄せ(故人との対話)、民間治療師などだ。また沖縄では、ノロとユタ、カミンチュとカミサマの区別は曖昧になっているとしても(「私は全部です」と言う人もいた)、ほとんどは持って生まれた才能の持ち主で、あなたの人生の現在や過去が本に書かれているようにはっきり見え、多くは電車にでも乗るように気軽に天体の世界にワープしていく……」と述べています。
「カミサマ」と呼ばれる彼女たちの多くと著者は良き友人になり、一緒にコーヒーを飲みながらいまでも楽しい時間を過ごしているそうです。著者は、「一緒にいると、彼女たちの話題は尽きず、スマホでスピリチュアルな写真を見せてくれたりして、退屈することがない。彼女たちが惜しみなく明かしてくれる霊的な話を聞く特権を持つには、日本風に静かな物腰で、事を荒立てずにアプローチしなければならなかった。私の誠意はあえて示す必要はなかった、というのも、彼女たちにはインタビューを引き受ける前に『見えていた』からだ(多くの人はあとで私に言った)」と述べます。
「歌舞伎、とくに能はさまよう霊に取り憑かれている」では、著者は「女性をだまし、見捨て、虐待した者に不幸あれ! フランスでは諺で「復讐は冷やして食べるのがいちばん」〔復讐は熱く反応するよりも、長い時間をかけて冷えた状態でするほうが効果的で満足できるという意味〕と言われるように、ひどい侮辱を受けた者が死後、時間をかけて亡霊となってあらわれれば、相手を恐怖で震えあがらせることができるという。日本の能や歌舞伎の演目には裏切られた女性が多く登場し、恨みを理由に出没している。すぐに思い浮かぶのが『四谷怪談』で、裏切られた女性が幽霊となって何度もあらわれ、加害者を恐怖に陥れる物語だ」と述べています。
歌舞伎には幽霊の話が山のようにあり、中には女性が化け猫に変身し、夜中にこっそり行燈の油をなめる場面もあります。「蘭平物狂」など、主人公が刀の霊に取り憑かれ、その霊に動かされて通りがかりの者すべてに斬りつける物語も多いと指摘します。「能に出没する幽霊」では、著者は「能の演目の大半は幽霊物で、能面の隙間から漏れ出る不気味な声はまさに幽霊を連想させる。能面をかぶった『幽霊』のほとんどは何か仕返しをすることがあり、最後に僧侶があらわれて、数珠をこすりながら念仏を唱え、幽霊のお祓いをして解決することになっている」と述べます。
超自然的な世界は村上春樹や吉本ばなな(『とかげ』新潮社、1996年)といった多くの現代文学の作家の作品にも見られるものだと指摘し、著者は「私が思い浮かべるのは、坂東眞砂子の小説で、映画にもなった『死国』(マガジンハウス、1993年)で、タイトルは四国と死をかけたものだ。このホラー作品の舞台となっているのは四国で、死者を蘇らせるには、八十八カ所の霊場(1400キロ)を死者の歳の数だけ時計と逆回りに巡るという儀式が土台になっている。また、幽霊とは一見関係のないように見える映画『鉄道員』――主演は高倉健――では、幼くして亡くなった娘が、生きていればその年齢になった頃に何度もあらわれている……」と述べます。
「日本には百以上の妖怪が出没」では、日本ではお化けや化け物が幽霊と同じに見られていると、著者は指摘します。ところが化け物には、動物や植物、鉱物に由来するものや、無機質の物体の発散物に由来するものまであるとして、「そこへ新しくあらわれたのが物の怪で、宮崎駿のアニメ『トトロ』もこの部類に入るだろう。同じく『千と千尋の神隠し』で千の後をついていく黒い影は、間違いなく妖怪だろう。超自然的な力を持ち、古い歴史を持つ妖怪は、悪意のある悪戯好きが多く、人間をからかって怖がらせては楽しんでいる。最も知られているのが鼻の長い天狗や、赤や青の角をつけた悪魔の一種の鬼で、鬼は黒澤明の映画『夢』にも出てくる」と述べます。
「無機質の物にも魂がある」では、2018年5月2日付の『ジャパン・タイムズ』の記事に、千葉の幸福寺(日蓮宗)の僧侶が、犬のロボット・アイボの供養を行なったことが書かれたことが紹介されます。この供養のために、寺には800体の亡くなったアイボが送られてきたそうです。アイボの元飼い主の女性の1人は、アイボの魂のために祈ることができるのを知って「安心した」と語りました。別れなければならないと思うと涙をおさえることができなかったからだそうです。著者は、「供養されたあとのアイボは、修理用の『臓器』提供者になることが明らかになっている。私はペットロス症候群の話は聞いたことがあるが、この『死の悲しみ』がロボットにまで広がるとは想像もしていなかった」と述べています。
「津波後の幽霊」では、2011年3月11日の東日本大震災後、東北大学教授[現在は関西学院大]で社会学者の金菱清氏が、ゼミの学生に震災で発生した幽霊の調査をするように提案したことが紹介されます。その研究成果が、一条真也の読書館『呼び覚まされる 霊性の震災学』で紹介した本です。著者は、「あの震災で1万5897人が亡くなり、2534人がいまだに行方不明(2019年3月8日現在)という事実を知ると、東北にこれらの苦しむ霊が出没してもなんら不思議ではない。仮設住宅に住む人たちもまた、自宅の座布団に亡くなったはずの隣人が『まるで生きているように』座っているのを発見し、その人たちに『あんたはもうこの世にはいないんだよとは、どうしても言えなかった』と語っている」と述べています。
第1部「イタコ」では、東北のイタコが取り上げられます。「盲目の女性たちの悲しい運命」では、イタコになることは、生まれつきや、病気または事故で目が見えない女性たちに与えられた受け皿の1つだったことが指摘され、著者は「盲目の女性が東北地方に比較的多いのは、貧しい食糧事情が原因とされることもある。寒い地方で、雪が多く、食べ物が不足していたからである。語り継がれていることによると、受け皿としての『イタコ』の前は、5年に1度、『口減らし』のために子どもを殺していた。『口減らし』という言葉は、子殺しを正当化するために使われた『間引き』と同じ意味である」と述べています。
社会階層のいちばん下に追いやられた盲目の女性たちは、蔑まれ、娼婦や物乞いと同じようにみなされていたといいます。障害を因果応報とされていたのです。一方、学術研究者のウィルヘルム・シファーは、宗教学者の堀一郎を引用して研究をさらに進化させ、「遊女」という言葉と「遊行する女性」を結びつけたことを紹介し、著者は「その生活様式はいわゆる旅芸人と近く、旅芸人自体、一時的な売春と関連づけられていた」と述べます。
瞽女〔盲目の女性芸能者〕はまた別の受け皿でした。著者は、「『門付』――人家の門口に立って芸能を見せ、金品を受け取る旅芸人――で知られるこの女性たちは、雪深い東北地方を、目が少し見える案内役の女性の肩に手を置いて3、4人が続き、1日に20キロを歩いてまわっていた。彼女たちは民家の門口に立ち止まり、三味線に合わせていわゆる瞽女唄を歌っていた。家人が与えたのは米一合のことが多く、彼女たちはそれを托鉢僧のように布袋で受け取っていた……。石を投げられることもあった。身を守ることができなかった彼女たちは、痛いとは一言も言わずに避難した」と述べます。
「差別され、社会の底辺で生きる」では、イタコは二重に差別されていたことが指摘されます。目が見えないことに加え、仕事が死に関係することで、社会階層のいちばん下に追いやられたままだったとして、著者は「それに対して1つ、妥当と思われる解釈がある。それはアメリカの人類学者、マリリン・アイヴィーが提案するもので日本の資料では見当たらない。テーマがタブーと言わないまでもデリケートだからイタコという言葉は実際、長く日本の社会で差別されていた部落民の『穢多の子(エタノコ)』を意味するというものだ」と述べます。また、「イタコの仕事」として、著者は「イタコは生者と死者のあいだをとりもつ仲介者と同義語になったとはいえ、伝統的にはお祓いや(健康や家族のために)、守護神の『オシラサマ』を呼び出して神にお伺いをたてる仕事もしていた」と述べるのでした。
「恐山――死のテーマパーク」では、巡礼地の入口にある恐山菩提寺本坊の曹洞宗・円通寺は、イタコが境内の外にいるのは大目に見ていますが、案内板にはわざわざ「恐山の寺とイタコには何の関係もありません。恐山寺務所へイタコについての問い合わせ等をされないようお願いします」と明記していることが紹介されます。したがって、彼女たちは寺の外にテントを張り(イタコマチ)、いっこうに減らない要望に応えています。なぜなら、年2回、旧暦のお盆と秋分に開催される恐山大祭には、現在も少なくとも2万人が訪れているからです。著者は、「これらの日付は、春と秋の年2回、山に入る信仰〔お山参り〕と関係がある。春先は、農民たちが稲田や耕作地を守ってもらうために入山して山の神を迎え、秋は、収穫に感謝して神を山の頂上まで送って行ったのだ」と述べています。
「絶滅危惧種」では、明治政府が日本の近代化のために「祈禱師」を排除し、医学を推奨しようとしていた1873年頃、イタコの数は200人ほどだったと紹介し、著者は「この魔女狩りがうまくいかなかったのは、お国のために死んだ兵士(日清戦争の日本人兵士の死者は約1万3800人、同じく日露戦争は約8万4000人)と対話したいという要望が減ることはなく、とくに遺体が見つからなかったケースが多かったからだ。同じ現象は、2011年3月11日の大震災後にも起きている。大津波に襲われ、現在もまだ遺体が見つかっていない人が2534人もいるからだ(2018年12月10日現在)。前述の松田によると、イタコは1980年代にはまだ300人前後いたそうだ」と述べます。
「1918年頃の承認儀式」では、イタコの承認儀式について詳しく説明されます。正式にイタコになる前の約2週間、弟子たちは修行の最後に五穀を断つ「穀断ち」や、火を通した食べ物を断つ「火の物断ち」、塩や塩味を断つ「塩断ち」など、いわゆる「断ち行」をして身を浄めなければならなかったといいます。それに加えて肉や魚を断つ「精進潔斎」や、冷水で身体を浄める「水垢離」の儀式もありました。著者は、「正式なイタコになる前の儀式は、3つの軸で組み立てられていた。寒さに対する耐久力(水垢離の儀式で)をつけ、睡眠と食べ物を自ら断つことである――意識を失うまで行なうことで、修行者の守り神が降りてきてその名前が明らかになった」と述べています。これらの証言で一致しているのは、死ぬかもしれないと思ったときに突然、外部の力に満たされ、それで命を維持するだけでなく、さらにはエネルギーを授かって、儀式を最後までやり抜く気持ちにさせるという事実です。
「儀式道具の伝達」では、「最後のイタコ」と呼ばれる松田広子の修行について紹介されます。「オダイジ」では、「長さ20センチほどの筒は、その名のとおり非常に『大事』なものである。というのも中には最後の試験を終えたときに師匠が入れた免状が入っているからだ。筒の中身は秘密で、誰にも見せてはならないとされている。松田の筒には、19本の竹棒を麻の紐で縛ったものと、熊野大社の八咫烏のお札が入っている。ちなみに19は彼女が独り立ちしたときの年齢である。この筒は専用の布で包んで紐がつけられ、イタコはどんな儀式のときも背中に背負っている。いっぽう民俗学者の柳田國男は、管(竹筒)につきまとう秘密っぽさから、民間伝承の憑き物の種『管狐』と結びつけている」と説明されています。
「苛高数珠」では、激しくこすって高い音を出させる「苛高数珠」が紹介されます。長さは1・5から2メートルですが、これはイタコをトランス状態にして死者と交信できるようにするための最高の道具です。直径1・5センチほどのムクロジ(無患子)の珠300個でできている数珠は、仏教徒が使うもっと小粒の108個(仏教でいう煩悩の数)の珠からなる数珠とは異なっている。「オダイジ」とともに、神や仏と接触するために欠かせない道具で、経文を唱えることで魂がそのなかに入る(魂入れ)とされているとして、著者は「両端には、いまや保護種になっている日本カモシカの骨や鹿の角、猪やほかの動物の牙、熊の爪、鷹の爪、狼の骨、小哺乳動物の上顎(何の動物かはわからないことがあるが、多いのはキツネ)などがついている。さらには貝殻や珪化木、天然石のスモーキークォーツ、あいだには穴のあいた古銭もはさまっている。牙や爪は『魔除け』で、憑き物や悪魔をお祓いするためのもの。子どもの『癖の虫』や夜泣きを鎮める効果もあるとされていた。江戸時代末期から明治にかけての古銭『天保銭』は、なかでもとくに冥土で三途の川を渡るためのお金である」と述べます。
「オシラサマと遊ぶ」では、イタコの重要な仕事の1つである「オシラサマ遊ばせ」が取り上げられます。オシラサマとは、桑の木に大ざっぱに彫刻された2本の棒で、1本は女性の顔、もう1本は馬または男性の顔になっています。布を着せられ、首のあたりを鈴で束ねられているのですが、毎年、新たに布が重ねられることから、各家に先祖代々伝わるオシラサマの年代がわかるようになっています。「オシラサマ遊ばせ」と呼ばれる儀式は、中国から来た長い物語と関係があるとして、著者は「昔、ある長者の娘が父の飼っている馬に恋をしてしまった。娘が馬に、もし人間だったら結婚したいと言ったところ、今度は馬も娘に恋をしてしまった。しかし、馬が食欲をなくした原因を知った父は怒り狂い、馬の首を切ってしまった。そのあと、娘は馬と一緒に天に飛び立ち、神になった。この昇天により、天から大量のカイコが降ってきたという」と紹介します。
この「オシラサマ」に関する昔話は、柳田國男の『遠野物語』にも登場します。この不思議な物語との関係を長期にわたって研究した「Shamanism in Japan(日本におけるシャーマニズム)」(『Folklore studies』誌、南山大学、1962年)の著者、ウィリアム・フェアチャイルドは、起源はシベリアやアイヌ(アイヌに存在する「シラツキカムイ」という木の人形)の伝統にまでさかのぼるとし、郷土史家の江刺家均は、「オシラサマ遊ばせ」のおもな機能は「五穀豊穣」や「大漁」の祈願で、家族を飢餓から守るためだったと説明しています。
「『死者との対話』の流れ」では、7月20日から24日の恐山大祭では、「口寄せ」のだいたいの流れをつかむことができると紹介しています。まずイタコは依頼者に接触したい人の名前と生年月日、亡くなった日を聞いたあと、呪文を3分間ほど唱え、そのあと死者の霊がイタコに憑依するとすぐ交信が始まります。著者は、「続く3分から5分のあいだ、死者はとぎれることなく話しつづけるのだが、最初は決まって、依頼者がわざわざ遠くから来てくれたことに『遠いとこ、よう来た』とお礼を言い、それから『先にいってしまって、申し訳ない』と謝りつつ、何かあったら夢に出てくるからと約束する。続いて、災難がくるかもしれないから気をつけるように、あるいは感情移入したかのように『人間関係で悩むことがあっても』とほのめかし、故人はあの世でちゃんと見守っているから安心するようにと言う。それから突然、イタコは話題を変え、故人に何か聞きたいことはないかと客に尋ねる。質問は1回しか許されていないのだが、しかしその答えには客の心を慰める効果があり、動揺させることも多い」と説明しています。
「金になる?」では、明治政府が組織的に呪術師狩りを展開したとき、霊能者は人々の信じやすさにつけこみ、死者から生者に復讐や「たたり」があるという恐怖を利用して、大儲けしていると非難されたことが紹介されます。著者は、「じつはイタコは、自宅での口寄せは1回につき5000円しか受け取らない。時間は20分ほどで、注連縄――神聖な境内の境界を示し、悪霊をつかまえるとされるで――のついた小さな祭壇の前で行なわれる。それでも礼儀として知っておいたほうがいいのは、神仏には果物やお菓子、酒、蠟燭や線香などのお供えをするということだ。そして忘れてならないのは、長いあいだ、この仕事は目が見えない女性の唯一の生き残り手段だったことと、1950年代初頭以来、組合がつくられて、統一料金で保護されているということだ」と述べます。また、「受け皿? 神の啓示?」では、イタコになるのは神の啓示ではなく「受け皿」であると指摘し、著者は「私が聞いたあるイタコのインタビューで、彼女は『繰り返し夢を見た』とか『神のお告げ』とか言っているが、しかしこれは伝統的に、目の見えない女性たちが家族の世話にならないための仕事の場だった」と述べます。
「人々が求めに来るもの」では、著者は「2万人もの人々――とくにお盆の時期――いまも恐山に殺到しているということは、彼女たちがつねに現に存在する要望に応えるという、重要な役割を果たしている証拠である。人々が死者から聞きたいのは、ちゃんと成仏している――仏教の八大地獄のなかの一つ、火で炙られたり、寒さのあまり死ぬことではなく――ことだとしても、津波で多くの死者と行方不明者を出した2011年3月11日の大震災後、残された人々のPTSD(心的外傷後ストレス障害)に応える役割もあることは、認めざるをえないだろう。僧侶や精神科医、小児精神科医たちはいまもなお、生き残った人々に残る心理的な後遺症の拡がりには力が及ばないと告白する」と述べます。また、「身近な人の死で悲嘆に暮れる人を支援する(グリーフケア)」では、松田広子の「あの世へ旅立った人への思いを断ち切ることができないと、みなさんは口寄せに来られます。そして、思いの丈をありのままにぶつけることで、心の整理がつくと、死を受け入れることができ、心穏やかに亡き人の供養ができます」という言葉を紹介します。松田は、相談者が安心し、感謝の言葉とともに帰っていくのを見て、口寄せには治療的な効果があることも確認しているそうです。
「子殺しの悲惨な現実」では、東北地方では長いあいだ「間引き」が行なわれていたことに言及しています。元来は植物の栽培に使われる「間引き」という言葉は、ここでは「口減らし」のために「余分なものを戻す」という意味になります。別の表現はもっと想像の世界のもので、たとえば「河鹿掬いにやる」というのがあり、同じ県(岩手)では、明治時代の最初の10年間(1868~1877年)、数十体の新生児の遺体が浅瀬に乗り上げていたと言われているそうです。著者は、「水中に住むと言われている想像上の動物『カッパ』は、一説によると、間引きされた子どもの遺体が河原にさらされている姿とも言われている。それが理由でカッパは、抹殺された子どもの亡霊と見られることもある。文化人類学者で民俗学者の小松和彦も、カッパ伝説と『間引き』を比べあわせている」と述べています。
カッパは「間引き」と深い関係がありました。子どもは4人以上はいらないというのが常識でした。よく言われる「一姫二太郎」の本当の意味は実際、それ以上の子どもはいらないということで、女の子1人と、男の子の2人は「後継ぎと予備」、つまり長男に何かあった場合の万が一に備えてのものだったといいます。著者は、「秋田県では、産婆――ときに『鬼ばあさん』と呼ばれていた――は、持ってまわった言い方をせず、ずばり親に『置くか、置かないか?』と聞いた。そして、当然のように『男なら置くとか、男女いずれも置かないとか?』と、確認することもあったそうだ。最もよく使われた方法は、新生児が産声を上げる前に――神に返すための絶対条件――、濡らした紙を顔にはって窒息させる(紙はり)やり方だった。福島県では、来た日に帰るのでるので『日帰りした』といった。女の子ばかりを産む女性をさす『女腹』は災難とみなされ、双子を産むと『畜生腹』と言われていた」と述べています。
「子どもを『消す』」では、東北地方の民芸品職人は、可愛らしい人形の「こけし」が「消された」子どもであることを知っていることが紹介されます。したがって、間引きされた子どもたちの「位牌」に近い働きをしていたのでしょう。「こけし」のほぼすべてが女の子をあらわしているのも偶然ではないのです。また、子殺しを描いた「間引き絵馬」の目的は、人口制限の手段となった間引きを行なう親に対して、警告を与えることでした。間引きは中絶よりも母体を危険にさらさないと言われ、また母親は家族の生き残りのための労働力としても必要だったのです。民俗学者の柳田國男(1875~1962年)が少年の頃、この悲しい絵馬に非常にショックを受けたことはよく引用されています。著者は、「この絵馬が、彼を地域の民間伝承の研究に身を捧げさせたのだ。本来の目的は、このような行為は非難すべきであることを大衆に警告するためのものだったのだが、時に逆効果を生み、間引きを煽るような絵になることもあった。それが理由で、多くは焼却されてしまった」と述べます。
「瞽女」では、2005年に105歳で亡くなった小林ハルが取り上げられます。彼女は、正真正銘の最後の瞽女でした。著者は、「彼女とともに、長い伝統も消えてしまった……。1900年、新潟県三条市に生まれた小林ハルは、生後3ヶ月で視力を失い、2歳のときに父が亡くなっている。家の恥と見なされたハルは、大叔父によって一部屋に閉じ込められ、そこから出ることができなかった。トイレは庭にあったので、家人がそこまで連れて行くのを近所の人に見られないよう、できるだけ水を飲まないように言われた。母親は彼女に、目が見えないと結婚もできないから、生きるために瞽女として一生三味線を弾かなければならないと言った。こうして彼女は、5歳で瞽女の弟子入りをした。8歳になるとすぐ幼いハルは、雨の日も風の日も、姉弟子と一緒に――荷物を運ぶ役として――、1日に20キロも歩く巡業に出た。母親は彼女に、何があっても親方に従い、辛いときは神仏に祈るようにと言っていた……。空腹にも毅然として耐え、ご馳走を出されても遠慮しろと教えていた。70年にわたる仕事で、彼女は地球を12周半するほど歩いたと言っている。新潟県と山形県だけで50万キロの距離である」と書いています。
「厳しい上下関係」では、社会の底辺に追いやられ、身体障害をカルマのせいにされて差別されていた瞽女たちでしたが、それでも芸を披露する相手は選んでいたことが紹介されます。山梨大学教授で日本の芸能史に詳しいジェラルド・グローマーによると、彼女たちは死と接触する「穢多(部落民)」(火葬や墓の仕事に携わる)や易者など、社会的に「いかがわしい」身分の客はなるべく避けるようにしていたといいます。著者は、「彼らの施しは、その低い地位に『汚染されている』と見られていたのである」と指摘します。また、「驚くべき記憶力」では、小林ハルのレパートリーは少なくとも500曲はあったことが紹介されます。著者は、「これは彼女たちの記憶力がどんなに優れているかの証拠である。それにもかかわらず、これ以上ないほどの弱者だった彼女たちは、あらゆる種類の憂き目にあい、性生活はすべて罰せられ、集団から追放された」と述べています。
これに着想を得たのが、1977年に公開された篠田正浩監督による映画「はなれ瞽女おりん」で、原作は1975年に発表された水上勉の同名の小説でした。1918年を舞台にした物語は、いったん追放されたら、あとは身体を売って生きるしかないことを示している……」と述べます。「78歳で『人間国宝』に」では、1978年、「最後の瞽女」である小林ハルは「人間国宝」の称号を授与されたことが紹介されます。彼女が選んで入所した目の見えない人のための養護施設では、当時の天皇皇后両陛下も迎えています。「瞽女とニワトリは死ぬまで唄わねばなんねえ」と言った彼女については、ゆうに80時間もの録音が残っていたといいます。1979年4月29日、彼女は日本政府から、他の模範となるような技術や事績を有する人が授与される黄綬褒章を受け取りました。
第2部「沖縄」では、ユタが取り上げられます。「ユタの影響力が仏教を上回るとき」では、沖縄ではユタの影響力が仏教を上回っていることが指摘されます。仏教が本州に浸透したのは6世紀の飛鳥時代だったのに対し、沖縄に紹介されたのは遅く、18世紀の終わりでした。自身が出家している鵜飼秀徳氏によると、15世紀から19世紀までの450年間、沖縄は王国で、「檀家制度」に加入する習慣も必要もありませんでした。これが理由で、本州では寺に墓地があり、葬儀代でおもな収入(しかも非課税)を得ているのと違って、沖縄にいくつかある寺(おもに臨済宗か真言宗)には隣接した墓地がなく、墓は自然のなかに点在しています。
故人の霊を供養するために僧侶を呼ぶ習慣はあるとしても、そのときはユタにも同じように無視できない役割があります。ちなみに誰かが亡くなった場合、ユタに来てもらうときは「ユタ買い」と言っています。ユタの役割は、交通事故やハブに襲われたショックなどで落ちた「魂」を、取り戻すことです。沖縄では「霊魂」をさすのに「マブイ」という言葉があり、これは「マブイオトシ」または「マブイ取れた」と言われています。西洋医学で治せないような急病にも、「マブイが落ちた」と診断する人がいるそうです。そんなときユタが呼ばれ、落ちたマブイを元に戻す儀式をするのです。あとはすべてが元どおりになると言われています。
「ノロとカミンチュ(神女)」では、沖縄の「ノロ」と呼ばれる女性聖職者が取り上げられます。ノロの存在理由は、任地である村の聖地(御嶽)で宗教儀式を執り行なうことと、世界と村の平和のために祈り、祖先や故人の霊を慰めることでした。著者は、「ここで注目すべきは、ノロは聖地に結びつき、彼女たちだけが村の外れに位置することの多い御嶽へ入ることが許されていたのに対し、ユタは御嶽とは関係がなかったぶん、自由に活動できることだろう」と述べます。鵜飼氏はノロとユタのあいだに興味深い境界線を引き、ノロは神の領域に属しているので「浄」を象徴し、対してユタは、死の領域に属していることから「不浄」の分野に結びつくとして見ています。こうして一部のユタはこの言葉に異議を申し立て、「カミンチュ」と呼ばれることを要求しているのです。
「沖縄――久高、伊平屋島、座間味」の「久高島とアマミキュによる女系信仰」では、「神の島」として知られる久高島が取り上げられます。本島から5キロの距離にあり、本島の安座間港と久高の徳仁港をフェリーが結び、所要時間はわずか15分から20分です。著者は、「この島が聖地なのは、琉球の歴史がここで始まったからで、島の北端にあるカベール岬に降り立った女神阿魔美久が、島々をつくったとされているからだ」と述べます。「女性が神に変わるとき」の「イザイホー――女性が神として認定を受ける儀式」では、仏教が浸透していなかった久高島で、12年ごとの午年に、きわめて特別な祭事が行なわれていたことが紹介されます。600年以上の歴史を持ち、「イザイホー」の名で知られる祭りです。
イザイホーは、一種の通過儀礼で、この祭事を通して女性は一人前の神女として認証を受けます。著者は、「琉球王国の管理下になる前、久高は自給自足で独立していたことから、儀式は島にノロが派遣される前からあるものだ。そこでノロによってもたらされた信仰と、一部は2000年以上の歴史がある先祖伝来の儀式が融合したと考えられている。いずれにしろこれは、島で最も古い聖地の一つ、フボー御嶽での評価である。ノロとカミンチュの役割は異なっていた。ノロは島を守るために祈ったのに対し、カミンチュはむしろ自分たちの家族を守るのが使命だった。そのためノロのほうが地位が高く、イザイホーのように神として認定される儀式では最高位が授与された」と述べます。
「準備に1ヵ月」では、イザイホーの祭りは4日間――旧暦の11月15日の満月の日から18日――にわたって行なわれ、準備にゆうに1カ月は必要だったことが紹介されます。まず本祭りの1ヵ月前に、イザイホーを執り行なうことを神々に報告しなければなりませんでした。この祭礼前の儀式に参加できるのは、前回のイザイホーのあと30歳から41歳になった女性でした。著者は、「この条件に合った女性たちは、まず島にある7カ所の聖地(御嶽)に参拝し、そこで神々から神女になるための「霊力」を授けてもらった。対して男性たちは、ノロの監督のもと、木々の枝を切って、「七つ橋」と呼ばれる橋をつくらなければならなかった」と述べています。拝殿(アシャギ)の入口で半分土に埋もれてかけられた七つ橋は、現世と聖なる世界の境界線、「現世と他界を結ぶ架け橋」でした。新たに神女(久高ではナンチュ)になる女性たちは、現世を捨てて他界空間に入るために、この橋を渡らなければならなりませんでした。そしてそこで適性とみなされたナンチュだけが渡ることができたのです。
イザイホーについて、著者は「新しく神になったことが、1人の男性の右中指で額と両頬に朱印を押されて認証された。次いで1人のノロが、前もって彼女たちの兄が持ってきた団子を朱と同じ場所に当て、粉をつけた。朱は太陽と男性原理を象徴していたのに対し、白は月と女性原理を象徴していた。団子は彼女たちの神女の地位を確認した印で、儀式のあと葉っぱの上に乗せて返された。こうしてサンチュたちもまた、イザイ花と呼ばれる赤と白と黄色の紙でつくった造花を鉢巻のあちこちに挿すことができ、そのあとは年長の神女と一緒に輪になって神歌を唱えながら、井戸の神と水の神に感謝したのである」と述べています。イザイホーは複雑な祭りで、それぞれの地位や序列は年齢で決まっていました。年とともに地位が上がるのですが、しかし最上級の階層になるのはやっと60歳になってでした。この年齢は、家では息子の妻のおかげで家事から解放されていました。70歳で、それまで40年間の貢献に区切りをつける儀式があったのです。
「水子供養」では、1970年代に始まった仏教の儀式である水子供養が、流産した胎児の魂を供養するのが目的であることが紹介されます。僧侶の故三浦道明は著書『愛――もし生まれていたら』(文化創作出版)で、流産した胎児の魂を鎮めることの必要性を強調し、供養しなければ兄弟に悪いことが起こると訴えました。対してイスラエルの宗教学者ツヴィ・ヴェルブロウスキーは、「水子供養」について「新宗教」で「恐怖を煽るビジネス」と言ってはばからず、仏教は胎児の復讐による祟りや呪いという考えを利用して、汚い金を稼いでいると暗に非難しています。もっと穏健なのは、アメリカ人の日本研究家ウィリアム・ラフルーアやジェフ・ウィルソンで、アメリカでも信仰に関係なく、子どもを失った女性たちの苦しみに答える儀式が徐々にあらわれていることを指摘しています。さらにアメリカの人類学者マーク・モスコウィッツは、この種の儀式は台湾にもあり、要望に応えていることを指摘します。
第4部「北海道」の「大学が保管するアイヌ遺骨の返還問題」では、アイヌと倭人のあいだで解決されていない大きな問題が、墓地を冒瀆されて奪われた先祖の遺骨の返還であると指摘しています。「全身の骨や頭蓋骨が研究目的で持ち去られ、各大学に保管されています。私たちはこれらの霊を供養したいので、強奪された遺骨を全部、返還してほしいと要求しています……」との遺族の声を紹介し、1930年から1965年のあいだ、アイヌの遺骨は研究者たちによって墓地で掘り起こされ、戦利品は12の大学で分配されたことを説明します。北海道大学は最大の「コレクション」を保有しており、2017年現在、個人が特定された遺骨1676体のうち、1015体があります。また12の博物館が76体の遺骨箱を所有し、うち27体は個人が特定されていません。一方、アイヌが要求する中心問題である遺骨の返還は、ほぼ目的を達成し、1985年から徐々に返還されています。
結論「最後のシャーマンを称えて」の「実験科学に対して経験のブリコラージュ(寄せ集め)」では、『〈反〉哲学教科書』の著者であるフランスの哲学者ミシェル・オンフレは、オーストリア出身の哲学者でアナーキスト認識論者〔科学に否定的な考え〕といわれるポール・ファイヤアーベントを引用して、シャーマンや魔術師、占い師や催眠術師のところへ行くようにと言ってはばからないことが紹介されます。というのも「すべての真実はやってみる価値があり、うまくいけばすべてよし」だからです。これはドイツの心理療法士バート・ヘリンガーがズールー族からヒントを得て、彼独自のファミリー・コンステレーション(家族の布置)〔人間の意識に無意識に影響を及ぼす家族の隠れた力動を顕著化させる手法]を考案したのにも少し通じます。
また、臨床心理学者で『野の医者は笑う――心の治療とは何か?』(誠信書房、2015年)の著者でもある東畑開人が、心の治療(おそらく魂の)を調査するのに、沖縄で6カ月以上、想像しうるかぎり怪しい治療をすべて体験した姿勢でもあるといいます。野の医者のドアを押しながら、彼は魔女のデトックスやリンパマッサージなどを受け、ついでにアドバイスやあらゆる種類の警告を録音しました。著者は、「これらすべてで彼が確認するに至ったのは、沖縄にこれだけ豊かな種類の治療法があるのは、みんながここで『ブリコラージュ』を実践していたということだった。彼がここで引用したブリコラージュは、フランスの人類学者クロード・レヴィ=ストロースが考案した概念である。使用されている言葉は現代風になっているものの(オーラソーマ〔カラーセラピーのこと〕、リンパマッサージ、マインド・ブロック・バスター〔潜在意識のブロックを外すこと〕)、『カミンチュ・カウンセラー』と名乗るいかさま治療師など、いずれもわかりやすいことはわかりやすい」と述べています。
「口寄せと催眠によるトランスコミュニケーション」では、多くの本を読んでいるうちに著者は、東北のイタコと、フランスの麻酔科医シャルボニエが開発して普及させたトランスコミュニケーションが同系列であることに思い至ったことを告白します。後者は催眠によって死者と交流して死を悼むメソッドです。第2世代のシャーマンを自認するマリアというシャーマンは、客がトラウマを克服するために催眠術を実施していましたが、しかし死者を哀悼するのにも使っています。それが理由で彼女はグリーフケアを勉強したのですが、それは生きている人を助けるのにすべての道はよいと考えているからでもあるといいます。「科学的未確認物」と形容されるシャルボニエ医師は、死後の世界や見えないものとの交流は、科学的に証明する必要がないと考えています。フランスのジャーナリスト、ピエール・バルネリアスが制作した臨死体験のドキュメンタリー「タナトス、最後の一節」で、シャルボニエは「困惑したのは、文化や宗教、哲学いかんにかかわらず、人は同じ体験をしていることがわかったことだ」と語っています。著者が個人的に集めた日本の臨死体験の証言は、シャルボニエの言葉を裏づけるのでした。
日本と西洋の臨死体験を比較分析した中部大学教授・バージニア大学客員教授の大門正幸とバージニア大学教授ブルース・グレイソンの記事では、臨死体験の文化的な違いや、いくつかの開きが説明されています。この比較は主として立花隆氏が『臨死体験』を執筆するときに作成した表をベースにしているのですが、たとえば日本人はアメリカ人と同じ光を見ても、特定の個人には当てはめていません。著者は、「日本人から見ると、光を神や愛と結びつけるのは、キリスト教や外国の伝統になるようだ。もう1つの違いは天国のイメージで、日本人の想像の世界では花畑になることが多い。また、この世とあの世を分ける川(三途の川)の存在も違いの一つで、アメリカ人の臨死体験には見られないものだ。最後は、人生全体を見直すような臨死体験がほとんどないことで、これは日本人には最後の審判の概念がないからだろうと解釈されている」と述べるのでした。
本書は、外国人(キリスト教圏)から見た日本のシャーマン像を採り上げた本として大変興味深い内容でした。しかしながら、神道と民俗学に詳しいサンレーの瀬津式典長も本書を読んだので、意見交換したところ、いろいろと疑問点が出てきました。まず、娼婦の存在や社会的地位について、キリスト教圏のそれと同様に捉えている点が気になります。遊女(特に吉原)の社会的地位が低下したのは近代以降、西洋的価値観が流入してからでした。もちろん遊女の社会的地位は高いものではありませんでしたが、社会からの評価は西洋とは違うものであったと思われます。
また、「こけし」に関する記述につきまして「こけし=子消し」説を事実として紹介していますが、「こけし」という語が今日いう「こけし人形」全体を指す名詞となったのは昭和以降で、それ以前には各地で様々な名称が確認できます。その中で「こけし」を用いていたのは仙台近郊のみであり、こけしが作成された東北地方の大部分でこの人形を「こけし」とは呼んでいなかったと考えられます。「こけし」を用いていた仙台地方においても間引きは「おろぬぎ」「おりぬき」「もどす」などの単語が用いられていたとされており、間引きに対して「消す」との表現の使用例は確認出来ないそうで、間引きされた子供とこけしを結びつけることは困難であると思われます。こけしは農民が湯治帰りに求めた品であり、その性質から、心身回復と五穀豊穣のイメージが重なった山の神と繋がる縁起物といわれます。
また、「こふけし=子受けし」やこけしに用いられる赤色の持つ魔除けの特徴から、先に挙げた性質のほか、子授けや子供の無事な生育を祈るためのもので、間引きした子供の慰霊や贖罪のためというよりもその正反対の性質を有していたと考えられます。なお、こけし=子消し説の登場は1960年代と言われており、その背景には(インターネット上の指摘になりますが)出生直後の子供にも人権があるとする(「七つまでは神の内」ではない)西洋的な人間観の影響を指摘する意見もありました。また、著者はこけしのほとんど全てが女児をかたどっているとしています。この点は多くの辞書でも採用されていますが根拠がある論ではなく、こけし=間引いた女児とする説の成立は困難かと思われます。以上の点から「こけし」に関する指摘は適切ではなく、本書における民俗的考察に関しては少々検討が必要な点があると感じました。