- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2294 心霊・スピリチュアル 『死者の告白』 奥野修司著(講談社)
2024.01.08
能登半島地震で亡くなられた石川県内の犠牲者数は、8日10時の時点で161人となっています。心より御冥福をお祈りいたします。2011年3月11日に発生した東日本大震災の死者について書かれた『死者の告白』奥野修司著(講談社)を紹介いたします。「30人に憑依された女性の記録」というサブタイトルがついています。著者は、ノンフィクション作家。『ナツコ――沖縄密貿易の女王』(文春文庫)で、講談社ノンフィクション賞と大宅壮一ノンフィクション賞をダブル受賞。著書に、『ねじれた絆――赤ちゃん取り違え事件の十七年』(文春文庫)、『心にナイフをしのばせて』(文春文庫)、一条真也の読書館『魂でもいいから、そばにいて』で紹介した新潮文庫など。
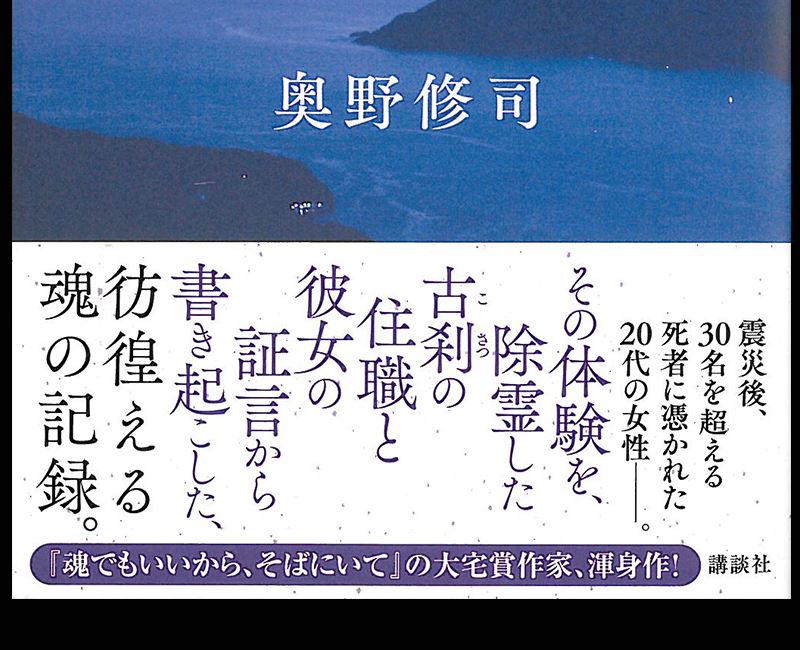
本書の帯
カバーには、夜の海と海辺の街のイラストが描かれ、帯には「震災後、30名を超える死者に憑かれた20代の女性――その体験を、除霊した古刹の住職と彼女の証言から書き起こした、彷徨える魂の記録。」「『魂でもいいから、そばにいて』の大宅賞作家、渾身作!」とあります。
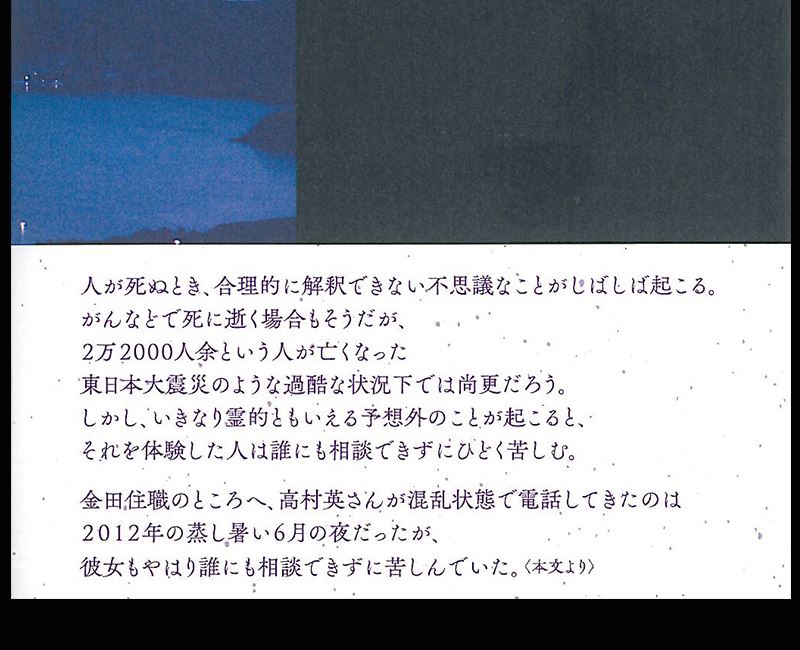
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「人が死ぬとき、合理的に解釈できない不思議なことがしばしば起こる。がんなどで死に逝く場合もそうだが、2万2000人余という人が亡くなった東日本大震災のような過酷な状況下では尚更だろう。しかし、いきなり霊的ともいえる予想外のことが起こると、それを体験した人は誰にも相談できずにひどく苦しむ。金田住職のところへ、高村英さんが混乱状態で電話してきたのは2012年の蒸し暑い6月の夜だったが、彼女もやはり誰にも相談できずに苦しんでいた。〈本文より〉」
アマゾン「内容紹介」には、「宮城県の古刹・通大寺では、人間に『憑依』した死者を成仏させる『除霊』の儀式が今もひっそりと行われている。震災後、30人を超える霊に憑かれた20代女性と、その魂を死者が行くべき場所に送った金田諦應住職。彼女の憑依体験から除霊の儀式まで、一部始終を、大宅賞作家・奥野修司(『ナツコ』『魂でもいいから、そばにいて』)が描く!」とあります。
本書の「目次」は、以下の通りです。
扉を開く前に
「普通の生活」
第1部 予兆
「おにぎりが食べたい」と言った男子高校生の思い
下半身がない海軍軍人が守りたかった家族の未来
「除霊」の儀式はどう行われたのか
5歳の男の子の魂に感じた罪の意識
第2部 乱入
「娘をさがしに行かせろ」と叫ぶ死者の慟哭
弟の手を離した少女の後悔
津波で家族を喪ったことに耐えられなかった男性の霊
津波から逃げ遅れた妊婦が伝えたかったこと
餓死した犬は最期に何を見たのか?
第3部 祈り
愛する老妻を1人残して死んだおじいさんの心配
死にたくなかったと訴える大学生の苦悶
2人の子供を残して亡くなった母親の無念
福島原発で亡くなった男性が訴える家族への心残り
「父より先に死んだぼくは、地獄に落ちますか?」
12歳の祈り
扉を閉じた後で
「扉を開く前に」では、柳田国男の『遠野物語』の冒頭にある「この話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり。昨明治42年の2月頃より始めて夜分をりをり訪ね来たり、この話をせられしを筆記せしなり。鏡石君は話上手にはあらざれども誠実なる人なり。自分もまた一字一句をも加減せず感じたるまゝを書きたり……」を紹介し、それにならって、著者は「この話はすべて宮城県の人、高村英さんより聞いたものである。令和2年の5月頃より、僕がたびたび仙台に足を運んで筆記したが、英さんは時折難しい異次元の言葉を遣うので理解するのがなかなか大変だった。しかし、彼女は誠実で理知的な人だ。耳にした話はできるだけ加減せず、感じたままを書いたつもりである」と書いています。こうして著者は、「憑依」物語の扉を開けることになりました。
本書に書かれてある内容は誰もが納得できるような物語ではありませんが、著者はこれを単なる作り話ではないことを確信して書いたそうです。その理由としては、まず「除霊」の儀式をしたのが、曹洞宗通大寺の金田諦應住職という、著者が信頼している僧だということです。また、儀式は密かに行われたのではなく、医療者や宗教者など第三者が何人も目撃しており、儀式そのものにも加わっていたからです。30人以上の霊に憑依されたという英さんの記憶が正しいかどうかは検証できませんが、少なくともその時起きた現象は「事実」であると言えるといいます。その内容も、金田住職と高村さんの間に多少の記憶違いはあるが、問題になるような差異はなかったそうです。
「普通の生活」の冒頭には、憑依された高村英さんの体験談として、「子供の頃から、いつもわたしにはお友達が1人多かったように思う。たとえば、お友達のおうちに遊びに行った時もそうです。お友達のお姉ちゃんが入って一緒に遊んだつもりで家に帰り、お姉ちゃんのことを母に報告すると、『だって英ちゃん、あそこはお兄ちゃんが2人で、女の子はあなたのお友達しかいないはずよ』と言われるんです。じゃ、一緒に遊んだあの子は誰なんだろうと思っていました」と書かれています。
他の人には見えないのに、自分だけに見える人がいるというのは、小さい頃からごく普通のことだったとして、高村さんは「見えるといっても、オカルト映画によくある幽霊のように、ぼんやりと浮遊している人形(ひとがた)ではないのです。死んでいるとはわからないけどリアルでしたから、見分けがつかない時もありました。でも学校では普通に過ごしていました。わたしの体質を知っている友人は数えるほどしかいませんでしたが、知られても気にしないし気にされたこともなかったと思う。ただしょっちゅう心霊現象に出遭うので、面倒くさいと思ったことはよくありました」と述べます。
第1章「予兆」の「『おにぎりが食べたい』と言った男子高校生の思い」の「光を目指しなさい」では、おにぎりが食べたかったという男子高校生の霊におにぎりを供えてあげた後、憑依された高村さんがそれを食べました。その後は太鼓を叩く音が聞こえ、それに合わせて金田住職の読経の声が響く中、死者の霊を光の世界に導くという儀式になりました。金田住職が「光を目指しなさい」と言うと、霊は光に向かって進んで行き、闇の世界から光の輪をくぐって光の世界に溶け込むのだといいます。著者は、「これはチベット『死者の書』にもあるそうで、仏教でいうところの成仏を指すのだろう」と述べています。
「下半身がない海軍軍人が守りたかった家族の未来」では、「彼女が『霊を信じていない』理由」として、著者は金田住職が行った除霊の儀式は、仏教でいう「迷える霊」を供養して成仏してもらうものだから、キリスト教でいう悪霊を取り除くニュアンスの『除霊』とはもちろん異なるのだが、他に言葉がないから便宜的に使っていると説明したが、それでも彼女は『除霊』も『憑依』も違和感があると言った。その違いは、霊との距離感の差かもしれない。僕にとって霊は空想の産物であって実体がない。しかし彼女は実体を感じるのだろう。『霊』という言葉を使わないのもそのためだと思われる。彼女には亡くなった死者の霊でも『人』なのである」と書いています。
「ほとんどが東日本大震災の津波に関係」では、英さんに憑依した30人以上の霊のほとんどが東日本大震災の津波の犠牲者であったと明かされます。その理由について、高村さんは「たぶん圧倒的な数のせいです」と言いました。数とは、2万2000人余といわれる津波で亡くなった死者の数のことである。彼女は、「300人収容できるホールを想像してください。わたしが舞台に立っているとします。そして、亡くなった方たちが客席から舞台のわたしをおとなしく見ています。そこへ津波が起きて、いきなり“生を奪われて苦しんでいる人(霊)たち”が大勢ホールに押し掛けてきます。舞台上のわたしを発見すると、おや、もしかしたら、あいつの体の中に入ったら救われるかもしれないぞ。ワンチャン生き返れるかもしれないぞと、一斉にわたしに近づいてくるんです。藁をも摑むという言葉がありますが、掴んで助かるわけでもないのに摑んでしまう。その藁がわたしだったのです」と説明しています。
「死者の『中継器』になっている」では、霊たちがどうして近づいてくるのかという著者の質問に対して、高村さんが「わたしは自分のことをよく『チューナー』とか『中継器』に喩えています。死者は魂のままだと何もできないのですが、たまたまこういう体質のわたしがいて、うまく体の中に入り込んでチューニングを合わせれば声を発することができます。肉体を得ることもできます。だから、みんなわたしの中に入って来たがるんです。あの時はとにかく人の声がすごかった。まるでスキャンダルを起こした芸能人が、大勢のマスコミの人たちに囲まれているかのようで、わたしのうしろに津波で亡くなった人たちが長蛇の列をつくって並んでいるんです。でも、それ以前に7、8人(の霊)がわたしの中に入っていましたから、その人たちを追い出さないと津波で死んだ人たちは入ってこれなかったんですね」と答えます。彼女によると、彼女の中に器のようなものがあって、憑依した霊で満員だと新たに憑依できないが、何人か出て行けば、入れ替わるように憑依できるそうです。
「『除霊』の儀式はどう行われたのか」の「春時雨にかすむ古刹」では、金田住職だけでなく、日本では浄土真宗を除けば、他の宗派でも「除霊」を行っている僧は少なからずいることが明かされます。ちなみに、金田住職は「除霊」を専門にしているわけではありません。たまたま高村英さんという女性が訪ねて来て、「このままでは死んでしまう」と訴えられたために、目の前で苦しんでいるのを放っておくわけにはいかないと、「見よう見まねでやりました」というからハラハラしながらの儀式だったのだろうと、著者は推測します。著者が金田住職に会ったのは、「看取り先生」として有名だった故・岡部健医師を介してでした。震災の直後から、金田住職らは、宗派を超えて移動傾聴喫茶「カフェ・デ・モンク」という遊び心満載の「がれきの中で安心して泣ける場所」を立ち上げましたが、岡部医師もこの設立に深く関わっていたのです。
「どうやって死者を納得させるか」では、金田住職の「最初から最後まで傾聴しても物語にはなりません。聞きながら、これはどうなんだと問うていけば、(霊が憑依した)彼女が訥々としゃべります。彼女の声を聞きつつ、少しだけ手助けしながら、物語にしていくのです。物語としては死者との対話といえますが、本当にそれが死者との対話かどうかはわかりません。ただ、ひとつの物語にすることで整理がついてくるのです」という言葉が紹介されます。結果的に、死者との対話は即興劇のようになります。この即興劇が成り立っために、金田住職が自分に課したことがありました。それは、霊魂や「あの世」の存在については問題にしないこと。その経験がその人にとってどのような意味を持つかを問題にすること。そして、徹底した傾聴と、彼女が精神病を疑っていたから、それを否定したうえで、彼女との信頼関係を構築することでした。
金田住職は、著書『東日本大震災――3.11生と死のはざまで』(春秋社)の中で、「除霊」に使った宗教儀礼について、「今回行った宗教儀礼は、女性の宗教的風土的背景を考慮し、曹洞宗寺院で一般におこなわれている施食会(施餓鬼会)を基本におこなった。施食会は、お盆の時期におこなわれる先祖供養の儀式である。曹洞宗の一般寺院においては普通におこなわれている。各家々の先祖、ならびに自然災害、戦争の犠牲者、その他いわゆる『浮かばれない諸霊』を供養する。その中心をなす経文が『甘露門』である」と記しています。また、「施食というのは食を施すという意味で、迷える鬼神たちに食べ物を施すことを意味します。ただ、それをあなたたち(鬼神。ここでは憑依した霊)に供養するのではなく、施した食べ物はあなたたちの手で仏・法・僧の三宝に供養しなさい。そうやって功徳を積みなさいということです。そして悟りの道を行きなさい。現世に災いを起こすべからずといったことが書かれています」と述べています。
「死者との対話、そして儀式」では、除霊の本質とはまさしく「傾聴」であり、足が重くても、納得して本堂まで行ってくれれば、あとは「太鼓」「読経」「洒水」といった伝統的な儀式の力で、死者の行くべき世界へ導くという流れであることが示されます。では、太鼓、読経、洒水にどんな意味があるのか。金田住職は、「太鼓はリズムをとるためです。ドンドンではなくドドーンドンドン。御神楽がそうですね。聞いているだけで涙が出てきます。日本人の心の奥襞に届いてこびりついたものを剥がすというか、あの力はすごいです。あのリズムで霊を追い出すというイメージです。甘露門というのは、鬼を集め、地獄の門を開けるという呪術性のあるお経で、霊がすすむ道を光のシャワーで照らしてくれます。ただ、これで憑依が解けるのは東北だからであって、外国人の前でやってもおそらく無理です。人間は意外にその土地の風土や文化に支えられているんですね。風土や文化を背景に納得させて引きずり出し、その後は伝統的な儀式の力で吹き飛ばす感じでしょうか」と述べています。
洒水は、キリスト教でいう聖水のようなイメージです。そうした水が湧き出る秘密の井戸でもあるか。金田住職は「ああ、それは水道水ですよ」と笑い、「この水はな、栗駒山から汲んできた聖水だぞ、ってかけたんです。水と人との関係って面白いですね」と述べました。「除霊」というので、著者は祈禱のような儀式で霊を祓うのかと思っていたそうですが、僧が死者の霊と対話しながら説得によって成仏させる、あるいは祀り上げるという、きわめて人間臭い方法だったのが意外だったといいます。聞いている著者の認識から、「あの世」と「との世」の境目が消えていくような錯覚を覚えたとか。彼女の中から本当に霊が消えたかどうかについては、金田住職は「霊の存在云々はどうでもいい話なんです。あるといえばあるし、ないといえばない。証明できるものではありません。あくまでその人の中での出来事なんです。だからとりあえず全部肯定します。その上で、それがその人にとってどういう意味を持つか。ここに来るまでの彼女は死にたいという意思表示をしていました。これは駄目です。絶対に死なせたくない、というのがあの儀式だったのです」と述べるのでした。
「5歳の男の子の魂に感じた罪の意識」の「彼女が抱く死者に対する罪悪感」では、高村さんの「こう言うと驚かれるかもしれませんが、死者(の霊)に体を奪われるという体験は、わたしにとってはレイプと一緒なんです。理解できないでしょうね。約1年の間に、わたしが嫌がるのもかまわず、30人以上の人(霊)が強引にわたしの体の中に入っては暴れたり怒鳴ったり、この体をよこせ、生き返らせろ、俺は死んでないとか……。わたしの意思を無視して好き勝手をしていました。わたしにすれば、あれはわたしの人権や尊厳を根こそぎ奪う行為でした」という言葉が紹介されます。
また、高村さんは「あの人(霊)たちは、苦しいから、わたしに助けを求めたのはわかります。でも、わたしにとって彼らは加害者であり、わたしは被害者なんです。(中略)たまたまわたしがこういう体質だったから、わたしという中継器にチューニングを合わせれば、それまで何もできなかった人(霊)たちが声を発することも肉体を得ることもできるので、みんなわたしの体に入りたがったのです。その人たちを、(儀式によって)再び死者の世界に送って死なすのですから、わたしは被害者であると同時に、加害者でもあると思いました。その罪悪感でずっと苦しんできたのです」とも述べています。
「『除霊』は死者を殺すこと」では、「住職さんたちは成仏させたという感覚ですが、わたしが見ている世界では、その人たちが人の形でなくなる瞬間を見ているので、わたしには殺したという感覚が残るんです」という高村さんの言葉を紹介して、著者は「おそらく彼女が見ている霊たちは、余人が想像する以上にリアルで、現実に存在するのと何ら変わらない姿であらわれるのだろう。だから、『霊』の形が消えてしまう『あの世』に送ることが『殺す』という感覚になるのだ。『霊』や『憑依』という言葉に違和感を覚えるのも、憑依する霊はまだ生きているという感覚があるからかもしれない」
「男の子が出ていって気づいたこと」では、憑依は2つに分けられることが明かされます。著者は、「霊媒師のように修行して憑かれる能力をもった人の憑依がその1つです。日本だったら青森のイタコや沖縄のカミンチュ、それに巫女もそうです。こうしたシャーマン的な専門家はどの国でもいます。もう1つは病気として捉えられている憑依。何らかの不幸があったり調子が悪かったりして普通の人に憑く憑依です」と書いています。
第2章「乱入」の「『娘をさがしに行かせろ』と叫ぶ死者の慟哭」の「『納得できない』霊との対話」では、死に臨んだ時、死を覚悟できるかどうかは「納得」できたかどうかだといわれますが、大半は「諦め」なのかもしれないとして、著者は「がんで死に逝く人を見ても、死ぬのは嫌だ嫌だと死を受け入れようとしなかったのに、体力が奪われていくにつれて、最後は生に執着する力も消えて諦めの境地に入っていく。そんな状態だったのかもしれない」と述べています。
「津波で家族を喪ったことに耐えられなかった男性の霊」の「目の前で娘を流された絶望」では、著者は「東日本大震災で愛する人を喪った人たちから霊体験を聞いていた時だった。高齢の母と一緒に屋上に逃げたが、母は途中で力尽きて目の前で津波に流されていくのを見たという女性がいると聞いた。あの震災から2年ほど経って、夢かうつつか、亡くなった母が毎日のように枕元で語りかけるというのである。ぜひ話を聞かせてほしいと頼んだのだが、思い出すだけで体が震えると言われた。目の前で愛しい家族が死んでいくのを見なければならなかったつらさは、僕たちには想像できない痛みなのだろう。この男性の話を聞きながら、そんなことを思い出す」と述べています。
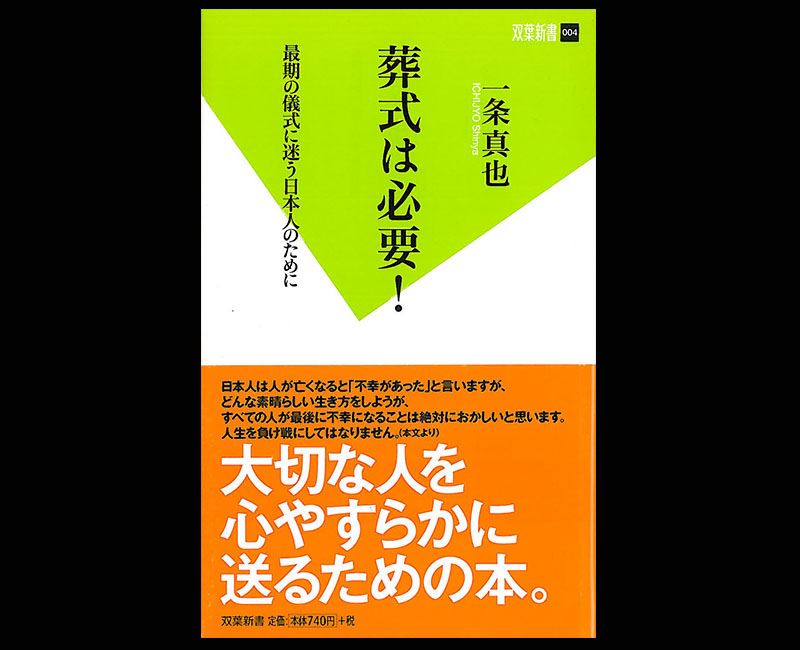
『葬式は必要!』(双葉新書)
また、金田住職は津波で亡くなったという男性に「お葬式はしてもらったのか?」と質問しました。男はしばらく黙っていましたが、「揉めた……。俺はそんなの、どっちでもよかったんだ」とポツリと言ったそうです。著者は、「宗派の違いだろうか、複雑な事情があったようだ。実際、新興宗教に入っていて、菩提寺に断りもなしにその宗教で葬式をし、後で親戚との間でごたごたするケースをよく聞いた。その類いだったのかもしれない。男は葬式の場面を思い浮かべたようだが、残念ながら、高村さんには映像が乱れてよく見えなかった」と書いています。この葬式を行わなかった霊の思念は乱れるというのは貴重な証言であると思います。

『のこされた あなたへ』(佼成出版社)
「津波から逃げ遅れた妊婦が伝えたかったこと」の「女性の霊の悔しさと無念さ」では、高村さんの「がんで亡くなる方は、死ぬまでに死を受け入れるプロセスがあります。でも、彼らはいきなり津波に呑まれて死んだので、自分に何が起きたのかもわからないし、死んだらしいとわかっても、あまりにも突然で死を納得できないのだと思います」と言う言葉が紹介されます。著者は、「これは生き残った遺族も同じだろう。愛する家族や恋人を津波にさらわれた遺族を訪ねると、遺骨を埋葬せずにいつまでも仏壇に置いていることがよくあった。それは、その死を納得できなかったからだ。大切な人との死別は、それがどんな死であっても突然死だ。とりわけ津波は、死を覚悟する時間がなかっただけに強い悲しみを残し、いつまで経っても納得できない。死者の思いも同じということだろうか」と述べるのでした。
「餓死した犬は最期に何を見たのか?」の「カオスのような『死後の世界』へ」では、宗教学者で京都大学「政策のための科学ユニット」のカール・ベッカー教授が、高村さんの憑依現象について、「大切なのは記録を大事にとっておくことだ」と言ったそうです。「いかがわしい」とか「非科学的」とかの理由で否定するのではなく、現象として存在したことを記録しておけば、いずれわかる時が来るかもしれないということだろうと推測する著者は、「かつて物理学者の中谷宇吉郎は『大自然という大海の中に論理という網を投げて、引っかかってきたものが科学的成果で、大半の水は科学という網目からこぼれ落ちる』と語ったと岡部健医師から聞いたことがある。人間が知っていることなんて、との自然のごく一部でしかないことを、謙虚に自覚することだろう」と述べるのでした。
第3章「祈り」の「愛する老妻を1人残して死んだおじいさんの心配」の「死者と生者の交わり」では、著者は「かつての日本には、生者と死者が共に生きる文化があったように思う。西馬音内盆踊りでなくても、お盆の時期になればお墓に故人が好きだった食べ物を供えたり、鴨居にご先祖の写真を掲げたり、子供が悪いことをすれば「ご先祖様が見ているぞ」と叱ったりするのもそうだ。死者と共に生きる文化が、日本人の倫理観を形成してきたともいえる。かつて死者は、僕たちの身近にいた」と述べています。
「死にたくなかったと訴える大学生の苦悶」の「死にたくない! 生きたい!」では、ちゃんと生まれ変われるように祈るために、大学生の霊に「名前はなんていう?」と訊いた金田住職に対して、霊は「名前? 名前は……、自分の名前さえわからないなんて!」とわっと泣き出したそうです。著者は、「名前を失って帰る家も見つからず、地縛霊となって彷徨う――。宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』に出てくる『ハク』を思い出す。名前を奪われて魔女の手先となっていたハクが、自分は『ニギハヤミコハクヌシ』であることを思い出したことで自分の世界を取り戻し、魔女の呪いから逃れるという物語だ。霊になっても、名前はその人の存在を示す道標なのかもしれない」と述べるのでした。
「『父より先に死んだぼくは、地獄に落ちますか?』12歳の祈り」の「悪夢からの脱出」では、憑依した霊を全て供養して光の世界に送ってもらった後、高村さんは家庭の事情でしばらく宮城県を離れることになったことが紹介されます。その惜別の日、金田住職は最後に「受戒」という儀式を彼女に行いました。お釈迦様が人間として正しい生き方をするために教えた戒を授けたのです。これによって高村さんはお釈迦様の弟子になったことになるのですが、著者は「この時、住職夫人は、夜っぴて縫ったお遍路さんが着るような白衣に、住職が筆で経を書き入れた経帷子を、お守りにと渡した。住職夫妻は、我が娘を送り出すような気持ちだったという。それ以来、彼女を苦しめるような異変は一度も起こっていない」と書いています。
「扉を閉じた後で」の冒頭を、著者は「人は死んだらどこへ行くのか?」と書きだし、「おそらく人類が誕生して以来、永遠のテーマだったはずだ。宗教が『天国』や『浄土』といった死後の世界を提供したのも、それに応えるためだったろう。『あの世』なんてフィクションであって、人は死ねばチリになると教えられてきた世代には、死後の世界なんておとぎ話にすぎないが、考えてみれば、千数百年にわたって何十億人という人が『あの世』を信じてきたことを考えると、死後の世界を信じなくなった現在こそ異常な時代なのかもしれない」と述べています。

『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)
拙著『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館、サンガ文庫)の「供養論」にも書いたように、供養本質とは死者に「死者であること」を自覚させ、より良き世界へと送ることにあります。信じられないような話が満載の本書『死者の告白』には、リアルでダイナミックな供養の現場が報告されていました。著者の前作『魂でもいいから、そばにいて』同様に、死者と生者のコミュニケーションの在り方についても考えさせられました。
なお、本書に登場する金田諦應住職は、わたしが客員教授を務めていた上智大学グリーフケア研究所でも講義されたり、全互協の公開講座にも登壇して下さいました。さらには、一条真也の映画館「グリーフケアの時代に」で紹介したドキュメンタリー映画に出演されています。わたしもこの映画に出演しているので共演者ということになりますが、お会いしたことはありません。島薗進先生や鎌田東二先生とは親しいと伺っていますが、一度お会いしたいと願っています。