- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2314 哲学・思想・科学 『恐怖の正体』 春日武彦著(中公新書)
2024.04.16
『恐怖の正体』春日武彦著(中公新書)を紹介します。サブタイトルは「トラウマ・恐怖症からホラーまで」です。著者は、1951(昭和26)年、京都府生まれ。日本医科大学卒業、医学博士.、産婦人科医を経て、精神科医に.、都立精神保健福祉センター、都立松沢病院,、都立墨東病院などに勤務.。多摩中央病院院長,、成仁病院院長を経て、同名誉院長。甲殻類恐怖症で、猫好き。著書多数。

本書の帯
本書の帯には児嶋都氏のイラストが描かれ、「知りすぎてはいけない――」「右も左も恐い。前も後ろも怖い。上も下も畏い。そんな方はご一読を。数多のコワイを集めて春日先生が暴きます。でも、今度は正体がこわい。 京極夏彦」と書かれています。
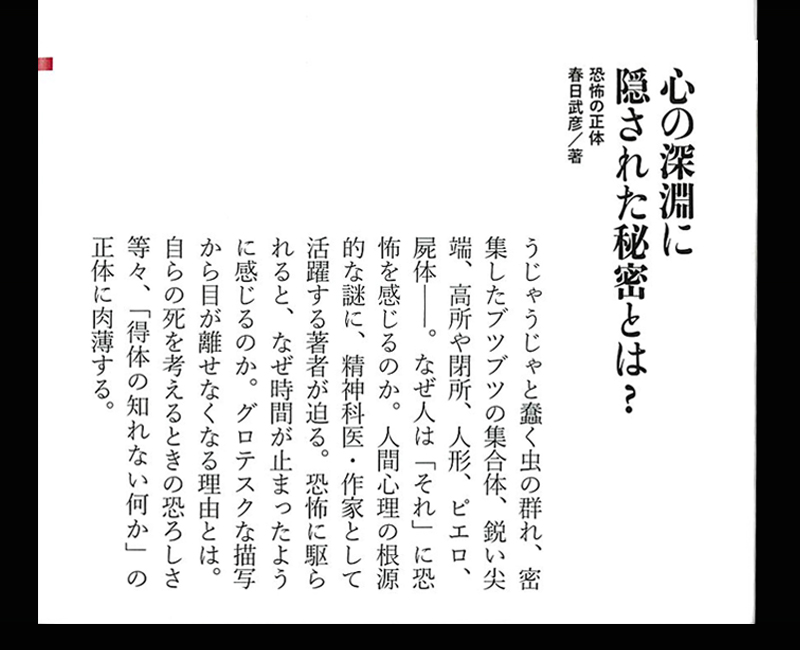
本書の帯の裏
帯の裏には「心の深淵に隠された秘密とは?」として、「うじゃうじゃと蠢く虫の群れ、おぞましいほど密集したブツブツの集合体、刺されば激痛が走りそうな尖端、高所や閉所、人形、ピエロ、屍体――。なぜ人は『それ』に恐怖を感じるのか。人間心理の根源的な謎に、精神科医・作家として活躍する著者が迫る。恐怖に駆られている間、なぜ時間が止まったように感じるのか。グロテスクな描写から目が離せなくなる理由とは。死の恐怖をいかに克服するか等々、『得体の知れない何か』の正体に肉薄する」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 恐怖の生々しさと
定義について
第二章 恐怖症の人たち
第三章 恐怖の真っ最中
第四章 娯楽としての恐怖
第五章 グロテスクの宴
第六章 死と恐怖
「おわりに」

アマゾンより
「はじめに」には、「恐怖というテーマは人を惹きつける」と書かれています。恐怖には、怪異や非日常から身につまされる体験までさまざまな出来事が含まれます。どんなものに恐怖を感じ、どのように振る舞い、それをどんな言葉で語るかによって、当人の人間性がありありと立ち上がってくるようにも思えるそうです。精神科医として臨床に携わっていると、恐怖そのものをダイレクトに訴えてくる人には滅多に出会わないことを知るといいます。だが彼らの症状の根底には、遠い過去に、さまざまな形で遭遇した「恐怖」が横たわって影響を及ぼしていることが少なくないと指摘し、著者は「いわゆるトラウマも、広義の恐怖体験と見なせるのではないか。自分ではうつ病だとさかんに主張しているが、実際には職場恐怖症であると判断されるケースもある。妄想と恐怖とが合体して、頭の中が大変なことになっている人もいた。自分では意識していない恐怖は案外多い」と述べています。
第一章「恐怖の生々しさと定義について」の「警戒心、不安」では、中国出身、アメリカで活躍した地理学者(人文主義地理学)であるイーフー・トゥアン(1930~2022)の『恐怖の博物誌』(金利光訳、工作舎)において、「では恐怖とはいったい何だろう? それは警戒心と不安という、はっきり区別されるふたつの心理的緊張がからみあった感情だ」と説明されていることが紹介されます。トゥアンは、「警戒心は環境にふだんとちがう出来事が発生することで喚起される」と述べ、さらに不安については、「不安とは何か危険が起こりそうな予感といっていいが、その危険の原因が何なのかははっきりわからない。これだと特定できる脅威が周囲に見あたらないため、確固とした対応をとろうにもとれないのだ」と記します。著者は、「一般的に、不安はそれをもたらすものの正体が曖昧である。他方、恐怖は正体が明確化して危険やダメージが予測されるけれども、逃げたり逆に立ち向かうのが困難な際に生ずる感覚だろう。いずれにせよ、無力感やもどかしさが大きな要素を占める」と述べます。
SUNABAギャラリー代表で文筆家の樋口ヒロユキ氏は、著書『恐怖の美学』(アトリエサード)で、恐怖についての説明しています。彼は、「恐怖とは単なる生理的、動物的な恐怖のセンサーであるだけではなく、死にまつわる記号に触れた時にも起こる、きわめて人間的な感情でもあるわけだ」と述べています。夜の墓場だとか暗がり、廃墟、(もちろん、信じ難い力で引き千切られた野生動物のパーツとか、無残に頭を齧り取られた家畜の死骸とかも)の類は「いずれも死や衰退、遠い過去といったものに結びついた記号」であり、「夜の墓場の肝試しとは一種の記号消費であり、原初的な文化鑑賞」なのだ」と述べます。
産婦人科医である著者は、あるとき分娩を担当した患者の中に、盲目の夫が出産に立ち会うという経験をします。目の見えない夫はどんなふうに世界を認識し理解しているのか。彼にとって世界の感触はわたしの感じるそれとどれだけ隔たっているのか。著者は、「どこか根源的な部分において自分とは大きく異なっているかもしれない人が、背後でこちらに向かって沈黙したまま座っているという居心地の悪さは、やはり恐怖につながっている。いや、それを敷衍すれば、あらゆる人たちが不可解かつ不気味といった結論になってくる」と述べています。詩人で評論家の遠丸立(1926~2009)は、著書『恐怖考』(仮面社)において、「恐怖とは空虚や無、それに未知なもの、異風なもの、深淵やくらやみ……に接したとき原意識からおしだされる第一次的情緒なのだと推察される」と書いていることが紹介されます。
「あらためて恐怖を定義する」では、著者は恐怖の定義として、(1)危機感、(2)不条理感、(3)精神的視野狭窄――これら3つが組み合わされることによって立ち上がる圧倒的な感情が、恐怖という体験を形づくると述べています。興味深いことに、(1)の「危機感」が実在していなくても、人は恐怖に駆られることがあるとか。いわゆる恐怖症、精神科領域に属するとされる症状です。たとえば高所恐怖、閉所恐怖、尖端恐怖、視線恐怖、対人恐怖、広場恐怖、自己臭恐怖、醜形恐怖、不潔恐怖、学校(職場)恐怖、巨像恐怖、人形恐怖、甲殻類恐怖など。著者は、「いずれも、当人は『本当の』危機には直面していないしその可能性すらない。ただし『危機感』に代わる別な要素が『不条理感』および『精神的視野狭窄』と作用し合って恐怖感もどきが立ち上がっている」と述べるのでした。
第二章「恐怖症の人たち」の「恐怖症のこと」の冒頭を、著者は「心の病のひとつとして、恐怖症phobiaと呼ばれるものがある。『精神症候学』(濱田秀伯、弘文堂)から、まさに必要十分といった趣の簡明な説明を引用してみたい。すなわち、『恐怖症は、恐れる理由がないと分っていながら、特定の対象や予測できる状況を不釣り合いに強く恐れ、これを避けようとすること。日常生活を侵害しない程度のものは小恐怖という。恐怖症の対象にはあらゆるものが含まれ、学術用語になっているだけでも200を超えるという』。」と書きだしています。
「びっしりと……集合体恐怖」では、集合体恐怖Trypophobiaについて、著者は「木肌にびっしりと産み付けられた蛾の卵、限度知らずといった按配に産み落とされたカエルの卵、岩肌を覆うフジツボ、コモリガエルの背中、海ぶどう、ハスの花托(丸い穴の集合)のひとつひとつに種がいちいち嵌り込んでいるところ、そういった小さな穴や突起やブツブツしたものの集合体に過剰反応をするのが集合体恐怖である」と述べています。
集合体恐怖の理由の説明として、寄生虫や皮膚病、伝染病などに皮膚が冒された状態を連想させてその危機感や不快感が恐怖につながる、といった話が比較的流布しているようです。著者は、「わたしはかつて小児喘息とアトピーに悩まされていたが、アトピーでは肌にみっしりとブツブツが生じ、それを目にするとますます痒みが激しくなる。いくら掻いても痒みは治まらず、自分の皮膚はいよいよ異様な状態に変化していく。透明な汁がじくじくと滲出し、落屑が雲母のようだ。おぞましいものに変身していくかのような気味の悪さをひしひしと自分自身に感じたものであった。そのせいか、集合体恐怖的な傾向が強く、それどころか自虐的な遊びに耽っていた時期さえある」と述べます。
「百度も考へて恐ろしく」では、高所恐怖症について考察されます。「なぜよりにもよって高い所だけが苦手となるのか」と問いかける著者は、「そのような疑問は、高所恐怖症のみならずあらゆる恐怖症に対しても生ずるだろう。恐怖症は特定の対象で生ずる精神のアレルギーと考えられようが、それをトラウマがどうしたといった単純な因果論では説明しきれまい。よもや前世の記憶などを持ち出すわけにもいかない。結論から述べるならば、それは心理学や精神病理学では扱いきれない領域だ。あえて(大真面目に)申せば、むしろ文学が取り扱うべきテーマではないのか。ある特定の事象に伴うイメージや言説とわたしたちの不安がどのようなミラクルを経て結びつくのか。ある種の相性のようなものがあるのか。恐怖症が特殊であると同時にそれなりの普遍性を感じさせるのは、つまり世界全体が油断のならぬ場所であるという事実を示唆しているからなのか。それらへの答えは、文学の営みこそがもたらしてくれるのではないか。考えれば考えるほど、恐怖症は科学の範疇から遠ざかっていくのである」と述べています。
また、高所恐怖症についての科学からも文学からもほど遠い説明として、遠丸立著『恐怖考』に書かれている内容が紹介されます。遠丸は、「人間の出産行為、つまり胎児が子宮から母胎外の世界へ飛び出すという行為は、右の衝動説からすれば、子宮から膣口を経て外部空間へまで墜落するということを意味するわけで、要するにそれは一個の個体としての人間が『墜落したい』という衝動に身をゆだねる最初の行為にほかならない(頭からさきに、産道を下へ下へと下降する胎児の姿勢を想像せよ。これはまさに人間が空間を墜落するさいの姿勢にそっくりではないか?)」と述べ提起ます。
「逆転する立場」では、尖端恐怖症について言及されます。実は尖端恐怖症の人々の一部は、自分が加害者になるのではないかという危惧も併せ持っているとされるそうです。もし他人を傷つけてしまったら、二次的に自分を窮地に追い込むことは必定であろうとして、著者は「自分が思うようなアブナイことは他人もまったく同様に思っていても当然といった発想も生じかねない。加害者・被害者という立場は、予想以上に簡単に入れ替わるものなのである。だから尖端恐怖症患者において、普段は押し隠している攻撃性や衝動性を首尾良くコントロールしきれるか否かの覚束なさがそのまま『目に刺さってくるような感じ』として立ち上がってくるわけだ」と述べています。
「おぞましい思い出」では、目を傷つけるのは恐ろしい出来事であるとして、著者は未だにルイス・ブニュエル監督の「アンダルシアの犬」(1928)の目に剃刀を当てて引く場面を正視できないといいます。にもかかわらず、ゲイリー・A・シャーマン監督のホラー映画「ゾンゲリア」(1981)で目に注射針を突き立てるとか、ルチオ・フルチ監督の「サンゲリア」(1979)で尖った木片が目に刺さるとか、そういったものが世の中には繰り返し登場することを指摘します。著者いわく、いわゆる「怖いもの見たさ」の最たるものが、怖いものを見るための道具である目そのものが傷つけられる光景であるのは、なかなか皮肉の効いた話ではあると述べます。
「この狭さが息苦しい……閉所恐怖症」では、閉所恐怖症に言及します。なぜ「すぐに」外へ出られないことが恐ろしいのでしょうか。事故や災害で生き埋めになるとか逃げ損ねるのを恐れる人はいます。かつて、実際に危険な目に遭遇した(あるいは親しい人がそのような体験をした)という経験が絡んでいるケースはあるに違いないとしながらも、著者は「全員がそうとは信じられない。両親が過干渉で常に束縛されていたがためにそれが心の傷として作用し、自由が利かない状況を極端に恐れるといった類の因果関係もあまり見たことがない(むしろ別な束縛を求めて自縄自縛に陥ってしまうパターンのほうが普通である)。わたしは閉所恐怖ではないものの、急に便意を催したり吐き気に襲われたりしたときのことをかなりリアルに想像してしまうので、映画館ではすぐに席を立てるように通路側に座るようにしている」と述べます。これは、わたしもまったく同じですね。
「空気が薄い」では、おしなべて閉所恐怖症の人たちは、〈後悔することになりそうで動きがとれない→息が詰まりそうだ〉〈狭い空間は逃げ場がない→息が詰まりそうだ〉といった具合に、案外シンプルな図式が症状の裏に成立することが多い気がするとして、著者は「わたしが精神科外来で出会った人たちを思い起こしても、そのような図式におおむね該当する傾向があった(ただ、そのような図式が見えてくるくらいに心の葛藤や苦しみを本人が言語化できれば、もはや症状は鎮静化しているのが通常のパターンであった)」と述べています。
「恐怖症とアイデンティティー」では、恐怖症の対象となるのは、本来、「危険ではない」ものである。場合によっては危険になり得ても、とりあえずそんな可能性はほぼゼロである――そんな状態にあっても、危険だと認識してしまうといいます。それどころか過剰反応をしてしまうとして、著者は「つまり多くの人にとっては安全と見なされる状況においても、恐怖症の人々は勝手に『危険』を見出して狼狽したり混乱に陥る。それは、捉えようによっては滑稽な姿にすら映るだろう」と述べます。
そもそも恐怖症とは、神経症の一種であるといいます。すなわち、恐怖症となるような人たちは普段から心の中に漠然とした不安や屈託を抱えているのです。著者は、「人間というものは、どうやら『漠然』とか『曖昧』というのが苦手のようで、だから摑み所のない不安や屈託などは苦痛になる。でも解消はできない。そうなると、とにもかくにもその不安や屈託を何か具体的な事象に託したくなる。とりとめのない状況に苦しむよりは、具体的なことに苦しむ――そのほうが気分的に楽になるのだ」と述べます。
「別の結末」では、人形恐怖症について説明を行った後で、ピエロに言及します。著者は、「ピエロはどうだろうか。首尾良く人間になりおおせた人形が、まだ自信を持てないので突飛な化粧をほどこし、悪意と躁的気分とで陽気に振る舞っているといった印象なのである。すなわちピエロのコスチュームやカラフルな化粧は『見え透いた嘘』そのものであり、その下には異常な心が隠されている。だから怖い。そのあたりを物語へと巧妙に仕立て直すと、すなわち社会現象を巻き起こした映画『ジョーカー』(トッド・フィリップス監督、2019)になりそうに思われる」と述べています。
さらにピエロの恐怖について考察する著者は、「つまりピエロは人間になりたての人形であると同時に、わたしの心に潜む超自我と『つるんで』いる。とんでもない奴であり、でも、もしもこのピエロを殺したら自分も同時に破滅することになりそうな不穏さがある。人形にせよピエロにせよ、わたしたち人間と適度な距離感を上手く保てないところにおぞましさが宿っているような気がするのだ」と述べるのでした。
第三章「恐怖の真っ最中」の「ゴキブリの件」では、床の上のゴキブリは、ちっぽけであるにもかかわらず、真っ白いシャツに跳ねた一滴の黒い飛沫のような強いマイナスイメージを伴った存在感を与えてくると指摘し、著者は「目にした途端、どこか取り返しのつかない気分がわたしの中に生じ、図々しい闖入者といった腹立ちもまた生ずる。ゴキブリなんて、所詮はゴミを漁るような汚らしく低劣な生き物である。そのくせ、3億年前から地球上に棲息している。なりふり構わぬ生命力を携えた昆虫の姿は、文明という病に感染しその結果として脆弱な存在と化してしまった当方を嘲笑うかのようでもある」
目の前に姿を現したゴキブリは、ひとつのメッセージを携えているといいます。それは、「お前の住む部屋は、もはや安全やプライバシーの確保された心地好い空間ではない、既にゴキブリが出入りしたり、それのみならずどこか見えない隙間でゴキブリが増殖したりするような不衛生で無防備な空間に堕してしまったのだ」というメッセージです。どれだけのゴキブリが隠れ潜んでいるのか、それは決して確認ができないと指摘し、著者は「電気を消して眠りに就いた途端、ゴキブリは再び姿を現すだろう。おそらく複数で。睡眠中のわたしの身体を這い回ったり、半開きの口の中を覗き込むかもしれない。床も壁も(ひょっとしたら天井も)家具も蒲団も食器も、ことごとく不潔な奴らに汚染されている可能性が高い。いつの間にかわたしの住処は事実上乗っ取られ、清潔で安全な感覚を剥奪されてしまった」と述べます。
また、人間は肉体がタマシイを包み込む構造になっていて、さらに住居が第二の皮膚となって日々を暮らしているといいます。でも、今や第二の皮膚の下をゴキブリが右往左往していると指摘し、著者は「それは『おぞましい』としか形容の言葉がない状態だ。その『おぞましさ』がみるみるドミノ倒しのように広がり、遂にわたしは恐怖に捕らえられる。タマシイを包む『層』の一部へ、生きたゴキブリが混入してしまったという不快感、いや絶望感はわたしを打ちのめす。その感触は、あたかも世界が変容して自分がまったく油断のならない――それこそ太古のジャングルへ放り込まれたようなものだろう。しかもわたしは、ゴキブリにはおそらく死の観念ないしは死を恐れる感覚が欠落していると信じている(逃げるのは、ただの反射的振る舞いでしかない。)」と述べるのでした。
「日常が変貌する」では、1970年代から80年代にかけて、アメリカの写真界でニューカラー New Color Photographyというムーブメントがあったことが紹介されます。メインの写真作家はスティーヴン・ショアやウィリアム・エグルストン、ジョエル・マイロウィッツなどで、カラー・フィルムによる画像によって描き出されたアメリカの日常が主なテーマとなっていました(それまではカラー写真は退色することが理由で芸術写真の範疇には入れられていなかった)。ことにスティーヴン・ショアが撮影した荒野やハイウェイ沿いの駐車場やガソリンスタンド、ダイナーなどの光景は見る者を圧倒したといいます。ちなみに、ネット検索でいくらでも鑑賞可能だそうです。
著者も写真集を通じてそれらに衝撃を受けたのですが、とにかく異様な写真だと思ったといいます。べつに画像に死体とか怪物とか気味の悪い物が写り込んでいるわけではありません。アメリカン・ニューシネマ以降の映画で見掛けるようなロードサイドの風景でしかないのです。だが大判フィルムで撮影されたそれは異様に解像度が高く、色も微妙に人工的な鮮やかさで、しかも画面の隅々までピントが合わせられていて曖昧な部分が一切ないとして、著者は「通常の人の目では、これほど鮮烈に風景を捉えることなど不可能である。端的に言ってしまうなら、過覚醒状態の人間の目に映った風景なのである」と述べます。
「慢性化する恐怖」では、死刑囚が味わう恐怖について言及されます。日本の場合、死刑との判決が下っても、それがいつ執行されるかは分かりません。複数の死刑囚がいても、そのうちで執行される順番が決まっているわけではありません。予想がまったくつかないのです。著者は、「ある朝、監房の扉の前で8名の係官たちの足音が止まったときに、はじめて恐怖の実体が目の前に立ちはだかる。促されて教誨室へ連れて行かれ、いくつかの確認事項を問われ、遺書を書いたり煙草を吸うなどの短い時間が与えられ、あとはあれよあれよと絞首刑が執行される。本日これから死刑が執行されると判明したときの恐怖も鮮烈であろうが、やはり執行当日に至るまでの重苦しい宙ぶらりんの日々こそが途方もない恐怖となるだろう」と述べます。
「二十の恐怖(1)」では、著者自身の不安体験が語られます。著者は、学生時代にひどい不安感に苦しめられていたそうです。それは試験がどうしたとか、恋愛がどうしたといった類の悩みではありませんでした。さながら警戒を促す不吉なサイレンが延々と鳴り続けているかのような持続的かつ切迫した不安で、そもそもの発端は、中学生時代にあるとして、「当時の母は毎晩のようにブロバリン(睡眠薬。飲み過ぎると死亡する)とアルコールをいっぺんに飲んで酩酊しており(そのような行為に耽溺するには相応の異様な理由があったが、それを知ったのはもっと後になってのことであった)、心肺停止寸前になったことすら何度かある。医師であった父が彼女を蘇生している場面も複数回目にした」と述べています。
そのような特異な体験のせいで、著者は、ある日いきなり母親が死ぬといった場面が容易かつリアルに想像されたそうです。そして、それは悲しみよりも葬式だとか火葬、納骨など俗世間の因習的なものに対する嫌悪感や拒否感となって著者を圧迫したといいます。著者は、「母が死ぬという事実もさることながら、世の中に存在しているどこか土俗的な気配すら垣間見られる『葬儀』という旧習に母もわたしも呑み込まれるであろうという生々しい気配のほうが、不快感を伴った恐怖として黒々とまとわりついてきたのだ」などと述べています。これは、葬儀は人間にとって最重要の儀式であると考えているわたしにとってスルーできない発言ですが、一種の精神疾患のようなものと考えれば、ここで突っ込むのも野暮かもしれません。
第四章「娯楽としての恐怖」では、恐怖小説が取り上げられます。まず、恐怖小説の読者は本当に恐怖を体験したいと望んでいるのか、そこに疑問があるといいます。著者は、「本物の恐怖なんて、精神衛生上よろしくない。トラウマになったりPTSDを引き起こすかもしれない。マゾヒストにおける『痛みや羞恥がもたらす屈折した快感』などとは種類が違うのではないか。希求しているのはあくまでも恐怖に似たもの、いわば『恐怖もどき』であろう。たんに中華料理といっても蝙蝠だの土竜までをも食材にしてしまうようなハードで生々しい中華料理でなく、日本人向きにアレンジされたマイルドな中華料理をわたしたちが好むように、人々が望むのは甘噛みの恐怖だ。本当に牙を立てて食いついてくる恐怖ではない」と述べています。
光人社NF文庫というレーベルがあります。太平洋戦争における戦記物を中心に、特攻兵器だの幻の試作戦闘機だの軍人の生涯だのを書き綴った作品が多いです。著者は、「このレーベルのキャッチフレーズが〈心弱きときの活性の糧〉となっている。軍歌を聞いて心を奮い立たせるといったノリではなく、家族や自分を守るためには戦争に参加せざるを得なかった人たち、懸命なあまりに突飛な(ときには残忍な)武器を考案してしまった技術者、そういった人たちへの共感とやるせなさ、感慨と自嘲といったものがそのキャッチフレーズから伝わってくるようで、わたしは心秘かに好意を寄せている。そして恐怖小説には、現実逃避の手段というよりも〈心弱きときの活性の糧〉といった性質があるような気がしているのだ」と述べます。
「身長13センチメートルの人」では、アレクサンダー・ペイン監督のSF映画映画「ダウンサイズ」(2017年)が取り上げられます。未来社会の食糧難を解決するべく人間を13センチの縮小人間に変える物語です。ただし、一度縮小した人間は元には戻れません。ここに恐怖を見出す著者は、「引き返せないような決断をすること自体が恐怖なのだ。それは自分自身の判断能力を自分で信用していないということもあるし、もともと臆病者だからでもある。顔にまでタトゥーを入れた人や、大胆な美容整形を行った人を見ると、彼らは内心『しまった、軽率なことをしてしまった』と悔やむことはないのだろうかと思い、たちまち胸がざわついてくる。もちろん彼らは『後悔なんかするわけないだろ!』と言い張るだろうが、夜中にふと目が覚めたとき、暗闇の中で忸怩たる気分に陥ることはないのか。心苦しくならないのか。そうした疑問は、最終的には、自殺を遂げた人に対して生じる気持ちと同質である」と述べています。
第六章「死と恐怖(1)」では、死はなぜ恐ろしいのか。そこを考察するために、死には3つの要素が備わっていて、それらがわたしたちを脅かすのではないかと想定してみるとして、著者は、(1)永遠。(2)未知。(3)不可逆。を挙げます。そして、「死は永遠と結びつくことで、恐ろしくはあっても形而上的で聖なるものとなる。けれども川沿いの墓地を眺めるたびに、永遠というものも案外脆弱なものだと思ったりしてしまう。大雨による川の増水と決壊で、あっさりと形而上も聖性も押し流されてしまうのだ。と、そのような感情移入に満ちた感想の中には、どこか永遠が帯びている峻厳さを突き崩すことで安心感を覚えたがっているような気配がある。おそらくわたしはそうした気配を、ある種の救いに近いとさえ考えているのだ」と述べています。
「不老不死」では、死後の世界について言及しています。天国や極楽は、あえて奇妙な言い方をしてみるならば、「死ぬことによってやっと獲得できた不老不死という安定状態」を多くの善男善女たちと一緒に分かち合い、味わい、ゆったりと暮らしていく世界なのかもしれないと指摘し、著者は「ここならば孤独とは無縁でいられる。死の恐怖もない。穏やかで平和だ。ただし退屈そうだ。竜宮城のエロい世界のほうがわたしは好みだけれど、こちらには玉手箱という罠が待っている。おそらく抜け道はない」と述べています。
「おわりに」では、著者が幼少の頃に父親と「人間魚雷回天」という映画を観たことが語られます。著者はそれがトラウマ作品となったそうです。その後、戦争末期に海軍に所属していた父親が伊号潜水艦への搭乗を志願していたという事実を知ったそうです。著者は、「なぜそんな自殺行為に等しいような志願をしたかといえば、死にたいと父は思っていたからである。彼には仲の良い兄がいて、その人は画家であった。気性の激しいところがあって、そのくせ黎明期のアニメーションの作画などにも関わっていたらしい。そのあたりはいずれ暇になったら調べてみたいと思っている。わたしと気が合いそうにも感じられるが、その『兄』は南方の島に送られて戦死し、結局会ったことは一度もない」と述べています。
「兄」が南の島で戦うことになったのは、父が原因であったそうです。少なくとも父はそう考えていました。著者は、「若気の至りなのか、父には反戦運動的な活動をした過去があったらしい。それに対する見せしめ的な意味合いで、既に徴兵されていた『兄』がとばっちりを受け、南方戦線に送られた。そして呆気なく戦死した。したがって父は『兄』を殺したも同然である(と、信じていた)。そんな顛末に対する贖罪および自己嫌悪の思いから、彼はあえて潜水艦で死のうとした。苦痛に満ちた死に方は、むしろ望むところだったのかもしれない」と述べます。
戦後まで生き延びてしまった著者の父にとって、映画「人間魚雷回天」との遭遇は亡霊と出会ってしまったかのような事態だったのではないかと、著者は考えます。死にまつわる遺恨と罪悪感と自己嫌悪とが、いきなり過去から生々しく蘇ってきたわけであろうと推測し、著者は「そんなふうに考えると、あの映画館という場そのものが亡霊、いや恐怖と同義であったように思えてくる。それを今になってやっと理解した。もはや60年以上も前のことなのに。この本を書かなかったらそんな忌まわしい『発見』をスルーできたのかもしれないと思うと、いささか複雑な気分になってくる」と述べるのでした。恐怖についての本かと思って読み進んでいたら、最後に著者の人生の秘密に触れて厳粛な気分になりました。「恐怖の正体」とは「人間の正体」でもあると思いました。