- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2331 宗教・精神世界 『華厳という見方』 玄侑宗久著(ケイオス出版)
2024.05.28
『華厳という見方』玄侑宗久著(ケイオス出版)を読みました。非常に読みやすく、仏教の真髄を知る最高の一冊でした。
 本書の帯
本書の帯
表紙には、「『空』であるがゆえにすべてはつながっている――ブッダの悟りを描いた『華厳経』の世界を、芥川賞作家がやさしく語る」と書かれています。
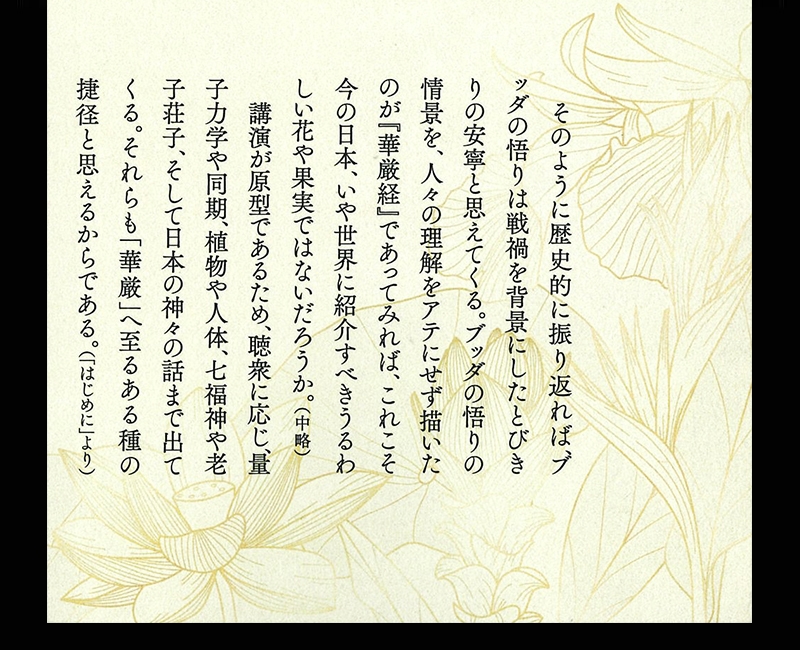 本書の帯の裏
本書の帯の裏
裏表紙には、「そのように歴史的に振り返れば、ブッダの悟りは戦禍を背景にしたとびきりの安寧と思えてくる。ブッダの悟りの情景を、人々の理解をアテにせず描いたのが『華厳経』であってみれば、これこそ今の日本、いや世界に紹介すべきうるわしい花や果実ではないだろうか。(中略)公演が原型であるため、聴衆に応じ、量子力学や同期、植物や人体、七福神や老子荘子、そして日本の神々の話まで出てくる。それらも『華厳』へ至るある種の捷径と思えるからである。(「はじめに」より)」とあります。
アマゾンの内容紹介には、以下のように書かれています。
「『華厳経』は4世紀頃、インド北方の中央アジアで生まれた。お釈迦様が菩提樹の下で深い禅定に入り、「悟り」を開いた時に見えた世界をそのままに描いたお経であるため、難解とも言われるが、般若系統の『空』の思想と唯識系統の『三界はただ心である』という思想が昇華された華厳思想は、『大乗仏典の頂点』とも言われている。一塵の中に世界が宿り、一瞬の中に永遠がある『一即一切、一切即一』の世界。『太陽の輝きの仏』によって衆生が遍く光に照らされる『序列のない』世界。すべてはただ心が作り出す『絶対的な価値のない』世界。物事の来歴、理由、原因は幾重にも重なり、探っても尽きることのない『重々無尽の縁起』の世界。自他が個別性を残したまま、礙(さまた)げなく通じ合うことができる『事事無礙法界』。我々一人一人の菩薩行(雑華)によって荘厳される『雑華厳飾』の世界――。本書では華厳とは関わりの深い禅の僧侶で、芥川賞作家でもある著者が『華厳経』の世界をやさしく語る。講演をベースにした書き下ろしであるため、聴衆に応じて量子力学や同期、植物や人体、七福神や老子荘子、日本の神々まで喩えに使って、わかりやすく「華厳という見方」を説いていく。終戦直後、鈴木大拙はいがみ合う世界に平和をもたらすのは華厳思想しかないと思い到り、『華厳経』を研究してその教えを語り始める。著者はコロナ禍とウクライナ戦争に衝撃を受けてそのことを思い出し、併せて、天然痘と飢饉で人々が苦しんでいた時代に、華厳経の教主を大仏として建立した聖武天皇の深い祈りを思い、改めて『華厳経』を読み直し、その世界を語り始めた。本書はその一端を書籍にしたものである」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
第一章 華厳という見方
――鈴木大拙翁とともに
第二章 「覇権主義」を溶かす思想
――華厳と日本仏教の教え
第三章 華厳の世界観
――ロゴスとレンマ
第四章 縁起について
――お釈迦さまの悟りとは
「おわりに」
「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。
「お釈迦さまが「悟り」を開かれたとき、どんな情景を目にし、なにを感じられたのか、それは仏弟子である私にとっては長年に亘る最大の関心事だった。しかしどういうわけか、なかなかそこに絞り込めなかった。言い訳するようだが、あまりに仏典が膨大なのである。私の場合、まず禅に関わる典籍が優先だったし、やはり上座部の仏典にも触れておきたい。『大乗起信論』や『中論』や唯識も気になるし、そのうち『浄土三部経』や密教系の陀羅尼なども学びたくなってくる。お寺の仕事をしながらでは、いくら時間があっても追いつかないのである」
さらに著者は、「そして『維摩経』はまだしも、『法華経』や『華厳経』となると、一つのお経じたい長大になる。そうなると、今年はとにかく『法華経』を読み通す、というような決意が必要になる。そうして『華厳経』に辿り着いたのはもう50歳を過ぎてから。人生もひときわ味わい深くなってからだったのである。遅きに失した感はあるものの、それは私にとってこれまで学び、経験したすべてを総合してくれるような、実り多き時間だった。いや、まだまだ途中ではあるものの、学べば学ぶほどに仏教の裾野が見えてくるように感じた。そして同時に、雲に覆われていた山の頂もなんとなく形を露わしてくるように思えたのである」と述べています。
思えばブッダが生きた時代のインドも、戦禍の連続でした。「仏の顔も三度まで」とは、隣国であるコーサラ国に故国・釈迦国が攻められようとするのを、ブッダが3度までは身を挺して防いだことに由来するとか。ちなみに4度目はブッダも止めに入らず、釈迦国はブッダの存命中に滅亡します。著者は、「そのように歴史的に振り返れば、ブッダの悟りは戦禍を背景にしたとびきりの安寧と思えてくる。ブッダの悟りの情景を、人々の理解をアテにせず描いたのが『華厳経』であってみれば、これこそ今の日本、いや世界に紹介すべきうるわしい花や果実ではないだろうか」と述べます。禅を世界に紹介した鈴木大拙は1955年に『華厳の研究』を著しました。著者は、「大拙翁が『東洋で発展し温存されたものの最高頂』と讃えた『華厳経』だから、その頂の踏破は無理だとしても、それぞれ身近な話題を通して山容を仰ぐポジションを見出し、『華厳という見方』に親しんでいただければ無上の歓びである」と述べるのでした。
第一章「華厳という見方――鈴木大拙翁とともに」の「今の世を覆う『覇権主義』」では、かつて鈴木大拙が名著『東洋的な見方』で述べた「今日の世界が、どうしてこうなったかというに、それは力というものを、重んじすぎたからである。第1、第2の世界戦争のもとは力の争いである。自分の力で他を圧しようとするからである。自分さえ勝手ができれば他はかまわぬと考えるのは昔からあるが、近代では、それが集団になった。自国他国とむやみに区別をつける。近ごろは主義の上に区別をつけ、それを暴力で実行せんとする」という言葉を紹介し、著者は「なんとなく、今の時代の話のように聞こえませんか? 今の世の中を覆っているのは、第2次世界大戦の時と同じ『覇権主義』の考え方なのではないか。そしてこの覇権主義の考え方を溶かす一番の特効薬が、華厳の思想なのではないかと思うのです」と述べています。
「聖武天皇が深く傾倒した華厳の教え」では、終戦直後に鈴木大拙が昭和天皇にご進講したことが紹介されます。そのときの内容をまとめた『仏教の大意』には、「『華厳経』に盛られてある思想は、実に東洋――インド・シナ・日本にて発展し温存せられてあるものの最高頂です。般若的空思想がここまで発展したということは実に驚くべき歴史的事実です。もし日本に何か世界宗教思想上に貢献すべきものがあるとすれば、それは華厳の教説にほかならないのです」と書かれています。大拙は、東洋の宗教思想の中でも、最も誇るべき考え方がこの『華厳経』にあると言っているわけです。この後、大拙は華厳の研究を推し進めて、昭和30年に法蔵館から『華厳の研究』という本を出すのでした。
「廬舎那仏の光が遍く一切を照らす」では、『華厳経』の内容が簡単に紹介されます。『華厳経』は「六十華厳」や「八十華厳」など何種類かありますが、いずれも単独のお経がいくつか集まったものです。著者は、「お経にはこういうものが多いのですね。はじめから誰かが通しで書いたものではなくて、これも素晴らしいから入れ込んじゃおうという形で、どんどん増殖していくのです。どのお経にも一貫して描かれているのは『華厳の浄土』です。浄土にもいろいろありますが、たぶん皆さんがご存じなのは、『阿弥陀の浄土』ですよね。西の方、夕日の彼方にあると言われています。しかし東の方には薬師如来の『瑠璃光浄土』があります。瑠璃色の朝日の中ですね。そして華厳の浄土は、どこにあるのか『蓮華蔵浄土』と言います」と述べます。わたしはかつて『リゾートの博物誌』(日本コンサルタントグループ)という本でありとあらゆる浄土を紹介したことがあるのですが、それを思い出しました。
「七福神の宝船が象徴する世界平和の姿」では、絶対的な価値はないという考え方を基に作り出したものが紹介されます。室町後期に原型ができて、江戸初期にだいたい完成した「七福神」です。七福神とは、当時の世界を象徴したものでした。まだオランダと交流のない頃、日本にとって世界というのは本朝と支那と天竺でした。このインド、中国、日本の代表者を集めて7人にしたのが七福神です。著者は、「能楽の世界では、室町後期に恵比寿、大黒、毘沙門、弁天という神様がもう知られています。そこに『あと3人を加えて、7人にしてもらえないか』と、臨済宗の坊さんに依頼した人がいるらしいのです。それが誰かということも一応、研究からわかっています」と述べています。これは初めて知りました。
7人にしたのは「7」が仏教の聖数だからです。日本の聖数は「8」ですが、中国は「9」で、インドは「7」です。ヨーロッパも「7」です。それゆえ仏教的な話は何事も7が規範になるのですが、「7人にしましょう」と言われて加えたメンバーを見ると、これを考えたのはどうしたって臨済宗の和尚だな、ということがはっきりするそうです。誰を加えたかというと、福禄寿と寿老人と布袋和尚の3人です。福禄寿と寿老人はもともと道教の神ですし、布袋和尚は実在した臨済宗のお坊さんですから、これは間違いないだろうと思えるわけです。
とは、イザナギ(伊邪那岐)とイザナミ(伊邪那美)の間に最初に生まれてきた未熟児です。ちょっと手続きを間違えて、蛭子ができてしまったと『古事記』に書かれています。蛭子という不完全な子どもができてしまったので、海へ流したと言われているのですが、流されたのを恨むどころか、海の守り神になって戻ってきました。その時「蛭子」という文字を「えびす」と読み替えて、「恵比寿」として戻ってきたとされます。蛭子が恵比寿になった。スタンダードどころか未熟児だった人が神になり、そこに「みんな集まれよ」といってインドから3人、中国から3人集まってできたのが七福神です。著者は、「つまり『スタンダードはない』ということが明確に示されている集団です。こういうものが日本人の考えた世界平和ではないでしょうか。誰かが力で圧倒するものではないのです」と述べます。まったく同感です。
 皇産霊神社の七福神
皇産霊神社の七福神
じつは、わたしは七福神が大好きで、『リゾートの博物誌』の姉妹本である『リゾートの思想』(河出書房新社)の中で、「日本的リゾートのヒント」として七福神について詳しく書きました。あのバラバラな7人が一緒にいられるのはなぜか。著者によれば、最後に布袋和尚を入れたからだそうです。著者は、「布袋さんというのは別名を『哄笑仏』と言いまして、哄笑ですから高笑いです。『あんた、おもろいやっちゃなぁ、ガッハッハ』と笑うのです。『ワシとは違うけど、ほんまおもろいなぁ』と言って笑うのが布袋さんです。そうしていれば、全く違う考えの人たちが一緒に仲良くできるじゃないか。江戸の初め頃にそういう世界平和のイメージが完成するのです。ここにも華厳の考え方が色濃く入っていると思います」と述べるのでした。布袋さんの「哄笑仏」という呼び方からは「笑い」とは「和来」であることを連想しますね。
「すべては心が作り出している」では、「華厳という見方」の一つ目として、序列のない世界というものが示されます。華厳の説く世界観で二つ目に大きいのは、「すべては心が作り出したものだ」という見方だといいます。大乗仏教に「唯識」という思想体系がありますが、著者は「この唯識も華厳に通底しています。ほとんど合流したと言ってもいいぐらいです。正しいということも、良いということも、美いということも、みんな心が作り出しています。ある意味で虚仮の世界でありまして、それが絶対に正しいということはない」と述べています。それは、七福神の示す多様な価値観とも似ています。「一滴の雫が大宇宙を宿している」では、『華厳経』の三つめの特徴が端的に示されます。このお経は「縁起」という考え方を細かく分析し、深く見つめています。縁起というのは、「重重無尽」というのですが、幾重にも重なって、それは尽きることが無い――「重重無尽の縁起」ということです。
物事というのは、今こうであるということの来歴、理由、原因、そういうものを探っていくと、無限の事柄に関係しています。仏教では「単独の私」はありえない、独立した存在はない、という考え方を執り、これを「諸法無我」と言います。著者は、「周りはどうであろうと、私はこうですということはあり得ないのです。すべては影響し合って、今、その結果がここにこうしてあります。むろん、今も変化しつづけているわけです。『華厳経』はこのことを非常に美しい比喩で描いています」と述べます。帝釈天(インドラ)の宮殿の天井に天の網があり、非常に細かい網の目なのですが、すべての交わり目に玉がついています。玉というのは輝く石です。この玉に他のすべての玉が映っています。1つの玉が動くと、網全体の玉に映っている様子もすべて変わります。その玉に一切が映り、一切の玉に1つが映っていることが「一即一切」であり、「一切一即」なのです。
「華厳思想の四つの見方」では、『華厳経』は、我々の目に見えたり、鼻で嗅げたり、耳で聞いたりする個別具体の世界を「事法界」と呼んでいることが紹介されます。「理法界」というのは、それらすべてに「空」という「理」を見ること。「空」の世界です。何かが空である、だからそれは変化し続けているし、それが自性ではない、というふうに見るわけです。「理事無礙法界」というのは「色」もわかるし、それが「空」であることも矛盾なく1つのものに宿っている、そのことがわかりますということです。「理事無礙法界」は、言語を使えるようになったホモ・サピエンスの世界と言うこともできるとして、著者は「我々は『花』とか『机』とか『理想』など、ずいぶんレベルの違う言葉を日常的に使っていますが、これは多くの具体物に何らかの共通する『理』を見出し、その『象徴』として言葉を生みだしたということです。共通項は、見た目や機能や理念だったりしますが、多少の食い違いはあるにしても、それによって細かい意思疎通が可能になったわけです」と説明しています。
「自他が礙げなく溶け合う『事事無礙法界』」では、状況によって名前まで変わるのが日本の神であると指摘し、著者は「これは誠に縁起的です。そして華厳的です」と述べます。「事無礙法界は『大悲心』によって実現する」では、慈悲について語られます。人の悲しみに同化できる能力――大乗仏教では特に「大悲心」ということを言いますが、この大悲心をもつことが必要だといいます。「華厳の教えで日本仏教をまとめなおす」では、鎌倉時代に、日本仏教は比叡山からいろいろな宗派に分かれていったことが指摘されます。それは比叡山があまりにも総合的でとっつけない。だから、とっつきやすい切り口を考えた方たちが、いろいろな宗派を作ってくれたというふうに著者は考えているそうです。
でも他方で、著者は「それをもう一回統合できないものだろうか」というふうにも時に思うそうです。日本仏教という1つのまとまりはできないものなのだろうかと考えるそうですが、その時に思うのは、日本仏教すべてに入り込んでいる考え方は華厳の教えだろうということだとか。著者は、「大拙先生が特にテーマにしたのは禅と浄土系ですけれども、先ほど申しましたように、真言宗にも明恵上人がいて、華厳が入っている。日蓮宗にも入っています。華厳の教えがほぼ全ての宗派に行き渡っているのです。鈴木大拙博士が注目した華厳を中心に日本仏教を語っていくと、全体としてまとまった日本仏教になるのではないか。ある意味では、いろいろある宗派を統合するような仏教を鈴木大拙という方は語ろうとしていたのではないか、という気がしているのです」と述べるのでした。
第二章「『覇権主義』を溶かす思想――華厳と日本仏教の教え」の「覇権主義に染まる世界」では、今どういう状況にあるのかを考えると、まず思い浮かぶのは「覇権主義」という言葉だといいます。自国の影響力を拡大するために、軍事・経済・政治などの面で自分より弱い国に介入して影響力を与え、その国の主権を侵害しようとする、これが辞書的な覇権主義の定義ですが、著者は「近頃は多くの国がそうです。もちろん、ロシアもそうです。中国もそうですし、トルコやインドもそうでしょう。どの国もかつて大帝国時代を経験している国々です」と述べています。
「『覇権』ともう一つの『ハケン』」では、終戦直後、鈴木大拙は覇権思想を溶かすもの、解毒剤は何だろうと考え、それは華厳思想なのではないかと思い到りました。そして、1946年に天皇皇后両陛下に御進講を行ないましたが、その内容は始めから終わりまで華厳でした。「華厳」という言葉は「雑華厳飾」の短縮形から来ています。「雑華厳飾」というのは「雑な華で厳飾る」という意味です。でも、著者によれば、我々は「雑な華」という時の「雑」という言葉にあまり良いイメージを持っていないといいます。ところが文学博士の中西進氏によると、古代では「雑」で「五つの彩」、「五彩」を表わしていたそうです。「雑誌」だって、べつに雑なわけではなくて、いろいろ載ってるということでしょう。
また鈴木大拙は『華厳の研究』を書いたとき、「雑華」を「普通の花」と訳しています。みんな普通の花なのです。多様なものに彩られた、序列のない世界を『華厳経』は説いています。著者は、「あるいは別の表現をしますと、仏さまの額の白毫から出た光は影ができないといいます。光が当たるとそこには影ができるのが普通ですが、すべてが光に満たされてしまう。そういう光を発する仏さまがいて、毘盧遮那仏あるいは盧舎那仏といいます。ヴァイローチャナブッダ、即ち『太陽の輝きの仏』が『華厳経』の教主です」と説明します。
ウクライナ戦争でも、ロシアでは12万人が亡くなっていると言われます(2023年3月現在)。もっと多いという人もいますが、そうすると、恩給は大変な金額になってきます。今後の国家財政をどれだけ圧迫するかということを考えると、これは大変なことです。そこで、インフラ整備で現地に行く方々をチェイニー副大統領がつくる派遣会社の社員にしてしまって、民間人のままでイラクに派遣した。これが派遣会社の始まりだと指摘し、著者は「これはいいということで、世界にどんどん広がっていったのです。おかげで非正規が増え中間層が激減して、先進国の国力衰退をもたらし、新自由主義の名の下にグローバルな経済覇権の流れがつくられていった。その元を辿れば、派遣会社に行きつくのではないかと、じつは私は思っているのです」と述べます。
「脳内に浸透する『覇権思想』」では、日本も戦前までは軍事的な覇権主義であり、領土もどんどん増やそうとしたことが指摘されます。しかし戦後の日本は、国民全体が豊かになるという経済復興に舵を切りました。著者は、「覇権思想とは無縁になったと思っていたのですが、ふと気づくと、経済の現場においてまた覇権思想が幅を利かせていたのです。その結果、今度は個人の脳の中にも覇権思想が浸透していったのではないかと私は考えています」と述べます。今、15歳~39歳の若い人たちの死因の第1位は自殺です。では10歳~14歳までの死因の第1位は何かと言いますと、小児がんです。しかし小児がんに次いで、自殺が第2位なのです。著者は、「若い人たちがなぜこんなに自ら死んでいくのかということは、本当に国家的な大問題だと思います」と述べるのでした。
「異なる考えや偶然を排除する風潮」では、著者が「合理的推論」と呼ぶ考え方が紹介されます。若者が自殺してしまうとき、「今後、自分はこうであるに違いない」「これは理想からするともはや回復を望むべくもない事態で、どうしようもない」と思うわけです。つまり、「絶望」するのです。禅には「風流」という言葉があります。違った考え方、予測できなかった出来事に遭ったとき、わたしたちは揺らぎます。揺らいで、なんとか揺れ戻りそうだなと思った時に「風流だなぁ」と呟く。だから実は動揺しているのだといいます。「I was moved」という感覚に近いと指摘し、著者は「それははじめは動揺だったのが、『感動しました』というふうに意味が変化した表現でしょう。それは心が動いたのですが、なんとか戻ったからそう言えるのです。そうやって、予測できなかった出来事や違う考え方を『風流だなぁ』と受け容れられたらいいと思うのですけれども、今はそうではないですね」と述べます。
「ラオスの会議には『レジュメ』がない」では、現代社会では、親愛の情を示すのは手紙の冒頭の「dear」だけだということが指摘されます。それで済ませているのが日本ですが、震災が起こった当時の東北には、親愛の情を示すという文化がまだありました。著者は、「最近は変化しつつあると思いますが、いわゆる午後3時のお茶です。『お茶っこ文化』と呼ぶ人もいますけれども、ご近所にお茶を飲みに行くのです。お茶を飲んで漬物を食べたり、お菓子を戴いたりして、よしなしごとを話す。そして30分ほどすると帰っていく。以前はうちのお寺でも鉄瓶のお湯がいつも湧いていましたから、3時になるとご近所の方が来ました。『何しに来たの?』と思うのですけれども、単にお茶を飲みに来たのですね。親愛の情を示しに来たんです。お寺の行事に茶礼という挨拶行事があるのですが、それもそういうことでしょうね。しかし儀式的な茶礼を除いては、3時のお茶もだんだん消えつつある。『誰々ちゃん、遊びましょ』というのもなくなりつつある。本当に寂しい限りです」と述べます。
「覇権主義を溶かすのは『宗教の行』」では、瞑想について語られます。瞑想とはどういうのかと言うと、脳の使い方として2つあるわけです。1つは言葉と論理、あるいは計算。これは主に左脳と言ってもいいですが、ロジカルな脳の使い方。いわゆる普通に言う「知」です。「分析知」と言ったりしますけれども、それに対して「瞑想智」は言葉を介在させない「知」です。仏教的にはこっちは「智」の文字を使いますが、これは明瞭に醒めていますけれども、言葉を生まない。著者は、「瞑想にはいろいろな技術がありますが、日本仏教はその技術のデパートです。鎌倉仏教で生み出したものは、瞑想のバラエティです。中国伝来の坐禅のままやろうというのが、禅宗です。それは大変だは大変だろうし、もうちょっと敷居を下げてあげようよというのが、『専修念仏』を唱えた法然さんです」と述べています。
簡単に三昧になるシステムを日本仏教はいくつも開発しましたが、それによって「脳内の覇権」は溶けるはずだといいます。では覇権が溶けて、どういう状態になっているのか。瞑想状態とは何なのかというと、理知以外の脳のもう1つの機能であることは確かで、直観力が増すと言われます。最近の脳科学では、習慣的な瞑想が海馬のニューロン新生を引き起こすとの報告もあります。著者は、「お経を唱えるというのもじつは瞑想の一種で、唱えはじめるとすぐに脳波がα波になります。今の皆さんの脳波は、よほど睡い方を除いてはβ波(13~40ヘルツ)だと思いますが、α波(8~13ヘルツ)とは何なのかというと、じつは小学生の脳波です。もっと深い三昧になると、θ波になると言われます。これは4~8ヘルツの脳波で、幼稚園児の脳波です。苦労してお経を覚えて、小学生や幼稚園児に戻っているわけです。しかし、これが覇権を溶かす非常に優れた方法なのです」と説明しています。そして最後に、著者は「結果だけAIからもらおうという、この極端な功利主義の流れが今後どうなっていくのか、非常に気にかかります」と述べるのでした。
第三章「華厳の世界観 ロゴスとレンマ」の「大乗仏教の完成形としての『華厳教』」では、色即是空という考え方をもとに発達した「空」の思想は、インドの真ん中あたりで広がったことが紹介されます。そして、インドの北方から中央アジアにかけて、大乗仏教のもう1つの大きな流れである「唯識」という考え方が生まれます。「心が世界を作っている」「三界はただ心である」というものですけれども、この唯識仏教がインド北方で発達していきます。さらには4世紀ぐらいから、般若と唯識という2つの大きな流れが合流して、大乗仏教の完成形のような案配で『華厳経』が出てきます。
「ロゴス的な世界とレンマ的な世界」では、「ロゴス」とは元々は並べて整理することであると紹介されます。だから言語化する、計算するということができるわけですが、世界はそれだけでは把握しきれません。ロゴスが盛んに語られた同じギリシャの時代に、全体を一瞬に把握するしかない世界があるということで、そうした捉え方は「レンマ」と呼ばれました。「ロゴス的な世界」と「レンマ的な世界」があるわけです。レンマという言葉をロゴスに対置する言葉として初めてはっきり使ったのは、西田幾多郎の弟子である山内得立です。彼自身は1982年に亡くなっていますが、主著である『ロゴスとレンマ』は2020年にフランス語訳され、オギュスタン・ベルクも自らの「風土学」に参照しています。
また中沢新一氏は、仏語訳以前に力作『レンマ学』をまとめています。この2つの智恵のあり方について、言語化して計算するというロゴスの方を「分析知」と呼ぶ著者は、「分析することで、わかることもあります。分けたから、分かった気になるわけです。そしてもう一方は『瞑想智』と呼んでいます。瞑想状態と通常の意識状態は明確に違います。だから見えているものも違います。しかし、両方とも人間が本来持っている知性(intelligence)です」と述べます。
「『相補性』を含んだインドの論理学」では、量子力学を世に知らしめたのはニールス・ボーアですが、彼は「相補性」ということを言っていることが紹介されます。たとえば光は粒子であったり、波であったりする。2つの対立する見方が補い合って1つの真実を説明するということです。この時初めて、西洋は「相補的」という見方を知ったのです。ところが、仏教は昔から「色即是空」と言っているわけです。あらゆる形あるものは「空」と見ることができる。「空」であるがゆえに、あらゆる個別のものの形をとることもできる。「空即是色」です。もともと仏教は、世界を「色」と「空」という相補的な見方で見ていたわけですね。
いわゆる客観性というものが、これでは否定されるだろうと考えたアインシュタインは、ニールス・ボーアや不確定性原理を唱えたハイゼンベルクと距離を取るようになります。何といっても、因果律が崩れるのは困る。原因と結果という法則のなかに世界は収まっているはずだという信念を抱いたまま、アインシュタインは向こうの世界に行かれたわけです。けれども、どうも真相はそうではなかったようだとして、著者は「客観的な世界というのは、もしかすると、ないのかもしれない。その時々の状態が観測によって個別に見える世界に我々は住んでいますけれども、同じ世界がすべてつながって見える状態というのも、あるのではないか。お釈迦さまが成道後にご覧になった華厳の世界とはそういうことではないか」と述べています。
「『相即相入』して生き延びた我々の命」では、華厳の世界は「一即多」であると指摘しています。「一」の中に「多」があり、「多」は「一」にすべて凝縮されている。これは「一即一切」「一切即一」という言葉にもなっています。そして、この全部がつながっている状態というのは、「相即相入」という言葉で表現されているとして、著者は「『即』は『つく」』とか『よる』という意味ですから、ピタッとくっついて、お互いに入り込んでしまう。生命というのは、実はそういうことをしながら、ずっと生き延びてきたのではないかという見方があります。皆さんの身体に、細胞ごとにミトコンドリアが入っているのはご存じですか。リン・マーギュリスという女性の生物学者が、このミトコンドリアに関して『細胞内共生説』を唱えます」と述べています。
「ある種の必然は『偶然の顔』をしてやってくる」では、「わらしべ長者」という昔話が取り上げられます。著者は、「最近はあまりはやらないのではないですかね。ああいう行き当たりばったりの生き方は、恐らく推奨されないでしょう。でも、縁起の全体を我々はつぶさに見ることができないですから、約半分はハプニング(happening)の形で起こります。そのハプニングを受け入れる形で、我々は我々の頭の偏りを補っている。何度も言いますが、『ハプニング(happening)』と『ハッピー(happy)』は語幹が同じ『happ』だということを忘れてはいけないと思います」と述べます。
第四章「縁起について お釈迦さまの悟りとは」では、「縁起」が取り上げられます。「縁起」というのは、お釈迦さまがお悟りになった一番大事な法です。日本語では「縁起がいい」とか「悪い」とか言いますけれども、本来は、この世はすべて「縁起の法」に従って動いているということです。「いい」も「悪い」もないおして、著者は「我々禅宗は坐禅という行をします。あるいは浄土系統は念仏をお称えします。天台宗には三千仏礼拝がありますし、日蓮宗や真言宗には滝行をする人々もいます。日本の仏教は何かの行に三昧になることを大事にするのですが、それによって何が起こるのかというと、『般若の智慧』が発現するというふうに考えているわけです。別の言葉で言いますと、『瞑想智』が発揮されるわけです」と述べています。
『華厳経』はいわゆる対機説法――悩んでいる人に応じていろいろな説き方をするお経ではなく、お悟りを開いた状態で世界はどう見えるかをそのまま説いているので、非常に難解だと言われます。しかしお釈迦さまがご覧になった世界を、解釈を加えず端的に表現しているとも言えます。また、「色即是空」という言葉について、著者は「あらゆる物、あるいは認識の対象すべてですから、心もそうなのですけれども、そこに実体はない。『自性』がない。つまり固定的なあり方がない。仮和合とも言います。そういう意味で『空である』とされます。その「空」を中心に説いたのが『般若経』と言われる一連の経典です。これはインドの中央部の平原あたりで発達します。その『空』ゆえの原理なのですが、空であるがゆえにすべては繋がりあうことができる。全体は部分の集合ではなく、繋がり合いつつ連動している。これが『縁起』という世界観の要です。この『縁起』を中心に説いたのが『華厳経』で、このお経が生まれたのは、今でいうと新彊ウィグル自治区のあたりになります」と述べます。
 『慈経 自由訳』(現代書林)
『慈経 自由訳』(現代書林)
「尋常ではない『不殺生』へのこだわり」では、お釈迦さまが説いたとされる『慈経』というお経の一部である「いかなる生物生類であっても、怯えているものでも剛強なものでも、悉く、長いものでも、大きなものでも、中くらいのものでも、短いものでも、微細なものでも、粗大なものでも、目に見えるものでも、見えないものでも、遠くに住むものでも、近くに住むものでも、すでに生まれたものでも、これから生まれようと欲するものでも、一切の生きとし生けるものは、幸せであれ。(中略)あたかも母が己が独り子を命を賭けても護るように、一切の生きとし生けるものに対して無量の慈しみの心を起こすべし」という教えが紹介されます。ちなみに、わたしは『慈経 自由訳』『慈経 自由訳』(現代書林)を書きました。
「『量子もつれ』を認めなかったアインシュタイン」では、最近の宇宙物理学において部分の集合が全体ではないということがはっきりしてきたことが紹介されます。わたしたちの宇宙はあらゆる部分に全体の影響が常にある世界だということがわかってきたのです。カリフォルニア大学バークレー校のジェフリー・チューという中国系アメリカ人の学者は、「ブーツストラップ理論」という仮説を唱えました。宇宙というのは、部分の集合としては捉えられない。あらゆる部分が他の部分に相互依存している一種のダイナミックな織物のようなものである。そういう宇宙論を唱えたのです。それが『華厳経』のインダラ網と全く同じ話だということに気づいて、チュー教授は驚いたそうです。息子が高校の仏教の授業でインダラ網の話を聞いて帰ってきたのです。それを父親に話したら、「なんだ、おれのブーツストラップ理論と同じじゃないか」と言って愕然としたというのです。
「ホモ・サピエンスにおける言葉や音楽の発生」では、ネアンデルタール人は歌も歌えなかったことが紹介されます。じつは『歌うネアンデルタール人』(スティーブン・ミズン/早川書房)という本があるのですが、彼らは「hmmm…」という歌のような発声はしていたようですが、「音階」というものを持てなかったといいます。著者は、「『理事無礙法界』を知った我々ホモサピエンスは、言葉と前後して音楽も持ちました。『同じ音』、あるいは倍音に対する『近似音』という『理』の感覚、つまり『似てる』、あるいは『同じだ』という感覚が、やがて音階やオクターブという概念を産みだします。ネアンデルタール人は、単独の音は理解したのかもしれませんが、その規則性には気づかず、いわゆる音楽は産みだせなかったわけです。ホモサピエンスだけのもつ音楽が、いかに瞬時に我々を別天地に運び、思いもよらぬものに繋げてくれるかは、皆さんも日々感じていらっしゃるかと思います」と述べています。
「華厳の世界観は『気』の考え方によれば理解しやすい」では、わたしたち日本人に華厳の考え方がわかりやすいのは、「気」というもので理解できるからではないかといいます。「天気」「元気」「陽気」「人気」「士気」「勇気」「殺気」「気が合う」「気にかかる」「気合を入れる」など、日本語から「気」という言葉を削除したら、話が通じなくなる恐れがあるぐらい「気」を使った日本語は多いですね。それぐらい「気」は、そこかしこに浸透しています。著者は、「ただ『気』とインダラ網の違いは、インダラ網には交わり目に宝玉がついていることから、個別性がもっとはっきりしていることです。個別性がありながら、すべてが調和してつながっている」と述べます。
「人生の最期に悟る『事事無礙法界』」では、いずれにしても、無数の命たちはおそらくみんな繋がっていると述べられます。もしかすると宇宙の果てでも相関するという「量子もつれ」のように、元が一つの生命体だったからかもしれません。著者は、「お釈迦さまの目で見ればそれらはきっと今でも繋がったままなのですが、これこそ私だと誤解したまま生き続ける我々には、なかなかそうは思えません。勝手に孤独になって悩み、そしてやっぱり誤解だったのかと思いながらやがてインドラ網の中に溶け込んでいく……。それがたぶん、普通の人の人生最期の時なのではないでしょうか。そうなるまえに、瞑想をしてみてください。毎日短い時間で結構ですから、習慣化させるのです。そのうち『奇なるかな奇なるかな』と呟くときが来るのを祈っております」と述べるのでした。