- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2326 社会・コミュニティ 『「今どきの若者」のリアル』 山田昌弘編著(PHP新書)
2024.05.09
明日で61回目の誕生日を迎えるのですが、若者についての本を紹介させていただきます。『「今どきの若者」のリアル』山田昌弘編著(PHP新書)を読みました。編著者の山田氏は、1957年、東京生まれ。1981年、東京大学文学部卒。1986年、東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。現在、中央大学文学部教授。専門は家族社会学。「パラサイト・シングル」「格差社会」「婚活」などの言葉を世に広めたことでも知られます。著書に、一条真也の読書館『結婚不要社会』で紹介した本をはじめ、『希望格差社会』(筑摩書房)、『新型格差社会』(いずれも朝日新書)、『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか?』(光文社新書)など多数。専門は家族社会学。学卒後も両親宅に同居し独身生活を続ける若者を「パラサイト・シングル」と呼び、「格差社会」という言葉を世に浸透させたことでも知られます。「婚活」という言葉を世に出し、婚活ブームの火付け役ともなりました。ちなみに、ブログ「無縁社会シンポジウム」で紹介した2012年1月18日に横浜で開催されたパネル・ディスカッションで、わたしは山田氏と共演したことがあります。その内容は、ブログ『無縁社会から有縁社会へ』で紹介した共著書に収録されています。
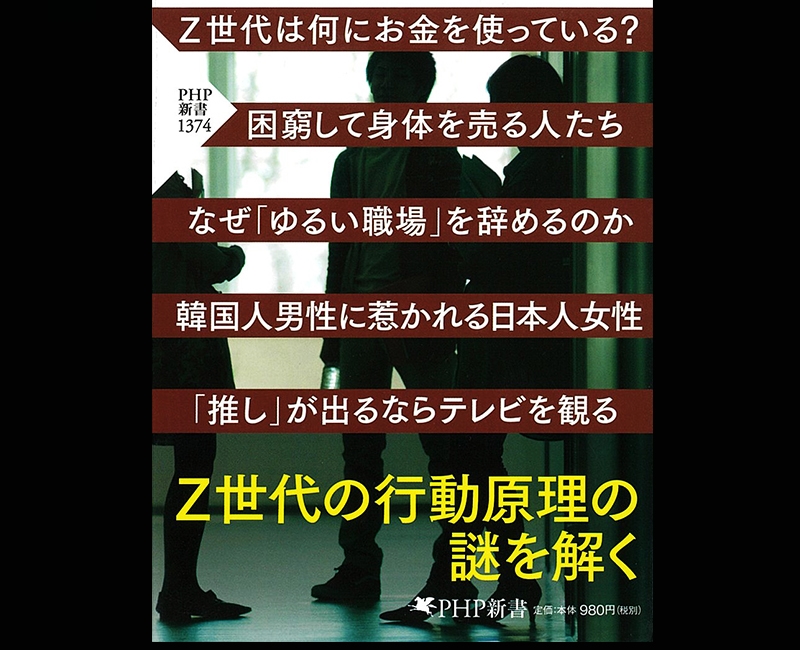 本書のカバー表紙
本書のカバー表紙
本書のカバー表紙には、「Z世代は何にお金を使っている?」「困窮して身体を売る人たち」「なぜ『ゆるい職場』を辞めるのか」「韓国人男性に惹かれる日本人女性」「『推し』が出るならテレビを観る」「Z世代の行動原理の謎を解く」と書かれています。
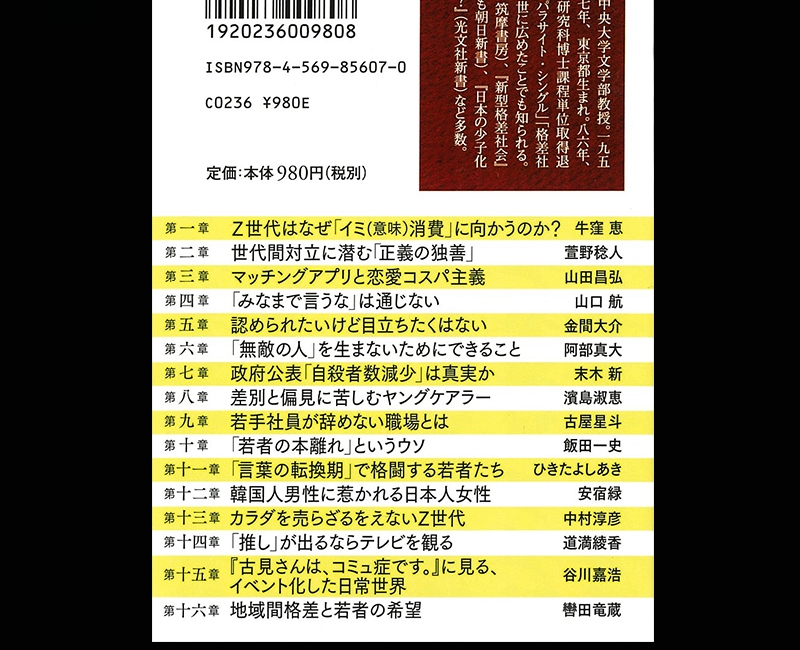 本書のカバー裏表紙
本書のカバー裏表紙
カバー裏表紙には「目次」が紹介され、さらにカバー前そでには「16人の識者による分析で、若者の実像が見えてくる!」として、「『今どきの若者は〇〇だね』と自らの印象で語られがちだが、研究者やノンフィクション作家たちは若者をどう捉えているのか。『承認欲求はあるが人前では褒められたくない』『「ゆるい職場」だと自分は成長できるのかと不安になる』『「SDGsに配慮したモノだと、堂々と胸を張れる」など「意味のある消費」を望む』……。Z世代の思考を知り、日本の今と将来を考える」と書かれています。
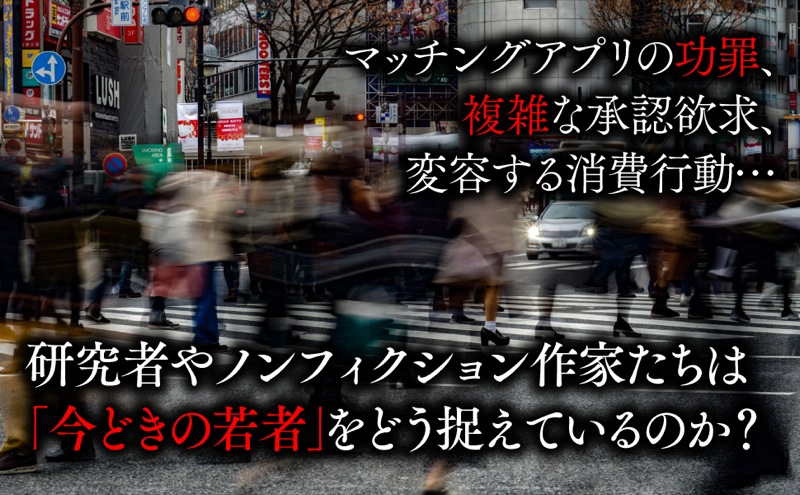 アマゾンより
アマゾンより
「まえがき」で、山田昌弘氏は「かつて、1960年代後半、学生運動が盛んだったとき、若者は、反抗の世代と言われた。しかし、その後、反体制だったはずの男性のほとんどが正社員(公務員)となってモーレツ社員と呼ばれるようになり、女性のほとんどが結婚し主婦となって教育ママと呼ばれるようになった。1960年代には、このまま日本社会はこれらの若者によって変革されるのでは、という期待と不安があったが、彼らは結局、高度成長の波に乗って、むしろ戦後体制に順応していった。後で、小熊英二氏に当時の学生運動は「自分探し」だったのでは、と評価されるまでになる(小熊英二著『1968』新潮社)。今の若者は、権威に反抗するものは少なく、政治的にも自民党支持が多く、保守的になったと言われている。だからといって、これからも同じ状態が続くとは限らない」と述べています。
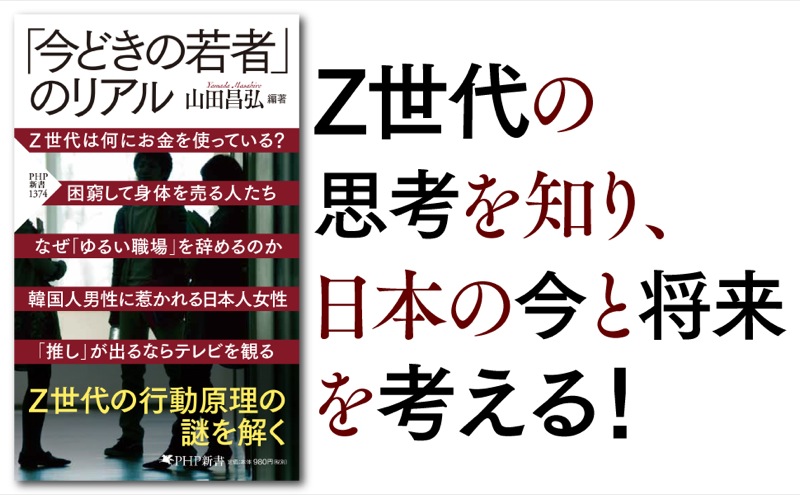 アマゾンより
アマゾンより
第一章「Z世代はなぜ『イミ(意味)消費』に向かうのか?」の「消費傾向は『快感』『達成』から『没頭』『関係』『意味』へ」では、世代・トレンド評論家で立教大学大学院(MBA)客員教授の牛窪恵氏が、「2000年代、アメリカの心理学者マーティン・セリグマン(Martin E.P.Seligman)氏は、ウェルビーイング(主観的幸福感)を量る指標として『PERMAモデル』を提唱しました。これに基づけば、日本でバブル期まで重視されていた幸福の要素は、おもに『P(Positive Emotion/快感)』や『A(Achievement/達成感)』にあったのではないかと考えられます。すなわち、『あのクルマに乗りたい』『あの家に住みたい』などと憧れ、その欲求が達成されると『やった!』と快楽を覚えるようなイメージです」と述べています。
バブル経済が崩壊し、あらゆるモノが身の回りに溢れ、さらに2011年3月、東日本大震災が襲ったことで、草食系世代(当時30歳前後)以降の若者らは、「モノより思い出」の意識を強くした印象があります。また、2015年頃からは「コト消費」が顕在化すると共に、物欲よりスマートフォン(スマホ)やSNSを介した「コミュ欲(コミュニケーション欲求)」が高まりました。牛窪氏は、「こうしたなかで若者たちは、かつての達成や快楽により、『PERMAモデル』の『E(Engagement)』や『R(Relationship)』、『M(Meaning)』、すなわち『没頭』や『人間関係(つながり)』、そして『イミ(意味合い)』を重視するようになったのです」と述べます。
「『周りにどう見られるか』を意識して旅行先を決める」では、Z世代が「SNS(動画)ネイティブ」と形容されることが紹介されます。彼らにとっては、スマホやSNSを通じて「ネタ」にできたり、「自分はこれがいいと思う」と堂々と胸を張って人に薦められたりすることが重要だといいます。2021年の流行語に「推し活」が選ばれたのも、若者を中心にSNS上で「推し」を共有する第三者とつながる行為が盛り上がりを見せたためであろうとして、著者は「Z世代がSNSや動画上で、なにかを共有・共感し合ううえでは、彼らの『SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)』に対するこだわりも、大きく関与すると言われています」と述べるのでした。
「『誰かの役に立ちたい』という思いが強い」では、アメリカで全人口の2割以上を占めるZ世代でることが紹介されます。日本では人口の1割程度(約13%)に留まるなど、数のうえでは少数派です(総務省「国勢調査」ほか)。それでも企業が彼らに注目する理由は、少なくとも3つあるのではないかと考えているといいます。その1つ目が、彼らが時代の先端を行き、トレンドに敏感であること。2つ目が、「SDGs」との親和性。そして3つ目が、SNSを通じた拡散力(口コミ力)や「人とのつながり」で消費するという、令和型消費の担い手である点です。
実は、Z世代を含むゆとり世代以降の若者は、学校教育で「エコロジー教育」や「ボランティア教育」などを受けて育ってきた世代です。2023年に博報堂が実施した調査でも、SDGsについて「内容までよく知っている」と答えた人は、年代が若いほど多く、50代以上では平均6%程度に留まるのに対し、Z世代中心の20代では約14%、さらに下の16~19歳では約3割にも達していました。著者は、「彼らは、地球温暖化や廃プラスチックなどの環境問題だけでなく、『ジェンダー平等』や『格差解消』『世界の人々に健康を』などにも関心が高い世代です」と述べます。
「高級品を買うことも」では、牛窪氏らのインタビューでも、Z世代は「SDGsに配慮したモノを身に着けると、堂々と胸を張れる」や「これなら友人や家族にも薦められる」と言うことが紹介されます。また、SNS上で社会性の高いブランド情報を発信したり、多様な価値観の人々とつながったりすると「皆でハッピーになれる」や「(社会に)良いことをした気分になれる」とも言います。近年、マーケティングで重要なキーワードとされる「共創(Co-Creation)」も、これと似たニュアンスであると指摘し、牛窪氏は「多様な立場の人たちとSNSなどを通じて対話しながら、社会をより良い方向へと導くような概念を、共に創りあげていく……。令和の若者たちは『これからは、国も会社も守ってくれない』と考えるからこそ、みずから周りと緩くつながることで、いま新たな価値や消費社会を切り拓こうとしているのではないでしょうか」と述べるのでした。
第三章「マッチングアプリと恋愛コスパ主義」の「マッチングアプリの浸透」では、山田昌弘氏が「マッチングアプリ」が広く一般に利用されるようになって久しいが、マッチングアプリという言葉が「恋人や結婚相手探しのネットを利用したサービス」という意味で使われるようになったのは最近のことであるし、和製英語でもあることを指摘します。『朝日新聞』に最初に登場するのは、2018年2月27日(夕刊)で、わざわざ「交流アプリ」と註がついていました。ところが、新型コロナ禍による外出制限も追い風になったのか、従来の出会い系といわれるサービス業者だけでなく、結婚情報サービス事業者、自治体関係の事業者もネット上での結婚相手紹介に乗り出すようになりました。山氏は、「もはや、マッチングアプリといえば、パートナー探しツールの代名詞的存在になっている」と述べています。
「『出会い』の3つのパターン」では、恋人や結婚相手との出会いのパターンはさまざまであることが指摘されます。『新婚さんいらっしゃい!』というテレビ番組があります。1971年(昭和46年)1月31日から朝日放送テレビ(ABCテレビ)の制作により、ABCテレビとテレビ朝日系列ほかで、毎週日曜12時55分から13時25分に放送されている視聴者参加型トーク番組です。この番組が開始されてしばらくのあいだは、司会の桂三枝(当時)さんは、新婚カップルに「見合いですか、恋愛ですか」と聞いていましたが、いつしか「奥さん、きっかけは」と聞くようになったそうです。山志田氏は、「それこそ昔は見合いが多かったが、最近は高齢の方が『ネットのブログを見つけて、連絡をとって会いに行った』というケースも放映された」と述べます。
山田氏は、山田昌弘氏は、恋人や結婚相手との出会いのパターンを大きく、①「自然な出会い」、②「偶然の出会い」、③「積極的な出会い」の3つに分けています。①「自然な出会い」とは、幼なじみ、学校、職場、趣味のサークルなど、身近にいる人を好きになり、交際を始めるというもの。②「偶然の出会い」とは、旅先や街中、バーなどで、素性をよく知らない人とたまたま出会って好きになり、交際が始まるというもの。③「積極的な出会い」とは、自分から交際相手、結婚相手を積極的に見つけにいくもの。以上が、山田氏のいう「婚活」(もしくは恋活)です。見合いでも、友人の紹介でも、合コンでも、結婚相談所でも、そしてマッチングアプリであっても、最初からお互いに交際(恋人、結婚)相手候補として相手と会うので、「積極的出会い」に含まれるそうです。
日本では、恋愛と結婚を結びつける考え方がいまだに強く、「交際相手が結婚相手につながる」確率が高いといいます。もちろん、「恋愛は恋愛として楽しむ、結婚は別」と考える人も存在しますが、現在の日本では少数派です。山田氏は、「となると、恋愛の場面でも、結婚相手としてふさわしい人とだけ交際したい、結婚相手としてふさわしくない人と交際するのを避けたい、と多くの人が考える。そのために、コスト(時間・お金)をかけるのは避けたいという意識が広く共有されている。これが、日本社会で『自然な出会い』が好まれる理由である。「自然な出会い』では、出会うコストはゼロ、つまり、職場や学校、サークルなどですでにお互いを知っている。そして、『外れ=結婚相手としてふさわしくない』の確率は低い。なぜなら、交際前に、相手の年齢から経済力、性格まで情報が得られているからである。学校で出会っても、学業成績から将来の経済力の推測はつく。同じ職場なら給料のおおよその額までわかるし、幼なじみなら相手の家族状況まで既知となる」と述べます。
「偶然の出会い」には、リスクがあります。相手の素性がはっきりしないし、ウソをついている可能性もあるからです。特に日本では、旅先や乗り物の中、飲食店、街なかで声をかけるのは、「危ない人」とみなされがちです。山田氏は、「自分をだまそうとする人、いいかげんな人ではないかという疑いが消えない。出生動向基本調査でも、「街なかや旅先で」出会って結婚した人は、戦後一貫して10%未満しかいない」と指摘します。マッチングアプリが含まれる「積極的な出会い」は、リスクに関して「自然な出会い」と「偶然の出会い」との中間といえます。山田氏は、「会う前から、釣書(自己紹介書)やネット上のプロフィールで相手のある程度の情報を知ることはできる。親戚の紹介での釣書にはウソはないかもしれないが、いわゆる仲人口で実際よりも誇張されて伝えられるかもしれない。一方、出会い系では職業や年齢でもウソが書かれている可能性がある」と述べています。やはり出会い方において日本と欧米は違うといえるでしょう。日本は「自然な出会い」を好み、「偶然の出会い」を忌避し、できれば「積極的出会い」は避けたいと思っています。しかしそうもいっていられない時代が来たことが、マッチングアプリの流行に関係してくるわけです。
「なぜ『自然な出会い』は減少したのか」では、日本社会における「出会い」における戦後の変化を簡単にまとめると「自然な出会い」の普及と衰退ということができると指摘します。「自然な出会い」が衰退するとともに、未婚率の上昇や男女交際の減少が起きたというのです。日本では、高度経済成長期に「自然な出会い」による恋愛結婚が急速に普及しました。山田氏は、「多くの学校が共学化した。企業も一般職で大量の未婚女性を採用し、企業福祉の一環として社員旅行やサークル活動が奨励され、労働組合青年部も活発に活動していた。地域では農協や商工会の青年部、そして青年団の活動が活発で、自営業や農家の息子、娘が参加していた。未婚の男女が同じ場所で一緒に勉強や仕事、活動などを行なえば、そこで好きになる人が出てくる」と説明しています。
ところが1990年頃から、職場での「自然な出会い」は減少します。理由の1つには、正社員の長時間労働(若年正社員の労働時間の増大)と非正規雇用の増大があると指摘し、山田氏は「非正規社員は入れ替わりが激しく、正社員との交流が少ない。とくに派遣やアルバイトなどの非正規社員には、未婚女性が多く就く。コスト削減などの理由で社内サークルや社員旅行を廃止する企業が増え、地方では青年団など全員加入の若者組織が衰退に見舞われた。また、収入が不安定で女性から結婚相手とみなされづらい男性が増えた。そうした要因が重なり、相対的にシャイな若者が出会ってゆっくり親しくなる機会が徐々に減少していったのである」と説明します。
「コスパとリスクの相反」では、山田氏が「婚活」という言葉をつくったきっかけは、2007年、雑誌『AERA』で白河桃子氏に取材を受けたことだったことが明かされます。「結婚をめざしてさまざまな活動をしている未婚女子」が増大している現象を説明するために、結婚活動、略して「婚活」と名付けたのです。翌年には白河氏との共著『「婚活」時代』(ディスカヴァー携書)を出版し、「自然な出会い」が衰退するなか、積極的に活動しないと結婚相手に巡り会えない確率が増大したことを述べました。それでは、「積極的な出会い」のなかで、マッチングアプリにはどのような特徴があるのでしょうか。1つ目は、コスパとリスクの相反だ。すなわち、手軽に多くの人と出会うことができる一方で、問題がある人と出会う可能性も高いということだといいます。
マッチングアプリの特徴の2つ目は、社会的な魅力格差が顕著である点です。男性にとっては学歴や職業、収入、女性にとっては容姿や年齢による「相手からの選ばれやすさ」の格差を解消するものではなく、むしろ際立たせる出会い方でもあると指摘し、山田氏は「現実問題として、プロフィールの収入が低かったり、定職についていなかったりする男性や、年齢が相対的に高い女性は選ばれにくい」と述べます。3つ目は、「もっといい人がいるかもしれないシンドローム」と「がっかり効果」です。マッチングアプリでは多くの人と出会えるため、マッチした人と出会える確率を高める半面、1人になかなか決められないという事態が起こります。この状況を山田氏は、著書『結婚の社会学』(丸善出版)で「もっといい人がいるかもしれないシンドローム」と名付けました。
そして、山田氏は「マッチングアプリにはこれらの問題点があるにしろ、自然な出会いが衰退し、偶然の出会いが好まれないとすると、結婚や交際相手を求める人は「積極的な出会い」に頼らざるをえないだろう。またマッチングアプリには、いままで『自然な出会い』では関わることができなかった人(特殊な趣味や性的志向を含む)と出会えるという大きなメリットがある。若者というより中高年の利用が近年増えているのも、身近に独身中高年が自然に出会う機会が少なかったからである」と述べるのでした。
第五章「認められたいけど目立ちたくはない――複雑な承認欲求の謎」の「身近な人からの承認欲求が強い若者」では、金沢大学融合研究域融合科学系教授(イノベーション論・マーケティング論・モチベーション論)の金間大介氏が、「人より頭がいい。人より見た目がいい。人より努力している。こうした『人より優れている』ことを他者が認めることで承認欲求は満たされる。しかし、そうしてストレートに承認欲求を満たすことは、カッコ悪く、恥ずかしい行為と受け取られる。ここが承認欲求充足の第一の難関だ。他者と比較してまで自分の欲求を満たすなんて、みっともない恥ずかしい行為。よって、承認欲求を満たす行為は、時代とともに複雑化、巧妙化してきた」と述べます。
「五十歳以上――競争とルールの世代」では、最近はめっきり「競争」も「努力」も聞かなくなりましたが、理由は大きく分けて3つあるとして、1つ目は、努力と結果の関係性が薄れてきたからだといいます。金間氏は、「これはビジネスの現場でよく言われることだが、明らかに『正解』が見えなくなってきている。『顧客ニーズの潜在化』がこの不透明感を高めている」と述べます。2つ目は、いまの時代、努力の推奨はハラスメントになりうるから。3つ目は、努力よりも、アイデアや知識・スキルの「質の高さ」が重要になってきたから。
「先輩世代の人はご注意を」では、Z世代の特徴の1つに、目立つことに恐怖に近い感覚があることが挙げられます。大学生から20代の若者を対象に、こうした特徴を持つ若者を「いい子症候群」と定義してみると、「いい子」にとっては、「人前で褒めるくらいなら、何も言わないでほしい」という心理があるそうです。人前で褒められることを圧だと感じるというのですが、金間氏によればその理由は主に次の3つです。1つ目は、自分への自信のなさとのギャップ。2つ目は、褒められて、それを聞いた周りの人の中での自分像が変化したり、自分への印象が強くなったりすることを恐れるため。特に、「意識高い系」のように思われることへの抵抗は大きいといいます。3つ目は、横並び気質に起因します。横並び意識が強く、目立つことに恐怖を覚える若者にとっては、自分だけが何らかの利益を得て、差が付くことを嫌がる傾向にあるといいます。
「社内表彰に冷めてしまう若手社員」では、上司が「こうすれば、部下たちのやる気につながる」と思っていることが、実は部下にとっては興味がなく、時には引いてしまう要因にもなることが明らかになってきたことが指摘されます。その中でも、特に認識の世代差が大きく出たのが社長賞などの社内表彰制度であるとして、金間氏は「上司の側は、表彰があることで競争意識が芽生えて、活性化すると信じている人が多い。一方で、若手側は、そういった社内表彰ではモチベーションは上がらず、むしろ『会社に誘導されているような気がして冷める』という考えも多く聞かれた。この中でとくに興味深かったのは、賞をもらった本人でさえ、長期的にはモチベーションはあまり上がらず、それどころか下がる可能性も見受けられたことだ」と述べています。
「若手は『現役選手』しか尊敬しない」では、いまの若者は目の前にいる先輩の過去の実績ではなく、先輩が今日何をして、明日何をするのかに興味があることが指摘されます。金間氏は、「つまり、現役選手としてのあなただ。現役選手なので、基本的に失敗もする。僕からの提案は、そんなあなた自身の失敗を、ぜひ若い世代に見せてあげてほしいということだ。負けても、くじけても、それでもなお次へ生かそうとする姿勢。若者は、その姿をストレートにカッコいいと受け止める傾向にある。僕はここに光を感じている」と述べます。そして、「自分はもう一度、これに挑戦したい。今度は成功させたい。だから、手伝ってもらえないか」というのが、いまの若者の心を動かすキラーフレーズだといいます。ポイントは、若者に「向き合う」のではなく、「同じ方向を向く」こと。金間氏は、「大切なのは、先輩世代のあなた自身の姿勢となる」と述べます。
第六章「『無敵の人』を生まないためにできること」の「ホアキン・ジョーカー=『無敵の人』」では、甲南大学文学部教授(労働社会学)の阿部真大氏が、一条真也の映画館「ジョーカー」で紹介した2019年のホアキン・フェニックス主演映画を取り上げて、「ホアキン・ジョーカー=『無敵の人』は、行動原理が理解可能であるがゆえに、私たちの手で何とかなりそうだと思えるのである。『無敵の人』が、社会からさまざまなものを奪われること=『社会的排除』によって生まれるのだとすれば、それに対抗するには、その人を社会の中に戻していくこと=『社会的包摂』のプロセスが不可欠である。それは、社会の問題として解決策を講じていくという意味で『社会的処方箋』と呼ぶことができるだろう」と述べています。
「『奪われている』感覚は相対的なもの」では、物質的な豊かさと個人が主観的に幸福と感じているか否かは次元の異なる話であることが指摘されます。社会学では「相対的剝奪」という概念があります。個々人の感じる幸福感は、その人が自らの考え方や行動を決める際の指針として準拠している集団(「準拠集団」と呼ぶ)との関係のなかで測られるものだとして、阿部氏は「だから、傍から見てどれほど幸せそうな人でも、その人が自身の準拠集団に照らし合わせて『享受すべき幸せを奪われている』と感じていることもある(その場合、幸福感は低いものとなるだろう)。個人の感じる『剝奪』の感覚は『相対的』なものなのだ」と述べます。
「本当の『社会的包摂』を成功させるために」では、かつて見田宗介が書いた「まなざしの地獄」という論文が取り上げられます。1968年に連続殺人事件を起こした永山則夫に関する1973年の論文なのですが、そこで見田は「永山のような『見すてられた人』を生み出してしまうことこそ、私たちの存在の『原罪性」である』と喝破しました。阿部氏は、「さまざまな凶悪事件のかたちをとって現れる見すてられた人=『無敵の人』の怨嗟の声を受け止め、対応していくこと。それこそが、私たちの社会がいま果たすべき責任なのではないだろうか」と述べます。
第七章「政府講評『自殺者減少』は真実か」の「自殺者は減っているのか」では、和光大学教授(教育学)で公認心理士、臨床心理士の末木新氏が、「このところ子ども・若者の自殺対策に関する話が世間を賑わしている。こども家庭庁の発足もあり、また、2006年の自殺対策基本法の公布・施行以来、中高年の自殺は着実に減ってきている『とされている』からである」と書きだしています。1997年の消費税増税、北海道拓殖銀行や山一証券の破綻に象徴される経済的混乱による自殺者の増加以降、しばらく自殺者3万人時代が続いていましたが、2006年の自殺対策基本法の公布・施行以来、自殺対策は国家的な事業となり、自殺者数は着実に減少しているように見えます。末木氏は、「とくに、元来、自殺者のボリュームゾーンであった中高年の自殺率は、98年の水準に比して大幅に減少し、自殺率についての世代間の差異はほぼ消滅したといっていいような状態になっている。一方、子どもの自殺は元来稀なものではあるものの、近年着実に増加しており、20代の若者の自殺も98年の水準に比して減少したとは言い難いものとなっている」と述べます。
「そもそも『自殺』とは何か」では、末木氏は「一般にわれわれは、自殺とは、本人が『死のう』とか『死にたい』と考えたすえに起こした意図的な行動の結果だと考えているだろう。しかし、当人が死んだあとになってしまえば、そんな目的・意図・願望があったのかを直接聞くことはできない。もちろん、これらを明確に記した遺書のようなものがあればはっきりするのかもしれないが、遺書が見つかるケースは限定的であり、また、必ずしもそうした内容のものとは限らない。つまり、そんな目的・意図・願望があったのか否かは遺された人間が推測するしかない場合も多く、その点、ある死亡が生じた際にそれが自殺か否かの数字の計上はそれほど簡単なものではない」と述べます。また、「自殺は『明確』な存在になる」では、遺書のような明確な証拠がないケースが自殺と計上されなくなったために、遺書の存在率は上昇したと推測しています。なお、残念ながら、2007年には検視・死体調査により遺体の死因を自殺と判断したケースについて作成される自殺統計原票が改正されたこともあり、その後の遺書の存在率については警察の自殺統計において公表されていないので不明だそうです。
「〈解決策〉自殺死亡以外のモニタリングを」では、と、これだけ原因不明の死亡が増えており、地域によってその発生率が10倍以上も異なっているという現状を考慮すれば、自殺対策について考えるに際しても、自殺死亡だけをモニタリングするのではなく、他の指標も参考にしながら、政策を考えていく必要があるだろうと、末木氏は提言します。少なくとも、自殺と近縁の死の増減については、注視していく必要があるといいます。さらに、末木氏は「統計の数字の上で、地域の自殺は減っているものの、それ以上に(とくに中高年の)原因不明の死が増えているとすれば、自身の政治/政策が上手くいっていると胸を張れる首長はいないであろう(原因不明の死が、われわれの考えるところの「自殺」であろうとなかろうと)」と述べるのでした。
第八章「差別と偏見に苦しむヤングケアラー」の「独り歩きする『ヤングケアラー』の定義」では、大阪公立大学准教授(家族介護研究)の濱島淑恵氏が、ヤングケアラーの定義は誤解されていることが多いと指摘します。長年、ヤングケアラーに関する活動に取り組んできた日本ケアラー連盟では、「家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている、18歳未満の子ども」という定義を示しているそうです。また、厚生労働省が2022年3月に示した「ヤングケアラー支援体制強化事業実施要綱」では、「一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている児童」とし、さらに若者世代への支援も重要としています。しかし、日本において、正式な定義が決まっているわけではないようです。
第九章「若手社員が辞めない職場とは」の「若手を活かす職場、2つの要素」では、リクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗氏が、現代において若手が意欲をもって仕事に全力投球できるのはどんな職場なのか、そのホントを探ります。リクルートワークス研究所が、1~3年目の社員2985名に2つの時期で調査したデータを用いて検証すると、若手が活躍する職場には「2つの要素」が存在していました。1つは、職場の「心理的安全性」です。その職場で自分が何かを言ったり始めたりしても誰かの言下に却下されたり、人格を否定されることがないという認識で、「チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる」「現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる」という職場です。
「心理的安全性」は広く共有された概念であり、その重要性に異議のある方は少ないでしょう。もう1つ、心理的安全性と同様に新入社員のワーク・エンゲージメントにプラスの影響を与えるものとして、職場の「キャリア安全性」とも言える要素が存在していました。キャリア安全性は、「所属する会社の仕事をこのまま続けていれば成長できる」「自分は別の会社や部署でも通用する人材に職場の仕事を通じてなることができる」といった認識の高さであり、若手が自分のことを俯瞰して、“自身の今後のキャリアがいまの職場でどの程度安全な状態でいられると認識しているか”を捉える尺度だといいます。
第十章「『若者の本離れ』というウソ」の「70年代以降の高校生は難しい本を読んでいない」では、ライターの飯田一史氏が、若者の読書について考察します。たとえば学校読書調査で毎年発表されている「5月の1か月間に読んだ本」(2021年度からは「今年度に入ってから読んだ本」)の高校生部門の上位にある本を見ると、近年の高校生には小坂流伽『余命10年』(文芸社)や宇山佳佑『桜のような僕の恋人』(集英社文庫)をはじめ、男女片方が死に至る病に冒されている悲恋を描いた、いわゆる『余命もの』の人気が高いそうです。飯田氏は、「こういうものは、以前は『難病もの』と呼ばれ、読書家からは『泣ける話をサプリメント的に消費している』などとかつても批判され、バカにされていた」と述べています。
では、たとえば1960年代にはどうだったのでしょうか。1964年には大島みち子・河野實著『愛と死を見つめて』(大和書房)が高校生男子3年と女子1~3年の1位になっています。これは難病の軟骨肉腫を患って亡くなった女性ミコと、死に別れた恋人の男性マコとの文通を書籍化したものです。ノンフィクションですが、構造としても読後感としても余命ものと同型です。「大人はなぜ若者の読書の実態を見誤るのか」では、「子ども・若者の本離れ」が意味することが「書籍離れ」なのであれば、それは事実に即していないとして、飯田氏は「『本離れ』=『書籍離れ』という解釈の前提になっているのは極めて狭量な『本』『読書』の定義であり、恣意的な選別である。その思想は、本当はもっと多様であるはずの『本』、広く許容されるべき『読書』のありようから、子ども・若者をいまも遠ざけ続けている」と述べるのでした。
第十一章「韓国人男性に惹かれる日本人女性」の「空前の韓流ブームの余波」では、ライターで編集者の安宿緑が、日韓カップルにおいては圧倒的に「韓国人男性×日本人女性」の組み合わせが多いことがうかがえると指摘します。「韓国人男性の魅力とは?」では、日本人女性たちの中にある韓国人男性像は、フィジカルとメンタルにおける男性的魅力に集約されるといいます。「背が高く筋肉質で、女性を甘えさせてくれる声かけができる点」「高身長で色白で美意識が高い。思ったことを率直に言ってくれるし、リードしてくれる」「紳士的で、尽くしてくれる」などです。韓国人男性の平均身長は172.5センチで、日本人男性の170.8センチより高いそうです。『韓国経済』によれば、1996年生まれの男性の平均身長は日本人が170.8センチであるのに対し、韓国人は174.9センチだとか。特に若い世代で日韓の対格差が出ています。
「靴紐まで結んでくれる男性も」では、日本人女性が抱く韓国人男性のイメージについて、韓国人男性のKさんは「現実とかけ離れている」と一蹴しています。平均的韓国人男性の容姿を模した「ハンナムコン」という画像が韓国で話題になったことがあります。角ばった顔に細く小さい目、太い縁のメガネをかけた男性のイラストです。元はラディカルフェミニストたちが自国の男性を嘲笑する意図で広めたものですが、ネットユーザーのあいだで共感を呼び、「韓国人男あるある」として定着しました。Kさんは、「韓国人男性に憧れを抱く彼女たちも、実際に韓国に来てみればわかると思いますよ。街中、ハンナムコンだらけだってことをね」と語ったそうです。
第十三章「カラダを売らざるをえないZ世代」の「強盗に走る男、買春に陥る女」では、ノンフィクションライターの中村淳彦氏が、女性や若者を直撃する日本の貧困問題、世代格差は行きつくところまで到達し、男の子は闇バイトで強盗、女の子は売春という異常な事態を生んでしまっていると指摘します。中村氏は、「戦後の混乱期に頻発した強盗は重罪であり、女性の街娼行為は売春防止法で厳しく禁止される。にもかかわらず、一線を越えてしまう若者たちがあとを絶たない末期的な状態となっている」と述べています。
「Z世代による売春が常態化」では、中年買春男性たちが若い女性たちの肉体を買い叩き、2万円に届かないお金でカラダを売るのが恵梨香さんのケースを紹介しています。声をかけてきた中年男性とホテルに行ってセックスして、それを3回ほど繰り返してからホストクラブに行く。そして深夜に帰宅し、翌日はスーパーマーケットに出勤する。中村氏は、「歌舞伎町ではZ世代による売春が常態化し、いまはモテない未婚の中年男性をターゲットにした恋愛詐欺が流行している。生涯未婚率の上昇が止まらない社会状況である。寂しい中年男性に女性たちが近づき、色仕掛けをして男性の財産を奪うことが横行、その方法が情報商材としてマニュアル化もされている」と述べるのでした。
第十四章「『推し』が出るならテレビを観る」の「作品を観るきっかけは切り抜き動画」では、N.D.Promotion取締役で、Z総研トレンド分析担当の道満綾香氏が「倍速視聴」について考察します。損保ジャパンの2022年9月の調査によれば、倍速で動画を視聴するZ世代は70%に及ぶそうです。上の世代と比べて最も倍速視聴をする世代なのです。道満氏は、「私がヒアリングした限りでは、『倍速視聴』や『ネタバレ視聴』、さらに『ながら視聴』(別の作業をしながら動画を観ること)も含めれば、Z世代のほとんど全員が、いずれかの視聴方法を経験したことがありました」と述べています。
「倍速視聴」をする理由としては、「時間がもったいないから」「早く結末が知りたいから」などが挙げられ、いわゆる「タイパ」(タイムパフォーマンス)を重視する傾向が見られるそうです。「ネタバレ視聴」については、「先に結末を知って良い作品か判断したうえで、観るかどうかを決めたい」ようです。「『王道の展開』のリバイバル」では、「いまの若者は社会問題への関心が低いのではないか」という見方は間違っているといいます。Z総研とマイナビ転職の共同プロジェクト「はたらきかたラボ」が2022年8月に実施した調査によれば、Z世代の8割以上がSDGsに「興味が非常にある」もしくは「興味がある」と回答し、SDGsの17の目標のなかで最も興味関心が高い分野は「ジェンダー」だったといいます。
「多様な価値観を受け入れるヒントに」では、Z世代のコンテンツ消費は「受動的」「タイパ重視」とよく語られることが紹介されます。たしかにそうした側面がある部分は否めませんが、Z世代はあらゆる情報があふれる中で情報に受動的に接していることを自覚した上で、タイパを意識しながら、自らに必要なコンテンツを主体的に取捨選択しているといいます。道満氏は、「他方で、自分が本当に好きと思える推しには時間やお金を惜しみません。同時に、SNSを駆使しながらファン同士でつながり、コンテンツのさまざまな視聴方法を実践しています。社会問題への関心が高く、多様な価値観を受け入れる柔軟性もあります。『それぞれの個性を認め合い、尊重する』。価値観の違いから世代間で対立することもあるなかで、Z世代のコンテンツ消費には、他者を尊重するヒントが詰まっているのです」と述べるのでした。
第十五章「『古見さんは、コミュ症です。』に見る、イベント化した日常世界」の「人生は芸術を模倣する」では、京都市立芸術大学デザイン科選任講師の谷川嘉浩氏が、「日常系」について考察します。日常系は、政治や社会問題やニュース(政局、災害、戦争、パンデミック、貧困など)が登場することなく、ただ身の回りの出来事が、その範囲を超え出ることのないまま描かれる作品を形容する言葉です。そこでは、穏やかな日々が淡々と描かれることもあれば、他人から見れば些細だが本人にしてみれば重大な変化が丁寧に描かれることもあるといいます。谷川氏は、「詩人のオスカー・ワイルドは、『芸術が人生を模倣するよりもはるかに、人生が芸術を模倣している』と言った。よくある考え方では、芸術は現実の写しや反映であって、いわば現実を『原作』ないし『元ネタ』としながら芸術は作られているとされる。しかし、ワイルドによると、この考えは逆転されるべきである。つまり、芸術が日常を反映するというより、日常のほうが芸術をなぞっている」と述べています。
「SNSでの一瞬の承認に依存してしまう」では、コンカフェ(コンセプトカフェ)店員や地下アイドル、V-TuberやYouTuberなどへの「推し活」を取り上げます。コラボカフェに行き、コラボグッズを買い、スパチャ(課金コメント)を投げ、イベントに行き、雑誌掲載をチェックし、推しと同じものを食べるというイベントは、それぞれ一瞬で終わってしまいます。だから、その体験をSNSでシェアし、そのリアリティを下支えしようとするといいます。それによって体験の価値を確信できるからです。谷川氏は、「私たちの暮らしが、可視的な場所に『シェア』されることを中心に編成され始める状況を念頭に置いて、心理学者のシェリー・タークルは、“I share,therefore I am.”と言ったことがある。私はシェアする、ゆえに私は存在する。まるでSNS依存のデカルトだが、このフレーズには、スマホ時代の日常世界のあり方がよく表れている。イベントがないと日常をリアルに感じられないし、その日々の価値は他人からリアクションをもらえないと確信できない。その確信を持続的とは言えない」と述べるのでした。
第十六章「地域間格差と若者の希望」の「東京に憧れない若者たち」では、同志社大学社会学部准教授(社会学)の轡田竜蔵氏が、編著『場所から問う若者文化――ポストアーバン化時代の若者論』(晃洋書房、2021年)で、近年の若者の文化やその価値観について、東京と地方の差が見出しにくくなっているという社会調査の結果に注目し、この現象について考察したことを紹介します。同書では、その背景要因として、以下の3点が重要であると指摘。第1に、「街」に集まることよりも、ウェブ上での日常的なコミュニケーションが相対的に重要になったこと。第2に、東京に行かなくても、大型ショッピングモールや全国チェーン店の立地が進み、大衆消費社会的な意味でのフラット化が進んだこと。そして、第3に、地域移動経験のある若者、モビリティ(可動性)の高い若者が増え、居住地域の違いがあまり問題にならなくなってきたことでした。これが、轡田氏が「ポストアーバン化」と呼ぶ現象だといいます。本書『「今どきの若者」のリアル』には、わたしの知らなかったことが多く書かれており、いろいろと学びを得ました。Z世代がちょっと好きになりましたね。