- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2334 宗教・精神世界 『むすんでひらいて』 玄侑宗久著、聞き手/大竹稽(集英社)
2024.06.10
『むすんでひらいて』玄侑宗久著、聞き手/大竹稽(集英社)をご紹介します。「今、求められる仏教の智慧」というサブタイトルがついています。芥川賞作家で臨済宗妙心寺派福聚寺住職の玄侑氏の発言を、教育者で哲学者の大竹氏が聞き取りをした一冊です。現代的な問題も広くカバーしており、非常に学びの多い本でした。
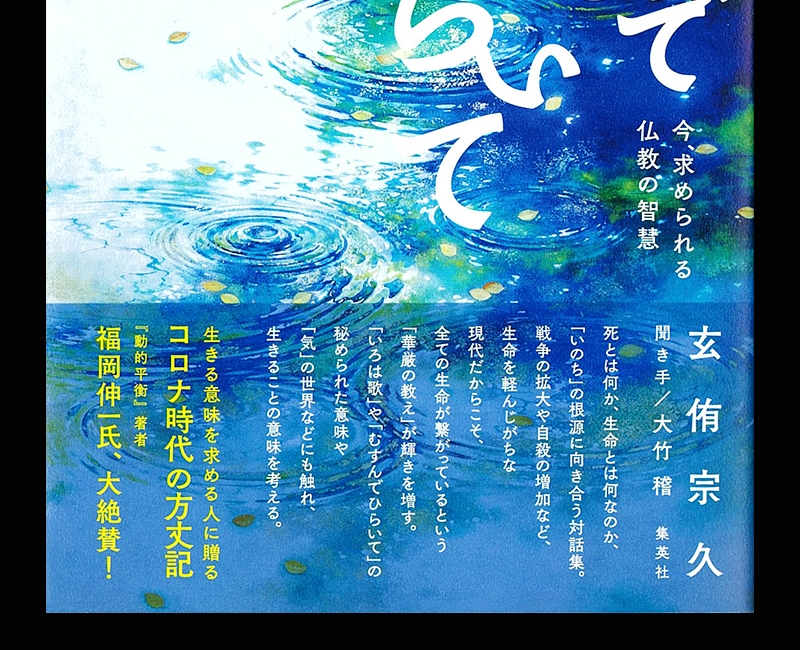 本書の帯
本書の帯
帯には、「死とは何か、生命とは何なのか、『いのち』の根源に向き合う対話集。戦争の拡大や自殺の増加など、生命を軽んじがちな現代だからこそ、全ての生命が繋がっているという『華厳の教え』が輝きを増す。『いろは歌』や『むすんでひらいて』の秘められた意味や『気』の世界などにも触れ、生きることの意味を考える」「生きる意味を求める人に贈る コロナ時代の方丈記」「『動的平衡』著者 福岡伸一氏、大絶賛!」と書かれています。
 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンの内容紹介には、【よりよく生きるために、死と向き合い、人と人のつながりを考える】として、以下のように書かれています。
「ウクライナや中東の戦争の死傷者は増え続け、突然の災害の被害者も尽きない。一方、日本では年間3万人を超える自殺者が年々増えている。『死』は数値化・映像化したものを見るばかりで、『実感としての死』は遠ざかっているのではないか……。そんな今だからこそ、改めて『己や身近な人の死』や『いのちの大切さ』、『人と人とのつながり』について真面目に語り合いたくなる。
『死んだら魂はどこにいくのか?』、『愛する人の死を、どのようにしたら乗り越えられるのか?』、妹のようだった少女の自殺を忘れられない哲学者が、玄侑和尚と生と死に関する対話を重ねることで、いのちの不思議さ、人と人との時空を超えた縁に導かれていく。
寄り道をするように対話は進み、平安時代の『いろは歌』に秘められた日本人の死生観や、突然に自殺をしてしまう人の心境、人生という物語を紡ぐ意味、東洋思想の根本に流れる『気』のはたらきなど、さまざまな話題に展開する。さらに多くの宗派に分かれた日本の仏教の歴史や、ブッダの説話が語る『宿縁』や『縁起』の考え方、輪廻転生についてなどの仏教の教えが、玄侑先生ならではの現代的でわかりやすい言葉で語られる。
圧巻は、過去・現在・未来のすべての生命や事象がつながりながら変化し続けていくという『華厳の思想』で、その雄大で深遠な世界観は、これからの時代に『いのちの大切さや人と人とのつながり』を見つめなおす鍵となるだろう。表題の『むすんでひらいて』は戦後にはやった唱歌だが、その意味するところも奥深い」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに……」
第一章
死が日常化した今、あらためて死について考える
第二章
昔の日本人は「死」をどのように捉えてきたのか
第三章
「いのち」の存在は、不滅なのか
第四章
人間の生死の営みには「物語」が必要である
第五章
魂と魂を繋ぐ「縁起」の世界
第六章
人間の本性は善なのか? 悪なのか?
第七章
東洋の「気」と西洋哲学の関係を考える
第八章
生命力を産みだす「渾沌」とは何か
第九章
全ては変化しつづける「唯識」のなかで生命を考える
最終章
むすんでひらいて 無限の可能性を信じて生きる
「はじめに……」では、「からだ」は語りやすくとも「いのち」は語りにくいように、「死」についての対話も当然「生」についての探求、ということになるとして、著者は「私は当初、覇権思想の強い今こそ『華厳』の思想をご紹介したいと考えていたが、話はどんどん深まりつつ広がり、『空』や『般若』、『戒律』や『唯識』など、仏教の嶺を心細く歩くような事態になっていった。禅と西洋哲学では話が収まらず、『気』や『風水』、『渾沌』、そしてついには『菩薩道』にまで話は及んだ」と述べています。また、著者は「若者に限らず現代社会に生きる人々は、問題には必ず答えがあると思い込んではいないか、どんな問題もすぐにすっきりわかるものと思っていないか」と疑問を抱きます。PCやスマホでの検索が当たり前になったせいもあるかもしれません。シミュレーション(合理的推論)が当然とされるせいもあるでしょう。「合理的推論」が本書のキーワードの1つですが、死にゆく若者たちが夢をもてず、「これ以上よくはならない」と合理的に推論したことは間違いないだろうと述べるのでした。
第一章「死が日常化した今、あらためて死について考える」の「コロナ禍とウクライナ戦争……、『死』が日常化した現在、あらためて『死』について考える」では、聞き手の大竹氏が「世界的に広がり今では日常化したコロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻、そして2023年秋のパレスチナ・イスラエル戦争……。この4年間に『死』は日常化し、ライブ化されました。常に「死」が、私たちの身近に存在するような時代になったのです」「パンデミックにせよ、戦争にせよ、世界が密に繋がっているこの時代に、日々、多くの誰かの『死』が日常化されて共有されることは、理屈を超えた衝撃でした。ある意味で、『一寸先は闇』という世の中に変わった現代社会において、あらためて「死」そのものを考察することは、『より良く生きる』ために大切なことではないでしょうか?」と問いかけます。
これに対して、著者は、「コロナ以前、最も直近に日本人に『死』をつきつけた災害、……それは私もごく身近に体験した東日本大震災だと思いますが……、あのときの状況と今回のパンデミックとは、かなり違うような気がします。あの震災では、関係者以外は津波の映像を視てもなかなか大量死を実感できず、なかには映像に釣り合う死の悲しみが実感できないため、倫理的な苦しみで身心不調を起こす人々もいました。日本の報道では、遺体や泣き顔を映さないという自主規制がはたらいていましたから、その影響も大きいのでしょうね。ところが今回は、誰もが『いつ自分に降りかかってもおかしくない』ものとして、死や感染そのものまで怖れていました。いわば死が、私のすぐ傍にあるものとして意識されていたのだと思います」と述べています。
第二章「昔の日本人は『死』をどのように捉えてきたのか」の「怨霊信仰となった″無念の死“」では、怨霊発生の仕組みに言及した後、著者は「要は、その人の人柄や人生に見合った穏やかな死であれば、なにも問題はない。しかしあんなに素晴らしい人だったのに、どうしてこれほど不遇な晩年を送り、非業の死を遂げたのか、となりますと、納得できない人々の意識や無意識が集合して『怨霊』を生みだします。本人の怨みとは限らない、ということですね」と述べます。怨霊とか地獄や極楽と聞けば、非合理なものと思う方も多いですが、むしろこれは人間の合理性が作りだしたわけです。著者は、「死は、その人の人生や行動に釣り合うものであってほしい。しかしあまりにも釣り合わないと思えるときは、死後世界も含めて帳尻を合わせるしかない、ということになるのでしょうね」と述べています。
「死者の『無念』や『心残り』と、どう折り合っていくのか?」では、檀家の水引職人のお通夜の話題に触れた著者は、故人について「年齢も85歳でしたし、大勢の方が望む『ポックリ』というのは、殆んどの場合、今回の原因になった心筋梗塞です。長患いも介護も不要だったという意味では望ましい死でもあるんです。そこで私はお通夜のとき、柩の蓋に筆文字でこんな句を書きました。『あれよとて 散るぞ目出度き 桜かな』。家族が亡くなってすぐに『目出度い』と思うのはまず無理ですが、時が経ってからそんなイメージを持ち直してほしいという、私の切なる願いですね。じつを申しますと、翌日の葬儀での一喝の前には『高砂や』を唱えました。亡くなったご本人が何度も結婚式に招かれ、祝謡として謡った旅立ちの歌です。お通夜や葬儀には、そういうふうに故人や家族の思いを慰撫し、心残りを流し去る効果もあると、私は信じています。特に『無念』は放置できませんね。平安時代のように、疫病も含めたあらゆる天災がそのせいとは考えないでしょうが、『無念』は今でも思いがけない不調を人の心に及ぼすものだと思います」と述べています。
「死後のビジョンが生者に救いをもたらす」では、多くの人にとって、「死」には「無念」や「心残り」があることについて、それは死や死後へのビジョンも関係しているという著者は、「たとえば阿弥陀さまに抱き取られるとか、神さまの許に行くんだと思えれば、安心してこちらでの生を閉じられるんじゃないでしょうか。宗教が与えてくれる死後世界のビジョンは、臨終の安心に大きく寄与していると思いますね」と述べます。また、「宗教ぬきでの道行きは、孤独な旅です。禅は宗教のようでいながら死後のビジョンは与えてくれず、『わからない』まま進むしかないんですが、その意味では孤独を愉しめる境涯が求められているのかもしれませんね」とも述べます。さらには、死は老若にかかわらず突然訪れるという認識が、今より遥かに高かったことが理解できるとして、著者は「今の日本は、乳幼児の死亡率が世界一低いのですが、たとえば徳川家第8代将軍吉宗の頃(1716~45年)など、人口統計に7歳未満の子どもは数えていないんですね。子どもは神の子だから人の数に入れない、などとも言いますが、要はいつ死ぬかわからない存在だったわけです」と述べるのでした。
「『いろは歌』に秘められた日本人の死生観」では、現代医学は、たとえば白血球の寿命が24時間程度しかないことを知っているという事実が紹介されます。昨日と同じ白血球の細胞が明日も生きていることはないのです。他の細胞も、一説では「一呼吸の間」に約1000個生まれ、同じく1000個の細胞が死んでいくとも言われていますが、次々に生まれては滅しながらそれぞれの寿命を終え、全体としては奇跡的な恒常性(ホメポパシー)を保っています。著者は、「まさに『方丈記』の冒頭、『行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず』。あるいは福岡伸一先生の『動的平衡』ですね。後付けと思われるかもしれませんが、仏教は、瞬間瞬間の生滅変化の連続こそ『生』なのだと、はっきり認識していたと思います。無常に生滅変化するのが『生』であり、『生滅』による変化そのものが滅してしまうのが『死』なのです」と述べています。明快にして卓見であると思います。
「いろは歌」の「浅き夢見じ酔ひもせず」について、人生全体が「夢」として思い返されるということは、死が「目覚め」かもしれないという認識であると指摘されます。この考え方の原型は『荘子』の「胡蝶の夢」にあります。荘子は「老いは楽しみ」だし「死は休息」だとも述べていますが、生まれることも死ぬことも受容すべき一連なりの変化と捉えています。終わりのない変化をインドの人々は「輪廻」と捉え、お釈迦さまも抜け出すべき苦しみと考えたようですが、荘子は違います。どう転んでも、それは新たな目覚めであるし、楽しむべき展開なのです。著者は、「この時代に即して考えれば、生きることを勝負に準え、死を『負け』と考える人々に大いなる慰めを与えた歌だったと思います。やがて時代は鎌倉時代に移り、勝負が避けられない世の中になっていきますが、平安後期にはまだ道教的な考え方が強かった。それが幸いしてこのような『無為』や『渾沌』へ向かう歌ができたのだと思います。『無為』も『渾沌』も命の源ですから、我々は死んで命の源に還る、と考えています」と述べるのでした。
第三章「『いのち』の存在は、不滅なのか」の「生命の根本である『存在』とは、どういうものなのか?」では、物理学者ニールス・ボーアが粒子と波の二重性から「相補性」という概念を定立し、それを教育や心理学やあらゆる分野で用いてほしいと勧めていることが紹介されます。ボーアは東洋哲学、とりわけブッダや老子、あるいは『易経』に深く傾倒していました。著者は、「粒子と波というのは、そういえば仏教の『色(ルーパ)と空(シューニャ)』にそっくりなんですね。『色即是空』という言葉をご存じの方も多いと思います。インドでは『存在の存在』めいた『自我の本質』として『アートマン(我)』を想定しました。仏教でも一部の学派はこれを不変の本質と考えたのですが、ブッダ自身は『単独で不変の自性』を認めず、『無我説』を唱えました。ここでは単純に『関係性のなかで変化しつづける状態』が『空』、ヒトの感覚器と脳で捉えられたその変化の一部が『色』なのだと思っておいてください」と述べます。また、もしも「存在」の在り方のこうした相補性を前提にすれば、「死」は粒子から波への移り際と考えることもできるかもしれないといいます。それは「色から空」でもあるし、「有為から無為」とも言えます。著者は、「愛する人の死は、どう考えようと悲嘆に暮れるものだとは思いますが、そういう考え方があると知っているだけで、その後の思いの深まり方が違うのではないでしょうか」と述べるのでした。
「ブッダが捉えた死後の世界、『中道』という考え方」では、「中道」がブッダの教えのなかでも非常に重要であると指摘されます。わたしたちの頭はどうしても善悪、美醜など、二元論的に働きます。一見その両者はどちらかが正しいように思えますが、本当は双方の対立を超えた地点にしか真理はない、という見方です。だから双方から距離をとる。換言すれば、双方の対立を包み込んでしまうような地点に立つ。それが「中道」です。儒教の「中庸」も少々似てはいますが、そこには「包み込む」という側面はないといいます。著者は、「死後に何もないという『断見』も、死んでも永遠不滅の何かがある、という『常見』も、ブッダは両極端として否定しました。どちらでもない、ということはどういうことなのか?それはじっくり瞑想を深めて体験するしかないのかもしれないですね」と述べています。
「『輪廻転生』生まれ変わりを信ずることの功罪」では、「輪廻転生」はブッダが唱えたわけではなく、むしろバラモン教やヒンドゥー教にも共通するインド古来の考え方であることが指摘されます。次の生がある、というのは救いでもあるかもしれませんが、苦しみでもあります。特に古代インドの場合は、次はどんな動物に生まれ変わるかわからないわけですから、そのことへの怯えを利用して道徳的な教化に用いた、という側面がありました。立派に暮らしていれば来世でもっと恵まれるということですチベット仏教では、ダライ・ラマが前のダライ・ラマの「生まれ変わり」だとしていますが、著者は「こうしたことが本当に起こるのかどうかは、『わからない』としか申し上げようがありません。ここでは『わからない』というのが中道だとも思います」と述べています。
輪廻転生の考え方じたいは仏教も否定はしませんでした。一部の人々が断ち切れるだけで、大部分は輪廻するということです。しかし仏教とセットで中国に伝わったこの考え方は、中国人を大いに困らせました。つまり、先祖が犬や豚だったなどという話ですから、先祖崇拝の国である中国で認められるはずがなかったのです。『梵網経』など大乗戒を扱った経典では、肉食を禁じるための論拠として輪廻を用いたりしましたが、基本的に中国から朝鮮半島を経て日本に伝わってきた仏教は、輪廻と切り離されていました。著者は、「日本では、あまり輪廻転生のことを言わないのはそういうわけなんです。仏教も受け容れられたその国のお国柄でだいぶ変化しているんですね」と述べます。
「瞑想によってブッダが捉えた『無我』」では、「色」とか「空」という見方もべつにブッダの発明ではなくて、当時瞑想をしていた修行者たちの共通認識であったことが指摘されます。「色」は普通に誰でも知覚する対象ですが、それが言わば「変化しつづける全体性」のなかに溶け込むような、そういう体験を瞑想によって得るのだといいます。ちなみにブッダは、「戒・定・慧」という3つの徳目をとても重視しましたが、戒によって制限され、その制限のなかで横溢していくエネルギーをすべて禅定(深い瞑想)に振り向けるよう勧めました。著者は、「そこに般若の智慧が開ける、世界の本当の姿が現れる、というのがブッダのセオリーですね。ブッダは、瞑想が深まれば死も体験できると説いていますから、きっと『有為の奥山』を越えることも瞑想によって可能なんでしょうね」と述べるのでした。
第四章「人間の生死の営みには『物語』が必要である」の「仏教を理解するために生まれた『物語』が経典になった」では、「断見」は、死後の物語が生まれにくい考え方ですが、逆に「常見」のほうも、永遠不滅では物語としての魅力に欠けることが指摘されます。もしかすると、そのどちらでもない「中道」とは、最も豊かに物語を育む土壌なのではないかとして、著者は「大乗仏教の中心のテーマは人々の救済ですから、当然さまざまな物語が多くの経典として生まれてきます。しかも登場人物の多くは菩薩や如来たちですから、天衣無縫というか、ほとんど超能力としか思えないような場面もたくさんあります。経典があまりに多く現れ、整合性も必ずしもとれていない。そこでは何が正しいかという見方ではなく、自分に合った物語を探すという観点が重要になってきます」と述べています。
たとえば。『法華経』では地面から金色の菩薩が湧き出ますし、。『華厳経』ではウルトラマンかと思うほどのスペシウム光線が体験できます。著者は、「もう円谷プロの特撮並みなんです。長大な経典、しかもそんな経典が無数にあるわけですから、普通の庶民が全部読んで自分に合ったものを探すなんて不可能です。そこでトータルに大乗仏典を学ぶ比叡山の学生たちのなかから、一部を切り取って人々に示そうという革新的な考え方が生まれてきます。仏教としては奇形だけれど、人々を救済するには何よりキャッチーじゃなくてはいけない、ということですね」と述べています。この円谷プロの特撮に例える話法は素晴らしいですね。ワクワクしてきます!
「さまざまな宗派に別れ、庶民の救済を求めた『鎌倉仏教』」では、阿弥陀仏について言及しています。阿弥陀仏というのは、「アミターユス(無量寿)」または「アミターバ(無量光明)」が語源とされています。著者は、「つまり阿弥陀仏に抱き摂られるというのは、無量の光の中に入っていく、そして無量の命を得るということでしょう。こうした物語が、先ほどの『いろは歌』に続いて平安末期から鎌倉時代の民衆の間に一気に広まっていくわけです。よく『燎原の火のように』と言われますが、本当に凄い勢いで広まったようですね。じつは『いろは歌』の『有為の奥山』を越える、という言い方には、すでに浄土教の考え方が示唆されています」と述べます。ちなみに、著者にはブログ『アミタ―バ 無量光明』で紹介した素晴らしい小説があります。
他にも鎌倉時代には臨済宗、曹洞宗など、中国仏教である禅が伝えられ、最後に登場した日蓮は「念仏」ならぬ「お題目」を唱えるという、世界でも唯一の方法論を提案します。臨済宗、曹洞宗はむろん坐禅によって「禅定」に至ろうとするわけですが、著者は「これはけっこう難しいんですね。脚も痛いし。ところが法華太鼓を打ちながら『南無妙法蓮華経』とお経のタイトルを唱えるという方法は、じつに速やかに禅定に入れます。無理やりまとめてしまいますが、結局どの宗派も『戒』は気にせず、ともかく『定』を深めて智慧(般若)に至ろうとしたのでしょう。それぞれの『行』に専念すれば自ずと『戒』も守られるという考え方です。そして死にゆくときには無量の光に包まれる。これは非常に救済力のある物語ではないですか。じつは我々の臨済宗でも、あるいは曹洞宗でも、最終的には『南無阿弥陀仏』と称えています。ただやっぱり気恥ずかしいのか、臨済宗などはわざと中国音で『ナムオミトーフー』などと称えているんです。チベット仏教でも、人は死ぬと純粋な光になる、などと言いますよね」と述べています。
立花隆氏の名著『臨死体験』でも、世界中の臨死体験者に共通していたのが、暗いトンネルを抜けると光の世界に出たという部分でした。その後の出来事には民族性やお国柄なども反映されていましたが、そこだけは万国共通だったのです。著者は、「これは非常に多くの人々を救い得る物語ではないでしょうか。チベット仏教はアメリカのターミナルケアの現場でも宗教色を抜いて使われています。私が普段しているお葬式も、やはり故人のために物語を探したり創ったりする仕事ですし、時には教義にこだわらず、必要なら道教や神道、外国の絵本の物語やキリスト教だって動員したことがあります」と述べます。結局のところ著者は、世に数知れないさまざまな宗教を、人が充足した生を生きるための、あるいは安らかな死を迎えるための、豊かな物語群と捉えているのです。著者は、「向き不向きは感じますが、あまりどれが正しいか、とは考えません。亡くなった人自身が信じていた物語が一番ですが、それがわからなければ『お知らせ』に来てくださった方からなんでも聞きだし、自分なりに故人のための物語を創りあげないと『引導』なんて渡せないんですよ」と述べます。
「『光』と『死』の関係を考える」では、ブログ『アミタ―バ 無量光明』で紹介した素晴らしい小説を著者が書いたのは、まずはなにより光の象徴である阿弥陀仏が、光そのものを想わせなくなってしまったからだといいます。現代人は、浄土にああいう仏さまがいて、そのお膝元で楽しく暮らせる、と言っても信じませんが、「阿弥陀=光明」に戻してしまえば、現代の物語としても通じるのではないかと思ったそうです。エリザベス・キューブラー・ロスは、約200人の死にゆく人々にインタビューして『死ぬ瞬間 死とその過程について』(中公文庫)を書きましたが、そのなかで、人が死ぬ直前の静かな状況を「デカセクシス(Decathexis)」と呼んでいます。世間という住み慣れた空間や時間から離れた状況で、ある意味では通常の時空から「解脱」していると言ってもいい。著者は、「まさに『有為の奥山』を越えた状態である」と述べています。
一方で、人が死ぬ瞬間にはその質量が減るという話もあります。アメリカでは「21グラム」(2003年)という映画も作られました。もし質量が本当に減るのだとしたらそれは「魂の重さ」ではないかとも騒がれましたが、著者は「それよりアインシュタインの示した相対性理論の法則E=MC²(E=エネルギー、M=質量、C=光速)から、減った分の質量がどこかにエネルギーとして現れてくるはずなんです。もしかすると、人が死ぬ瞬間に不思議な現象が起こったり、「虫の知らせ」と言われることが起こるのも、そのエネルギーのせいではないか。使い切れなかったエネルギーの総体こそ『アミターバ』なのではないか。そんな思いで書いたのが、あの作品だったわけです」と述べています。
「死に対する共同幻想としての物語」では、原型的な物語は風土に大きく関係しているということが指摘されます。たとえば沖縄では海の彼方に「ニライカナイ」という場所が想定され、人はそこから来てそこへ帰るのだと信じられました。神の住まいもそこで、神は定期的にやってきては此の世に豊穣をもたらしてくれます。一方、海から遠い地域のほとんどでは、人の死後の行く先は「山の向こう」に想定されました。「有為の奥山」を越えて行く、というのは、その観点からも納得できたわけです。著者は、「日本で一番多い山の名前をご存じですか? ハヤマです。文字は葉山、羽山、端山、早山、麓山、といろいろですが、要するに各地の山がその土地と異界との端境だと考えられたわけです」と述べています。
日本民俗学の創始者である柳田國男が全国を調査した結果、ほとんどの地域で信じられている死後のイメージは、まずはホトケになり、一定期間を過ごしたあとは「祖霊神」というカミの集団に入ります。そこから春は農業神になって降りてきたり、子どもが生まれるときは産土の神として降りてきたり、また年末には歳徳神になってやってきて門松に降り立ちます。著者は、「つまり、ヒトがホトケになり、やがてカミになってこの世に出入りし、またヒトが生まれるわけですから、循環しているんです。自然の循環を取り込んだ考え方だと思います。ところでヒトが死ぬと、どこかへ往くのか、それとも帰るのか、という視点で考えると、日本人はどうも『帰る』ほうに安心感を抱いているような気がします。浄土や天国は、知らない場所ですから不安ですが、ニライカナイや大自然は生まれる前に居たところと解釈されますから、『回帰』する安心感があるのではないでしょうか」と述べます。ちなみに著者の場合は、位牌の一番上に「新帰元」と書くそうですが、これは「新たに元に帰る」ということ。元というのは「元気」、つまり宇宙根源のエネルギーのことです。
 『ロマンティック・デス』(オリーブの木)
『ロマンティック・デス』(オリーブの木)
「新帰元」とは、わたしたちは「元気」から元気を分与されて生きてきたけれど、いかんせん器の寿命がきたので此の世での生を終え、元気は元気の本体に帰っていくという意味だそうです。著者は、「本当は『物語(=杖)』なしで進むのが一番強いのかもしれませんよね。『人はただ生まれ、しばらく生きて、死んでいく』、虫や動物たちと同じように、それだけのことだと思いつつ、彼らのように真摯に生きられるのだとしたら、凄いことじゃないですか。しかしたぶん人間は、そうはできない因業な生き物なのでしょう。死をこれほど意識する生き物は他にいませんよね。ただ人間は、大切な人を失ったときに、その同じ因業さで救われたりもします。『物語』が本当に有効なのは、そんなときなのだと思います。たとえ後付けであっても、悲しみから癒えるために人は『物語』を必要とするのでしょう。ちなみに拙著『ロマンティック・デス 死を恐れない』(オリーブの木)の帯には、著者の「日本人の古層に宿った物語が、いま佐久間さんによって新たに甦った。これは現代人の安らかな死を支える、ゆるぎない物語である」との推薦文を寄せて下さいました。
「自殺を望む人にとっての『物語』とは?」では、自殺の問題に言及します。著者は、「親しい檀家さんのなかにも、自殺をしてしまう人は一定数います。そんなとき私がまず思うのは、単純な『物語』は放棄しよう、ということです。『物語』というのは、なんとなく『わかった』と思うための器ですから、原因も含め『わかった』と思うことは、他者の越権行為のような気がするんです。福島県の霊山に『霊山こどもの村』という施設があるのですが、そこにボタン1つでガラスケースの中に竜巻が起こる装置があります。とても面白いと思ったのですが、竜巻というのは、4つの風を別な角度から合流させて起こすんですね。2つでも3つでも難しいようですが、4種類の風が絶妙なバランスで合流すると発生するんです。私は、自殺というのはこの竜巻のようなものだと思っています。そしてたまたま合流した4つの風すべてを知ることができない以上、自殺を簡単な『物語』で解釈するのはやめておこうと思います」と述べています。非常にわかりやすい喩えで、感心しました。
ここで大切なのは、体を殺そうとした「私」は普段の私ではないということだそうです。鬱とか心身症のことも多いですし竜巻がさまざまな要因で起こっているのかもしれない。そう思いながら、著者はなんとか自殺者の葬儀も行なっていますが、「物語」という観点で言うと、自殺が起こるのは現実の変化に対応するための「物語」の再構成ができなかったということではないかと推測しています。ちなみに、カトリックは基本的に自殺を禁じています。著者は、「神さまの被造物が自殺するなんて、これほど傲慢なことはありませんし、何より神への冒瀆です。ですから地域と時代によっては自殺者の葬儀は行なわれず、遺体は池や沼に捨てられました。これは、バイブルに書かれた物語を重視するキリスト教徒には許しがたいし、自殺者のために『物語』を改編する気などないということです」と述べています。カトリックの自殺者への態度には、わたしも強い違和感をおぼえます。
第五章「魂と魂を繋ぐ『縁起』の世界」の「神はむすぶもの、仏はほどけるもの」では、「神はむすぶもの、仏はほどけるもの」という言葉について考察します。人は「結ぶ」ことでわかったと感じます。しかし「結ぶ」ことはいわば自己規定ですから、往々にして結びすぎてキツくなってしまいます。そうすると、今度は「解く」ことが必要になります。まだ学術的には証明されていませんが、著者は「仏」を「ほとけ」と呼んだのは「ほどけ」に由来すると思っているそうです。「解脱」だって、その意味合いの言葉ですね。民俗学者の柳田國男は、仏が神になるまでの一定期間、魂は個性を保ったまま存在していると考えました。著者は、「人情としてはどうしてもそう思いたいですよね。しかし同じ民族学者であり国文学者でもある折口信夫さんは、どちらかといえば無個性化すると考えたんです。そう考えたほうが救いになるケースは確かに多いのではないでしょうか。ですから私のなかでは、どうしても『ほどけ』て無個性化することが『成仏』なんです。個性があまりに偏重される世の中では、『成仏』も難しくなっているような気がします」と述べます。
「『たましひ』とは何か?」では、古語としての「たましひ」は、丸いから「たま」なのでしょうし、「しひ」は動きまわるものに付く接尾語であることが紹介されます。もしかすると古代の人々は、土葬で埋めた遺体に起こる「ひとだま」という物理現象を見て、そういう発想を得たのかもしれないと考える著者は、「土葬で埋められた骨からリンが分離し、土中の隙間を昇るうちに自然発火するようです。私も一度見たことがありますが、それは本当に明るくて、よく動きまわります。昔の人々は、どうやら物にも人間にもこの『たま』が内在していると考えていて、傷つかないよう心がけて暮らしていたようです。人の場合は死後もその『たま』が活動してその人を護ると考えられ、体内から自由に抜け出ることもできて、他人の『たま』と逢うこともできると考えていたようです」と述べています。
古代的な宗教観が、我々の執り行なう宗教儀礼にも反映されているといいます。たとば今でも、遺体の上に小さな刀を置きます。よく「獣除け」「魔除け」などとも言われますが、そうではなく、あれは死の自覚を持てない死者自身の魂が、体に戻ろうとするのを拒絶するためのものです。そして昔は、僧侶があの刀を抜き、額と繋がっている見えない糸を切ったとも言われます。著者は、「いわば生への執着を断ち切って、『自由』への一歩を踏みだしてもらうのだと思います。しかし此の世での自由と違って、知らない世界での自由は心許ないものです。しばらくはその辺を漂いながら、気になる場所に行ったりするのではないでしょうか。『アミターバ』で私が描いたのは、そのときあらゆる時間と空間を自在に行き来できる様子です。そうして最終的に僧侶が葬儀を執行し、此の世に見切りをつけてもらう。禅の世界では『引導を渡す』と言いますが、此の世で生きてきた足跡を顕彰し、辛酸に共感し、最終的に納得まではいかなくともある種の諦念をもって一歩を踏みだしてもらう。その背中を押すくらいが、私たち僧侶の仕事なのではないかと思います」と述べます。
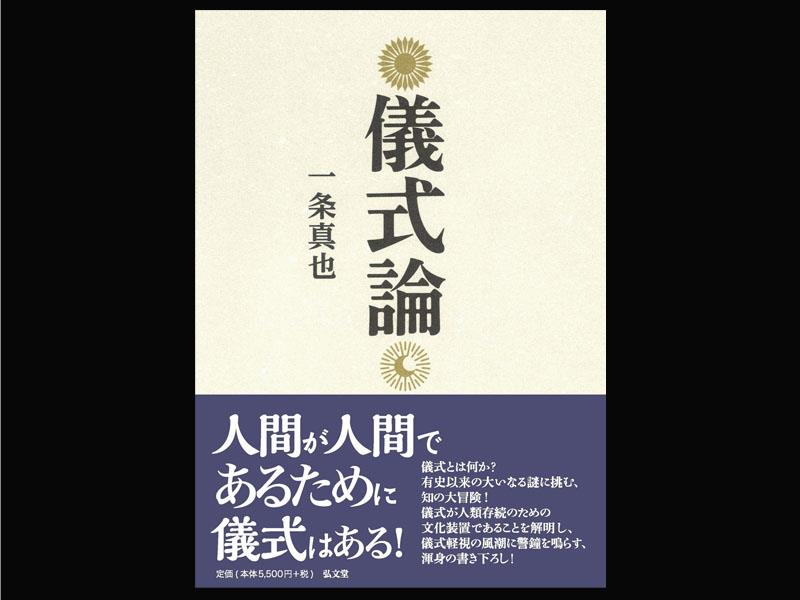 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
「浄土へ往くのは何か」という質問に対して、著者は「出発するときは明らかに個性を持ったその人の『魂のようなもの』だと思いますが、到着するときは『娑婆の衣を脱ぎ棄てた』元気そのもののイメージですね。そういったイメージを、参列者も含めて持っていただければ、『魂のようなもの』も『ほどけ』て『成仏』するのではないでしょうか」と述べます。いわゆる横死や頓死、自殺、夭折など、なかなか「ほどけ」にくそうなケースでは「引導」に苦労します。時には叱って送りだすこともあるそうです。悔しくて叫ぶこともあるとか。しかし結局、死そのものはいずれ受け容れるしかありませんし、その際「時の経過」は非常に重要になるといいます。著者は、「神道では『荒魂』と『和魂』という言葉を使いますが、時の経過と共にこちらが受け容れる気分になったとき、『魂のようなもの』はようやく『和魂』になって、我々を見守ってくれる存在になるのではないでしょうか。私はなにも、『魂のようなもの』が実在すると申し上げているわけではありません。ただそれは、親しかった人との関係性のなかにリアルに立ち現れます。その姿を少しでも穏やかなものに変成するのが儀式の役目だと思います」と述べています。これには、『儀式論』(弘文堂)の著者であるわたしも大いに納得しました。
 『唯葬論』(三五館)
『唯葬論』(三五館)
古来、「身」から「魂」が抜けた状態を「からだ」と呼びました。17世紀初めに編纂された『日葡辞書』の「Carada」の項目には、現在の「身体」の意味が「卑語」として使われはじめたと記載されていますが、メインの意味は「死体」です。おそらく室町時代くらいまでは英語の「Body」と同じような使われ方だったのだと推測する著者は、「生きている、ということは『からだ』にきちんと『魂』が収まり、『身』として機能していることです。つまり、弥生の島の考え方が、古代日本的と言えるのかもしれませんね。おそらく『魂』の在り処は弥生と同じように心臓と考えていたのではないでしょうか。『たまげる(魂消る)』とドキドキするじゃないですか」と述べています。「『たましひ』の向かう場所『渾沌』と『浄土』の違い」では、「渾沌」が陰陽の二気に分かれ、やがてあらゆる命が生じることが説明されます。葬儀は人情を踏まえたうえで人情を絶する儀式ですから、一喝して個別性から渾沌、あるいは元気に還そうとするわけです。しかし、著者は「そうは言いましても関係性次第では、時間がかかる場合があるということです。ただ、亡くなった本人は案外スーッと成仏しているんじゃないですか。問題は残って見送る人々でしょう。死はその両者の間に起こっている出来事だから厄介なのです」と述べるのでした。これには『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』(三五館、サンガ文庫)の著者であるわたしも大いに納得しました。
第六章「人間の本性は善なのか? 悪なのか?」の「親鸞聖人の『悪人正機説』の真意とは?」では、「性悪説」と「性善説」で言えば、仏教は間違いなく「性善説」であると指摘されます。『大乗起信論』の「自性清浄心」という考え方、あるいは「光明蔵」「如来蔵」といった考え方が「華厳思想」に流れ込み、それが仏教各宗に浸透しているからです。著者は、「この『華厳思想』というのは本当に凄い思想で、すべてが『雑華』として世界を『厳飾』、つまり飾っていて、そこに毘盧遮那仏から光明が差しているというんです。影のない光の世界ですね。鈴木大拙博士は『華厳の研究』という本のなかで、『雑華厳飾』の『雑華』を『普通の花』と訳しました。此の世的な価値観では出来不出来もいろいろあるでしょうが、みんな『普通』なんです。『雑』といえば反対語の『純』が浮かぶかもしれませんが、その区別もない。序列もなく評価もなく、みんな『雑』だしみんな『普通』なんです。しかもすべては『重重無尽』に繋がっていて連動するし、それでいながら独立しています」と述べます。まさに「インダラ網」ですね。これは此の世的な価値観では理解しにくいことですが、親鸞聖人はそういうところから此の世を眺めていたのかもしれません
「個性を重視しすぎると辛くなる? 全体の繋がりと自分」では、もともと「個性」とか「個人(individual)」というのは、キリスト教の長い歴史のなかで、神と向き合うことで出来上がってきたものであることが指摘されます。カトリックには「告解」という習慣があり、電話ボックスみたいな箱のなかで神さまに1年間の罪を告白します。実際は裏に司祭がいて聴いているわけですが、何が罪なのか、という細かい擦り合わせを通して近代的な自我というものが12世紀くらいから徐々にできてきました。こうした個人がいて、ヒエラルキーがあって、それが社会を構成する、というのが西洋的な在り方です。しかし「華厳」的な見方をすると、個人というのは初めから単独では存在しないとして、著者は「『みんな』と一体なのです。『今ここ』の人の在り方は、全体との繋がりのなかに暫定的に現れているにすぎない。だから私だけが幸せ、というのはあり得ないんです」と述べています。
「多様な仏教思想に影響を与えた『空』の思想」では、仏教全体に影響した大きな考え方として「空」の思想が取り上げられます。これは主に『般若経典』の中心テーマで、あらゆるモノには自性がない、すべては関係性のなかでの「無常」な出来事だという見方です。著者は、「たとえば『赤い花』があったとしても、犬には赤く見えていませんし、飛んできた蜂にもそうは見えていません。しかも『花』という名付けゆえに人間は『花』だけを切り分けますが、それは命の実体にそぐわないのかもしれない。自性がないもの同士ゆえにさまざまに関係しあい、変化しつづけているのがこの世界、というわけです」と述べます。だから人間のなかに芽生える感情についても、あくまで暫定的な出来事と見ます。そのような見方が本当の智慧(=般若)だというのが「般若思想」です。『般若経典』ではその智慧に到る方法論として6つの「波羅密多」(実践法)も追求されます。他の仏教思想も、大乗仏教ではすべてこの思想を前提にしていると思っていいといいます。
著者が特筆するのは、『般若心経』などにもこの智慧を体現した「観自在菩薩」が出てきますが、これはサンスクリットの「アヴァローキテーシュヴァラ」の翻訳語であるということです。翻訳者は玄奘三蔵です。そして「アヴァ」は英語で言えば「Away」で、次の「ローキタ」が「Look」、つまり「離れて見る」ことこそ真相を観るには肝要だと考えています。感情や価値判断を付着させない見方が「イーシュヴァラ」(=自在)に通じるというのです。『法華経』も「空」を前提にして説かれていますが、1つ大きな特徴は「久遠の釈迦仏」というイメージを提案したことです。要するにクシナガラの林の中で、お釈迦さまは故郷のある北を枕に、涅槃に入られた(入滅された)とされますが、あれはじつは人々を油断させないための「方便」で、本当は死んでいないというのです。生きつづけている釈尊が「久遠の釈迦仏」で、こうした在り方を「久遠実成」と呼びます。
また『華厳経』や『法華経』では、特に「菩薩」という生き方が強調されます。「利他」つまり隣人の救済を、「自利(自ら悟りを目指すこと)」と同時に進めていくということです。なかには「自未得度 先度他」(『大乗涅槃経』)などという表現もあり、自らが救われるまえに先ず他人を救済するという考え方もありますが、著者は、これは心がけとしてはいいとしても、実際の行動指針にはならないと述べます。泳げない人が溺れた人を救うことはできません。ただ他人の救済は常に自己救済のあと、と割り切るのも問題で、そうなると「利他」の機会はいつまでも来ないかもしれません。「この世を四つに分けて捉える『華厳』の世界観」では、『華厳経』を元に華厳宗という学派ができることが紹介されます。その中心テーマは「重重無尽」の「縁起」です。インダラ網のイメージも大きく寄与しているでしょう。すべての関係性の中心に存在する仏は毘盧遮那仏で、梵語ではヴァイローチャナ・ブッダと呼ばれますが、「太陽の輝きの仏」という意味です。この光があらゆる衆生を照らして衆生は光に満たされ、同時に毘盧遮那の宇宙は光り輝く衆生で満たされています。この関係を「一即一切、一切即一」と言います。
「神と人間の『葛藤』が根本にある西洋哲学」では、ドイツの哲学者イマニュエル・カントが取り上げられます。カントが面白いのは、「人間は空間と時間を先験的(ア・プリオリ)に理解している」と述べている点です。また、人間の認識方法を「感性」と「悟性(知性)」の2つに分けたうえで、我々は対象物(object)そのものを見ているのではなく、その両者が提供する「認識の枠」で捉えた現象(phenomenon)を見たり聞いたりしているに過ぎないと、『純粋理性批判』に書いています。著者は、「つまり、鳥を見たから鳥と認識したのではなく、鳥と認識したから鳥に『なった』ということです。自分でも『コペルニクス的転回』と言っていますが、これはまさに仏教の『空』に近い認識だと思います。こうしてカント以後、西洋でも物事を『空』という『理』で理解することは可能になったのでしょう。これは仏教的認識でもありますが、現代の大脳生理学が導いた研究成果にも合致します。ですから大拙先生も、『理事無礙法界』までは哲学者も理解しているとおっしゃったのでしょう」と述べています。
「『事事無礙法界』の根底にある心の在り方」では、仏教では、「大地」と「天空」のもつ力を、「地蔵」と「虚空蔵」で象徴することが紹介されます。「場所」と「空間」に言い換えることも可能かもしれません。「地蔵」とは大地のもつ生産性ですが、別な見方をすれば「変わらない」「動かない」と見えながら何でも生みだして変化させてしまう力です。一方の「虚空蔵」は、虚空つまり天空が、「変わりつづけている」「動きつづけている」と見えながら、総体としては常に変わらないという在り方の象徴です。共に胎蔵界曼荼羅に属する菩薩ですが、これは両方ともお釈迦さまや人間のもつ能力の象徴です。著者は、「事事無礙の世界には、まだ矛盾も葛藤もないのだと思いますよ。ただエネルギーの根源としての神と『渾沌』を比べますと、『渾沌』の内部では常に陰陽の鬩ぎ合いが発生しています。いわゆる『太極図』ですが、これが『元気』の源です。つまり葛藤がエネルギーを産みだしているわけです。ここから全てが『なる』ことになりますから、東洋には創造主としての神は要らないのです。その意味で西洋の神は、おっしゃるように初めから『ある』のかもしれませんね」と述べるのでした。
第七章「東洋の『気』と西洋哲学の関係を考える」の「時間と空間を超えて万物を繋ぐ『気』の発見」では、著者は、時間と空間を貫きながら変化しつづけるこの「気」を発見したことが、東洋あるいは「華厳」哲学の背景にある最大の強みだと述べます。人間のなかの「気」の様子は「気持ち」とか「気分」「気ごころ」などと言いますが、「気」は山川草木の全てを遍く繋いでいます。「華厳」の「光明遍照」も、光として考えるとどうしても影を思い浮かべてしまうのですが、「気」ならばそれも可能ではないかというのです。著者は、「思えば人間の生活は、空間的に動きながら時間的経過を辿るもので、これは同時に起こっています。時間と空間は分けられないはずなんです。これを無理やり分けた西洋と、『気』の離合集散として統一的に捉えた東洋の違いは大きいと思いますね。『縁起』は時間と空間の双方に関わる在り方です」と述べています。
分節やカテゴリー化は西洋文化のお家芸というです。デカルトによって身心二元論が成立しますが、これはキリスト教への抵抗のため、ある意味やむを得なかったと言えます。しかもそれによって産業革命が起こり、市民社会の誕生にも繋がりました。しかし科学技術や市場経済が自然や人間をおびやかす現代に至って、ようやく身心を統一的に捉える「気」に注目が集まってきたのではないかとして、著者は「要は、住む場所によって人の気分も変わるし、佳い気の溢れる場所に住めば人間も大きく成長できる、という考え方です。当然、『縁起』の思想にも馴染みやすい考え方で、私は『華厳』の思想もこの『気』の文化あればこそ、中国や日本でスムースに広まったと思うんです」と述べます。
「アリストテレスとプラトンの『イデア』の捉え方」では、「万学の祖」と言われるアリストテレスは、あらゆる物事をとにかく整然と分類したことが指摘されます。ある意味、分類じたいが「イデア」への抵抗にも思えますが、アリストテレスは「プシュケー」をまともに論じています。プシュケーという言葉は、じつは本来「気息」の意味とされます。インドの「アートマン」も、ドイツ語の「ガイスト」も、同じように「魂」を意味しながら本来は「息」のことです。やはりどこでも「息」に魂を感じたということでしょうか。しかも「プシュケー」には「蝶」という意味もあります。そして日本の『万葉集』には蝶々が一度も出てこないそうですが、これも「魂」も運んでいると思われていたため、言葉にするのがタブーだったのではないかと言う人もいるそうです。
第八章「生命力を産みだす『渾沌』とは何か」の「『気』の自己増殖力と日本の神話への影響」では、陰と陽とは対等であることが指摘されます。序列はありません。両者が絡み合って新たな命が産みだされるその大元です。この考え方は荘子の「両行」にも通じます。『荘子』には「天鈞」という言葉も出て来ますが、これは西洋的な二元論ではなく、「天から見れば、どっちもどっち」、釣りあってるじゃないかという見方です。是非善悪や美醜尊卑といった1つの価値観の高低で見るのではなく、見方さえ変えたら両方OKだろう、という考え方なのです。荘子は「道枢」という言葉も使っていますが、「枢(とぼそ)」というのは回転ドアの軸のことです。つまり二元論じゃなくて、見方は360度あり得るというわけです。
この「道枢」という考え方は、じつは「八百万の神」にもしっくり来ます。もともと最初の三神じたい、同じ存在への3つの見方で生まれた名前です。神々がどれほど増えてもおかしくないわけです。しかも「ギリシャ神話」のように親子関係などはあるものの、そこには明確な序列はなく、基本的には対等ですから、争ったりもします。「八百万の神」には役割分担はありますが、ヒエラルキーはないのだと思います。著者は、「かなり独特の見方かもしれませんが、私はこうした感受性が予めあったからこそ、『華厳』の考え方がこの国にすんなり浸透したのだと思います。ニーチェがむきになって否定した『絶対神』はもとより日本には存在しませんでしたし、私たちの先祖たちが崇めたのは自然の生産性や、その増殖力だったのではないでしょうか。そして自己増殖も、じつは死を呑み込みながら円環をなしています」と述べます。
「日本人の精神に根差す、序列なき『両行』の思想」では、日本の場合、幾層にも「両行」がはたらいていますが、一番大きいのは言葉であろうとして、著者は「中国から入った漢字文化はありがたく享受しながら、それまでの話し言葉も『訓読み』という形で残しました。「腕」という文字は使いながら、『ワン』だけじゃなく『うで』と、これまでどおりにも訓んだわけです。また仮名を発見したことで、視覚文字である漢字といわゆる表音記号としての仮名文字も両行させました。漢字仮名交じり文という日本語のこの形は、世界でも稀ですし、情報処理に使われる脳の範囲が最も広いとも言われます。つまり仮名は通常の音声処理ですが、漢字のほうは一瞬に絵画として読み取っているということです。しかもこのとき、漢字を『真名』と持ち上げ、自分たちの文字は「仮名」とへりくだっています。そうして更に『仮名』のなかにも平仮名と片仮名を両行させました。平仮名は和歌など、主に国風の文化を担いますが、片仮名は漢文の書き下しの際の送り仮名など、主に僧侶たちが漢文の読解のために用いました。片仮名はその後、外国語を受け容れるための音声文字としても有効に使われていきます」と述べています。
こうした両行(=デュアル・スタンダード)は、たとえば武家と貴族が共に600年以上権威を保ったところにも表れています。建築も、『方丈記』のように庵というコンパクトな住み方が推奨される一方で、世界にも稀なほど勇壮な城郭建築を作ったわけです。この庵と城郭に対応するように、「ワビ・サビ」と「伊達・婆娑羅」という極端に違う美学もありますよね。鄙びと雅びも両行です。さらには、「義理と人情」などのように個人の心に両方ある、というものもあります。「本音と建て前」「私と公」、人によっては「意気と通」なども個人のなかで両行できるのかもしれませんね。また「侘び茶」というのは、「雅びのなかに鄙びを見出す」個人のなかでの両行であると、著者は指摘します。
たとえば諺も、正反対の意味合いのものがほぼ必ずあります。「嘘つきは泥棒の始まり」に対して「嘘も方便」、「芸は身の仇」と言いながら「芸は身を助く」とも言う。「栴檀は双葉よりも芳し」と早熟を誉めながら、「大器晩成」という言葉も用意してあります。「血は水よりも濃い」と言いながら「遠くの親戚より近くの他人」と言うし、「大は小を兼ねる」と言うのに「山椒は小粒でもピリリと辛い」とも言う。「武士は食わねど高楊枝」などとプライドを重んじるのに、いざとなれば「背に腹は代えられぬ」と食べるのもアリです。「立つ鳥跡を濁さず」のはずなのに、「旅の恥はかきすて」と言われる去り方もあります。「三つ子の魂百まで」と肝に銘じることは大事ですが、時には「喉元過ぎれば熱さ忘れる」ことがいい場合もあります。著者は、「キリがないですが、要するにどちらに転んでも対応できるように、両極端の在り方を共に知っておくべきだと考えているのではないでしょうか」と述べます。
人さまざまだからこそ、我々は両極端を踏まえたうえで、現実にはその間のどこかベストな場所を直観的に判断して着地する方法をとるわけです。日本人は、この両行と直観で自らの行動を決めているような気がします。フランスの地理学者で東洋学者のオギュスタン・ベルクの言う「一見矛盾と見える性向の鍵」は、直観がはたらけばこそ。だから直観を磨くために、この国ではあらゆる「道」の付く文化が盛んになったとして、著者は「剣道、柔道、弓道などの武道はもちろん、花道、茶道やあらゆる古典芸能もその範疇に入ると思います。要するに、繰り返し同じ行為を『稽古』することで、無意識にその動きができるようになる。そうなった状態を『身についた』と言いますよね。これこそ直観の発露する場です。そして日本人は、その状態こそ『無意識』が『ケ』として発露する場と考えた。つまり思っていた以上のことが無意識のおかげでできるわけです。意識より無意識は遥かに膨大なことを知ってるはずですから」と述べるのでした。
「『曖昧』と『両行』の関係」では、日本語の「やさしい」という言葉が取り上げられます。古語としては「やさし」ですが、これは「痩せる」と同根の言葉で、本来は「身が痩せてしまいそうな」という意味だといいます。つまり、両極端は踏まえたものの、その間の最適解を選べない人は痩せるほど苦しむのでしょう。場合によっては「大悲」の気持ちが強すぎて身動きがとれなくなることもあるのかもしれません。今は「やさしさ」というと、「温かく思いやり深い」というような褒め言葉に使うことが多いですが、基本的に著者はこの言葉に両行における直観の機能不全状態を感じるといいます。
「『名付け』前の入り混じった状態を『混沌(カオス)』と捉える西洋、創造の場を『渾沌』とする東洋」では、わたしたちが「有」と認識するには、「名と形」が必要ですが、それを「創世記」は端的に示していることが指摘されます。やがて人は、神に倣って言葉を使い、さまざまなものを細かく名付け、分節して、いわゆる現実としての存在世界を作っていきますが、言葉による分節行為はいつだって強引で暴力的あることを忘れてはいけません。たとえばある土地の隆起を「山」と名付け、近くを流れる水を「川」と名付けるわけですが、それによって「山」と「川」は一体でなくなります。また「花」などは、「茎」や「葉」や「根」がなければ存在することもできないのに、名付けた途端に「花」だけで存在できるような錯覚さえ招きます。著者は、「全体が繋がって関係し合いながら存在しているのに、『名付け』によって単独性が出てしまう憂いは避けられない。だからこそ、中国の老子は『道』を規定して『名無し』と言い切るのです。名の弊害を熟知していたわけです」と述べています。
光が当たると存在が区別され、物と物との境界がはっきり見えますが、それは「名付け」と同様、繋がったものを無理に分けることにもなると認識すべきであるといいます。そのことを承知すれば、先ほど『華厳経』から紹介した「一は即ち是れ多、多は即ち是れ一」という言葉も、混融した「一」と分節後の「多」であることがわかりますし、「有は即ち是れ非有」というのも「相は即ち是れ非相」も、共にコスモスとカオスにおける存在状態の違いなのだと納得できるはずです。コスモスとは、先ほどのオリンポスの神々による明るい存在秩序の世界、西洋ではこれが善であり美なのであるとして、著者は「西洋と東洋とは、大雑把に言えば、このカオスとコスモスの扱いの違いによって大きな決別を経験したと言えるかもしれません。カオスを悪や醜と見て、ひたすら秩序を追求した西洋と、『渾沌』や『無』、『空』などをも肯定的に捉えた東洋の違いですね」と述べます。
「『無』とは、分断される前の無限の可能性を含む世界」では、直観の本質が明かされます。直観とは、そこに稲妻が走ることに似ているといいます。脳科学でも、閃きが起こる瞬間は、全体が低電圧のときだと言っていますが、稲妻が走ればその瞬間にはありのままの姿が短時間ですが見えます。直観が閃くその一瞬の姿こそ重要なのだというのです。これには大いに納得しました。比喩が素晴らしいですね。おそらく「両行」というのも、世界に「曖昧」に向き合うための大切な手立てではないかという著者は、「いわゆる二元論は、世界をあっさり分断する大鉈のようなものです。意志的で、人間的な振る舞いと映るかもしれませんが、それは『重重無尽』の華厳世界からすればどうしたって破壊的で人工的です。まずは二元の両方を肯定し、とりあえず命の全体性を担保しておいて、あとは直観で最も相応しい着地点をウパーヤ(方便)として選択するわけですね」と述べます。
「華厳」という見方は、ですからじつは現実には見えない無分節の世界を、特殊な光のもとで全て見せてくれたのではないかといいます。この状態では物と物とが区別されず、私とあなたの仕切りもない。もしも稲光が光れば、すべては繋がったまま見えるはずです。だから「事事無礙法界」も可能になる。救いの手を差し伸べるという意識さえまだ芽生えないうちに、直観的に救ってしまっている世界です。それこそ見性直後にブッダが見た本源的「一」の世界ではないでしょうか(見性とは、性(もちまえ)を見(あらわ)すことで、禅宗では「悟りを得ること」を意味します)として、著者は「荘子は同じ事態を『斉物』と呼びました。あらゆるものが繋がっていて区別されず、『斉しい』ということです。同じ事態を、荘子は『広漠の野』『無何有の郷』など、さまざまに表現しましたが、何と言っても極めつけは『渾沌』でしょう。荘子の哲学を象徴するだけでなく、『渾沌』の一語は東洋的な『無』に蠢く力を集約していると思います」と述べるのでした。
第九章「すべては変化しつづける『唯識』のなかで生命を考える」では、唯識が取り上げられます。唯識とは、個人とってのあらゆる存在が、ただ8種類の識(八識)によって成り立っていると考える大乗仏教の教えの1つです。ここでいう8種類の識とは5種類の感覚(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)、意識、そして二層の無意識を指します。インド北方の瑜伽行唯識学派と言われる人々が提唱し、仏教が流入した当初に日本には将来されましたが、大元のインドや中国では資料の大半が現存せず、消えかかっていると言っても過言ではありません。唯識では、肉体もじつは心が深く管理していると考えます。そのため、いわゆる「識」というのを、表面化する意識だけでなく、更に二層の無意識に分けて捉えます。
わたしたちは、眠ると意識が途絶えます。そのときは感覚もだいたい休んでいます。しかし朝起きても認識が変わっているわけではありませんし、昨日と同じ統一体を保っています。これは、自分では意識できませんが、意識の領域をバックアップしている眠らない心があるからだと考えるわけです。いわば心の基盤のようなものですが、これを唯識では阿頼耶識と呼びます。アラヤというのは、倉庫や蔵を意味します。意訳では「含蔵織」とも言いますが、あらゆる行動や認識の残り香のようなものを全て記憶して保存するとされ、個々の情報は種子(しゅうじ)、あるいは習気(じっけ)と呼ばれます。このおかげで我々は人格と呼べるような一定のまとまりを保てるわけです。最も深い無意識が阿頼耶識ですが、その少し上部にあるのが末那識です。これは梵語の「マナス(意)」を玄奘三蔵が音写した言葉で、意識の背後で常に自己中心的にはたらくとされます。
末那識は、自分中心の方向に我々を仕向けますが、この阿頼耶識もわたしたちの認識作用にさまざまにはたらきかけます。わたしたちは無限の過去の影響を受けながら、今を生きる存在だということです。ところで我々が今生きているのは、前世で生への執着を捨てきれなかったからだと唯識では考えるとして、著者は「阿頼耶識の情報の基盤には、突き詰めると『生きたい』という執着心があるようなのです。前世で生への執着心が捨てきれなかったから今の生がある。滅多にないことでしょうが、肉体が滅びるときに生への執着が断ち切れている状態を『解脱』とか『涅槃』と言います。むろんお釈迦さまはそれを35歳で生きたまま成し遂げたことになっています。しかし普通は、肉体が死ぬときも『生きたい』という執着心が残っていますから、それは今までいた肉体を離れ、新たな肉体に宿ることになります。これが『輪廻』ですね」と説明します。
「普遍的な事実というものは存在せず、全ては『識』が作りだすフィクション」では、大切なのは、我々が見たり感じたりする世界は世界そのものではなく、「唯(ただ)識」に過ぎないということだといいます。阿頼耶識は気づかないうちに行為や認識の基盤になっていますし、末那識は自分好みにその認識を加工し、色づけし、時には嘘とも思えるほど対象をデフォルメしてしまいます。無かったものを有ったことにする、などという大胆な演出までしてしまうのが末那識の恐ろしさです。更に五感や意識も、当然その影響で変化します。こうした変化を唯識では「能変」と呼びますが、阿頼耶識で起こるのが「初能変」、次に末那識で「第二能変」が起こり、最後の意識や前五識による「第三能変」までが連続してこれまた瞬時に起こるわけです。現行を起こす潜勢力はむろん阿頼耶識にあって、そこから現行が芽吹くのですが、決してそのまますんなり行為や認識になるわけではありません。著者は、「注目すべきは、最初の能変が意識や感覚レベルで起こるのではなく、一番深い阿頼耶識で真っ先に起こってしまうことですね。ある意味、手がつけられない感じがしますが、それでも我々は『現行薫種子』を信じて微力な上書きを続けるしかないのです」と述べます。
「全ての『識』は『空』に通ずる」では、著者は最終的には「色即是空」であると共に「識即是空」という見方が大事だと思うと述べています。何層にも重なった「識」が能変して作り上げるのが我々の見聞きする「色」の世界ですが、結局それは大元の「識」が「空」なのだというのです。単独の自性を持たず、縁起のなかでの無常なる現れに過ぎません。『般若経』には「輪廻を怖れず」とか「涅槃に往せず」という言葉も出てきますが、それは「輪廻」も「涅槃」も執着しなければ「空」だからです。実体のわからない阿頼耶識に怯え、輪廻を怖れることも、阿頼耶識が止滅するという「涅槃」にこだわることも、『般若経』は否定するのです。「自然」の象徴が「龍」ですが、西洋のドラゴンはサタンの使いですから撲滅すべき相手ですが、東洋ではとにかく「龍」を味方につけようと各宗教がいろんな儀式をします。著者は、「臨済宗では本堂に法鼓という大きな太鼓があって儀式の前に独特のたたき方をしますが、あれは雷を真似た音で龍を招き、その儀式がうまくいくようにという祈りの太鼓です。『法鼓雷鳴』と言います。何事も、自然に味方してもらい、ご縁が調わないとうまくいかないと考えている、ということですね」と述べます。
「『大乗円頓戒』の『十重禁戒』に集約される仏道」では、伝教大師最澄が一生をかけて実現した大乗戒壇での戒律、つまり「大乗円頓戒」の中の「十重禁戒」が取り上げられます。これは比叡山で修行した各宗の祖師たちにも受け継がれていますから宗派色がありません。ただ親鸞聖人の浄土真宗は、持戒によって自力の念が生ずることを懸念し、「無戒」という独特の立場を取りますが、これも優先事項が違うだけで、特にこの戒を否定するわけではありません。さまざまな経典の思想を集合した「仏教」は、戒を受け、具体的に行動を伴うことで「仏道」になるといいます。人において1つにまとまるわけです。いや、むしろ「仏教」という言葉こそ明治以後の新しい術語で、それまではずっと「仏道」と呼ばれていましたから、それこそまさに終わりのない生き方の指針なのだといいます。著者は、「終わりのない、というのは、人間『わかっちゃいるけど……』というのがありますから、これらの戒に全く抵触しなくなる日はなかなか来ないということです」と述べるのでした。
最終章「むすんでひらいて 無限の可能性を信じて生きる」では、今、15歳から39歳までの死因の第1位は自殺(10歳から14歳の1位は小児がん。2位が自殺)であることが紹介されます。著者は、「むろん戦争も感染症も大きすぎるほど大きな問題ですが、こんなせつない体験をしている家族が今の日本には無数にある。また今日も大勢の若者が、竜巻に吹き飛ばされようとしている。これほど重い事実はないのではないでしょうか」と述べています。自殺は幾つもの原因が竜巻のように合流すると考えているのは事実ですが、これはある意味で死者の尊厳のための物語でもあります。著者は、「実際のところ、自死する人の根底には、鬱的な思いがあります。つまり、現状の悪い要素は更に深まっていき、突発的な慶事が起こるはずもない。なぜかそんなふうに思い込んでいるわけです。これは限られた情報や能力による思い込みの覇権主義ではないでしょうか。いわば大脳皮質、もっと言えば左脳による思い込みが、我々の全身に対して今のロシアのように覇権的に振る舞うわけです。それがたぶん自殺なんです」と述べます。
最近岸田政権は閣議決定で軍備増強を決め、その後に文科省がにわかに理工農系の学部を増やすと発表しました。今後10年かけて、文系学部の多い私立大を理系に学部再編するというのですが、これはますます左脳の覇権主義を強める道です。大脳皮質によるナチズムとも言えるような、論理や推論を絶対化する社会が更に苦しむ若者を増やすことだろうとして、著者は「そう考えると、コロナ禍も戦争も自殺も、じつはすべて覇権主義の産物として理解できます。戦争は旧来の覇権主義、コロナは自然への人類の科学技術による覇権主義、そして自殺は左脳の思い込みによる生命への覇権主義です。この覇権主義を解毒できるのは、やなり『空』や『華厳』の思想、つまりどんな事象も無常で無限なる関係性における仮の現れにすぎないという認識であり、多種多様の在り方が根源的な『一』という体験的実感に収斂するという考え方です。もっとざっくり言えば、思い込んだ固い結び目のような考えは、ほどくに限る、ほどくしかない、ということなのです」と述べています。
「『結ぶ』ことで渾沌から産まれる『思い』 『ほどく』ことで渾沌に還る『迷い』」では、仏教は、どんな考え方であれ、絶対化することを嫌うことが指摘されます。釈迦は亡くなる前に、「自らが経験的に会得した『法』以外、よりどころにしてはいけない」と言い残しましたが、そんな釈迦に対してさえ、禅は「釈迦に逢っては釈迦を殺せ」と言います。これはつまり、お釈迦さまといえども絶対化するなという教えです。著者は、「人がなにかを学んで思いをまとめることは、『結ぶ』と表現できるかと思います。脳内シナプスの接合を思い浮かべるかもしれませんが、神道の神さまも『結ぶ』ものです。結ぶことで渾沌のなかに姿を現し、現実的な力を発揮します。しかし人はその大元の渾沌をすぐに忘れ、結んだ思いを必ず強める方向に感覚器を駆使します。思い込みに適う情報を探すわけですから、思い込みは必ず強まり、結びもきつくなるのです。そして結局、思い込みの覇権主義に突き進むことになるのだと思います」と述べます。
少子化問題だって、この「合理的推論の絶対化」のせいだと言えます。一生の収入を予測し、子育てにかかる経費を類推した結果、育て得る子どもの数がどんどん減っているということですから。むろん根底には格差の拡大や非正規職の増大があるにしても、です。著者は、「仏教、とりわけ禅は、『今』に生きよと言うのですが、現状の我々は、増大する過去のデータと膨張する未来予測に挟まれて、『今』を見失っているのではないでしょうか」と述べます。人間が人間社会で生きていくためには、弊害は多いけれども言語の「結ぶ」機能がどうしても必要になります。しかし人は、原初のほどけたエネルギッシュな状態、つまり「渾沌」をどこかで覚えているのでしょう。そこへ繋がる回路を、もう1つの知性として蘇らせたのが東洋の宗教ではないかとして、著者は「いわゆる『瞑想』や『坐禅』、あるいはチャンティング(読経)というのもそのための技術だと思います。少なくともそれがうまく行なわれていれば、我々は『今ここ』に居つづけることができます」と述べています。
「むすんでひらいて……繰り返し向き合うことで、生は紡がれる」では、日本人なら誰でも知っている「むすんでひらいて」の歌が取り上げられます。この歌は、終戦後、鈴木大拙が「華厳」思想を天皇皇后両陛下にご進講された翌年、つまり1947年の5月に、『一ねんせいのおんがく』に掲載された文部省唱歌です。音楽を小学校の科目として教えたのはこれが初めてだったわけですが、著者はこの歌に、戦後の心の復興を願う気持ちをとても強く感じるといいます。もともとこの曲は、ジャン=ジャック・ルソーの作曲と言われていて、ルソーが夢のなかで閃いたとされることから「ルソーの夢」とも呼ばれました。そして、明治初期から中期にかけて、すでに「見わたせば」という題名の小学唱歌として歌われ、明治30年代後半からは幼児教育の現場で、「むすんでひらいて」という遊戯唱歌として用いられていました。ただ不思議なことですが、この歌の作詞者がわからないといいます。昭和23年の教科書にも「作者・不明、作曲・外国民謡」となっており、その後の検定教科書でも、ルソー作曲と書いてあるのは半数くらいのようです。
「結んで開いて、手を拍って、結んで、また開いて、手を拍って、その手を上に」という歌詞を誰かが作詞したのは間違いないはずですが、なにゆえ「作者不詳」なのか。この歌は、日本人であることを呼び醒ます歌であるように思えるとして、著者は「第二次世界大戦の敗戦のショックは、今では想像もつかないくらい大きいものだったと思います。日本語廃止論まであって、完全に英語教育を押しつけられる可能性だってあった時代です。民俗学者で国文学者でもある折口信夫は、このとき『日本文化の永遠の敗北』を危惧したといいますが、鈴木大拙翁が『日本的霊性』を書いたのも、そうした切迫した危機感のなかでした。昭和天皇皇后ご夫妻に『華厳』についてご進講したのも戦後の立て直しのためだったわけです。そして私は、この『むすんでひらいて』にもそれに似た日本復興のための深謀遠慮を感じるのです。結んで開く、と始まりますが、これは本来、神と仏です」と述べます。神はカミムスビの神やタカミムスビの神を持ちだすまでもなく「結ぶ」ものです。そして、次は「ほどける」仏の登場になります。仏とは、解脱した存在ですから、まさに「ほどけた」わけです。
著者はこの歌を憶いだすと、「さまざまな人生上の問題って、じつは解決できるものじゃなくて、何度も結んだり開いたりしながら向き合っていくものだと思えてきます。そうしているうちに、いつしか状況は変わってきます。今の若い人たちは、何にでも『1つの正解』があると思っているように見えて仕方ないんですが、人生は後戻りできない以上、結んだり開いたりしながら、悩みながら、自分の歩む道を『正解の1つ』にしていくしかないんじゃないでしょうか。自殺を考える若者たちは、結んだ『思い込み』を開くことができず、どんどん自縄自縛になっていきます。しかも思い込んだ『正解』から乖離していく自分が許せない、というより、『取り返しがつかない』という感じに近いのだと思います」と述べています。
最後に、人生はひたすら目的に沿って結びつづけるものではなく、結んだり開いたりを繰り返すものだと思ってほしいという著者は、「結んだり開いたりすることがコミュニケーションでもあるし、何かと向き合うことだと思うのです。だから人は、死に対しても、結んだり開いたりを繰り返しながら近づいていくしかない。それはつまり、死ぬ直前でも人は笑うことができる、ということでしょう。実際そうなんです。開けば渾沌に触れ、孤独も繋がり、やがて笑いも起こって、華厳の世界も見えてくる。そうなってほしいと、切に願います」と述べるのでした。本書は、コロナ禍や戦争の問題からはじまり、現代人の自殺の問題まで広く、深く考察した素晴らしい対話集でした。1人でも多くの人、特に人生に悩んでいる若い人に読んでほしい名著です。