- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2333 宗教・精神世界 『新版 まわりみち極楽論』 玄侑宗久著 (KKロングセラーズ)
2024.06.07
『新版 まわりみち極楽論』玄侑宗久著(KKロングセラーズ)をご紹介いたします。もともとは2003年にオリジナル版が刊行され、2022年に新版が刊行されています。芥川賞作家として、また臨済宗僧侶として著名な著者が、常識的な「幸福観」にしばられず、柔らかな発想で前向きに人生をとらえ、日々を「安楽に暮らす」心の持ちようを教えてくれます。混迷を極める現代社会で心悩み、不安を抱える私たちに生きる糧を与えてくれる本です。
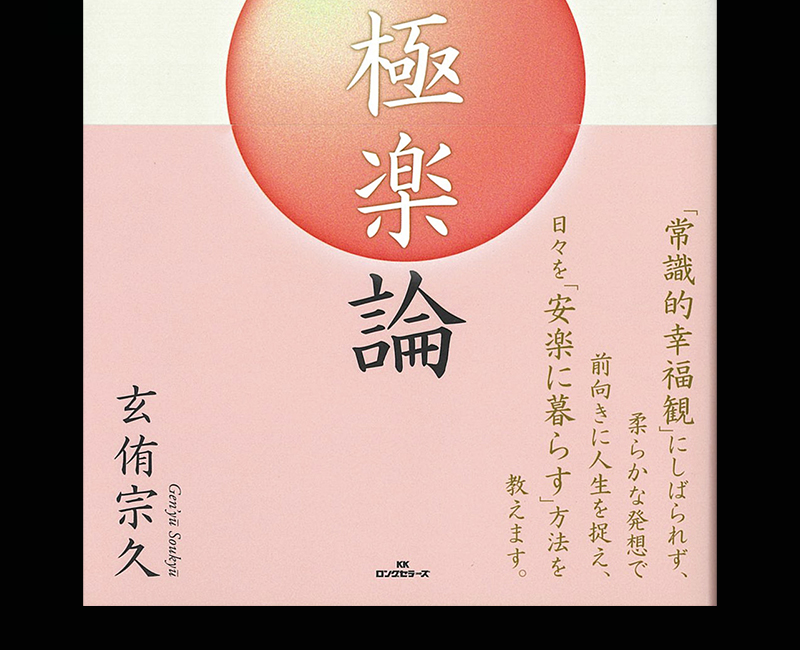 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「『常識的幸福感』にしばられず、柔らかな発想で前向きに人生を捉え、日々を『安楽に暮らす』方法を教えます」と書かれています。また帯の裏には、「べつに特定の宗教を勧めるわけではないし、特定の学問を紹介したいわけでもない。ただ自分自身の人生観を解体してみると、かくのごとき無節操でツギハギだらけの内実が明らかになったのである。読者諸賢には、こうした要素の気に入ったものを、さらに解体して適宜拾い、実用に供していただければ嬉しい。実用というのは、むろん前向きに人生をとらえ、日々をできるかぎり『安楽』に暮らすための糧である――本文より」と書かれています。
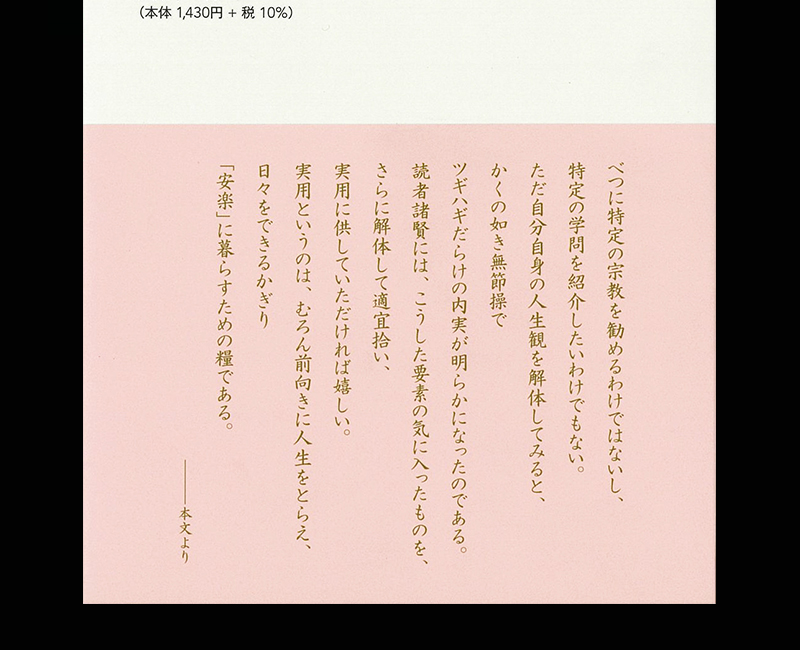
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「新版のための『まえがき』」
1 人間関係に悩んだら……
2 ウソについて……
3 自分自身と向き合う……
4 体は言葉に従うというセオリー……
5 二者択一で迷ったら……
6 反省することより輝くことが大切……
7 聴くことの功徳……
8 笑いの力――桃的人生とは?……
9 働きながら疲れをとってしまう日本人……
10 神さま仏さま……
11 「死」について……
12 時間に救われるということ……
13 「泣く」ということ……
14 男と女の間……
15 子供と大人……
16 老いてから生まれる輝き……
17 幸と不幸……
18 ご縁……
19 生きていく意味……
1「人間関係に悩んだら……」の「相手ではなく、自分の記憶を憎んでる」では、「人間」、人の間というくらいですから、その時々の間柄でいろんな自分が出てくることが指摘されます。しかも知っている相手の場合はこれまでの出来事の記憶が蓄積されてますから、普段憎らしいと思ってる人に遭うとその記憶が甦ります。考えようによっては、人はその人を憎んでいるのではなくて、その人に関する自分の記憶を憎んでいるわけです。著者は、「今日は別に何も嫌なことしていない。今日はまだいい人なのに、過去の記憶の延長上にしかその人を見ることができない」と述べています。
日本人の挨拶で「こんにちは」っていうのがあります。これはすごく意味深長だといいます。たとえば「グッド モーニング」とか「グーテン ターク」とか言う場合は、「今日は」である必要はないわけわけです。つまり「今日も」佳い朝、佳い日であることを祈っているわけです。著者は、「しかし私たちが言うのは『こんにちも』ではない。『こんにちは』なんですね。この挨拶は、昨日までの過去はともかく、と言ってますよね。過去は忘れて、今、仕切りなおしましょう、って挨拶してるんです。極端に言えば、『今日こそは』っていう意味あいですね。今まで生きてきた永い時間の記憶から解放されて、ニュートラル(思い込みのない真っ白な状態)に戻りましょう、っていうのが日本人の挨拶なんですね」と述べます。
著者によれば、蓄積された記憶の印象がわたしたちの最も深い意識である「アーラヤ(阿頼耶)識」に薫習されていくといいます。つまりあらゆる経験の移り香、残り香が染みついていくということです。それは唯識によれば完全に払拭できるものではないようです。しかし、わたしたちは、普段そんなに深い意識で生きているわけではないので、日常的なレベルではけっこうコントロールできると思うとして、著者は「敷居の前でお辞儀するというのもそう。それまで持ってたイライラとか腹立ちの感情を、敷居の前で一旦捨てて、それから客に対しましょう、ってことですね」と述べます。
二次的な感情というのはつまり、愛とか憎しみです。これは他人と会ってすぐに芽生えるものではなくて、どちらかと言えば一次感情を坩堝に入れて煮詰めたようなものだといいます。ここでは記憶の蓄積が大いに働いてきます。さまざまな情報を、ある意味で「物語」に作り替えていくわけです。この「物語」というものが、人間関係だけではなくて、自分というものを確認する上でもとても重要な言葉だといいます。少なくとも著者、そう考えているとして、「人は『物語』によって幸とか不幸を紡ぎだしているんじゃないでしょうか。じつは苦というのも、そうなんですね」と述べるのでした。
3「自分自身と向き合う」の「無意識に『物語』を作っている私たち」では、結局人間は、誰しも自分が歩んだ道を肯定したいということが確認されます。人は自分にも他人にも一貫性を求めています。その一貫性を保証するように作られるある種の器が「物語」なのです。「『分かる』は断面が見えたに過ぎない」では、「物語」がないと、自分も他人も把握することができないというのは確かであるといいます。だから全体ではないと知りつつも人は何らかの「物語」によって自分や他人を掴まえようとします。別な言葉で言えば、それは「分かる」ということです。「分かる」というのは「分けた」結果、断面が見えた、ということです。だから飽くまでも切り口が違えば違った姿が見えるはずです。著者は、「そのことを深く認識した上で、人はいろんなことに向き合うべきだろうと思います」と述べます。
「自分を変えるんじゃなく、新しいことを始めよう」では、東洋では、「志」というものを設定して心を不自由にし、そして無指向性の心に方向付けをすることが指摘されます。「こころざし」というのは心を刺して不自由にするのか、あるいは心の指す方向を指定することなのか、いずれにしても本来の心を少し不自由にしてやることです。著者は、「不思議なことに、人間はある程度の不自由のなかでしか自由というものを感じないらしいんですね。仮面もあったほうが生きやすいのでしょう。方向性だけ意志的に定めて、しかも新しいことにどんどん挑戦していく。それだけでいいんです。だからまあ、志の持ち方ですね、問題は」と述べるのでした。
4「体は言葉に従うというセオリー」の「体に潜む、言葉への信仰」では、わたしたちはもしかすると体の奥深くに、すでに表現されてしまったあらゆる「言葉への信仰」めいたものを持っている可能性を指摘します。あるいは「合理性への信仰」として、著者は「体が受けたことを合理化するために言葉が探されますし、逆に言葉を吐いてしまうとそれを実現すべく体が変化してきます。妙な喩えかもしれませんが、この両者の関係はお年寄りと杖みたいなものかもしれません。どちらも独りでは立っていられないから支え合ってるのです」と述べています。
「お経は人を、どこに導くのか?」では、言葉の意味、あるいはロジック(論理)が体をある状態に誘導するということについて述べた後、言葉には意味だけではなくて音もあるということを指摘します。意味に関係なく音がもってる力というのもあるといいます。たとえば「南無阿弥陀仏」。何度も繰り返してると「ナンマイダブ」とか言いやすい音に変化しますけど、これを何度も何度も繰り返してると、不思議なことに「分かりました。受け容れましょう」という気分になってくるといいます。そうかと思うと日蓮「南無妙法蓮華経」の場合は、「ナンミョーホーレンゲキョウ」を繰り返していると、これはまた全然別な気分になってくる。「誰がなんと言おうと、私はやるもんね」という気分になるというのです。著者は、「その分析はうまくできませんが、インドにはそうした音の持つ力に着目する考え方があったんですね。空海さんの真言宗の真言ですね。インドではマントラと言ったわけですが、言葉の音や響きそのものに力が宿ると考えたわけです。詳しく学びたいという方には空海さんの『声字実相義』という本があります」と述べています。
5「二者択一で迷ったら」の「二者択一という方法」では、中国の『荘子』という本に、「両行」という言葉があることが紹介されます。ふたつながら行われる。その場合は矛盾するふたつですが、たぶんそうした矛盾を抱え込んで渾沌としてるのが人生なのであり、しかもその渾沌がエネルギーを生んでいくといいます。著者は、「ちょっと難しいですけど、例えば生と死は反対の概念ですけど、死を抱え込むことで生は充実するのかもしれないですよね。だから嫌だと思うことも、たぶんある程度は生きていくエネルギーを生むのに必要なんじゃないでしょうか?私たちの社会には知らないうちに儒教的な規範が忍び込んでますから、どうしても『一途』が褒められる。それに普通は、そのほうが楽ですよね。1つに絞ったほうが」と述べます。
創造性(クリエイティヴィティー)を発揮することは大切ですが、著者は「人間関係にそんなに創造性を使ってたら、ほかに廻せなくなりますよね。そういう問題じゃないでしょうか? おそらく二者択二という道は、男女関係に限らず、非常にエネルギーを使うでしょうし創造性を刺激するはずです。ただ問題は、生活のどの部分にそういう方法論を採り入れるか、でしょう。『択一』という生き方が『正しさ』とか『美しさ』をめざしているのに対し、『択二』や『択三』はおそらく『楽しさ』をめざしている」と述べています。これは非常に説得力があると思いました。
7「聴くことの功徳」の「聴くとは、同じヴィジョンを共有すること」では、相手の声を聴くことにかけて模範的なのは、わたしたちの体内の臓器であるといいます。五臓六腑がお互いに相手の声に耳を傾けています。脳だって連動していますし、手足だって、みんな自分の正しさなんて主張しません。ただ冷静に相手の様子を見て聞いて、完璧に対応しています。著者は、「まさに響きあってる。同じヴィジョンを持とうとするとだんだん相手と響きあうようになるんですね。全身が響きあうのが健康というものでしょうし、相手と響きあうのがコミュニケーションでしょう」と述べます。
8「笑いの力――桃的人生とは?」の「無邪気さが笑いにつながる」では、中国では『詩経』で「桃の夭夭たる」と詠われていることが紹介されます。ここでは一点の陰りもない少女の生命力が桃に喩えて称えられます。大きい実、茂った葉、そういう様子をしたこの少女が嫁ぐ先は、きっと宜しかろうと詠うのです。著者は、「やはりどうも、生き生きとした生命力、思わず染まってしまうような無邪気さの象徴なんですね。鬼が来たときに鬼で対抗したんでは戦争になるしかないわけですが、鬼の邪気を奪ってしまうのが、桃の無邪気なんです。じっさい私の修行していた天龍寺の屋根の上には、鬼瓦だけじゃなく桃の実を象った瓦があるんです。この考え方には道教が色濃く影響しています。道教では不老長寿を得ることのできる桃というのがありましたし。桃太郎というのもやはりその思想の延長でできたんじゃないでしょうか」と述べています。
9「働きながら疲れをとってしまう日本人」の「労働も極楽のひとつ?」では、おそらくは総務省による発表によれば、日本人は今現在、一生のあいだに21万時間の余暇があるといいます。幼稚園から大学まで進んだとして、学校にいる時間のトータルがだいたい2万時間です。それから学校を卒業して、何かの職業につくわけですが、どんな職業でも一人前になるまでに最大で2万時間かかるそうです。著者は、「つまりお医者さんでも坊さんでも、なんかの職人さん、畳屋さんでも建具屋さんでも2万時間あれば一丁前になるわけですね。21万時間の余暇というのは、もちろん食事時間とか睡眠時間とか、誰でも必要な時間は除いてありますから、純粋に何をしてもいい時間です。だからその余暇を利用すれば、人は誰でも10種類くらいの職業のプロになれる計算になりますよね」と述べています。
ストレス指数というのがありますが、配偶者の死をストレス100として、さまざまなストレスが測定されて表になっています。著者はそれを見て驚いたそうです。なんと「温泉の2泊目」というのがその表にランクインしていたのです。日本人にとっては、温泉に一泊するくらいはストレス解消になるわけですが、二泊目はすでにストレスになっているわけです。著者は、「古来日本人はどうやってストレスを解消したのか? どうやって疲れをとってきたんでしょう? 祭なんですね。準備やら片づけ、あるいは練習とかもあって却って忙しくなるのが祭ですが、この祭をすることで日本人はリフレッシュしてきたんだと思います」と述べます。
「日常をほどいてくれる祭の力」では、著者は「祭では短い時間に集中的にエネルギーを使います。御神輿かつぐのもそうですよね。大声だして。これは体のこととして考えると、脱力するためにわざわざ全身に力を込めるという方法なんです。それで限界まで力んだあとには以前よりずっと脱力します。まあ、気持ちのほうもあるでしょうね。普段は自分や家族のために動いているのに、その日は神様や仏様のために動くわけですから。なんのためにしているのか、ちょっと考えただけじゃ解らない。そういう時に人は遊べるんですね。純粋な遊戯ですから疲れもとれるはずです」と述べています。
「人助けも観音さまにとっては遊び」では、日本人は、いろんな種類の仕事をして疲れをとることもできると指摘します。たとえば著者の場合、原稿を書くのも仕事、お経あげるのも卒塔婆書くのも仕事といえば仕事ですが、これがうまくお互い助け合っているといるとして、「つまり、小説を書くのが疲れないとは言いませんが、小説を書いた疲れはお経あげてとる。お葬式をした疲れはエッセイ書いてとる。エッセイ書いた疲れは草むしりでほぐす、草むしりで疲れたらまた小説を書くという理想的循環になってるわけですよ。考えてみれば心臓とか肝臓とかって働きっぱなしじゃないですか。彼らをどうしたら心地よくしてあげられるか、と考えると、必ずしも休暇をとったら効果的とは言えませんよね。それはつまり、仕事をどれだけ遊びとしてエンジョイしてるかにもよるんでしょうね。仕事が肝臓や心臓に悪いというなら休めばいいわけですけど、そうじゃない人も日本には多勢いるはずです」と述べるのでした。
10「神さま仏さま」の「『お蔭様』と呼ぶ理由」では、20世紀初頭に活躍したアインシュタインはこの世界を考えるパラダイム(軌範)を変更させるほどの業績を残したことが紹介されます。そのバリバリの科学者である彼が、「神はいると思いますか?」と訊かれ「この世のなかをつぶさに見て、これほどの調和が、なにか計り知れない偉大な存在なしに実現しているとは思えない」と答えたそうです。しかし彼ら物理学者たちは、ゴッドという表現を避けて、Something Greatと言います。「この偉大なる何者か」を、人によって地域によって、神と呼び、仏と呼んでいると思っていいでしょう。あるいは老子の「タオ」も荘子の「渾沌」や「真」もそうでしょう。もっと言えば、ギリシャの哲学者であるプロティノスの言う「一者」あるいは「かのもの」、サンスクリットの「タタータ」、その訳語としての「真如」、またイスラム哲学でいわれる「ウジュード(存在)」というのもそうでしょう。プロティノスの言葉を借りれば、「強いてなんとか仮の名をつけるために、やむをえず『一者』と呼んでおく」ということになります。仏教ではこれらを全部含めて「仮名(けみょう)」と呼んでいます。
科学としての因果律は確かにあるとしながらも、しかしそれは決して人間に見届けられるものではないとして、著者は「今のこの行為がどのように結果するのか、それが私の目の前で起きるとは限りませんし、私が生きている間に起きるのかどうかも分からない。だから私たちが感じることもできないし、直接見ることもできない因果律のことを、私たちは『お陰さま』と呼んで尊重するわけです。『冥福』というのもそうですね。冥福とはよく見えない福ですが、供養した結果を我々は確かめることができない。でもきっと、なにかいいことが起こってくれるんじゃないか、そう思って『冥福』を祈るわけです。ある意味で、神とか仏というのは、そうした遠大な因果律を統率している存在なんでしょうね」と述べます。
11「『死』について」の「『死』とは、ほどけること?」では、日本では死者も「ほどけた」状態ではないかというのでいつのまにか「仏」と呼ぶようになったと指摘します。仏教では死のことを「四大分離」と言います。四大というのは地・水・火・風という4つの働き、つまり骨とか爪とかの堅さを作る地大、血液・リンパ液というような液体の性質を司る水大、体温や熱をあらしめている火大、手足や心臓のように動く働きを司る風大の4つです。これが縁によって集まることが誕生であり、縁がほどけて四大が分離することを「死」と考えます。「ほどける」という言葉は、仏教的な死を実にうまく表現していたわけです。
考えてみれば仏教は初めから火葬です。世界で火葬という埋葬法を採っているのはヒンドゥー教と仏教ですが、日本には仏教の流入とともに火葬が入ってきたわけです。火葬を考えてみると、死を四大分離と規定したことが理解できます。なぜなら、煙になって四散していくのですから。そして四大は分離して「空」に帰ります。著者は、「とにかく仏教における死は、ほどけて空に帰っていくことであり、『帰る』という表現からも解るように、元々の状態に戻ることなんですね。私たち僧侶は亡くなった人の位牌の一番上に『新帰元』とか『新帰空』、あるいは『新帰真』などと書きます。新たに元に、あるいは空や真に、帰ったという意味ですね」と述べます。
「魂はあるか?」では、中国では死者の世界は「鬼」という言葉で表されることが紹介されます。その世界、つまり幽冥界は、山の上にあったり、丑寅の方角、北東から入っていくと考えられたり、いろいろですが、とにかく暗くて冷たい世界だということになっています。丑寅が鬼門という幽冥界の入口なので、鬼という生き物に姿を与え、牛の角を生やし虎の皮のパンツを穿かせたのは日本人の仕業です。そういう冷暗たる幽冥界を前提にして生み出されたのが「お盆」という行事です。つまり暗くて冷たい世界にご先祖様がいらっしゃるから、此の世に戻ってくるのが楽しかろうと思ったわけです。ところがその後、浄土教の発生とともに極楽というのが発生します。著者は、「本当は極楽ができちゃうと先祖が此の世に戻ってくる必然性はなくなるんですね。だけど、その戻ってくるという話はそのまま残された」と述べます。
「たましい」というのはやはり何か球形のものだろうと、著者は推測します。「たま」ですから。そういうものがあらゆる山川草木に宿っていると、古代の日本人は考えていたようです。そしてそれは勿論人間にもあるとして、著者は「言葉にも『ことだま』が宿っていたりする。この『たま』はどうも出たり入ったりもするようですね。びっくりしたりすると『たま』がどこに行ったか分からなくなる。それを『たまきえる』つまり『たまげる』と言ったわけです。人間は現在、実に多くの物を創造できるようになり、かなり複雑な結晶体も作ることができます。しかし、今のところまだそれに生命を吹き込むことはできないでいます。37兆もの細胞を有機的に動かす力の源になっているエネルギー、それを『たましい』と呼んでも私は別に構わないと思いますよ」と述べます。
「臨死体験が教えてくれること」では、浄土教は中国で曇鸞や善導などがいわゆる臨死体験をすることで成立してきたヴィジョンであると指摘しています。そのあたりは京都大学のカール・ベッカー氏が『死の体験』という本の中で詳しく検証しています。そういう意味では、中国にはすでに5世紀から臨死体験の記録があるわけですが、そうした実際の体験報告をもとに、著者は『アミターバ』という小説を書きました。同作では「臨死体験」だけでなく、臨死を超えた「死後体験」が生き生きと描写されています。自身の葬儀の場面なども故人が詳しく観察し、報告しており、これはもう前代未聞ではないでしょうか。それも、「闘病」「死ぬ瞬間」「死後の世界」といったように区切って書かれているわけではありません。主人公の意識は変化を遂げつつも、あくまで1人の人間としての思いや考えや体験がそのまま連続して語られているのです。人が死んでから葬儀が行われるまでの様子を死者の側から描く前代未聞の小説であり、一読すれば誰でも葬儀の必要性を痛感するでしょう。
「埋葬法と輪廻のこと」では、死後を「無」と捉えたのは、最近では共産主義の人々であると指摘します「宗教は阿片」と言われてあらゆる宗教が憎まれたわけですが、彼らは死後の世界を宗教のでっちあげと解釈し、主にキリスト教系の宗教の天国入りを待つ肉体を、火葬してしまおうとしたのです。1963年にカソリックは火葬を認めてしまいますが、本来は土葬にしていたわけです。ですから最近共産主義から解放された国では本来の土葬がどんどん復活してきています。世界的には土葬が増えているわけです。日本みたいに95パーセント以上が自主的に、しかも宗教に関係なく火葬にするなんていう国は世界中に皆無です。しかし本来は、宗教によって埋葬法は全て決まっているとして、著者は「イスラム教は土葬。キリスト教も土葬。神道も土葬。統一教会も土葬ですね。古代ゲルマン民族は火葬で、ギリシャ・ローマでは火葬も土葬も両方あったみたいですが、それもキリスト教が国教になると土葬になってしまいます。ですから共産主義が火葬を強制したのはある種の宗教弾圧だったわけです。でも日本人は、土葬にするのは田舎、みたいな認識で唯々諾々とどんどん火葬になっています」と説明します。
初めて火葬が行なわれたのは奈良の元興寺というお寺でしたが、まるでオウム真理教の所行を非難するように、その残酷な埋葬法を群衆が取り囲んで大騒ぎしたといいます。著者は、「そりゃあ残酷に見えるんじゃないですか、初めて火葬を見れば。しかもインドでは『輪廻』という考え方一般的ですから、死んでもしばらくするとまた新しい体をもてます。それが人間である保証はありませんが、とにかく遺体はもう要らないわけですから、燃やしても抵抗はなかったわけです。ところがこの『輪廻』という考え方は、中国を無事通過できなかった。簡単に言ってしまえば、中国というのは先祖を大切にする国ですから、同じく生命の連続を重視するといっても人間だけの流れなんですね」と述べています。
遺体を焼くことに抵抗がなくなったのは、浄土教が出てきてからだといいます。阿弥陀仏を信じれば、極楽に往生できるというわけですから。仏教にはいろんな宗派がありますが、死後のヴィジョンに関して浄土教を超えるものはないのではないかとして、著者は「禅宗のお葬式でも、結局阿弥陀仏に登場していただかないと収まりがつかないんです。阿弥陀仏というのはサンスクリットの『アミターユス』とか『アミターバ』からできた言葉ですが、前者は『無量寿』、後者は『無量光』と中国で訳されました。死後、人は純粋な光になる、なんてチベットでも考えられていますが、まあ光にせよ命にせよ、それが無量だという考え方が示されました。死によって終わらないわけです。だから心おきなく焼けるんですね」と述べます。
「死とはどのポイントなのか?」では、平安時代などは人の死に立ち会っているのは医師ではなく、僧侶だったことが紹介されます。貴族や皇族などは死が近づいたと認識すると黒い衣装に着替えて「涅槃堂」と呼ばれる建物に入ります。そして僧侶が陪席していわゆる現在でいうターミナルケアにあたる対応があったわけです。恵心僧都源信という比叡山の僧侶などは「二十五三昧会」というケア・グループを組織したほどです。著者は、「まあそういう人々に囲まれて、阿弥陀如来の指に結ばれた五色の糸を握りしめて、その時を待ったわけです。これは完全な告知による死と言えます。亡くなると、僧侶はお経はあげるでしょうけど、まもなく帰っちゃうんです。そしてその後は葬送人といわれる人々に任される。つまり、当時、亡くなったという判断をしたのは僧侶だったと思うんです」と述べるのでした。
12「時間に救われるということ」の「人間にとって最大で最後の煩悩=時間」では、わたしたちが意識する「時間」というものは、仏教的に言うとすでに自己愛の元になる潜在意識、「マナ識」が勝手に作り上げた文脈に沿って括ったものであると指摘します。著者はこれを、人間の最大で最後の煩悩だと思っているそうです。最後の、というのは、死の間際までなくならない、という意味だといいます。ということはつまり、死の直前にはこの煩悩からも解放されるのではないかと考えているわけです。著者は、「言ってみれば私たちは、常に『たった今の気分』という色眼鏡で過去も現在も未来も見ている。その色眼鏡が変わるんですから、なにもかも変わらないはずがありません。『たった今の気分』が極楽になれば、色眼鏡も素通しの透明になるはずなんですが、それが難しいからせめて好きな色の眼鏡で見直すことを勧めたいだけです」と述べます。
13「『泣く』ということ」の「鳴くが真か、鳴かぬが実か?」では、泣くという行為は、なんらかの意味で天からの恵みではないかと述べられています。むろん医学で云う「蒸泄」行為、つまり水分を排出していることも確かですが、それだけではなくて何か言葉にできないものが通る気がするとして、著者は「人間は『泣く』と『笑う』に分かれちゃいましたけど、やはり両方大事にするべきじゃないですか? 泣くも笑うも鳥なんかには全て囀りなんですし。共に自然な生命力の発露と考えれば、それが出ていくことで入ってくるものが大いにあるような気がします。泣くことも笑うことも、じつに活発なエネルギーの動きですよね」と述べるのでした。
14「男と女の間」の「戒律と結婚の意味」では、世界の仏教徒の中では日本の僧侶だけが妻帯するわけですが、これはかなり説明が難しいといいます。著者は、「どういうきっかけで、と訊かれたら親鸞聖人にでも答えてもらいたいですが、その結果どうなったのか、ということについては私の師匠がこんなことを言ってくださいました。『大乗仏教が最もソフィスティケイトされた姿だろう』って。つまり衆生の悩みに対応するのが我々僧侶だとするなら、とても大きな苦悩を生みだす結婚生活に対しても、してみなきゃ応じられないだろって。そういう意味だと受け止めましたね、私は。実際、全く別な育ち方をして別な考え方をもった人間が一緒にやっていくわけですから大変ですよ。しかし、物理学の相補性でも中国の陰陽でもそうですけど、違う者どうしだからこそエネルギーが生まれるんじゃないでしょうか?」と述べています。
15「子供と大人」の「子供性を含みながら歳を重ねて深くなる」では、孔子は50で天命を知って、60で「耳順」と言ったことが紹介されます。著者は、「60になるとどんな意見も「ああ、なるほどね」と言って理解でき、腹も立たないというんですから、これは一応完成形なんでしょうね。じゃあそのあとどうなるのかっていうと、70は『心の欲する所に従って距を踰えず』。これは一見『中庸』が実現されたか見えるんですが、どうもそれよりエネルギーの自然退縮を感じますね。孔子さんは74歳で亡くなりますから、それも無理はないかと思いますが、なんとなく孔子さんの晩年の不遇を感じさせますね。私としては、人間は加齢に伴って、老子の言うように『回帰』するという考え方が好きです。老子はある意味で子供の柔弱さを理想にしていますが、これは仏教が、確立した自己を逃げ水のような一時的な姿、つまり『虚仮』なるものとして乗り越えていくのと通底しています」と述べています。
「脱皮する豊かさ……東洋的大人」では、これは親にも子供にも言えることですが、最近はいわゆる成長過程での通過儀礼というのが重視されないことが指摘されます。このことで、人は生まれ変わるチャンスを持てなくなっているのではないかとして、著者は「釈尊の、瞑想による意識や心の変容の体験はそうそう簡単に味わえるものじゃない。だから現実の私たちは、解脱なんて程遠いわけです。しかしそんな私たちを外側から変化に導いてくれるのが、通過儀礼だと思うんです。たとえば昔の『元服』、それが済めば一人前として親の名代を務めた。しかもその際は幼名を改めて別な名前になった。これは生まれ変わりですよね。周囲がそう仕向けてくれたから本人も大きく変化できた」と述べるのでした。わたしが著者の意見に全面的に賛成なのは言うまでもありません。
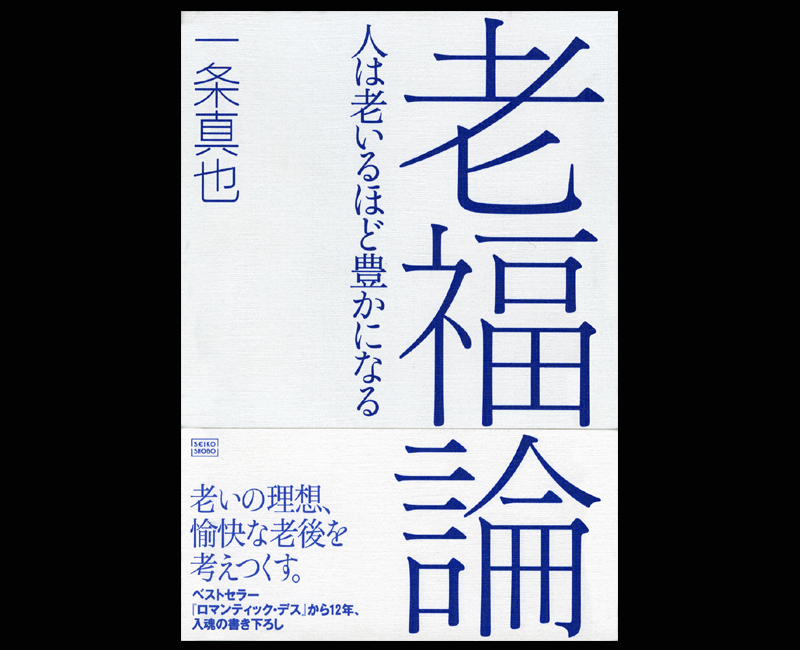 『老福論』(成甲書房)
『老福論』(成甲書房)
16「老いてから生まれる輝き」の「向上しつづける判断力」では、人は生まれて子供から大人になり、やがて老いて病んで死ぬことが取り上げられます。お釈迦さまはこの「生・老・病・死」の4つ全てを苦しみとされました。老・病・死が苦しみなのは分かりますが、どうして生まれることも苦しみなのか。これは輪廻の考え方が背景にあります。つまり生まれるというのは前回の生で卒業できなかった「業=カルマ」を背負っての誕生なのです。一方、日本には昔から、「翁」という思想があります。これこそ円満な智慧と優しさを具現化した象徴的な人格ではないかといいます。翁はいわば最も神に近い、清らかでしかも慈悲深い存在です。著者は、「だから歳をとるほど極楽に近くなるというのは、ふつう言われる意味じゃなく、老年の輝きのことだと思いますよ」と述べるのでした。このあたりの考え方は、「翁」の思想を含めて、拙著『老福論〜人は老いるほど豊かになる』(成甲書房)にも詳しく書かれています。
19「生きていく意味」の「宇宙そのものが持った意識」では、わたしたちの中には宇宙そのものが凝縮されて入っているという考え方が紹介されます。『華厳経』の中には「一即一切」「一切即一」という考え方が非常に色濃く出てくるのですが、要するにわたしたち自身の中に一切、ですから宇宙そのものも含まれているということです。体の中の元素のことを考えてもそうですよね。わたしたちの中のナトリウムもカリウムも、この地球でできたものではありません。地球くらいの圧力や温度ではできないのです。では、なぜに生命が地球上に現れたのか、このことから、多くの神話は語りだしますし、宗教にとっても大きなテーマでした。著者は、「それは、偶然とは思えなかったからでしょうね。しかも宇宙という存在が、初めて自分を認識したのは私たち人間の意識を通してだった。このことの意味はとても大きいと思います。いわば宇宙が持った初めての自分の眼が人間の眼だったわけですし、宇宙の耳は人間の耳、宇宙の口は人間の口なんです」と述べます。
むろん人間の他にも、優れた生命体はいるはずだと考える人々はいますし、実際そうなのかもしれません。しかし、著者は「それはそれとして、私たちが宇宙を意識する存在であることに変わりはないのです」と述べます。また、「自己意識という煩悩」では、人間は宇宙を意識ででますが、わたしたち人間はじつはそれだけではなくて、「自己」という意識をはっきり持ったほぼ最初の生き物であることが指摘されます。自己意識を司っているのは「前頭連合野」といわれる脳の一部で、霊長類にも少しありますが、人間において特徴的に発達したと考えられているのです。著者は、「宇宙を意識するのはいいのですが、この自己意識が、じつは宇宙と直結するのを妨げてるような気がするんです」と述べています。
「エネルギーの流れに乗って生きる」では、「頑張る」つまり「我を張る」のとは逆に、お任せしていいといいます。著者は、「暗在系のエネルギーそのものの向かう方向に任せればいい。きっと極楽は、その先というか、そのエネルギーの流れに乗った時に現れる世界じゃないでしょうか」と述べます。また、「自力と他力の現在形」では、自力というのは「はからい」の世界、有為の世界であることが指摘されます。他力というのは「はからいのない」無為の世界のことです。著者は、「だからどんな宗派も、まず自力から入るしかないわけですが、やがて他力に気づいて身を任せるようになるのだと思います。念仏だって最初は自力で称えるんですから。極楽浄土は他力の専売特許みたいに思っているかもしれませんが、やっぱりそこへ行くには、自力と他力と両方必要だということですね」と述べています。
「『頓悟漸修』答えはすでに存在している、あとは気づくだけ」では、釈迦は意識の変容を促す瞑想こそ涅槃に到る道であるとして、それを勧めることが紹介されています。そして釈迦は「瞑想によって体験する以上のことは、死後にも起こらない」とまで言い切ります。ですから著者は、「宇宙の始まりのことも終わりのことも、死後についても今の意識レベルで思い悩んでも答えは出ないと思ってください。やがて意識が変容することがあって、自然に体験するかもしれませんよ。あえて『生きていく意味』は何か、ともう一度訊かれれば、私としては大いなる命の流れに身を任せながら、無常を楽しむことだと申し上げたいですね。無常なるものの中でも、とりわけ自己意識の変容です」と述べています。
自己意識というのも、一度変化すれば全てが分かるというようなものではありません。何度も何度も、あるとき不意にそれは起こるといいます。これを「頓悟(とんご)」と言いますが、わたしたちはその悟りでどんな現実も乗り切っていけるわけではありませんから、また困難にぶつかったら宇宙意識に沿って努力するのです。全てを「ご縁」と受けとめる努力といってもいいでしょう。これが「漸修(ぜんしゅう)」です。言ってみれば、この「漸修」という努力があるからこそ「頓悟」もあるとして、著者は「結局のところ、私たちの人生は『頓悟漸修(とんごぜんしゅう)』なのだと思います。今、答えが出ない問題を抱えているからといって、性急にそれを求めなくていいんです」と述べるのでした。
日本人は素敵だと思った表現は『聖書』からだって貪欲に採り入れています。儒教や道教だったらもっともっとあるわけですが、著者は「どんな宗教や思想からでも、自分にとって必要な極楽の材料はいただけるでしょう。トータルに宗教どうしを比較して優劣を決めるのではなくて、いろんな考え方から幅広く安楽を頂戴するんです。そしてそういう廻り道の過程そのものが人生だし、廻り道だと余裕をもって思っているほうが頓悟の機会は増えるような気がします」と述べます。そして、「最終的に辿り着くところは極めつきの安楽、『極楽』だと信じてください。その上で、散策を楽しむように、今自分の足許に見えている道を歩いていくしかない。道端の景色を楽しむように、医学でも生物学でも物理学でも天文学でも、あるいは仏教、キリスト教、イスラム教、なんでも齧ればいい。みんな自分が極楽に辿りつくための考え方の宝庫です」と述べるのでした。本書は、一読して心が軽くなる、日本人のための素晴らしい幸福論です。