- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2336 評伝・自伝 『妖怪少年の日々 アラマタ自伝』 荒俣宏著(角川書店)
2024.07.17
『妖怪少年の日々 アラマタ自伝』荒俣宏著(角川書店)を読みました。著者は、1947年東京生まれ。作家・博物学者。1985年に執筆を開始した『帝都物語』は、500万部を超える大ベストセラーに。膨大な知識を駆使してジャンルを超えた文筆活動を展開、テレビでも活躍中。
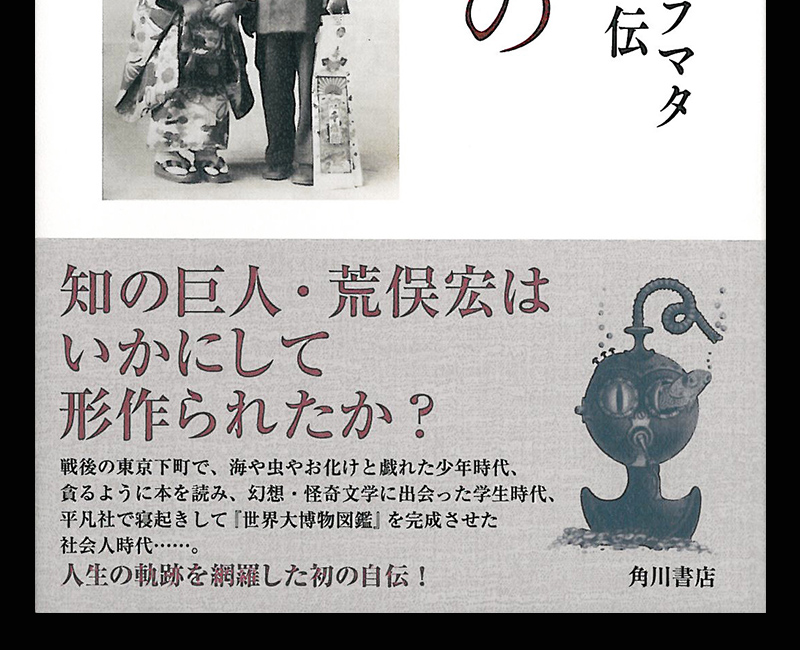 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、幼少期の著者と妹が一緒に写った七五三の写真が使われ、帯には「知の巨人・荒俣宏はいかにして形作られたか?」「戦後の東京下町で、海や虫やお化けと戯れた少年時代、貪るように本を読み、幻想・怪奇文学に出会った学生時代、平凡社で寝起きして『世界大博物図鑑』を完成させた社会人時代……。人生の軌跡を網羅した初の自伝!」と書かれています。
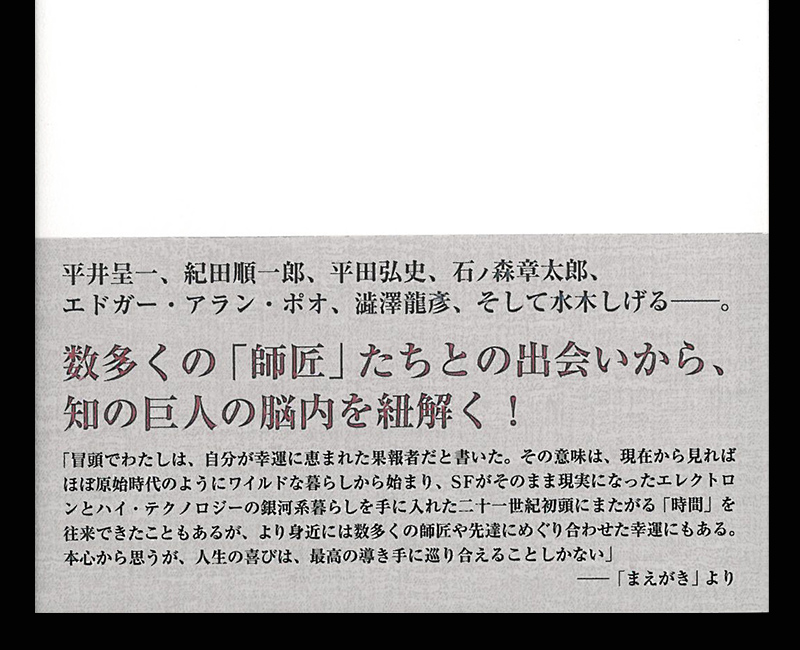 本書の帯の裏
本書の帯の裏
「平井呈一、紀田順一郎、平田弘史、石ノ森章太郎、エドガー・アラン・ポオ、澁澤龍彦、そして水木しげる――。数多くの『師匠』たちとの出会いから、知の巨人の脳内を紐解く!」「冒頭でわたしは、自分が幸運に恵まれた果報者だと書いた。その意味は、現在から見ればほぼ原始時代のようにワイルドな暮らしから始まり、SFがそのまま現実になったエレクトロンとハイ・テクノロジーの銀河系暮らしを手に入れた二十一世紀初頭にまたがる『時間』を往来できたこともあるが、より身近には数多くの師匠や先達にめぐり合わせた幸運にもある。本心から思うが、人生の喜びは、最高の導き手に巡り合えることしかない――『まえがき』より」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
第一章 下谷の幼児、「神隠し」に遭う
第二章 板橋で「狸の国」に迷い込んだ
第三章 昔話への疑問と死の習俗
第四章 学校図書館で「怪奇実話」に出会う
第五章 「師匠」が多すぎて
第六章 文体と実体のあいだ
第七章 「大学」行って、働いて
第八章 もとめよ、さらば見出さん「人の生涯」
第九章 「驚異の旅」としての世界旅行
第十章 晩年に青年期と再会す
第十一章 理科室の解剖台で
リュウグウノツカイと妖怪が出会う
付録「妖怪と生命のミュージアム」誕生する
第二章「板橋で『狸の国』に迷い込んだ」の「両親のことを今になって知る」では、大正から平成まで波乱万丈の人生を送った著者の実母が96歳で逝去したとき、3人兄弟の長兄である著者が弟や妹に相談して、「最期の霊送りくらいは三人揃うことにしよう」と申しあわせたエピソードを披露します。まずは恰幅のよかった母親を精いっぱいきれいにしようということになり、納棺師の方に頼んで死化粧を念入りにしてもらったそうです。そうしたら驚くほど若々しい姿になったとか。著者は、「死んだ後の自分の姿がどうなるか気にしていた母だったが、急死のおかげで窶れがなかった。化粧した顔が楽しげに見えた。わたしたちはお別れのときに、『ミッちゃん、お疲れさま、あっぱれな一生でした』と褒めた。考えてみたら、これまで子どもがそろって母を褒めたことがなかった」と書いています。
「怪談噺を聞かされる」では、著者が怪談や幻想文学にのめり込んだエピソードが明かされます。それは小学生の時からでしたが、高校生になって盛んに読んだのが小泉八雲でした。翻訳家として有名な平井呈一が恒文社という出版社から刊行することになった『小泉八雲作品集』の影響ですが、著者は「八雲がじつは昆虫好き、さらに海好きで夜光虫が好きだったということも、平井先生を通じて知った。とりわけ蛍を題材にしたエッセイに感動した。この話を題材にして『蛍火』という少女漫画を描きだしたのも、高校時代である」と述べています。
「狸が開いた『お化けの国』」では、さまざまな狸映画に言及して、「タヌキ妖怪がなぜ阿波踊りと結びついて爆発的な人気を誇ったか、すこし真剣に書いておく必要がある」と述べます。それをひとことでいえば、妖怪狸と人間界のあいだに共存共栄関係が成立したからであるといいます。著者は、「『七変化狸御殿』の最終場面、月の砂漠の王子様さながらの幻想衣装で登場する高田浩吉らに見送られ、狸のお花が若殿さま(これも高田浩吉が演じた)のお城に興入れするというシンデレラストーリーの結びに、こんなナレーションが入る『でもこれは人間世界の話ではございません。狸の森の物語なのです』と」と述べます。
これぞ幸福な「化かし」の本質だったと指摘し、著者は「辛い戦後生活が一瞬のうちにファンタジーの国に変わる、この化かしこそが、たぬきの本領だった。わたしは生まれながらにして化かされることに快感を覚える子供だったが、多くの大人も『こうした狸ミュージカル』を観ることで、化かされて幸せになる喜びを知ったはずだ。つまり、戦時中から戦後の昭和30年代にかけて、日本人は狸に化かされることで現実と対峙する力をもらっていたのだ」と述べるのでした。
第三章「昔話への疑問と死の習俗」の「本当は『納得』がいかないおとぎ話」では、著者が今もって怖いと感じているおとぎ話の代表は『ハメルンの笛吹き』であると述べます。著者は、「読んだ絵本の挿絵までも覚えている。これはまことに不思議な話で、基本はどこかの正体不明の男が笛を吹いて子どもを誘拐した、という『人さらい』の話だ、と理解した。でも、この笛吹きは魔法の笛を持っているところが、ただの人さらい事件と違う。『笛吹童子』の話も頭にあったせいか、何か途轍もない謎を宿した『異人』に思えた。とりわけ、まだらの道化衣装を着けた笛吹が、町からネズミを一掃した笛の音をもって、子どもまでも森に連れ込んでしまう場面がおそろしかった。いったい、この笛吹きは何者なのか。これがまた、実際に横行していた人さらへの恐怖と重なって、ただひたすらに恐ろしかった」と述べています。
それから『桃太郎』も『酒呑童子』も、なんだか後味が悪かったといいます。なぜなら、鬼がいつも退治されるからです。著者は、「鬼はどうしていつも退治される側に回されるのか。『カチカチ山』も納得がいかなかった。だまして泥船に乗せ、沈めてしまうからだった。そうした『奇妙に納得がいかない』おとぎ話の中に、『瓜子姫とあまんじゃく』という変な話しも入っていた。このあまんじゃく、すなわち天邪鬼になんとも説明のつかない興味を抱いていた。こうして絵本という新たなメディアが、納得のいかない物語の裏を考えるという、子供にあるまじき変態的な楽しみを教えてくれたのだった。突っ込みどころが多い化け物だとか忍術だとか、あるいは宇宙などに興味を持った原因も、ここにあったと思う」と述べます。
また、著者が少年時代を過ごした板橋の大山駅前商店街がlowな文化の殿堂であり、古本屋が少なくとも4軒あったと報告されています。著者は、「父が生まれたばかりの弟をおんぶして大山にパチンコ通いする行き帰りだったから、おそらく昭和29年か30年のころ、わたしはここの古本屋で光文社版の『少年探偵団』シリーズや学童社版『ジャングル大帝』を発見、古本屋通いの味をしめた。とくに『ジャングル大帝』や山川惣治の『少年ケニヤ』は思い出が深い。動物がすきだったせいもあるが。わたしがここ板橋在住の時期を『黄金時代』と呼ぶのは、そういうわけなのである。後年掘り下げることとなる文化的主題のすべては、ここで遭遇したのだった」と述べます。
「墓の謎――なぜ墓場は寺にあるのか」では、「お墓はなぜお寺にあるのか」という疑問お取り上げます。これは逆にいうと、なぜ神社に墓がないのか、ということになります。おかげでたいへんに重要な事実が、あとで分かったといいます。それは「死は穢れである」と、日本の人たちが考えていたことを知ったからです。この穢れという発想は、仏教の不浄という感覚とも少し違うと指摘し、著者は「最大の違いは、穢れは死の世界に触れるところにある。死の世界に落ちた死者が幽霊となって現れた場合、幽霊は穢れを有する。したがって、幽霊と睦めば、命までが汚れる。穢れの語源はおそらく命の源である気(き、け)が枯れるという意味だったのだと思う。だから死の世界であるあの世は畏れられた。この呪縛を破って、死の世界は黄泉なる汚れた場所でなく、この世と並行して存在する幽冥界だと言い放ったのが平田篤胤だった。だから、穢れを嫌う神社は清浄を何よりも好むのである」と述べています。
「お露さんに同情する理由」では、死は「穢れ」をもたらし、もしこれを地上に残せば地上が穢れることを指摘します。したがって、墓地は穢れた死体の「地下保存所」であり、穢れを払うのが職務である神社では、墓地を作らないという理屈があるとして、著者は「そうなると、穢れた世界でも人々を教導できる仏教が、お墓の面倒を看るしかなくなるだろう。もちろん、死者の一種である亡霊も、穢れた存在であるから、地上に迷って出た幽霊を家に招き入れるなどはもってのほかだ。新三郎恋しさに『牡丹燈籠』のお露さんが毎晩通ってくるなどという話も、本来なら純愛ロマンなのだが、相手が幽霊だという理屈で、この世が穢れるから愛を交わしてはいけない、という結末になる。それでお露は、かわいそうに、霊験あるお札を貼った室内に逃げ込んだ新三郎と逢瀬ができなくなるのだ。お化け差別もまた、この『穢れ』なる究極の呪文によって生まれた習俗といえる」と述べています。
死女の愛を受け入れてやらなかった新三郎を非難する心情はよく分かると、著者は言います。八雲の随想を読んだとき、じつにすっきりした気持ちになれたとして、著者は「わたしが小学生以来抱いてきた『お化けはなぜ嫌われるか』という疑問に、答えが出たように思えたからだ。そう、わたしはここで、『お化けを愛せる』理論的裏づけを受け取ったといっていい」と述べます。また、「お墓には死者があふれている」では、このあたりからお化けやらオカルトやらの虜になったという著者は、テレビが一般家庭に普及したころには、『空想科学劇場』『ヒッチコック劇場』『世にも不思議な物語』、そして会社の倒産でテレビに解禁されたユニヴァーサルの旧作ホラー映画などに、深夜までかじりつく少年になっていたことを告白するのでした。
第四章「学校図書館で『怪奇実話』に出会う」の「化け物と異常な事象に惹かれる」では、ハリウッド映画の話題作『大アマゾンの半魚人』の思い出が述べられます。1954年の製作ですので、著者が実際に観たのは7歳頃だといいます。著者は、「あのクリーチャー造形は、笑える部分もあったが、水中から水着美女を襲うシーンにはぴったりくる淫獣らしさがあった。したがって、子どもでもゾクゾクした」と回想しています。しかもこの映画の製作はユニヴァーサルでした。戦前にロン・チェニー主演の『オペラの怪人』、ベラ・ルゴシ主演の『魔人ドラキュラ』、そしてボリス・カーロフ主演の『フランケンシュタイン』を公開して怪物映画のブームを築き上げた会社です。
ユニヴァーサルが戦後にぶつけた新たなモンスターが、アマゾンの半魚人でした。その前後に日本映画界も負けじと怪物映画を製作しました。東宝からは『ゴジラ』、大映からは『宇宙人東京に現わる』などが登場。しかし著者は生きもの好きでもあったから、アクアラングを発明したジャック・イヴ・クストーの『沈黙の世界』や、ディズニーがつくった自然記録映画『砂漠は生きている』にも熱中したといいます。馬も食い尽くしてしまうピラニアが初めて登場したのは、『緑の魔境』という、アマゾン川の情景を撮影した映画でした。おかげで、著者は魔境探検に憧れたそうです。
アメリカのTV番組も初期から観ることができました。著者が最も興奮した番組といえば、ターザン役者ジョニー・ワイズミュラーが主演した魔境探検ドラマ『ジャングル・ジム』、今でもいくつかの話のあらすじを覚えている画期的なSFドラマ『空想科学劇場』、そしてこれまた怪奇幻想の小説世界を視覚化した傑作『ヒッチコック劇場』でした。著者は、「このラインナップが昭和30年代に日本で鑑賞できたことは、SFとホラーが氾濫する現在のメディア環境に比べても、一歩も引けをとるまい。ひょっとすると、番組の質は昔のほうが高かったかもしれない」と述べています。
「『信じようと信じまいと』vs.『動物妖怪譚』」では、戦後すぐに怪奇ノンフィクションの著作を刊行しだした作家は、なんらか別の分野で地位を築いた人物であることが多いことが指摘されます。庄司浅水は印刷業界に身を置いていましたし、黒沼健は戦前に推理小説の創作と翻訳で名を成していました。黒沼の場合は、祖父と父が経済界の名士であり、本人も東大の法学科を出ています。翻訳家として推理小説の原書に親しむ中で、SFやミステリー・ノンフィクションへと関心を広めたようです。神智学やUFO問題にも深い関心を寄せる先駆者でもありました。
著者が最も印象に残っているのは、H・P・ラヴクラフトがまだ日本でほとんど関心を抱かれなかった時代に、この怪奇小説作家に関する噂を書いた記事を発表したこと(黒沼健著『謎と怪奇物語』新潮社刊、1957)でした。著者は、「一日じゅう暗い自室に閉じこもり、ろうそくをともして恐ろしい異次元の恐怖を描いたラヴクラフトが、ある日行方不明となり、どうやら宇宙人に拉致されたらしいという内容だった。ネタ元は当時のゴシップ雑誌などだったのではないかと推察できるが、これはラヴクラフトに触れた最初期の日本語記事ではないだろうか」と述べます。
第五章「『師匠』が多すぎて」の「ポオから贈られた新しい宇宙観」では、著者がポオから受け取った最大の恩恵に言及しています。それは、ポオの壮大な哲学随想『ユリイカ』の影響です。著者は、「ポオが没した後から近代心霊学(スピリチュアリズム)が勃興して、霊界との交信可能性が喧伝されると、心霊エネルギーなり情報なりをこの世に伝達する媒質が仮想されるようになってきた。そこで、科学者サイドにも波動と仮定できる光を媒介するのに媒質が必要だとの発想が生まれた。しかもこの空間は、霊魂のような非エネルギー的で質量が増えたり減ったりせず、しかも瞬時にどこへでも伝わる性質を持っているに違いない、と考えられた。じつは宮沢賢治が宇宙や銀河鉄道の空間をイメージしたときのアイデアは、この仮想的なエーテル空間だったのである。ポオの『ユリイカ』は、宮沢賢治が描こうとした宇宙的童話の本質に迫ろうとした「科学的想像力」の限界だったといっていい。そういうなんだか途方もない現象を扱った自由詩に、中学生の魂は燃え上がったのだった」と述べます。
それから現在までのトンデモ本を含めた著者の読書は、ポオの「ユリイカ」を理解すための回りくどい作業となったそうです。著者は、「そう考えなければ、なぜ貧乏な中学生がアタナシウス・キルヒャーだのロバート・フラッドだのといった『ルネサンス期最後の宇宙論学者』の筆になる、古めかしい、ラテン語でつづられた読解不能のフォリオ本を、高級車なんかすぐに買えるような高い金を払って購入したのか、その理由が付かないではないか」と述べます。また、この『ユリイカ』が縁となり、著者は『僕の“ユリーカ”』というポオに倣って現代宇宙論を執筆した稲垣足穂を知り、ここから足穂が愛読したアイルランドの幻想作家ロード・ダンセイニを知り、さらに足穂とダンセイニ両方の線から、編集工学研究所を主催する松岡正剛を知ることとなるのでした。
「もう一人、忘れてやしませんか、ってんだ!」では、澁澤龍彦の『夢の宇宙誌』が取り上げられます。著者は、「一読して、まさしく自分が渇望していたタイプの本であることが分かった。とくに『異端』という言葉が新鮮だった。ながらくカトリックが支配してきたフランスの文壇を相手にしてきた人の感覚なのか、英米文学ではあまり使われない言葉なのだ。しかも、この異質な文化がヨーロッパ近代には知られざる別種の美学を生みだしていたことも分かった。しびれたのは、『マニエリスム』という用語だった。悪魔と怪物がものすごくとり憑いていそうなゴシック教会を連想した」と述べています。ちなみに、わたしも澁澤の『夢の宇宙誌』には夢中になり、その強い影響のもとに『遊びの神話』(東急エージェンシー)を書きました。
 『遊びの神話』(東急エージェンシー)
『遊びの神話』(東急エージェンシー)
また、澁澤龍彦について、著者はこう述べます。
「すでに澁澤には、プリニウスやルドルフ2世、解剖学者ドン・ヴェサリウスやアンブロワズ・パレら博物学に連なる偉人への言及があったので、もしかしたら博物学への興味も、澁澤の影響だったかもしれない。だが、そんなことはまだどうでもよかった。決定的にわたしをしびれさせた話題は、なんといってもオカルティズムだった。悪魔学や魔術、さもなくば怪物学や天使学と呼んでもいい。今でも、『夢の宇宙誌』をひもとくと、心が騒ぐのが愛おしい。目次のラインナップは、本当にただ事ではなかった。まず、『玩具について』の章には、『ホムンクルスについて』『怪物について』『貝殻について』と見出しが続く」と述べます。
澁澤ワールドの虜になり果てたという著者は、「黒魔術はのちに『世界恐怖小説全集』で平井呈一先生が訳出したデニス・ホイートリーの『黒魔団』からイニシエーションを受けたが、神秘学としてのオカルティズムは、澁澤龍彦の血筋から伝えられたと思っている。慶應大学に入学してから、この血筋はさらにシュタイナー研究を開始されて高橋巌先生の薫陶を受けることで濃くなった。わたしは澁澤龍彦さんに直接お目にかかったことはない。たとえお目にかかったとしても、単なるミーハーの賛辞以上のことを語れなかったし、寺山修司さんや麿赤兒さんと先に出会った関係で、澁澤さんの独特な生活や美学も印象が薄かったからかもしれない。しかし手紙はやりとりしたことがある。また、アングラ仲間からよく噂は聞いていたし、澁澤さんの書くものが大好きだった関係で、親しみはあった」と述べています。
一度、博物図鑑のことで澁澤から著者に問い合わせもあったそうです。そうこうしているうちに著者は『世界大博物図鑑』全5巻という大きな仕事に着手し、第1回配本の『鳥類篇』を刊行するにあたって、澁澤に一部を献本せずにいられなかったことを明かし、著者は「きっと、博物誌のことなら澁澤さんと話ができる、直接の知り合いになる資格ができた、と思ったからだろう。これが昭和62年5月のことである。すると思いがけず、澁澤さんから葉書をいただいた。ベッドの横に置いて楽しく読んでいる、という文章だった。最初で最後の交信だったが、これで澁澤さんともつながりができたと大喜びした。その澁澤龍彥が亡くなったのは、葉書をもらってから3か月後、昭和62年8月だった。わたしは、これから本格化しようとしていた博物学復興の得がたい師匠を、永久に失ってしまった」と述べています。澁澤龍彦と荒俣宏の邂逅は幻と終わりましたが、2人の対談をぜひ読んでみたかったですね。
第七章「『大学』行って、働いて」の「妖怪は『モノ』から『ムシ』に変わった!」では、かつて自然界には目に見えぬものが存在すると信じられたことに言及します。著者は、「見えないが、人にも自然物にも人工物にもとり憑ける。とり憑くと人語を話し、禍をもたらす。病気や災難のおおもとは、どうもコイツにとり憑かれるのが原因らしい、と古代の賢者は結論した。そして、眼に見えない恐ろしいそやつを、『モノ』と呼んだ。正体不明だから、『モノ thing』というしかない。スティーブン・キングなら、『イット it』、J・K・ローリングなら『名を言ってはならないあのお方』とでも呼んだことだろう。でも、こいつらは人語を解し、人の秘密を暴露する!」と述べます。
この「物の怪」による怪異現象が実際に存在する島があるといいます。かつて日本移民が暮らし、大本教が布教活動したポナペ島です。そこには「オニ」と呼ばれる憑き物がいて、宿主が恨みを抱いた相手はオニにとり憑かれ、人前でとつぜん、自分の罪状を告白してしまうという話を紹介し、著者は「不倫したとか、金をだまし取ったといった罪状を近隣の人が知り、とり憑かれた本人を村八分にする。自分の悪事が虫の告発によって露見することは、村社会にとっては一番恐ろしいことだった。わたしは実際にポナペで呪術師からその話を聞いた。そして、これこそ『ムシ』の祟りの根源的原理だという事実を知った」と述べています。
第九章「『驚異の旅』としての世界旅行」の「『ワンダー』の誕生」では、ワンダーという心の機能は、西洋でも古くから関心を持たれていたとして、著者は「それは信仰心とも少し近い関係なので、スコラ派の研究家すらも解明に取り組んでいた。アリストテレスは、『ワンダーというのは人の目と心を引き付ける力だ』と述べている。これだけだと、何か磁石のような物理的な力に見えるので、ロジャー・ベーコンの説を引こう。ベーコンは、『ワンダーには歓びがある。それも、未知のものにぶつかるときでなく、未知のものの正体が理解できたときに初めて発生する』と。これで少し分かった。ワクワクと嬉しくなることが、ワンダーの要素なのだ」と述べています。
続いて、魔術にも造詣が深かったアルベルトゥス・マグヌスの「ワンダーなるものに対したとき、無知ゆえに恐れおののけば迷信的信条となり、知ることに夢中になれば好奇心となる」という言葉も紹介されます。ゴシック小説の金字塔である『オトラント城奇譚』の著者であるウォルポールがゴシック的美術や文学にもとめたことも、まさにこのマグヌスの理論だったのだろうと推測し、著者は「怖いだけなら昔ながらの怪談だが、ここに好奇心という積極姿勢が加わることで、怖かったものがおもしろくてたまらなくなる。そして決定打は、あのトマス・アクィナスの考え方だった。アクィナス曰く、『ワンダーに接したときは、キリストや神でさえも、びっくり驚く!』」と述べます。
第十章「晩年に青年期と再会す」の「『他人任せの挑戦』??」では、著者の代表作である『帝都物語』が映画化されたときの話が書かれています。自分が何か映画作りにかかわることになるとは夢にも思えなかったという著者でしたが、そんなあり得ないことが、1988年というから昭和でいえば63年に、ほんとうに起きてしまいました。その年の1月、『帝都物語』が映画になったのです。著者は、「小説家の立場で言えば、かぎりなく興味深い世界創造のチャンスが与えられたことになるわけだが、わたしには別の感慨があった。子どもの頃、舞台の上で寝転がりながら観た映画館が、壮年になって帰ってきたような気がしたのである。最初は文字で創造されたものが、今度は全知覚を刺激する映画として再創造される。映画は一つの巨大な『全感覚の開放空間』と言える。それも、恐ろしく費用が掛かる創造を、自分が引いた設計図を元に、自己負担することなく実現できる。作家なら一度は体験したい、他人任せの挑戦と言えた。『他人任せの挑戦』?? そう、映画というビッグプロジェクトは、創造が一人でなく集団によって実現される世界なのである」と述べるのでした。
第十一章「理科室の解剖台でリュウグウノツカイと妖怪が出会う」の「推理小説の『下戸』」では、著者が膨大な蔵書を処分したことに言及します。著者は、「幸か不幸か、作家なんて仕事は、結局のところ頭脳がわりの本があればなんとかなるようにできている……と思ったところが、肝心の本もこのタイミングでみんな売り払ったことを忘れていた。それでも、今回の断捨離にはいいこともあった。2年間にわたって蔵書を処分する中で、忘れかけていた発見をあらためて思い出す「最後の機会」に恵まれたからだ。そこに運よく、平井呈一先生の年表を編むという仕事も重なったので、自分の人生を蔵書の処分という形でまるっと回顧する結果にもなった。紀田順一郎先生が一足先に蔵書を処分され、『蔵書一代』に書かれたことも刺激になった。わたしは諦めがよいから、蔵書を手放すことに紀田先生ほどの感慨はなかったが、人生を過ごす上での大黒柱が本であったこと、そしてその本は平井先生の導きで自然に溜まったもの、ということを身に染みて味わった」と述べています。
最後に、『吸血鬼ドラキュラ』や『黒魔団』をはじめ、日本における怪奇小説の偉大な紹介者であった平井呈一との思い出が語られ、著者は「わたしは平井先生と文通を始めたころ、こわいもの知らずにも程があって、『お化けとか超自然現象とかいうもんは、いずれ真相が解明され、存在しないことがはっきりします。そのとき、怪奇幻想小説も絶滅するでしょう』と、書き送ったことがある。正岡子規ら明治人が、17文字の組み合わせにはやがて数学的に限界が来て、新しい旬の生まれる余地がなくなるのじゃないかと杞憂したようなことを、考えたのだ。そのとき平井先生は『大いに研究なさい。それにはたくさん読むことです。ただし、私は怪奇小説はなくならないと信じています』という、激励とも悪戯ともとれる返事をくださった」と述べています。
わたしは、この平井呈一の「私は怪奇小説はなくならないと信じています」という言葉に深い感銘を受けました。一条真也の読書館『葬式不滅』で紹介した本は、2022年8月6日に亡くなられた作家の青木新門さんの「葬儀は絶対になくなりませんよ」という言葉に拠っています。一条真也の読書館『納棺夫日記』の著者として知られる青木さんにお会いした日の最後に、青木さんは「葬儀は絶対になくなりませんよ」と言われました。「『葬式は、要らない』じゃなくて、『葬式は、なくならない』ですよ」とも言われました。そのときの青木新門さんの言葉が、『葬式不滅』のタイトルには込められています。そして、その青木さんの言葉が「私は怪奇小説はなくならないと信じています」という平井呈一の言葉と重なったのです。まさに「怪奇小説不滅」ですが、著者の荒俣宏氏は「わたしはその御言葉に励まされたのかだまされたのか、知らぬうちに半世紀ものあいだ、幻想怪奇の世界を歩き回った。それが自然の神秘世界だったのか、あるいは脳内の異世界だったか判然としないが、少なくとも焼け跡や墓場ではなかったような気がしている」と述べるのでした。わたしは著者の本をほとんど全部読んでいる大ファンですが、「知の巨人」「幻想文学の案内人」のルーツを垣間見ることができて、非常に満足しました。