- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2346 宗教・精神世界 『ごまかさない仏教』 佐々木閑・宮﨑哲弥著(新潮選書)
2024.08.20
『ごまかさない仏教』佐々木閑・宮﨑哲弥著(新潮選書)を読みました。「仏・法・僧から問い直す」というサブタイトルがついています。共著者の佐々木氏は、1956年福井県生まれ。花園大学文学部仏教学科教授。京都大学工学部工業化学科および文学部哲学科仏教学専攻卒業。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学。カリフォルニア大学大学院留学を経て、現職。文学博士。専門は仏教哲学、古代インド仏教学、仏教史。著書多数。もう1人の宮﨑氏は、1962年福岡県生まれ。慶應義塾大学文学部社会学科卒業。テレビ、ラジオ、雑誌などで、政治哲学、生命倫理、仏教論、サブカルチャー分析を主軸とした評論活動を行う。著書多数。
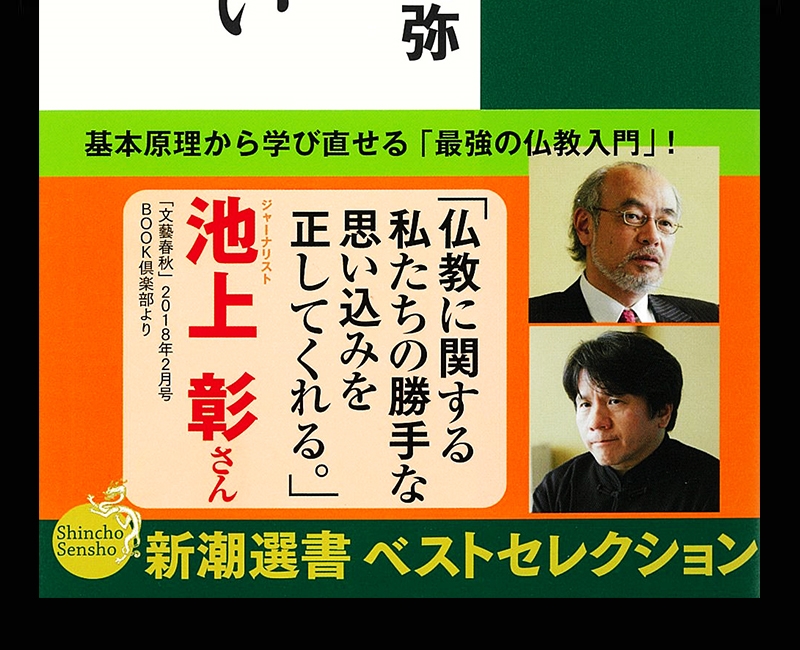 本書の帯
本書の帯
本書のカバーには佐々木氏と宮﨑氏の顔写真が使われ、「基本原理から学び直せる『最強の仏教入門』!」というコピーが踊っています。また、「文藝春秋」2018年2月号の「BOOKクラブ」より「仏教に関する私たちの勝手な思い込みを正してくれる」というジャーナリストの池上彰氏の言葉が紹介されています。
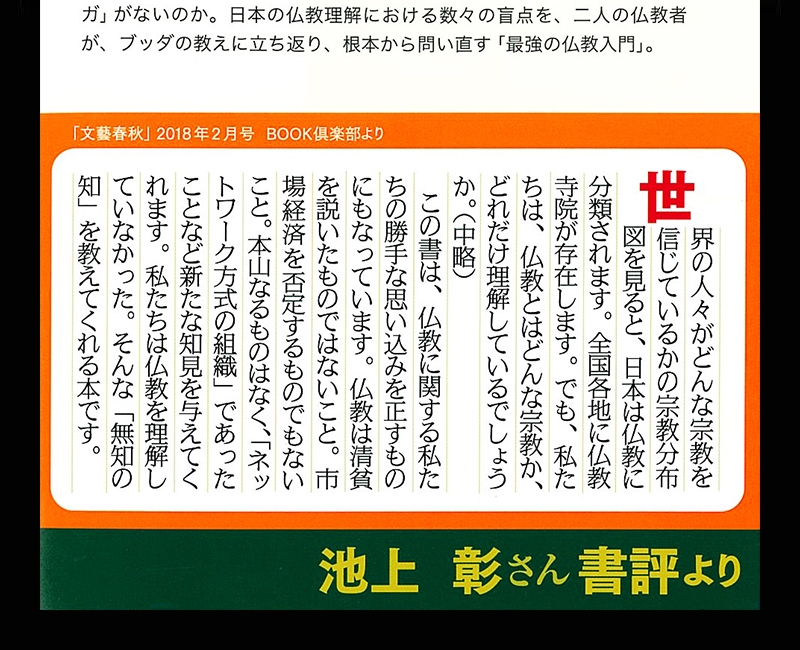 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には池上彰氏の書評より、「世界の人々がどんな宗教を信じているかの宗教分布図を見ると、日本は仏教に分類されます。全国各地に仏教寺院が存在します。でも、私たちは、仏教とはどんな宗教か、どれだけ理解しているでしょうか。(中略)この書は、仏教に関する私たちの勝手な思い込みを正すものにもなっています。仏教は清貧を説いたものではないこと。市場経済を否定するものでもないこと。本山なるものはなく、『ネットワーク方式の組織』であったことなど新たな知見を与えてくれます。私たちは仏教を理解していなかった。そんな『無知の知』を教えてくれる本です」という言葉が紹介されています。
さらに、カバー裏表紙には「基本原理から学び直せる『最強の仏教入門』!」として、「どのお経が『正典』なのか? 『梵天勧請』はなぜ決定的瞬間なのか? 釈迦が悟ったのは本当に『十二支縁起』なのか? 『無我』と『輪廻』はなぜ両立するのか? 日本仏教にはなぜ『サンガ』がないのか? 日本の仏教理解における数々の盲点を、二人の仏教者が、ブッダの教えに立ち返り、根本から問い直す『最強の仏教入門」』と書かれています。
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
はじめに――宮﨑哲弥
序章 仏教とは何か
第一章 仏――ブッダとは何者か
第二章 法――釈迦の真意はどこにあるのか
仏教の基本OS
1.縁起
2.苦
3.無我
4.無常
第三章 僧――ブッダはいかに教団を運営したか
おわりに――佐々木閑
序章「仏教とは何か」の「仏教の不思議」の冒頭で、宮崎氏は「仏教は、いわゆる一般的な『宗教』という枠組みで捉えるよりも、『自己と世界の関係』を根本的に組み替えるための『思考―実践の体系』だと考えた方が、その本質をより把握しやすいと思います」と述べています。一方、佐々木氏は「まずは『三宝』、つまり『仏・法・僧』という三つの要素を受け入れよ、というのが仏教ですから、そこには普通の人が受け入れがたいような、超自然的な要素はほとんどありません。その意味では、きわめて敷居の低い宗教だと言えるでしょう」と述べます。
この三宝、すなわち「仏・法・僧」はサンスクリット語で「トリラトナ」と言います。「三種の財宝」という意味です。三宝という言葉自体は、聖徳太子の十七条憲法の「篤く三宝を敬え」にも登場し、日本人にもよく知られていますが、佐々木氏は「この三宝こそが仏教の定義です。『仏・法・僧』、この三つの要素がそろった宗教活動のことを仏教と呼びます。この定義は日本だけではなく、あらゆる仏教界に共通して通用する唯一の定義です」と述べています。
では、「仏・法・僧」とは具体的には何のことか。簡単に言えば、「仏」(ブッダ)とは「釈迦」のことです。すなわち釈迦という人物を自分たちの生きる拠り所として信頼するということであるとして、佐々木氏は「後の大乗仏教になれば、この『仏』が釈迦以外の創作上のブッダを指すということになってブレが生じてくるのですが、本来の意味で『仏』とは釈迦のことです。それから『法』(ダンマ)とは釈迦が説いた『教え』のこと。釈迦の教えをベースとして自己の生活を組み立てていくということ」と述べます。
そして3番目の「僧」(サンガ)はいささか複雑ですが、これは1人1人のお坊さんのことを指すのではなく、4人以上の比丘(男性のお坊さん)、あるいは4人以上の比丘尼(女性のお坊さん)が集まってつくる修行の組織のことを意味します。佐々木氏は、「つまり『僧』というのは、個別の人間を指す言葉ではなくて、組織を指す言葉です。したがって、『仏・法・僧』という3つの要素が仏教を構成するということは、釈迦を信頼し、釈迦の教えに従って暮らすお坊さんたちが、修行組織を守りながら生きている状態を指します」と説明します。
「『正典』は何か」では、「仏教の聖典と言えば、やはり阿含・ニカーヤと呼ばれる初期経典である」と、佐々木氏は言います。たとえば、パーリ語で書かれたものなら長部・中部・相応部・増支部・小部の初期経典ですなぜかと言えば、この「パーリ五部」が数ある仏教経典の中で一番古いものだからです。古ければ古いほど釈迦の創ったオリジナルの仏教に近いと考えられます。ただし、釈迦の時代にはまだ文字が定着しておらず、教えは基本的にすべて口伝だったので、初期経典といえども「釈迦直伝のことば」とまでは言えません。
佐々木氏は、「そこは気を付ければなりませんが、まずは阿含・ニカーヤを起点と考えればいいでしょう」と述べます。しかし、宮崎氏は「私もそう思いますが、当然、大乗仏教の側から強い反発が起こるのは避けられないでしょうね(笑)。『般若経』『維摩経』『法華経』『華厳経』『浄土三部経』『大乗涅槃経』『解深密経』『大日経』などなどの大乗経典はどうなるのかと。それどころか大乗側はずっと阿含・ニカーヤ系の経典を軽視し続けてきました」と述べるのでした。
第一章「仏――ブッダとは何者か」の「釈迦はどうやって悟ったのか」では、釈迦が菩提樹の下で悟りを開いたというのはじつに象徴的であるとして、佐々木氏が「風通しの良い丘の、生い繁った菩提樹の木陰というのは、太陽の照射が厳しいインドではもっとも快適で安楽な場所でしょう。つまり苦行とは正反対に、なるべく肉体的な負荷を少なくし、ひたすら精神集中して自分の心に向き合うのが仏教なんだということです」と述べています。宮崎氏も、「釈迦は苦行ではなく瞑想によって悟りを得た」と言います。
「布施と托鉢の始まり」では、佐々木氏が「仏教は初めから都市宗教として出発したのです。人気のない山奥でひっそりと修行に専念する僧侶の姿を私たちはよくイメージしますがそういうことは実際にはありえないのです。仏教というのは、支えてくれる在家信者たちのそばにいなければ成り立たない宗教なのです」と言います。すると、宮崎氏が「近年、仏教はまるで清貧を説き、市場経済を否定するものであるかのごとき誤解が拡がっていますが、はっきりいって間違いです。そうではないからこそ、商業活動を営む人達が釈迦の教えに熱心に耳を傾け、そのうちの何人かは出家していった。バラモン教やヴェーダ(バラモン教の基本原理となる聖典)の権威に懐疑的で、よりプラグマティックで、相対主義的な宗教を求めていた人々だと思います」と言います。
この宮崎氏の発言を受けて、佐々木氏は「そうです。仏教の「人からもらったものだけで生きる」という方針は、一見、市場経済に反するものに思えますし、サンガをとても脆弱な基盤の上に置いてしまう気もしますが、歴史的事実として、仏教サンガは2500年も続いてきたわけです。実際、2500年も続いている組織というのは、他にはどこにもありません。それだけに、ここには釈迦の深い洞察が隠されていると考えるべきです。支援者に完全依存して組織を運営するという釈迦の敷いた路線が、どれほど強力なサステナビリティを持っているか、改めて注目する必要があるでしょう」と言うのでした。
「梵天勧請①――釈迦はエゴイストなのか」では、佐々木氏が「出家」と「世捨て」は違うと指摘し、「出家とは、俗世間で死ぬか生きるかの状態になってしまった人たちが、同じような価値観を持った者同士で身を寄せ合って作った行の世界へ入ること。出家の本当の意味は、言ってみれば『自殺する人を救う』ところにあるわけです」と言います。すると、宮崎氏は「裏を返すと『世間の流れ』あるいは『生の流れ』に乗って、滞りなく生きる、ということがどうしてもできない人間のための教えなんですよね。そういう生き方が虚妄に思えて仕方がない……。そんな原生的なズレ、疎外感、疎隔感に苛まれている者たちへの救済が仏教の第一義のような気がします。極言するなら、そういう者でなければ仏教は要らないのかもしれない」と述べ、佐々木氏は「私はいつもそう言ってます。仏教は心に苦しみを抱えていて、助けを求めてやってくる人たちを受け入れる『心の病院』だと言っています」と語るのでした。
 『慈経 自由訳』(現代書林)
『慈経 自由訳』(現代書林)
「梵天勧請②――釈迦はなぜ他人を救う決意をしたのか」では、佐々木氏は「最近はテーラワーダ仏教も大乗的な要素を取り入れるところが出てきて、たとえばスリランカなどでは在家出家の区別なく仏道修行が同じレベルで可能だということを主張する人もいるようです。そういった流れの一環として大乗菩薩的あり方が入っているのかも知れませんね。少なくとも『慈経』の教えには、釈迦の立場での慈悲の心が過不足なくきれいに表現されていると思われます」と述べています。この「慈経」ですが、わたしは自由訳して、『慈経 自由訳』(現代書林)を上梓しました。
「慈経」(メッタ・スッタ)は、仏教の開祖であるブッダの本心が最もシンプルに、そしてダイレクトに語られている、最古にして、最重要なお経です。上座仏教の根本経典であり、大乗仏教における「般若心経」にも比肩します。上座仏教はかつて、「小乗仏教」などと蔑称された時期がありました。しかし、上座部仏教の僧侶たちはブッダの教えを忠実に守り、厳しい修行に明け暮れてきました。「メッタ」とは、怒りのない状態を示し、つまるところ「慈しみ」という意味になります。「スッタ」とは、「たていと」「経」を表します。ブッダは8月の満月の夜に「慈経」を説いたと伝えられています。満月は、満たされた心のシンボルです。
「釈迦のお葬式は誰がやったのか」では、ブッダの葬儀が取り上げられます。ずっと在家の人々によって執り行われたというのが通説でしたが、近年、出家も関与していたという説も力を増してきています。グレゴリー・ショペンというアメリカの仏教学者が、釈迦の葬式に僧侶が関わっていたという説を唱えているのです。宮崎氏は、「インドや東南アジアの伝統教理では、出家者は葬式に主体的に関与してはならないとされています。経証(お経による裏付け)はやはりパーリ語の『大般涅槃経』で、アーナンダがブッダに『修行完成者(如来=ブッダ)の遺体をどのように扱えばよいか』を尋ねたところ、『アーナンダよ。お前たちは修行完成者の遺骨の供養(崇拝)にかかずらうな。どうか、お前たちは、正しい目的のために努力せよ。正しい目的を実行せよ。正しい目的に向って怠らず、勤め、専念しておれ』と戒めています。供養は在家に任せればよい、というわけです」と述べています。
ショペンの理解だと、この「かかずらうな」「関わってはならない」とする禁止の命令は出家者全員を対象としたものではなく、アーナンダにだけ発されたということになると指摘し、宮崎氏は「そういった推定も出てきたため、仏教は本来的にも僧侶が弔い儀式に関わることを否定していなかったという立場が脚光を浴びるようになった。『葬式仏教正当論』で名を馳せた鈴木隆泰氏はその急先鋒ですね」と述べています。一条真也の読書館『葬式仏教正当論』で紹介した仏教学者にして東京都日蓮宗善應院住職でもある鈴木氏は、インドの仏教原典に基づき従来の日本仏教批判を明解に論破しました。そこで、釈迦が葬式を禁じていたというのは完全な誤解であるということも明らかにしました。インドでは、不幸な誤解によって仏教が葬儀と関わらなかったため、仏教そのものが衰退しました。一方で、葬儀と深く関わったヒンドゥー教は隆盛を極めました。葬儀こそは宗教の核心であり、葬式仏教は正しい道なのです。
 『葬式不滅』(オリーブの木)
『葬式不滅』(オリーブの木)
釈迦の葬儀については佐々木氏にも独自の考えがあるそうで、「当時のインドでは、葬儀というのは生前その人と親交のあった人々が最後のお別れをするある種の感謝的儀礼であったと思われます。ですからショペンが言うように、釈迦の葬儀に仏弟子がかかわるということは、当然あっておかしくないことだと思います。しかし、それは釈迦とその弟子の間の関係で成り立つ葬儀なのであって、他人の葬儀に僧侶がかかわるという話とはまったく別次元のことです。ですから、たとえ仏弟子が釈迦の葬儀にかかわったとしても、だからと言って僧侶が人々の葬儀に積極的にかかわったということにはなりません。やはり出家者は葬式の主体として関与してはならないという考えは有効でしょう。そして重要なのは、葬儀やその後の遺骨崇拝といった行為は大きな世俗的果報が伴うという点です。だからこそ釈迦は自分の葬儀やその後の遺骨崇拝を在家者に委ね、彼らに大きな果報が来るように計らった。ここには在家者に対する釈迦の思いやりが現れているのです」と述べています。
第二章「法――釈迦の真意はどこにあるのか」の「仏教の基本OS」では、宮崎氏が「巷間、仏教と自然科学は親和性が高いなどといわれますね。世間がそう看做しているだけではなく、例えばダライ・ラマ14世なども欧米の科学者と対話して仏教の『心の科学』性をアピールしている。ダライ・ラマはさらに踏み込んで、アインシュタインの相対性理論や思考実験と龍樹の三時門破の議論とを類比的に論じたりもしています。また最近では瞑想の状態や悟りの境地を心理学や脳科学によって解明しようという試みが一部で出てきている」と言えば、佐々木氏が「だから、意外に理科系の人が仏教にハマったりする」と言い、さらに宮崎氏が「事実、大学では理学部や工学部で学んだ変わり種の仏教学者もいます。先に名前を挙げた鈴木隆泰氏がそうですね。東京大学工学部の精密機械工学科出身です」と述べています。
自然科学の場合は、観察に基づく仮説を設定、そして実験・証明といった人為的検証方法による仮説の承認、といった手順が繰り返されるところに特性がありますが、仏教にそういった方法は導入されていないと指摘し、佐々木氏は「科学の場合は、新たな情報が登場することで常に仮説は変更されてくのですが、そういった科学的方法を用いない仏教においては必然的に仮説が更新されていくという現象は起こりません。そういう点で仏教と近代科学を同一視することなどできません。両者の唯一の共通性は、そのベースとなる世界観、すなわち原因と結果の因果則に基づく機械的世界の中にわれわれがたまたま存在しているという世界観です」と述べます。
ダンマというと一応「法」という定訳がありますが、宮崎氏によれば「法」といっても憲法や法律などの実定法のことではないといいます。コンテキストによって「法則」と解するのが妥当だったり、「真理」と取るのが適切だったり、あるいは「存在の構成要素」を指す場合もあるといいます。「ここでは『釈迦の説いた教法』ぐらいに捉えておきましょう。では、その教えの最も基本的な要素とは何か?」と問う宮崎氏に対して、佐々木氏は「それは『縁起』『一切皆苦』『諸法無我』『諸行無常』の4つだと思います。この4つの概念は相互に深く絡まり合いながら、仏教の教えの中心を形成しています」と述べます。
佐々木氏の発言に対して、宮崎氏は「そうですね。この4つの項が相互に連関している。大乗仏教の、とくに中観派の立場からすると『空』や『無自性』も加えたくなりますが、『空』は『縁起』と、『無自性』は『無我』との近縁的な概念ですから、あえて別項として立てる必要はないでしょう。これらはいわば仏教の基本ソフト、OS(オペレーティング・システム)です。テーラワーダ仏教や大乗仏教、禅や浄土教、密教などとハードウェアが違っていても、このOSが揃って載っていれば一応仏教のかたちが整う。仏教を起動できる。さらにOSと連携した様々なアプリケーション・ソフトを使える。またアプリケーションを自分で開発もできる」と述べるのでした。
1「縁起」の「縁起とは何か」では、縁起をひと言で説明すれば、「この世界の物事はすべて原因と結果の関係で動いている」ということであるとして、佐々木氏は「他の宗教のように、絶対的な神様がいて、不可思議なパワーで世界を動かしたり、人々に何かを強制したりするとは考えない。すべては、原因となる何かがあって、その影響を受けたがゆえの結果として現れているという、ある意味で、とても合理的で科学的な世界観です。ただし本来的にそれはわれわれ生き物に限定する縁起則だったと思われます。物質世界をどう理解するかという問題は、仏教が本質的に関知するところではなかったからです。しかし、ずれにせよこの世界を因果則に基づいて見ていくという点で、縁起的世界観は仏教の動かしがたい土台です」と述べています。
一方の宮崎氏は、「仏教は、一切の事物を縁起的に生ずると捉えます。一定の条件によって生起し、その条件が解除されれば消滅する。その一定の条件もまた他の条件によって『在ら』しめられていて、もし他の条件が変滅すれば、それに従って変滅する。ですから、そこで認められるのは、存在というよりも仮構という語がふさわしい仮の存在性に過ぎない。自立し独存し永続するものは何もなく、また万物に変滅しない固有の本質などない。一言でいえば実体というものはない。私達の目に『在る』ようにみえてようにみえているものも実体として『在る』のではない、ということです。然るに『煩悩』に覆われた私達の目は、耳は、鼻は、舌は、触覚は、そして心はそのことを正しく把握できない……」と述べます。
それを聴いた佐々木氏は、「一口に煩悩と言っても、強欲とか傲慢とか嫉妬とか、いろいろなものがあるわけです。なかでも、釈迦が一番おおもととなる煩悩だと考えたのは『無明』です。無明とは智慧がないこと、つまり『愚か』ということです。それは単に知識がないとか学がないといった表層的な意味ではなく、物事を正しく合理的に見ようとする力が欠如している、本質的な暗愚を指しています。本質的な暗愚とは、すなわち縁起的世界を正しく見ることのできない愚かさです」と述べるのでした。
「四縁説の縁起観とは」のでは、「アビダルマの縁起論」というものが紹介されます。「所縁縁」の所縁というのは、わたしたちの6つの知覚器官、認識装置の対象となるものごとを指しています。6つの知覚器官というのは眼、耳、鼻、舌、身(=触覚器官)、意(=心)です。これらの器官によって、様々な対象と接触することにより、心中にいろいろな知覚、認識が生じる。そのような縁起を所縁縁というわけです。ざっくりいうと知覚や認識の対象が知覚や認識の働きを触発する、そういう関係を指します。佐々木氏は、「これは十二支縁起でいうところの『触』に近い。触というのは目や耳などの認識器官が、外界のいろ・かたちや音といった認識対象と接触し、それが私たちの心に特定の認識を生み出す。すなわち、認識器官と、対象と、認識そのものの接触という意味です」と述べ、宮崎氏は「これらの要素を全部まとめると、いわゆる多因多果的な四縁説が形成されるわけですね」と述べています。
「釈迦は輪廻を認めていたのか」では、宮崎氏が「佐々木さんは釈迦は当時のインド社会全体の通念である輪廻という世界観を受容れ、それを前提に教えを説いたとのお考えを示されていますが、他方で輪廻を『現代の私たちにそのまま認めろというのはムチャな話』で、またご自身も輪廻を信じていないと明言されています」と言うと、佐々木氏は「そうです。釈迦も輪廻については『好ましからざるものとしてではあるが、その存在を認めていた』というのが私の考えです。やはり、輪廻説を認めない限り、サンガという組織は成り立たないですからね。前に話した通り、一般の人に『来世は天に生まれ変わりますよ』と生天説を説いて布施を募るわけですから、輪廻は絶対に受け入れていたはずです。ただ、釈迦は『来世はどこに生まれ変わるか』などという問題よりも、『目の前の苦とどう向き合い解消するか』という問題をメインに考えていたんだと思います」と語ります。
インドの通念では輪廻自体はそもそも苦ではありません。あくまで苦というのは、その輪廻が老病死という現象を宿命的に含みこんでいるということなのだと指摘し、佐々木氏は「しかし仏教は、その老病死の際限のない繰り返しが輪廻の本質だと考えることで、輪廻=苦と見るようになった。ですから、輪廻は苦ではないと考える人にとって、仏教の教えは不必要で意味のないものと映るのです。梵天勧請の話で、「世の中には釈迦の教えを聞いても理解できない人がいる」という言葉は、それを意味しています」と述べます。それを受けた宮崎氏は、「『四門出遊』の挿話でも死苦を表しているのは単なる屍です。もし生老病死が輪廻の本質だとするなら、死苦を象徴するのは、死んで地獄に堕ち、獄卒に苛まれる咎人の有様や天で五衰を遂げていく神の姿だったはずです。しかし死の門の外にあったのは単なる骸だった……」と述べるのでした。
2「苦」の「苦とは何か」では、「一切皆苦」の苦は「ドゥッカ」と呼ばれることが紹介されます。宮崎氏によれば、「楽・苦・不苦不楽」がすべてドゥッカであるといいます。ラーフラは経証として増支部や中部を挙げていますが、相応部六処篇の「受相応」の経にも「すべての感受が苦である」とあります。宮崎氏は「直覚によっては把握し難く、やはり無常や縁起と密接に関わる抽象度の高い概念であることがわかります。アルボムッレ・スマナサーラ長老も『生きていることの総体がドゥッカである』(取意)と述べています」と言います。
すると、佐々木氏が「まさに一切皆苦。すべては生老病死という『四苦』の上に成り立っている。一切皆苦の本質は、私たちが生命体であるというところにあります。『四苦』とは、つまり生命体が生命体であるがゆえに必然的に抱え込む苦であり、したがって『決してそこから逃れられない』ものであり、『誰にでも等しく襲いかかる』ものです」と述べます。この「四苦」を上回る「楽」というものは、どこにもありません。もし仮に生老病死の後に永遠の天国といった絶対的な楽の世界が待っているのなら、それによって生老病死は克服できます。それこそがまさにキリスト教やイスラム教のような一神教的世界観であり、阿弥陀信仰のような絶対的救済者の信仰なのですが、ブッダはそういう絶対的な楽はどこにもないと言ったとして、佐々木氏は「生老病死を打ち負かす楽がこの世に存在しない以上、この世は一切皆苦に違いないのです」と言うのでした。
「四苦八苦」では、「四苦」は「生老病死」であり、文字通り、生まれ生きることだと説明されます。老いること。病むこと。死ぬこと。かかる苦を解消することが仏教の最終的な課題ですが、宮崎氏は「『老病死』が苦であることは直感的にわかりますが、『生』を最初に置くことで問題の深刻性が際立ちます。なお、この『生』を『生まれたこと』と解すると輪廻性が強調され、『生きること』とすると現世での実存苦の色が濃くなります。私はどちらの意味も含むと考えていますが」と言います。すると、佐々木氏が「それ以外にも、『生』を新生児が母親の産道を通って来る時の苦しみだ、などといった解釈もあります」と言い、さらに宮崎氏が「続いて『八苦』ですが、まずは『愛別離苦』。これは『愛したものと別れ離れる苦悩』と覚えるのがいいでしょう。キリスト教をはじめ他のほとんどの宗教や思想が『愛』を好ましいものと肯定し、尊び、果ては崇高なるものとして賞賛すらしますが、仏教では単なる煩悩。ドゥッ力そのものです。ニカーヤでも『愛するものに会ってはならない』と繰り返し戒められています」と述べるのでした。
「一切皆楽と常楽我浄」では、キリスト教の世界観は本質的に一切皆楽であると指摘し、佐々木氏が「いま自分が苦しんでいるのは神にいろいろ試されているだけであって、すべてを神に委ねれば救済されることが確定しているわけですから、これほど幸せな世界はない。だからその世界に没入できる人は絶対的に幸せでしょう。しかしながら、仏教の場合は、救済者はいない、つまり『見捨てられている』という感覚がある」と述べます。すると、宮崎氏は「ただ、世界が本質的な不全性を抱えているという認識は、グノーシス主義などの古代ヨーロッパ思想にもあるし、ひょっとすると一部のキリスト教、ユダヤ教の中にもあるかも知れない。それを救済するために、その世界を創り出した神がいるというような外部性を設定する。たとえばグノーシス主義だと、この世界は悪神によって創られたものだから本質的な不全性を抱えていて、私たちは苦しんでいる。私たちは本来の完全な世界から、この不完全な世界へと頽落してしまったと考えるわけです。だから、本来の完全な世界へ帰還することが救済であり目的なんだ、となるのです」と述べます。
この宮崎氏の発言を受けて、以下の対話が交わされます。
佐々木 ところが仏教の場合、戻る場所がない。われわれは完全に放り出されているわけです。これは非常に厳しい世界観ですよね。まさに一切皆苦。
宮崎 でも、大乗仏教になると、ここも変わってしまって「常楽我浄」なんて言い出す。原始仏教が否定したものを、ぜんぶ肯定項に反転させてしまう。
佐々木 「身受心法・楽常我」とも言いますね。本来ならば、体は汚い、感受作用はすべて苦、心は無常であり、法は無我というのが釈迦の教えだったのに、大乗の一派がすべて正反対にひっくり返してしまいました。
宮崎 この考え方は如来蔵思想からですね。さっきのグノーシス主義とちょっと似ていて、本来的にわれわれは心の奥底に如来を蔵していると考えるわけ。
3「無我」の「無我とは何か」では、いま私が実在している、自分が「在る」という観念が「我見」であるとして、宮崎氏が「いま『在る』限りは、ずっと、この先も私は永続するに違いない、永遠に存在し続けなくては不条理だ、という観念が『我執』です。この邪見と執着・ら渇愛が生じ、渇愛によって輪廻が起動される、というのが伝承されている教義ですね。従って解脱するには有我の見を滅ぼし、我への執着を断ずる必要がある」と述べています。「有身見という根本煩悩」では、宮崎氏は「死への苦しみ、死の恐怖をはじめとする様々な苦が、我見、我執によって、換言すれば『私はずっと生存しなければならない』『永遠に存在していたい』という欲望によって発生しているからです。本当にざっくりいってしまえば、存在しなくなることへの怖れは、そもそも現在も存在などしていないと真実を悟ることで消える」と述べます。
「自己責任と回向」では、宮崎氏が「現代の大乗仏教には、理想社会をつくるために社会にコミットしようとする動きもあるようですが、それは仏教の目的を履き違えていると私は思います。改めて強調しておきますが、理想社会をつくるのではなく、どんな理想社会が実現したとしても必ず残る苦というものを説くのが仏教のはずです」と言います。それを受けて、佐々木氏は「その通り。『仏教にもとづく理想社会』などということを言い出すと、世間の人々に仏教的な生き方を強制するなんてことになりかねない。仏教は社会の中でどうにもならなくなった人を引き受ける『病院』なのであって、それを超えて仏教的な生き方を社会に勧めたりしては絶対にいけない。『皆さんも出家しましょう。みんなで無我の境地で生きましょう』なんて言ったら、社会を破壊することになりかねない」と述べるのでした。
「無常とは何か」では、佐々木氏が「極微というのは、いわゆる原子です。仏教最初期には『物質は地・水・火・風という4種の要素からできている』という素朴な元素論しかなかったのですが、アビダルマ、特に説一切有部のアビダルマになると、すべての物質は何種類かの基本粒子の組み合わせで出来ているという、精緻な原子論が展開されるようになりました」と述べています。宮崎市が「中観派は不可分な実在としての極微も刹那も認めません」と言えば、佐々木氏は「中観派は、そもそも要素の存在を認めないわけですから、その要素が『現れて、消える』といった現象を認められるはずがない。刹那滅を架空の表れだとするのも当然でしょうね」と述べます。
「三世実有――未来から過去に流れる時間」では、宮崎氏が「私達は何となく、時間とは過去から現在へ、そして現在から未来に向かって『流れる』ものだと思い做していますよね。一直線上に過去→現在→未来と並んでいるイメージ。でも、これはよく考えてみるとあまり根拠のない想定です。例えば部派仏教の説一切有部の時間論、『三世実有』説では、時間は未来から現在を経て過去に流れるのです」と述べています。このあと、有名な「映写機の喩え」による説明が紹介されますが、非常に興味深いです。
映写機は、上下2つの大きなリールと、その中間に置かれた映写用のランプからなっています。(上のリールには、今から上映されるフィルムが巻かれており、それが下のリールにどんどん巻き取られていく。フィルムがランプの前を通り過ぎるとき、1コマずつスクリーンに映写されるという仕組みです。上のリールにあるフィルムは「存在はするが、まだ作用はしていない状態」、つまり未来ということになります。下のリールに巻かれたフィルムは「存在はするが、もう作用できない状態」、つまり過去。フィルムがランプの前を通過する瞬間が、すなわち現在ということになります。佐々木氏は、「ちなみに映画の場合、コマの進む速さは1秒間に24コマ、つまり1コマが約0・04秒ということになりますが、じつはこれが『倶舎論』で言うところの『一刹那』とほぼ同じ長さ。映画と現実世界が、まったく同じような錯覚原理によって見えているというのも面白いところです」と説明しています。
宮崎氏はこれを「自動車と風景」の喩えで説明しますが、いずれにせよ、三世実有説は、時間の流れを空間内の運動、もしくは空間内の物体の移動に転換しているわけです。梶山雄一も「有部は時間を空間化することによって、過去と未来の二物の間の因果関係を、空間に同時的に存在する二物の作用という関係として説明したのである」と指摘していると紹介し、宮崎氏は「ここでの時間の空間化の操作は取りも直さず時間の概念化に他ならず、本来分別できない時間を概念として分別してしまっています。これは虚妄であり、戯論ではないのか。つまり仏説に反しているのではないか。龍樹が、難解とされる『中論』の『三時門破』で批判したのは、本質的にこの点だと思うのです」と述べます。
「経部と唯識派」では、宮崎氏が「『倶舎論』を書いた世親は、説一切有部や経部の論者だったとされていますが、最終的には唯識派の理論的支柱として、また新たな時間論を提唱するようになりますね」と言うと、佐々木氏は「はい。唯識派の場合は、過去や未来だけではなく、現在もまた実体がないと言うんです。じゃあ、何もかも実体を持たないのかというとそうではなく、それらを生み出すベースとなる阿頼耶識という本当の実体があると言うわけです。阿頼耶識が、過去・現在・未来を一種のバーチャル映像のように映し出していて、それを認識している自分でさえも阿頼耶識から生み出される1つの映像に過ぎない」と述べ、宮崎氏が「つまり、阿頼耶識はパーフェクトな映写機のようなもの。識の外界には実体がないというのが『唯識無境』の考え方です。これはバークリーなどの独我論、唯心論に非常に近い」と言うのでした。
「龍樹の『空』の理論」では、佐々木氏から、龍樹についての説明があります。ナーガールジュナこと龍樹は、釈迦の死後から700年余り後、2世紀後半から3世紀前半にかけてインドで活躍した、大乗仏教における最初にして最大の哲学者です。その著書『中論』によって創始された中観派は、唯識派と並び、その後の大乗仏教の流れを決定的に変えました。チベット仏教・密教系はもとより、禅宗や日本の浄土系などにも多大な影響を及ぼしています。宮崎氏が「さらに言えば、龍樹の洗練された論理の批判的形式性は現代の西洋哲学とも相性が良く、ポストモダンをはじめとする哲学者たちの間でも、その認識論や言語論がよく話題にされています」言えば、佐々木氏は「中観派の特徴は、『般若経』で強調された『空』の概念をさらに徹底させ、あらゆる実体(自性)を否定し、すべての存在は無自性であると説いたことです」と述べるのでした。
第三章「僧――ブッダはいかに教団を運営したか」の「サンガと律」では、僧の原語は「サンガ(僧伽)」と言って、もともとは「集団」という意味だと説明されます。佐々木氏は、「個々人のお坊さんを指しているのではなく、正確に言うと、『4人以上のお坊さんが、独自の規則を守りながら、修行のための集団生活を営む組織』を指しています」と述べますが、宮崎氏が「4人以上の比丘(男性出家修行者)、比丘尼(女性出家修行者)さえいれば、世界中のどこであっても、その場はもうサンガと呼べるんですよね」と補足します。
「幻のサンガ復興運動」では、宮崎氏が「平安末期に奥州藤原氏が平泉の地に築いた都市には可能性があったかもしれない。平泉は中尊寺を中核とする仏教都市として描かれることが多いのですが、いわば『国家仏教』の本拠地、京都と異なり、民衆の救済や『怨親平等』の理念が生かされていたようです。奥州藤原氏が4代で滅びず、さらに100年ほど仏教都市として発展していったとすれば、全国から自覚的かつ自立的な僧が集まり、やがてサンガを形成したのではないか、と妄想します(笑)」と述べています。
「オウム真理教と律」では、宮崎氏が「結局、禅宗を除けば、日本の仏教系新興宗教で、サンガらしきものをつくったのはオウム真理教だけだったという……(笑)」と言うと、佐々木氏が「本当にそう。皮肉なことです。誤解を恐れずに言えば、オウム真理教がもし麻原のような人物ではなく、もっと謙虚な人をリーダーに持ち、律のような規則を導入して正しく教団を運営することができていたら、日本では独自の、非常に面白い出家教団が生まれた可能性はあったかも知れない」と呼応します。宮崎氏は「日本の仏教系新興宗教は、みんな『本当の仏教』を謳っているんだから、本来は仏法僧を一セット持ってなきゃいけないはず」と言うのですが、オウム真理教がさも本当の仏教であったかのような言い方には大きな疑問を抱きました。
宮崎氏が「タイやスリランカなどアジアの国々でも、いくつか仏教系新興宗教がありますが、彼らもちゃんとサンガを作ります。それなのに、なぜか日本の仏教系新興宗教は、大概在家集団なんですよ。あれは不思議ですよね」と述べると、佐々木氏は「それに対し、オウム真理教は曲がりなりにも出家教団というものを実現したから、たくさんの人の気持ちを引き付けてしまったんです。俗世とは一線を画した修行空間というのは、本来の仏教が持つ大きな魅力の一つですから。もちろん、仏教とオウム真理教とではサンガの運営方法が根本的に異なるんですが。オウムには律がなく、代わりに麻原彰晃という個人が恣意的に規則を決めていました。たとえば、麻原がゴキブリを殺してはいけないと言ったもんだから、サティアン(オウム真理教の宗教施設)の中はゴキブリだらけだった。一応、『不殺生』ということらしいけど」と述べます。この会話も、わたしは不愉快でした。
 『唯葬論』(三五館)
『唯葬論』(三五館)
結局、この2人は「人間を幸せにする」「社会を良くする」などの理念や志を抜きにして仏教の専門用語で遊んでいるだけのように思えてなりませんでした。言葉遊びをしたり、「仏・法・僧」にこだわるよりも、人々の心を安定させ、幸せにする宗教として仏教は存在していると思います。そして、「葬式仏教」などと呼ばれる日本仏教は正しいと思います。拙著『唯葬論』(三五館、サンガ文庫)に書いたように、オウム真理教の「麻原彰晃」こと松本智津夫が説法において好んで繰り返した言葉は、「人は死ぬ、必ず死ぬ、絶対死ぬ、死は避けられない」という文句でした。死の事実を露骨に突きつけることによってオウムは多くの信者を獲得しましたが、結局は「人の死をどのように弔うか」という宗教の核心を衝くことはできませんでした。言うまでもありませんが、人が死ぬのは当たり前です。「必ず死ぬ」とか「絶対死ぬ」とか「死は避けられない」など、ことさら言う必要なし。最も重要なのは、人が死ぬことではなく、死者をどのように弔うかということなのです。