- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.2364 プロレス・格闘技・武道 『1985年のクラッシュ・ギャルズ』 柳澤健著(光文社未来ライブラリー)
2024.11.07
『1985年のクラッシュ・ギャルズ』柳澤健著(光文社未来ライブラリー)を読みました。著者は1960年東京都生まれ。ノンフィクションライター。慶應義塾大学法学部卒業後、空調機メーカーを経て株式会社文藝春秋に入社。花田紀凱編集長体制の『週刊文春』や設楽敦生編集長体制の『スポーツ・グラフィック ナンバー』編集部などに在籍し、2003年に独立。著書に、一条真也の読書館『完本 1976年のアントニオ猪木』、『1964年のジャイアント馬場』、『1984年のUWF』、『2000年の桜庭和志』で紹介した一連のプロレス・ノンフィクション、一条真也の読書館『2016年の週刊文春』で紹介した古巣のノンフィクションなどがあります。
 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙にはリング上で歌うクラッシュ・ギャルズの写真が使われ、帯には「『私はもう死んでもいいと思いました』――青春格闘ノンフィクションの傑作、待望の復刊!」「クラッシュ・ギャルズ結成40周年」「解説:尾崎ムギ子(『女の答えはリングにある』著者)」「◆著者あとがき『雨宮まみさんのこと』」と書かれています。
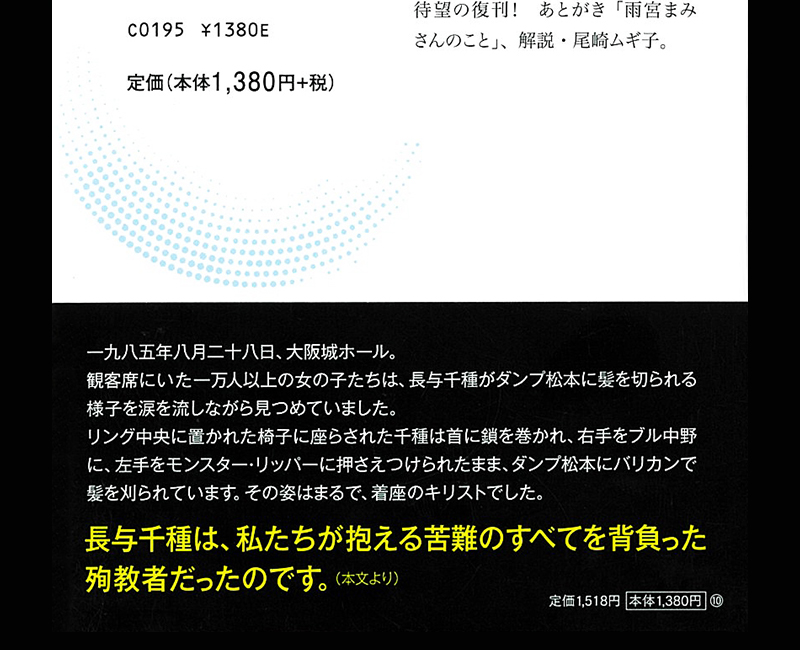 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、以下のように書かれています。
「一九八五年八月二十八日、大阪城ホール。観客席にいた一万人以上の女の子たちは、長与千種がダンプ松本に髪を切られる様子を涙を流しながら見つめていました。リング中央に置かれた椅子に座らされた千種は首に鎖を巻かれ、右手をブル中野に、左手をモンスター・リッパ―に押さえつけられたまま、ダンプ松本にバリカンで髪を刈られています。その姿はまるで、着座のキリストでした。長与千種は、私たちが抱える苦難のすべてを背負った殉教者だったのです。(本文より)」
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「1985年、一つの巨大な社会現象が生じた。10代の少女たちが、男しか興味を持たなかった女子プロレスの新星『クラッシュ・ギャルズ』に熱狂したのだ。タッグを組んだ2人、長与千種とライオネス飛鳥は、何を背負って自らをいじめ抜き、過酷な闘いを続けたのか? 10代の少女たちは彼女らに何を託したのか? 熱く切ない青春格闘ノンフィクションの傑作、待望の復刊! あとがき『雨宮まみさんのこと』、解説・尾崎ムギ子」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
第一章 観客席の少女
第二章 置き去りにされ
第三章 光り輝くエリート
第四章 赤い水着
第五章 青い水着
第六章 親衛隊
第七章 引退
第八章 現実と向きあう季節
第九章 新団体
第十章 冬の時代に輝く
第十一章 夢見る頃を過ぎても
第十二章 そして誰もいなくなった
終章 クラッシュ再び
「あとがき」
「井田真木子さんのこと――
文春文庫版のためのあとがき」
「雨宮まみさんのこと――
光文社未来ライブラリーのためのあとがき」
解説(尾崎ムギ子)
わたしは三度の飯よりプロレスが好きで、特に「昭和プロレス」への思い入れが強いです。しかし、それは男子プロレスに限った話で、女子プロレスにはまったく関心がありませんでした。それが一変したのは、ブログ「極悪女王」で紹介したNetflixドラマを観たときです。女子プロレスラーのダンプ松本が仲間たちとの友情と戦い、さまざまな代償や葛藤を抱えながらカリスマ的人気で1980年代に女子プロレス旋風を巻き起こし、日本史上最も有名なヒールに成り上がっていくさまを描いています。ゆりやんレトリィバァが演じた主人公ダンプ松本の最大のライバルが、ライオネス飛鳥(剛力彩芽)と長与千種(唐田えりか)のクラッシュ・ギャルズの2人でした。ドラマにハマったわたしは、すぐさま本書『1985年のクラッシュ・ギャルズ』をアマゾンで購入し、一気読みした次第です。
第二章「置き去りにされ」の「雑草組」では、「日本の女子プロレスは、戦後まもない頃にロープもないマットの上で太腿にはめたガーターを取り合う『ガーター争奪戦』から始まる。意外なことに、力道山の日本プロレスよりも古い歴史を持っているのだ。全日本女子プロレスの経営者は松永兄弟である。三男の松永高司会長が天皇として君臨し、次男の健司と五男の俊国は営業担当。四男の国松が現場マネージャーとして選手に接する」と書かれています。
「全女の知られざるルール」では、プロレスとは徹頭徹尾ショーであり、見世物であることが指摘されます。勝敗はあらかじめ決まられており、2人のレスラーは観客を喜ばせるために一致協力して試合を盛り上げます。しかし、この世界的な常識が全日本女子プロレスに限っては通用しないとして、著者は「当時、若手のために用意されたタイトル、すなわち新人王、全日本ジュニア、全日本シングル王座のすべては、驚くべきことに独特の押さえ込みルールの下に行われる真剣勝負であった」と述べます。理由はギャンブル好きの松永兄弟が賭けの対象にするためでした。
先輩と後輩が対戦すれば体重のある選手が圧倒的に有利ですが、横田利美(ジャガー横田)のように小柄であっても首と背筋の力が強く、ブリッジがしっかりしているレスラーなら、押さえ込まれる可能性は低いです。本書には、「押さえ込みルールの試合は、観客が見て面白いものではまったくない。喜ぶのは松永兄弟だけだ。兄弟の中でも互いにライバル心を抱く四男の国松と末弟の俊国は常に賭けをしていた、と長与千種は証言する」と書かれています。
勝敗は出世に直結したので、全日本女子プロレス(全女)のレスラーたちは誰もが真剣に押さえ込みを研究しました。著者は、「ずっと後になってから気づいたことだが、当時の千種は押さえ込まれると右にしか逃げられなかった。ある時、同期のひとりがそのことに気づき、情報は瞬時に同期全員に行き渡った。動きを詠まれた千種は、連日のように仰向けでスリーカウントを聞く羽目に陥った」と述べています。
全女が選手に求めるのは、女同士のリアルなケンカでした。著者は、「リング上では激しいケンカを見せるものの、試合が終われば和気藹々。冗談ではない。女にそんな器用なことができるはずがない。リング上で激しい戦いを見せるためには、普段から険悪な人間関係を作っておく必要があるのだ。そのように考える松永兄弟は、選手たちの精神状態をコントロールして、常に関係を悪化させる方向へと誘導していく」と述べます。
1981年2月15日、横浜文化体育館でジャッキー佐藤に横田利美が挑戦したWWWA世界シングル選手権試合では、押さえ込みで横田が勝利しました。その後、佐藤は引退。全女のリーダーは横田になりましたが、彼女は女子プロレスに多くの観客を呼ぶことはできませんでした。全女の経営状態は極度に悪化しました。著者は、「旅館代を払うのに興行収入や売店の売上を注ぎこんでも足りず、松永国松マネージャーが財布の小銭まで集めたこともしばしばあった」と述べます。
その横田利美の後継者が北村智子でした。のちのライオネス飛鳥です。1980年5月にデビューした彼女は12月には大森ゆかりを破って新人王になり、翌年1月には空位となっていた全日本ジュニア王座を先輩の川上法子を破って獲得。数回防衛した後、相手がいなくなって返上、82年7月にはマスクド・ユウ(本庄ゆかり)を破って全日本王者ろなりました。しかし、マネージャーの松永国松は、横田に「お前は確かに強い。技もすぐに覚える。でもお客さんに伝わるものが何もなく、見ていてまったく面白くない」と言い放ち、飛鳥はショックを受けます。
押さえ込みで必要なのは強さだけです。ライオネス飛鳥は、押さえ込みルールの試合ではジャガー横田とともに全女史上最強選手の1人でした。しかし、プロレスは観客の存在を前提としています。著者は、「試合を通して観客に自分の感情と痛みを伝え、はっきりとした起承転結の物語を提示し、観客に次の展開を予測させた上で『この選手の次の試合を見てみたい』と思わせること。それこそがプロレスラーの技量なのだ。簡単な仕事ではない。恐ろしく強いライオネス飛鳥には、感情と痛みと物語を観客に伝える力、すなわち表現力が不足していたのだ」と述べるのでした。
一方、プロレスにおける表現力が図抜けていたのが長与千種でした。1983年の全女開幕戦での全日本選手権で、王者の飛鳥と挑戦者の長与が闘いますが、この一戦は壮絶なケンカ・マッチとなりました。前日に長与が飛鳥に「禁じ手のない試合がしたい」と申し入れていたのでした。結果は飛鳥が勝利しますが、この試合は大変な評判となりました。松永国松は、ついに飛鳥と長与のタッグチーム結成を決意します。兄の松永高司会長の了承を得て、本格的に2人の売り出しをはかりましたが、新しいタッグチームの中心となるのがライネオネス飛鳥ではなく、長与千種であることは、松永国松にとっては自明でした。クラッシュ・ギャルズの誕生です。
第四章「赤い水着」の「プロレスは言葉だ」では、長与が先輩レスラーであるデビル雅美の部屋に転がり込み、ビデオで男子プロレスの研究をしたエピソードが紹介されます。著者は、「たまの休日に一日中ビデオを見ていると、面白いことがわかる。たとえばジャイアント馬場がタッグマッチを戦っている。ピンチに陥った馬場がコーナーにいるパートナーに助けを求めて手を伸ばす・この時、伸ばされた馬場の手のひらが下を向いていれば、パートナーは決してタッチしない。いまは後退する時ではないと、馬場の手の平の向きが教えている。手を伸ばすのはポーズに過ぎず、馬場はさらなる危機を演出しようとしているのだ。だがもし、馬場が手の平を上に向けて手を伸ばしていれば、パートナーは即座にタッチして、馬場に代わってリングに入らなければならない。馬場は心からタッチを望んでいるからだ。衆人環視の中、プロレスラーは無数の身体言語と暗号を使って会話をしている」と書いています。
また、長与千種はプロレス雑誌の写真を切り抜き、技ごとに分類してノートに貼り、さらにレスラーの印象的な発言を書き抜きました。「俺はお前のかませ犬じゃない」という長州力の言葉は特に心に響いたそうです。“お前”とはアントニオ猪木の愛弟子である藤波辰巳のことです。テレビで見る長州は恐ろしく不機嫌で、少し触れれば血が出そうな刺々しさがあったとして、著者は「プロレスは言葉だ。口から出るものばかりではない。相手にフォールされた時に、必死で跳ね返せば、観客には選手の闘志が伝わる。すべてのワザ、すべての動きを言葉として観客に伝えること。それがプロレスラーの仕事なのだ。観客は心に響く言葉を求めている」と述べます。
長与千種は貪欲に学びました。極真空手の山崎照朝から本格的に空手を学び、シュートボクシングのシーザー武志からはキックを学び、さらにはボクシングジムではフットワークを学びました。UWFの「関節技の鬼」藤原喜明とはスパーリングして、文字通りおもちゃにされました。1分間に何度ギブアップしたかわからかったとか。元タイガーマスクの佐山聡と前田日明からはスープレックス、つまり後方への反り投げを学びましたが、著者は「興味深いことに、ふたりのスープレックスはまったく異なるものだった。同じフロントスープレックスで投げられても、佐山のスープレックスは滞空時間が長く、プロレス的なスペクタクルに溢れている。要するに見せるための投げだ。反対に前田日明のスープレックスは抱えられた瞬間にマットの上に倒されていた。それでいて受け身はしっかりと取れている。前田日明は長与千種にこう言った。『ホンマにやろうと思ったら、一発で仕留めることができんねん。でもそれをやらずにギリギリのところで相手にしっかりと受け身を取らせるのもプロレスやねん』」と書いています。
「天才の開花」では、クラッシュの基本イメージが「中性」にあることを指摘し、それはウルトラマンや水戸黄門のような単純な構図を持つ“戦う少女たち”の物語なのであるといいます。著者は、「クラッシュ・ギャルズ以前に『凛々しく戦う少女』が主役となることはなかった。『サイボーグ009』の003や『秘密戦隊ゴレンジャー』のモモレンジャーは、少年の世界観を一歩も出ることなく、少年にとって都合のいい脇役であり続けたし、ビューティ・ペアにおいても、女性的なマキ上田は男性的なジャッキー佐藤に庇護される存在だった。クラッシュ・ギャルズと同時期の1980年代半ばに映画『風の谷のナウシカ』(1984年)が登場し、男女雇用均等法が施行(1986年)されたのは決して偶然ではない。日本経済がバブルに向けて疾走していたこの時期、女性たちは自由と平等、そして戦いを求めていたのだ」と述べています。
「ダンプ松本の誕生」では、クラッシュ・ギャルズの2人と同期のレスラーに松本香がいたことが紹介されます。クラッシュの活躍に、松本香は心穏やかではいられませんでした。フィジカルエリートで、自分とも仲のいいライオネス飛鳥はともかく、どうしようもない落ちこぼれだった長与千種までもが、いまや自分の遥か先を走っていたからです。松本香は名前をダンプ松本と変え、金髪に染め、顔に派手なペイントをして、極彩色のコスチュームを身に纏うと、デビル雅美の下を離れて同期のクレーン・ユウと共に、クラッシュ・ギャルズに対抗する新たなるヒール軍団・極悪同盟を結成しました。著者は、「プロレスとは言葉であり物語であり、物語であればこそ観客はわかりやすい正義と悪の対立を望む。ベビーフェイス(正義の見方)がヒール(悪役)に散々痛めつけられれば、観客席の少女たちは大いに興奮する。ヒールがチェーンや竹刀を振り回し、卑怯な反則行為を繰り返せば、興奮はさらに倍増される」と述べています。
基本的にダンプは道具屋でした。凶器を駆使してクラッシュ・ギャルズを痛めつけることが仕事だったのです。ダンプ松本の使うフォークは妙に尖っていて、エッジだけがピカピカに光っていました。おそらくヤスリで研いだのでしょう。それを突き刺される長与千種の目には、その輝きがはっきりと見えました。著者は、「フォークばかりではない。ハサミ、有刺鉄線、鎖、竹刀、ダンプ松本は様々な凶器を駆使して千種を痛めつけた。悪役レフェリー(!)阿部四郎は、当然のようにダンプの凶器攻撃を見て見ぬふりをする。赤コーナーにいるライオネス飛鳥は名優千種に声援を送り、観客の少女たちもまた、スーパーヒロインの危機を、息をのんで見守っている。会場にいる人々の視線を一身に集めつつ、リングの中心で血を流し続ける長与千種は、試合のすべてを支配する演出家でもあった」と述べるのでした。
第五章「青い水着」の「飛鳥の焦燥」では、「飛鳥はプロレスを考えない。だから私が考える」と千種が思っていたことが明かされます。天才演出家の長与千種が作り出すクラッシュ・ギャルズのプロレスが観客を興奮の渦に巻き込み、全日本女子プロレスに莫大な利益をもたらしている以上、千種に文句を言える人間など1人もいないはずでした。著者は、「しかし、全日本女子プロレスは普通のプロレス団体ではなかった。押さえ込みルールが存在する特殊な実力社会なのだ。ライオネス飛鳥は、強い自分が弱い千種の下に置かれることが納得できない。押さえ込みルールの試合で、すでにレスラーとしての格付けは済んでいる。同期の中で最も強い自分は、ごく近いうちにWWWA世界シングル王座の赤いベルトを巻く人間なのだ。お前とは違う。ライオネス飛鳥には高いプライドがあった」
第七章「引退」の「ダンプが引退したとき、わたしの半分が死んだ」の冒頭を、著者は「全日本女子プロレスのハードスケジュールは有名だ。クラッシュ・ギャルズ人気がピークだった1985年には、なんと年間269試合を組んでいる。だが、わずか2年後の87年には150試合しか組めなかった。地方で興行が売れなくなっていたのである。クラッシュ・ギャルズのブームは去ったと判断した松永兄弟は商品の入れ替えを図り、給料の高いベテラン選手に次々と引退を勧告していく」と書きだしています。87年12月にはデビル雅美が引退。88年1月4日にはダンプ松本が引退を示唆、同月15日には大森ゆかりも引退を表明しました。1988年2月25日、川崎市体育館は4500人という超満員の観客で埋まりました。引退するダンプ松本と大森ゆかりがタッグを組み、クラッシュ・ギャルズと対戦したからです。著者は、「長与千種、ライオネス飛鳥、ダンプ松本、大森ゆかり。女子プロレス人気の立役者である彼女たちは花の55年組と呼ばれる。同期4人が同時にリングに上がるのは最初で最後。客の入りも熱気もクラッシュ・ギャルズの全盛期を彷彿とさせた」と書いています。
長与千種も、ライオネス飛鳥も、そして大森ゆかりまでもがダンプのフォークの餌食となって試合終了のゴングが鳴りました。しかし、中途半端なマクギレに「もう1回」コールが置きました。そのとき、ダンプ松本がマイクをつかんで、「長与! お前とは敵だけじゃ終われないんだ。長与こい! こっちへこい!」と叫んだのです。血まみれのままコーナーポストにもたれていた長与千種は、ダンプが投げてよこしたマイクを拾って「やってやるよ。一度は組んでやるよ、お前と! 本当のプロレスってものがどんなものか教えてやるよ! 4人で見せつけてやるよ、プロレスを。大森! 本当にやりたかったプロレスをやるんだ。4人しかできないプロレスをやるんだ! ほかに誰もいないんだよ。4人でやるしかできないんだよ! 一緒にやるんだよ!」と叫びました。大森が、そして飛鳥が両賞し、ダンプが長与と握手しました。赤コーナーに千種とダンプ、青コーナーに飛鳥と大森が湧かれました。
そのまま5分間のエキシビションマッチが行われ、最後は大森が千種をカバー、ダンプが飛鳥をサソリ固めにとった状態で試合終了のゴングが鳴りました。特別レフェリーの松永国松がダンプと大森の手を上げ、続いてクラッシュの手を上げました。飛鳥と大森が抱き合い、ダンプは泣きじゃくる長与千種を抱え上げて、ファンの大きな声援に応えました。著者は、「エリートだった飛鳥と大森ゆかり、落ちこぼれだった千種とダンプ。入団からすでに8年。レスラーたちの心の中には、毎日のように嫉妬と憎しみが降り積もり、踏み固められていく。しかし、どれほどの葛藤があろうとも、いったん試合が始まれば、観客を熱狂させるという目的に向かって一致協力するいがいにはない。相手を殴り蹴り、傷つける。相手を気遣い、思いやり、信頼する。すべてが混然一体となったままフィニッシュへと突き進む。プロレスとはなんと奇妙で魅力的なものだろう」と述べるのでした。その後、長与千種とライオネス飛鳥も1989年に引退し、全女を去ります。
第十二章「そして誰もいなくなった」の「クラッシュ2000」では、1999年、女子プロレスは冬の時代に突入していたことが紹介されます。にもかかわらず、フリーとして多くの団体からひっぱりだこになっていたライオネス飛鳥は、Jd’、GAEA、全女、FMW、ネオ・レディース、JWPのリングで週に3試合のスケジュールをこなし、男子を含めて最多の年間170試合出場を記録しました。飛鳥は東京スポーツが選定する1999年度の「女子プロレス大賞」を受賞し、翌年には悩んだ末にクラッシュの再結成を決意します。著者は、「もはや自分は日本一の女子プロレスラーなのだ。クラッシュに従属するのではなく、クラッシュを自分の一部にしてしまおう。GAEA専属になることを避け、フリーランスの立場を堅持したまま、クラッシュをビッグマッチ限定にすれば問題ない」と書いています。こうして、2000年5月14日のGAEA JAPAN旗揚げ5周年記念大会で「クラッシュ2000」が誕生したのでした。
クラッシュ・ギャルズが引退した1989年以後、低迷を続けた女子プロレスを変えたのはブル中野とアジャ・コングでした。以後、女子プロレスは危険に充ち満ちたものへと変貌し、団体対抗戦ブームは女子プロレスをついに東京ドームへと導いた。1994年11月のことだ。著者は、「1990年に女子プロレスを支配したのは『危険で激しいプロレスでなければ客を呼べない』という思想であり、その結果、プラム麻里子という犠牲者を出してしまった。そして2000年5月、90年代の女子プロレスの常識を覆したのは、新時代のプロレスではなかった。皮肉なことに、80年代のクラッシュの復活だったのだ」と述べるのでした。本書は、女子プロレスに疎かったわたしに基本知識と歴史認識を与えてくれました。正直言って、女子プロレスを見直しました。しかし、巻末に置かれた「井田真木子さんのこと――文春文庫版のためのあとがき」、「雨宮まみさんのこと――光文社未来ライブラリーのためのあとがき」を読むと、女子プロレスの世界がライターの生命までも吸い込む魔界であることがわかります。解説を書かれた尾崎ムギ子氏の無事を祈るばかりです。