- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
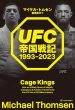
No.2388 プロレス・格闘技・武道 『UFC帝国戦記1993ー2023』 マイケル・トムセン著(亜紀書房)
2025.04.04
『UFC帝国戦記993-2023』マイケル・トムセン著(亜紀書房)を読みました。〝人間闘鶏〟が世界最高峰の興行ビジネスに上り詰めた理由が書かれた本です。1990年代から21世紀初頭に至るアメリカ文化・経済の劇的な変容ぶりを見事に体現した総合格闘技(MMA)と興行ビジネスの現代史が記録されています。著者は、1966年アメリカ合衆国生まれ。カリフォルニア大学卒。1993年にコロラド州デンバーで開催された〈アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ〉の海賊版ビデオを19歳のとき見て魅了され、以後総合格闘技の試合と情報を追いはじめるようになります。スポーツ、ゲーム、テクノロジー、政治文化などについて『ニューヨーカー』『ニューヨーク・タイムズ』『アトランティック』『ヴァニティ・フェア』『フォーブス』『ワイアード』『ニュー・リパブリック』などに寄稿。ニューヨーク在住。
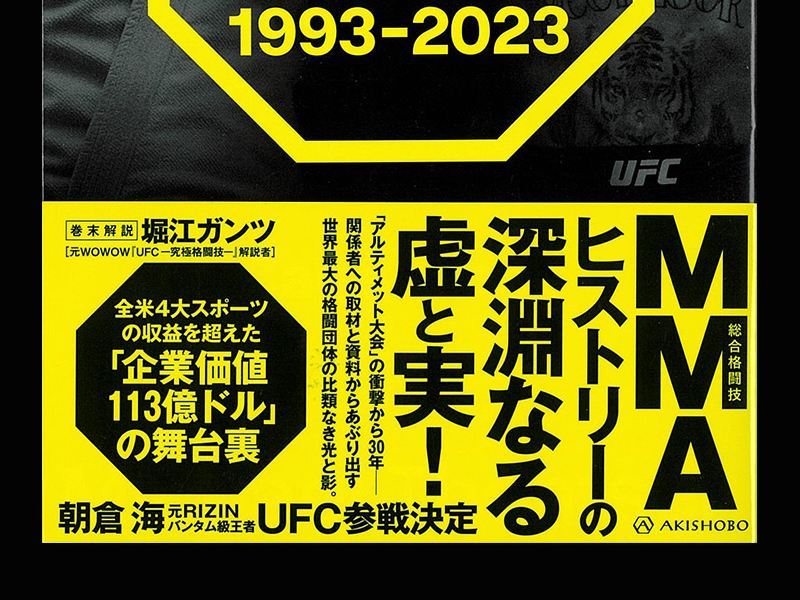 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、ホイス・グレイシーとコナー・マクレガーの写真が使われ、帯には「「MMA(総合格闘技)ヒストリーの深淵なる虚と実!」「『アルティメット大会』の衝撃から30年──関係者への取材と数々の資料からあぶり出した世界最大の格闘団体UFCの比類なき『光と影』」「巻末解説 堀江ガンツ[元WOWOW『UFC―究極格闘技―』解説者]「全米4大スポーツを超えた『企業価値113億ドル』の舞台裏」「朝倉海(元RIZINバンタム級王者)UFC参戦決定」とあります。
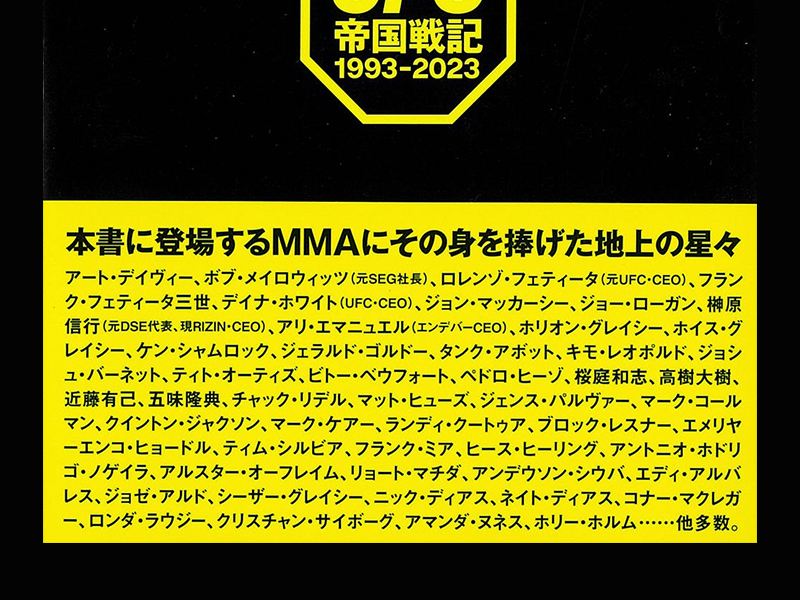 本書の帯の裏
本書の帯の裏
帯の裏には、「本書に登場するMMAにその身を捧げた地上の星々」として、UFCに参戦した多くの格闘家の名前が並んでいます。さらにカバー前そでには、「『グレイシー柔術』の名が世に轟いた1993年の第1回大会。その後経営を握ったズッファとデイナ・ホワイトの奮闘。莫大な収益をもたらしたスパイクTV、FOX、ESPNとの契約。日本のPRIDEやアメリカンプロレスの巨人WWEとのディール。コナー・マクレガーやロンダ・ラウジーら選手の闘いとその葛藤……。格闘技ファンなら必携、そして垂涎の翻訳ノンフィクション――」と書かれています。
本書の「目次」は、以下の通りです。
「日本語版刊行に寄せて」
プロローグ「覇権をつかんだ闘いの祝祭」
第一章 成功の確信と障壁
──アート・デイヴィーとSEG
第二章 ズッファの船出
──フェティータ兄弟とデイナ・ホワイト
第三章 38歳のUFC王者
──ランディ・クートゥアの葛藤
第四章 総損失3000万ドルの危機
──PRIDE絶頂の裏側で
第五章 リアリティ番組でV字回復
──スパイクTVの野心
第六章 競合団体の買収劇
──放浪するニック・ディアス
第七章 ホワイトの強権発動
──ヒョードルを巡る運命の糸
第八章 FOXと結んだ巨額契約
──大型買収の完了
第九章 スーパースターの誕生
──柔道王ロンダ・ラウジー
第十章 ドル箱ペイパービューから
ライセンス事業への転換
第十一章 生活保護からカリスマに
──悪童コナー・マクレガー
第十二章 ズッファ、40億ドルで売却
──波乱のUFC200
第十三章 大量解雇とエンタメ路線
──ラウジー最後の二敗
第十四章 WBCが懸けた豪華ベルト
──マクレガー対メイウェザー
エピローグ「限界を超えろ」
【解説】堀江ガンツ「UFCと日本格闘技界」
「日本語版刊行に寄せて」の冒頭を、著者は「MMA(総合格闘技)の歴史に、日本はずっと特別な位置を占めてきた。本書は、プロ総合格闘技団体UFC〈アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ〉を最も成功したプロスポーツ団体のひとつに押し上げたアメリカの文化と経済の力に焦点を当てている。しかし、そもそも日本文化の貢献がなければ今日の隆盛はなかった可能性が高い。19世紀、オクタゴンの扉が初めて開く100年以上も前に「柔道」を創始した嘉納治五郎の努力がなかったら、おそらくUFC第1回大会(1993年)は実現していなかっただろう」と書きだしています。
初期のMMAファイターにとっては、パンクラスをはじめ、〈RINGS〉、〈修斗〉、そして最も重要な〈PRIDE〉など、1980年代末から90年代に日本で産声をあげた総合格闘技団体が経済的な生命線となったとして、著者は「90年代後半にUFCが主要ケーブルテレビのほとんどから排除され、倒産寸前に追い込まれたときは、ホイス・グレイシー、ドン・フライ、ヴィトー・ベウフォート、マーク・コールマン、ゲーリー・グッドリッジ、ダン・スバーンら、UFCで最も知名度の高い選手たちが続々と日本のマットに上がった」と述べています。
彼らの存在は藤田和之、船木誠勝、髙阪剛、五味隆典ら、まだ欧米で評価を確立していなかった多くの日本人MMAスターの国際的知名度を結果的に高めました。とくにPRIDEは旧国立競技場に9万1000人を超えるファンを集め〔2002年8月28日開催の『Dynamite!』〕、何千万人ものファンがテレビ観戦した〔生中継はペイパービュー。9月1日に録画放送された〕のです。
プロローグ「覇権をつかんだ闘いの祝祭」では、UFCは1990年代前半にビール輸入業者のための売り込み戦略として考案され、さまざまな格闘技の実際の戦闘力を試すというアイデアの下、まったく新しいスポーツとして打ち立てられたと説明し、著者は「ブラジリアン柔術、柔道、ムエタイ、テコンドー、サンボなど、何十種類もの格闘技の訓練を受けた戦士たちが金網張りの檻に閉じ込められて、ノックアウトされるか、首を絞められて意識を失うか、あるいは関節技の痛みに屈してタップアウト(ギブアップ)の意思を示すかするまで戦わされた。やがて格闘技間の差異は不明瞭になり、総合格闘技(MMA)という新しいスポーツが誕生した」と述べています。
どの世代にもそれぞれのブラッドスポーツがあるといいます。人気がありながらも穏当な社会の枠外に存在する、不穏なたぐいの娯楽のことです。ガウジングは17世紀から18世紀にかけて植民地アメリカに広まりました。相手の目をくりぬき、口や、鼻や、耳の周りの皮膚を引き裂くことを目的にした自由度の高い格闘技です。イギリスでは18世紀から19世紀にかけてベアナックル・ボクシングが人気を博し、1万人以上の観衆を集めることもありましたが、ほとんどは違法な興行でした。20世紀初頭にはキャッチレスラーが世界を転戦して、相手から降参を奪う激しい組み技の試合を繰り広げ、これがUFCやWWEの礎となりました。
1970年代には〈プロ空手協会〉(PKA)がABCの「ワイド・ワールド・オブ・スポーツ」やESPNで血みどろのフルコンタクト・キックボクシングを提供しましたが、頭部に対する蹴りのダメージを心配する〈ボクシング・コミッション協会〉(ABC)から注視と批判を受けました。同時期、アメリカ郊外ではおおよそボクシングルールの〈タフマンコンテスト〉が人気を博し、おもにブルーカラーの男性たちが賞金目当てに乱打戦を繰り広げる、一夜限りのトーナメントが開催されました。
第一章「成功の確信と障壁──アート・デイヴィーとSEG」では、アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ(UFC)がまだ何の形にもなっていなかったころ、カリフォルニア州トーランス公共図書館の閲覧室に座っていたアート・デイヴィーは、ある着想から現実的なブレイクスルーを得るために資料を漁っていたことが紹介されます。彼は何ヵ月もかけて賞金格闘試合と格闘技の歴史を調べ、物語を集め、フォルダー用のメモを取っていました。とりわけ興味があったのは、異なる格闘ジャンルの選手が戦った試合です。どちらが優れたファイターかを証明するためではなく、どちらがより効果的な護身術を選んだかを確かめる戦いでした。彼のノートには、1963年に柔道の黒帯ジーン・ラベールとボクサーのマイロ・サヴェージが戦ったエキシビションマッチ(第4ラウンド、ラベールか道衣の襟を使ってサヴェージの首を絞め、勝利)をはじめ、好奇心をそそる不思議な試合が多かったです。
1976年、ビンス・マクマホン・シニアがニューヨークのシェイ・スタジアムを押さえ、レスラーのアンドレ・ザ・ジャイアント(本名アンドレ・ルネ・ロシモフ)とヘビー級ボクサーのチャック・ウェブナーによるエキシビションマッチを行いました。同日、この試合のあと、東京の日本武道館で行われたモハメド・アリ対アントニオ猪木の一戦はクローズドサーキット形式でテレビ中継されました。著者は、「この試合は当初、猪木が背後からサブミッションホールドでアリを仕留める筋書きだったが、直前に急遽ルールが書き換えられ、猪木はレスリングのテイクダウンが禁じられた。猪木は15ラウンドの大半を仰向けに寝たまま、アリの膝を蹴ることに終始した。試合中盤、観客の一部がリングにごみを投げ入れて『金返せ! 金返せ!』と叫びはじめた」と述べます。
アート・デイヴィーにとって、ボクシングはコストがかかりすぎるし、プロレスは幼稚すぎるが、格闘技には可能性が見えました。彼はベトナム従軍時、兵士の一団がバンコクへの研究旅行中に見たという地下格闘技戦の話を耳にしました。小柄なムエタイ選手と巨体のインド人レスラーという極端なミスマッチでしたが、試合は小柄な男が勝利しました。著者は、「その話が本当かどうか知るすべはなかったが、デイヴィーはそこに名案の芽を感じた。ほかにもそんなふうに変わった戦士たちがいるだろうか? 日本のレスラーはヘビー級ボクサーに勝てるか? アメリカのキックボクサーは相撲取りと戦えるか? クラヴマガ〔イスラエルの実践的護身術〕の戦士は柔道家から身を守れるか? デイヴィーはテカテをスポンサーにこれらの疑問に答えるテレビシリーズ『ザ・ワールズ・グレイテスト・ファイターズ(世界最強の格闘家たち)』の企画をまとめた」と述べています。
1993年11月12日にアメリカのコロラド州のデンバーで開催されたUFC1の光景には非現実感が漂っていたといいます。いや、もっと正確に言えば、新しい現実がむきだしになったのかもしれません。ホイス・グレイシーのような小柄で非力そうな人間がウェィン・シャムロックやアート・ジマーソンのような大きくたくましい人間に勝てるはずはなかったとして、著者は「なのにホイスは合計5分足らずで自分より大きな男を3人撃破した。仰向けになって両脚を宙に振りながら試合の主導権を握る技術の効果は、超自然的にさえ思われた」と述べています。
のちにアート・デイヴィーはデンバーで戦った選手たちを、音速の壁に挑んだテストパイロット、チャック・イェーガーになぞらえました。しかし、彼らはむしろ、人間にも空を飛ぶことができることを証明しようとノースカロライナ州キティホークの砂丘上に実験用グライダーを飛ばしたライト兄弟に近かったと指摘し、著者は「上昇の瞬間さえほんの短時間で、不時着に終わり、すべてが崩れ落ちたときに、何がうまくいって何が間違っていたのかという混乱の余韻。それは人の心をとらえて離さない。啓示的であり、薄気味悪く、喜劇的で、破滅的。こんなものはマスメディアで放送されたことがなかった」と述べます。
アート・デイヴィーが新しい選手をスカウトしつづけるうち、UFCの登録選手名簿は奇怪の度を増してきました。エキセントリックな、ときにまったく作り事の武術が実践されていた郊外のボロ道場から引き出されてきたようなキャラクターが満載だったとして、著者は「キモ・レオポルドはUFC3で『ジョー・サン道』を世に知らしめた。彼の師匠で23歳のジョー・サンが考案した格闘術で、テコンドーの分派であるかのように喧伝していた。レオポルドは敬虔なクリスチャンでもあり、実物大の木の十字架を肩に担いでオクタゴンへ向かった。セコンドたちはイエス・キリストが十字架上で血を流しているバナーを掲げていた」と述べています。
UFC5ではジョン・ヘスが〈SAFTA(全米攻撃的格闘科学)〉という独自の格闘技の達人と紹介されました。対戦相手のアンディ・アンダーソンはテキサス州のサイトクラブのオーナーで、ギャング団〈アーリアン・ブラザーフッド〉の一員でもあり、SEGが同州グレッグ郡にある彼の店のひとつ〈トータリー・ヌード・ステーキハウス〉の店員をラウンドガールに雇った縁で、トーナメントへの出場が打診されました。UFC8では長身のカナダ人で“ビッグ・ダディ”の愛称を持つゲーリー・グッドリッジがデビューしました。
第四章「総損失3000万ドルの危機──PRIDE絶頂の裏側で」では、PRIDEのスター選手は日本の伝説的プロレス団体の出身者が多いとして、著者は「まるでアスリートではなく、人の生き様についてつかの間の教訓を伝える寓話中の人物であるかのような民俗学的オーラを放っていた。〈UWF(ユニバーサル・レスリング・フェデレーション)〉の目立たないプロレスラーだった桜庭は、「グレイシー・キラー」と称されてカルト的な人気を得た」と述べています。
PRIDEはUFCで最高の選手の多くを吸い上げ、UFCは新たな有望株の獲得が難しくなっていました。2001年、UFCのディナ・ホワイトは7勝1敗の戦績から〈修斗〉ミドル級王者に輝いたばかりの有望なブラジル人戦士アンデウソン・シウバとの契約に力を傾けていました。デビュー予定日の1ヵ月前、シウバはPRIDEからのオファーに応じてUFCとの契約から手を引きました。ホワイトとロレンゾ・フェティータのUFC最高責任者両名は歯噛みしながらも、選手にとってPRIDEがどんなに魅力的かを理解していたのでした。
ブロック・レスナーは、ランディ・クートゥアと同じく、アスリートとしての夢をかなえるためにケージファイトへの転向を決意しました。2007年に〔6月にロサンゼルスで開催された日本のHERO’Sの大会〈ダイナマイト=USA〉で〕鮮烈なデビューを飾ったレスナーは〔10月〕UFCと契約を結びました。デビュー戦で元ヘビー級王者フランク・ミアに敗れましたが、2戦目の08年夏、UFC87で元PRIDEのベテラン、ヒース・ヒーリングを圧倒しました。
ホワイトはレスナーをヒョードル以上の大スター、恐るべき選手として育て上げようと躍起になり、クートゥアにUFC復帰と11月のレスナーとの王座防衛戦を打診しました。クートゥアはこれを受け入れました。著者は、「ヒョードルに比べればはるかに実績は劣るものの、レスナーは世界的スーパースターだ。純粋なスポーツ的意義には欠けても、ヒョードル戦以上の一大文化的イベントになりえると判断した。試合は08年11月15日、〈MGMグランド・ガーデン・アリーナ〉で開催されるUFC91のメインイベントに決定した」と述べます。
第十四章「WBCが懸けた豪華ベルト──マクレガー対メイウェザー」では、コナー・マクレガーとフロイド・メイウェザー・ジュニアの対戦が初めて公の場で口にされたのは、深夜のトーク番組での冗談だったことが明かされます。2015年夏、コナン・オブライエンが冠番組「コナン」のある回で、この対戦についてマクレガーに「もしあなたがフロイド・メイウェザーとリングに上がったら、どうなりますか?」と質問しました。マクレガーは「フロイドと戦いたいかと訊かれているのなら、1億8000万ドルのためにリングで踊りたいと思わないやつはいないだろうな……。あいつが俺の世界、つまり、何の制限もない純粋な非武装格闘技の世界に踏み込もうとしないのはわかってる。でも、俺はあいつの世界に足を踏み入れよう」と答えたのです。
メイウェザーvsマクレガー戦のリングを囲む最初の数列は、レブロン・ジェームズ、クリス・ヘムズワース、ジェイミー・フォックス、シャーリーズ・セロン、ジェニファー・ロペス、ヴァネッサ・ハジェンズ、カーリー・クロス、ドン・チードル、スティーブ・ハーヴェイ、カーディ・B、ショーン・コムズら有名人で埋め尽くされました。それは、権力者や富裕層が作品を注文したルネサンス期の絵画を思い起こさせたといいます。アリーナの3分の1近くが空席だったにもかかわらず、観客の富を結集したチケット売り上げは5540万ドルに達し、これはメイウェザーが2015年マニー・パッキャオと戦った試合に次ぐボクシング史上2番目の売り上げで、UFC史上最大のライブチケット売上額の3倍以上でした。
エピローグ「限界を超えろ」では、著者は「皮肉なことに、UFCはパンデミック中に過去最高の1年を迎えた。この新しい疫病が世界に蔓延し、180万人以上が亡くなり、2020年には1億1400万人以上が新たに失業するなか、UFCの収益は過去最高の約8億9000万ドルに達し、その48パーセントがEBITDA(企業価値指標)に計上された。ホワイトによれば、UFCの総視聴者数はパンデミック期間中に47パーセント増加し、ESPNでの視聴率は前年比16パーセント増となった。UFC大会は定期的にツイッター〔現X〕のトレンドトピック上位を占め、同団体のインスタグラムフォロワー数はNBAに次いでNFLのフォロワー数を大きく引き離し〔現在4200万超〕、ユーチューブのチャンネル登録者数は1700万人を超えた。1994年、『ニューヨーク・タイムズ』紙が最初にUFCを、西洋文明の衰退を映し出す『ペイパービュー・プリズム』と評価したが、これはある意味もっともなことだった。世界が着々と正常な感覚を失っていくなかで、2人の人間が檻に閉じ込められ、数ヵ月分の収入を懸けて戦う光景くらい理にかなったことはなかったのだ」と述べています。
UFCの華やかさの裏で、多くの選手が自分の職業について葛藤しているようだといいます。ニック・ディアスは、2015年のインタビューで「MMAとか格闘選手の多くは、『戦うことが好きなんだ』って言うだろう」と語りました。』彼はまた、「俺は非暴力主義者だよ。戦うのが大好きなんかじゃない。戦わなけりゃならないから戦うんだ」とも言いました。著者は、「ある意味、UFCの魔法の1つは、現実をゆがめて、あたかも人々が本当に戦わなければならないかのように見せかけ、出口のない檻に閉じ込められた2人の人間の姿を、森の木立の中で草を食む鹿のような自然な光景を見せるところにある。照明やカメラ、轟きわたる音楽が作り出した人工的な現実の中では、戦う選手たち自身が残酷さを求める身勝手な本能に従うことをためらい、相手と対峙したときみずからの本性と戦っているかのように見えることがある。このスポーツの最も象徴的な人物ホイス・グレイシーでさえ、自分は生まれついての格闘家ではないと認めている。『まともな世界だったら、私は格闘家ではなかっただろう』と、彼は2015年に自身のキャリアを振り返った」と述べます。
UFCのアプローチは、嘉納治五郎(20世紀初頭にブラジルに渡ってグレイシー一族に柔術を指導した前田光世の師)が信じていた武術の価値と目的に多くの点で逆行していると指摘する著者は、「嘉納が亡くなる数年前、1934年に、彼はアテネのパルナソス文学協会で行った講演で、武道の基本原理は敵を圧倒したり批判者を出し抜いたりすることではなく、『相互扶助と譲歩を生み出し、相互の福祉と利益をもたらすこと』と主張した。心身ともに厳しい鍛錬は人々を謙虚にさせ、自分の進歩がいかに他者の寛大さと支援に依存しているかを教えてくれる」と述べています。嘉納によれば、「社会の中で生きているかぎり、人は社会の進歩から恩恵を受ける。社会が劣化すれば、本来得られるはずのものを得られなくなる・・・・・・。社会生活を維持するには、社会の構成員一人ひとりが利己的な行動を慎み、常に他人を助けなければいけない」というのです。
解説「UFCと日本格闘技界」の冒頭を、堀江ガンツ氏は「1993年9月23日、東京ベイNKホール。パンクラス旗揚げ戦の大会開始前、ケン・(ウェイン・)シャムロックが会場の一室で記者会見を開き、同年11月12日にアメリカ・コロラド州デンバーで行われる“フリースタイルトーナメント”に、パンクラス代表として出場することを発表した。これが日本において「アルティメット・ファイティング・チャンピオンシップ=UFC」の存在が、初めて公の場で言及された瞬間だった。まだMMA(ミックスド・マーシャル・アーツ)という呼び名がなく、それどころか黎明期の呼称であったNHB(ノー・ホールズ・バード)やバーリ・トゥードという言葉も日本にはなかった時代。眼球と急所以外への攻撃がすべて許される“なんでもあり”の闘いは“フリースタイル”と呼ぶしかなかったのだろう」と書きだしています。
パンクラスの旗揚げ戦で、2ヵ月後に行われる第1回UFCについて初めて発表された事実には、歴史的必然を感じずにはいられないという堀江氏は、「とはいえ、シャムロックの“フリースタイルトーナメント”出場は、当初ほとんど話題にはならなかった。日本でも名の知られた“死神”ジェラルド・ゴルドーの出場も決まっていたためコアな格闘技好きの興味は惹いたが、多くの人たちにとっては『アメリカのケンカ大会にシャムロックが出場するんだ』という程度の認識。また『普通にシャムロックが優勝するだろう』という漠然とした安心感もあり、大会前に関心は高いとは言えなかった。しかし、その結果は衝撃をもって迎えられる。リアルファイト時代の扉を開いた“最先端の団体”であるパンクラス旗揚げ戦でエースの船木を破った“最強戦士”であるはずのシャムロックが、トーナメント準決勝でグレイシー柔術なる未知の格闘技を操るファイター、ホイス・グレイシーに、チョークスリーパーで完敗を喫してしまったからだ。試合時間はわずか57秒」と述べます。
日本では、70年代の極真空手ブームやアントニオ猪木の一連の異種格闘技戦の時代から、誰が一番強いのか、どの格闘技が一番強いのかは、格闘技好きにとっての最大のロマンでした。しかし実際は異なる競技間でのルールの問題が常に横たわり、それは空想の世界でしかありませんでしたが、UFCではそれをほぼノールールにすることであっさりと解決しました。しかも、ルールがなければそれは凄惨な殺し合いとなり、スポーツ競技の範疇を逸脱してしまうという常識も、護身術でもあるグレイシー柔術(ブラジリアン柔術)が覆してみせたとして、堀江氏は「流派、競技の枠を超えて誰が一番強いのかを決めるUFCという舞台がついに現れ、そこで圧倒的な強さをみせて優勝したのは、日本古来の柔術を地球の裏側ブラジルで発展させたグレイシー一族だったという壮大なロマンは、日本の格闘技ファンを瞬く間に虜にしたのである」と述べます。
日本でグレイシーやバーリ・トゥードへの関心が高まっていったのと同時期、UFCはアメリカで苦戦を強いられていました。本書にもあるとおり、ボクシング業界からの圧力や親ボクシング派のアメリカ共和党上院議員ジョン・マケインの働きかけにより、ニューヨーク州を含む36州が総合格闘技大会の開催を禁じるノー・ホールズ・バード禁止法を制定したのです。UFCは規制の緩い州や海外でしか大会を行えなくなり、さらに97年にはマケイン議員が商業委員会委員長に就任したことで多くのケーブルテレビ会社がUFCのPPV放送から撤退。UFCの財政状況は急速に悪化していきました。
そんな状況下でUFCが活路を見出したのが、総合格闘技人気が高まりつつある日本でした。UFCを主催するSEGは、日本法人であるUFC-J事務局とフランチャイズ契約を締結し、97年12月21日に横浜アリーナで初の日本大会「UFC JAPAN」を開催しました。そこで桜庭和志が、カーウソン・グレイシー柔術黒帯のマーカス・コナンに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちして、UFC-Jヘビー級トーナメントで優勝したのです。試合後のインタビューでは、笑顔で「プロレスラーは本当は強いんです」と語り、髙田のヒクソン戦完敗で打ちひしがれていたファンの心を救い、プロレス界と日本格闘技界の救世主となったのでした。
「世界最強の格闘技イベント」とまで呼ばれたPRIDEは、2006年に反社会勢力との結びつきが疑われるスキャンダルに見舞われ、地上波テレビ放送が撤退したことで急速に力を失っていきました。そして2007年3月、PRIDEを運営するドリーム・ステージ・エンターテインメント社の榊原信行代表は、UFCを主催するズッファ社のオーナー、ロレンゾ・フェティータにPRIDEの興行権や映像アーカイブなどを譲渡しました。これによってUFCは事実上PRIDEを呑み込むかたちとなり、名実ともにMMAの世界最高峰となったのです。
その後もUFCは成長を続け、16年7月にWEM-IMG(のちにエンデバーに企業名を変更)がズッファからUFCを買収しました。23年4月にはエンデバーが世界最大のプロレス団体WWEを買収し、UFCとWWEを統合した新会社TKOグループホールディングスとして上場。経済誌「フォーブス」が発表したUFCの格闘技プロモーションとしての企業価値は113億ドルで、プロレスやボクシングも含めてランキング1位となっています。本書は総合格闘技の歴史書としても興味深いですが、UFCのビジネスとしての側面に光を当てているところが秀逸でした。それにしても、UFCが名実ともに世界一の格闘技団体になったことを知り、かつてのPRIDEにノスタルジーを感じてしまいました。